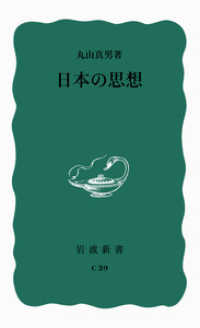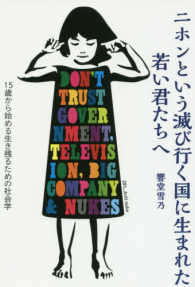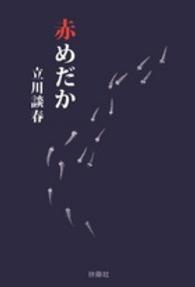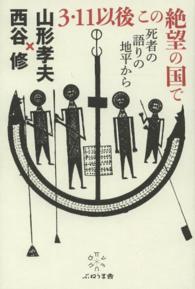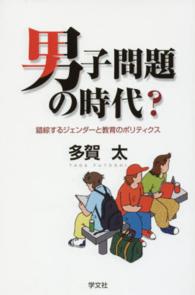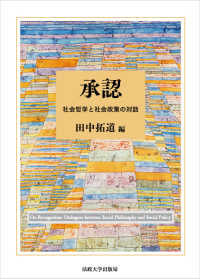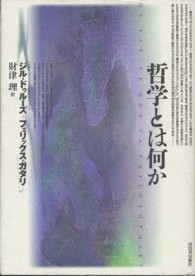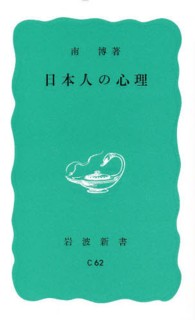-
推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科(日本史学講座)・教員)
仏教って、こんなに素晴らしいものなんだ。
仏教発見! / 西山厚著. - 講談社, 2004
 北大ではどこにある?
本書は、仏教関連の一般書である。ご自身断っておられるように、本書は純粋に正統的な仏教書ではない、かもしれない。だが、長年、奈良国立博物館で研鑽を積んでこられた氏の、仏教やモノへの愛がギュッと詰まった〈啓蒙の書〉である。
北大ではどこにある?
本書は、仏教関連の一般書である。ご自身断っておられるように、本書は純粋に正統的な仏教書ではない、かもしれない。だが、長年、奈良国立博物館で研鑽を積んでこられた氏の、仏教やモノへの愛がギュッと詰まった〈啓蒙の書〉である。
ある日、私はこの本を電車のなかで読み始め、終盤近くでとうとう泣き出してしまった。新書を読んで泣いたり笑ったりなどという経験は、初めてのことである。読者に直接繙いて貰いたいので、ここに詳しくは書かないが、西山氏の手がけた「東大寺のすべて」展(奈良博・二〇〇二年)を、東大寺附属の幼稚園児たちに展示解説するくだり(→笑... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
戦後日本の思想的骨格を掴む
日本の思想 / 丸山真男著. - 岩波書店, 1961
 北大ではどこにある?
先日必要があって高校の倫理の用語集を見ていたら、丸山眞男が項目立てされて解説が書かれていたので少しびっくりした。同時にもうそういう時代になったのか(=丸山もそういう存在になったのか)とあらためて感じるものがあった。ということは、かなりの北大生が高校時代におそらくこの『日本の思想』を読んでいると思われるので、今更紹介するまでもないのかもしれないが、まだ読んでいない人のためにここに推薦しておきたい。
北大ではどこにある?
先日必要があって高校の倫理の用語集を見ていたら、丸山眞男が項目立てされて解説が書かれていたので少しびっくりした。同時にもうそういう時代になったのか(=丸山もそういう存在になったのか)とあらためて感じるものがあった。ということは、かなりの北大生が高校時代におそらくこの『日本の思想』を読んでいると思われるので、今更紹介するまでもないのかもしれないが、まだ読んでいない人のためにここに推薦しておきたい。
実は、僕自身はこの本を今読んでも率直に言って“程度の低い常識論”にしか読めない。しかし、裏を返せばそれは、今や常識論に思われるほどに... [続きを読む] -
推薦者 : 今井 一郎 (水産科学研究院・教員)
ニホンという滅び行く国に生まれた若い君たちへ送る言葉
ニホンという滅び行く国に生まれた若い君たちへ : 15歳から始める生き残るための社会学 / 響堂雪乃著. - 白馬社, 2017
 北大ではどこにある?
かつては「陰謀論」あるいは「都市伝説」と言われて一笑に付される様な一見荒唐無稽とも思える事項が,実は真実の場合がある。アメリカ同時多発テロ事件は,陰謀論の最たるものと言われて来た。しかし,死の床にあった元 CIA 局員、マルコム・ハワード氏は、ビル等の破壊に関する経歴や技術を持っていたことから、ニューヨークの世界貿易センタービルの破壊プロジェクトを CIA の幹部から強要されたとの内容を告白した。この事から,同時多発テロ事件は CIA の実行した,アメリカ政府による自作自演のテロである事がつい先日(2017年7月13日)判明した。この事件はアルカイダによる... [続きを読む]
北大ではどこにある?
かつては「陰謀論」あるいは「都市伝説」と言われて一笑に付される様な一見荒唐無稽とも思える事項が,実は真実の場合がある。アメリカ同時多発テロ事件は,陰謀論の最たるものと言われて来た。しかし,死の床にあった元 CIA 局員、マルコム・ハワード氏は、ビル等の破壊に関する経歴や技術を持っていたことから、ニューヨークの世界貿易センタービルの破壊プロジェクトを CIA の幹部から強要されたとの内容を告白した。この事から,同時多発テロ事件は CIA の実行した,アメリカ政府による自作自演のテロである事がつい先日(2017年7月13日)判明した。この事件はアルカイダによる... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
哲学を体現した人の生涯
ウィトゲンシュタイン : 天才哲学者の思い出 / ノーマン・マルコム著 ; 板坂元訳. - 平凡社, 1998
 北大ではどこにある?
20世紀以降の哲学に最も影響力のあった哲学者ウィトゲンシュタインに親しく接した著者が、その人柄、哲学に対する姿勢、同時代人との関わりからゼミナールの雰囲気までを生き生きと描いた人物伝である。ウィトゲンシュタインの哲学に関心がなくても、哲学者という人びとが自分の思索にどのような姿勢で臨んでいるかを知る上で一読の価値がある。
北大ではどこにある?
20世紀以降の哲学に最も影響力のあった哲学者ウィトゲンシュタインに親しく接した著者が、その人柄、哲学に対する姿勢、同時代人との関わりからゼミナールの雰囲気までを生き生きと描いた人物伝である。ウィトゲンシュタインの哲学に関心がなくても、哲学者という人びとが自分の思索にどのような姿勢で臨んでいるかを知る上で一読の価値がある。 -
推薦者 : 橋本 努 (経済学院・教員)
「幸福とは何か」「善く生きるとはどういうことか」を問う新しい教養の書
The Routledge handbook of philosophy of well-being / Fletcher, Guy. - Routledge, 2015
 北大ではどこにある?
この数年間で、「幸福」や「ウェルビイング」に関する研究が、社会科学の諸分野を巻き込みつつ大きく発展している。さまざまな国際指標が提案され、膨大な社会調査研究が蓄積されてきた。実証的な成果を受けて、哲学や社会理論においても新たな発展がみられる。本書はこのテーマに関する最新の社会諸科学の研究成果を展望するハンドブックであり、と同時に、「幸福とは何か」「善く生きるとはどういうことか」を問う新しい教養の書といえる。こうした書物を契機に、若い世代から新たな研究が生まれることを願っている。
北大ではどこにある?
この数年間で、「幸福」や「ウェルビイング」に関する研究が、社会科学の諸分野を巻き込みつつ大きく発展している。さまざまな国際指標が提案され、膨大な社会調査研究が蓄積されてきた。実証的な成果を受けて、哲学や社会理論においても新たな発展がみられる。本書はこのテーマに関する最新の社会諸科学の研究成果を展望するハンドブックであり、と同時に、「幸福とは何か」「善く生きるとはどういうことか」を問う新しい教養の書といえる。こうした書物を契機に、若い世代から新たな研究が生まれることを願っている。
登録日 : 2017-08-04
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「知の巨人」たちはいかに思索したか
柳田国男と梅棹忠夫 : 自前の学問を求めて / 伊藤幹治著. - 岩波書店, 2011
 北大ではどこにある?
先に竹内好の『日本とアジア』をこの「本は脳を育てる」に推薦したが、その中で竹内好がしばしば言及している一人が梅棹忠夫である。日本の知識人―という言い方を梅棹は嫌うだろうが―のアジア理解、文明観を問題にする上で避けて通れないと竹内は感じ取ったのだろう。その梅棹の知的営為を、先行する柳田国男のそれと対比的に考察し、そこに共通するものと相違するものを読み解こうとしたのが本書である。一つの学問を作り上げることの奥深さを知ることのできる好著として推薦したい。
北大ではどこにある?
先に竹内好の『日本とアジア』をこの「本は脳を育てる」に推薦したが、その中で竹内好がしばしば言及している一人が梅棹忠夫である。日本の知識人―という言い方を梅棹は嫌うだろうが―のアジア理解、文明観を問題にする上で避けて通れないと竹内は感じ取ったのだろう。その梅棹の知的営為を、先行する柳田国男のそれと対比的に考察し、そこに共通するものと相違するものを読み解こうとしたのが本書である。一つの学問を作り上げることの奥深さを知ることのできる好著として推薦したい。 -
推薦者 : 田畑 伸一郎 (スラブ・ユーラシア研究センター・教員)
フィンランドの歴史を深く理解するための好著
「大フィンランド」思想の誕生と変遷 : 叙事詩カレワラと知識人 / 石野裕子著. - 岩波書店, 2012
 北大ではどこにある?
フィンランドの文化を知るうえで重要な叙事詩カレワラが同国の歴史において,あるいは同国が独立を遂げていくなかでどんな役割を果たしのかがよく分かります。フィンランドの歴史について思想面を含めて深く学びたい人にとって必読書です。
北大ではどこにある?
フィンランドの文化を知るうえで重要な叙事詩カレワラが同国の歴史において,あるいは同国が独立を遂げていくなかでどんな役割を果たしのかがよく分かります。フィンランドの歴史について思想面を含めて深く学びたい人にとって必読書です。 -
推薦者 : 松田 康子 (教育学研究院・教員)
すべての学び手に
ケアの本質 : 生きることの意味 / ミルトン・メイヤロフ著 ; 田村真, 向野宣之訳. - ゆみる出版, 1987
 北大ではどこにある?
本書は、MILTON MAYEROFF著 On Caringの訳書です。対人援助職にとどまらず、すべてのケアの担い手にとって、ケアの営みにおいて常に立ち戻るべき本質が示されており、哲学書にしてはやさしい言葉で綴られている書物です。日本語も英語も一見すると、平易な言葉が並んでいるのですが、何度でも噛み締め味わうことができる論考です。高等教育機関において、「すべての学び手に」としてオススメしたい点は、メイヤロフが、ケアの対象を人のみならず、芸術、概念、理念というものにまで広げて考えているところです。メイヤロフは、ケアリングとは、ケアの受け手が他の誰かをケアできるよ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
本書は、MILTON MAYEROFF著 On Caringの訳書です。対人援助職にとどまらず、すべてのケアの担い手にとって、ケアの営みにおいて常に立ち戻るべき本質が示されており、哲学書にしてはやさしい言葉で綴られている書物です。日本語も英語も一見すると、平易な言葉が並んでいるのですが、何度でも噛み締め味わうことができる論考です。高等教育機関において、「すべての学び手に」としてオススメしたい点は、メイヤロフが、ケアの対象を人のみならず、芸術、概念、理念というものにまで広げて考えているところです。メイヤロフは、ケアリングとは、ケアの受け手が他の誰かをケアできるよ... [続きを読む] -
推薦者 : 野中 雄司 (附属図書館・職員)
これから「どう生きるか」を改めて考えたいときに
君たちはどう生きるか / 吉野源三郎. - 岩波書店, 1982
 北大ではどこにある?
この本は、軍国主義が勢力を強めつつあった昭和十二年に山本有三が少年少女向けに偏狭な国枠主義を越えた自由で豊かな文化のあることを伝えようとして編纂した『日本少国民文庫』シリーズ中の「倫理」を扱ったものです。私はこの少年少女向けの本を25歳を過ぎてから読みましたが、恥ずかしながら「勉強する意味」などハッとさせられる部分が多くあり感銘を受けました。読了後少し恥ずかしく思いつつ解説を読んでいると、なんとかの丸山眞男も大卒後東大法学部の助手になり研究者になった後に読み「私の魂をゆるがした」と記されており、驚いたのと同時にほっとしたことを覚... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、軍国主義が勢力を強めつつあった昭和十二年に山本有三が少年少女向けに偏狭な国枠主義を越えた自由で豊かな文化のあることを伝えようとして編纂した『日本少国民文庫』シリーズ中の「倫理」を扱ったものです。私はこの少年少女向けの本を25歳を過ぎてから読みましたが、恥ずかしながら「勉強する意味」などハッとさせられる部分が多くあり感銘を受けました。読了後少し恥ずかしく思いつつ解説を読んでいると、なんとかの丸山眞男も大卒後東大法学部の助手になり研究者になった後に読み「私の魂をゆるがした」と記されており、驚いたのと同時にほっとしたことを覚... [続きを読む] -
推薦者 : 小林 和也 (高等教育推進機構オープンエデュケーションセンター・職員)
ゾーンへの招待
ストーカー / アルカジイ・ストルガツキー,ボリス・ストルガツキー著 ; 深見弾訳. - 早川書房, 1983
 北大ではどこにある?
アンドレイ・タルコフスキー監督による映画のほうが有名かもしれないが、この原作もまた偉大な文学作品だ。
北大ではどこにある?
アンドレイ・タルコフスキー監督による映画のほうが有名かもしれないが、この原作もまた偉大な文学作品だ。
本作は通常SFとされる。しかしそれだけではない。戦争や核汚染後の世界のメタファーとも言える突如現れた謎の危険地帯「ゾーン」。ストーカーはそこに侵入して、異星人が残したとされる異物を採取する。ストーカーとは何者であるのか? この問いに対する答えを、主人公レドリックの述懐に読み取ることができなければ、それはこの本との出会い損ね、悲しい接触と言わざるをえない。 -
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
関西弁のゾウの神様に教わる人生で大事なこと
夢をかなえるゾウ / 水野敬也. - 飛鳥新社, 2011
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 小林 和也 (高等教育推進機構オープンエデュケーションセンター・職員)
生き方について考えることをやめて何らかの実験を生きるには
千のプラトー : 資本主義と分裂症 / ジル・ドゥルーズ, フェリックス・ガタリ [著] ; 宇野邦一 [ほか] 訳. - 河出書房新社, 1994
 北大ではどこにある?
生き方がわからないなんて不思議なお話だ。だって君は現に生きているのに? それでも問うてみたくなるのはなぜだろう。生きているのは苦しいし、悩みは耐えない。だからなぜこんなに苦労してまで生き続けなければならないの? どう生きればいい?と問いたくなるものだ。
北大ではどこにある?
生き方がわからないなんて不思議なお話だ。だって君は現に生きているのに? それでも問うてみたくなるのはなぜだろう。生きているのは苦しいし、悩みは耐えない。だからなぜこんなに苦労してまで生き続けなければならないの? どう生きればいい?と問いたくなるものだ。
こういう時はたいてい「生き方」なんていう言葉遣いが分析・分節されてつくしていないからだ。こういう乱暴な言葉遣いには気をつけたほうがいい。「生き方」が違うから分かり合えません。じゃあどうやって人とやっていくのさ?
言葉を分析するには、どうしたらいいだろう。こう考えることはで... [続きを読む] -
推薦者 : 佐々木 亨 (文学部・教員)
「修行とは矛盾に耐えること」とは、名言?、迷言?
赤めだか / 立川談春. - 扶桑社, 2015
 北大ではどこにある?
私がこの本に出会ったのは、つい最近です。それは、このところ落語に興味を持ってきたことに関係しています。著者の立川談春は、5年前に亡くなった立川談志の弟子です。
北大ではどこにある?
私がこの本に出会ったのは、つい最近です。それは、このところ落語に興味を持ってきたことに関係しています。著者の立川談春は、5年前に亡くなった立川談志の弟子です。
談志は、名言、迷言、暴言の多い落語家でした。名言としては、「修行とは矛盾に耐えることである」、「己が努力、行動を起こさずに対象となる人間の弱みを口であげつらって、自分のレベルまで下げる行為、これを嫉妬という」など、短い文で人間の行為の本質を的確に捉えたものが多いです。この本には、その談志の弟子である談春の修業時代からの苦労話が、たくさん詰まっています。
私は、もう一度... [続きを読む] -
推薦者 : 戸田 聡 (文学研究科・教員)
いかに生きるか ―附属図書館企画「少年よ、学部を選べ」に寄せて―
『余の尊敬する人物』 他 / 矢内原忠雄 他. - 岩波書店 他,
 北大ではどこにある?
学内の知らせで、「少年よ、学部を選べ」という附属図書館企画があることを知ったが、この文章の主たる対象読者は既に学部を選んでしまっている学生諸君であるだろう。とすれば、今さら「学部を選べ!」と言われても「は?」といった応答しか返ってこないであろうことは必至である。むしろやはり、「生き方を選べ!」とか(ちと高圧的か?)、「いかに生きるか?」といった見出しで書くほうが、どのみち同じ内容だとしても、まだしも受け入れられやすいのではなかろうか。
北大ではどこにある?
学内の知らせで、「少年よ、学部を選べ」という附属図書館企画があることを知ったが、この文章の主たる対象読者は既に学部を選んでしまっている学生諸君であるだろう。とすれば、今さら「学部を選べ!」と言われても「は?」といった応答しか返ってこないであろうことは必至である。むしろやはり、「生き方を選べ!」とか(ちと高圧的か?)、「いかに生きるか?」といった見出しで書くほうが、どのみち同じ内容だとしても、まだしも受け入れられやすいのではなかろうか。
などと書きはしたものの、自分の人生論をぶつことができるほど筆者(戸田)は老成しているとも... [続きを読む] -
推薦者 : 敷田 麻実 (高等教育推進機構・教員)
君は、「面白い研究」をつまらなくプレゼンできないはずだ
勝率2割の仕事論 : ヒットは「臆病」から生まれる / 岡康道. - 光文社, 2016
 北大ではどこにある?
岡はクリエイティブディレクターであり、またコマーシャルを作成するプランナーの肩書きを持つ。大手の広告代理店に勤めた後、仲間と独立し「TUGBOAT(タグボート)」(広告代理店)の代表を努めている。その岡が本書で強調するのは、「仕事の勝率は2割でよい」ということではない。岡が、クライアントの要求を超えて、彼らが気づいていない隠れた意図を提案したり、メッセージ性の強い仕事をしていると、結果的に勝率は2割になってしまうということだ。
北大ではどこにある?
岡はクリエイティブディレクターであり、またコマーシャルを作成するプランナーの肩書きを持つ。大手の広告代理店に勤めた後、仲間と独立し「TUGBOAT(タグボート)」(広告代理店)の代表を努めている。その岡が本書で強調するのは、「仕事の勝率は2割でよい」ということではない。岡が、クライアントの要求を超えて、彼らが気づいていない隠れた意図を提案したり、メッセージ性の強い仕事をしていると、結果的に勝率は2割になってしまうということだ。
彼の仕事と研究者の仕事の共通点は、「人の金」を使って仕事をしていることである。彼らはクライアントの資金を使い... [続きを読む] -
推薦者 : 瀬名波 栄潤 (文学部・教員)
男性性研究の古典
男同士の絆 : イギリス文学とホモソーシャルな欲望(原タイトル:Between men) / イヴ・K・セジウィック. - 名古屋大学出版会, 1985年(原書)、2001年(翻訳)
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 橋本 努 (経済学研究科)
現代を代表する思想家のチャールズ・テイラーの最新書であり、英語の教材としても最適である。
The language animal : the full shape of the human linguistic capacity / Taylor, Charles. - Belknap Pr, 2016
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
登録日 : 2016-11-08
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
東北大震災以後の日本を世界史的規模で考える
3・11以後この絶望の国で : 死者の語りの地平から / 山形孝夫・西谷修. - ぷねうま舎, 2014
 北大ではどこにある?
この本は、東北大震災で被災した宗教学者の山形孝夫氏と、現代思想のあり方を問い続けてきた哲学者の西谷修氏との対談である。表題を見ると、現代の日本を直接の対象としているようであるが、むしろ対談者のお二人の中心問題は、(制度的)キリスト教世界の成立とそれが世界に何をもたらしたかということにあり、その延長線上で、ある時点から道を踏み外し始めた世界と、「死者の口封じ」の道具と化してしまった宗教への危機感が語られる。東北大震災はその具体的な危機の露呈の現場として考察され、その危機的状況からのどのような救いの道があるかは、山形氏の”つぶやき... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、東北大震災で被災した宗教学者の山形孝夫氏と、現代思想のあり方を問い続けてきた哲学者の西谷修氏との対談である。表題を見ると、現代の日本を直接の対象としているようであるが、むしろ対談者のお二人の中心問題は、(制度的)キリスト教世界の成立とそれが世界に何をもたらしたかということにあり、その延長線上で、ある時点から道を踏み外し始めた世界と、「死者の口封じ」の道具と化してしまった宗教への危機感が語られる。東北大震災はその具体的な危機の露呈の現場として考察され、その危機的状況からのどのような救いの道があるかは、山形氏の”つぶやき... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
いつの時代にも共通する「悶々」
恋愛論 / スタンダール. - 岩波書店,
 北大ではどこにある?
スタンダールの『恋愛論』と言えば、「結晶作用」や「恋愛の四分類」であまりにも有名であるが、これらのことばだけが一人歩きしてしまっている観がなきにしもあらずである。この本は、周知のようにスタンダール自身がある女性との恋愛に悶々としていた経験を下敷きにして、当時のヨーロッパの知識人の12世紀から18世紀にわたる古典的教養を背景として書かれた人間観察の集成と言えるものである。そこに描かれる様々な恋愛事情の「悶々」は、21世紀日本の我々には分かりにくい部分や、今なら御法度になる部分を含んではいるものの恋愛という経験について今なお教えてくれると... [続きを読む]
北大ではどこにある?
スタンダールの『恋愛論』と言えば、「結晶作用」や「恋愛の四分類」であまりにも有名であるが、これらのことばだけが一人歩きしてしまっている観がなきにしもあらずである。この本は、周知のようにスタンダール自身がある女性との恋愛に悶々としていた経験を下敷きにして、当時のヨーロッパの知識人の12世紀から18世紀にわたる古典的教養を背景として書かれた人間観察の集成と言えるものである。そこに描かれる様々な恋愛事情の「悶々」は、21世紀日本の我々には分かりにくい部分や、今なら御法度になる部分を含んではいるものの恋愛という経験について今なお教えてくれると... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「男対女」の構図をいかに乗り越えるか
男子問題の時代?-錯綜するジェンダーと教育のポリティクス- / 多賀太. - 学文社, 2016
 北大ではどこにある?
ジェンダー、あるいは男女平等/差別の問題が語られるときにほぼお決まりになっているパターンとして「男は支配する側、女は支配される側」あるいは「男は加害者、女は被害者」という言説がある。日本の社会のかなりの部分でそれは当てはまるのかもしれないが、僕はこの見方には強烈な反発を持っている。それは、“日本語教師”という「女性8割、男性2割」の業界で働いてきた経験から、女性が多数者側になれば「女性は加害者、男性は被害者」という事態も容易に出現することを知っているからである。そのような意味で日本のジェンダー研究はまだ色々なことを考え直さなければ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ジェンダー、あるいは男女平等/差別の問題が語られるときにほぼお決まりになっているパターンとして「男は支配する側、女は支配される側」あるいは「男は加害者、女は被害者」という言説がある。日本の社会のかなりの部分でそれは当てはまるのかもしれないが、僕はこの見方には強烈な反発を持っている。それは、“日本語教師”という「女性8割、男性2割」の業界で働いてきた経験から、女性が多数者側になれば「女性は加害者、男性は被害者」という事態も容易に出現することを知っているからである。そのような意味で日本のジェンダー研究はまだ色々なことを考え直さなければ... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
新たな歴史哲学を考える原点として
歴史における言葉と論理-歴史哲学基礎論- / 神川正彦. - 勁草書房, 1970-1971
 北大ではどこにある?
この本については、少し過激な(?)推薦文を書きたい。
北大ではどこにある?
この本については、少し過激な(?)推薦文を書きたい。
先日、某大学(敢えて名は秘す)の日本現代(1950年代以降)哲学の授業のシラバスを見ていたら、そこで取り上げてられているのが大森莊藏、廣松渉、坂部恵であった。しかしこれでは、結局戦前は「京都学派」で、それが戦後になったら“東大”に変わっただけじゃないか、という印象を拭えない。日本の哲学というのは京大と東大の“官学アカデミズム”の中で選手交代をやっていただけだとしたらあまりにも悲しい。ここに推薦する神川正彦は、今はもう哲学専攻の学生でも名前を知らない人が多いかもしれないが、上記... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「承認」を切り口にして社会を考える
承認-社会哲学と社会政策の対話- / 田中拓道. - 法政大学出版局, 2016
 北大ではどこにある?
「承認」というと堅苦しい響きがあるが、要するに「認めてくれ!」ということである。ではなぜある人びとやある問題が社会の中で認められていないのか、どのようにすればその問題にアプローチできるのか、といったことに気鋭の研究者たちが正面から取り組んだ労作である。その際の基本的視角となっているのは現代ドイツの哲学者アクセル・ホネットの“承認の哲学”と、それに関するナンシー・フレイザーとの論争である。決して易しくはないが、ここからさらに各自の関心に応じて(芋づる式に!)読書の範囲を広げ問題を整理することができるだろう。よく言われる「哲学が何... [続きを読む]
北大ではどこにある?
「承認」というと堅苦しい響きがあるが、要するに「認めてくれ!」ということである。ではなぜある人びとやある問題が社会の中で認められていないのか、どのようにすればその問題にアプローチできるのか、といったことに気鋭の研究者たちが正面から取り組んだ労作である。その際の基本的視角となっているのは現代ドイツの哲学者アクセル・ホネットの“承認の哲学”と、それに関するナンシー・フレイザーとの論争である。決して易しくはないが、ここからさらに各自の関心に応じて(芋づる式に!)読書の範囲を広げ問題を整理することができるだろう。よく言われる「哲学が何... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
古典と現代をつなぐ読み方を知る
社会契約論-ホッブズ、ヒューム、ルソー、ロールズ- / 重田園江. - 筑摩書房, 2013
 北大ではどこにある?
高校の世界史や政治経済の授業で「社会契約論」という考え方を知ったときに感じたのは、ルソーにせよロックにせよなぜあの時代の西ヨーロッパの思想家がそういうことをわざわざ考えなければならなかったのか、という強烈な違和感だった。「社会」というものをみんなで作ろう(?)といった感じで最初に約束事をするという発想自体について行けなかったのである。実は今でもその違和感は抜けきらず、“起源”ということをやたらに理屈を付けて解き明かしたがる(そのくせ割合に最後は「神」が出現して一切が片付く)西欧の思想にとことん付き合いきれない思いがある。
北大ではどこにある?
高校の世界史や政治経済の授業で「社会契約論」という考え方を知ったときに感じたのは、ルソーにせよロックにせよなぜあの時代の西ヨーロッパの思想家がそういうことをわざわざ考えなければならなかったのか、という強烈な違和感だった。「社会」というものをみんなで作ろう(?)といった感じで最初に約束事をするという発想自体について行けなかったのである。実は今でもその違和感は抜けきらず、“起源”ということをやたらに理屈を付けて解き明かしたがる(そのくせ割合に最後は「神」が出現して一切が片付く)西欧の思想にとことん付き合いきれない思いがある。
この本... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
さらに一段上の文章表現力のために
論理が伝わる世界標準の「書く技術」-「パラグラフ・ライティング」入門- / 倉島保美. - 講談社, 2012
 北大ではどこにある?
ここに何度か書いたことだが数年前から「一般教育演習(フレッシュマンセミナー)」で文章表現が苦手な学生のための日本語文章表現法の授業を展開してきた。ただ、色々と訳あってこの授業は今年度で終わりにすることにした。そこで、これに替わるものとして、また、“苦手”のレベルを脱した学生がさらに上のレベルの文章表現力を身につけてもらう上で参考にすることができるようにこの本を推薦しておく。この本は、それ自体が主題としている「パラグラフ・ライティング」によって書かれているので、技法と実例を同時に身につけることができる点で優れている。あとは練習あるの... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ここに何度か書いたことだが数年前から「一般教育演習(フレッシュマンセミナー)」で文章表現が苦手な学生のための日本語文章表現法の授業を展開してきた。ただ、色々と訳あってこの授業は今年度で終わりにすることにした。そこで、これに替わるものとして、また、“苦手”のレベルを脱した学生がさらに上のレベルの文章表現力を身につけてもらう上で参考にすることができるようにこの本を推薦しておく。この本は、それ自体が主題としている「パラグラフ・ライティング」によって書かれているので、技法と実例を同時に身につけることができる点で優れている。あとは練習あるの... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
戦後日本の思想の絡まりを解きほぐす
現代日本思想論-歴史意識とイデオロギー- / 安丸良夫. - 岩波書店, 2004
 北大ではどこにある?
この本は、戦後日本の社会科学(主として政治学と歴史学)の中で誰がどのような議論を展開しそれが誰に受け継がれ誰に批判されその中からどのような議論が新たに形成されてきたかを論じる第一部と、戦後の主に海外の歴史学研究方法論、丸山眞男の思想史研究、そして著者自身の現代社会状況分析からなる第二部とに分かれている。読者の関心に応じて興味を引かれる部分は異なると思うが、特に第一部は戦後の社会科学研究の“思想地図”といった内容になっており、広く日本の戦後政治や思想を学ぶ上での基本的な知識を提供してくれている。これらの方面に関心のある学生に一読... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、戦後日本の社会科学(主として政治学と歴史学)の中で誰がどのような議論を展開しそれが誰に受け継がれ誰に批判されその中からどのような議論が新たに形成されてきたかを論じる第一部と、戦後の主に海外の歴史学研究方法論、丸山眞男の思想史研究、そして著者自身の現代社会状況分析からなる第二部とに分かれている。読者の関心に応じて興味を引かれる部分は異なると思うが、特に第一部は戦後の社会科学研究の“思想地図”といった内容になっており、広く日本の戦後政治や思想を学ぶ上での基本的な知識を提供してくれている。これらの方面に関心のある学生に一読... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
現代哲学の源流をたどる
人間知性の探究・情念論 / デイヴィッド・ヒューム. - 晢書房, 1990
 北大ではどこにある?
現代哲学、あるいは哲学史に於ける「現代」というのがなに/いつを指すのかは色々議論があるであろうけれども、(ニーチェを別にすれば)20世紀以降の西洋哲学のかなりの部分が目指そうとしたことは、ヒュームの哲学を練り直し、彼が問題としてことを問い直して現代に甦らせようとすることだったと言って良い。(例えば、ジョン・デューイはそのことをはっきりと述べている。) ヒュームは、哲学史の教科書的に言えば、懐疑論者でありイギリス経験論の完成者であるなどと言われるが、-そう見ることも可能であるとしても-彼が目指したのは日常的な経験をいかに概念化して人間の... [続きを読む]
北大ではどこにある?
現代哲学、あるいは哲学史に於ける「現代」というのがなに/いつを指すのかは色々議論があるであろうけれども、(ニーチェを別にすれば)20世紀以降の西洋哲学のかなりの部分が目指そうとしたことは、ヒュームの哲学を練り直し、彼が問題としてことを問い直して現代に甦らせようとすることだったと言って良い。(例えば、ジョン・デューイはそのことをはっきりと述べている。) ヒュームは、哲学史の教科書的に言えば、懐疑論者でありイギリス経験論の完成者であるなどと言われるが、-そう見ることも可能であるとしても-彼が目指したのは日常的な経験をいかに概念化して人間の... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
西洋哲学の基本の「き」
方法序説 / ルネ・デカルト. - 岩波書店, 1997
 北大ではどこにある?
「われ考える、ゆえにわれあり」や「明晰判明」、あるいは”方法的懐疑”といったことばであまりにも有名な、西洋(近世)哲学の始まりを飾る書である。哲学書というと初めから難しいものと考えて敬遠してしまう向きもあるかもしれない-そのような書物があることを否定はしない-が、この本は、きちんと読んでいけばそれなりに分かるように書かれているものである、同時にまた、西洋近世~近現代の哲学が多くの考えるべき課題をそこからくみ取っていった、西洋の知の基本をなす書物でもある。そのようなものを読んでおくことは、洋の東西を問わず学問を研究しようとするも... [続きを読む]
北大ではどこにある?
「われ考える、ゆえにわれあり」や「明晰判明」、あるいは”方法的懐疑”といったことばであまりにも有名な、西洋(近世)哲学の始まりを飾る書である。哲学書というと初めから難しいものと考えて敬遠してしまう向きもあるかもしれない-そのような書物があることを否定はしない-が、この本は、きちんと読んでいけばそれなりに分かるように書かれているものである、同時にまた、西洋近世~近現代の哲学が多くの考えるべき課題をそこからくみ取っていった、西洋の知の基本をなす書物でもある。そのようなものを読んでおくことは、洋の東西を問わず学問を研究しようとするも... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「分からなさ」を味わい、楽しむ
哲学とは何か / ジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリ. - 河出書房新社, 1997
 北大ではどこにある?
この推薦文は、「本は脳を育てる」の趣旨には反するが、たまにはこういった推薦もあっていいのではないかと思い、ここに挙げることにした。
北大ではどこにある?
この推薦文は、「本は脳を育てる」の趣旨には反するが、たまにはこういった推薦もあっていいのではないかと思い、ここに挙げることにした。
哲学の本を数多く読んできたが、これほど分からない本を読んだことはない。普通は分からなければなんとか分かろうと努力し、それなりに考えながら読むものであるが、この本は読んでも読んでも分からず、そのうちにその「分からなさ」が心地よく思えてきさえする。読んでいる自分が「分からなさ」という感覚に身をゆだね、それを楽しむ境地(?)に至った気分になってくるのである。それは著者両名の巧妙な仕掛けにあり、著者たちはお... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
日本の未来を考える視点はどこにあるのか
日本 / 姜尚中・中島岳志. - 河出書房新社, 2011
 北大ではどこにある?
著者二人の対談であるこの本は、僕なりの理解でまとめると「国家権力に絡め取られない自分のあり方をどう構築するか」という問題意識で貫かれており、それを、過去の歴史的文脈も振り返りながら徹底して論じようとしたものである。その基盤をなす発想は「パトリ」(故郷、郷土、あるいは根拠地といったもの)であり、熊本出身の在日韓国人二世である姜氏と大阪出身の中島先生がそれぞれの「パトリ」を意識しつつ、国家権力、あるいはその表象としての「東京」を挟撃するといった展開となっている。読者はそれぞれの「パトリ」に応じてこの対談にさまざまな共感や反発を感じ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
著者二人の対談であるこの本は、僕なりの理解でまとめると「国家権力に絡め取られない自分のあり方をどう構築するか」という問題意識で貫かれており、それを、過去の歴史的文脈も振り返りながら徹底して論じようとしたものである。その基盤をなす発想は「パトリ」(故郷、郷土、あるいは根拠地といったもの)であり、熊本出身の在日韓国人二世である姜氏と大阪出身の中島先生がそれぞれの「パトリ」を意識しつつ、国家権力、あるいはその表象としての「東京」を挟撃するといった展開となっている。読者はそれぞれの「パトリ」に応じてこの対談にさまざまな共感や反発を感じ... [続きを読む] -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
日本人の幸福感・運命主義・根性主義
日本人の心理 / 南博. - 岩波書店, 1956
 北大ではどこにある?
社会心理学者・南博先生による日本人の心理的特性を扱った本。初版は1953年と結構昔のものであるが、個人的には今でも十分読み応えのあるものだと感じた。江戸時代の各種養生書・処世書などをベースとしつつ、出版の処世書(今でいう自己啓発本か?)などからも引用をし、日本人の心理を整理している。日本人論の初期作品と言っていいかもしれない。もっとも日本人論と言っても、出版された当時の社会状況を反映してか、多くの日本人論に見られるような日本の素晴らしさを唱導する論調は見られない。むしろ軍隊や戦争、日本の権威主義的人間関係などを鋭く批判するというスタン... [続きを読む]
北大ではどこにある?
社会心理学者・南博先生による日本人の心理的特性を扱った本。初版は1953年と結構昔のものであるが、個人的には今でも十分読み応えのあるものだと感じた。江戸時代の各種養生書・処世書などをベースとしつつ、出版の処世書(今でいう自己啓発本か?)などからも引用をし、日本人の心理を整理している。日本人論の初期作品と言っていいかもしれない。もっとも日本人論と言っても、出版された当時の社会状況を反映してか、多くの日本人論に見られるような日本の素晴らしさを唱導する論調は見られない。むしろ軍隊や戦争、日本の権威主義的人間関係などを鋭く批判するというスタン... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「近代」は人をいかに突き動かしたか
日本近代思想の相貌-近代的「知」を問いただす- / 綱澤満昭. - 晃洋書房, 2001
 北大ではどこにある?
この本の表題には「日本近代思想」とあるけれども、おなじみの人々、例えば福沢諭吉や内村鑑三、新渡戸稲造、そして西田幾多郎や田邊元や和辻哲郎などはまったく主題化されていない(叙述の一部に僅かながら登場することはあるが)。著者は9人の人物を取り上げ、それらの人々の姿を描き出すことで「近代」という時代を捉え返しさらにそれらの捉え返しが「現代」、あるいは戦後日本に何をもたらし得るか、ということを問題にする。9人の人物は、宮沢賢治と長谷川如是閑を除けば今日のアカデミックな思想史研究では殆ど顧みられることがない人々ではあるが、それだけに日本の「... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本の表題には「日本近代思想」とあるけれども、おなじみの人々、例えば福沢諭吉や内村鑑三、新渡戸稲造、そして西田幾多郎や田邊元や和辻哲郎などはまったく主題化されていない(叙述の一部に僅かながら登場することはあるが)。著者は9人の人物を取り上げ、それらの人々の姿を描き出すことで「近代」という時代を捉え返しさらにそれらの捉え返しが「現代」、あるいは戦後日本に何をもたらし得るか、ということを問題にする。9人の人物は、宮沢賢治と長谷川如是閑を除けば今日のアカデミックな思想史研究では殆ど顧みられることがない人々ではあるが、それだけに日本の「... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
哲学書を読み解く技術とは
『純粋理性批判』を噛み砕く / 中島義道. - 講談社, 2010
 北大ではどこにある?
中島義道氏は、いろいろなところで一人っきりで哲学書を読むことの危うさを論じ、ご自身の「哲学塾カント」のホームページでも「哲学書を正確に読み解くには独特の技術が必要で、いい加減なわかり方ほど危険なことはありません。」と書いている。その中島氏がカント『純粋理性批判』の「アンチノミー論」を中心に据えてカントの-そしておそらくは中島氏の考える、「哲学書」の-読み方を実践したのが本書である。
北大ではどこにある?
中島義道氏は、いろいろなところで一人っきりで哲学書を読むことの危うさを論じ、ご自身の「哲学塾カント」のホームページでも「哲学書を正確に読み解くには独特の技術が必要で、いい加減なわかり方ほど危険なことはありません。」と書いている。その中島氏がカント『純粋理性批判』の「アンチノミー論」を中心に据えてカントの-そしておそらくは中島氏の考える、「哲学書」の-読み方を実践したのが本書である。
この本は、難解な哲学書である(と思われている)『純粋理性批判』について意外にわかりやすいことを書いているのだ、というスタンスからカントの行論を追いつ... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
西田哲学の実践としての西田評伝
西田幾多郎 / 大橋良介. - ミネルヴァ書房, 2013
 北大ではどこにある?
西田哲学の難しさについてはその一端を、以前この「本は脳を育てる」に『善の研究』を推薦したときに書いておいた。この『西田幾多郎』は、現在西田幾多郎研究の世界水準を牽引する著者が、単に「伝記」=時間の流れの中である人物がなしたあれこれのことを書くだけでなく、まさに西田を一つの”出来事”とし、それに西田哲学を実践してみせることによって新たな西田像を明らかにしたものである。西田の伝記はこれまでさまざまなものがあったけれども、西田自身の歴史哲学的思索によって書かれた西田には、これまでのものにはない新鮮な人間像が見られる。「哲学」という特... [続きを読む]
北大ではどこにある?
西田哲学の難しさについてはその一端を、以前この「本は脳を育てる」に『善の研究』を推薦したときに書いておいた。この『西田幾多郎』は、現在西田幾多郎研究の世界水準を牽引する著者が、単に「伝記」=時間の流れの中である人物がなしたあれこれのことを書くだけでなく、まさに西田を一つの”出来事”とし、それに西田哲学を実践してみせることによって新たな西田像を明らかにしたものである。西田の伝記はこれまでさまざまなものがあったけれども、西田自身の歴史哲学的思索によって書かれた西田には、これまでのものにはない新鮮な人間像が見られる。「哲学」という特... [続きを読む] -
推薦者 : 和多 和宏 (理学部 生物科学科(生物))
ヒトを含む生物の「生まれと育ち」を考える
やわらかな遺伝子 / マット・リドレー著 ; 中村桂子, 斉藤隆央訳. - 紀伊国屋書店, 2004
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
思索するカントの姿に迫る
理性の不安-カント哲学の生成と構造- / 坂部 恵. - 勁草書房, 2001
 北大ではどこにある?
この推薦文を書いている今日の昼間、書店に行ったら故石川文康先生訳『純粋理性批判(上下)』(筑摩書房)が棚に並んでいるのを見てびっくりした。石川先生は昨年逝去されたし、『純粋理性批判』を翻訳していらっしゃったことも知らなかった。同時に、どうしてこうも日本の哲学研究者(あるいは出版社?)は『純粋理性批判』の翻訳を出したがるのかなぁ、とも思ってしまった。この「本は脳を育てる」に文学研究科の千葉先生が熊野純彦先生の翻訳を推薦していらっしゃるが、それ以外にも多くの翻訳があり、訳書の多さという点では哲学書に限定せずとも『純粋理性批判』、ハイデガー... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この推薦文を書いている今日の昼間、書店に行ったら故石川文康先生訳『純粋理性批判(上下)』(筑摩書房)が棚に並んでいるのを見てびっくりした。石川先生は昨年逝去されたし、『純粋理性批判』を翻訳していらっしゃったことも知らなかった。同時に、どうしてこうも日本の哲学研究者(あるいは出版社?)は『純粋理性批判』の翻訳を出したがるのかなぁ、とも思ってしまった。この「本は脳を育てる」に文学研究科の千葉先生が熊野純彦先生の翻訳を推薦していらっしゃるが、それ以外にも多くの翻訳があり、訳書の多さという点では哲学書に限定せずとも『純粋理性批判』、ハイデガー... [続きを読む] -
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
Japan’s Best
Living for Jesus and Japan : the social and theological thought of Uchimura Kanzō / edited by Shibuya Hiroshi and Chiba Shin. - Eerdmans Pub., 2013
 北大ではどこにある?
本書は皆さんの大先輩札幌農学校二期生内村鑑三の研究書です。
北大ではどこにある?
本書は皆さんの大先輩札幌農学校二期生内村鑑三の研究書です。
新しい日本の黎明期、明治、大正そして昭和初期を力一杯駆け抜けたこの人物は思想家として信念を貫いた魅力ある人物です。外国人にも魅力的に見え、彼の諸著作は数カ国語に翻訳され、外国人による研究書は私の知る限りでも10冊を超えています。
本書は主に日本の内村研究者たちにより、彼の平和思想、愛国心そして神学思想を中心に人文学、自然科学に通じたジェネラリスト、社会思想家そして信仰者にしてキリスト教独立伝道者としての内村の諸側面を明らかにすることをめざし編集された英語論文集です。この... [続きを読む] -
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
最後まで読めるカントの『純理』
純粋理性批判(熊野純彦訳) / カント. - 作品社, 2012
 北大ではどこにある?
この名著については邦語においても数種類の翻訳を容易に手にすることができます。今年出版されたあたらしい熊野純彦氏による訳業は、従来の成果を取り入れつつ、従来のゴツゴツした訳業とは異なり、あまり負荷をかけられることなしに「分かる」という感覚の中で読み進めることができます。学問に憧れをもつ多くの人々が大学生になったことを期にこの難解の誉れ高い書を手にして挑戦してきました。私もそのひとりでしたが、その当時最後まで読み進めることはできませんでした。今の若者は幸いな翻訳にであえたと言うことができます。カントはこの書で理性が理性自身を吟味し... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この名著については邦語においても数種類の翻訳を容易に手にすることができます。今年出版されたあたらしい熊野純彦氏による訳業は、従来の成果を取り入れつつ、従来のゴツゴツした訳業とは異なり、あまり負荷をかけられることなしに「分かる」という感覚の中で読み進めることができます。学問に憧れをもつ多くの人々が大学生になったことを期にこの難解の誉れ高い書を手にして挑戦してきました。私もそのひとりでしたが、その当時最後まで読み進めることはできませんでした。今の若者は幸いな翻訳にであえたと言うことができます。カントはこの書で理性が理性自身を吟味し... [続きを読む] -
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
あらゆる学問の基礎
The Oxford Handbook of Aristotle / ed.Christopher Shields. - Oxford University Press, 2012
 北大ではどこにある?
本書においては、その後の人類の知的な営みにおける思考の規範となりあらゆる学問の基礎となったアリストテレスの哲学についてそれぞれの領域の第一人者24人(26章)の執筆者により包括的な研究および紹介がなされています。推薦者が今思いますのは人間の正しい思考方法がアリストテレスにより明晰に提示されたからこそ、ひとはいかなる領域においてであれ思考を進めるためにはアリストテレス的に思考せざるをえないということです。彼は「美しく問い(行き詰まり・アポリア)をたてること」が、その解に導くと言います。そして人類にとって、そのような方法は他にない... [続きを読む]
北大ではどこにある?
本書においては、その後の人類の知的な営みにおける思考の規範となりあらゆる学問の基礎となったアリストテレスの哲学についてそれぞれの領域の第一人者24人(26章)の執筆者により包括的な研究および紹介がなされています。推薦者が今思いますのは人間の正しい思考方法がアリストテレスにより明晰に提示されたからこそ、ひとはいかなる領域においてであれ思考を進めるためにはアリストテレス的に思考せざるをえないということです。彼は「美しく問い(行き詰まり・アポリア)をたてること」が、その解に導くと言います。そして人類にとって、そのような方法は他にない... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「田辺元ルネサンス」のために
田辺元哲学選I~IV(全4冊) / 田辺元. - 岩波書店, 2010
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
哲学の始原がよくわかる
Definition in Greek Philosophy / ed.David Charles. - Oxford University Press, 2010
 北大ではどこにある?
本書により哲学の揺籃であるギリシア哲学において、とりわけソクラテスがこだわった事物の同一性とその認識の問題がプラトン、アリストテレスそしてストアにおいてどのように理解され、哲学理論へと展開されていったかをテクストに即して理解することができる。周知のようにソクラテスは会う人ごとに、勇気とは、節制とは正義とはそして幸福とは「何であるか?」を尋ね、共に探求した。当時の人々同様多くの人が持つ哲学の理屈っぽさのイメージはこのソクラテスの問答の持つ吟味、論駁の詳細さそして厳密さに起因しているように思われる。しかし、本書によりこの「何である... [続きを読む]
北大ではどこにある?
本書により哲学の揺籃であるギリシア哲学において、とりわけソクラテスがこだわった事物の同一性とその認識の問題がプラトン、アリストテレスそしてストアにおいてどのように理解され、哲学理論へと展開されていったかをテクストに即して理解することができる。周知のようにソクラテスは会う人ごとに、勇気とは、節制とは正義とはそして幸福とは「何であるか?」を尋ね、共に探求した。当時の人々同様多くの人が持つ哲学の理屈っぽさのイメージはこのソクラテスの問答の持つ吟味、論駁の詳細さそして厳密さに起因しているように思われる。しかし、本書によりこの「何である... [続きを読む]