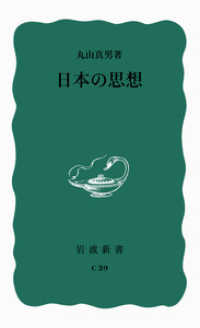推薦者: 中村 重穂
所属: 国際連携機構国際教育研究センター
身分: 教員
研究分野: 日本語教育史、意味論
戦後日本の思想的骨格を掴む
タイトル(書名):
日本の思想
著者:
丸山真男著
出版者:
岩波書店
出版年:
1961
ISBN:
400412039X
北大所蔵:
推薦コメント
先日必要があって高校の倫理の用語集を見ていたら、丸山眞男が項目立てされて解説が書かれていたので少しびっくりした。同時にもうそういう時代になったのか(=丸山もそういう存在になったのか)とあらためて感じるものがあった。ということは、かなりの北大生が高校時代におそらくこの『日本の思想』を読んでいると思われるので、今更紹介するまでもないのかもしれないが、まだ読んでいない人のためにここに推薦しておきたい。
実は、僕自身はこの本を今読んでも率直に言って“程度の低い常識論”にしか読めない。しかし、裏を返せばそれは、今や常識論に思われるほどに丸山の思想が戦後日本に浸透したということでもあると言える。まさに戦後日本の思想的骨格を為す著作だということができよう。今の日本の社会を考える上で多くの視点を(良くも悪くも)提供してくれる本である。そこから、今日に至るまで丸山がなぜ様々に論じられてきたかを考えることで自分の思考を鍛えることもできると思う。
ちなみに、講談社はなぜか丸山関連の本を出すのが大好き(?)で、選書メチエだけでも田中久文『丸山眞男を読みなおす』、伊東祐吏『丸山眞男の敗北』、橋爪大三郎『丸山眞男の憂鬱』を、さらに「再発見-日本の哲学-」シリーズで遠山敦『丸山眞男―理念への信―』、現代新書で長谷川宏『丸山眞男をどう読むか』を出している。本書を読んで興味が湧いたらこれらの本にも目を向けてみることを勧めたい。
実は、僕自身はこの本を今読んでも率直に言って“程度の低い常識論”にしか読めない。しかし、裏を返せばそれは、今や常識論に思われるほどに丸山の思想が戦後日本に浸透したということでもあると言える。まさに戦後日本の思想的骨格を為す著作だということができよう。今の日本の社会を考える上で多くの視点を(良くも悪くも)提供してくれる本である。そこから、今日に至るまで丸山がなぜ様々に論じられてきたかを考えることで自分の思考を鍛えることもできると思う。
ちなみに、講談社はなぜか丸山関連の本を出すのが大好き(?)で、選書メチエだけでも田中久文『丸山眞男を読みなおす』、伊東祐吏『丸山眞男の敗北』、橋爪大三郎『丸山眞男の憂鬱』を、さらに「再発見-日本の哲学-」シリーズで遠山敦『丸山眞男―理念への信―』、現代新書で長谷川宏『丸山眞男をどう読むか』を出している。本書を読んで興味が湧いたらこれらの本にも目を向けてみることを勧めたい。
※推薦者のプロフィールは当時のものです。