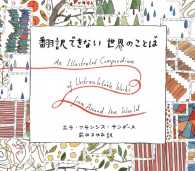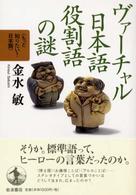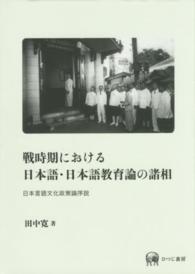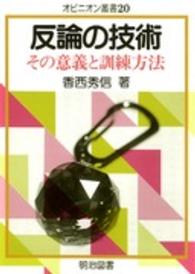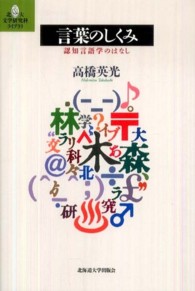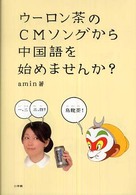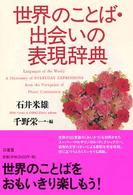-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「新しい」学問の「古典」
言語と社会 / P.トラッドギル著 ; 土田滋訳. - 岩波書店, 1975
 北大ではどこにある?
推薦文タイトルの”「新しい」学問の「古典」”という表現はそのまま読めば形容矛盾でしかない。しかし、この本は、社会言語学という1960年代から形成され始めた「新しい」学問の分野においては紛れもなく今や「古典」であり、タイトル通り「言語」と「社会」を見るための視点や研究の方法を手際よく整理して提示している。現在、社会言語学についての概論書、入門書は数多く出版されているし、その対象や方法も発展しているけれども、この本に盛り込まれた内容は今日でも(あるいは今日なお)有益であり学ぶことが多い。社会言語学という個別分野だけでなく、言語と社会の関... [続きを読む]
北大ではどこにある?
推薦文タイトルの”「新しい」学問の「古典」”という表現はそのまま読めば形容矛盾でしかない。しかし、この本は、社会言語学という1960年代から形成され始めた「新しい」学問の分野においては紛れもなく今や「古典」であり、タイトル通り「言語」と「社会」を見るための視点や研究の方法を手際よく整理して提示している。現在、社会言語学についての概論書、入門書は数多く出版されているし、その対象や方法も発展しているけれども、この本に盛り込まれた内容は今日でも(あるいは今日なお)有益であり学ぶことが多い。社会言語学という個別分野だけでなく、言語と社会の関... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
その日本語にはわけがある!
揺れ動くニホン語 : 問題なことばの生態 / 田中章夫. - 東京堂書店, 2007
 北大ではどこにある?
「日本語の乱れ」ということが時々メディアを賑わせる。しかし、これは言ってみればジャーナリズムや素朴な庶民感覚レベルの言い方で、その背後には(どこかに)“正しい(あるいは美しい)”日本語のあるべき用い方がある(はずだ)という一種の思い込みが隠れている。言語研究の観点から言えばこれが「乱れ」ではなく「変化」や「揺れ」であることは専門家の間では周知のことである。この本は、多様な現れ方をする日本語の表現を歴史的・計量的に分析し、実は「乱れ」と見えたものもそれなりの背景や理由があることを分かりやすく説明している。言語現象に対する切り口も... [続きを読む]
北大ではどこにある?
「日本語の乱れ」ということが時々メディアを賑わせる。しかし、これは言ってみればジャーナリズムや素朴な庶民感覚レベルの言い方で、その背後には(どこかに)“正しい(あるいは美しい)”日本語のあるべき用い方がある(はずだ)という一種の思い込みが隠れている。言語研究の観点から言えばこれが「乱れ」ではなく「変化」や「揺れ」であることは専門家の間では周知のことである。この本は、多様な現れ方をする日本語の表現を歴史的・計量的に分析し、実は「乱れ」と見えたものもそれなりの背景や理由があることを分かりやすく説明している。言語現象に対する切り口も... [続きを読む] -
推薦者 : 水本 秀明 (外国語教育センター・その他)
日本初の本格的な日本語・フィンランド語辞典
日本語・フィンランド語辞典 = Japani-Suomi sanakirja / 日本フィンランド協会編. - 日本フィンランド協会, 2017
 北大ではどこにある?
企画から約20年、何度か頓挫しかけた日本語・フィンランド語辞典が日本フィンランド語協会の手でやっと2017年2月完成しました。フィン日、フィン英辞典はこれまでそれなりのものが手に入りましたが、日フィン辞典としては日本初の本格的なものです。学習用にぜひ利用してください。2017年6月には電子版もリリース予定です。
北大ではどこにある?
企画から約20年、何度か頓挫しかけた日本語・フィンランド語辞典が日本フィンランド語協会の手でやっと2017年2月完成しました。フィン日、フィン英辞典はこれまでそれなりのものが手に入りましたが、日フィン辞典としては日本初の本格的なものです。学習用にぜひ利用してください。2017年6月には電子版もリリース予定です。 -
推薦者 : 小泉 均 (工学研究院・教員)
英語に関する素朴な疑問について、英語の歴史に基づき答える本
はじめての英語史 : 英語の「なぜ?」に答える / 堀田隆一. - 研究社, 2016
 北大ではどこにある?
英語に関する素朴な疑問について、英語の歴史に基づき答えている本である。なぜ母音で始まる単語の前の不定冠詞はanで子音で始まる単語の前はaなのか?(通常の英文法の解説とは逆で、oneの弱形のanがはじめにあり、子音で始まる単語では、子音が連続するためnが脱落した)、数詞oneに対して、なぜ1番目はfirstなのか?なぜ日本語では姓+名の順なのに、英語では名+姓の順なのかなど興味深い話題が多い。このような事を知らなくても、英語の習得には支障はないのかもしれない。しかし、そうなる理由がわかっている方が記憶に残るし、英語に対する興味が増す。英語の修得に、必ず... [続きを読む]
北大ではどこにある?
英語に関する素朴な疑問について、英語の歴史に基づき答えている本である。なぜ母音で始まる単語の前の不定冠詞はanで子音で始まる単語の前はaなのか?(通常の英文法の解説とは逆で、oneの弱形のanがはじめにあり、子音で始まる単語では、子音が連続するためnが脱落した)、数詞oneに対して、なぜ1番目はfirstなのか?なぜ日本語では姓+名の順なのに、英語では名+姓の順なのかなど興味深い話題が多い。このような事を知らなくても、英語の習得には支障はないのかもしれない。しかし、そうなる理由がわかっている方が記憶に残るし、英語に対する興味が増す。英語の修得に、必ず... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
言語をめぐる思惟を広く捉えるために
ドイツ言語哲学の諸相 / 麻生建. - 東京大学出版会, 1989
 北大ではどこにある?
以前奨めてくれる人があって、飯田隆『言語哲学大全Ⅰ~Ⅳ』(勁草書房)を読んでみたことがある。確かに現代の言語哲学、あるいは分析哲学をフレーゲからデヴィッドソンまで熱く語っている良書ではあるのだが、これをもって「大全」ということには大きな不満を覚える。その点は飯田氏も分かっているようで、第Ⅰ巻の冒頭で「『大全』というのは、さすがに私にしても調子に乗り過ぎという感がしないでもない」と書いている。この本を「大全」と言ってほしくないのは、対象がフレーゲとヴィトゲン... [続きを読む]
北大ではどこにある?
以前奨めてくれる人があって、飯田隆『言語哲学大全Ⅰ~Ⅳ』(勁草書房)を読んでみたことがある。確かに現代の言語哲学、あるいは分析哲学をフレーゲからデヴィッドソンまで熱く語っている良書ではあるのだが、これをもって「大全」ということには大きな不満を覚える。その点は飯田氏も分かっているようで、第Ⅰ巻の冒頭で「『大全』というのは、さすがに私にしても調子に乗り過ぎという感がしないでもない」と書いている。この本を「大全」と言ってほしくないのは、対象がフレーゲとヴィトゲン... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「日本語を教える」現場の熱気を伝える
世界の日本語教室から-日本を伝える30ヵ国の日本語教師レポート- / 国際交流基金. - アルク, 2009
 北大ではどこにある?
ここ何年か国際教育研究センターで(旧留学生センター時代から)全学教育科目に「外国人に日本語を教える」という「総合科目」を提供している。受講動機は様々であろうが日本語教育に関心を持ってくれる学生が一定数いるようで関係者としては有り難く思っている。この本は、そんな、日本語教育に関心を持っている学生がちょっとだけその―特に海外の―現場を覗いてみたいと思った時に気軽に読めるものとして紹介しておきたい。内容は、外務省の外郭団体である国際交流基金が世界各国に派遣した日本語教育専門家の手になる現地レポートである。日本語教育の現場の雰囲気を少しで... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ここ何年か国際教育研究センターで(旧留学生センター時代から)全学教育科目に「外国人に日本語を教える」という「総合科目」を提供している。受講動機は様々であろうが日本語教育に関心を持ってくれる学生が一定数いるようで関係者としては有り難く思っている。この本は、そんな、日本語教育に関心を持っている学生がちょっとだけその―特に海外の―現場を覗いてみたいと思った時に気軽に読めるものとして紹介しておきたい。内容は、外務省の外郭団体である国際交流基金が世界各国に派遣した日本語教育専門家の手になる現地レポートである。日本語教育の現場の雰囲気を少しで... [続きを読む] -
推薦者 : 小俣 友輝 (URAステーション・その他)
言葉の違い、考え方の違いは面白い!
翻訳できない世界のことば / エラ・フランシス・サンダース著イラスト ; 前田まゆみ訳. - 創元社, 2016
 北大ではどこにある?
生まれたところ、住んでいるところが違えば、人の気持ちやことばも違ってくるようです。
北大ではどこにある?
生まれたところ、住んでいるところが違えば、人の気持ちやことばも違ってくるようです。
様々な国で使われていることばが表すものは、外国人である自分の想像を超えているにも関わらず、なるほどと思えるものでした。
新しいものの見方・考え方に触れられるのと同時に、ことばを使う世界の人々とのつながりをも感じるのでした。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
おじさんも、若い人も語学を楽しむために
おじさん、語学する / 塩田勉. - 集英社, 2001
 北大ではどこにある?
あるきっかけからフランス語を勉強することになったおじさんの奮闘記、という形をとって語学を身につけるための秘訣と、それだけでなく異文化との関わり方を気づかせてくれるユニークな本。語学大好きな人にも語学嫌いな人にもお薦めしたい。
北大ではどこにある?
あるきっかけからフランス語を勉強することになったおじさんの奮闘記、という形をとって語学を身につけるための秘訣と、それだけでなく異文化との関わり方を気づかせてくれるユニークな本。語学大好きな人にも語学嫌いな人にもお薦めしたい。
ただ、悲しいかな外国語の先生は日本語はお得意ではないようで、この中にも日本語の間違いが一箇所ある。探してみてほしい。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「辞書にはドラマがある」
<辞書屋>列伝-言葉に憑かれた人びと- / 田澤耕. - 中央公論新社, 2014
 北大ではどこにある?
以前の推薦文に、最近岩波新書(新赤版)がつまらなくなってきた、と書いたが、最近の新書(岩波に限らない)ときたら、もう池上彰、佐藤優、島田裕巳、内田樹ばかり目立つ(少し前ならこれに香山リカも入っていた)。商業的に売れる本を書きたいというのは出版社の本音だろうし、若者の読書離れなどということも言われる中で出版社の新書編集部も大変だろうなぁとは思うが、こうも顔ぶれが変わらないと彼らの熱烈なファンでない限り購買意欲が逆にそがれてしまう。それにしても、この四人はよくも新書の大量執筆ができるもので、その点はうらやましい限りである。
北大ではどこにある?
以前の推薦文に、最近岩波新書(新赤版)がつまらなくなってきた、と書いたが、最近の新書(岩波に限らない)ときたら、もう池上彰、佐藤優、島田裕巳、内田樹ばかり目立つ(少し前ならこれに香山リカも入っていた)。商業的に売れる本を書きたいというのは出版社の本音だろうし、若者の読書離れなどということも言われる中で出版社の新書編集部も大変だろうなぁとは思うが、こうも顔ぶれが変わらないと彼らの熱烈なファンでない限り購買意欲が逆にそがれてしまう。それにしても、この四人はよくも新書の大量執筆ができるもので、その点はうらやましい限りである。
閑話... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
日本語研究の面白さに触れる
ヴァーチャル日本語役割語の謎 / 金水敏. - 岩波書店, 2003
 北大ではどこにある?
最近は学問研究、あるいは学術研究の対象化のペースが極度に速くなっていて、ついこの間「オネエ言葉」という表現が使われ出したと思ったらもうオネエ言葉の研究書が出ている、といった具合である。この本は、様々な職業・性別・時代等々に応じて現れる固有の(と見える)表現を「役割語」という概念によって分析することで見えてくる日本語の姿を明らかにしたものであるが、古今東西の文学作品からマンガ、はては『スター・ウォーズ』から『ハリー・ポッター』まで題材にしてまさに縦横無尽に切りまくる、読み応えのある一冊となっている。日本語に興味はあるが難しそうで... [続きを読む]
北大ではどこにある?
最近は学問研究、あるいは学術研究の対象化のペースが極度に速くなっていて、ついこの間「オネエ言葉」という表現が使われ出したと思ったらもうオネエ言葉の研究書が出ている、といった具合である。この本は、様々な職業・性別・時代等々に応じて現れる固有の(と見える)表現を「役割語」という概念によって分析することで見えてくる日本語の姿を明らかにしたものであるが、古今東西の文学作品からマンガ、はては『スター・ウォーズ』から『ハリー・ポッター』まで題材にしてまさに縦横無尽に切りまくる、読み応えのある一冊となっている。日本語に興味はあるが難しそうで... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
ことばはどのように情報を伝えるのか?
文法と談話の接点-日本語の談話における主題展開機能の研究- / 砂川有里子. - くろしお出版, 2005
 北大ではどこにある?
この本は、本格的な専門書であるが、丹念に読んでいけばきちんと分かるように書かれた本であり、日本語の働き方について新しい知見を与えてくれるものである。専門的に言えば、談話文法を機能言語学的に考察したものであるが、その内容を噛み砕いて言うならば、日本語の中でどのように情報が情報として現れそれが伝えられていくか、そのメカニズムを明らかにしたものである。将来日本語について研究してみたいと考えている人や、既に談話文法に関心のある人に広く一読を勧めたい。
北大ではどこにある?
この本は、本格的な専門書であるが、丹念に読んでいけばきちんと分かるように書かれた本であり、日本語の働き方について新しい知見を与えてくれるものである。専門的に言えば、談話文法を機能言語学的に考察したものであるが、その内容を噛み砕いて言うならば、日本語の中でどのように情報が情報として現れそれが伝えられていくか、そのメカニズムを明らかにしたものである。将来日本語について研究してみたいと考えている人や、既に談話文法に関心のある人に広く一読を勧めたい。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
日本語教育史研究の金字塔、ついに成る!
戦時期における日本語・日本語教育論の諸相-日本言語文化政策論序説- / 田中寛. - ひつじ書房, 2015
 北大ではどこにある?
長年にわたって、日本語教育史、日本語教育政策の研究に携わってこられた著者の業績の集大成とも言える大著である。副題に「序説」とあるが、決して「序説」ではなく、日本語教育の過去の歴史を批判的に受け止め、これと対決しながら日本語教育のあるべき姿を真摯に問うたその解答と言うべき著作である。今後の日本語教育史研究、日本語教育政策研究は、本書と、これに先行した関正昭『日本語教育史研究序説』(スリーエーネットワーク)を不可欠の必読書として出発しなければならない。まさに今、日本語教育史研究の“新しい”歴史が始まる。本書はその幕開けとなるものと... [続きを読む]
北大ではどこにある?
長年にわたって、日本語教育史、日本語教育政策の研究に携わってこられた著者の業績の集大成とも言える大著である。副題に「序説」とあるが、決して「序説」ではなく、日本語教育の過去の歴史を批判的に受け止め、これと対決しながら日本語教育のあるべき姿を真摯に問うたその解答と言うべき著作である。今後の日本語教育史研究、日本語教育政策研究は、本書と、これに先行した関正昭『日本語教育史研究序説』(スリーエーネットワーク)を不可欠の必読書として出発しなければならない。まさに今、日本語教育史研究の“新しい”歴史が始まる。本書はその幕開けとなるものと... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「まとも」な議論をするために
反論の技術-その意義と訓練方法- / 香西秀信. - 明治書院, 1995
 北大ではどこにある?
この本は実は一時期僕の日本語の授業のタネ本であった。どのようにしたら留学生に、与えた課題とかみ合う文章(議論)を書けるように指導できるのか困っていたときにこの本に出会って、その説得力ある書きぶりと豊富な実例に蒙を啓かれる思いがしたものである。(ただ、正直、この本の助けを借りて行った授業実践に対する留学生の反応は賛否真っ二つであった。)
北大ではどこにある?
この本は実は一時期僕の日本語の授業のタネ本であった。どのようにしたら留学生に、与えた課題とかみ合う文章(議論)を書けるように指導できるのか困っていたときにこの本に出会って、その説得力ある書きぶりと豊富な実例に蒙を啓かれる思いがしたものである。(ただ、正直、この本の助けを借りて行った授業実践に対する留学生の反応は賛否真っ二つであった。)
書名に「技術」と書いてあるが、所謂ハウツー本の域を超えて「反論する」ということが学問にとっていかに重要な知的営為かを詳しく説いており、読み物としてもおもしろい。この本に書いてある「訓練方法」を実践... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
ちょっと残念な、しかし面白い対談
対論 言語学が輝いていた時代 / 鈴木孝夫・田中克彦. - 岩波書店, 2008
 北大ではどこにある?
鈴木孝夫と田中克彦のお二人は、特に日本語に於ける漢字の使用を巡ってそれぞれの著書の中でまったく反対の立場を表明してきた。この本ではそのあたりを巡って激論が交わされるのかと思いきや、お二人とも妙におとなしくなってしまっていて(よく言えば紳士的なのかもしれないが)日頃の舌鋒の鋭さはどこへやら、落としどころをうまく見つけて話が進んでしまっている。これはちょっと読者の期待を裏切りすぎるんじゃないのかなぁ、と思う。日本語教師の僕としては、日本語教育に好意的な鈴木氏と、(今の)日本語教育に批判的な田中氏の論争も期待したのだが、それはタイトルが... [続きを読む]
北大ではどこにある?
鈴木孝夫と田中克彦のお二人は、特に日本語に於ける漢字の使用を巡ってそれぞれの著書の中でまったく反対の立場を表明してきた。この本ではそのあたりを巡って激論が交わされるのかと思いきや、お二人とも妙におとなしくなってしまっていて(よく言えば紳士的なのかもしれないが)日頃の舌鋒の鋭さはどこへやら、落としどころをうまく見つけて話が進んでしまっている。これはちょっと読者の期待を裏切りすぎるんじゃないのかなぁ、と思う。日本語教師の僕としては、日本語教育に好意的な鈴木氏と、(今の)日本語教育に批判的な田中氏の論争も期待したのだが、それはタイトルが... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
人の振り見て我が振り直せ
カネを積まれても使いたくない日本語 / 内館牧子. - 朝日新聞出版, 2013
 北大ではどこにある?
最近の出版業界は「脅迫産業」めいてきたところがあり、本の表題にやたらと「知らないと恥をかく~」だの「あなたもきっとだまされる」だの「~のウソ」だの「その○○は恥をかく」だの、これでもかとばかりに読者を不安がらせ(て買わせ)ようとするフレーズを入れるものが多い。こういった表題の本は、おおむね中身はたいしたことがないので買わないことにしているが、ここに挙げた内館氏の本は、その大仰な表題に似合わず、今使われている、あまり適切とは言えないことばづかいを丁寧に拾い上げて論評しており、まさに「人の振り見て我が振り直せ」で、自分の日本語の使... [続きを読む]
北大ではどこにある?
最近の出版業界は「脅迫産業」めいてきたところがあり、本の表題にやたらと「知らないと恥をかく~」だの「あなたもきっとだまされる」だの「~のウソ」だの「その○○は恥をかく」だの、これでもかとばかりに読者を不安がらせ(て買わせ)ようとするフレーズを入れるものが多い。こういった表題の本は、おおむね中身はたいしたことがないので買わないことにしているが、ここに挙げた内館氏の本は、その大仰な表題に似合わず、今使われている、あまり適切とは言えないことばづかいを丁寧に拾い上げて論評しており、まさに「人の振り見て我が振り直せ」で、自分の日本語の使... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
日本語教育に関わりたい人に
日本のことばとこころ / 山下秀雄. - 講談社, 1986
 北大ではどこにある?
日本語教師として30年近く働いてきてまだ人生を回顧するのは早すぎると思うけれども、この仕事を選んだ自分にとって「恩師」と呼べる先生は3人いる。この推薦書の著者である山下秀雄先生もそのお一人で、講習会や研究会で多くのことを教えていただき、海外に教えに行っていたときにもいろいろと心配りをしていただいた。先生は、平成10年9月に交通事故で亡くなられ、その前日の夕刻に僕に宛てて出されたお手紙がこの世での最後の書簡となった。それは今も僕の手元にある。
北大ではどこにある?
日本語教師として30年近く働いてきてまだ人生を回顧するのは早すぎると思うけれども、この仕事を選んだ自分にとって「恩師」と呼べる先生は3人いる。この推薦書の著者である山下秀雄先生もそのお一人で、講習会や研究会で多くのことを教えていただき、海外に教えに行っていたときにもいろいろと心配りをしていただいた。先生は、平成10年9月に交通事故で亡くなられ、その前日の夕刻に僕に宛てて出されたお手紙がこの世での最後の書簡となった。それは今も僕の手元にある。
本書は、山下先生が、日本語教師としての長年の経験と研究から、外国語としての日本語を見るための目を... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
読み物として面白い文章読本
思考のための文章読本 / 長沼行太郎. - 筑摩書房, 1998
 北大ではどこにある?
ここ何年か、「一般教育演習(フレッシュマンセミナー)」で日本語文章表現関係の授業を開講しており、その参考とするためにあれこれの文章読本を45冊ほど読んで、今46冊目を読んでいる。率直に言って授業の素材として役に立ったものはほとんどなく、推奨できるものは4、5冊程度である。そして、これらの推奨できる数少ない本も、どう言ってみても結局はハウツー本であり、面白さという点ではほとんど期待できない。その中にあって、長沼氏のこの本は唯一と言っていいほど読み物としての面白さがある文章読本である。この本を通して読者は、文章作成の根本にある「問い」を立てる... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ここ何年か、「一般教育演習(フレッシュマンセミナー)」で日本語文章表現関係の授業を開講しており、その参考とするためにあれこれの文章読本を45冊ほど読んで、今46冊目を読んでいる。率直に言って授業の素材として役に立ったものはほとんどなく、推奨できるものは4、5冊程度である。そして、これらの推奨できる数少ない本も、どう言ってみても結局はハウツー本であり、面白さという点ではほとんど期待できない。その中にあって、長沼氏のこの本は唯一と言っていいほど読み物としての面白さがある文章読本である。この本を通して読者は、文章作成の根本にある「問い」を立てる... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
英語と格闘した日本人の足跡を辿る
日本英学のあけぼの-幕末・明治の英語学- / 惣郷正明. - 創拓社, 1990
 北大ではどこにある?
20年以上まえに出たこの本を今頃推薦するのは実は大変恥ずかしい。というのは、出版されてから割合すぐに買い求めたのだけれど、最近まで“本棚の肥やし”にしてあって読んでいなかったからである。(言い訳すれば、昔、僕の恩師も「20年前に買った本がまだ読めないんだ」とぼやいていたので、同じようなことは案外あるのかもしれない。)
北大ではどこにある?
20年以上まえに出たこの本を今頃推薦するのは実は大変恥ずかしい。というのは、出版されてから割合すぐに買い求めたのだけれど、最近まで“本棚の肥やし”にしてあって読んでいなかったからである。(言い訳すれば、昔、僕の恩師も「20年前に買った本がまだ読めないんだ」とぼやいていたので、同じようなことは案外あるのかもしれない。)
「英学」という表題はいかめしいが、要するに日本人が英語と接して以来、どのようにこの言語を勉強しようと工夫なり悪戦苦闘なりを重ねてきたかの歴史が描かれているものであり、具体的な教科書や参考書や辞書、果てはかなり怪しげな学... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
short talks about language and linguistics
The 5 Minute Linguist: Bite-Sized Essays on Language and Languages, 2nd edition / E. M. Rickerson (Author, Editor), Barry Hilton (Editor). - Equinox Publishing, 2012
 北大ではどこにある?
Did you know that 75 percent of the world's population speaks more than 1 language?
北大ではどこにある?
Did you know that 75 percent of the world's population speaks more than 1 language?
'The 5-minute linguist' explains various topics on language and linguistics.
Learn, for example, what it means to be bilingual (that is, speaking 2 languages), or how many languages we can learn.
The series started as an audio program developed in 2005 by the College of Charleston and the National Museum of Language. The book is based on that radio program.
Download the audio files for free from iTunes U (http://itunes.apple.com/us/itunes-u/the-five-minute-linguist/id452255394 -- accessed 2012-07-20). -
推薦者 : 高橋 英光 (文学研究科)
北大の全学教育から誕生した言語学の本
言葉のしくみー認知言語学のはなしー / 高橋英光. - 北海道大学出版会, 2010
 北大ではどこにある?
なぜ言葉は自分の思いをそのまま伝えてくれないのか、なぜ母語の学習はふつう成功するのに外国語の学習は失敗するのか、交通標識などの記号と言語の共通点は何か相違点は何か、日本語は特殊な言葉か否か、日本語のようなS0V言語と英語のようなSVO言語はどちらが多いのか、ヒトはなぜメタファーが好きなのか、「明日は忙しくて、ごめんなさい」はなぜ断りになるのか、そもそもなぜどの言語にも語彙と文法があるのか、などの疑問をもったことはないだろうか。
北大ではどこにある?
なぜ言葉は自分の思いをそのまま伝えてくれないのか、なぜ母語の学習はふつう成功するのに外国語の学習は失敗するのか、交通標識などの記号と言語の共通点は何か相違点は何か、日本語は特殊な言葉か否か、日本語のようなS0V言語と英語のようなSVO言語はどちらが多いのか、ヒトはなぜメタファーが好きなのか、「明日は忙しくて、ごめんなさい」はなぜ断りになるのか、そもそもなぜどの言語にも語彙と文法があるのか、などの疑問をもったことはないだろうか。
本書は、これらの疑問に触れながら言葉のしくみを丁寧に噛み砕いて説明する。豊富なエピソードとイラストを用い... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
一つの国を知るということ
オーストラリアの言語教育政策 / 青木麻衣子. - 東信堂, 2008
 北大ではどこにある?
オーストラリアという国は、私が小学生の頃(!)は「白豪主義」というキーワードとともに社会科で教えられていた。しかし、その後この国は「白豪主義」から「多文化主義」へと大きな方針転換を遂げることになる。本書は、オーストラリアの言語教育政策に焦点を絞って、上記の方針転換過程でそこに浮かび上がる「国家統合」と「多文化主義」の緊張関係を明らかにした労作である。しかし、ただ言語教育政策の検討だけでなく、(比較)教育研究や地域研究、マイノリティ研究に関してもこの本が提供してくれる知見は多い。広い意味での社会科学研究とは何かを、そしてまた、その方法... [続きを読む]
北大ではどこにある?
オーストラリアという国は、私が小学生の頃(!)は「白豪主義」というキーワードとともに社会科で教えられていた。しかし、その後この国は「白豪主義」から「多文化主義」へと大きな方針転換を遂げることになる。本書は、オーストラリアの言語教育政策に焦点を絞って、上記の方針転換過程でそこに浮かび上がる「国家統合」と「多文化主義」の緊張関係を明らかにした労作である。しかし、ただ言語教育政策の検討だけでなく、(比較)教育研究や地域研究、マイノリティ研究に関してもこの本が提供してくれる知見は多い。広い意味での社会科学研究とは何かを、そしてまた、その方法... [続きを読む] -
推薦者 : 清水 誠 (文学研究科)
比較言語学の最前線
East and West. Papers in Indo-European Studies / Kazuhiko Yoshida, Brent Vine (eds.). - Ute Hempen, 2009
 北大ではどこにある?
インドからヨーロッパ全域までに広がり、世界中に伝播した印欧語は、私たちが学んでいる英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、スペイン語などをすべて含んだ世界最大の大言語群です。歴史的系統関係を同一にする印欧諸語は、古くからの豊富な文献を備え、グリム兄弟たちが活躍した19世紀にその礎が築かれました。これをもって、言語学が初めて独立した学問分野として誕生したのです。この本はその研究の最前線を日本のすぐれた研究者たちが主導しつつ、世界のトップレベルの研究者たちと共同研究した成果が再録されています。編者の吉田和彦先生は京都大学言語学科教授で、... [続きを読む]
北大ではどこにある?
インドからヨーロッパ全域までに広がり、世界中に伝播した印欧語は、私たちが学んでいる英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、スペイン語などをすべて含んだ世界最大の大言語群です。歴史的系統関係を同一にする印欧諸語は、古くからの豊富な文献を備え、グリム兄弟たちが活躍した19世紀にその礎が築かれました。これをもって、言語学が初めて独立した学問分野として誕生したのです。この本はその研究の最前線を日本のすぐれた研究者たちが主導しつつ、世界のトップレベルの研究者たちと共同研究した成果が再録されています。編者の吉田和彦先生は京都大学言語学科教授で、... [続きを読む] -
推薦者 : 高見 敏子 (メディア・コミュニケーション研究院)
2年間で英語を100万語読もう―英語多読図書の薦め
英語多読図書 (Penguin Readers, Macmillan Readersほか) / . - ピアソンエデュケーション他,
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
楽しみながら中国語を学ぶ入門書
ウーロン茶のCMソングから中国語を始めませんか? / amin著. - 小学館,
 北大ではどこにある?
おなじみの烏龍茶CMソングの歌詞から、楽しみながら中国語を学ぶ入門書。中国人歌手として史上初のNHK紅白歌合戦出場を果たしたamin(阿明)自らが吹きこんだ解説CD付き。中国人の前で歌がうたえれば絶対ウケるし、なにより楽しい。楽しいがいちばん!
北大ではどこにある?
おなじみの烏龍茶CMソングの歌詞から、楽しみながら中国語を学ぶ入門書。中国人歌手として史上初のNHK紅白歌合戦出場を果たしたamin(阿明)自らが吹きこんだ解説CD付き。中国人の前で歌がうたえれば絶対ウケるし、なにより楽しい。楽しいがいちばん! -
推薦者 : 清水 誠 (文学研究科)
未知の言語の全体像が手に取るようにわかる
「言葉のしくみ」シリーズ / . - 白水社, 2005-
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 吉野 悦雄 (経済学研究科)
正しい日本語を書くために
日本語文法セルフ・マスターシリーズ / 寺村秀夫企画・編集 全7巻 / 野田尚史 ほか. - くろしお出版, 1986
 北大ではどこにある?
問 次の(1)〜(4)のうち日本語として誤っているものを選びない(複数回答可)。
北大ではどこにある?
問 次の(1)〜(4)のうち日本語として誤っているものを選びない(複数回答可)。
(1)今日の夜は図書館は何時まで開いていますか。
(2)今日の夜は図書館が何時まで開いていますか。
(3)象の鼻は長い。
(4)象は鼻が長い。
この解(正解はこの文章の最後にあります)を間違えた方,少し考えこんだ方には次の全7巻の本,特に第1巻をお薦めします。出版者などは上記のとおりです。
第1巻 はとが / 野田尚史著
第2巻 する・した・している / 砂川有里子... [続きを読む] -
推薦者 : 清水 誠 (文学研究科)
世界のことばの多様性に目を向けよう
世界のことば・出会いの表現辞典 / 石井米雄・千野栄一(編). - 三省堂, 2004
 北大ではどこにある?
同じ人間に生まれて、外国語ほど不思議なものはありません。大学生になったことを実感するのは、多くの場合、英語以外の外国語を学ぶという、時には苦しい体験を通じてではないでしょうか。現在、世界で起こっているさまざまの問題も、ことばを通じてとらえ直すとき、別の角度から問題の本質が見えてくることがあります。世界の言語は本当に多様であって、異質な歴史的文化的背景の一端を垣間見るとき、だれでも大きな驚きを覚えることでしょう。
北大ではどこにある?
同じ人間に生まれて、外国語ほど不思議なものはありません。大学生になったことを実感するのは、多くの場合、英語以外の外国語を学ぶという、時には苦しい体験を通じてではないでしょうか。現在、世界で起こっているさまざまの問題も、ことばを通じてとらえ直すとき、別の角度から問題の本質が見えてくることがあります。世界の言語は本当に多様であって、異質な歴史的文化的背景の一端を垣間見るとき、だれでも大きな驚きを覚えることでしょう。
ことばそのものは、すべての話者にとって本質的に固有で、しかも平等なものであるはずです。わたしたち日本人には、日本... [続きを読む] -
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
変容著しい東北アジアの文化と言語の現在を読み解く!
東北アジア諸民族の文化動態 / 煎本孝編著. - 北海道大学図書刊行会, 2002.2
 北大ではどこにある?
日本、ロシア、中国、モンゴルを含む東北アジアには、広大で多様な環境が展開している。それは、民族学(文化人類学)的には北アジア、中央アジア、東アジアを含む地域である。生態的にも、地理的にもけっして閉鎖的な地域ではないこの多様な環境に生活する人々は、さまざまな文化と言語とをもっている。本書では東北アジアの文化と言語の動態を多角的に比較検討し、東北アジアの現在について考察する。
北大ではどこにある?
日本、ロシア、中国、モンゴルを含む東北アジアには、広大で多様な環境が展開している。それは、民族学(文化人類学)的には北アジア、中央アジア、東アジアを含む地域である。生態的にも、地理的にもけっして閉鎖的な地域ではないこの多様な環境に生活する人々は、さまざまな文化と言語とをもっている。本書では東北アジアの文化と言語の動態を多角的に比較検討し、東北アジアの現在について考察する。 -
推薦者 : 花井 一典 (文学研究科)
待望の名著復刊
ラテン広文典 / 泉井 久之助. - 白水社, 2005
 北大ではどこにある?
ラテン語入門書は数多いが、これはウェルギリウスの叙事詩『アエネイス』の翻訳や、言語学者フンボルトの紹介、研究で知られる一代の碩学がものしただけあって単なる語学書ではない。どの行間にも自ずと滲む底知れぬ無言の学識、悠揚迫らざるおおどかな叙述、それはひとつの作品の風格を備えており、読者は触角さえ伸ばせばどこからでも言語の深みにはまるようにできている。本書味読の後では人はラテン語の(否、総じて外国語の)修得を「ただの語学」呼ばわりすることを恥じるであろう。
北大ではどこにある?
ラテン語入門書は数多いが、これはウェルギリウスの叙事詩『アエネイス』の翻訳や、言語学者フンボルトの紹介、研究で知られる一代の碩学がものしただけあって単なる語学書ではない。どの行間にも自ずと滲む底知れぬ無言の学識、悠揚迫らざるおおどかな叙述、それはひとつの作品の風格を備えており、読者は触角さえ伸ばせばどこからでも言語の深みにはまるようにできている。本書味読の後では人はラテン語の(否、総じて外国語の)修得を「ただの語学」呼ばわりすることを恥じるであろう。 -
推薦者 : 園田 勝英 (言語文化部)
最良の英単語参考書
英語語義イメージ辞典 / 政村秀實著 ; Paulus Pimomo英文校閲. - 大修館書店, 2002.5
 北大ではどこにある?
『永久記憶の英単語』、『ネイティブスピーカーの単語力』、『語源とイラストで一気に覚える英単語』、などなど。あの手この手の書名とともに売り出される英単語の参考書の数は、おそらく明治以来数百冊になるであろう。このように数ある英単語参考書の中で私が現在もっとも良いと思っているのがこの本である。約3,000の見出し語について、発音記号、定訳、原義... [続きを読む]
北大ではどこにある?
『永久記憶の英単語』、『ネイティブスピーカーの単語力』、『語源とイラストで一気に覚える英単語』、などなど。あの手この手の書名とともに売り出される英単語の参考書の数は、おそらく明治以来数百冊になるであろう。このように数ある英単語参考書の中で私が現在もっとも良いと思っているのがこの本である。約3,000の見出し語について、発音記号、定訳、原義... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
Historical linguistics at its best
The American heritage dictionary of Indo-European roots / revised and edited by Calvert Watkins. - Houghton Mifflin, 2000
 北大ではどこにある?
Archaeology tells us where ancient people lived, what food they ate, what tools they used. But it doesn't tell us much about their religion, family structure, or knowledge of the world. Language tells
北大ではどこにある?
Archaeology tells us where ancient people lived, what food they ate, what tools they used. But it doesn't tell us much about their religion, family structure, or knowledge of the world. Language tells
us more than material artifacts.
Watkin's book is mostly a dictionary. Read the introduction (not the dictionary) to learn how people 8,000 years ago viewed the world. The Indo-European family of languages includes English, Dutch, Danish, French, German, Latin, Greek and Sanskrit. Their ancestors spoke a common language. By reconstructing a common ancestral language, we learn more than the remaining historical record.
From words common in all existing languages, we know the proto-Indo-Europeans (as they are called) formed a patriarchal society, kept livestock, drank honey, celebrate... [続きを読む]