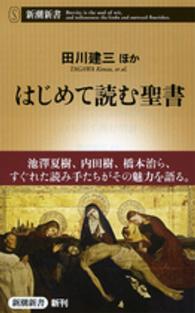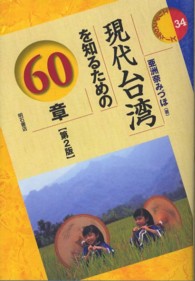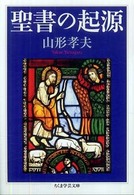-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
宗教を信じつつ宗教を超える
はじめて読む聖書 / 田川建三ほか著. - 新潮社, 2014
 北大ではどこにある?
この本を推薦するのは、僕がキリスト教徒であるからでもなく、『聖書』にありがたみを感じているからでもない。どのような本にせよ、読み手の体験を通してその内面と響き合うものでなければそもそも本を読む意味はないということをこの本の中の第Ⅳ章「レヴィナスを通して読む『旧約聖書』」(内田樹)が慄然たる厳しさを持って教えてくれるからである。この本を手にした人は全部読まなくても良い(読めば読んだでそれなりに得るものはあろうけれども)が、上記の箇所だけはじっくりと読んで欲しい。その上で、関心があればレヴィナスの本に向かうこともお勧めする。わかり... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本を推薦するのは、僕がキリスト教徒であるからでもなく、『聖書』にありがたみを感じているからでもない。どのような本にせよ、読み手の体験を通してその内面と響き合うものでなければそもそも本を読む意味はないということをこの本の中の第Ⅳ章「レヴィナスを通して読む『旧約聖書』」(内田樹)が慄然たる厳しさを持って教えてくれるからである。この本を手にした人は全部読まなくても良い(読めば読んだでそれなりに得るものはあろうけれども)が、上記の箇所だけはじっくりと読んで欲しい。その上で、関心があればレヴィナスの本に向かうこともお勧めする。わかり... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
イスラム教を「信じる」とはどのようなことか
日本の中でイスラム教を信じる / 佐藤兼永. - 文藝春秋社, 2015
 北大ではどこにある?
日本社会の中ではイスラム教信者、中でも特に日本人の信者というのは姿が見えにくい存在である。この本は、日本社会の中でイスラム教信仰に生きる人びとの姿を描いたルポルタージュであり、イスラム世界というものが西アジア・中東・アフリカという遠いところにある(だけな)のではなく、我々のすぐそばにもあるものだということに気づかせてくれる。現在、多少緩和されたとはいえ、まだイスラム教に対する様々な偏見が社会の中に存在することは否定できない。著者の佐藤氏は、その偏見を我々も持つことを認めた上でそれを肯定的なものへと転換する契機を示してくれている... [続きを読む]
北大ではどこにある?
日本社会の中ではイスラム教信者、中でも特に日本人の信者というのは姿が見えにくい存在である。この本は、日本社会の中でイスラム教信仰に生きる人びとの姿を描いたルポルタージュであり、イスラム世界というものが西アジア・中東・アフリカという遠いところにある(だけな)のではなく、我々のすぐそばにもあるものだということに気づかせてくれる。現在、多少緩和されたとはいえ、まだイスラム教に対する様々な偏見が社会の中に存在することは否定できない。著者の佐藤氏は、その偏見を我々も持つことを認めた上でそれを肯定的なものへと転換する契機を示してくれている... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「思想劇」としての般若心経
真釈般若心経 / 宮坂宥洪. - 角川書店, 2004
 北大ではどこにある?
この本の表題は書き間違いではない。「新釈」ではなく「真釈」、つまり著者は「俺の解釈こそ本物だ!」と宣言しているわけである。もの凄い自信である。仏教学が専門ではない僕には、その「真」の度合いは測れないが、内容は確かに説得力に富む。それはひとえに、サンスクリット原典を文法的に厳密にたどりながら漢訳般若心経の問題点を的確に指摘し「四階の建物の比喩」という説明の枠組みを駆使して読み解いていく著者の態度からもたらされるものである。それだけに「あとがき」に書かれた、従来の般若心経解説書やそれらの執筆者に対する批判は秋霜烈日を極める。著者は... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本の表題は書き間違いではない。「新釈」ではなく「真釈」、つまり著者は「俺の解釈こそ本物だ!」と宣言しているわけである。もの凄い自信である。仏教学が専門ではない僕には、その「真」の度合いは測れないが、内容は確かに説得力に富む。それはひとえに、サンスクリット原典を文法的に厳密にたどりながら漢訳般若心経の問題点を的確に指摘し「四階の建物の比喩」という説明の枠組みを駆使して読み解いていく著者の態度からもたらされるものである。それだけに「あとがき」に書かれた、従来の般若心経解説書やそれらの執筆者に対する批判は秋霜烈日を極める。著者は... [続きを読む] -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
人びとの日常から台湾を学ぶ
暮らしがわかるアジア読本「台湾」 / 笠原政治, 植野弘子編. - 河出書房新社, 1995
 北大ではどこにある?
河出書房新社のアジア地域研究シリーズの1冊。政治・経済・教育・文化・宗教・日台関係、言語など様々なトピックを紹介しています。「暮らしがわかる」とあるように日常のひとコマや具体的な人々の話を中心に説明していますので、台湾の臨場感が伝わります。
北大ではどこにある?
河出書房新社のアジア地域研究シリーズの1冊。政治・経済・教育・文化・宗教・日台関係、言語など様々なトピックを紹介しています。「暮らしがわかる」とあるように日常のひとコマや具体的な人々の話を中心に説明していますので、台湾の臨場感が伝わります。 -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
より学術的な台湾の入門書
もっと知りたい台湾(第2版) / 若林正丈編. - 弘文堂, 1998
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
日本も案外、宗教的か?
宗教と社会のフロンティア―宗教社会学からみる現代日本 / 高橋典史, 塚田穂高, 岡本亮輔編著. - 勁草書房, 2012
 北大ではどこにある?
若手の研究者らによる宗教社会学の入門テキスト。
北大ではどこにある?
若手の研究者らによる宗教社会学の入門テキスト。
いわゆる宗教社会学の古典を開設するタイプのテキストではなく、現代日本において宗教が関係する社会現象をわかりやすく解説するタイプのテキストです。トピックごとにオムニバス形式にしてあります。参考文献や宗教調査の方法なども詳しく書かれていますので、発展的な学習もできます。 -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
気軽に読める現代台湾の概説書
現代台湾を知るための60章(第2版) / 亜洲奈みづほ. - 明石書店, 2012
 北大ではどこにある?
明石書店の地域研究シリーズの1冊。1章4~6ページの分量で、政治・経済・教育・文化・宗教・日台関係など様々なトピックを60章で紹介しています。内容も現代台湾に関する読み切り型のエッセイ・ルポルタージュ風のものが多いため、興味をもった箇所から気軽に読むことができます。現代台湾に興味をもったらまずは本書を手に取ってみると良いでしょう。
北大ではどこにある?
明石書店の地域研究シリーズの1冊。1章4~6ページの分量で、政治・経済・教育・文化・宗教・日台関係など様々なトピックを60章で紹介しています。内容も現代台湾に関する読み切り型のエッセイ・ルポルタージュ風のものが多いため、興味をもった箇所から気軽に読むことができます。現代台湾に興味をもったらまずは本書を手に取ってみると良いでしょう。 -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
エビデンスに基づく宗教の国際比較研究
Sacred and Secular :Religion and Politics Worldlwide (2nd ed) / Pippa Norris and Ronald Inglehart. - Cambridge University Press, 2011
 北大ではどこにある?
中級から上級向けの本(英語)。世界最大規模の国際比較価値観調査データの1つであるWorld Values Survey(世界価値観調査)を用いた宗教の計量的国際比較研究。ジェンダー意識、経済倫理、政治行動などに対する宗教の影響力はどうなっているのか、どう変化したのか、地域によってどう異なっているのか、などが論じられています。近年の欧米(特にアメリカ)における、宗教の国際比較研究の特徴を知る上でも有益な著作です。
北大ではどこにある?
中級から上級向けの本(英語)。世界最大規模の国際比較価値観調査データの1つであるWorld Values Survey(世界価値観調査)を用いた宗教の計量的国際比較研究。ジェンダー意識、経済倫理、政治行動などに対する宗教の影響力はどうなっているのか、どう変化したのか、地域によってどう異なっているのか、などが論じられています。近年の欧米(特にアメリカ)における、宗教の国際比較研究の特徴を知る上でも有益な著作です。
読むには宗教の知識や計量分析の基本知識が必要ですが、宗教学、社会学、政治学、社会心理学など幅広い専攻の人々にとって興味深い著作だと思います。 -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
タイの僧侶についての重厚な実証研究
東北タイの開発僧─宗教と社会貢献 / 櫻井義秀. - 梓出版, 2008
 北大ではどこにある?
タイにおいて教育や地域開発、福祉事業などの各種開発を行ういわゆる「開発僧」と呼ばれる僧侶たちへの丹念な聞き取り調査に基づいた実証的な宗教研究・地域研究。「宗教と社会貢献」「タイ研究の動向」「南部タイの暴力」などの大きな議論を踏まえたうえで、僧侶の実証研究が紹介される。
北大ではどこにある?
タイにおいて教育や地域開発、福祉事業などの各種開発を行ういわゆる「開発僧」と呼ばれる僧侶たちへの丹念な聞き取り調査に基づいた実証的な宗教研究・地域研究。「宗教と社会貢献」「タイ研究の動向」「南部タイの暴力」などの大きな議論を踏まえたうえで、僧侶の実証研究が紹介される。
実証研究の最大の目玉は、東北タイの三地点、約100名を超える僧侶の比較研究である。「開発僧」として著名な僧侶のみならず「一般的」な僧侶なども検討していくことで、地域社会における僧侶の役割、「開発僧」と「一般的」な僧侶の連続性、「開発僧」が「開発僧」たる上での政治的コン... [続きを読む] -
推薦者 : 戸田 聡 (文学研究科)
イエス・キリストってどんな人だったの?
イエスの影を追って / ゲルト・タイセン. - ヨルダン社, 1989
 北大ではどこにある?
聖書やキリスト教の中心的テーマはやはり何と言ってもイエス・キリストであり、そのイエスがどういう人物だったのかという問いは、そういう研究の根底にある問題だと言えます。学問的にイエスの生涯を論じた書物は他にも数多くあり、その意味では別の本も薦められますが(例えばE・P・サンダース『イエス』)、読み物としてはタイセンのこの本がお薦めです。
北大ではどこにある?
聖書やキリスト教の中心的テーマはやはり何と言ってもイエス・キリストであり、そのイエスがどういう人物だったのかという問いは、そういう研究の根底にある問題だと言えます。学問的にイエスの生涯を論じた書物は他にも数多くあり、その意味では別の本も薦められますが(例えばE・P・サンダース『イエス』)、読み物としてはタイセンのこの本がお薦めです。
実は、イエスの生涯を物語風に書いた本も既に数多く世に出ており(例えばモーリヤック、遠藤周作、三浦綾子)、それらもそれぞれに一読の価値がありますが、このタイセンという著者は、もともと新約聖書を専門的に研... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
誤解の連続は新たな思想を生むか
仏教、本当の教え-インド、中国、日本の理解と誤解- / 植木雅俊. - 中央公論新社, 2011
 北大ではどこにある?
大学で哲学を学んでいた時、先輩から「結局ドイツ観念論哲学というのは、フィヒテとシェリングとヘーゲルがカントをどのように“誤読”したかの歴史だ」と言われて、へえぇ、そんなもんなの、と思ったことがある。この本は、帯に書かれた「壮大な伝言ゲームの果てに。」という一句に惹かれて買ってしまったのだが、読んでみると結構面白かった。その面白さというのは、-著者には申し訳ないけれど-謂わば底意地の悪い面白さで、これまでの翻訳者(=謂わばその学問の世界ではお偉いさん)や、さらには道元や親鸞などの宗祖までもがどのように仏典を誤読してきたかが、宗教... [続きを読む]
北大ではどこにある?
大学で哲学を学んでいた時、先輩から「結局ドイツ観念論哲学というのは、フィヒテとシェリングとヘーゲルがカントをどのように“誤読”したかの歴史だ」と言われて、へえぇ、そんなもんなの、と思ったことがある。この本は、帯に書かれた「壮大な伝言ゲームの果てに。」という一句に惹かれて買ってしまったのだが、読んでみると結構面白かった。その面白さというのは、-著者には申し訳ないけれど-謂わば底意地の悪い面白さで、これまでの翻訳者(=謂わばその学問の世界ではお偉いさん)や、さらには道元や親鸞などの宗祖までもがどのように仏典を誤読してきたかが、宗教... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
『聖書』成立のドラマに迫る
聖書の起源 / 山形孝夫. - 筑摩書房, 2010
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「自分」の深奥をのぞく
砂漠の修道院 / 山形孝夫. - 平凡社, 1998
 北大ではどこにある?
ややもすれば抹香臭い表題ですが、エジプトの砂漠の修道院に引きつけられてきた人々の心の遍歴と葛藤、そのような心性を生み出すエジプトの社会と歴史が生き生きと描かれている、読み応えのある本です。特に修道士一人一人の聞き取り調査に基づくストーリーは、普段うかがい知ることが難しい「修道院」の生活と、そこに何かを求める魂のありようをキリスト教という枠組みを超えて明らかにしてくれます。キリスト者であってもなくてもここに描かれた修道士の誰かに、読者が共感できる人物を見つけることができると思います。「世間」と「自分」との葛藤をどう受け止めるかと... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ややもすれば抹香臭い表題ですが、エジプトの砂漠の修道院に引きつけられてきた人々の心の遍歴と葛藤、そのような心性を生み出すエジプトの社会と歴史が生き生きと描かれている、読み応えのある本です。特に修道士一人一人の聞き取り調査に基づくストーリーは、普段うかがい知ることが難しい「修道院」の生活と、そこに何かを求める魂のありようをキリスト教という枠組みを超えて明らかにしてくれます。キリスト者であってもなくてもここに描かれた修道士の誰かに、読者が共感できる人物を見つけることができると思います。「世間」と「自分」との葛藤をどう受け止めるかと... [続きを読む] -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
フランス人画家が描く日本古代神話の色彩曼陀羅の世界
日本神話 / マークエステル. - Xiang-Hap社(香港), 2006
 北大ではどこにある?
このずっしりと重い大判の画集を開いてゆくと、驚きを禁じえない。日本の原点とされてきた『古事記』の世界が、われわれが何となく思い描いていたものとはまるで違う壮大な色彩宇宙として展開してゆくのだ。古事記の物語世界に肉迫してゆくそのイメージ力の雄渾さ。創世神話を彩って華麗に舞い上がるその色彩のド迫力。これまで誰がこのような途轍もないスペクトルでわれわれの神話世界を表現してきただろうか。
北大ではどこにある?
このずっしりと重い大判の画集を開いてゆくと、驚きを禁じえない。日本の原点とされてきた『古事記』の世界が、われわれが何となく思い描いていたものとはまるで違う壮大な色彩宇宙として展開してゆくのだ。古事記の物語世界に肉迫してゆくそのイメージ力の雄渾さ。創世神話を彩って華麗に舞い上がるその色彩のド迫力。これまで誰がこのような途轍もないスペクトルでわれわれの神話世界を表現してきただろうか。
描いているのは、大の親日家であり――首相経験者から著名歌手にまで及ぶその交友の広さは驚くばかりである――、日本文化に非常に造詣の深い現代フランス人... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
宗教と科学
The God Delusion / Richard Dawkins. - Bantam Press, 2006
 北大ではどこにある?
ドーキンス氏はこの書において、神が存在しないことがその存在することよりも圧倒的に確からしいことを、進化論的観点から示します。(ただし、ここでいう神とは、万物を創造し人間に賞罰を与える超自然的存在のことで、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の神が想定されています。)しかし、有史以来、人類は宗教とともに歩んできたようです。宗教を信奉するひとが無宗教のひととの相克に勝ち抜き、自然淘汰の試練を潜り抜けてきたからには、少なくとも宗教に存在価値があるからではないかという疑問が起こります。著者は、それが危険に満ちた環境での人類の生存に適した心... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ドーキンス氏はこの書において、神が存在しないことがその存在することよりも圧倒的に確からしいことを、進化論的観点から示します。(ただし、ここでいう神とは、万物を創造し人間に賞罰を与える超自然的存在のことで、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の神が想定されています。)しかし、有史以来、人類は宗教とともに歩んできたようです。宗教を信奉するひとが無宗教のひととの相克に勝ち抜き、自然淘汰の試練を潜り抜けてきたからには、少なくとも宗教に存在価値があるからではないかという疑問が起こります。著者は、それが危険に満ちた環境での人類の生存に適した心... [続きを読む] -
推薦者 : 池田 清治 (法学研究科)
原始キリスト教の多様性を探る
禁じられた福音書 : ナグ・ハマディ文書の解明 / エレーヌ・ペイゲルス(松田和也訳). - 青土社, 2005.3
 北大ではどこにある?
昨今『捏造された聖書』(柏書房、2006年)など)、西洋思想の源流を辿りたい方には是非とも一読を薦めたい。
北大ではどこにある?
昨今『捏造された聖書』(柏書房、2006年)など)、西洋思想の源流を辿りたい方には是非とも一読を薦めたい。 -
推薦者 : 花井 一典 (文学研究科)
自分の中の魔物を見つめて!
仏教vs.倫理 / 末木文美士著. - 筑摩書房, 2006.2
 北大ではどこにある?
思想研究の課題は過去の思想の解説にあるわけではない。キレイゴトの倫理道徳の手に負えない何かをいつも抱えているのが人間であって、実はそうした人間の中の魔物を冷静に見定めるところに研究の最終目的があると言ってよいくらいである。著者は専門の仏教思想を交えながらも、現代の闇をどこまでも追究しており、裃を脱いだその語り口は魔の世界を体験した者だけがもつ不思議な明るさが漂っている。情けない、ダメな自分に滅入っていてはいけない。自分のそうした部分を見つめることで人は本当に成長するのだから。
北大ではどこにある?
思想研究の課題は過去の思想の解説にあるわけではない。キレイゴトの倫理道徳の手に負えない何かをいつも抱えているのが人間であって、実はそうした人間の中の魔物を冷静に見定めるところに研究の最終目的があると言ってよいくらいである。著者は専門の仏教思想を交えながらも、現代の闇をどこまでも追究しており、裃を脱いだその語り口は魔の世界を体験した者だけがもつ不思議な明るさが漂っている。情けない、ダメな自分に滅入っていてはいけない。自分のそうした部分を見つめることで人は本当に成長するのだから。 -
推薦者 : 宇都宮 輝夫 (文学研究科)
日本人として知っておきたい「宗教」のこと
日本宗教事典 / 村上重良 [著]. - 講談社, 1988.7
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 宇都宮 輝夫 (文学研究科)
キリスト教の流れを知るために
キリスト教の歴史 / 小田垣雅也 [著]. - 講談社, 1995.5
 北大ではどこにある?
キリスト教に関する入門書は、書店にいけば沢山のものが並んでいます。それらの中でも、この本は要点をきちんとおさえた良い一冊だと思われます。知られているようで実はあまり知られていない「キリスト教」ですが、欧米社会では「常識」です。今のうちに欧米宗教の基礎について学びましょう。
北大ではどこにある?
キリスト教に関する入門書は、書店にいけば沢山のものが並んでいます。それらの中でも、この本は要点をきちんとおさえた良い一冊だと思われます。知られているようで実はあまり知られていない「キリスト教」ですが、欧米社会では「常識」です。今のうちに欧米宗教の基礎について学びましょう。