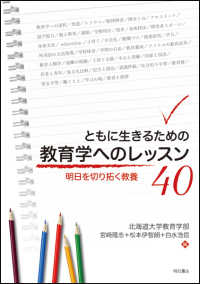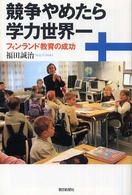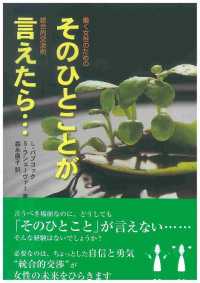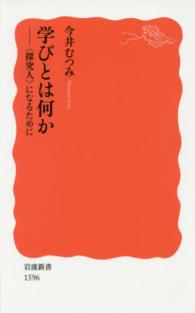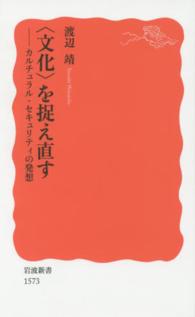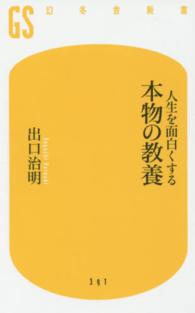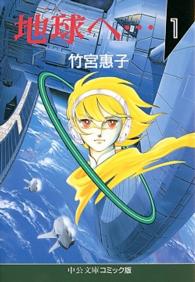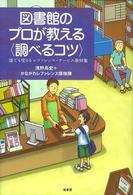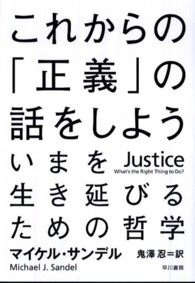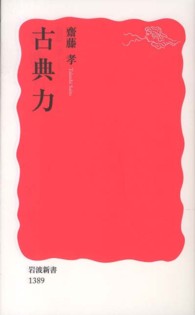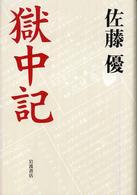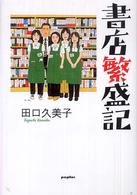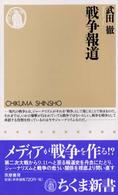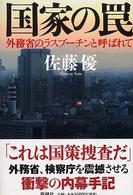-
推薦者 : 松本 伊智朗 (教育学研究院・教員)
教育学の面白さを伝えたい
ともに生きるための教育学へのレッスン / 北海道大学教育学部他編. - 明石書店, 2019
 北大ではどこにある?
北大教育学部に所属する教員が、それぞれの研究テーマにもとづいて初学者向けに執筆した40の論考です。「こころと身体」「学びと教育」「社会と文化」の3つの領域で編集され、「教育」の研究の領域や方法がイメージできます。各教員が推薦するブックガイドも掲載されており、以後の学習に有益です。教育学部のほぼすべての教員が執筆しているので、学部の研究内容のガイド本としても役立ちます。
北大ではどこにある?
北大教育学部に所属する教員が、それぞれの研究テーマにもとづいて初学者向けに執筆した40の論考です。「こころと身体」「学びと教育」「社会と文化」の3つの領域で編集され、「教育」の研究の領域や方法がイメージできます。各教員が推薦するブックガイドも掲載されており、以後の学習に有益です。教育学部のほぼすべての教員が執筆しているので、学部の研究内容のガイド本としても役立ちます。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「研究者」になるための知的基礎体力をつけたい人に
これから研究を書くひとのためのガイドブック : ライティングの挑戦15週間 / 佐渡島紗織, 吉野亜矢子著. - ひつじ書房, 2008
 北大ではどこにある?
何年か前に、日本各地の大学で文章表現法関係の授業を担当している教員が集まって実践研修会をしたことがある。各人が自分の授業実践を発表し、ワークショップを通してよりよい授業のあり方を考えるというものだったが、そこで僕が言ったのは、文章表現法の授業をやるということが「自分が教わっていないことを教える”恐怖”」を伴う営為であるということだ。欧米の大学(院)に留学した人は別だろうが、僕自身の高校・大学時代には文章表現法やレポート作成法、論文執筆法は誰も教えてくれなかった。(僕の卒業した大学の教養科目の「文章表現法」は、1年間の総仕上げに短... [続きを読む]
北大ではどこにある?
何年か前に、日本各地の大学で文章表現法関係の授業を担当している教員が集まって実践研修会をしたことがある。各人が自分の授業実践を発表し、ワークショップを通してよりよい授業のあり方を考えるというものだったが、そこで僕が言ったのは、文章表現法の授業をやるということが「自分が教わっていないことを教える”恐怖”」を伴う営為であるということだ。欧米の大学(院)に留学した人は別だろうが、僕自身の高校・大学時代には文章表現法やレポート作成法、論文執筆法は誰も教えてくれなかった。(僕の卒業した大学の教養科目の「文章表現法」は、1年間の総仕上げに短... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
研究のための「転ばぬ先の杖」
実証的教育研究の技法 : これでできる教育研究 / 西川純著. - 大学教育出版, 2000
 北大ではどこにある?
この本は著者の学生(大学院生)指導体験から得た知見をもとに書かれた「研究」のための手引き書である。素材の多くは教育学、特に教育現場の実践を想定しており、それらをどのように研究テーマとして成立させ処理していくかについて解説してくれている。副題に「これでできる教育研究」とあるが、実際の教育研究は現場の生身の人間(生徒・学生)を相手にするのだからこの本を読めば全て滞りなく研究ができるというわけではない。そのことは著者自身が最もよく分かっているだろう。それでもこの本を推薦するのは、学生が、壁にぶつかったり悩んだり理解しにくかったりする... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は著者の学生(大学院生)指導体験から得た知見をもとに書かれた「研究」のための手引き書である。素材の多くは教育学、特に教育現場の実践を想定しており、それらをどのように研究テーマとして成立させ処理していくかについて解説してくれている。副題に「これでできる教育研究」とあるが、実際の教育研究は現場の生身の人間(生徒・学生)を相手にするのだからこの本を読めば全て滞りなく研究ができるというわけではない。そのことは著者自身が最もよく分かっているだろう。それでもこの本を推薦するのは、学生が、壁にぶつかったり悩んだり理解しにくかったりする... [続きを読む] -
推薦者 : 池田 文人 (高等教育推進機構・教員)
学力世界一の秘密
競争やめたら学力世界一 : フィンランド教育の成功 / 福田誠治. - 朝日新聞社, 2006
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
やっぱり東京大学は凄い…。
アクティブラーニングのデザイン : 東京大学の新しい教養教育 / 永田敬, 林一雅編. - 東京大学出版会, 2016
 北大ではどこにある?
平成24年8月24日付中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~」に於いて、今後の中等教育・大学教育に積極的にアクティブ・ラーニング型授業を導入するべきであることが打ち出された。この本は、東京大学教養学部で実践されたアクティブラーニングの理念と方略を報告したものである。読者としては、これからアクティブラーニングに取り組もうとする大学教員を想定しているものであるが、学生が読んでも21世紀に求められる能力をどの... [続きを読む]
北大ではどこにある?
平成24年8月24日付中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~」に於いて、今後の中等教育・大学教育に積極的にアクティブ・ラーニング型授業を導入するべきであることが打ち出された。この本は、東京大学教養学部で実践されたアクティブラーニングの理念と方略を報告したものである。読者としては、これからアクティブラーニングに取り組もうとする大学教員を想定しているものであるが、学生が読んでも21世紀に求められる能力をどの... [続きを読む] -
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
女性を”交渉が苦手”にさせているメカニズムとは?
そのひとことが言えたら… : 働く女性のための統合的交渉術 / L.バブコック, S.ラシェーヴァー著 ; 森永康子訳. - 北大路書房, 2005
 北大ではどこにある?
女子学生の皆さんに質問です。
北大ではどこにある?
女子学生の皆さんに質問です。
「自分のほしいものを欲しいと言えますか?」
「自分にふさわしい評価を求めていますか?」?”
「パートナー(彼氏)に、フェアじゃないと思いつつ、何となく料理や家事を提供する側になっていませんか?」
それは「女性は自分の気持ちを抑えるように周囲から期待され、気づかないうちにその期待に沿うように行動してしまっている」場合があるからです。その仕組みを理解してはじめて「どうすればよいか?」「どのように言えば良いか?」How toが役に立ちます。
男子3人を育てている親として、女子も男子も「幸せなパートナーシップ」を築き... [続きを読む] -
推薦者 : 笹岡 正俊 (文学研究科・教員)
大学での「学び」で何を掴み取るのか
優秀なる羊たち : 米国エリート教育の失敗に学ぶ / ウィリアム・デレズウィッツ著 ; 米山裕子訳. - 三省堂, 2016年
 北大ではどこにある?
「社会というのはそれ自体が、真実から遠ざかり、それに触れまいとする陰謀だ。僕らは宣伝工先にどっぷりつかって一生を過ごす。―商品の広告、政治家の弁舌、現状を伝えるジャーナリズムの断言、大衆文化の陳腐な表現、当や会派やクラスの会則・・・(中略)・・・プラトンはこれをドクサ(注:推測に基づいた考え、見方)と呼んだ。その力は・・・(中略)・・・お構いなしに浸透していくほど強い。真の教育(リベラルアーツ教育)の第一の目的はこのドクサを認識し、疑問に感じ、それにとらわれずに考える術を教え、そこからわれわれを自由にすることなのである」
北大ではどこにある?
「社会というのはそれ自体が、真実から遠ざかり、それに触れまいとする陰謀だ。僕らは宣伝工先にどっぷりつかって一生を過ごす。―商品の広告、政治家の弁舌、現状を伝えるジャーナリズムの断言、大衆文化の陳腐な表現、当や会派やクラスの会則・・・(中略)・・・プラトンはこれをドクサ(注:推測に基づいた考え、見方)と呼んだ。その力は・・・(中略)・・・お構いなしに浸透していくほど強い。真の教育(リベラルアーツ教育)の第一の目的はこのドクサを認識し、疑問に感じ、それにとらわれずに考える術を教え、そこからわれわれを自由にすることなのである」
... [続きを読む] -
推薦者 : 伊藤 孝行 (メディア・コミュニケーション研究院・教員)
一文字も読まない日なんて,ほぼない(でしょ)。
「読む」技術 : 速読・精読・味読の力をつける / 石黒圭. - 光文社, 2010
 北大ではどこにある?
スマホで,読む。
北大ではどこにある?
スマホで,読む。
電車で,読む。
黒板やホワイトボードの字を,読む。
空気も,よむ。
うれしい日もかなしい日も,
晴れの日も雪の日も,
一文字も読まない日なんて,
ほぼない(でしょ)。
夢の中だって読んでいるかも。
読み方が増えれば,
もう少しだけ,つよくなれるかもしれない。 -
推薦者 : 敷田 麻実 (高等教育推進機構・教員)
学ぶことを学べる本
学びとは何か : 「探究人」になるために / 今井むつみ. - 岩波書店, 2016
 北大ではどこにある?
大学を出たときが学びのピークで、それ以降は知識レベルが下がっていくだけという批判には三分の理を認めるが、それは学習や学びをなめてかかっている。本当は社会に出てからが学びの本番であり、答えのない問題を解くチャンスに日々恵まれる。学校を出たときが学力のピークだという考えは、教室でインプットした知識だけで社会が理解できるという誤解に基づいている。学びは重要である。大学では、膨大な資料を読み、それを知ったうえでの研究を求められる。そのため、知識を得ること、レクチャーされることが大学生活の中心となりがちである。しかし、本書を読めば、知る... [続きを読む]
北大ではどこにある?
大学を出たときが学びのピークで、それ以降は知識レベルが下がっていくだけという批判には三分の理を認めるが、それは学習や学びをなめてかかっている。本当は社会に出てからが学びの本番であり、答えのない問題を解くチャンスに日々恵まれる。学校を出たときが学力のピークだという考えは、教室でインプットした知識だけで社会が理解できるという誤解に基づいている。学びは重要である。大学では、膨大な資料を読み、それを知ったうえでの研究を求められる。そのため、知識を得ること、レクチャーされることが大学生活の中心となりがちである。しかし、本書を読めば、知る... [続きを読む] -
推薦者 : 敷田 麻実 (高等教育推進機構・教員)
調査で「なぜ」と聞いてはいけない
途上国の人々との話し方 : 国際協力メタファシリテーションの手法 / 和田信明, 中田豊一著. - みずのわ出版, 2010
 北大ではどこにある?
本書の筆者である和田と中田は国際協力のベテランであり、アジアなどの途上国の現場で学んだこと、特に、相手の状態を理解する調査について、ていねいに解説している。相手を知ることの第一は観察であるが、その次は質問を介したコミュニケーションである。それは地域調査でのやり取りでも同じである。
北大ではどこにある?
本書の筆者である和田と中田は国際協力のベテランであり、アジアなどの途上国の現場で学んだこと、特に、相手の状態を理解する調査について、ていねいに解説している。相手を知ることの第一は観察であるが、その次は質問を介したコミュニケーションである。それは地域調査でのやり取りでも同じである。
彼らは「問題は何か」や「原因は何か」と相手に聞いてはいけないと述べる。例示された、医者は患者を前に「なんで熱があるのか?」と聞くのではなく、医者が聞くべきは「いつから熱が出たのか」という事実であるというアドバイスは、まったく当を得ている。考えを聞... [続きを読む] -
推薦者 : 敷田 麻実 (高等教育推進機構・教員)
この難しい時代のグローバル化政策を学ぶ
「文化」を捉え直す : カルチュラル・セキュリティの発想 / 渡辺靖. - 岩波書店, 2015
 北大ではどこにある?
グローバリゼーションは、国際社会とは関係がない私たちの日常にも影響する。こちらの都合や好き嫌いにかかわらず、勝手に影響してくるのがグローバル化であって、自治体が意図して進めていく国際化とは大きな差がある。大学の近くの保育園には、異なる国々の子供たちが通う保育園をよく見かけるが、地域が好んでインターナショナルスクールを誘致したのではない。立地する大学の教職員、留学生の影響で結果的にそうなったのだ。
北大ではどこにある?
グローバリゼーションは、国際社会とは関係がない私たちの日常にも影響する。こちらの都合や好き嫌いにかかわらず、勝手に影響してくるのがグローバル化であって、自治体が意図して進めていく国際化とは大きな差がある。大学の近くの保育園には、異なる国々の子供たちが通う保育園をよく見かけるが、地域が好んでインターナショナルスクールを誘致したのではない。立地する大学の教職員、留学生の影響で結果的にそうなったのだ。
このようにグローバル化の中では、新しい文化が遠慮なく地域に入ってくる。しかしその一方で、固有の伝統文化の維持は難しくなってきてい... [続きを読む] -
推薦者 : 瀬名波 栄潤 (文学部・教員)
21世紀の混沌を解く名著
ある学問の死 : 惑星思考の比較文学へ (原タイトル:Death of a discipline) / G. C. スピヴァク. - みすず書房, 2003年(原書)、2004年(翻訳)
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
今読まずにいつ読むか。
言論・出版の自由 / ジョン・ミルトン. - 岩波書店, 2008
 北大ではどこにある?
つい最近、マスメディアに対する権力側の幾つかの横暴とも言える対応が報道された。報道機関やジャーナリストたちはそれなりに危機感を示しているもののいよいよ政治権力が牙をむき始めた、という慄然たる思いがする。大学に身を置く我々にとって大切な、日本国憲法で保障されている学問・良心の自由もいつ危うくなるか分からない。その前に読んでおくべきものとしてこの本を推薦しておく。
北大ではどこにある?
つい最近、マスメディアに対する権力側の幾つかの横暴とも言える対応が報道された。報道機関やジャーナリストたちはそれなりに危機感を示しているもののいよいよ政治権力が牙をむき始めた、という慄然たる思いがする。大学に身を置く我々にとって大切な、日本国憲法で保障されている学問・良心の自由もいつ危うくなるか分からない。その前に読んでおくべきものとしてこの本を推薦しておく。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
この難しい時代をどう生きるか
感情で釣られる人々 : なぜ理性は負け続けるのか / 堀内進之介. - 集英社, 2016
 北大ではどこにある?
去年から書店の本棚に“反知性主義”ということばを含む表題の本が並ぶようになってきた。国内・国外にわたって難しい問題が山積し、それらに対する処方箋がなかなか見つからない中で人びとのある種のいらだちのようなものが確かに感じられるし、それが時としてこれまでの価値観に対する破れかぶれの破壊衝動のように見える場合もあって、そのようなことばが現代社会の懸念すべき問題として本の表題になることは理解できる。しかし、その一方で、問題のあり方が様々に複雑化・多様化している世界の状況を“反知性主義”という術語で語ろうとするのもある種の“メタ・反知性... [続きを読む]
北大ではどこにある?
去年から書店の本棚に“反知性主義”ということばを含む表題の本が並ぶようになってきた。国内・国外にわたって難しい問題が山積し、それらに対する処方箋がなかなか見つからない中で人びとのある種のいらだちのようなものが確かに感じられるし、それが時としてこれまでの価値観に対する破れかぶれの破壊衝動のように見える場合もあって、そのようなことばが現代社会の懸念すべき問題として本の表題になることは理解できる。しかし、その一方で、問題のあり方が様々に複雑化・多様化している世界の状況を“反知性主義”という術語で語ろうとするのもある種の“メタ・反知性... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
あなたの知らないディープな大学図書館
変わりゆく大学図書館 / 逸村裕・竹内比呂也. - 勁草書房, 2005
 北大ではどこにある?
北大図書館を頻繁に利用する人や図書館ウェブサイトをよく見る人の中でどのくらいの人が図書館トップページの一番右にある「附属図書館について」を見ているだろうか。図書館ホームページの中で蔵書検索やお知らせと同じくらい閲覧されていいページはこの「附属図書館について」の中にある様々な情報だと思う。それほど更新頻度が高いわけではないが、図書館がどのように北大の研究・教育活動に貢献しているか、そのために職員の方々がどのような仕事をしていらっしゃるかがよく分かる。時間があるときには是非見てほしい。それと関連して... [続きを読む]
北大ではどこにある?
北大図書館を頻繁に利用する人や図書館ウェブサイトをよく見る人の中でどのくらいの人が図書館トップページの一番右にある「附属図書館について」を見ているだろうか。図書館ホームページの中で蔵書検索やお知らせと同じくらい閲覧されていいページはこの「附属図書館について」の中にある様々な情報だと思う。それほど更新頻度が高いわけではないが、図書館がどのように北大の研究・教育活動に貢献しているか、そのために職員の方々がどのような仕事をしていらっしゃるかがよく分かる。時間があるときには是非見てほしい。それと関連して... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
大学の「勉強」は大変なのである!
「知」の方法論-論文トレーニング- / 岩崎美紀子. - 岩波書店, 2008
 北大ではどこにある?
この本を推薦するに当たっては苦い思い出から始めたい。高校時代の「倫理・社会」の授業で、「大学に行く目的は何か?」というテーマでグループ・ディスカッションをしたことがあった。僕のグループ5人の中で、「大学へは勉強しに行く」という意見を出したのは僕だけで、他の同級生は全員「大学へは遊びに行く」と答えたのである。グループ代表として結論を報告した同級生の、僕を小馬鹿にしたような目つきはいまだに目に浮かぶ。そんな高校だったから、卒業時、男子生徒20名中現役で大学に進学したのは2名だけだった(僕も浪人組)。
北大ではどこにある?
この本を推薦するに当たっては苦い思い出から始めたい。高校時代の「倫理・社会」の授業で、「大学に行く目的は何か?」というテーマでグループ・ディスカッションをしたことがあった。僕のグループ5人の中で、「大学へは勉強しに行く」という意見を出したのは僕だけで、他の同級生は全員「大学へは遊びに行く」と答えたのである。グループ代表として結論を報告した同級生の、僕を小馬鹿にしたような目つきはいまだに目に浮かぶ。そんな高校だったから、卒業時、男子生徒20名中現役で大学に進学したのは2名だけだった(僕も浪人組)。
北大に進学してきた学生諸君の高校... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「教養」は実践するものである。
人生を面白くする本物の教養 / 出口治明. - 幻冬舎, 2015
 北大ではどこにある?
この本の推薦文は、僕の体験したエピソードの紹介を以てこれに替えたいと思う。
北大ではどこにある?
この本の推薦文は、僕の体験したエピソードの紹介を以てこれに替えたいと思う。
大学時代に読んだ本の中に、イギリス人は初対面の相手にまず政治の話題を振って、相手がその話題についてこられなかったら「こいつは付き合う価値のない奴だ」と見切りをつける、という趣旨のことが書いてあった。いくら何でもそれは決めつけすぎだろうと思ったものの、そのことを忘れて十年ほどが経過し、機会を得てエジプトに赴任することになった。そして、彼の地でイギリス人のカップルと知り合い、ある日彼らの家に夕食に招待された。席についてまずワインで乾杯となったのだが、一口... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
サンデルとの対話は成功したのか?
日本生まれの「正義論」-サンデル「正義論」に欠けているもの- / 川本兼. - 明石書店, 2011
 北大ではどこにある?
著者は、サンデルの正義論が結局はアメリカの「力」の論理によるものではないかという疑問を呈するところから始めて、サンデルの正義論に対する対抗思想としての正義論を生み出そうとした。その懸命な思索の成果がこの本である。著者の思想的格闘が成功したかどうかは、読者それぞれが判定されたい。その中で読者自身が自分なりに正義について考えることをきっと始めているだろう。
北大ではどこにある?
著者は、サンデルの正義論が結局はアメリカの「力」の論理によるものではないかという疑問を呈するところから始めて、サンデルの正義論に対する対抗思想としての正義論を生み出そうとした。その懸命な思索の成果がこの本である。著者の思想的格闘が成功したかどうかは、読者それぞれが判定されたい。その中で読者自身が自分なりに正義について考えることをきっと始めているだろう。
ネタバレになるかもしれないが、僕の読後感としては著者は正面からサンデルの思想に切り込もうとしているがところどころで自分に不都合な証拠を-忘れているのか意図的にかは分からないが-出... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
異質な他者との共存は可能か
地球(テラ)へ… (全3巻) / 竹宮惠子. - 中央公論新社, 1995
 北大ではどこにある?
この作品は日本のSF漫画史上に語り継がれるべき大傑作である。それがこの北海道大学附属図書館に置いてあることについて、北大附属図書館スタッフの見識を僕は高く評価したい。単に傑作漫画を置いているからということではなく、この漫画が突きつけてくるあまりにも重い問いが、今日の我々にとって何よりも考え抜かれ、かつ実践されねばならない問いだからである。
北大ではどこにある?
この作品は日本のSF漫画史上に語り継がれるべき大傑作である。それがこの北海道大学附属図書館に置いてあることについて、北大附属図書館スタッフの見識を僕は高く評価したい。単に傑作漫画を置いているからということではなく、この漫画が突きつけてくるあまりにも重い問いが、今日の我々にとって何よりも考え抜かれ、かつ実践されねばならない問いだからである。
グローバル化した社会で異文化としての他者と向き合ってそこで、関わりを深めていこうとするか相手を拒絶するかの選択に迫られることは現代では以前よりも遙かに頻繁にかつ容易に起こりえる。この漫画は、コン... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
図書館の達人になる!
図書館のプロが教える「調べるコツ」 : 誰でも使えるレファレンス・サービス事例集 / 浅野高史とかながわレファレンス探検隊. - 柏書房, 2006
 北大ではどこにある?
図書館を、「本を借りる」ところ、「勉強する」ところだと思っている学生はおそらく今では少ないと思うけれども、では、図書館を有効に使えている学生(教員も)がいるかというと、どのように自分たちの勉強やそれ以外の活動に役立つのかまだぼんやりとしたイメージしか抱けない学生も多いと思う。そんなときこの本は役に立つ。図書館が、”お勉強”のためだけの建物ではなくわくわくするような=知的に興奮できる世界だ、ということがわかるだろう。読んだらきっとあなたも図書館に行きたくなる!
北大ではどこにある?
図書館を、「本を借りる」ところ、「勉強する」ところだと思っている学生はおそらく今では少ないと思うけれども、では、図書館を有効に使えている学生(教員も)がいるかというと、どのように自分たちの勉強やそれ以外の活動に役立つのかまだぼんやりとしたイメージしか抱けない学生も多いと思う。そんなときこの本は役に立つ。図書館が、”お勉強”のためだけの建物ではなくわくわくするような=知的に興奮できる世界だ、ということがわかるだろう。読んだらきっとあなたも図書館に行きたくなる! -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
ブームが沈静化した今こそ冷静に読んでみよう
これからの「正義」の話をしよう-いまを生き延びるための哲学- / マイケル・サンデル. - 早川書房, 2010
 北大ではどこにある?
言わずと知れた、「NHK白熱教室」のネタもととなった本である。テレビでのサンデルの講義に独特のスタイルがあったこともあって売れに売れたらしい(僕の持っているのは第78版!)が、こうした本はブームが去った今こそ落ち着いて読んでその内実を判断する必要があるだろう。
北大ではどこにある?
言わずと知れた、「NHK白熱教室」のネタもととなった本である。テレビでのサンデルの講義に独特のスタイルがあったこともあって売れに売れたらしい(僕の持っているのは第78版!)が、こうした本はブームが去った今こそ落ち着いて読んでその内実を判断する必要があるだろう。
サンデルは、現代世界のアクチュアルな問題を古典から現代までの政治思想と結びつけて論じながら彼なりの(=コミュニタリアンとしての)哲学を開陳していくが、その解決が妥当であるかどうかは読者が今一度批判の目をもって考えるに値するものである。
今は文庫版も出て読みやすくなっているので、... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
インタビュー調査に必読の一冊
聞きとりの作法 / 小池和男. - 東洋経済新報社, 2000
 北大ではどこにある?
研究の必要からインタビュー調査をすることになって、そのためのノウハウが書いてある本を数冊読んだが、その中で最も役に立ったのがこの本である。
北大ではどこにある?
研究の必要からインタビュー調査をすることになって、そのためのノウハウが書いてある本を数冊読んだが、その中で最も役に立ったのがこの本である。
内容は著者の小池氏が専門とする経済学の、主として職場の技術移転を例にとって書かれているが、その分インタビューの実際に関する記述が非常に豊富でわかりやすい。また、インタビューデータからどのように読み取りを行ったらいいかの例やインタビューの前後に行っておくべきことなども書かれていて、将来、聞きとり調査が必要となる分野で研究しようと考えている学生にとっては必読の一冊である。 -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
日本人は日本的なのか?何を以て日本的と言えるのか?
日本人論の方程式 / 杉本良夫, ロス・マオア. - 筑摩書房, 1995
 北大ではどこにある?
「日本人論」というものがしばしば人口に膾炙することがあります。古くは新渡戸稲造『武士道』、最近では藤原雅彦『国家の品格』といったところでしょうか。そうした書籍では、日本国内の格言、歴史上の人物の言動録、著者の国内外での体験などをエビデンスとして「日本人は〇〇である」とされることがしばしばあります。そうしたエビデンスの使い方によって「本当に日本人は日本的である」と言っていいのか?と疑問を呈したのが本書です。
北大ではどこにある?
「日本人論」というものがしばしば人口に膾炙することがあります。古くは新渡戸稲造『武士道』、最近では藤原雅彦『国家の品格』といったところでしょうか。そうした書籍では、日本国内の格言、歴史上の人物の言動録、著者の国内外での体験などをエビデンスとして「日本人は〇〇である」とされることがしばしばあります。そうしたエビデンスの使い方によって「本当に日本人は日本的である」と言っていいのか?と疑問を呈したのが本書です。
社会科学方法論としても重要な書籍ですが、日本文化や日本と海外の比較に関心がある人も一度目を通してみるといろいろ頭のトレーニン... [続きを読む] -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
人々のものの見方や考え方を社会学的に分析する
階層・教育と社会意識の形成─社会意識論の磁界 / 吉川徹著. - ミネルヴァ書房, 1998
 北大ではどこにある?
社会意識論の重要書。人々のものの見方や考え方を社会学的に分析するとはどういうことなのかが方法論も含めて理解できると思います。統計を駆使した専門書でやや難しいですが、著者も書いている通り、家電製品のマニュアルを注意深く読むだけの力を入れれば、考え方は十分理解できると思います。
北大ではどこにある?
社会意識論の重要書。人々のものの見方や考え方を社会学的に分析するとはどういうことなのかが方法論も含めて理解できると思います。統計を駆使した専門書でやや難しいですが、著者も書いている通り、家電製品のマニュアルを注意深く読むだけの力を入れれば、考え方は十分理解できると思います。 -
推薦者 : 森川 正章 (地球環境科学研究院)
柔軟な思考能力を鍛えるのに最適な書
なぜ、それを考えつかなかったのか? / チャールズ W マッコイ Jr(ルディー和子訳). - ダイヤモンド社, 2003
 北大ではどこにある?
本書は合理的な思考や意思の決定の仕方について例をあげながら教えてくれます。
北大ではどこにある?
本書は合理的な思考や意思の決定の仕方について例をあげながら教えてくれます。
ひとはついつい先入観にとらわれて物事をあいまいなまま判断しがちです。
私たちが陥りやすい勘違いや錯覚を指摘してくれるので、なるほどと思わせるところがたくさんあります。登録日 : 2014-04-10
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
もう一つの「本は脳を育てる」
古典力 / 斎藤 孝. - 岩波書店, 2012
 北大ではどこにある?
以前森鴎外の『舞姫』を推薦した時に、「古典」を読むということについて少しだけ書いたことがある。では「古典」とは何か、と言うことになると答えはそれほど簡単ではない。そのわかりやすい見取り図の一つがこの『古典力』である。これを読むと、読んだことがある本に再会したり、名前は知っていても(案外それで分かった気になって)読んでいない本に出遭ったりするだろう。そこで興味が湧いた本があればためらうことなく手にとって欲しい。なぜそれが「古典」になっているかは、斉藤氏の解説を手がかりに読めば自分なりの理解を獲得することができると思う。
北大ではどこにある?
以前森鴎外の『舞姫』を推薦した時に、「古典」を読むということについて少しだけ書いたことがある。では「古典」とは何か、と言うことになると答えはそれほど簡単ではない。そのわかりやすい見取り図の一つがこの『古典力』である。これを読むと、読んだことがある本に再会したり、名前は知っていても(案外それで分かった気になって)読んでいない本に出遭ったりするだろう。そこで興味が湧いた本があればためらうことなく手にとって欲しい。なぜそれが「古典」になっているかは、斉藤氏の解説を手がかりに読めば自分なりの理解を獲得することができると思う。
ちなみに、... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「英学」のもう一つの姿
日本における近代倫理の屈折 / 堀孝彦. - 未来社, 2002
 北大ではどこにある?
さきにこの「本は脳を育てる」に、惣郷正明『日本英学のあけぼの』を推薦した。今度の『日本における近代倫理の屈折』は、惣郷の本にも登場する幕末の英語通詞・堀達之助の子孫である堀孝彦氏が、達之助の営為を通じて「英学」を語学としてのみではなく「人文学」と捉え、その内実が急激な近代化を急ぐ日本の中でいかなる変化を余儀なくされたか-著者のことばで言えば「屈折」を経たか-を明らかにし、現代にまで繋がるその「屈折」の影響を読み取ろうとしたものである。その「屈折」の延長線上には、明治期から現代までの日本の倫理道徳上の様々な問題が関連してくること... [続きを読む]
北大ではどこにある?
さきにこの「本は脳を育てる」に、惣郷正明『日本英学のあけぼの』を推薦した。今度の『日本における近代倫理の屈折』は、惣郷の本にも登場する幕末の英語通詞・堀達之助の子孫である堀孝彦氏が、達之助の営為を通じて「英学」を語学としてのみではなく「人文学」と捉え、その内実が急激な近代化を急ぐ日本の中でいかなる変化を余儀なくされたか-著者のことばで言えば「屈折」を経たか-を明らかにし、現代にまで繋がるその「屈折」の影響を読み取ろうとしたものである。その「屈折」の延長線上には、明治期から現代までの日本の倫理道徳上の様々な問題が関連してくること... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
論理学の深さを知る
現代論理学入門 / 沢田 允茂. - 岩波書店, 1962
 北大ではどこにある?
今から50年前に出たこの本は、いまなお論理学の名著としての価値を失っていない。もちろん50年の間には論理学にも進歩があって、多値論理、様相論理、量子論理などはこの本では取り扱われていないし、用語や記号の表記も古いところがあるが、それは仕方ないこととしても、論理学を専門的に研究するならともかく、それ以外の幅広い哲学的関心に広く答え得る点でこの本をしのぐ内容のものはいまだにほとんどないと言って良い。こうした優れた本を絶版にしないで出し続けている岩波書店の“営業努力”は賞讃されてしかるべきである。
北大ではどこにある?
今から50年前に出たこの本は、いまなお論理学の名著としての価値を失っていない。もちろん50年の間には論理学にも進歩があって、多値論理、様相論理、量子論理などはこの本では取り扱われていないし、用語や記号の表記も古いところがあるが、それは仕方ないこととしても、論理学を専門的に研究するならともかく、それ以外の幅広い哲学的関心に広く答え得る点でこの本をしのぐ内容のものはいまだにほとんどないと言って良い。こうした優れた本を絶版にしないで出し続けている岩波書店の“営業努力”は賞讃されてしかるべきである。
この本を紹介する際に、記号の使用を最小限... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
to tie a knot literally
The Ashley Book of Knots / Clifford Ashley. - Doubleday, 1944
 北大ではどこにある?
Sometimes a person collects, organizes, and delivers information in such a way that the exhaustive knowledge is clearly explained along with its background culture and history. The Ashley Book of Knots (or ABOK for short) is such a treatise. It is rare that a book as old as my parents continues to reign as the standard reference. We academics should learn humility from a work of this scope.
北大ではどこにある?
Sometimes a person collects, organizes, and delivers information in such a way that the exhaustive knowledge is clearly explained along with its background culture and history. The Ashley Book of Knots (or ABOK for short) is such a treatise. It is rare that a book as old as my parents continues to reign as the standard reference. We academics should learn humility from a work of this scope.
For more information about ABOK, visit Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Ashley_Book_of_Knots
View parts of this book including its wonderful drawings at Google Books:
http://books.google.com/
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
文章を書くことが苦手な人に安心を与えてくれる本
「書くのが苦手」をみきわめる / 渡辺哲司. - 学術出版会, 2010
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「大学」の行く末を考えたい人に
学問の下流化 / 竹内洋. - 中央公論新社, 2008
 北大ではどこにある?
竹内洋の著書を既に何冊か読んでいる人が、その社会学的分析によって表題の「学問の下流化」という現象を理論的に解明し、その処方箋を論じたものであると期待して読むとやや肩すかしを喰います。これは別段否定的に評価しようというわけではなく、書評や短い評論の集成という書き方のスタイルに起因するもので、内容は広い意味での学問論や大学論を幅広く取り上げ、そのある種の病理的状況を竹内氏独特の切り口と語り口で捌いていくものになっています。「学問の下流化」そのものが全体的な主題とは言い難い面があるので、読み方によっては不満が残る面もあるかもしれませ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
竹内洋の著書を既に何冊か読んでいる人が、その社会学的分析によって表題の「学問の下流化」という現象を理論的に解明し、その処方箋を論じたものであると期待して読むとやや肩すかしを喰います。これは別段否定的に評価しようというわけではなく、書評や短い評論の集成という書き方のスタイルに起因するもので、内容は広い意味での学問論や大学論を幅広く取り上げ、そのある種の病理的状況を竹内氏独特の切り口と語り口で捌いていくものになっています。「学問の下流化」そのものが全体的な主題とは言い難い面があるので、読み方によっては不満が残る面もあるかもしれませ... [続きを読む] -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
文系の学生、院生の必読書
大学生の論文執筆法 / 石原千秋. - 筑摩新書, 2006
 北大ではどこにある?
漱石の研究家である著者が大学の教育の中で、痛感した学生のレポートや論文の書き方の不備、欠点を指摘し、如何に書くか、また書く準備として書く心構えから、資料の扱い方、何が資料とはならないかなど詳しく指摘したもの。ネットで集めた知識は評価されないことなど教員には分り切ったことだが、学生はちゃんと知らない人もいることが書かれていて、こういうことを大学院生になってもいい加減な人もいるので、必読書である。この程度のことは先刻承知だという人は大変結構です。論文の推敲例もあるので、参考になります。
北大ではどこにある?
漱石の研究家である著者が大学の教育の中で、痛感した学生のレポートや論文の書き方の不備、欠点を指摘し、如何に書くか、また書く準備として書く心構えから、資料の扱い方、何が資料とはならないかなど詳しく指摘したもの。ネットで集めた知識は評価されないことなど教員には分り切ったことだが、学生はちゃんと知らない人もいることが書かれていて、こういうことを大学院生になってもいい加減な人もいるので、必読書である。この程度のことは先刻承知だという人は大変結構です。論文の推敲例もあるので、参考になります。 -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
どこでも勉強はできる
獄中記 / 佐藤優. - 岩波書店, 2006
 北大ではどこにある?
著者が512日間東京拘置所に勾留された日々の記録。鈴木宗男氏と共に逮捕、起訴され、公判に臨んだ著者は、拘置所の中で何をしていたのか。公判について弁護士と手紙のやりとりはあたりまえだが、興味深いのは、大量の本を読み、ノートに思索を記録し、ラテン語やドイツ語を勉強する姿である。神学の研究者でもある著者の旺盛な勉学欲には驚かされる。国策捜査の標的になり、自由を奪われても、勉強を続ける姿に若い人は何かを感じてほしい。
北大ではどこにある?
著者が512日間東京拘置所に勾留された日々の記録。鈴木宗男氏と共に逮捕、起訴され、公判に臨んだ著者は、拘置所の中で何をしていたのか。公判について弁護士と手紙のやりとりはあたりまえだが、興味深いのは、大量の本を読み、ノートに思索を記録し、ラテン語やドイツ語を勉強する姿である。神学の研究者でもある著者の旺盛な勉学欲には驚かされる。国策捜査の標的になり、自由を奪われても、勉強を続ける姿に若い人は何かを感じてほしい。 -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
本屋は好きですか
書店繁盛記 / 田口久美子. - ポプラ社, 2006
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
メディアとは 2
戦争報道 / 武田徹. - ちくま新書, 2003
 北大ではどこにある?
ジャーナリズムは戦争の悲惨さを伝える一方、9.11以後のアメリカのように戦争を煽る愛国報道になる。第二次世界大戦からアフガン戦争まで戦争と報道の問題を論じる。そして戦時においては中立の報道どころか広告(プロパガンダ)に加担する姿を示す。これで基礎知識を得てから、他の戦争とメディア論に進むと良いと思う。
北大ではどこにある?
ジャーナリズムは戦争の悲惨さを伝える一方、9.11以後のアメリカのように戦争を煽る愛国報道になる。第二次世界大戦からアフガン戦争まで戦争と報道の問題を論じる。そして戦時においては中立の報道どころか広告(プロパガンダ)に加担する姿を示す。これで基礎知識を得てから、他の戦争とメディア論に進むと良いと思う。 -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
メディアとは 1
国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて / 佐藤優. - 新潮社, 2005
 北大ではどこにある?
あなたは鈴木宗男議員を知っているだろうか。マスメディアでは汚い政治家の代表とされ、北方領土関係などで癒着を指弾され、疑惑の総合商社と言われ、逮捕・起訴された政治家である。彼と共に歩み、外務省を毒したとされた外交官が著者である。彼も逮捕・起訴された。私たちはそのようなイメージを自明のものと受け取ってきた。しかし彼らの言い分をちゃんと聞いたことがあったろうか。この本を読むと政治の裏の複雑さと権力抗争のすざまじさを知ることができる。国益を巡る立場の違いを知ると、一面的に著者を弾劾することはためらわれる。鈴木議員に関しても同じである... [続きを読む]
北大ではどこにある?
あなたは鈴木宗男議員を知っているだろうか。マスメディアでは汚い政治家の代表とされ、北方領土関係などで癒着を指弾され、疑惑の総合商社と言われ、逮捕・起訴された政治家である。彼と共に歩み、外務省を毒したとされた外交官が著者である。彼も逮捕・起訴された。私たちはそのようなイメージを自明のものと受け取ってきた。しかし彼らの言い分をちゃんと聞いたことがあったろうか。この本を読むと政治の裏の複雑さと権力抗争のすざまじさを知ることができる。国益を巡る立場の違いを知ると、一面的に著者を弾劾することはためらわれる。鈴木議員に関しても同じである... [続きを読む] -
推薦者 : 眞崎 睦子 (メディア・コミュニケーション研究院)
北海道、はじめて?
北海道わくわく地図えほん / 堀川 真. - 北海道新聞社, 2006
 北大ではどこにある?
地元の小さな川の名前は全部知っているのに、
北大ではどこにある?
地元の小さな川の名前は全部知っているのに、
都道府県パズル得意だったのに、
あこがれの北大に来てみたら、
北海道物産展に来ていた美味しいもの以外、
北海道のこと何にも知らないっ!
あの家の横のカニみたいなものは何?(灯油タンクでした、念のため)
「投げといて」って言われても、何をどこにっ?
…と2年前の私のようにあせっている新入生はいませんか?
こんな読書もたまにはいいと思います。
これから暮らす北海道のこと、
豊かな自然から、まちの暮らし、方言まで、わくわくしながら学べます。
登録日 : 2006-04-18
-
推薦者 : 吉野 悦雄 (経済学研究科)
論理を体験する
論理トレーニング101題 / 野矢茂樹著. - 産業図書, 2001.5
 北大ではどこにある?
この本は脳を鍛えるのにふさわしい本です。決してパズル問題集ではありません。どの問題にも,集合と補集合という初歩的な概念からはじまって,ド・モルガンの法則など高度な記号論理学の論理が埋め込まれています。公務員試験や法科大学院をめざす4年生には定番の参考書となっています。しかしその内容は平易で,高校生にも理解できます。文系学部のみなさんにとっても無理なく読み進めることのできる本です。附属図書館の本館と北分館の開架図書におさめられていますが,人気のある本なので,ご自分で購入してもよいでしょう。
北大ではどこにある?
この本は脳を鍛えるのにふさわしい本です。決してパズル問題集ではありません。どの問題にも,集合と補集合という初歩的な概念からはじまって,ド・モルガンの法則など高度な記号論理学の論理が埋め込まれています。公務員試験や法科大学院をめざす4年生には定番の参考書となっています。しかしその内容は平易で,高校生にも理解できます。文系学部のみなさんにとっても無理なく読み進めることのできる本です。附属図書館の本館と北分館の開架図書におさめられていますが,人気のある本なので,ご自分で購入してもよいでしょう。 -
推薦者 : 佐伯 宏樹 (水産科学院・水産科学研究院)
科学を志す人にとって座右の一冊!
理科系の作文技術 / 木下是雄著. - 中央公論社, 1981.9
 北大ではどこにある?
「私の文章のどこがいけないのかわからない?」
北大ではどこにある?
「私の文章のどこがいけないのかわからない?」
「考察がなっていないって指摘されたけど,いったいどこが悪いのだろう?」
レポートを返却されてこんな悩みを持った人に一読をお薦めします!
***********
皆さんはこれから,さまざまな実験・実習を体験し,続いて卒業研究,さらには大学院での本格的な研究活動を経て社会に巣立つことになります。この過程で学ぶべきレベルは,日を追うごとに高くなりますが,一方で,学部,修士課程,博士課程のいずれの場合にも実験結果を文章で表現するという作業が求められ続けます。
***********
科学の分野で「ものを書く」ということは... [続きを読む] -
推薦者 : 稗貫 俊文 (法学研究科)
高校生向きだって侮れないぞ!
アメリカ式勉強法 / ロン・フライ著 ; 金利光訳. - 東京図書, 1996.11
 北大ではどこにある?
アメリカの高校生向きに書かれた本の翻訳です。アメリカ式とは日本の本屋さんが勝手につけたタイトルです。しかし、さすが、あの勤勉家のB・フランクリンを生んだ国の本だなーという印象をもちます(暇があれば「論文作法 : 調査・研究・執筆の技術と手順』という本のことです。(北分館2007/03/07)
北大ではどこにある?
アメリカの高校生向きに書かれた本の翻訳です。アメリカ式とは日本の本屋さんが勝手につけたタイトルです。しかし、さすが、あの勤勉家のB・フランクリンを生んだ国の本だなーという印象をもちます(暇があれば「論文作法 : 調査・研究・執筆の技術と手順』という本のことです。(北分館2007/03/07)