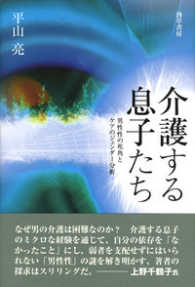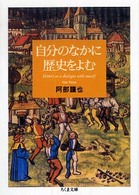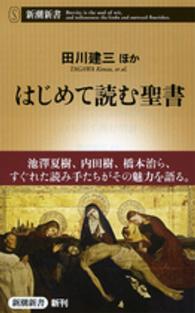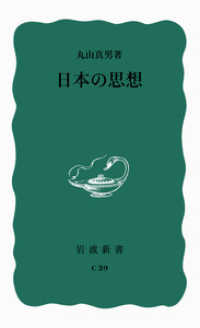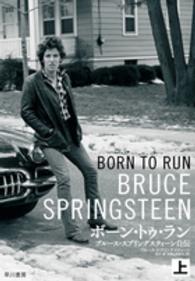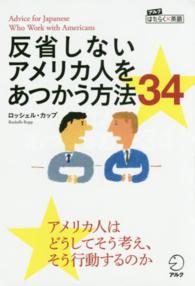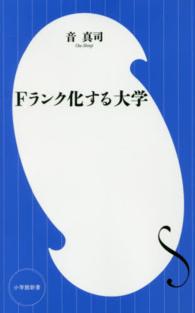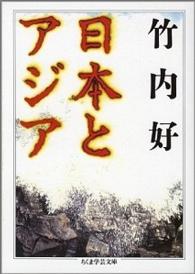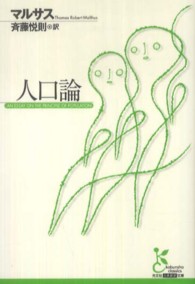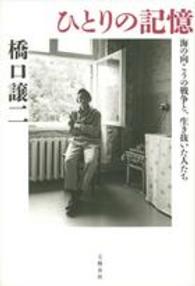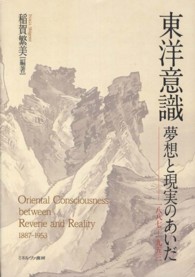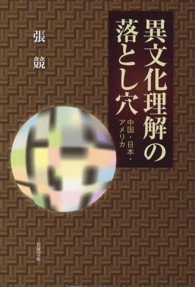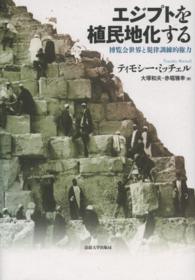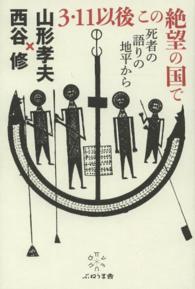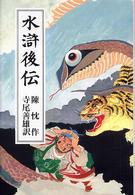-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
不愉快な、しかし有益な本
介護する息子たち : 男性性の死角とケアのジェンダー分析 / 平山亮. - 勁草書房, 2017
 北大ではどこにある?
これを書いている僕は3月31日付けで北海道大学を退職する。理由は介護離職、つまりこの本の標題にもなっている「介護する息子」になるわけだ。この本は、そのような「介護する息子」になる前に参考とするべき点を調べようと思って読んだのだが、内容は全く違っていて、所謂ジェンダー社会学の立場から「介護する息子」たちが一見親の介護で苦労しているように見えながら、その背後には女性(配偶者や姉妹)からの支援や女性に対する差別やジェンダー的不均衡があるという可視性の低い問題点をこれでもかとばかりに暴き出す研究書だった。
北大ではどこにある?
これを書いている僕は3月31日付けで北海道大学を退職する。理由は介護離職、つまりこの本の標題にもなっている「介護する息子」になるわけだ。この本は、そのような「介護する息子」になる前に参考とするべき点を調べようと思って読んだのだが、内容は全く違っていて、所謂ジェンダー社会学の立場から「介護する息子」たちが一見親の介護で苦労しているように見えながら、その背後には女性(配偶者や姉妹)からの支援や女性に対する差別やジェンダー的不均衡があるという可視性の低い問題点をこれでもかとばかりに暴き出す研究書だった。
考えてみれば著者の平山氏は... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
揺るぎない体験と明敏な眼と強靱な思索の結晶
自分のなかに歴史をよむ / 阿部謹也著. - 筑摩書房, 2007
 北大ではどこにある?
何年かにわたって「一般教育演習」や「多文化交流科目」で異文化間コミュニケーションの理論と実践といった類いの授業を展開してきたが、この本はそうした授業の設計思想を作る上で常に座右に置いていたものである。この本が出たとき、ある夕刊紙の書評が「これは真に感動的な本である。」と書いた。「感動的」ということばが適切かどうかは分からないが、「目からウロコが落ちる」という感覚が得られる本ではあると確かに思う。内容は、少年時の修道院生活、大学時代の上原専録との出会い、ヨーロッパ留学生活等々著者の体験談が多いように見えるが、その根底で著者はヨー... [続きを読む]
北大ではどこにある?
何年かにわたって「一般教育演習」や「多文化交流科目」で異文化間コミュニケーションの理論と実践といった類いの授業を展開してきたが、この本はそうした授業の設計思想を作る上で常に座右に置いていたものである。この本が出たとき、ある夕刊紙の書評が「これは真に感動的な本である。」と書いた。「感動的」ということばが適切かどうかは分からないが、「目からウロコが落ちる」という感覚が得られる本ではあると確かに思う。内容は、少年時の修道院生活、大学時代の上原専録との出会い、ヨーロッパ留学生活等々著者の体験談が多いように見えるが、その根底で著者はヨー... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「新しい」学問の「古典」
言語と社会 / P.トラッドギル著 ; 土田滋訳. - 岩波書店, 1975
 北大ではどこにある?
推薦文タイトルの”「新しい」学問の「古典」”という表現はそのまま読めば形容矛盾でしかない。しかし、この本は、社会言語学という1960年代から形成され始めた「新しい」学問の分野においては紛れもなく今や「古典」であり、タイトル通り「言語」と「社会」を見るための視点や研究の方法を手際よく整理して提示している。現在、社会言語学についての概論書、入門書は数多く出版されているし、その対象や方法も発展しているけれども、この本に盛り込まれた内容は今日でも(あるいは今日なお)有益であり学ぶことが多い。社会言語学という個別分野だけでなく、言語と社会の関... [続きを読む]
北大ではどこにある?
推薦文タイトルの”「新しい」学問の「古典」”という表現はそのまま読めば形容矛盾でしかない。しかし、この本は、社会言語学という1960年代から形成され始めた「新しい」学問の分野においては紛れもなく今や「古典」であり、タイトル通り「言語」と「社会」を見るための視点や研究の方法を手際よく整理して提示している。現在、社会言語学についての概論書、入門書は数多く出版されているし、その対象や方法も発展しているけれども、この本に盛り込まれた内容は今日でも(あるいは今日なお)有益であり学ぶことが多い。社会言語学という個別分野だけでなく、言語と社会の関... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「日本国」の主権者であるために
新解説世界憲法集 / 初宿正典, 辻村みよ子編. - 三省堂, 2017
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
宗教を信じつつ宗教を超える
はじめて読む聖書 / 田川建三ほか著. - 新潮社, 2014
 北大ではどこにある?
この本を推薦するのは、僕がキリスト教徒であるからでもなく、『聖書』にありがたみを感じているからでもない。どのような本にせよ、読み手の体験を通してその内面と響き合うものでなければそもそも本を読む意味はないということをこの本の中の第Ⅳ章「レヴィナスを通して読む『旧約聖書』」(内田樹)が慄然たる厳しさを持って教えてくれるからである。この本を手にした人は全部読まなくても良い(読めば読んだでそれなりに得るものはあろうけれども)が、上記の箇所だけはじっくりと読んで欲しい。その上で、関心があればレヴィナスの本に向かうこともお勧めする。わかり... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本を推薦するのは、僕がキリスト教徒であるからでもなく、『聖書』にありがたみを感じているからでもない。どのような本にせよ、読み手の体験を通してその内面と響き合うものでなければそもそも本を読む意味はないということをこの本の中の第Ⅳ章「レヴィナスを通して読む『旧約聖書』」(内田樹)が慄然たる厳しさを持って教えてくれるからである。この本を手にした人は全部読まなくても良い(読めば読んだでそれなりに得るものはあろうけれども)が、上記の箇所だけはじっくりと読んで欲しい。その上で、関心があればレヴィナスの本に向かうこともお勧めする。わかり... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「研究者」になるための知的基礎体力をつけたい人に
これから研究を書くひとのためのガイドブック : ライティングの挑戦15週間 / 佐渡島紗織, 吉野亜矢子著. - ひつじ書房, 2008
 北大ではどこにある?
何年か前に、日本各地の大学で文章表現法関係の授業を担当している教員が集まって実践研修会をしたことがある。各人が自分の授業実践を発表し、ワークショップを通してよりよい授業のあり方を考えるというものだったが、そこで僕が言ったのは、文章表現法の授業をやるということが「自分が教わっていないことを教える”恐怖”」を伴う営為であるということだ。欧米の大学(院)に留学した人は別だろうが、僕自身の高校・大学時代には文章表現法やレポート作成法、論文執筆法は誰も教えてくれなかった。(僕の卒業した大学の教養科目の「文章表現法」は、1年間の総仕上げに短... [続きを読む]
北大ではどこにある?
何年か前に、日本各地の大学で文章表現法関係の授業を担当している教員が集まって実践研修会をしたことがある。各人が自分の授業実践を発表し、ワークショップを通してよりよい授業のあり方を考えるというものだったが、そこで僕が言ったのは、文章表現法の授業をやるということが「自分が教わっていないことを教える”恐怖”」を伴う営為であるということだ。欧米の大学(院)に留学した人は別だろうが、僕自身の高校・大学時代には文章表現法やレポート作成法、論文執筆法は誰も教えてくれなかった。(僕の卒業した大学の教養科目の「文章表現法」は、1年間の総仕上げに短... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「革命」の担い手は誰だったのか。
青きドナウの乱痴気 : ウィーン1848年 / 良知力著. - 平凡社, 1985
 北大ではどこにある?
1848年、西ヨーロッパに勃発した「革命」の一つの舞台となったウィーンでの、様々な人びとの思惑や欲望や理想や愚痴(?)が渦巻く展開を、帝国、国家、権力者の立場からではなく、「革命」に参加した人びとの目線から描いたすぐれた本である。歴史を庶民、あるいは当事者の立場に寄り添って書くということは決して簡単ではない。その困難な試みがいかに為されたかを読み取ってみてほしい。特に、「あとがき」に書かれているグレーテというウィーン子のことばは心に染みる。
北大ではどこにある?
1848年、西ヨーロッパに勃発した「革命」の一つの舞台となったウィーンでの、様々な人びとの思惑や欲望や理想や愚痴(?)が渦巻く展開を、帝国、国家、権力者の立場からではなく、「革命」に参加した人びとの目線から描いたすぐれた本である。歴史を庶民、あるいは当事者の立場に寄り添って書くということは決して簡単ではない。その困難な試みがいかに為されたかを読み取ってみてほしい。特に、「あとがき」に書かれているグレーテというウィーン子のことばは心に染みる。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
研究のための「転ばぬ先の杖」
実証的教育研究の技法 : これでできる教育研究 / 西川純著. - 大学教育出版, 2000
 北大ではどこにある?
この本は著者の学生(大学院生)指導体験から得た知見をもとに書かれた「研究」のための手引き書である。素材の多くは教育学、特に教育現場の実践を想定しており、それらをどのように研究テーマとして成立させ処理していくかについて解説してくれている。副題に「これでできる教育研究」とあるが、実際の教育研究は現場の生身の人間(生徒・学生)を相手にするのだからこの本を読めば全て滞りなく研究ができるというわけではない。そのことは著者自身が最もよく分かっているだろう。それでもこの本を推薦するのは、学生が、壁にぶつかったり悩んだり理解しにくかったりする... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は著者の学生(大学院生)指導体験から得た知見をもとに書かれた「研究」のための手引き書である。素材の多くは教育学、特に教育現場の実践を想定しており、それらをどのように研究テーマとして成立させ処理していくかについて解説してくれている。副題に「これでできる教育研究」とあるが、実際の教育研究は現場の生身の人間(生徒・学生)を相手にするのだからこの本を読めば全て滞りなく研究ができるというわけではない。そのことは著者自身が最もよく分かっているだろう。それでもこの本を推薦するのは、学生が、壁にぶつかったり悩んだり理解しにくかったりする... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
戦後日本の思想的骨格を掴む
日本の思想 / 丸山真男著. - 岩波書店, 1961
 北大ではどこにある?
先日必要があって高校の倫理の用語集を見ていたら、丸山眞男が項目立てされて解説が書かれていたので少しびっくりした。同時にもうそういう時代になったのか(=丸山もそういう存在になったのか)とあらためて感じるものがあった。ということは、かなりの北大生が高校時代におそらくこの『日本の思想』を読んでいると思われるので、今更紹介するまでもないのかもしれないが、まだ読んでいない人のためにここに推薦しておきたい。
北大ではどこにある?
先日必要があって高校の倫理の用語集を見ていたら、丸山眞男が項目立てされて解説が書かれていたので少しびっくりした。同時にもうそういう時代になったのか(=丸山もそういう存在になったのか)とあらためて感じるものがあった。ということは、かなりの北大生が高校時代におそらくこの『日本の思想』を読んでいると思われるので、今更紹介するまでもないのかもしれないが、まだ読んでいない人のためにここに推薦しておきたい。
実は、僕自身はこの本を今読んでも率直に言って“程度の低い常識論”にしか読めない。しかし、裏を返せばそれは、今や常識論に思われるほどに... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
アメリカに生まれて生きる、とは
ボーン・トゥ・ラン : ブルース・スプリングスティーン自伝 / ブルース・スプリングスティーン著 ; 鈴木恵, 加賀山卓朗他訳. - 早川書房, 2016
 北大ではどこにある?
“ボス”と呼ばれるアメリカのロックンロール・ミュージシャン、ブルース・スプリングスティーンが7年をかけて執筆した自伝である。この本から彼の音楽に対する姿勢を窺えるのは当然だが、それ以上にアメリカ東海岸の労働者階級の家庭にアイルランド系、イタリア系、オランダ系という様々な血脈を受けて生まれ育ったスプリングスティーンが自分の出自を絶えず意識しながら音楽を作り演奏していく姿は、日本人のかなりの部分=日本(ヤマト)民族という出自を普段意識することのない存在には、強い印象を与えるであろう。彼の音楽が好きな人だけでなく、帰属意識(カタカナ言... [続きを読む]
北大ではどこにある?
“ボス”と呼ばれるアメリカのロックンロール・ミュージシャン、ブルース・スプリングスティーンが7年をかけて執筆した自伝である。この本から彼の音楽に対する姿勢を窺えるのは当然だが、それ以上にアメリカ東海岸の労働者階級の家庭にアイルランド系、イタリア系、オランダ系という様々な血脈を受けて生まれ育ったスプリングスティーンが自分の出自を絶えず意識しながら音楽を作り演奏していく姿は、日本人のかなりの部分=日本(ヤマト)民族という出自を普段意識することのない存在には、強い印象を与えるであろう。彼の音楽が好きな人だけでなく、帰属意識(カタカナ言... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
国際関係を複眼的に解きほぐす
大英帝国の親日派 : なぜ開戦は避けられなかったか / アントニー・ベスト著 ; 武田知己訳. - 中央公論新社, 2015
 北大ではどこにある?
国際関係、分けても戦時期の国際関係を理解することは容易ではない。この本は、日英の政治家(外交官)に対象を絞り、それぞれの言説と行動を分析しつつ第二次大戦期の日英関係を解明しようとするものである。その際、直接の対象である日英関係の背後にあって大きな影響を及ぼしていた日中、英中、英米、英露の国際関係にも目を配り、当時の国際関係が複眼的に理解できるようになっている点が特徴である。国際関係論や政治学のみならず、歴史記述の方法についても学ぶところの多い本である。
北大ではどこにある?
国際関係、分けても戦時期の国際関係を理解することは容易ではない。この本は、日英の政治家(外交官)に対象を絞り、それぞれの言説と行動を分析しつつ第二次大戦期の日英関係を解明しようとするものである。その際、直接の対象である日英関係の背後にあって大きな影響を及ぼしていた日中、英中、英米、英露の国際関係にも目を配り、当時の国際関係が複眼的に理解できるようになっている点が特徴である。国際関係論や政治学のみならず、歴史記述の方法についても学ぶところの多い本である。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
君は世界をまたにかけるビジネスパースンになれるか?
反省しないアメリカ人をあつかう方法34 / ロッシェル・カップ著. - アルク, 2015
 北大ではどこにある?
北大生の中には将来外資系企業、あるいは海外で働くことを希望している人もいるだろう。また、国内の職場でも上司や同僚や部下が外国人という環境は最早珍しくない。この本は、「反省しないアメリカ人を~」と書いてあるとおり、アメリカ人の、主に従業員に対してどう接し、どのように良好なビジネス上の関係を構築するかについてアドバイスを述べたものであるが、アメリカ人に限らず異なる文化的背景の人間―日本人でもその範疇に入ってくる可能性は大いにある―と仕事をする上でヒントになるものと思う。比較文化研究や異文化間コミュニケーションに関心のある人には、色... [続きを読む]
北大ではどこにある?
北大生の中には将来外資系企業、あるいは海外で働くことを希望している人もいるだろう。また、国内の職場でも上司や同僚や部下が外国人という環境は最早珍しくない。この本は、「反省しないアメリカ人を~」と書いてあるとおり、アメリカ人の、主に従業員に対してどう接し、どのように良好なビジネス上の関係を構築するかについてアドバイスを述べたものであるが、アメリカ人に限らず異なる文化的背景の人間―日本人でもその範疇に入ってくる可能性は大いにある―と仕事をする上でヒントになるものと思う。比較文化研究や異文化間コミュニケーションに関心のある人には、色... [続きを読む]登録日 : 2017-08-07
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
哲学を体現した人の生涯
ウィトゲンシュタイン : 天才哲学者の思い出 / ノーマン・マルコム著 ; 板坂元訳. - 平凡社, 1998
 北大ではどこにある?
20世紀以降の哲学に最も影響力のあった哲学者ウィトゲンシュタインに親しく接した著者が、その人柄、哲学に対する姿勢、同時代人との関わりからゼミナールの雰囲気までを生き生きと描いた人物伝である。ウィトゲンシュタインの哲学に関心がなくても、哲学者という人びとが自分の思索にどのような姿勢で臨んでいるかを知る上で一読の価値がある。
北大ではどこにある?
20世紀以降の哲学に最も影響力のあった哲学者ウィトゲンシュタインに親しく接した著者が、その人柄、哲学に対する姿勢、同時代人との関わりからゼミナールの雰囲気までを生き生きと描いた人物伝である。ウィトゲンシュタインの哲学に関心がなくても、哲学者という人びとが自分の思索にどのような姿勢で臨んでいるかを知る上で一読の価値がある。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
やっぱり大学の未来は心配だ。
Fランク化する大学 / 音真司著. - 小学館, 2016
 北大ではどこにある?
この本を「本は脳を育てる」に推薦することに対して旧帝国大学である“天下の北海道大学”の真面目な先生や優秀な学生から異論や批判が巻き起こるかもしれない。筆者自身も、この本に書いてあることは100%そのままであるとは思いたくないし、著者がやや大げさに書いている=「話を盛っている」面もあるかもしれないと思っている。しかし、他大学につとめる友人知人の現場の声を聞くと、ここに書いてあることを頭ごなしに否定することもできないと思う。そして、筆者自身が何より恐れるのは、―ここまでひどくないとしても―これらに近似する状況がここ数年の間に静かに北海道... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本を「本は脳を育てる」に推薦することに対して旧帝国大学である“天下の北海道大学”の真面目な先生や優秀な学生から異論や批判が巻き起こるかもしれない。筆者自身も、この本に書いてあることは100%そのままであるとは思いたくないし、著者がやや大げさに書いている=「話を盛っている」面もあるかもしれないと思っている。しかし、他大学につとめる友人知人の現場の声を聞くと、ここに書いてあることを頭ごなしに否定することもできないと思う。そして、筆者自身が何より恐れるのは、―ここまでひどくないとしても―これらに近似する状況がここ数年の間に静かに北海道... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
モンゴルの魅力に近づくために
草原の革命家たち : モンゴル独立への道 / 田中克彦著. - 中央公論社, 1990
 北大ではどこにある?
この「本は脳を育てる」の過去の推薦文に何回か書いたことであるが、僕は1990年代にエジプトに赴任していた。だが、最初に赴任先候補地としてあげられたのは、実はモンゴルであった。それがどこかでどうにかこうにかなってエジプトに落ち着いた(?)のであるが、今でも時々、あのときモンゴルに行っていたらどうなっていただろうかと思うことがある。今は、モンゴルと言えば相撲の世界が思い浮かぶだろうが、多くの日本人の間でこの国の歴史と現在の姿は意外に知られていないと言ってよいだろう。この本は、モンゴルが中国、ソヴィエトという巨大な国に挟まれて―しかもここ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この「本は脳を育てる」の過去の推薦文に何回か書いたことであるが、僕は1990年代にエジプトに赴任していた。だが、最初に赴任先候補地としてあげられたのは、実はモンゴルであった。それがどこかでどうにかこうにかなってエジプトに落ち着いた(?)のであるが、今でも時々、あのときモンゴルに行っていたらどうなっていただろうかと思うことがある。今は、モンゴルと言えば相撲の世界が思い浮かぶだろうが、多くの日本人の間でこの国の歴史と現在の姿は意外に知られていないと言ってよいだろう。この本は、モンゴルが中国、ソヴィエトという巨大な国に挟まれて―しかもここ... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
日本人はアジアとどう向き合ってきたか
日本とアジア / 竹内好著. - 筑摩書房, 1993
 北大ではどこにある?
これは、竹内好という稀代の中国文学者の手になるすぐれた日本、及びアジア研究の書である。初版が刊行されてから50年以上が経過しているが、そこに示される分析(あるいは同時代思想批判の)の観点には今なお学ぶものが多くある。中国、アジアだけでなく、というよりむしろ欧米社会・文化に関心を持つ人にこそ読んでほしいと思う。特に「二つのアジア史観」、「方法としてのアジア」は人文社会科学を勉強する上で貴重な示唆を含んでいる。
北大ではどこにある?
これは、竹内好という稀代の中国文学者の手になるすぐれた日本、及びアジア研究の書である。初版が刊行されてから50年以上が経過しているが、そこに示される分析(あるいは同時代思想批判の)の観点には今なお学ぶものが多くある。中国、アジアだけでなく、というよりむしろ欧米社会・文化に関心を持つ人にこそ読んでほしいと思う。特に「二つのアジア史観」、「方法としてのアジア」は人文社会科学を勉強する上で貴重な示唆を含んでいる。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「知の巨人」たちはいかに思索したか
柳田国男と梅棹忠夫 : 自前の学問を求めて / 伊藤幹治著. - 岩波書店, 2011
 北大ではどこにある?
先に竹内好の『日本とアジア』をこの「本は脳を育てる」に推薦したが、その中で竹内好がしばしば言及している一人が梅棹忠夫である。日本の知識人―という言い方を梅棹は嫌うだろうが―のアジア理解、文明観を問題にする上で避けて通れないと竹内は感じ取ったのだろう。その梅棹の知的営為を、先行する柳田国男のそれと対比的に考察し、そこに共通するものと相違するものを読み解こうとしたのが本書である。一つの学問を作り上げることの奥深さを知ることのできる好著として推薦したい。
北大ではどこにある?
先に竹内好の『日本とアジア』をこの「本は脳を育てる」に推薦したが、その中で竹内好がしばしば言及している一人が梅棹忠夫である。日本の知識人―という言い方を梅棹は嫌うだろうが―のアジア理解、文明観を問題にする上で避けて通れないと竹内は感じ取ったのだろう。その梅棹の知的営為を、先行する柳田国男のそれと対比的に考察し、そこに共通するものと相違するものを読み解こうとしたのが本書である。一つの学問を作り上げることの奥深さを知ることのできる好著として推薦したい。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
それでも君はボランティアをするか?!
ボランティアという病 / 丸山千夏著. - 宝島社, 2016
 北大ではどこにある?
ボランティアはいいことだと思っている人、実際にやってみたことはないが関わってみたいという潜在的な魅力を感じている人は少なくないと思われる。しかし、ボランティアが全て手放しで賞賛されるべきものかというとそうでもない。この本は、「ヤバい」ボランティア、あるいはボランティアの「ヤバさ」についていろいろと教えてくれる。内容には賛否両論あるだろうが、「善意」が無条件にもてはやされることに疑問を感じるなら、折角のボランティア参加が心ならずも不本意な結果に終わらないよう一度目を通しておいてもいいと思う。
北大ではどこにある?
ボランティアはいいことだと思っている人、実際にやってみたことはないが関わってみたいという潜在的な魅力を感じている人は少なくないと思われる。しかし、ボランティアが全て手放しで賞賛されるべきものかというとそうでもない。この本は、「ヤバい」ボランティア、あるいはボランティアの「ヤバさ」についていろいろと教えてくれる。内容には賛否両論あるだろうが、「善意」が無条件にもてはやされることに疑問を感じるなら、折角のボランティア参加が心ならずも不本意な結果に終わらないよう一度目を通しておいてもいいと思う。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
韓国は「異星」である、か?
韓国、愛と思想の旅 / 小倉紀藏. - 大修館書店, 2004
 北大ではどこにある?
仕事柄韓国人留学生とのつきあいが少なからずあるが、いつも彼ら彼女らとの独特の距離の置き方にはかなりデリケートに神経を使う。こういうことを“国際交流”の入り口で仕事をしている人間が書くと問題だと感じる人もいるだろうが、むしろそうした仕事をしているからこそ適度な距離感が必要であるとも言える。この小倉氏の本は、韓国滞在・渡航経験の中でその距離を縮めようとしてついに叶わなかった(もしくは彼なりのやり方でその距離を消滅させていった)異文化間コンフリクトの記録である。韓国に対する読者のスタンスの取り方に応じてそれなりに“ツッコミどころ”も... [続きを読む]
北大ではどこにある?
仕事柄韓国人留学生とのつきあいが少なからずあるが、いつも彼ら彼女らとの独特の距離の置き方にはかなりデリケートに神経を使う。こういうことを“国際交流”の入り口で仕事をしている人間が書くと問題だと感じる人もいるだろうが、むしろそうした仕事をしているからこそ適度な距離感が必要であるとも言える。この小倉氏の本は、韓国滞在・渡航経験の中でその距離を縮めようとしてついに叶わなかった(もしくは彼なりのやり方でその距離を消滅させていった)異文化間コンフリクトの記録である。韓国に対する読者のスタンスの取り方に応じてそれなりに“ツッコミどころ”も... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
その日本語にはわけがある!
揺れ動くニホン語 : 問題なことばの生態 / 田中章夫. - 東京堂書店, 2007
 北大ではどこにある?
「日本語の乱れ」ということが時々メディアを賑わせる。しかし、これは言ってみればジャーナリズムや素朴な庶民感覚レベルの言い方で、その背後には(どこかに)“正しい(あるいは美しい)”日本語のあるべき用い方がある(はずだ)という一種の思い込みが隠れている。言語研究の観点から言えばこれが「乱れ」ではなく「変化」や「揺れ」であることは専門家の間では周知のことである。この本は、多様な現れ方をする日本語の表現を歴史的・計量的に分析し、実は「乱れ」と見えたものもそれなりの背景や理由があることを分かりやすく説明している。言語現象に対する切り口も... [続きを読む]
北大ではどこにある?
「日本語の乱れ」ということが時々メディアを賑わせる。しかし、これは言ってみればジャーナリズムや素朴な庶民感覚レベルの言い方で、その背後には(どこかに)“正しい(あるいは美しい)”日本語のあるべき用い方がある(はずだ)という一種の思い込みが隠れている。言語研究の観点から言えばこれが「乱れ」ではなく「変化」や「揺れ」であることは専門家の間では周知のことである。この本は、多様な現れ方をする日本語の表現を歴史的・計量的に分析し、実は「乱れ」と見えたものもそれなりの背景や理由があることを分かりやすく説明している。言語現象に対する切り口も... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
真実の発見に生涯をかけた医師のドラマ
手洗いの疫学とゼンメルワイスの闘い / 玉城英彦. - 人間と歴史社, 2017
 北大ではどこにある?
今年2月のある日、この本の著者である玉城英彦先生(現名誉教授)が僕の研究室に突然いらして、「中村先生、最近元気ないみたいだけどこの本を読めば元気になるよ」と仰言ってサイン入りの本をくださった。その頃そんなに元気がなさそうだったのか、自分では分からないのだけれども成績提出などのドタバタで疲れていたことは確かだ。折角頂いたご本なのだが、その後もあれこれと忙しく、5月になってからようやく読むことができた。そして、確かに少し元気になれたので、こうして推薦することにした次第である。
北大ではどこにある?
今年2月のある日、この本の著者である玉城英彦先生(現名誉教授)が僕の研究室に突然いらして、「中村先生、最近元気ないみたいだけどこの本を読めば元気になるよ」と仰言ってサイン入りの本をくださった。その頃そんなに元気がなさそうだったのか、自分では分からないのだけれども成績提出などのドタバタで疲れていたことは確かだ。折角頂いたご本なのだが、その後もあれこれと忙しく、5月になってからようやく読むことができた。そして、確かに少し元気になれたので、こうして推薦することにした次第である。
ゼンメルワイスと産褥熱の研究については、僕も中学生時代に読... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
言語をめぐる思惟を広く捉えるために
ドイツ言語哲学の諸相 / 麻生建. - 東京大学出版会, 1989
 北大ではどこにある?
以前奨めてくれる人があって、飯田隆『言語哲学大全Ⅰ~Ⅳ』(勁草書房)を読んでみたことがある。確かに現代の言語哲学、あるいは分析哲学をフレーゲからデヴィッドソンまで熱く語っている良書ではあるのだが、これをもって「大全」ということには大きな不満を覚える。その点は飯田氏も分かっているようで、第Ⅰ巻の冒頭で「『大全』というのは、さすがに私にしても調子に乗り過ぎという感がしないでもない」と書いている。この本を「大全」と言ってほしくないのは、対象がフレーゲとヴィトゲン... [続きを読む]
北大ではどこにある?
以前奨めてくれる人があって、飯田隆『言語哲学大全Ⅰ~Ⅳ』(勁草書房)を読んでみたことがある。確かに現代の言語哲学、あるいは分析哲学をフレーゲからデヴィッドソンまで熱く語っている良書ではあるのだが、これをもって「大全」ということには大きな不満を覚える。その点は飯田氏も分かっているようで、第Ⅰ巻の冒頭で「『大全』というのは、さすがに私にしても調子に乗り過ぎという感がしないでもない」と書いている。この本を「大全」と言ってほしくないのは、対象がフレーゲとヴィトゲン... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「日本語を教える」現場の熱気を伝える
世界の日本語教室から-日本を伝える30ヵ国の日本語教師レポート- / 国際交流基金. - アルク, 2009
 北大ではどこにある?
ここ何年か国際教育研究センターで(旧留学生センター時代から)全学教育科目に「外国人に日本語を教える」という「総合科目」を提供している。受講動機は様々であろうが日本語教育に関心を持ってくれる学生が一定数いるようで関係者としては有り難く思っている。この本は、そんな、日本語教育に関心を持っている学生がちょっとだけその―特に海外の―現場を覗いてみたいと思った時に気軽に読めるものとして紹介しておきたい。内容は、外務省の外郭団体である国際交流基金が世界各国に派遣した日本語教育専門家の手になる現地レポートである。日本語教育の現場の雰囲気を少しで... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ここ何年か国際教育研究センターで(旧留学生センター時代から)全学教育科目に「外国人に日本語を教える」という「総合科目」を提供している。受講動機は様々であろうが日本語教育に関心を持ってくれる学生が一定数いるようで関係者としては有り難く思っている。この本は、そんな、日本語教育に関心を持っている学生がちょっとだけその―特に海外の―現場を覗いてみたいと思った時に気軽に読めるものとして紹介しておきたい。内容は、外務省の外郭団体である国際交流基金が世界各国に派遣した日本語教育専門家の手になる現地レポートである。日本語教育の現場の雰囲気を少しで... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
イスラム教を「信じる」とはどのようなことか
日本の中でイスラム教を信じる / 佐藤兼永. - 文藝春秋社, 2015
 北大ではどこにある?
日本社会の中ではイスラム教信者、中でも特に日本人の信者というのは姿が見えにくい存在である。この本は、日本社会の中でイスラム教信仰に生きる人びとの姿を描いたルポルタージュであり、イスラム世界というものが西アジア・中東・アフリカという遠いところにある(だけな)のではなく、我々のすぐそばにもあるものだということに気づかせてくれる。現在、多少緩和されたとはいえ、まだイスラム教に対する様々な偏見が社会の中に存在することは否定できない。著者の佐藤氏は、その偏見を我々も持つことを認めた上でそれを肯定的なものへと転換する契機を示してくれている... [続きを読む]
北大ではどこにある?
日本社会の中ではイスラム教信者、中でも特に日本人の信者というのは姿が見えにくい存在である。この本は、日本社会の中でイスラム教信仰に生きる人びとの姿を描いたルポルタージュであり、イスラム世界というものが西アジア・中東・アフリカという遠いところにある(だけな)のではなく、我々のすぐそばにもあるものだということに気づかせてくれる。現在、多少緩和されたとはいえ、まだイスラム教に対する様々な偏見が社会の中に存在することは否定できない。著者の佐藤氏は、その偏見を我々も持つことを認めた上でそれを肯定的なものへと転換する契機を示してくれている... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
現代に活きる「古典」
人口論 / マルサス. - 光文社, 2011
 北大ではどこにある?
この『人口論』は、食糧供給と人口増加の関係を軸に貧困や失業や労働移動などの社会問題にどのように対応するべきかを考察した古典である。18世紀のイングランドが叙述の背景となっているが、マルサスが述べる考察は現代のアクチュアルな問題に通じるものであることを納得できるであろう。古典が現代に活きることを示すものとして薦めたい。
北大ではどこにある?
この『人口論』は、食糧供給と人口増加の関係を軸に貧困や失業や労働移動などの社会問題にどのように対応するべきかを考察した古典である。18世紀のイングランドが叙述の背景となっているが、マルサスが述べる考察は現代のアクチュアルな問題に通じるものであることを納得できるであろう。古典が現代に活きることを示すものとして薦めたい。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「ボランティア」のあり方を見つめ直すために
「ボランティア」の誕生と終焉 : 「贈与のパラドックス」の知識社会学 / 仁平典宏. - 名古屋大学出版会, 2011
 北大ではどこにある?
学生時代に7年ほどあるボランティア活動に携わっていたことがあるのだが、最初に活動に参加しようとした時、親に言われたのは「自分の頭のハエも追えない奴が偉そうに人助けなんかやるな!」という暴言(!)であった。今考えてもあんまりな言い方だと思うが、そうした意識は程度の差こそあれ日本の社会にある時期流通していたボランティア理解ではなかったかとも思う。この本の帯には「『善意』と『冷笑』の狭間で」と書かれているのだが、このことばはボランティアというものに対して注がれる、あるいは浴びせられる視線の複雑さを見事に言い当てている。そうした複雑さを... [続きを読む]
北大ではどこにある?
学生時代に7年ほどあるボランティア活動に携わっていたことがあるのだが、最初に活動に参加しようとした時、親に言われたのは「自分の頭のハエも追えない奴が偉そうに人助けなんかやるな!」という暴言(!)であった。今考えてもあんまりな言い方だと思うが、そうした意識は程度の差こそあれ日本の社会にある時期流通していたボランティア理解ではなかったかとも思う。この本の帯には「『善意』と『冷笑』の狭間で」と書かれているのだが、このことばはボランティアというものに対して注がれる、あるいは浴びせられる視線の複雑さを見事に言い当てている。そうした複雑さを... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
ネット空間で被害者にも加害者にもならないようにするために。
ネット炎上の研究 : 誰があおり、どう対処するのか / 田中辰雄, 山口真一著. - 勁草書房, 2016
 北大ではどこにある?
この本は、インターネット上で発生するいわゆる「炎上」という現象を分析し、その実態と歴史(!)と対応策を分かりやすく述べている。特に最後の「付録 炎上リテラシー教育のひな型」では、高校生を対象として想定し、「炎上」の仕組みとそれに巻き込まれそうになったらどうするべきかを丁寧に説いてくれている。インターネットがこれだけ広範囲に利用されるようになった社会で安全に生活し、かつ自分が加害者にならないためにも読んでおくべき1冊である。
北大ではどこにある?
この本は、インターネット上で発生するいわゆる「炎上」という現象を分析し、その実態と歴史(!)と対応策を分かりやすく述べている。特に最後の「付録 炎上リテラシー教育のひな型」では、高校生を対象として想定し、「炎上」の仕組みとそれに巻き込まれそうになったらどうするべきかを丁寧に説いてくれている。インターネットがこれだけ広範囲に利用されるようになった社会で安全に生活し、かつ自分が加害者にならないためにも読んでおくべき1冊である。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「戦争」を陳腐なことばで語らないために
ひとりの記憶 : 海の向こうの戦争と、生き抜いた人たち / 橋口譲二. - 文藝春秋, 2016
 北大ではどこにある?
この本は、太平洋戦争前後に植民地を含む海外に渡り、様々な事情でその地に残り、あるいは再渡航してそこで生き抜くことを選んだ人々からの聞き取りの記録である。現代に於ける戦争に対する反対・批判・抑止のことばの一つとして「戦争は人間の運命を狂わせる」といったものがある。それを否定するつもりはないし、そうした事例もあることを認めはするが、この本を読んだあとでここに描かれている人々の人生が戦争によって“狂った(あるいは狂わされた)”と―「戦争を知らない子供たち」である我々が―いうことには大きな躊躇いを覚えてしまう。その背後にあったはずのお... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、太平洋戦争前後に植民地を含む海外に渡り、様々な事情でその地に残り、あるいは再渡航してそこで生き抜くことを選んだ人々からの聞き取りの記録である。現代に於ける戦争に対する反対・批判・抑止のことばの一つとして「戦争は人間の運命を狂わせる」といったものがある。それを否定するつもりはないし、そうした事例もあることを認めはするが、この本を読んだあとでここに描かれている人々の人生が戦争によって“狂った(あるいは狂わされた)”と―「戦争を知らない子供たち」である我々が―いうことには大きな躊躇いを覚えてしまう。その背後にあったはずのお... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「東洋」と「西洋」とは何か、あらためて考える。
東洋意識 : 夢想と現実のあいだ1887-1953 / 稲賀繁美編著. - ミネルヴァ書房, 2012
 北大ではどこにある?
学問―特に人文科学―の世界に於ける「東洋-西洋」という枠組み或いは二分法は、実は相当にうさんくさい。そのうさんくささを“学問的に”剔抉したのは言うまでもなくエドワード・サイードの『オリエンタリズム』だったが、そのとらえ方自体が西洋的な学問世界の中で一定の権威になってしまうという戯画的な状況が生まれ、相変わらず「東洋-西洋」という枠組みをめぐる思索は混迷している。今回推薦する本は、編著者の稲賀氏自身が書いているように「『東洋』と呼ばれる―あるいは時代遅れとな... [続きを読む]
北大ではどこにある?
学問―特に人文科学―の世界に於ける「東洋-西洋」という枠組み或いは二分法は、実は相当にうさんくさい。そのうさんくささを“学問的に”剔抉したのは言うまでもなくエドワード・サイードの『オリエンタリズム』だったが、そのとらえ方自体が西洋的な学問世界の中で一定の権威になってしまうという戯画的な状況が生まれ、相変わらず「東洋-西洋」という枠組みをめぐる思索は混迷している。今回推薦する本は、編著者の稲賀氏自身が書いているように「『東洋』と呼ばれる―あるいは時代遅れとな... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
異文化理解はぼちぼちこのあたりから…。
異文化理解の落とし穴 : 中国・日本・アメリカ / 張競. - 岩波書店, 2011
 北大ではどこにある?
この本は、上海出身中国人で日本に留学し学位を得て日本で教職に就きアメリカで研究生活も送った著者の異文化体験の記録である。読後感としては標題にあるような「異文化理解」というレベルに達しているとは思えないし、ましてやその「落とし穴」を明解にしているとも言い切れない。むしろ表層的な体験と感想が連ねられているというのが率直なところである。しかし、それは裏を返せば、「異文化理解」ということに到達するには誰もがこの段階をくぐらなければならないということを示す一つの基準点になり得ている、ということであり、また、日本に限らず「文化」というもの... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、上海出身中国人で日本に留学し学位を得て日本で教職に就きアメリカで研究生活も送った著者の異文化体験の記録である。読後感としては標題にあるような「異文化理解」というレベルに達しているとは思えないし、ましてやその「落とし穴」を明解にしているとも言い切れない。むしろ表層的な体験と感想が連ねられているというのが率直なところである。しかし、それは裏を返せば、「異文化理解」ということに到達するには誰もがこの段階をくぐらなければならないということを示す一つの基準点になり得ている、ということであり、また、日本に限らず「文化」というもの... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
世界はどうしてこうなっているのか。
エジプトを植民地化する : 博覧会世界と規律訓練的権力 / ティモシー・ミッチェル著 ; 大塚和夫, 赤堀雅幸訳. - 法政大学出版局, 2014
 北大ではどこにある?
一見この本とは関係なさそうな話から推薦文を書く。みなさんは、観光旅行に行くとはどのようなことだと思っているだろうか。理由はいろいろあるにせよ、大きな共通点は世界遺産に代表されるような歴史的建造物や名所旧跡を辿ることが目的である、ということだろう。しかし、である。その時、観光旅行する我々は、実は名所旧跡を”見に”行っているのではなく、ガイドブックなどに一定の秩序で並べられた空間の”確認”をしに行っているに過ぎないのである。なぜそう言えるのか、の答えを与えてくれるのが、この本の副題になっている「博覧会世界」である。
北大ではどこにある?
一見この本とは関係なさそうな話から推薦文を書く。みなさんは、観光旅行に行くとはどのようなことだと思っているだろうか。理由はいろいろあるにせよ、大きな共通点は世界遺産に代表されるような歴史的建造物や名所旧跡を辿ることが目的である、ということだろう。しかし、である。その時、観光旅行する我々は、実は名所旧跡を”見に”行っているのではなく、ガイドブックなどに一定の秩序で並べられた空間の”確認”をしに行っているに過ぎないのである。なぜそう言えるのか、の答えを与えてくれるのが、この本の副題になっている「博覧会世界」である。
この本は、表題か... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
おじさんも、若い人も語学を楽しむために
おじさん、語学する / 塩田勉. - 集英社, 2001
 北大ではどこにある?
あるきっかけからフランス語を勉強することになったおじさんの奮闘記、という形をとって語学を身につけるための秘訣と、それだけでなく異文化との関わり方を気づかせてくれるユニークな本。語学大好きな人にも語学嫌いな人にもお薦めしたい。
北大ではどこにある?
あるきっかけからフランス語を勉強することになったおじさんの奮闘記、という形をとって語学を身につけるための秘訣と、それだけでなく異文化との関わり方を気づかせてくれるユニークな本。語学大好きな人にも語学嫌いな人にもお薦めしたい。
ただ、悲しいかな外国語の先生は日本語はお得意ではないようで、この中にも日本語の間違いが一箇所ある。探してみてほしい。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
やっぱり東京大学は凄い…。
アクティブラーニングのデザイン : 東京大学の新しい教養教育 / 永田敬, 林一雅編. - 東京大学出版会, 2016
 北大ではどこにある?
平成24年8月24日付中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~」に於いて、今後の中等教育・大学教育に積極的にアクティブ・ラーニング型授業を導入するべきであることが打ち出された。この本は、東京大学教養学部で実践されたアクティブラーニングの理念と方略を報告したものである。読者としては、これからアクティブラーニングに取り組もうとする大学教員を想定しているものであるが、学生が読んでも21世紀に求められる能力をどの... [続きを読む]
北大ではどこにある?
平成24年8月24日付中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~」に於いて、今後の中等教育・大学教育に積極的にアクティブ・ラーニング型授業を導入するべきであることが打ち出された。この本は、東京大学教養学部で実践されたアクティブラーニングの理念と方略を報告したものである。読者としては、これからアクティブラーニングに取り組もうとする大学教員を想定しているものであるが、学生が読んでも21世紀に求められる能力をどの... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「音楽」に対する屈折した思い
ピアニストのノート / ヴァレリー・アファナシエフ. - 講談社, 2012
 北大ではどこにある?
著者のアファナシエフの演奏を学生時代に聴いたことがある。山田一雄指揮の東京都交響楽団定期演奏会でシューマンの「ピアノ協奏曲」だった。なぜそんな昔のことを覚えているかというと、その時初めて聴いたアファナシエフの演奏が非常に“奇妙”だったからである。「違和感」というのでもない、「斬新」というのでもない、ただ、「こんなふうにシューマンも弾けるんだ」という感覚を抱いたことを今でも覚えている。その後、彼のプロフィールなどを知る機会もあったが、この本を読んでみて昔聴いた演奏とどこか重なり合うような感覚を思い出すことができた。この本は、エッ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
著者のアファナシエフの演奏を学生時代に聴いたことがある。山田一雄指揮の東京都交響楽団定期演奏会でシューマンの「ピアノ協奏曲」だった。なぜそんな昔のことを覚えているかというと、その時初めて聴いたアファナシエフの演奏が非常に“奇妙”だったからである。「違和感」というのでもない、「斬新」というのでもない、ただ、「こんなふうにシューマンも弾けるんだ」という感覚を抱いたことを今でも覚えている。その後、彼のプロフィールなどを知る機会もあったが、この本を読んでみて昔聴いた演奏とどこか重なり合うような感覚を思い出すことができた。この本は、エッ... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
運命の残酷さとは
ベルリン、愛の物語 : エメーとジャガー / エーリカ・フィッシャー. - 平凡社, 1998
 北大ではどこにある?
これは、第二次世界大戦期のベルリンに生きた二人の女性同性愛者の運命の記録である。そして、彼女たちの1人はナチスの軍人の妻であり、もう1人は密かにナチスの目を逃れて暮らすユダヤ人だった。あとは本書を読んでいただく方がここに下手な推薦文を書くよりも遙かにその事実が持つ運命的な過酷さとそのような状況を生み出す戦争の本質を感じ取れると思う。彼女たち2人だけでなく、ナチス政権下のベルリンに潜伏するユダヤ人青年たちがどのようにして生き延びるかをそれこそ命がけで考え抜く場面を読んだときには胸が凍るような息苦しさを覚えたものである。
北大ではどこにある?
これは、第二次世界大戦期のベルリンに生きた二人の女性同性愛者の運命の記録である。そして、彼女たちの1人はナチスの軍人の妻であり、もう1人は密かにナチスの目を逃れて暮らすユダヤ人だった。あとは本書を読んでいただく方がここに下手な推薦文を書くよりも遙かにその事実が持つ運命的な過酷さとそのような状況を生み出す戦争の本質を感じ取れると思う。彼女たち2人だけでなく、ナチス政権下のベルリンに潜伏するユダヤ人青年たちがどのようにして生き延びるかをそれこそ命がけで考え抜く場面を読んだときには胸が凍るような息苦しさを覚えたものである。
この本はか... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
いつの時代にも共通する「悶々」
恋愛論 / スタンダール. - 岩波書店,
 北大ではどこにある?
スタンダールの『恋愛論』と言えば、「結晶作用」や「恋愛の四分類」であまりにも有名であるが、これらのことばだけが一人歩きしてしまっている観がなきにしもあらずである。この本は、周知のようにスタンダール自身がある女性との恋愛に悶々としていた経験を下敷きにして、当時のヨーロッパの知識人の12世紀から18世紀にわたる古典的教養を背景として書かれた人間観察の集成と言えるものである。そこに描かれる様々な恋愛事情の「悶々」は、21世紀日本の我々には分かりにくい部分や、今なら御法度になる部分を含んではいるものの恋愛という経験について今なお教えてくれると... [続きを読む]
北大ではどこにある?
スタンダールの『恋愛論』と言えば、「結晶作用」や「恋愛の四分類」であまりにも有名であるが、これらのことばだけが一人歩きしてしまっている観がなきにしもあらずである。この本は、周知のようにスタンダール自身がある女性との恋愛に悶々としていた経験を下敷きにして、当時のヨーロッパの知識人の12世紀から18世紀にわたる古典的教養を背景として書かれた人間観察の集成と言えるものである。そこに描かれる様々な恋愛事情の「悶々」は、21世紀日本の我々には分かりにくい部分や、今なら御法度になる部分を含んではいるものの恋愛という経験について今なお教えてくれると... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
今読まずにいつ読むか。
言論・出版の自由 / ジョン・ミルトン. - 岩波書店, 2008
 北大ではどこにある?
つい最近、マスメディアに対する権力側の幾つかの横暴とも言える対応が報道された。報道機関やジャーナリストたちはそれなりに危機感を示しているもののいよいよ政治権力が牙をむき始めた、という慄然たる思いがする。大学に身を置く我々にとって大切な、日本国憲法で保障されている学問・良心の自由もいつ危うくなるか分からない。その前に読んでおくべきものとしてこの本を推薦しておく。
北大ではどこにある?
つい最近、マスメディアに対する権力側の幾つかの横暴とも言える対応が報道された。報道機関やジャーナリストたちはそれなりに危機感を示しているもののいよいよ政治権力が牙をむき始めた、という慄然たる思いがする。大学に身を置く我々にとって大切な、日本国憲法で保障されている学問・良心の自由もいつ危うくなるか分からない。その前に読んでおくべきものとしてこの本を推薦しておく。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
東北大震災以後の日本を世界史的規模で考える
3・11以後この絶望の国で : 死者の語りの地平から / 山形孝夫・西谷修. - ぷねうま舎, 2014
 北大ではどこにある?
この本は、東北大震災で被災した宗教学者の山形孝夫氏と、現代思想のあり方を問い続けてきた哲学者の西谷修氏との対談である。表題を見ると、現代の日本を直接の対象としているようであるが、むしろ対談者のお二人の中心問題は、(制度的)キリスト教世界の成立とそれが世界に何をもたらしたかということにあり、その延長線上で、ある時点から道を踏み外し始めた世界と、「死者の口封じ」の道具と化してしまった宗教への危機感が語られる。東北大震災はその具体的な危機の露呈の現場として考察され、その危機的状況からのどのような救いの道があるかは、山形氏の”つぶやき... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、東北大震災で被災した宗教学者の山形孝夫氏と、現代思想のあり方を問い続けてきた哲学者の西谷修氏との対談である。表題を見ると、現代の日本を直接の対象としているようであるが、むしろ対談者のお二人の中心問題は、(制度的)キリスト教世界の成立とそれが世界に何をもたらしたかということにあり、その延長線上で、ある時点から道を踏み外し始めた世界と、「死者の口封じ」の道具と化してしまった宗教への危機感が語られる。東北大震災はその具体的な危機の露呈の現場として考察され、その危機的状況からのどのような救いの道があるかは、山形氏の”つぶやき... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
物語はまだ終わらない。
水滸後伝 / 陳忱. - 平凡社, 1966
 北大ではどこにある?
ここに推薦するのは、『水滸後伝』である。『水滸伝』ではない。まずその点を間違えないようにお願いしたい。『水滸伝』=本編を推薦していないのに『水滸後伝』=続編を推薦するのは無茶苦茶だという批判もあることは承知の上である。ましてや僕は、本編は横山光輝の漫画版で読んだ(だけな)ので、この推薦はなおさら無謀である。しかしそれでもなお推薦するには理由がある。一つには、大方の学生諸君は小説であれ漫画版であれ本編を読んでいる人は多いだろうと想像できること、二つには、続編という位置づけながらそれ自体でなかなか想像力に溢れた活劇として面白い、と... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ここに推薦するのは、『水滸後伝』である。『水滸伝』ではない。まずその点を間違えないようにお願いしたい。『水滸伝』=本編を推薦していないのに『水滸後伝』=続編を推薦するのは無茶苦茶だという批判もあることは承知の上である。ましてや僕は、本編は横山光輝の漫画版で読んだ(だけな)ので、この推薦はなおさら無謀である。しかしそれでもなお推薦するには理由がある。一つには、大方の学生諸君は小説であれ漫画版であれ本編を読んでいる人は多いだろうと想像できること、二つには、続編という位置づけながらそれ自体でなかなか想像力に溢れた活劇として面白い、と... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
この難しい時代をどう生きるか
感情で釣られる人々 : なぜ理性は負け続けるのか / 堀内進之介. - 集英社, 2016
 北大ではどこにある?
去年から書店の本棚に“反知性主義”ということばを含む表題の本が並ぶようになってきた。国内・国外にわたって難しい問題が山積し、それらに対する処方箋がなかなか見つからない中で人びとのある種のいらだちのようなものが確かに感じられるし、それが時としてこれまでの価値観に対する破れかぶれの破壊衝動のように見える場合もあって、そのようなことばが現代社会の懸念すべき問題として本の表題になることは理解できる。しかし、その一方で、問題のあり方が様々に複雑化・多様化している世界の状況を“反知性主義”という術語で語ろうとするのもある種の“メタ・反知性... [続きを読む]
北大ではどこにある?
去年から書店の本棚に“反知性主義”ということばを含む表題の本が並ぶようになってきた。国内・国外にわたって難しい問題が山積し、それらに対する処方箋がなかなか見つからない中で人びとのある種のいらだちのようなものが確かに感じられるし、それが時としてこれまでの価値観に対する破れかぶれの破壊衝動のように見える場合もあって、そのようなことばが現代社会の懸念すべき問題として本の表題になることは理解できる。しかし、その一方で、問題のあり方が様々に複雑化・多様化している世界の状況を“反知性主義”という術語で語ろうとするのもある種の“メタ・反知性... [続きを読む]