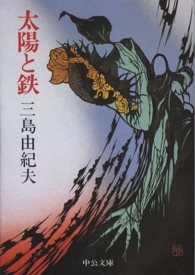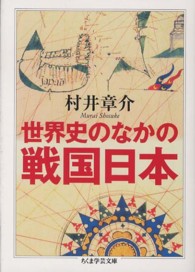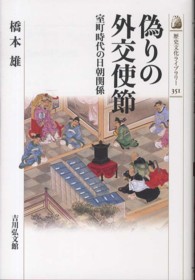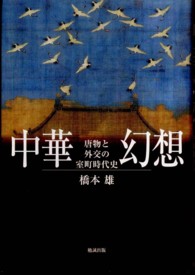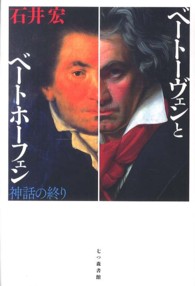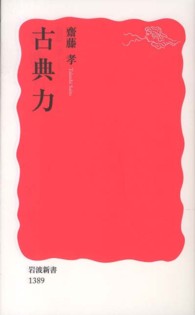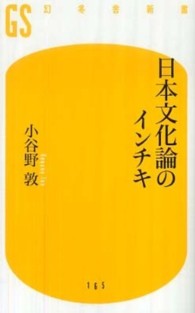-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
西田哲学の実践としての西田評伝
西田幾多郎 / 大橋良介. - ミネルヴァ書房, 2013
 北大ではどこにある?
西田哲学の難しさについてはその一端を、以前この「本は脳を育てる」に『善の研究』を推薦したときに書いておいた。この『西田幾多郎』は、現在西田幾多郎研究の世界水準を牽引する著者が、単に「伝記」=時間の流れの中である人物がなしたあれこれのことを書くだけでなく、まさに西田を一つの”出来事”とし、それに西田哲学を実践してみせることによって新たな西田像を明らかにしたものである。西田の伝記はこれまでさまざまなものがあったけれども、西田自身の歴史哲学的思索によって書かれた西田には、これまでのものにはない新鮮な人間像が見られる。「哲学」という特... [続きを読む]
北大ではどこにある?
西田哲学の難しさについてはその一端を、以前この「本は脳を育てる」に『善の研究』を推薦したときに書いておいた。この『西田幾多郎』は、現在西田幾多郎研究の世界水準を牽引する著者が、単に「伝記」=時間の流れの中である人物がなしたあれこれのことを書くだけでなく、まさに西田を一つの”出来事”とし、それに西田哲学を実践してみせることによって新たな西田像を明らかにしたものである。西田の伝記はこれまでさまざまなものがあったけれども、西田自身の歴史哲学的思索によって書かれた西田には、これまでのものにはない新鮮な人間像が見られる。「哲学」という特... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
バッハを聴くために
J・S・バッハ / 礒山雅. - 講談社,
 北大ではどこにある?
私事から始めるので恐縮だが、僕の父親は、生前「バッハは何を聴いても同じに聞こえるから嫌いだ」と言っていた。まあ、ギターで「湯の町エレジー」(知らないだろうなぁ)を弾くような父親だったから、バッハにそれほど縁があったとは思えないが、幼少時の僕には結構このことばは刷り込みになってしまい、後年楽器を習うようになってからもバッハは聴くのを避けていたところがある。しかし、チェロを習うようになって「無伴奏チェロ組曲第一番」を自分で演奏してみたとき、一見単純に見える楽譜から実に調和に満ちた曲が立ち現れてくるのに驚き、いかに父親のことばがいい... [続きを読む]
北大ではどこにある?
私事から始めるので恐縮だが、僕の父親は、生前「バッハは何を聴いても同じに聞こえるから嫌いだ」と言っていた。まあ、ギターで「湯の町エレジー」(知らないだろうなぁ)を弾くような父親だったから、バッハにそれほど縁があったとは思えないが、幼少時の僕には結構このことばは刷り込みになってしまい、後年楽器を習うようになってからもバッハは聴くのを避けていたところがある。しかし、チェロを習うようになって「無伴奏チェロ組曲第一番」を自分で演奏してみたとき、一見単純に見える楽譜から実に調和に満ちた曲が立ち現れてくるのに驚き、いかに父親のことばがいい... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
読み物として面白い文章読本
思考のための文章読本 / 長沼行太郎. - 筑摩書房, 1998
 北大ではどこにある?
ここ何年か、「一般教育演習(フレッシュマンセミナー)」で日本語文章表現関係の授業を開講しており、その参考とするためにあれこれの文章読本を45冊ほど読んで、今46冊目を読んでいる。率直に言って授業の素材として役に立ったものはほとんどなく、推奨できるものは4、5冊程度である。そして、これらの推奨できる数少ない本も、どう言ってみても結局はハウツー本であり、面白さという点ではほとんど期待できない。その中にあって、長沼氏のこの本は唯一と言っていいほど読み物としての面白さがある文章読本である。この本を通して読者は、文章作成の根本にある「問い」を立てる... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ここ何年か、「一般教育演習(フレッシュマンセミナー)」で日本語文章表現関係の授業を開講しており、その参考とするためにあれこれの文章読本を45冊ほど読んで、今46冊目を読んでいる。率直に言って授業の素材として役に立ったものはほとんどなく、推奨できるものは4、5冊程度である。そして、これらの推奨できる数少ない本も、どう言ってみても結局はハウツー本であり、面白さという点ではほとんど期待できない。その中にあって、長沼氏のこの本は唯一と言っていいほど読み物としての面白さがある文章読本である。この本を通して読者は、文章作成の根本にある「問い」を立てる... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
死と美意識と
太陽と鉄 / 三島由紀夫. - 中央公論新社, 1987
 北大ではどこにある?
この作品は三島の、精神と肉体の拮抗を軸とした自己認識過程の吐露であるとともに、己の死と向き合おうとする冷徹な美意識の自己表現の書でもある。この本に書かれた思索とその基盤をなす体験の延長線上で三島はあのような「自決」という仕方を選び取ったのであり、その死は三島の、死に対する美意識の自己完結的結晶であったのだ。「国(でも何でもいいが要するに他者)のために自分の生命を投げ出して死ぬ」ということを自分の真剣な問題として考えたいなら、この本は、その内容を肯定するにせよ否定/批判するにせよ、避けて通れない作品であり、今の時代にあらためて読... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この作品は三島の、精神と肉体の拮抗を軸とした自己認識過程の吐露であるとともに、己の死と向き合おうとする冷徹な美意識の自己表現の書でもある。この本に書かれた思索とその基盤をなす体験の延長線上で三島はあのような「自決」という仕方を選び取ったのであり、その死は三島の、死に対する美意識の自己完結的結晶であったのだ。「国(でも何でもいいが要するに他者)のために自分の生命を投げ出して死ぬ」ということを自分の真剣な問題として考えたいなら、この本は、その内容を肯定するにせよ否定/批判するにせよ、避けて通れない作品であり、今の時代にあらためて読... [続きを読む] -
推薦者 : 岸 玲子 (環境健康科学研究教育センター)
広範囲な予防医学や公衆衛生学の諸領域をわかりやすく理念に基づいて記述
NEW予防医学・公衆衛生学(改訂第3版) / 岸玲子 [ほか] 編. - 南江堂, 2012
 北大ではどこにある?
予防医学・公衆衛生学の目的や理念がわかりやすい学習書です。
北大ではどこにある?
予防医学・公衆衛生学の目的や理念がわかりやすい学習書です。
人々の健康と疾病予防の重要性を歴史や社会との関係で学ぶことができます。
50人を超える専門家がそれぞれの章を書いており学問的にも高いレベルです。 -
推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)
室町幕府の対中国外交史を4本立てのドラマで!
”日本国王”と勘合貿易(NHKさかのぼり日本史・外交篇7・室町) / 橋本雄. - NHK出版, 2013
 北大ではどこにある?
歴史をさかのぼって考える(倒叙法)という、2012年11月放映のEテレ(NHK教育)歴史番組を書籍化したものです。「義政、勘合貿易の再開(1451年)」>「義満、明使との接見(1402年)」>「懐良親王への明使の捕縛(1372年)」>「天龍寺船の派遣決定(1341年)」という4本柱を立てました。自説のみならず、最新の諸研究を参考にしながら、室町期日明関係史の刷新を図っています。勘合ってどんなかたちのものだったのか? なぜ足利将軍家は中華皇帝に「朝貢」したのか? 義満ら足利将軍は心から中国に臣従したのか?――などなど、さまざまな謎解きも楽しんでもらえるはずです。
北大ではどこにある?
歴史をさかのぼって考える(倒叙法)という、2012年11月放映のEテレ(NHK教育)歴史番組を書籍化したものです。「義政、勘合貿易の再開(1451年)」>「義満、明使との接見(1402年)」>「懐良親王への明使の捕縛(1372年)」>「天龍寺船の派遣決定(1341年)」という4本柱を立てました。自説のみならず、最新の諸研究を参考にしながら、室町期日明関係史の刷新を図っています。勘合ってどんなかたちのものだったのか? なぜ足利将軍家は中華皇帝に「朝貢」したのか? 義満ら足利将軍は心から中国に臣従したのか?――などなど、さまざまな謎解きも楽しんでもらえるはずです。 -
推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)
中世後期の日本対外関係史を俯瞰
世界史のなかの戦国日本 / 村井章介. - 筑摩書房, 2012
 北大ではどこにある?
中世後期(近世初頭までを含む)の対外関係史の要点を押さえた名著です。ヨーロッパ勢力(「近代世界システム」)の東漸により世界史の舞台に本格的に躍り出た中世日本社会を、南北の境界領域(蝦夷地・琉球王国)も含めて広やかに照射する目配りの広さ! 世界史と日本史とをつなぐことが喫緊の課題である現在、まず参照されるべき書物でしょう。なお、文庫版解説は推薦子が書かせていただいています。
北大ではどこにある?
中世後期(近世初頭までを含む)の対外関係史の要点を押さえた名著です。ヨーロッパ勢力(「近代世界システム」)の東漸により世界史の舞台に本格的に躍り出た中世日本社会を、南北の境界領域(蝦夷地・琉球王国)も含めて広やかに照射する目配りの広さ! 世界史と日本史とをつなぐことが喫緊の課題である現在、まず参照されるべき書物でしょう。なお、文庫版解説は推薦子が書かせていただいています。
※図書館注:ちくま新書『海から見た戦国日本 : 列島史から世界史へ』(1997年刊)の改題増補版です。 -
推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)
中世前期の日本対外関係史を俯瞰
中世日本の内と外(増補版) / 村井章介. - 筑摩書房, 2013
 北大ではどこにある?
大学初年次向けの授業をそのまま採録。基本的な論点を押さえつつ、平安期から南北朝期頃までの様子がよく分かるように仕立てられています。すなわち、「自尊と憧憬」「人の境、国の境」「鎌倉幕府と武人政権――日本と高麗」といった視角から中世日本の国家像・対外観に肉薄し、「アジアの元寇」「中世の倭人たち」などを論ずることで、国家のもつ虚妄性を見事にあぶりだしてみせた名著です。
北大ではどこにある?
大学初年次向けの授業をそのまま採録。基本的な論点を押さえつつ、平安期から南北朝期頃までの様子がよく分かるように仕立てられています。すなわち、「自尊と憧憬」「人の境、国の境」「鎌倉幕府と武人政権――日本と高麗」といった視角から中世日本の国家像・対外観に肉薄し、「アジアの元寇」「中世の倭人たち」などを論ずることで、国家のもつ虚妄性を見事にあぶりだしてみせた名著です。 -
推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)
偽装・捏造・うそ・いつわりの歴史はすぐそこに
偽りの外交使節――室町時代の日朝関係(歴史文化ライブラリー) / 橋本雄. - 吉川弘文館, 2012
 北大ではどこにある?
世の中、詐欺や捏造が至るところで見られます。ところが、一部の心ない日本の人種主義者によって、それは大半が外国人のしわざだ、などという意見がネット上のあちこちに見られます。本当にそうでしょうか? そうした「悪さ」は今でも昔でも、日本人だろうと無かろうと、あちこちでなされてきたことです。
北大ではどこにある?
世の中、詐欺や捏造が至るところで見られます。ところが、一部の心ない日本の人種主義者によって、それは大半が外国人のしわざだ、などという意見がネット上のあちこちに見られます。本当にそうでしょうか? そうした「悪さ」は今でも昔でも、日本人だろうと無かろうと、あちこちでなされてきたことです。
本書では、対馬や博多あたりの人間が「偽使(偽造/偽装された使節)」を頻繁に渡し、朝鮮王朝に無心を繰り返していたことを、その状況や理由、背景等の諸問題に分け入りながら解明しています。通信機器手段のない前近代の外交がどんなものだったのか、皆さん、想像が... [続きを読む] -
推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)
室町時代史と対外関係史とを接合する
中華幻想――唐物と外交の室町時代史 / 橋本雄. - 勉誠出版, 2011
 北大ではどこにある?
1990年代以降、日本中世史のなかで急速に研究が進んでいる分野に、室町時代史と対外関係史とがあります。ところが2000年代まで、それらはほとんど没交渉のまま存在してきたと言ってもいいでしょう。しかしながら、それぞれの分野が孤立したままの状態では、いずれ学問全体のバランスを失いかねません。何より、隣の果実と掛け合わせることでさらに豊かな成果を得られます。そこで、唐物(舶来品)文化や外交儀礼などの諸側面を通じて両者の接続を図ったのが本書です。扱う史資料は問題の性質上、文献(文字資料)だけとは限りません。絵画、書跡、染織、五山文学……。どんな「... [続きを読む]
北大ではどこにある?
1990年代以降、日本中世史のなかで急速に研究が進んでいる分野に、室町時代史と対外関係史とがあります。ところが2000年代まで、それらはほとんど没交渉のまま存在してきたと言ってもいいでしょう。しかしながら、それぞれの分野が孤立したままの状態では、いずれ学問全体のバランスを失いかねません。何より、隣の果実と掛け合わせることでさらに豊かな成果を得られます。そこで、唐物(舶来品)文化や外交儀礼などの諸側面を通じて両者の接続を図ったのが本書です。扱う史資料は問題の性質上、文献(文字資料)だけとは限りません。絵画、書跡、染織、五山文学……。どんな「... [続きを読む] -
推薦者 : 高橋 正宏 (工学研究院)
リスク論で”福島”の現実に寄り添う
原発事故と放射線のリスク学 / 中西準子. - 日本評論社, 2014
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 森川 正章 (地球環境科学研究院)
柔軟な思考能力を鍛えるのに最適な書
なぜ、それを考えつかなかったのか? / チャールズ W マッコイ Jr(ルディー和子訳). - ダイヤモンド社, 2003
 北大ではどこにある?
本書は合理的な思考や意思の決定の仕方について例をあげながら教えてくれます。
北大ではどこにある?
本書は合理的な思考や意思の決定の仕方について例をあげながら教えてくれます。
ひとはついつい先入観にとらわれて物事をあいまいなまま判断しがちです。
私たちが陥りやすい勘違いや錯覚を指摘してくれるので、なるほどと思わせるところがたくさんあります。登録日 : 2014-04-10
-
推薦者 : 和多 和宏 (理学部 生物科学科(生物))
ヒトを含む生物の「生まれと育ち」を考える
やわらかな遺伝子 / マット・リドレー著 ; 中村桂子, 斉藤隆央訳. - 紀伊国屋書店, 2004
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
偶像破壊の果てに聞こえるものは
ベートーヴェンとべートホーフェン-神話の終わり- / 石井 宏. - 七つ森書館, 2013
 北大ではどこにある?
近年(だけの現象ではないのかもしれないが)、歴史上の人物像の見直しや新解釈の本が目白押しである(例えば、エヴァリスト・ガロアやレオナルド・ダ・ヴィンチ)。その中で、この本はベートーヴェンの名前の読み方が実は「べートホーフェン」である、というところから説き起こして、よく知られている(らしい)髪の毛を振り乱した眼光鋭い「ベートーヴェン」の肖像が実像とはずれていることに進み、あとはひたすらこれまで語られてきた「べートーヴェン」像を解体して実像を描き出そうとする。その書きぶりは、副題の「神話の終わり」どころかまさに「偶像破壊」といった勢いであ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
近年(だけの現象ではないのかもしれないが)、歴史上の人物像の見直しや新解釈の本が目白押しである(例えば、エヴァリスト・ガロアやレオナルド・ダ・ヴィンチ)。その中で、この本はベートーヴェンの名前の読み方が実は「べートホーフェン」である、というところから説き起こして、よく知られている(らしい)髪の毛を振り乱した眼光鋭い「ベートーヴェン」の肖像が実像とはずれていることに進み、あとはひたすらこれまで語られてきた「べートーヴェン」像を解体して実像を描き出そうとする。その書きぶりは、副題の「神話の終わり」どころかまさに「偶像破壊」といった勢いであ... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
日本と日本人を見る目の背後にあるもの
日本人論・日本論の系譜 / 石澤靖治. - 丸善, 1997
 北大ではどこにある?
この本は、ルース・ベネディクトの『菊と刀』以後の代表的な日本人論・日本論を取り上げてそれらを関連づけて論じることを通して日本と日本人に対する内外の見方がどのように関連し合ってどう変化してきたかのわかりやすい見取り図を描き出すものである。
北大ではどこにある?
この本は、ルース・ベネディクトの『菊と刀』以後の代表的な日本人論・日本論を取り上げてそれらを関連づけて論じることを通して日本と日本人に対する内外の見方がどのように関連し合ってどう変化してきたかのわかりやすい見取り図を描き出すものである。
この本の眼目は、所謂広義の「日本(文化)論」と言われるものを「日本論」と「日本人論」に分けてそれぞれが登場してくる歴史的・政治的文脈を明らかにしている点である。これを読むと、結局のところ、“代表的な”(と言われている)「日本人論」や「日本論」は、実は-カレル・ヴァン・ウォルフレンを除くと-基本的にア... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
思索するカントの姿に迫る
理性の不安-カント哲学の生成と構造- / 坂部 恵. - 勁草書房, 2001
 北大ではどこにある?
この推薦文を書いている今日の昼間、書店に行ったら故石川文康先生訳『純粋理性批判(上下)』(筑摩書房)が棚に並んでいるのを見てびっくりした。石川先生は昨年逝去されたし、『純粋理性批判』を翻訳していらっしゃったことも知らなかった。同時に、どうしてこうも日本の哲学研究者(あるいは出版社?)は『純粋理性批判』の翻訳を出したがるのかなぁ、とも思ってしまった。この「本は脳を育てる」に文学研究科の千葉先生が熊野純彦先生の翻訳を推薦していらっしゃるが、それ以外にも多くの翻訳があり、訳書の多さという点では哲学書に限定せずとも『純粋理性批判』、ハイデガー... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この推薦文を書いている今日の昼間、書店に行ったら故石川文康先生訳『純粋理性批判(上下)』(筑摩書房)が棚に並んでいるのを見てびっくりした。石川先生は昨年逝去されたし、『純粋理性批判』を翻訳していらっしゃったことも知らなかった。同時に、どうしてこうも日本の哲学研究者(あるいは出版社?)は『純粋理性批判』の翻訳を出したがるのかなぁ、とも思ってしまった。この「本は脳を育てる」に文学研究科の千葉先生が熊野純彦先生の翻訳を推薦していらっしゃるが、それ以外にも多くの翻訳があり、訳書の多さという点では哲学書に限定せずとも『純粋理性批判』、ハイデガー... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
東ユーラシア世界に目を開く
「シベリアに独立を!」-諸民族の祖国(パトリ)をとりもどす- / 田中 克彦. - 岩波書店, 2013
 北大ではどこにある?
推薦者の義父は戦後シベリアで抑留生活を送った。そのことについて推薦者には何も語らずに亡くなったが、そこでの苦労は並大抵のことばで語れるものではなかったようである。シベリア、と聞けば推薦者も含めてかなりの日本人は戦後のシベリア抑留のことを、あるいはまた天然ガスパイプラインを、さらには水野晴郎の映画『シベリア超特急』を思い浮かべるかと思うが、この本で描かれるのは、そうしたイメージとは異なる自然豊かなシベリアで独立運動を戦い抜いたポターニンという人物の生涯である。そのまわりには、ドストエフスキーやバクーニンをはじめ、アイヌ語研究で有... [続きを読む]
北大ではどこにある?
推薦者の義父は戦後シベリアで抑留生活を送った。そのことについて推薦者には何も語らずに亡くなったが、そこでの苦労は並大抵のことばで語れるものではなかったようである。シベリア、と聞けば推薦者も含めてかなりの日本人は戦後のシベリア抑留のことを、あるいはまた天然ガスパイプラインを、さらには水野晴郎の映画『シベリア超特急』を思い浮かべるかと思うが、この本で描かれるのは、そうしたイメージとは異なる自然豊かなシベリアで独立運動を戦い抜いたポターニンという人物の生涯である。そのまわりには、ドストエフスキーやバクーニンをはじめ、アイヌ語研究で有... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
ワールドカップの原点はここだ!
フットボールの原点-サッカー、ラグビーのおもしろさの根源を探る- / 吉田 文久. - 創文企画, 2014
 北大ではどこにある?
サッカー(フットボール)の起源は諸説あるようで、スポーツにほとんど関心がない推薦者でもイギリス起源かイタリア起源か、くらいのことは知っている。この本は、イギリスの民俗フットボールにその起源を求め、今なお残るそのゲームの現場にいくたびも足を運んで取材とインタビューを重ねた筆者の労作である。ただのスポーツ蘊蓄本と思うなかれ、この本では「民俗フットボール」からサッカーへの変化の歴史が史料に基づいて丹念に追跡され、同時にそのような変化を促したイギリス社会の歴史についても理解を深めることができるものとなっている。サッカーやスポーツだけで... [続きを読む]
北大ではどこにある?
サッカー(フットボール)の起源は諸説あるようで、スポーツにほとんど関心がない推薦者でもイギリス起源かイタリア起源か、くらいのことは知っている。この本は、イギリスの民俗フットボールにその起源を求め、今なお残るそのゲームの現場にいくたびも足を運んで取材とインタビューを重ねた筆者の労作である。ただのスポーツ蘊蓄本と思うなかれ、この本では「民俗フットボール」からサッカーへの変化の歴史が史料に基づいて丹念に追跡され、同時にそのような変化を促したイギリス社会の歴史についても理解を深めることができるものとなっている。サッカーやスポーツだけで... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
もう一つの「本は脳を育てる」
古典力 / 斎藤 孝. - 岩波書店, 2012
 北大ではどこにある?
以前森鴎外の『舞姫』を推薦した時に、「古典」を読むということについて少しだけ書いたことがある。では「古典」とは何か、と言うことになると答えはそれほど簡単ではない。そのわかりやすい見取り図の一つがこの『古典力』である。これを読むと、読んだことがある本に再会したり、名前は知っていても(案外それで分かった気になって)読んでいない本に出遭ったりするだろう。そこで興味が湧いた本があればためらうことなく手にとって欲しい。なぜそれが「古典」になっているかは、斉藤氏の解説を手がかりに読めば自分なりの理解を獲得することができると思う。
北大ではどこにある?
以前森鴎外の『舞姫』を推薦した時に、「古典」を読むということについて少しだけ書いたことがある。では「古典」とは何か、と言うことになると答えはそれほど簡単ではない。そのわかりやすい見取り図の一つがこの『古典力』である。これを読むと、読んだことがある本に再会したり、名前は知っていても(案外それで分かった気になって)読んでいない本に出遭ったりするだろう。そこで興味が湧いた本があればためらうことなく手にとって欲しい。なぜそれが「古典」になっているかは、斉藤氏の解説を手がかりに読めば自分なりの理解を獲得することができると思う。
ちなみに、... [続きを読む] -
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
Japan’s Best
Living for Jesus and Japan : the social and theological thought of Uchimura Kanzō / edited by Shibuya Hiroshi and Chiba Shin. - Eerdmans Pub., 2013
 北大ではどこにある?
本書は皆さんの大先輩札幌農学校二期生内村鑑三の研究書です。
北大ではどこにある?
本書は皆さんの大先輩札幌農学校二期生内村鑑三の研究書です。
新しい日本の黎明期、明治、大正そして昭和初期を力一杯駆け抜けたこの人物は思想家として信念を貫いた魅力ある人物です。外国人にも魅力的に見え、彼の諸著作は数カ国語に翻訳され、外国人による研究書は私の知る限りでも10冊を超えています。
本書は主に日本の内村研究者たちにより、彼の平和思想、愛国心そして神学思想を中心に人文学、自然科学に通じたジェネラリスト、社会思想家そして信仰者にしてキリスト教独立伝道者としての内村の諸側面を明らかにすることをめざし編集された英語論文集です。この... [続きを読む] -
推薦者 : 戸田 聡 (文学研究科)
イエス・キリストってどんな人だったの?
イエスの影を追って / ゲルト・タイセン. - ヨルダン社, 1989
 北大ではどこにある?
聖書やキリスト教の中心的テーマはやはり何と言ってもイエス・キリストであり、そのイエスがどういう人物だったのかという問いは、そういう研究の根底にある問題だと言えます。学問的にイエスの生涯を論じた書物は他にも数多くあり、その意味では別の本も薦められますが(例えばE・P・サンダース『イエス』)、読み物としてはタイセンのこの本がお薦めです。
北大ではどこにある?
聖書やキリスト教の中心的テーマはやはり何と言ってもイエス・キリストであり、そのイエスがどういう人物だったのかという問いは、そういう研究の根底にある問題だと言えます。学問的にイエスの生涯を論じた書物は他にも数多くあり、その意味では別の本も薦められますが(例えばE・P・サンダース『イエス』)、読み物としてはタイセンのこの本がお薦めです。
実は、イエスの生涯を物語風に書いた本も既に数多く世に出ており(例えばモーリヤック、遠藤周作、三浦綾子)、それらもそれぞれに一読の価値がありますが、このタイセンという著者は、もともと新約聖書を専門的に研... [続きを読む] -
推薦者 : 高橋 是太郎 (水産科学研究院)
北海道で親しまれる森となった北越のブナ
評伝関矢孫左衛門 / 石村義典. - 関谷信一郎, 2012
 北大ではどこにある?
本書の「関矢孫佐衛門」という人物は、1844年生まれ、北越戊辰の役、西南戦争に参加、そのあと北越の農民を率いて、野幌に入植しました。彼が持参した北越のブナの種子は、永遠の森林サイクルの中で薪炭用林として、野幌の森となって遺っています。
北大ではどこにある?
本書の「関矢孫佐衛門」という人物は、1844年生まれ、北越戊辰の役、西南戦争に参加、そのあと北越の農民を率いて、野幌に入植しました。彼が持参した北越のブナの種子は、永遠の森林サイクルの中で薪炭用林として、野幌の森となって遺っています。
今、ブナは大木となり、森は野幌原始林と呼ばれ、道民に親しまれております水産学部1、2年生のみならず、学部の枠を超えて、北海道に住む者が本書を目にすることは、学生達に北海道を強く印象付けて、心を豊かにするものと考え、本書を推薦致します。 -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
The insanely funny author is back!
Insane City / Dave Barry. - Putnam Adult, 2013
 北大ではどこにある?
Dave Barry is a Pulitzer-winning comical journalist -- or was -- in Miami, Florida. He hadn't written for some time. But he's back in 'Insane City'. Get some laughs and insights on American society.
北大ではどこにある?
Dave Barry is a Pulitzer-winning comical journalist -- or was -- in Miami, Florida. He hadn't written for some time. But he's back in 'Insane City'. Get some laughs and insights on American society.
Also read 'Dave Barry Does Japan' -- a hilarious and warm-hearted account of Dave, Beth, and Robby traveling for 3 weeks in Japan when Toshiki Kaifu was prime minister. The times have changed and hopefully the Japanese youth are better at rock'n roll and the entire population has lightened up. Or not. Either way, it's a great way to look at yourselves.
-
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
Mirror, mirror, on the wall
Dave Barry Does Japan / Dave Barry. - Ballantine Books, 1993
 北大ではどこにある?
Dave Barry is a Pulitzer-winning comical journalist in Miami, Florida. In the early 1990s when Dave was working for the 'Miami Herald', Random House (a major publisher) sponsored Dave and his family for a 3-week trip through Japan.
北大ではどこにある?
Dave Barry is a Pulitzer-winning comical journalist in Miami, Florida. In the early 1990s when Dave was working for the 'Miami Herald', Random House (a major publisher) sponsored Dave and his family for a 3-week trip through Japan.
The result: 'Dave Barry Does Japan' -- a hilarious and warm-hearted account of Dave, Beth, and Robby mesmerized, confused, horrified, and upset in Japan when Toshiki Kaifu was prime minister. The times have changed, the elevator girls are gone, and hopefully the Japanese youth are better at rock'n roll and the entire population has lightened up. Or not. Either way, it's a great way to look at yourselves.
By the way, I received this book as a present when I left the USA to study at graduate school in Japan. My colleagues thought the book would prepare me f... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
道を極むる者を極道といふ
シャングリ・ラの夢 原信太郎が描き続ける理想郷 (DVD) / 原信太郎 (出演), 久地浦恭寛 (監督). - TCエンタテインメント, 2012
 北大ではどこにある?
Noburato Hara was born in a wealthy family and spent a fortune on trains. He photographed them, made home movies about them, rode them, and occasionally drove them. His biggest accomplishment was his model train collection that he built from scratch. Check out his own private model railway company -- the Shangri La -- on his DVD.
北大ではどこにある?
Noburato Hara was born in a wealthy family and spent a fortune on trains. He photographed them, made home movies about them, rode them, and occasionally drove them. His biggest accomplishment was his model train collection that he built from scratch. Check out his own private model railway company -- the Shangri La -- on his DVD.
Visit his museum at:
http://www.hara-mrm.com/ -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
異文化の底辺で詩人は何を見たか
ねむれ巴里 / 金子光晴. - 中央公論新社, 2005
 北大ではどこにある?
詩人・金子光晴は、昭和初期に妻とともにパリに渡って住み着く。この本は、そのパリ生活の記録であるが、金の工面に困った金子はそれこそ何でもありの阿漕な金稼ぎをして糊口をしのぎ、社会の底辺を這い回るようにして生き抜いていく。同時に、パリという異文化の中で、同じように底辺にうごめく日本人や異国人、そしてフランス人たちの生活を驚くほど鋭い観察眼で活写していく。ここに描かれるパリ(フランス)の姿は、「芸術の都」として近代の日本人エリートが憧れた世界とはほど遠く、様々な葛藤を抱えて死んでいく人間の描写も多い。こうしたことは、昭和初期のパリ特有の... [続きを読む]
北大ではどこにある?
詩人・金子光晴は、昭和初期に妻とともにパリに渡って住み着く。この本は、そのパリ生活の記録であるが、金の工面に困った金子はそれこそ何でもありの阿漕な金稼ぎをして糊口をしのぎ、社会の底辺を這い回るようにして生き抜いていく。同時に、パリという異文化の中で、同じように底辺にうごめく日本人や異国人、そしてフランス人たちの生活を驚くほど鋭い観察眼で活写していく。ここに描かれるパリ(フランス)の姿は、「芸術の都」として近代の日本人エリートが憧れた世界とはほど遠く、様々な葛藤を抱えて死んでいく人間の描写も多い。こうしたことは、昭和初期のパリ特有の... [続きを読む] -
推薦者 : 山崎 健一 (地球環境科学研究院)
遺伝子デザイナーを目指す君に
遺伝子デザイン学入門I / 山崎健一、伊藤健史. - 北海道大学出版会, 2012
 北大ではどこにある?
著者は2010年,北大の学部生チームを編成し,iGEM(生物ロボットコンテスト)2010(於:米国マサチューセッツ工科大学)への参加に挑戦し始めました。この国際大会への各国からの参加チームが標準として用いている遺伝子作製技術が,工学原理に基づいて構築されており,これに用いる遺伝子部品が質的にも量的にもすぐれていることに気付いた著者は,北大理系の新入生を対象として開講されている一般教育演習(フレッシュマンセミナー)の一メニューとして「遺伝子デザイン学入門」を開講し,そのテキストとしてこの本を使用しています。
北大ではどこにある?
著者は2010年,北大の学部生チームを編成し,iGEM(生物ロボットコンテスト)2010(於:米国マサチューセッツ工科大学)への参加に挑戦し始めました。この国際大会への各国からの参加チームが標準として用いている遺伝子作製技術が,工学原理に基づいて構築されており,これに用いる遺伝子部品が質的にも量的にもすぐれていることに気付いた著者は,北大理系の新入生を対象として開講されている一般教育演習(フレッシュマンセミナー)の一メニューとして「遺伝子デザイン学入門」を開講し,そのテキストとしてこの本を使用しています。
本書は高校で生物学をちゃんと勉強した学生なら理... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
日本陸軍の戦争理念に迫る
未完のファシズム-「持たざる国」日本の運命- / 片山杜秀. - 新潮社, 2012
 北大ではどこにある?
アジア・太平洋戦争についてある程度勉強してきた時、頭に浮かんだ疑問というのが、「なぜ日本軍は兵員を無駄死にさせるような戦闘行動や作戦を行ったのか」ということだった。戦争-特に近代戦-にあっては、いかに戦闘手段の損失を少なくしつつ有利に戦況を進めるかということが目標になる。にもかかわらず、日本軍は、例えば「バンザイ突撃」等に見られるような「玉砕」戦を実行し、それらに対して日本軍の狂気じみた精神主義、あるいはまた「戦陣訓」の影響といったことが原因として指摘されてきた。
北大ではどこにある?
アジア・太平洋戦争についてある程度勉強してきた時、頭に浮かんだ疑問というのが、「なぜ日本軍は兵員を無駄死にさせるような戦闘行動や作戦を行ったのか」ということだった。戦争-特に近代戦-にあっては、いかに戦闘手段の損失を少なくしつつ有利に戦況を進めるかということが目標になる。にもかかわらず、日本軍は、例えば「バンザイ突撃」等に見られるような「玉砕」戦を実行し、それらに対して日本軍の狂気じみた精神主義、あるいはまた「戦陣訓」の影響といったことが原因として指摘されてきた。
この本は、第一次世界大戦以降の日本陸軍内部の戦争指導理念の変容を... [続きを読む] -
推薦者 : 佐藤 淳二 (文学研究科)
ロマン主義の怒濤をいかにして21世紀のうちに始末できるのか?
Oeuvres complètes de Victor Hugo / Victor Hugo. - Robert Laffont,
 北大ではどこにある?
(Théâtre 1&2, Romans 1,2,3, Politique, Critique, Histoire , Voyages, Poésie 1,2,3, Océan, Chantiers, Correspondance familiale et écrits intimes 1&2 計15冊)
北大ではどこにある?
(Théâtre 1&2, Romans 1,2,3, Politique, Critique, Histoire , Voyages, Poésie 1,2,3, Océan, Chantiers, Correspondance familiale et écrits intimes 1&2 計15冊)
フランスの19世紀の国民詩人と言えばユゴーだ。幅広い人気をいまだに保ち、フランス文化の土台の一つになっている。「ブカン」叢書の15冊は、現代人に接近しやすく、古い大全集のいかめしさに比べるとぐっと身近だろう。といってもフランス語だから、日本では読者も限られている。しかし、敢えて推薦したい。フランス語をいくらかでもやったら、これほどまでに激しい才能の迸り、ほとんど怒濤とも咆哮ともいえる天才の活躍にすこしでも触れたいものである、... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「英学」のもう一つの姿
日本における近代倫理の屈折 / 堀孝彦. - 未来社, 2002
 北大ではどこにある?
さきにこの「本は脳を育てる」に、惣郷正明『日本英学のあけぼの』を推薦した。今度の『日本における近代倫理の屈折』は、惣郷の本にも登場する幕末の英語通詞・堀達之助の子孫である堀孝彦氏が、達之助の営為を通じて「英学」を語学としてのみではなく「人文学」と捉え、その内実が急激な近代化を急ぐ日本の中でいかなる変化を余儀なくされたか-著者のことばで言えば「屈折」を経たか-を明らかにし、現代にまで繋がるその「屈折」の影響を読み取ろうとしたものである。その「屈折」の延長線上には、明治期から現代までの日本の倫理道徳上の様々な問題が関連してくること... [続きを読む]
北大ではどこにある?
さきにこの「本は脳を育てる」に、惣郷正明『日本英学のあけぼの』を推薦した。今度の『日本における近代倫理の屈折』は、惣郷の本にも登場する幕末の英語通詞・堀達之助の子孫である堀孝彦氏が、達之助の営為を通じて「英学」を語学としてのみではなく「人文学」と捉え、その内実が急激な近代化を急ぐ日本の中でいかなる変化を余儀なくされたか-著者のことばで言えば「屈折」を経たか-を明らかにし、現代にまで繋がるその「屈折」の影響を読み取ろうとしたものである。その「屈折」の延長線上には、明治期から現代までの日本の倫理道徳上の様々な問題が関連してくること... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
論理学の深さを知る
現代論理学入門 / 沢田 允茂. - 岩波書店, 1962
 北大ではどこにある?
今から50年前に出たこの本は、いまなお論理学の名著としての価値を失っていない。もちろん50年の間には論理学にも進歩があって、多値論理、様相論理、量子論理などはこの本では取り扱われていないし、用語や記号の表記も古いところがあるが、それは仕方ないこととしても、論理学を専門的に研究するならともかく、それ以外の幅広い哲学的関心に広く答え得る点でこの本をしのぐ内容のものはいまだにほとんどないと言って良い。こうした優れた本を絶版にしないで出し続けている岩波書店の“営業努力”は賞讃されてしかるべきである。
北大ではどこにある?
今から50年前に出たこの本は、いまなお論理学の名著としての価値を失っていない。もちろん50年の間には論理学にも進歩があって、多値論理、様相論理、量子論理などはこの本では取り扱われていないし、用語や記号の表記も古いところがあるが、それは仕方ないこととしても、論理学を専門的に研究するならともかく、それ以外の幅広い哲学的関心に広く答え得る点でこの本をしのぐ内容のものはいまだにほとんどないと言って良い。こうした優れた本を絶版にしないで出し続けている岩波書店の“営業努力”は賞讃されてしかるべきである。
この本を紹介する際に、記号の使用を最小限... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
日本文化に絡まる「思いこみ」を引き剥がす
希望の倫理学-日本文化と暴力をめぐって- / 持田季未子. - 平凡社, 1998
 北大ではどこにある?
「日本文化」は、実は様々な「思いこみ」や、近代に於ける「意味づけ」に絡め取られている。俗耳に入ってくるものの一つとして例えば「日本人は古来から自然を愛する」が挙げられよう。この本は、中世謡曲から始まって近代の帝国主義的イデオロギーまでを分析し、「日本文化」に絡みついている思いこみ、俗説、恣意的な意味付与を引き剥がそうとする試みである。その中から見えてくる「日本文化(と言われるもの)」の根底にはどうしようもない暴力的、閉塞的な性格が顕れてくる。それは単なる“ステレオタイプ”などと言ってすませられるレベルではない、重い倫理的課題を我々... [続きを読む]
北大ではどこにある?
「日本文化」は、実は様々な「思いこみ」や、近代に於ける「意味づけ」に絡め取られている。俗耳に入ってくるものの一つとして例えば「日本人は古来から自然を愛する」が挙げられよう。この本は、中世謡曲から始まって近代の帝国主義的イデオロギーまでを分析し、「日本文化」に絡みついている思いこみ、俗説、恣意的な意味付与を引き剥がそうとする試みである。その中から見えてくる「日本文化(と言われるもの)」の根底にはどうしようもない暴力的、閉塞的な性格が顕れてくる。それは単なる“ステレオタイプ”などと言ってすませられるレベルではない、重い倫理的課題を我々... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
東大入試問題から見える「倫理」
東大入試 至高の国語「第二問」 / 竹内康浩. - 朝日新聞出版, 2008
 北大ではどこにある?
過去のある時期、東京大学の入学試験(二次試験)の現代国語の第二問は、200字以内で作文を書かせるという問題だった。この本は、その「第二問」を分析して東大が年度に関わりなく執拗に問おうとしたものを明らかにしていくという著作である。著者の竹内氏によれば、「底流には『死』という大問題があって、死を見ることで『生きること』について考えさせる」(「あとがき」より)というのがこの問題の勘所となっている。これだけ読むと、入試問題から人生訓を牽強付会しているような印象を与えてしまうかもしれないが、この本の真骨頂は、後半に進むに従って「死(と生)」の問題... [続きを読む]
北大ではどこにある?
過去のある時期、東京大学の入学試験(二次試験)の現代国語の第二問は、200字以内で作文を書かせるという問題だった。この本は、その「第二問」を分析して東大が年度に関わりなく執拗に問おうとしたものを明らかにしていくという著作である。著者の竹内氏によれば、「底流には『死』という大問題があって、死を見ることで『生きること』について考えさせる」(「あとがき」より)というのがこの問題の勘所となっている。これだけ読むと、入試問題から人生訓を牽強付会しているような印象を与えてしまうかもしれないが、この本の真骨頂は、後半に進むに従って「死(と生)」の問題... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
インチキを見抜く考え方を学ぶ
日本文化論のインチキ / 小谷野敦. - 幻冬舎, 2010
 北大ではどこにある?
日本文化論というグループに括られる書物はものすごく(と言っていいほど)多くのものが出版されていて、他方、それらに対する批判の書も少なからず出されている。大学で日本文化を専門として学び研究する人間にとってそうした批判に目を通しておくのは当然だが、小谷野氏は、「日本文化論批判は行われているものの、批判のほうはいっこうに広まらないのである」と嘆いており、それがこの本を書いた動機の一部となっている。
北大ではどこにある?
日本文化論というグループに括られる書物はものすごく(と言っていいほど)多くのものが出版されていて、他方、それらに対する批判の書も少なからず出されている。大学で日本文化を専門として学び研究する人間にとってそうした批判に目を通しておくのは当然だが、小谷野氏は、「日本文化論批判は行われているものの、批判のほうはいっこうに広まらないのである」と嘆いており、それがこの本を書いた動機の一部となっている。
内容は、土居健郎『「甘え」の構造』やベネディクト『菊と刀』以来の日本文化論をめぐる研究状況に対するやや毒舌めいた批判であるが、新書版という-... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
英語と格闘した日本人の足跡を辿る
日本英学のあけぼの-幕末・明治の英語学- / 惣郷正明. - 創拓社, 1990
 北大ではどこにある?
20年以上まえに出たこの本を今頃推薦するのは実は大変恥ずかしい。というのは、出版されてから割合すぐに買い求めたのだけれど、最近まで“本棚の肥やし”にしてあって読んでいなかったからである。(言い訳すれば、昔、僕の恩師も「20年前に買った本がまだ読めないんだ」とぼやいていたので、同じようなことは案外あるのかもしれない。)
北大ではどこにある?
20年以上まえに出たこの本を今頃推薦するのは実は大変恥ずかしい。というのは、出版されてから割合すぐに買い求めたのだけれど、最近まで“本棚の肥やし”にしてあって読んでいなかったからである。(言い訳すれば、昔、僕の恩師も「20年前に買った本がまだ読めないんだ」とぼやいていたので、同じようなことは案外あるのかもしれない。)
「英学」という表題はいかめしいが、要するに日本人が英語と接して以来、どのようにこの言語を勉強しようと工夫なり悪戦苦闘なりを重ねてきたかの歴史が描かれているものであり、具体的な教科書や参考書や辞書、果てはかなり怪しげな学... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
to tie a knot literally
The Ashley Book of Knots / Clifford Ashley. - Doubleday, 1944
 北大ではどこにある?
Sometimes a person collects, organizes, and delivers information in such a way that the exhaustive knowledge is clearly explained along with its background culture and history. The Ashley Book of Knots (or ABOK for short) is such a treatise. It is rare that a book as old as my parents continues to reign as the standard reference. We academics should learn humility from a work of this scope.
北大ではどこにある?
Sometimes a person collects, organizes, and delivers information in such a way that the exhaustive knowledge is clearly explained along with its background culture and history. The Ashley Book of Knots (or ABOK for short) is such a treatise. It is rare that a book as old as my parents continues to reign as the standard reference. We academics should learn humility from a work of this scope.
For more information about ABOK, visit Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Ashley_Book_of_Knots
View parts of this book including its wonderful drawings at Google Books:
http://books.google.com/
-
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
最後まで読めるカントの『純理』
純粋理性批判(熊野純彦訳) / カント. - 作品社, 2012
 北大ではどこにある?
この名著については邦語においても数種類の翻訳を容易に手にすることができます。今年出版されたあたらしい熊野純彦氏による訳業は、従来の成果を取り入れつつ、従来のゴツゴツした訳業とは異なり、あまり負荷をかけられることなしに「分かる」という感覚の中で読み進めることができます。学問に憧れをもつ多くの人々が大学生になったことを期にこの難解の誉れ高い書を手にして挑戦してきました。私もそのひとりでしたが、その当時最後まで読み進めることはできませんでした。今の若者は幸いな翻訳にであえたと言うことができます。カントはこの書で理性が理性自身を吟味し... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この名著については邦語においても数種類の翻訳を容易に手にすることができます。今年出版されたあたらしい熊野純彦氏による訳業は、従来の成果を取り入れつつ、従来のゴツゴツした訳業とは異なり、あまり負荷をかけられることなしに「分かる」という感覚の中で読み進めることができます。学問に憧れをもつ多くの人々が大学生になったことを期にこの難解の誉れ高い書を手にして挑戦してきました。私もそのひとりでしたが、その当時最後まで読み進めることはできませんでした。今の若者は幸いな翻訳にであえたと言うことができます。カントはこの書で理性が理性自身を吟味し... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
A backstage tour of Maus
Metamaus / Art Spiegelman. - Pantheon Books: New York, 2011
 北大ではどこにある?
So you've read Maus. (No? Then what are you waiting for? Read it now. It's been translated into many languages.) Metamaus (a book about Maus) takes us on a backstage tour of the making of Maus and the Spiegelman family.
北大ではどこにある?
So you've read Maus. (No? Then what are you waiting for? Read it now. It's been translated into many languages.) Metamaus (a book about Maus) takes us on a backstage tour of the making of Maus and the Spiegelman family.
Maus should be easy reading for Japanese readers because manga is a popular medium for entertainment and learning. Art Spiegelman met considerable criticism for depicting his relationship with his father, religion, and race when he chose to draw comics. The word comic to me is synonymous with manga but some occidental readers were insulted by the 'comic' aspect of comics -- in fact one critic suggested the word 'tragics' be used. And if I found this bizarre, then Art Spiegelman found one Japanese version of Ann Frank's diary equally bizarre -- Ann was telling her story ... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
short talks about language and linguistics
The 5 Minute Linguist: Bite-Sized Essays on Language and Languages, 2nd edition / E. M. Rickerson (Author, Editor), Barry Hilton (Editor). - Equinox Publishing, 2012
 北大ではどこにある?
Did you know that 75 percent of the world's population speaks more than 1 language?
北大ではどこにある?
Did you know that 75 percent of the world's population speaks more than 1 language?
'The 5-minute linguist' explains various topics on language and linguistics.
Learn, for example, what it means to be bilingual (that is, speaking 2 languages), or how many languages we can learn.
The series started as an audio program developed in 2005 by the College of Charleston and the National Museum of Language. The book is based on that radio program.
Download the audio files for free from iTunes U (http://itunes.apple.com/us/itunes-u/the-five-minute-linguist/id452255394 -- accessed 2012-07-20). -
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
あらゆる学問の基礎
The Oxford Handbook of Aristotle / ed.Christopher Shields. - Oxford University Press, 2012
 北大ではどこにある?
本書においては、その後の人類の知的な営みにおける思考の規範となりあらゆる学問の基礎となったアリストテレスの哲学についてそれぞれの領域の第一人者24人(26章)の執筆者により包括的な研究および紹介がなされています。推薦者が今思いますのは人間の正しい思考方法がアリストテレスにより明晰に提示されたからこそ、ひとはいかなる領域においてであれ思考を進めるためにはアリストテレス的に思考せざるをえないということです。彼は「美しく問い(行き詰まり・アポリア)をたてること」が、その解に導くと言います。そして人類にとって、そのような方法は他にない... [続きを読む]
北大ではどこにある?
本書においては、その後の人類の知的な営みにおける思考の規範となりあらゆる学問の基礎となったアリストテレスの哲学についてそれぞれの領域の第一人者24人(26章)の執筆者により包括的な研究および紹介がなされています。推薦者が今思いますのは人間の正しい思考方法がアリストテレスにより明晰に提示されたからこそ、ひとはいかなる領域においてであれ思考を進めるためにはアリストテレス的に思考せざるをえないということです。彼は「美しく問い(行き詰まり・アポリア)をたてること」が、その解に導くと言います。そして人類にとって、そのような方法は他にない... [続きを読む]