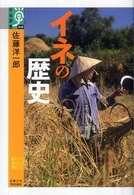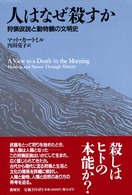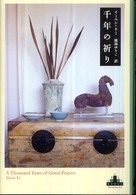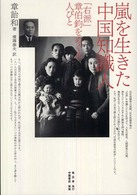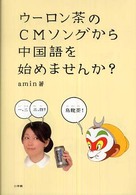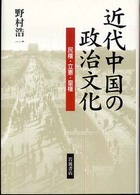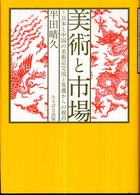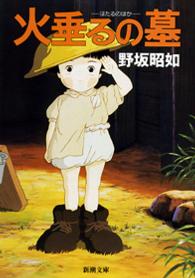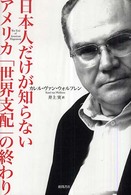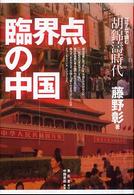-
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
Every walk of life has its experts
電車の運転―運転士が語る鉄道のしくみ / 宇田 賢吉. - 中央公論新社, 2008
 北大ではどこにある?
Kenkichi Uda, the author, is a former train engineer with over 40 years of experience with JR West Japan (formerly Japan National Railways).
北大ではどこにある?
Kenkichi Uda, the author, is a former train engineer with over 40 years of experience with JR West Japan (formerly Japan National Railways).
What impresses me is not just Uda's considerable experience, but his crisp, succinct, to-the-point writing style.
Obviously Uda is a proactive learner, a dedicated professional, and most likely, an effective instructor.
Read this book to learn two things:
(a) Every walk of life has its experts.
Never underestimate people just because they hold blue collar jobs.
Any person can be eloquent and intelligent.
(A corollary of my claim is that every walk of life --
even those professing to deal in knowledge -- includes mediocrity.
Could be me. Or you.)
(b) Skills make the worker, but ethics make the person.
Both are needed to ... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
Pulitzer-winning definitive text on ants
The Ants / Bert Holldobler and Edward O. Wilson. - Belknap Press of Harvard University Press, 1990
 北大ではどこにある?
Fascinating book. Chock-full of information on the fascinating micro-cosmos of ants.
北大ではどこにある?
Fascinating book. Chock-full of information on the fascinating micro-cosmos of ants.
Equally fascinating is the authors' devotion to their subject.
This is a large book -- what some would call a coffee table book -- but do not be misled by its size and abundance of photographs.
This is a serious, comprehensible treatise on ants.
Those of you aspiring careers in research -- and I hope that includes most of you, because academic research is a small subset of research -- aim for this level of depth and coverage.
No wonder the authors won a Pulitzer!
Don't miss their more accessible semi-sequel, "The superorganism". -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
Great sequel to Pulitzer-winning definitive text on ants
The Superorganism : The Beauty, Elegance, and Strangeness of Insect Societies / Bert Holldobler , E. o. Wilson. - W W Norton, 2008
 北大ではどこにある?
I was hoping for a more accessible semi-sequel to the authors' Pulitzer-winning text, "The ants", and here it is.
北大ではどこにある?
I was hoping for a more accessible semi-sequel to the authors' Pulitzer-winning text, "The ants", and here it is.
While "The ants" is an encyclopedic treatise of ants, "The superorganism" deals with social insects including ants and bees.
What do humans and insect communities have in common?
Do you see analogues of evolutions among human societies?
Or are insect societies more optimized than ours? -
推薦者 : 筑和 正格 (メディア・コミュニケーション研究院)
歴史の決定的転換点を追体験する!
世界に衝撃を与えた日 全30巻 (DVD) / BBC Active. - キュービカル・エンタテインメント (発売), 2006
 北大ではどこにある?
貴重な映像資料が閲覧できるようになった。
北大ではどこにある?
貴重な映像資料が閲覧できるようになった。
イギリスBBC作成の30巻に及ぶドキュメンタリー映像は、私たちに歴史の決定的転換点を追体験させてくれる。
「世界に衝撃を与える事件」は、歴史が、また時代・社会が内包する矛盾が、何らかの形で顕在化したものだと捉えることができる。
したがって、私たちは、映像がもつ迫力をまず受け止めながら、その矛盾と矛盾を通じて伝えられる時代像・社会像について考えるという喜びを経験できるのである。
学生諸君には、是非一度閲覧していただきたいものである。 -
推薦者 : 川村 周三 (農学研究科)
イネはどこから来た?そしてどこへ行く?
イネの歴史 / 佐藤洋一郎. - 京都大学学術出版会, 2008
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 川村 周三 (農学研究科)
なぜ日本人はモチを食べるのか?
照葉樹林文化とは何か 東アジアの森が生み出した文明 / 佐々木高明. - 中公新書, 2007
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 川村 周三 (農学研究科)
従来からの稲作の起源に異論を唱える
稲作の起源 イネ学から考古学への挑戦 / 池橋宏. - 講談社, 2005
 北大ではどこにある?
従来からの稲作起源の定説に異論を唱え,波紋を投げかける。
北大ではどこにある?
従来からの稲作起源の定説に異論を唱え,波紋を投げかける。
稲作の起源は照葉樹林農耕の焼畑ではなく,根菜農耕の株分けであると提唱する。
推薦者もこの説を興味深く感じるが,この説に対する考古学や植物遺伝学の専門家からの批判も大きい。 -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
フランス人画家が描く日本古代神話の色彩曼陀羅の世界
日本神話 / マークエステル. - Xiang-Hap社(香港), 2006
 北大ではどこにある?
このずっしりと重い大判の画集を開いてゆくと、驚きを禁じえない。日本の原点とされてきた『古事記』の世界が、われわれが何となく思い描いていたものとはまるで違う壮大な色彩宇宙として展開してゆくのだ。古事記の物語世界に肉迫してゆくそのイメージ力の雄渾さ。創世神話を彩って華麗に舞い上がるその色彩のド迫力。これまで誰がこのような途轍もないスペクトルでわれわれの神話世界を表現してきただろうか。
北大ではどこにある?
このずっしりと重い大判の画集を開いてゆくと、驚きを禁じえない。日本の原点とされてきた『古事記』の世界が、われわれが何となく思い描いていたものとはまるで違う壮大な色彩宇宙として展開してゆくのだ。古事記の物語世界に肉迫してゆくそのイメージ力の雄渾さ。創世神話を彩って華麗に舞い上がるその色彩のド迫力。これまで誰がこのような途轍もないスペクトルでわれわれの神話世界を表現してきただろうか。
描いているのは、大の親日家であり――首相経験者から著名歌手にまで及ぶその交友の広さは驚くばかりである――、日本文化に非常に造詣の深い現代フランス人... [続きを読む] -
推薦者 : 寺田 龍男 (メディア・コミュニケーション研究院)
『太平記』が描く時代を見る
太平記 : 完全版 (DVD) / 吉川英治原作 ; 池端俊策, 仲倉重郎脚本 ; 高橋康夫, 一柳邦久制作. - NHKエンタープライズ, 2008
 北大ではどこにある?
『太平記』が描く時代(14世紀前半)は、南北朝の分裂などもあり、日本社会の大きな転換期となりました。この時代ならではの現象が噴出し、戦後歴史学では進展が著しい一方で、今なお小説には書きにくい時代とも言われています。
北大ではどこにある?
『太平記』が描く時代(14世紀前半)は、南北朝の分裂などもあり、日本社会の大きな転換期となりました。この時代ならではの現象が噴出し、戦後歴史学では進展が著しい一方で、今なお小説には書きにくい時代とも言われています。
この作品は原著『太平記』を吉川英治が脚色し、さらにNHKが大河ドラマ化したものです。その点を理解しておく必要はありますが、佐藤進一『私本太平記』 -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
《2008年ノーベル文学賞受賞!!》芸術、文学、ヨーロッパ思想を学ぶ者にとって必読の書
悪魔祓い / J.M.G.ル・クレジオ〔著〕 ; 高山鉄男訳. - 新潮社, 1975
 北大ではどこにある?
ル・クレジオは現代のフランスの作家。1960年代に前衛的作家として華々しくフランスの文壇にデビューしたあと、現代の西洋文明に飽き足らず、パナマでアメリカ先住民とともに長らく暮らし、スペインに征服される前のメキシコの文明に深く分け入って、芸術とは何か、文学とは何か、文明とは何かを、人類的なトータルな視野から探り続けてきた。本書は、パナマ先住民との生活を通して、彼らの芸術観、生命観、宇宙観をヨーロッパとの比較のもとで描き出したもの。ル・クレジオは、よくあるように、アメリカ先住民の文明を、西洋文明にまだ犯されていない無垢なるものとして語... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ル・クレジオは現代のフランスの作家。1960年代に前衛的作家として華々しくフランスの文壇にデビューしたあと、現代の西洋文明に飽き足らず、パナマでアメリカ先住民とともに長らく暮らし、スペインに征服される前のメキシコの文明に深く分け入って、芸術とは何か、文学とは何か、文明とは何かを、人類的なトータルな視野から探り続けてきた。本書は、パナマ先住民との生活を通して、彼らの芸術観、生命観、宇宙観をヨーロッパとの比較のもとで描き出したもの。ル・クレジオは、よくあるように、アメリカ先住民の文明を、西洋文明にまだ犯されていない無垢なるものとして語... [続きを読む] -
推薦者 : 高見 敏子 (メディア・コミュニケーション研究院)
2年間で英語を100万語読もう―英語多読図書の薦め
英語多読図書 (Penguin Readers, Macmillan Readersほか) / . - ピアソンエデュケーション他,
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 小川 泰寛 (メディア・コミュニケーション研究院)
狩りの観点からなされた西欧文明批判の書
人はなぜ殺すか : 狩猟仮説と動物観の文明史 / マット・カートミル著 ; 内田亮子訳. - 新曜社, 1995
 北大ではどこにある?
狩りの観点からなされた西欧文明批判の書。
北大ではどこにある?
狩りの観点からなされた西欧文明批判の書。
西欧文明において、動物は征服されるべき自然の一環とみなされた。受難は必至だった。これが著者の論点。創見ではないにもせよ、独自の説得力がある。というのも、本書では犠牲になる動物に目線が置かれているからである。
本書で展開されているのはしかし、本質的には人間論である。端的に言えば、人はなぜ何の罪もない動物を慰みに狩るのか。邦題に謳われているように、そもそも「人はなぜ殺すか」。この重い問いが終始省察されている。
生物人類学と解剖学が著者の専門。ただ、本書には西洋古典学、神学、精神分析学... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
小説のなかの中国・米国
千年の祈り / イーユン・リー (篠崎ゆりこ訳). - 新潮社, 2007
 北大ではどこにある?
アメリカンドリームという言葉があります。こういう言葉が長いあいだ一国において命脈を保ってきたというのは、島国にすむものとしては不思議な気がしますが、思うに、常に受け入れてきた移民という新陳代謝が大いに関与しているのかもしれません。その希望の国が(ローマが共和制の衣を脱ぎ帝政の鎧をまとうことになる歴史の転換点にも似て)希望を捨て不安の投網のなかに市民を絡めとりつつあるという悲観的な見方もあるのですが(Naomi Wolf: The end of America, 2007)、なかなかどうして、こういう本に接す... [続きを読む]
北大ではどこにある?
アメリカンドリームという言葉があります。こういう言葉が長いあいだ一国において命脈を保ってきたというのは、島国にすむものとしては不思議な気がしますが、思うに、常に受け入れてきた移民という新陳代謝が大いに関与しているのかもしれません。その希望の国が(ローマが共和制の衣を脱ぎ帝政の鎧をまとうことになる歴史の転換点にも似て)希望を捨て不安の投網のなかに市民を絡めとりつつあるという悲観的な見方もあるのですが(Naomi Wolf: The end of America, 2007)、なかなかどうして、こういう本に接す... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
西洋文明と哲学
反哲学入門 / 木田元. - 新潮社, 2007
 北大ではどこにある?
アメリカでは最近哲学専攻の学生が増えていると云います(ニューヨークタイムズ2008年4月6日の記事)。ただし、歴史上の哲学者のあれこれに興味があるのではなく、将来の見通しが立たない現代社会にあっては、思索で頭脳を鍛え論争の術を身につける必要があるという認識にたってのようです。哲学がそういう処世術にも通ずる生きた学問だと意識されていることに驚きました。
北大ではどこにある?
アメリカでは最近哲学専攻の学生が増えていると云います(ニューヨークタイムズ2008年4月6日の記事)。ただし、歴史上の哲学者のあれこれに興味があるのではなく、将来の見通しが立たない現代社会にあっては、思索で頭脳を鍛え論争の術を身につける必要があるという認識にたってのようです。哲学がそういう処世術にも通ずる生きた学問だと意識されていることに驚きました。
同時にアメリカ大統領予備選挙の記事を追っていると、度を越したような泥試合のなかにも、時として当事者に正気がもどり、その晴れ間をぬって歴史を貫いてきたギリシャ以来の精神が現前すると思われ... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
天才数学者列伝
God created the integers / Stephen Hawking. - Running Press, 2007
 北大ではどこにある?
ピタゴラスは、エーゲ海に浮かぶサモス島で、宇宙は全き数(自然数)によって表される、と考えたそうです。そののちルート2が全き数の割合で表されない(有理数でない)ことを発見したとき、自らの宇宙観への危機をひそかに感じ、その秘匿を弟子たちに命じました。漏洩者には死がまっていました。
北大ではどこにある?
ピタゴラスは、エーゲ海に浮かぶサモス島で、宇宙は全き数(自然数)によって表される、と考えたそうです。そののちルート2が全き数の割合で表されない(有理数でない)ことを発見したとき、自らの宇宙観への危機をひそかに感じ、その秘匿を弟子たちに命じました。漏洩者には死がまっていました。
ギリシャの人々の数学にかけた情熱は、広大無辺の宇宙に肉薄しようという真理にかけた宗教的情熱と一体不可分のようです。後のキリスト教の席巻はこの情熱を本物の宗教的情熱で窒息させてしまい、ギリシャ数学への新風はデカルト(1596−1650)までお預けになりま... [続きを読む] -
推薦者 : 杉山 滋郎 (理学研究科)
科学技術コミュニケーションの入門書!
はじめよう!科学技術コミュニケーション / 北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット(CoSTEP)編著. - ナカニシヤ出版, 2007.12
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 三上 直之 (科学技術コミュニケーター養成ユニット)
科学技術コミュニケーションの基本書!
はじめよう!科学技術コミュニケーション / 北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット(CoSTEP)編著. - ナカニシヤ出版, 2007.12
 北大ではどこにある?
北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット(CoSTEP) での教育実践にもとづいて、科学技術コミュニケーションの基本的 な考え方や、具体的な活動手法をコンパクトに解説しています。
北大ではどこにある?
北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット(CoSTEP) での教育実践にもとづいて、科学技術コミュニケーションの基本的 な考え方や、具体的な活動手法をコンパクトに解説しています。
CoSTEPの講義・演習・実習の基本文献となるほか、大学院でや学部で開講される科学技術コミュニケーションに関わるいくつかの講義でも、主要参考文献として取り上げられることになっています。 -
推薦者 : 眞崎 睦子 (メディア・コミュニケーション研究院)
イヤイヤ古典を読んできたあなたへ
源氏の男はみんなサイテー / 大塚ひかり. - 筑摩書房, 2004
 北大ではどこにある?
でも時々、「あれっ、面白い」、「ふーん」なんて思った瞬間がありませんでしたか?
北大ではどこにある?
でも時々、「あれっ、面白い」、「ふーん」なんて思った瞬間がありませんでしたか?
そんな人は大塚ひかりの古典エッセイを読んでみて。
いくつか、アマゾンにもレビューを書きましたが、まずおすすめの一冊としてこの源氏本をあげます。
「えっ、こういう人だったの?」
源氏物語はじめ、古典の中のあの人この人が血の通った人間となって身近にせまりくる喜び。
ちなみにこの本の解説を書いたのは米原万里で、
大塚ひかりを「紫式部の強烈なPRエージェント」と称しています。同感!登録日 : 2008-02-04
-
推薦者 : 小川 泰寛 (メディア・コミュニケーション研究院)
ニュルンベルク裁判の記録映像
ニュルンベルク裁判 : 裁かれたナチス戦争犯罪の真実 (DVD) / . - 丸善, 2006
 北大ではどこにある?
1945年から1946年にかけ敗戦国ドイツで行われた国際軍事法廷の記録映像。被告のナチス戦犯には四つの罪が帰せられた。そのうち刮目すべきは、「人道に対する罪」。主として、ナチスがヨーロッパ・ユダヤ人に対し犯した凶悪な犯罪行為が念頭に置かれていた。本ドキュメンタリーは取分け、この罪が裁かれる模様を伝えている。
北大ではどこにある?
1945年から1946年にかけ敗戦国ドイツで行われた国際軍事法廷の記録映像。被告のナチス戦犯には四つの罪が帰せられた。そのうち刮目すべきは、「人道に対する罪」。主として、ナチスがヨーロッパ・ユダヤ人に対し犯した凶悪な犯罪行為が念頭に置かれていた。本ドキュメンタリーは取分け、この罪が裁かれる模様を伝えている。
史上類を見ないナチズムの悪行が見過ごされ、繰り返されるようなことになれば文明は滅ぶ。米主席検察官による冒頭の論告には、説得力がある。ニュルンベルク裁判では勝者が敗者を裁いた。「人道に対する罪」にしても、新たに案出されたものである。... [続きを読む] -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
日中関係の近代美術における交流
中国の近代美術と日本:20世紀日中関係の一断面 / 陸偉榮著. - 大学教育出版, 2007
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 小川 泰寛 (メディア・コミュニケーション研究院)
シェイクスピア劇全37作のテレビ映画!
シェークスピア全集 DVD 全37巻 (DVD) / BBC. - Telesis International, 2007
 北大ではどこにある?
英国の主要なメディアBBCはシェイクスピア劇全37作をテレビ映画として制作した。着手は1978年。完結したのは1985年。文化的に意義深い試みとして、好意的に評価されたように記憶している。わが国では、NHKで放送され、ビデオが市販されもした。ただ、ビデオはもはやあまりに古く、映像の劣化が甚だしい。ほぼすべてのタイトルが閲覧に堪えない、というのが現実である。死に体同然と言って過言でない。
北大ではどこにある?
英国の主要なメディアBBCはシェイクスピア劇全37作をテレビ映画として制作した。着手は1978年。完結したのは1985年。文化的に意義深い試みとして、好意的に評価されたように記憶している。わが国では、NHKで放送され、ビデオが市販されもした。ただ、ビデオはもはやあまりに古く、映像の劣化が甚だしい。ほぼすべてのタイトルが閲覧に堪えない、というのが現実である。死に体同然と言って過言でない。
そのような中、DVD化を通し本企画が蘇生したのは朗報である。
BBCシェイクスピア、全タイトル粒ぞろいの逸品とは、言い難い。困ったことに、主要なシェイクスピア劇で完成度... [続きを読む] -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
現代中国を代表する哲学者による回想録
馮友蘭自伝 : 中国現代哲学者の回想 1・2 (東洋文庫 ; 767-768) / 馮友蘭著 ; 吾妻重二訳 . - 平凡社, 2007
 北大ではどこにある?
現代中国を代表する哲学者による回想録。19世紀末から1980年代に至る、変貌の時代を生きた著者が同時代史を記し、自己の経験をまとめた書で、激動の中国近現代史を理解するうえで必読書といってもよい名著の翻訳である。なかでも中華人民共和国成立後の部分は、知識人の内面史として他書に類例をみぬ価値を持つ。翻訳も平明で読みやすい。
北大ではどこにある?
現代中国を代表する哲学者による回想録。19世紀末から1980年代に至る、変貌の時代を生きた著者が同時代史を記し、自己の経験をまとめた書で、激動の中国近現代史を理解するうえで必読書といってもよい名著の翻訳である。なかでも中華人民共和国成立後の部分は、知識人の内面史として他書に類例をみぬ価値を持つ。翻訳も平明で読みやすい。 -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
現代中国への認識を深めるのに一読の価値あり
嵐を生きた中国知識人 : 「右派」章伯鈞をめぐる人びと / 章詒和著 ; 横澤泰夫訳. - 集広舎, 2007
 北大ではどこにある?
現代中国への認識を深めるのに一読の価値あり。50年前に開始された「反右派闘争」の中で「最大の右派」とされた父・章伯鈞をめぐる人びとを活写することにより、「中国共産党の政治」のあり方を世に問うた問題作。流麗な文章と深い人間理解、歴史への洞察によって中国内外で高い評価を受けたものの、発売後2ヶ月で再版不許可・発禁処分となった『往事並不如煙』を香港で改題・出版した完全版『最後的貴族』(香港・牛津大学出版社2004年)の日本語版。
北大ではどこにある?
現代中国への認識を深めるのに一読の価値あり。50年前に開始された「反右派闘争」の中で「最大の右派」とされた父・章伯鈞をめぐる人びとを活写することにより、「中国共産党の政治」のあり方を世に問うた問題作。流麗な文章と深い人間理解、歴史への洞察によって中国内外で高い評価を受けたものの、発売後2ヶ月で再版不許可・発禁処分となった『往事並不如煙』を香港で改題・出版した完全版『最後的貴族』(香港・牛津大学出版社2004年)の日本語版。 -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
楽しみながら中国語を学ぶ入門書
ウーロン茶のCMソングから中国語を始めませんか? / amin著. - 小学館,
 北大ではどこにある?
おなじみの烏龍茶CMソングの歌詞から、楽しみながら中国語を学ぶ入門書。中国人歌手として史上初のNHK紅白歌合戦出場を果たしたamin(阿明)自らが吹きこんだ解説CD付き。中国人の前で歌がうたえれば絶対ウケるし、なにより楽しい。楽しいがいちばん!
北大ではどこにある?
おなじみの烏龍茶CMソングの歌詞から、楽しみながら中国語を学ぶ入門書。中国人歌手として史上初のNHK紅白歌合戦出場を果たしたamin(阿明)自らが吹きこんだ解説CD付き。中国人の前で歌がうたえれば絶対ウケるし、なにより楽しい。楽しいがいちばん! -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
現代中国社会の悲哀を、リアルに、多少の皮肉も交じえ、温かい目で描く物語
飛べない龍 / 蘇童著 ; 村上満里子訳. - 文芸社, 2007
 北大ではどこにある?
著者は現代中国文壇を代表する作家の一人。経済成長著しい中国社会の底辺で、もがきながら生きる男と女。目まぐるしい変化と発展の中で、取り残されたままの人々の姿、そして現代中国社会の悲哀を、リアルに、多少の皮肉も交じえ、温かい目で描く物語。
北大ではどこにある?
著者は現代中国文壇を代表する作家の一人。経済成長著しい中国社会の底辺で、もがきながら生きる男と女。目まぐるしい変化と発展の中で、取り残されたままの人々の姿、そして現代中国社会の悲哀を、リアルに、多少の皮肉も交じえ、温かい目で描く物語。 -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
「外地」研究の新しい研究動向
大日本帝国のクレオール : 植民地期台湾の日本語文学 / フェイ・阮・クリーマン著 ; 林ゆう子訳 . - 慶應義塾大学出版会, 2007
 北大ではどこにある?
台湾の日本植民地時代に創作された日本語文学(植民地下での公用語・日本語によって書かれた文学)を〈クレオール=文化的混淆〉という視点から読み解き、米国・台湾等で高い評価を得た研究論文の日本語版。「外地」研究は本学の「伝統的」学問の一つの柱をなす部分であり、本学図書館は戦前の台湾関係文献資料を豊富に所蔵することで、その分野ではつとに有名であるが、こうした新しい研究動向もしっかりフォローしていきたいものである。
北大ではどこにある?
台湾の日本植民地時代に創作された日本語文学(植民地下での公用語・日本語によって書かれた文学)を〈クレオール=文化的混淆〉という視点から読み解き、米国・台湾等で高い評価を得た研究論文の日本語版。「外地」研究は本学の「伝統的」学問の一つの柱をなす部分であり、本学図書館は戦前の台湾関係文献資料を豊富に所蔵することで、その分野ではつとに有名であるが、こうした新しい研究動向もしっかりフォローしていきたいものである。 -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
現代中国理解のために
近代中国の政治文化 : 民権・立憲・皇権 / 野村浩一. - 岩波書店, 2007
 北大ではどこにある?
改革開放の進む中国では近年、魯迅と同時代に活躍した現代中国を代表する知識人・胡適の研究がますます盛んになっているが、日本では残念ながらあまり注目されていない。その胡適を中心に近代中国における「自由主義」の位置づけを試みた第三章は本書の圧巻で、現代中国理解のためにも一読に値する。
北大ではどこにある?
改革開放の進む中国では近年、魯迅と同時代に活躍した現代中国を代表する知識人・胡適の研究がますます盛んになっているが、日本では残念ながらあまり注目されていない。その胡適を中心に近代中国における「自由主義」の位置づけを試みた第三章は本書の圧巻で、現代中国理解のためにも一読に値する。 -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
日中関係について美術品の交流とそのマーケットという視点から迫ろうというユニークな書
美術と市場 : 日本と中国の美術品交流と変遷からの視点 / 半田晴久著. - たちばな出版, 2007
 北大ではどこにある?
日中関係について美術品の交流とそのマーケットという視点から迫ろうというユニークな書。美術はもちろん芸術品であるが、それと同時に、価格がつき、売買される、れっきとした〈商品〉としての一面も無視することはできない。アートを通じた国際交流が今後ますます盛んになっていくであろう現在、考え、行動するためのヒントが見つかるかもしれない。
北大ではどこにある?
日中関係について美術品の交流とそのマーケットという視点から迫ろうというユニークな書。美術はもちろん芸術品であるが、それと同時に、価格がつき、売買される、れっきとした〈商品〉としての一面も無視することはできない。アートを通じた国際交流が今後ますます盛んになっていくであろう現在、考え、行動するためのヒントが見つかるかもしれない。 -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
文系の学生、院生の必読書
大学生の論文執筆法 / 石原千秋. - 筑摩新書, 2006
 北大ではどこにある?
漱石の研究家である著者が大学の教育の中で、痛感した学生のレポートや論文の書き方の不備、欠点を指摘し、如何に書くか、また書く準備として書く心構えから、資料の扱い方、何が資料とはならないかなど詳しく指摘したもの。ネットで集めた知識は評価されないことなど教員には分り切ったことだが、学生はちゃんと知らない人もいることが書かれていて、こういうことを大学院生になってもいい加減な人もいるので、必読書である。この程度のことは先刻承知だという人は大変結構です。論文の推敲例もあるので、参考になります。
北大ではどこにある?
漱石の研究家である著者が大学の教育の中で、痛感した学生のレポートや論文の書き方の不備、欠点を指摘し、如何に書くか、また書く準備として書く心構えから、資料の扱い方、何が資料とはならないかなど詳しく指摘したもの。ネットで集めた知識は評価されないことなど教員には分り切ったことだが、学生はちゃんと知らない人もいることが書かれていて、こういうことを大学院生になってもいい加減な人もいるので、必読書である。この程度のことは先刻承知だという人は大変結構です。論文の推敲例もあるので、参考になります。 -
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
人文学はどのようなひとを育てるか
哲学修業時代 / H.G.ガーダマー (中村志朗訳). - 未来社 , 1982
 北大ではどこにある?
本書は哲学、そして広くは文学、神学などを含む人文学一般への、生き生きした人物評伝を媒介にしたものとしては、最良の入門書であろう。1900年ドイツ生まれという著者が生きたその時代が人類史においても特筆すべき時代であったことからくる興味深さもさることながら、本書は人文学を学んだひとはどのようなひととなり、そしてどのように人々と交わるかを、さらに人間を愛情をもってどれほど豊かなものとして、また正確さにおいて説得的なものとして描きうるかをいかんなく伝えている。それにしても彼の交流のなんと豊かなことか、P.ナトルプ、E.フッサール、N.ハルトマン、R.... [続きを読む]
北大ではどこにある?
本書は哲学、そして広くは文学、神学などを含む人文学一般への、生き生きした人物評伝を媒介にしたものとしては、最良の入門書であろう。1900年ドイツ生まれという著者が生きたその時代が人類史においても特筆すべき時代であったことからくる興味深さもさることながら、本書は人文学を学んだひとはどのようなひととなり、そしてどのように人々と交わるかを、さらに人間を愛情をもってどれほど豊かなものとして、また正確さにおいて説得的なものとして描きうるかをいかんなく伝えている。それにしても彼の交流のなんと豊かなことか、P.ナトルプ、E.フッサール、N.ハルトマン、R.... [続きを読む] -
推薦者 : 寺田 龍男 (メディア・コミュニケーション研究院)
命と平和について
火垂るの墓 / 野坂昭如. - 新潮社, 1972/2001
 北大ではどこにある?
この本は学習とは直接関係がありません。ですが、命の尊さや家庭・平和の大切さを考えさせてくれます。高畑勲監督のアニメ(1988年)は海外でも、「もっとも強く心をゆさぶるアニメ作品」のひとつとして知られています。
北大ではどこにある?
この本は学習とは直接関係がありません。ですが、命の尊さや家庭・平和の大切さを考えさせてくれます。高畑勲監督のアニメ(1988年)は海外でも、「もっとも強く心をゆさぶるアニメ作品」のひとつとして知られています。
小説(野坂昭如著作) [単行本 文庫本]
アニメ(高畑勲監督) [DVD -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
アメリカの覇権と現状
日本人だけが知らないアメリカ「世界支配」の終わり / カレル・ヴァン・ウォルフレン. - 徳間書店, 2007
 北大ではどこにある?
見事な風景に接して、それを描こうとしても、きっとどこかで見た絵画のものまねになるように、この世界の現実を突きつけられても、それよりひとつの物語を紡ごうとすれば、きっとどこかで刷り込まれた解釈の焼き直しになるようです。著者によると(あるいは常識というべきでしょうか)、この世界の解釈は長いあいだアメリカより発信されてきました。たとえば、自由信仰にもとづく経済が世界に繁栄と安定をもたらすという託宣です。しかし(日本を除く)世界の国々はこの米国主導の解釈に対して疑念を抱き始めたようです。(例えば、昔からアメリカの支配下にあった中南米の国々... [続きを読む]
北大ではどこにある?
見事な風景に接して、それを描こうとしても、きっとどこかで見た絵画のものまねになるように、この世界の現実を突きつけられても、それよりひとつの物語を紡ごうとすれば、きっとどこかで刷り込まれた解釈の焼き直しになるようです。著者によると(あるいは常識というべきでしょうか)、この世界の解釈は長いあいだアメリカより発信されてきました。たとえば、自由信仰にもとづく経済が世界に繁栄と安定をもたらすという託宣です。しかし(日本を除く)世界の国々はこの米国主導の解釈に対して疑念を抱き始めたようです。(例えば、昔からアメリカの支配下にあった中南米の国々... [続きを読む] -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
「考える」という営みへの最良の入門書
哲学、脳を揺さぶる / 河本英夫. - 日経BP, 2007
 北大ではどこにある?
分類すれば哲学という分野に入るのだろうが、思考のエクササイズはもとより、芸術あり、科学あり、身体論あり、イメージ論あり、認知論あり、といった具合に間口はひろく、総合的であり、そして(多少は苦労もしながら)ひとたび読み終わってみれば、脳は活性化し、何やらいっぱしの知的ナヴィゲーションをしてきた充実感が得られること間違いなし。著者は、「考える」という人間の不思議なイトナミに深く広く分け入らんとする先端的な探求者のひとり。大学生たる者、たまにはこうした本を読みこなさなくちゃ。
北大ではどこにある?
分類すれば哲学という分野に入るのだろうが、思考のエクササイズはもとより、芸術あり、科学あり、身体論あり、イメージ論あり、認知論あり、といった具合に間口はひろく、総合的であり、そして(多少は苦労もしながら)ひとたび読み終わってみれば、脳は活性化し、何やらいっぱしの知的ナヴィゲーションをしてきた充実感が得られること間違いなし。著者は、「考える」という人間の不思議なイトナミに深く広く分け入らんとする先端的な探求者のひとり。大学生たる者、たまにはこうした本を読みこなさなくちゃ。 -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
私という存在を操縦している生命なるものの仕組みを知ろう
生物と無生物のあいだ / 福岡伸一. - 講談社(講談社現代新書), 2007
 北大ではどこにある?
目下(2007年8月時点)大評判の書である。生命というとすぐ自然科学と思うなかれ、科学についてのみならず、人間について、世界について関心がある者すべてにこの書は開かれている。生命の謎を解明してゆく分子生物学の最先端の探究を語りながら、いつの間にかこの本は、現代における科学のあり方や人間の生き方までをも、著者独特の広角レンズでみごとに浮かび上がらせてくれる。著者の語り口は一級のストーリー・テラーのように冴え渡っていて、読む者は、まるで冒険小説を読むように、生命の演ずる壮大なドラマにぐいぐいと引き込まれてゆく。知的興奮をたっぷりと与えられ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
目下(2007年8月時点)大評判の書である。生命というとすぐ自然科学と思うなかれ、科学についてのみならず、人間について、世界について関心がある者すべてにこの書は開かれている。生命の謎を解明してゆく分子生物学の最先端の探究を語りながら、いつの間にかこの本は、現代における科学のあり方や人間の生き方までをも、著者独特の広角レンズでみごとに浮かび上がらせてくれる。著者の語り口は一級のストーリー・テラーのように冴え渡っていて、読む者は、まるで冒険小説を読むように、生命の演ずる壮大なドラマにぐいぐいと引き込まれてゆく。知的興奮をたっぷりと与えられ... [続きを読む] -
推薦者 : 高井 潔司 (メディア・コミュニケーション研究院)
研究や他者を批判することの厳しさを知る
激辛書評で知る中国の政治・経済の虚実 / 矢吹晋. - 日経BP社, 2007
 北大ではどこにある?
本書は、中国関係図書に対する書評を通して、中国の政治・経済の実相を知るスタイルを取っている。台頭する中国をめぐってはさまざまな著作が出版されているが、ベストセラーとなっている本の中にも、偏見や憎しみに基づいて編集され、事実からかけ離れたものがある。著者は、生半可な書評ではなく、該博な知識と厳密な調査に基づいて、ベストセラーになった中国関係図書を解剖し、辛らつな批判を行っている。中国を理解するだけでなく、研究の厳しさ、他者を批判することの厳しさを教えてくれる。
北大ではどこにある?
本書は、中国関係図書に対する書評を通して、中国の政治・経済の実相を知るスタイルを取っている。台頭する中国をめぐってはさまざまな著作が出版されているが、ベストセラーとなっている本の中にも、偏見や憎しみに基づいて編集され、事実からかけ離れたものがある。著者は、生半可な書評ではなく、該博な知識と厳密な調査に基づいて、ベストセラーになった中国関係図書を解剖し、辛らつな批判を行っている。中国を理解するだけでなく、研究の厳しさ、他者を批判することの厳しさを教えてくれる。 -
推薦者 : 高井 潔司 (メディア・コミュニケーション研究院)
全うな現代中国論
臨界点の中国 / 藤野 彰. - 中国書店, 2007年
 北大ではどこにある?
巷にあふれている現代中国論、現実の中国から出発せず、中国脅威論や崩壊論、あるいはそれらとは対極の中国待望論がほとんどである。著者は、10年を超える中国特派員の経験と知識を活用し、中国全土を歩き回り、様々なレベルの中国人の声を集め、それを基礎に穏当な中国論を展開してている。地に足の着いた中国論である。好きであれ、嫌いであれ、日本の将来にとって、対中関係のあり方はますます重要になっている。そのためには、まず中国の実像をしっかり抑えておく必要がある。本書は極めて有用な視点と知識を提供してくれよう。
北大ではどこにある?
巷にあふれている現代中国論、現実の中国から出発せず、中国脅威論や崩壊論、あるいはそれらとは対極の中国待望論がほとんどである。著者は、10年を超える中国特派員の経験と知識を活用し、中国全土を歩き回り、様々なレベルの中国人の声を集め、それを基礎に穏当な中国論を展開してている。地に足の着いた中国論である。好きであれ、嫌いであれ、日本の将来にとって、対中関係のあり方はますます重要になっている。そのためには、まず中国の実像をしっかり抑えておく必要がある。本書は極めて有用な視点と知識を提供してくれよう。 -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
人は弱いものらしい
The Lucifer Effect -- Understanding How Good People Turn Evil / Philip Zimbardo. - Random House, 2007
 北大ではどこにある?
最近の日本政府は先の大戦で我国の犯した残虐行為を軽視する傾向にあるようです。先ごろも、「従軍慰安婦の募集は軍部の強制によるのではない」という発言をしたひとが、米国で物議をかもすと、わざわざ向こうの大統領の前で釈明し「その謝罪を受け入れる」というお墨付きをもらうという訳のわからないことがありました。
北大ではどこにある?
最近の日本政府は先の大戦で我国の犯した残虐行為を軽視する傾向にあるようです。先ごろも、「従軍慰安婦の募集は軍部の強制によるのではない」という発言をしたひとが、米国で物議をかもすと、わざわざ向こうの大統領の前で釈明し「その謝罪を受け入れる」というお墨付きをもらうという訳のわからないことがありました。
正直なところこの問題は当時の日本の犯した犯罪行為としては軽微な方だったのではないかと思われます。それよりも、たとえば強制労働のほうが問題です。これは規模も大きく死亡率も(他国の同様の場合と比べ)かなり高かったようです。さらに、これが... [続きを読む] -
推薦者 : 岡田 敦美 (メディア・コミュニケーション研究院)
遠い世界の「他者」へ、思いをはせる
先住民ミヘの静かな変容―メキシコで考える / 黒田悦子. - 朝日選書, 1996
 北大ではどこにある?
ラテンアメリカの民族誌として定評ある一冊で、メキシコ南部オアハカ州での参与観察に基づいた著者の研究は、現地メキシコでも出版されているほどです。だまされたと思って、読んでみてください。
北大ではどこにある?
ラテンアメリカの民族誌として定評ある一冊で、メキシコ南部オアハカ州での参与観察に基づいた著者の研究は、現地メキシコでも出版されているほどです。だまされたと思って、読んでみてください。
1970年代にミヘの村に住んで、調査を済ませてから10年以上経った1990年代に、ミヘの村を再訪するところからこの本は始まります。出稼ぎや、都市への移住をはじめとする村の外部との行き来を通して、大きな変貌を遂げたミヘの人々を、「心の触れ合える人たち」として身近にとらえる、著者、すなわちフィールドワーカーの目を通して、私たちは遠いメキシコの先住民の人々の世界... [続きを読む] -
推薦者 : 岡田 敦美 (メディア・コミュニケーション研究院)
「他者」と向きあう人類最初の経験――コミュニケーションや異文化について考える
他者の記号学―アメリカ大陸の征服 / ツヴェタン・トドロフ. - 法政大学出版局, 1986(日本語初版)
 北大ではどこにある?
著者のトドロフは、ブルガリア生まれでパリで活躍する言語学者。本のテーマは「他者の発見」で、その手がかりとして、新大陸の発見と征服の時期が、もっと具体的にいえば、新大陸とヨーロッパ人が出会って以降の100年あまりの間に新大陸に渡ったヨーロッパ人によって書かれた記録や文書が、分析対象として選ばれたのである。トドロフによれば、1492年は、「ヨーロッパの歴史上、最も驚嘆に値する他者との出会い」の画期をなした。「今あるヨーロッパ人のアイデンティティが示され、基礎づけられたのはまさにこの新大陸の発見にあるのだ」。その意味で、1492年以来、ヨーロッパ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
著者のトドロフは、ブルガリア生まれでパリで活躍する言語学者。本のテーマは「他者の発見」で、その手がかりとして、新大陸の発見と征服の時期が、もっと具体的にいえば、新大陸とヨーロッパ人が出会って以降の100年あまりの間に新大陸に渡ったヨーロッパ人によって書かれた記録や文書が、分析対象として選ばれたのである。トドロフによれば、1492年は、「ヨーロッパの歴史上、最も驚嘆に値する他者との出会い」の画期をなした。「今あるヨーロッパ人のアイデンティティが示され、基礎づけられたのはまさにこの新大陸の発見にあるのだ」。その意味で、1492年以来、ヨーロッパ... [続きを読む] -
推薦者 : 岡田 敦美 (メディア・コミュニケーション研究院)
グローバリゼーション研究の一人者による入門書
グローバリゼーションとは何か―液状化する世界を読み解く / 伊豫谷登士翁. - 平凡社新書, 2002
 北大ではどこにある?
「グローバリゼーション」というとき、それは「国際化」とどう違うのか、そしてグローバリゼーション研究が、いかなる問題意識に立脚して、どのような現象を分析対象としてきたのかを知るうえで、最良の一冊です。
北大ではどこにある?
「グローバリゼーション」というとき、それは「国際化」とどう違うのか、そしてグローバリゼーション研究が、いかなる問題意識に立脚して、どのような現象を分析対象としてきたのかを知るうえで、最良の一冊です。
キーワードは、たとえば国民国家の相対化、世界秩序、南北問題、多国籍企業、メディア、移民、労働市場・・・。アクチュアルな現象に関心がある人、開発援助に関心がある人は、是非読んでみましょう。
第一章:グローバリゼーションの課題は何か、 第二章:時代としてのグローバリゼーション、 第三章:グローバリゼーションをマッピングする、 第四章... [続きを読む]