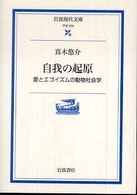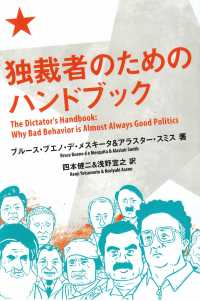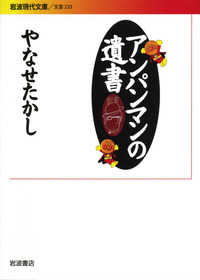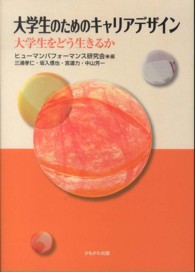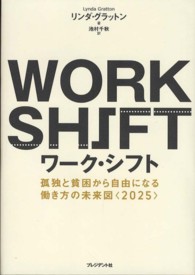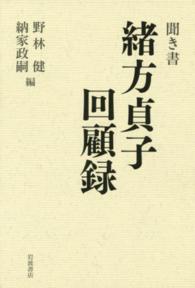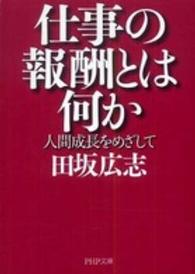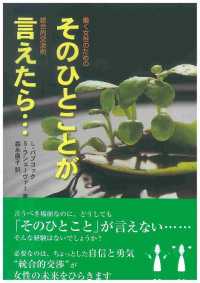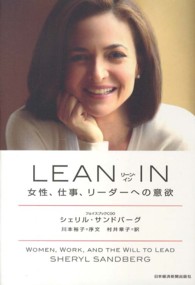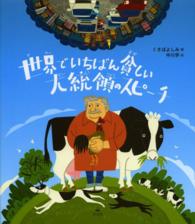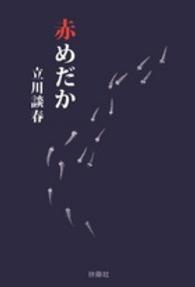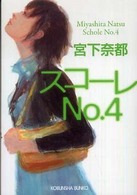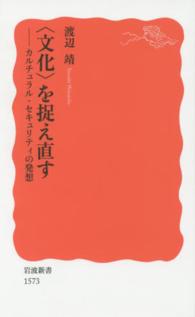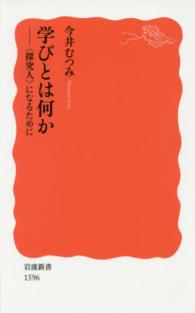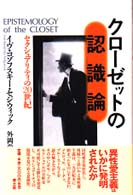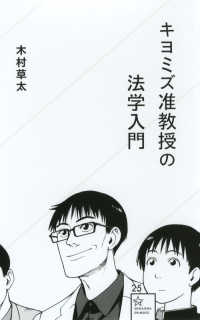-
推薦者 : 野中 雄司 (附属図書館・職員)
これから「どう生きるか」を改めて考えたいときに
君たちはどう生きるか / 吉野源三郎. - 岩波書店, 1982
 北大ではどこにある?
この本は、軍国主義が勢力を強めつつあった昭和十二年に山本有三が少年少女向けに偏狭な国枠主義を越えた自由で豊かな文化のあることを伝えようとして編纂した『日本少国民文庫』シリーズ中の「倫理」を扱ったものです。私はこの少年少女向けの本を25歳を過ぎてから読みましたが、恥ずかしながら「勉強する意味」などハッとさせられる部分が多くあり感銘を受けました。読了後少し恥ずかしく思いつつ解説を読んでいると、なんとかの丸山眞男も大卒後東大法学部の助手になり研究者になった後に読み「私の魂をゆるがした」と記されており、驚いたのと同時にほっとしたことを覚... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、軍国主義が勢力を強めつつあった昭和十二年に山本有三が少年少女向けに偏狭な国枠主義を越えた自由で豊かな文化のあることを伝えようとして編纂した『日本少国民文庫』シリーズ中の「倫理」を扱ったものです。私はこの少年少女向けの本を25歳を過ぎてから読みましたが、恥ずかしながら「勉強する意味」などハッとさせられる部分が多くあり感銘を受けました。読了後少し恥ずかしく思いつつ解説を読んでいると、なんとかの丸山眞男も大卒後東大法学部の助手になり研究者になった後に読み「私の魂をゆるがした」と記されており、驚いたのと同時にほっとしたことを覚... [続きを読む] -
推薦者 : 小浜 祥子 (公共政策学連携研究部・法学研究科・教員)
突如として権力者が消えた世界、そこで何が起こるか
別荘 : Casa de campo / ホセ・ドノソ著 ; 寺尾隆吉訳. - 現代企画室, 2014
 北大ではどこにある?
権力と自由こそ、政治学におけるメインテーマである。チリの作家ホセ・ドノソの傑作『別荘』では、ある小国で栄華を誇るベントゥーラ家の大人たちがピクニックに出かけ、33人の子どもたちだけが別荘に残される。突如として権力者が消えてしまった世界で、何が起こるのか。本作は1973年にチリで起こったアウグスト・ピノチェト将軍によるクーデターに着想を得て執筆されたものと言われている。ぜひ自分を取り巻く権力と自由に思いを馳せながら、このドラマチックな小説を楽しんでほしい。チリや中南米の政治史を学べばよりいっそう味わい深いに違いない。
北大ではどこにある?
権力と自由こそ、政治学におけるメインテーマである。チリの作家ホセ・ドノソの傑作『別荘』では、ある小国で栄華を誇るベントゥーラ家の大人たちがピクニックに出かけ、33人の子どもたちだけが別荘に残される。突如として権力者が消えてしまった世界で、何が起こるのか。本作は1973年にチリで起こったアウグスト・ピノチェト将軍によるクーデターに着想を得て執筆されたものと言われている。ぜひ自分を取り巻く権力と自由に思いを馳せながら、このドラマチックな小説を楽しんでほしい。チリや中南米の政治史を学べばよりいっそう味わい深いに違いない。 -
推薦者 : 武藤 俊雄 (公共政策大学院・教員)
文系・理系区分なんてぶっ飛ばせ!
自我の起原 : 愛とエゴイズムの動物社会学 / 真木悠介. - 岩波書店, 2008
 北大ではどこにある?
日々更新されてゆく自然科学は、私たちに新しい生命や、人間の理解を提示してくれる。そうしたサイエンスとしての生命と人間の理解を、人文・社会科学の知見と自在に往復しながら、深く問いかけてくる名著である。学問領域の枠にとらわれない、生き生きとした精神の持ち主に読んで欲しい。
北大ではどこにある?
日々更新されてゆく自然科学は、私たちに新しい生命や、人間の理解を提示してくれる。そうしたサイエンスとしての生命と人間の理解を、人文・社会科学の知見と自在に往復しながら、深く問いかけてくる名著である。学問領域の枠にとらわれない、生き生きとした精神の持ち主に読んで欲しい。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
やっぱり東京大学は凄い…。
アクティブラーニングのデザイン : 東京大学の新しい教養教育 / 永田敬, 林一雅編. - 東京大学出版会, 2016
 北大ではどこにある?
平成24年8月24日付中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~」に於いて、今後の中等教育・大学教育に積極的にアクティブ・ラーニング型授業を導入するべきであることが打ち出された。この本は、東京大学教養学部で実践されたアクティブラーニングの理念と方略を報告したものである。読者としては、これからアクティブラーニングに取り組もうとする大学教員を想定しているものであるが、学生が読んでも21世紀に求められる能力をどの... [続きを読む]
北大ではどこにある?
平成24年8月24日付中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~」に於いて、今後の中等教育・大学教育に積極的にアクティブ・ラーニング型授業を導入するべきであることが打ち出された。この本は、東京大学教養学部で実践されたアクティブラーニングの理念と方略を報告したものである。読者としては、これからアクティブラーニングに取り組もうとする大学教員を想定しているものであるが、学生が読んでも21世紀に求められる能力をどの... [続きを読む] -
推薦者 : 小浜 祥子 (公共政策学連携研究部・法学研究科・教員)
政治学の最先端理論を分かりやすく
独裁者のためのハンドブック / ブルース・ブエノ・デ・メスキータ, アラスター・スミス著 ; 四本健二, 浅野宜之訳. - 亜紀書房, 2013
 北大ではどこにある?
なぜ国民を弾圧し飢えさせる独裁者がこれほど長く権力の座に居続けるのか?なぜ往々にして、資源の豊かな国ほど国民が貧しいのか?対外援助は本当に人々を救うのか?なぜ民主主義国家はこれほど戦争に強いのか?
北大ではどこにある?
なぜ国民を弾圧し飢えさせる独裁者がこれほど長く権力の座に居続けるのか?なぜ往々にして、資源の豊かな国ほど国民が貧しいのか?対外援助は本当に人々を救うのか?なぜ民主主義国家はこれほど戦争に強いのか?
本書では、第一線で活躍する政治学者二人がこれらの謎を解き明かす。彼らがこの本を書いた理由は「問題に取り組む方法を学生に教えること、問題解決のための訓練をきちんとほどこしてから彼らを世の中に出すこと…自分が事態を良くしているのか、それとも悪くしているのかもわからず、ただものごとを掻き乱すだけの人間を、世界に送り出したくない」からだという... [続きを読む] -
推薦者 : 武藤 俊雄 (公共政策大学院・教員)
「市町村」はどう作られたか?
町村合併から生まれた日本近代 : 明治の経験 / 松沢裕作. - 講談社, 2013
 北大ではどこにある?
現在の市町村という、基本的な行政区分がどのような歴史的経緯で形成されてきたのかを、明治期の変革を中心に描いている本である。わが国の社会構成の基本単位が形成される過程には、近代へと向かう人々のダイナミックな動きが見て取れる。私たちが目にする社会の基本構造を支えている「基盤」のようなものの存在を知ることは、少子高齢化・人口減少という大きな変動期を迎える今、ここから先を見通す知的な武器になるだろう。
北大ではどこにある?
現在の市町村という、基本的な行政区分がどのような歴史的経緯で形成されてきたのかを、明治期の変革を中心に描いている本である。わが国の社会構成の基本単位が形成される過程には、近代へと向かう人々のダイナミックな動きが見て取れる。私たちが目にする社会の基本構造を支えている「基盤」のようなものの存在を知ることは、少子高齢化・人口減少という大きな変動期を迎える今、ここから先を見通す知的な武器になるだろう。 -
推薦者 : 増田 哲子 (メディア・コミュニケーション研究院・教員)
選択をする「自分」について知ること
おとなの進路教室。 / 山田ズーニー. - 河出書房新社, 2007
 北大ではどこにある?
著者の山田ズーニーさんは、企業や大学でコミュニケーションや文章表現についての研修・教育を行っている方です。著者自身、30代後半に教育系の大手出版社を辞め、独立という大きな選択をしました。
北大ではどこにある?
著者の山田ズーニーさんは、企業や大学でコミュニケーションや文章表現についての研修・教育を行っている方です。著者自身、30代後半に教育系の大手出版社を辞め、独立という大きな選択をしました。
大学進学、就職、転職といったさまざまな進路選択において、選ぶ基準となる自分自身の気持ちをどのように掘り下げ、どのように表現するのか?本書は、こうした問いについて、著者自身の経験や著者が出会ったさまざまな人たちのケースから考えさせてくれます。
人生のなかで、進路選択は1回きりではありません。高校進学、大学進学、就職の後も、まだまだ選択の機... [続きを読む] -
推薦者 : 宮本 淳 (高等教育推進機構・教員)
「少年よ、迷い悩め」
アンパンマンの遺書 / やなせたかし. - 岩波書店, 2013
 北大ではどこにある?
この本のタイトルにちょっとドキッとした人もいるかもしれません。「遺書」とありますし、この本の著者で、アンパンマンの作者であるやなせたかしさんは、2013年10月13日に94歳で永眠されています。でも、タイトルを見て是非読んでみたいと思った人もいませんか?小さいころ大好きだったアンパンマンの遺書?!何が書かれているのだろう...ちなみに絵本ではありません。推薦する私がこの本を読んだ理由は2つです。ひとつは、私の実家が高知県にあること。高知県はやなせさんの出身地です。私は高知で暮らしたことがありませんが、両親がリタイヤ後に自分たちのふるさとである... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本のタイトルにちょっとドキッとした人もいるかもしれません。「遺書」とありますし、この本の著者で、アンパンマンの作者であるやなせたかしさんは、2013年10月13日に94歳で永眠されています。でも、タイトルを見て是非読んでみたいと思った人もいませんか?小さいころ大好きだったアンパンマンの遺書?!何が書かれているのだろう...ちなみに絵本ではありません。推薦する私がこの本を読んだ理由は2つです。ひとつは、私の実家が高知県にあること。高知県はやなせさんの出身地です。私は高知で暮らしたことがありませんが、両親がリタイヤ後に自分たちのふるさとである... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (外国語教育センター・教員)
大名の生活を英語で説明しよう
The life and culture of samurai lords : masterworks from the Tokugawa Art Museum / The Tokugawa Art Museum. - 徳川美術館, 2016
 北大ではどこにある?
諸君、和服が着られるかな?女の子なら振袖を着た経験があるだろうか?男の子なら羽織・袴。しかし所有していない人も多いのでは?まさか着方を知らない?日本の民俗衣裳だぞ。しかも意外と安いのもある。
北大ではどこにある?
諸君、和服が着られるかな?女の子なら振袖を着た経験があるだろうか?男の子なら羽織・袴。しかし所有していない人も多いのでは?まさか着方を知らない?日本の民俗衣裳だぞ。しかも意外と安いのもある。
さてさて。日本の文化を英語で説明できれば、日本の文化を知っているといえるだろうし、日本の文化を知ってもらう力を有しているともいえるだろう。
本書は、御三家大名のひとつ尾張名古屋の徳川藩ゆかりの徳川美術館が著した、大名生活の英語による説明だ。日本を知り、日本を知ってもらう力を身につけよう。 -
推薦者 : 加藤 真樹 (大学力強化推進本部 / 理学研究院・職員)
生物学をベースにしたムツゴロウさんのSF小説
海からきたチフス / 畑正憲. - 角川書店, 1973
 北大ではどこにある?
動物王国のムツゴロウさんこと畑正憲氏が初めて書いたSF小説。離島で起きた無細胞生物「ヌル」による不思議な事件の謎に生物好きの家族が挑むサイエンスフィクションです。ムツゴロウさん自身、東京大学で生理学を学んでいたこともあり、細胞生物学の知見をちりばめた謎解きは今読んでみても面白いです。
北大ではどこにある?
動物王国のムツゴロウさんこと畑正憲氏が初めて書いたSF小説。離島で起きた無細胞生物「ヌル」による不思議な事件の謎に生物好きの家族が挑むサイエンスフィクションです。ムツゴロウさん自身、東京大学で生理学を学んでいたこともあり、細胞生物学の知見をちりばめた謎解きは今読んでみても面白いです。 -
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
将来のキャリアと”今”をつなげよう
大学生のためのキャリアデザイン : 大学生をどう生きるか / ヒューマンパフォーマンス研究会編 ; 三浦孝仁 [ほか執筆]. - かもがわ出版, 2013
 北大ではどこにある?
学生向けに書かれた「キャリア」本が各種ある中で、キャリア開発の考え方と学びつつ「学生時代の今をどう過ごすか?」についての指南を与えてくれる本です。
北大ではどこにある?
学生向けに書かれた「キャリア」本が各種ある中で、キャリア開発の考え方と学びつつ「学生時代の今をどう過ごすか?」についての指南を与えてくれる本です。
大学生の時期は、自分を理解し、自己管理能力を身につける大変良い時期です。やみくもに努力するよりも、キャリア開発の知識を持ったうえでの努力の方が、より成長につながると思います。
-
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
2025年、働き方はどうなっているか?
ワーク・シフト : 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図「2025」 = Work shift / リンダ・グラットン著 ; 池村千秋訳. - プレジデント社, 2012
 北大ではどこにある?
”2025年”に、今大学生の皆さんは、ちょうど30歳前後です。あなたはその時、どのような働き方をしていますか?
北大ではどこにある?
”2025年”に、今大学生の皆さんは、ちょうど30歳前後です。あなたはその時、どのような働き方をしていますか?
自分の親世代の常識から、働き方の常識が大きく変わってきています。大きく3つのシフトが予測されています。「食えるだけの仕事」から意味を感じる仕事へ。忙しいだけの仕事から価値ある経験としての仕事へ。勝つための仕事からともに生きるための仕事へ。
現在40代の私の世代でも、既にその変化は広がっています。
自然に見聞きする情報だけで将来を考えてはもったいない。未来への理解を深め、幸せに生きるための働き方に興味がある方はぜひ、読ん... [続きを読む] -
推薦者 : 髙橋 彩 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
仕事・生き方を模索するあなたに
聞き書緒方貞子回顧録 / 緒方貞子 [述] ; 野林健, 納家政嗣編. - 岩波書店, 2015
 北大ではどこにある?
本書をあえてキャリア支援の書として紹介したい。
北大ではどこにある?
本書をあえてキャリア支援の書として紹介したい。
国連難民高等弁務官として様々な難局に立ち向かった緒方貞子氏には数々の賞賛があろう。また、本書は国際政治学、外交史、国際関係論など、いくつかの分野で貴重な資料ともなろう。
しかし、ここでは緒方氏の人生が一人の人間と歩みとして描かれていることに注目したい。
心あるその人が、仕事の各局面で、何を考え、どのような意思を持って、どう行動したのか。分野や進路を問わず、今後、社会の未来とどう向き合っていくのかを、読者自身が問われているようだ。 -
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
フィールドワークと出産・育児の両立ノウハウ
女も男もフィールドへ / 椎野若菜, 的場澄人編. - 古今書院, 2016
 北大ではどこにある?
野生動物の研究、地球や環境科学の研究、言語学の研究、文化人類学の研究まで、調査対象を求めて世界各地に出かけるフィールドワークはたくさんあります。フィールドワークとと出産・育児って両立できるの?どうやって?という疑問に、様々な分野のフィールドワーカーが実例で答えてくれています。研究者の仕事に興味がある方、女性に不利(?)と思われがちな分野での仕事に興味がある方、ヒントがたくさん詰まっていますよ。
北大ではどこにある?
野生動物の研究、地球や環境科学の研究、言語学の研究、文化人類学の研究まで、調査対象を求めて世界各地に出かけるフィールドワークはたくさんあります。フィールドワークとと出産・育児って両立できるの?どうやって?という疑問に、様々な分野のフィールドワーカーが実例で答えてくれています。研究者の仕事に興味がある方、女性に不利(?)と思われがちな分野での仕事に興味がある方、ヒントがたくさん詰まっていますよ。 -
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
関西弁のゾウの神様に教わる人生で大事なこと
夢をかなえるゾウ / 水野敬也. - 飛鳥新社, 2011
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 小林 和也 (高等教育推進機構オープンエデュケーションセンター・職員)
生き方について考えることをやめて何らかの実験を生きるには
千のプラトー : 資本主義と分裂症 / ジル・ドゥルーズ, フェリックス・ガタリ [著] ; 宇野邦一 [ほか] 訳. - 河出書房新社, 1994
 北大ではどこにある?
生き方がわからないなんて不思議なお話だ。だって君は現に生きているのに? それでも問うてみたくなるのはなぜだろう。生きているのは苦しいし、悩みは耐えない。だからなぜこんなに苦労してまで生き続けなければならないの? どう生きればいい?と問いたくなるものだ。
北大ではどこにある?
生き方がわからないなんて不思議なお話だ。だって君は現に生きているのに? それでも問うてみたくなるのはなぜだろう。生きているのは苦しいし、悩みは耐えない。だからなぜこんなに苦労してまで生き続けなければならないの? どう生きればいい?と問いたくなるものだ。
こういう時はたいてい「生き方」なんていう言葉遣いが分析・分節されてつくしていないからだ。こういう乱暴な言葉遣いには気をつけたほうがいい。「生き方」が違うから分かり合えません。じゃあどうやって人とやっていくのさ?
言葉を分析するには、どうしたらいいだろう。こう考えることはで... [続きを読む] -
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
仕事の報酬は”収入・能力・仕事・成長”
仕事の報酬とは何か : 人間成長をめざして / 田坂広志. - PHP研究所, 2008
 北大ではどこにある?
「働かない人生なんてあり得ない?!」
北大ではどこにある?
「働かない人生なんてあり得ない?!」
「何のために働くのか?」という問いに、シンプルかつ本質的に答えています。
「仕事には、目に見える報酬と目に見えない報酬がある」仕事の報酬とは「収入・能力・仕事・成長」~気になった方は是非、読んでみてください。
仕事とはそもそも何なのか自分なりに答えを見つけたい方、将来仕事と子育て(家庭)の両立で悩むかも、、、と漠然と思っている方、おススメです。
働いて何年たって読み返しても、自分がその仕事をする目的やモチベーションを再確認することができる良本です。
-
推薦者 : 小林 和也 (高等教育推進機構オープンエデュケーションセンター・職員)
ゾーンへの招待
ストーカー / アルカジイ・ストルガツキー,ボリス・ストルガツキー著 ; 深見弾訳. - 早川書房, 1983
 北大ではどこにある?
アンドレイ・タルコフスキー監督による映画のほうが有名かもしれないが、この原作もまた偉大な文学作品だ。
北大ではどこにある?
アンドレイ・タルコフスキー監督による映画のほうが有名かもしれないが、この原作もまた偉大な文学作品だ。
本作は通常SFとされる。しかしそれだけではない。戦争や核汚染後の世界のメタファーとも言える突如現れた謎の危険地帯「ゾーン」。ストーカーはそこに侵入して、異星人が残したとされる異物を採取する。ストーカーとは何者であるのか? この問いに対する答えを、主人公レドリックの述懐に読み取ることができなければ、それはこの本との出会い損ね、悲しい接触と言わざるをえない。 -
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
女性を”交渉が苦手”にさせているメカニズムとは?
そのひとことが言えたら… : 働く女性のための統合的交渉術 / L.バブコック, S.ラシェーヴァー著 ; 森永康子訳. - 北大路書房, 2005
 北大ではどこにある?
女子学生の皆さんに質問です。
北大ではどこにある?
女子学生の皆さんに質問です。
「自分のほしいものを欲しいと言えますか?」
「自分にふさわしい評価を求めていますか?」?”
「パートナー(彼氏)に、フェアじゃないと思いつつ、何となく料理や家事を提供する側になっていませんか?」
それは「女性は自分の気持ちを抑えるように周囲から期待され、気づかないうちにその期待に沿うように行動してしまっている」場合があるからです。その仕組みを理解してはじめて「どうすればよいか?」「どのように言えば良いか?」How toが役に立ちます。
男子3人を育てている親として、女子も男子も「幸せなパートナーシップ」を築き... [続きを読む] -
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
社会は理不尽だ、、、それでも一歩踏み出そう!
Lean in (リーン・イン) : 女性、仕事、リーダーへの意欲 / シェリル・サンドバーグ著 ; 村井章子訳. - 日本経済新聞出版社, 2013
 北大ではどこにある?
ある社会的に成功した女性の個人の経験をもとにしていますが、その時に感じた「壁」について、様々な統計と理論から多面的に考察しています。社会には女性にとって理不尽なことがまだまだたくさんあります。何故、理不尽を感じるのか?その仕組みについても解説されています。ひとつひとつの理不尽に対して「それは不公正である」ことを社会に伝える努力と、理不尽な現実を前提として自分がどう考え行動していくか、個人の戦略としての努力のどちらも必要ですが、それらをバランス考えていくことが大事だ、ということが分かる内容です。
北大ではどこにある?
ある社会的に成功した女性の個人の経験をもとにしていますが、その時に感じた「壁」について、様々な統計と理論から多面的に考察しています。社会には女性にとって理不尽なことがまだまだたくさんあります。何故、理不尽を感じるのか?その仕組みについても解説されています。ひとつひとつの理不尽に対して「それは不公正である」ことを社会に伝える努力と、理不尽な現実を前提として自分がどう考え行動していくか、個人の戦略としての努力のどちらも必要ですが、それらをバランス考えていくことが大事だ、ということが分かる内容です。 -
推薦者 : 笹岡 正俊 (文学研究科・教員)
大学での「学び」で何を掴み取るのか
優秀なる羊たち : 米国エリート教育の失敗に学ぶ / ウィリアム・デレズウィッツ著 ; 米山裕子訳. - 三省堂, 2016年
 北大ではどこにある?
「社会というのはそれ自体が、真実から遠ざかり、それに触れまいとする陰謀だ。僕らは宣伝工先にどっぷりつかって一生を過ごす。―商品の広告、政治家の弁舌、現状を伝えるジャーナリズムの断言、大衆文化の陳腐な表現、当や会派やクラスの会則・・・(中略)・・・プラトンはこれをドクサ(注:推測に基づいた考え、見方)と呼んだ。その力は・・・(中略)・・・お構いなしに浸透していくほど強い。真の教育(リベラルアーツ教育)の第一の目的はこのドクサを認識し、疑問に感じ、それにとらわれずに考える術を教え、そこからわれわれを自由にすることなのである」
北大ではどこにある?
「社会というのはそれ自体が、真実から遠ざかり、それに触れまいとする陰謀だ。僕らは宣伝工先にどっぷりつかって一生を過ごす。―商品の広告、政治家の弁舌、現状を伝えるジャーナリズムの断言、大衆文化の陳腐な表現、当や会派やクラスの会則・・・(中略)・・・プラトンはこれをドクサ(注:推測に基づいた考え、見方)と呼んだ。その力は・・・(中略)・・・お構いなしに浸透していくほど強い。真の教育(リベラルアーツ教育)の第一の目的はこのドクサを認識し、疑問に感じ、それにとらわれずに考える術を教え、そこからわれわれを自由にすることなのである」
... [続きを読む] -
推薦者 : 池見 真由 (経済学研究科・教員)
今日の経済と社会と自分を見つめ直す
世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ / [ムヒカ述] ; くさばよしみ編 ; 中川学絵. - 汐文社, 2014
 北大ではどこにある?
「経済」とは元々、お金を儲けることや利潤を増やすことではなく、経世済民、つまり世の中をうまく経(おさ)めて民を救済する・幸せにすることが本来の意味だったと思います。
北大ではどこにある?
「経済」とは元々、お金を儲けることや利潤を増やすことではなく、経世済民、つまり世の中をうまく経(おさ)めて民を救済する・幸せにすることが本来の意味だったと思います。
あなたは、ホセ・ムヒカ氏の立ち振る舞いや言葉に感銘し、彼の考え方を理解し、共感できる人であるでしょうか?
そしてあなたは、現在の世界経済や国際社会のあり方に興味関心を向け、「こんなんじゃだめだ」と、自分のことのように危機感を感じられる人であるでしょうか?
もしそうであれば、あなたは私にとって見ず知らずの他人ですが、それでも、自分のことのようにとても嬉しいです。
こんな... [続きを読む] -
推薦者 : 伊藤 孝行 (メディア・コミュニケーション研究院・教員)
一文字も読まない日なんて,ほぼない(でしょ)。
「読む」技術 : 速読・精読・味読の力をつける / 石黒圭. - 光文社, 2010
 北大ではどこにある?
スマホで,読む。
北大ではどこにある?
スマホで,読む。
電車で,読む。
黒板やホワイトボードの字を,読む。
空気も,よむ。
うれしい日もかなしい日も,
晴れの日も雪の日も,
一文字も読まない日なんて,
ほぼない(でしょ)。
夢の中だって読んでいるかも。
読み方が増えれば,
もう少しだけ,つよくなれるかもしれない。 -
推薦者 : 種村 剛 (高等教育推進機構 科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP)・教員)
生き方のフォームをつくる
うらおもて人生録 / 色川武大. - 新潮社, 2014
 北大ではどこにある?
20数年前に大学生だった私は、麻雀に多くの時間を割いていました。そんなとき古本屋で『麻雀放浪記』(阿佐田哲也著)を見つけました。戦後の混乱期、博打で生きる人々の生き様が、筆者独特のリズムと文体で描かれていました。それに魅了された私は、阿佐田さんの書いた本を買い集め、読みふけりました。その過程で、阿佐田哲也(朝だ、徹夜)とは、色川武大さんのペンネームであることを知ったのでした。
北大ではどこにある?
20数年前に大学生だった私は、麻雀に多くの時間を割いていました。そんなとき古本屋で『麻雀放浪記』(阿佐田哲也著)を見つけました。戦後の混乱期、博打で生きる人々の生き様が、筆者独特のリズムと文体で描かれていました。それに魅了された私は、阿佐田さんの書いた本を買い集め、読みふけりました。その過程で、阿佐田哲也(朝だ、徹夜)とは、色川武大さんのペンネームであることを知ったのでした。
今回『うらおもて人生録』を推薦するにあたって、もう一度読み返してみました。この本の初出は1984年、今からもう30年以上になります。もうすっかり古びてしまっているの... [続きを読む] -
推薦者 : 佐々木 亨 (文学部・教員)
「修行とは矛盾に耐えること」とは、名言?、迷言?
赤めだか / 立川談春. - 扶桑社, 2015
 北大ではどこにある?
私がこの本に出会ったのは、つい最近です。それは、このところ落語に興味を持ってきたことに関係しています。著者の立川談春は、5年前に亡くなった立川談志の弟子です。
北大ではどこにある?
私がこの本に出会ったのは、つい最近です。それは、このところ落語に興味を持ってきたことに関係しています。著者の立川談春は、5年前に亡くなった立川談志の弟子です。
談志は、名言、迷言、暴言の多い落語家でした。名言としては、「修行とは矛盾に耐えることである」、「己が努力、行動を起こさずに対象となる人間の弱みを口であげつらって、自分のレベルまで下げる行為、これを嫉妬という」など、短い文で人間の行為の本質を的確に捉えたものが多いです。この本には、その談志の弟子である談春の修業時代からの苦労話が、たくさん詰まっています。
私は、もう一度... [続きを読む] -
推薦者 : 戸田 聡 (文学研究科・教員)
いかに生きるか ―附属図書館企画「少年よ、学部を選べ」に寄せて―
『余の尊敬する人物』 他 / 矢内原忠雄 他. - 岩波書店 他,
 北大ではどこにある?
学内の知らせで、「少年よ、学部を選べ」という附属図書館企画があることを知ったが、この文章の主たる対象読者は既に学部を選んでしまっている学生諸君であるだろう。とすれば、今さら「学部を選べ!」と言われても「は?」といった応答しか返ってこないであろうことは必至である。むしろやはり、「生き方を選べ!」とか(ちと高圧的か?)、「いかに生きるか?」といった見出しで書くほうが、どのみち同じ内容だとしても、まだしも受け入れられやすいのではなかろうか。
北大ではどこにある?
学内の知らせで、「少年よ、学部を選べ」という附属図書館企画があることを知ったが、この文章の主たる対象読者は既に学部を選んでしまっている学生諸君であるだろう。とすれば、今さら「学部を選べ!」と言われても「は?」といった応答しか返ってこないであろうことは必至である。むしろやはり、「生き方を選べ!」とか(ちと高圧的か?)、「いかに生きるか?」といった見出しで書くほうが、どのみち同じ内容だとしても、まだしも受け入れられやすいのではなかろうか。
などと書きはしたものの、自分の人生論をぶつことができるほど筆者(戸田)は老成しているとも... [続きを読む] -
推薦者 : 三上 直之 (高等教育推進機構・教員)
就職活動にやさしく効くクスリ
スコーレNo.4 / 宮下奈都. - 光文社, 2009
 北大ではどこにある?
よい成績で高校を卒業し、親もとを遠く離れた国立大学に進学した麻子は、3年になって就職活動を始めようとして戸惑った。もともと少し不器用なところのある麻子は、説明会やパンフレットで会社の様子を見聞きしても、そこで自分が働いている姿が想像できない。働きたくないのではない。どんな仕事が自分に向いているのか全然思いつかないのだ。結局、唯一得意だと思える英語を生かした仕事を、というあいまいな動機で輸入貿易商社をいくつか受け、幸い給料のよい大手に入ることができた。ところが入社後、ろくな研修もないまま靴屋に出向させられ、知識も興味もない靴の売り... [続きを読む]
北大ではどこにある?
よい成績で高校を卒業し、親もとを遠く離れた国立大学に進学した麻子は、3年になって就職活動を始めようとして戸惑った。もともと少し不器用なところのある麻子は、説明会やパンフレットで会社の様子を見聞きしても、そこで自分が働いている姿が想像できない。働きたくないのではない。どんな仕事が自分に向いているのか全然思いつかないのだ。結局、唯一得意だと思える英語を生かした仕事を、というあいまいな動機で輸入貿易商社をいくつか受け、幸い給料のよい大手に入ることができた。ところが入社後、ろくな研修もないまま靴屋に出向させられ、知識も興味もない靴の売り... [続きを読む] -
推薦者 : 駒川 智子 (教育学研究院・教員)
企業はブラックだけじゃない!
ホワイト企業 : 女性が本当に安心して働ける会社 / 経済産業省監修. - 文藝春秋, 2013
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 敷田 麻実 (高等教育推進機構・教員)
この難しい時代のグローバル化政策を学ぶ
「文化」を捉え直す : カルチュラル・セキュリティの発想 / 渡辺靖. - 岩波書店, 2015
 北大ではどこにある?
グローバリゼーションは、国際社会とは関係がない私たちの日常にも影響する。こちらの都合や好き嫌いにかかわらず、勝手に影響してくるのがグローバル化であって、自治体が意図して進めていく国際化とは大きな差がある。大学の近くの保育園には、異なる国々の子供たちが通う保育園をよく見かけるが、地域が好んでインターナショナルスクールを誘致したのではない。立地する大学の教職員、留学生の影響で結果的にそうなったのだ。
北大ではどこにある?
グローバリゼーションは、国際社会とは関係がない私たちの日常にも影響する。こちらの都合や好き嫌いにかかわらず、勝手に影響してくるのがグローバル化であって、自治体が意図して進めていく国際化とは大きな差がある。大学の近くの保育園には、異なる国々の子供たちが通う保育園をよく見かけるが、地域が好んでインターナショナルスクールを誘致したのではない。立地する大学の教職員、留学生の影響で結果的にそうなったのだ。
このようにグローバル化の中では、新しい文化が遠慮なく地域に入ってくる。しかしその一方で、固有の伝統文化の維持は難しくなってきてい... [続きを読む] -
推薦者 : 敷田 麻実 (高等教育推進機構・教員)
学ぶことを学べる本
学びとは何か : 「探究人」になるために / 今井むつみ. - 岩波書店, 2016
 北大ではどこにある?
大学を出たときが学びのピークで、それ以降は知識レベルが下がっていくだけという批判には三分の理を認めるが、それは学習や学びをなめてかかっている。本当は社会に出てからが学びの本番であり、答えのない問題を解くチャンスに日々恵まれる。学校を出たときが学力のピークだという考えは、教室でインプットした知識だけで社会が理解できるという誤解に基づいている。学びは重要である。大学では、膨大な資料を読み、それを知ったうえでの研究を求められる。そのため、知識を得ること、レクチャーされることが大学生活の中心となりがちである。しかし、本書を読めば、知る... [続きを読む]
北大ではどこにある?
大学を出たときが学びのピークで、それ以降は知識レベルが下がっていくだけという批判には三分の理を認めるが、それは学習や学びをなめてかかっている。本当は社会に出てからが学びの本番であり、答えのない問題を解くチャンスに日々恵まれる。学校を出たときが学力のピークだという考えは、教室でインプットした知識だけで社会が理解できるという誤解に基づいている。学びは重要である。大学では、膨大な資料を読み、それを知ったうえでの研究を求められる。そのため、知識を得ること、レクチャーされることが大学生活の中心となりがちである。しかし、本書を読めば、知る... [続きを読む] -
推薦者 : 敷田 麻実 (高等教育推進機構・教員)
君は、「面白い研究」をつまらなくプレゼンできないはずだ
勝率2割の仕事論 : ヒットは「臆病」から生まれる / 岡康道. - 光文社, 2016
 北大ではどこにある?
岡はクリエイティブディレクターであり、またコマーシャルを作成するプランナーの肩書きを持つ。大手の広告代理店に勤めた後、仲間と独立し「TUGBOAT(タグボート)」(広告代理店)の代表を努めている。その岡が本書で強調するのは、「仕事の勝率は2割でよい」ということではない。岡が、クライアントの要求を超えて、彼らが気づいていない隠れた意図を提案したり、メッセージ性の強い仕事をしていると、結果的に勝率は2割になってしまうということだ。
北大ではどこにある?
岡はクリエイティブディレクターであり、またコマーシャルを作成するプランナーの肩書きを持つ。大手の広告代理店に勤めた後、仲間と独立し「TUGBOAT(タグボート)」(広告代理店)の代表を努めている。その岡が本書で強調するのは、「仕事の勝率は2割でよい」ということではない。岡が、クライアントの要求を超えて、彼らが気づいていない隠れた意図を提案したり、メッセージ性の強い仕事をしていると、結果的に勝率は2割になってしまうということだ。
彼の仕事と研究者の仕事の共通点は、「人の金」を使って仕事をしていることである。彼らはクライアントの資金を使い... [続きを読む] -
推薦者 : 敷田 麻実 (高等教育推進機構・教員)
調査で「なぜ」と聞いてはいけない
途上国の人々との話し方 : 国際協力メタファシリテーションの手法 / 和田信明, 中田豊一著. - みずのわ出版, 2010
 北大ではどこにある?
本書の筆者である和田と中田は国際協力のベテランであり、アジアなどの途上国の現場で学んだこと、特に、相手の状態を理解する調査について、ていねいに解説している。相手を知ることの第一は観察であるが、その次は質問を介したコミュニケーションである。それは地域調査でのやり取りでも同じである。
北大ではどこにある?
本書の筆者である和田と中田は国際協力のベテランであり、アジアなどの途上国の現場で学んだこと、特に、相手の状態を理解する調査について、ていねいに解説している。相手を知ることの第一は観察であるが、その次は質問を介したコミュニケーションである。それは地域調査でのやり取りでも同じである。
彼らは「問題は何か」や「原因は何か」と相手に聞いてはいけないと述べる。例示された、医者は患者を前に「なんで熱があるのか?」と聞くのではなく、医者が聞くべきは「いつから熱が出たのか」という事実であるというアドバイスは、まったく当を得ている。考えを聞... [続きを読む] -
推薦者 : 天野 麻穂 (大学力強化推進本部 URAステーション・その他)
科学者を目指したいけれど、不安や悩みが尽きない学生さんへ
科学者の卵たちに贈る言葉 : 江上不二夫が伝えたかったこと / 笠井 献一. - 岩波書店, 2013年
 北大ではどこにある?
戦後日本の生命科学を牽引した一人である、江上不二夫先生にまつわるエピソードを、お弟子さんの笠井献一先生がエッセイとしてまとめた本です。
北大ではどこにある?
戦後日本の生命科学を牽引した一人である、江上不二夫先生にまつわるエピソードを、お弟子さんの笠井献一先生がエッセイとしてまとめた本です。
「研究」を「しごと」や「人生」に置き換えて読むこともできそうなので、科学者を目指す新入生はもちろん、どの道に進もうか、将来のことで悩んでいる大学院生や研究員の方にも、ぜひ薦めたい一冊です。
たとえば、世の中には「つまらない研究」なんて存在しない。本質的なものを見つけ出そう、という高い志をもっていれば、不可欠で立派な研究だから。大事なのは、自然を素直にみつめて、謙虚に接すること。
ある... [続きを読む] -
推薦者 : 多田 泰紘 (高等教育推進機構・職員)
フィールドワークで進化を「観察」する
フィンチの嘴 : ガラパゴスで起きている種の変貌 / ジョナサン ワイナー (著), 樋口 広芳 (翻訳), 黒沢 令子 (翻訳). - 早川書房, 1995年 初版
 北大ではどこにある?
本書は生物の進化を「観察」したその研究記録です。人間が進化を観察することは不可能と言われた中で,進化生物学者のグラント夫妻は20年にも及ぶ地道な現地調査で,ガラパゴス島のダーウィン・フィンチに起こった嘴(くちばし)の進化を観察しました。研究成果もさることながら,その研究姿勢こそフィールドワークの真髄と言えます。本書は進化論に興味がある人に限らず,野外でフィールドワークを行う皆さんにも読んでいただきたいと思います。
北大ではどこにある?
本書は生物の進化を「観察」したその研究記録です。人間が進化を観察することは不可能と言われた中で,進化生物学者のグラント夫妻は20年にも及ぶ地道な現地調査で,ガラパゴス島のダーウィン・フィンチに起こった嘴(くちばし)の進化を観察しました。研究成果もさることながら,その研究姿勢こそフィールドワークの真髄と言えます。本書は進化論に興味がある人に限らず,野外でフィールドワークを行う皆さんにも読んでいただきたいと思います。 -
推薦者 : 瀬名波 栄潤 (文学部・教員)
男性性研究の古典
男同士の絆 : イギリス文学とホモソーシャルな欲望(原タイトル:Between men) / イヴ・K・セジウィック. - 名古屋大学出版会, 1985年(原書)、2001年(翻訳)
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 瀬名波 栄潤 (文学部・教員)
21世紀の混沌を解く名著
ある学問の死 : 惑星思考の比較文学へ (原タイトル:Death of a discipline) / G. C. スピヴァク. - みすず書房, 2003年(原書)、2004年(翻訳)
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 瀬名波 栄潤 (文学部・教員)
クイア理論の古典
クローゼットの認識論 : セクシュアリティの20世紀(原タイトル:Epistemology of the closet) / イヴ・K・セジウィック. - 青土社, 1990年(原書)、1999年(翻訳)
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 橋本 努 (経済学研究科)
現代を代表する思想家のチャールズ・テイラーの最新書であり、英語の教材としても最適である。
The language animal : the full shape of the human linguistic capacity / Taylor, Charles. - Belknap Pr, 2016
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
登録日 : 2016-11-08
-
推薦者 : 堀田 尚徳 (法学研究科)
法学って何を勉強するの?と思っておられる方へ
キヨミズ准教授の法学入門 / 木村草太. - 株式会社星海社, 2012年
 北大ではどこにある?
本書は、「法学部に入って講義を受けてみたけれど、『法学』ってイマイチよく分からない」「他学部だけれど、法学部って何を勉強する所なんだろう」等と思っておられる方にオススメしたい本です。
北大ではどこにある?
本書は、「法学部に入って講義を受けてみたけれど、『法学』ってイマイチよく分からない」「他学部だけれど、法学部って何を勉強する所なんだろう」等と思っておられる方にオススメしたい本です。
どの学問でもそうだと思いますが、「法学」にも考え方の特徴があります。その特徴の要点について、物語風で読み手を飽きさせないように工夫しながら、しかも300頁に満たない分量で解説してくれている本です。例えば、法学系の講義を既に受けられた方は、法的三段論法という言葉に出会われたはずです。本書のChapter1を読んでみてください。講義の良い復習になると思います。... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「音楽」に対する屈折した思い
ピアニストのノート / ヴァレリー・アファナシエフ. - 講談社, 2012
 北大ではどこにある?
著者のアファナシエフの演奏を学生時代に聴いたことがある。山田一雄指揮の東京都交響楽団定期演奏会でシューマンの「ピアノ協奏曲」だった。なぜそんな昔のことを覚えているかというと、その時初めて聴いたアファナシエフの演奏が非常に“奇妙”だったからである。「違和感」というのでもない、「斬新」というのでもない、ただ、「こんなふうにシューマンも弾けるんだ」という感覚を抱いたことを今でも覚えている。その後、彼のプロフィールなどを知る機会もあったが、この本を読んでみて昔聴いた演奏とどこか重なり合うような感覚を思い出すことができた。この本は、エッ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
著者のアファナシエフの演奏を学生時代に聴いたことがある。山田一雄指揮の東京都交響楽団定期演奏会でシューマンの「ピアノ協奏曲」だった。なぜそんな昔のことを覚えているかというと、その時初めて聴いたアファナシエフの演奏が非常に“奇妙”だったからである。「違和感」というのでもない、「斬新」というのでもない、ただ、「こんなふうにシューマンも弾けるんだ」という感覚を抱いたことを今でも覚えている。その後、彼のプロフィールなどを知る機会もあったが、この本を読んでみて昔聴いた演奏とどこか重なり合うような感覚を思い出すことができた。この本は、エッ... [続きを読む]