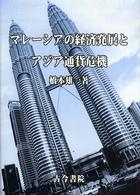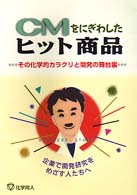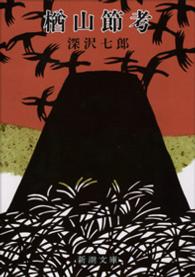-
推薦者 : 橋本 雄一 (文学研究科)
地理と経済をアジアで学ぶ
マレーシアの経済発展とアジア通貨危機 / 橋本雄一著. - 古今書院, 2005.10
 北大ではどこにある?
将来いかなる分野に進もうと,現代社会に生きる者として経済・金融の基礎知識は必須です。本書はマレーシアと日本の経済的関係を中心として書かれた地理学の入門本であるが,経済・空間・技術・知的所有権などに関する基礎知識を学ぶのに適している。
北大ではどこにある?
将来いかなる分野に進もうと,現代社会に生きる者として経済・金融の基礎知識は必須です。本書はマレーシアと日本の経済的関係を中心として書かれた地理学の入門本であるが,経済・空間・技術・知的所有権などに関する基礎知識を学ぶのに適している。 -
推薦者 : 河野 敬一 (理学研究科)
君の未来は全てDNAによって決まっていると思いますか?
遺伝子と運命 : 夢と悪夢の分岐点 / ピーター・リトル著 ; 美宅成樹訳. - 講談社, 2004.12
 北大ではどこにある?
人のゲノムの全配列が決まりました。クローン人間を作ることも技術的には可能です。病気になりやすさを決める遺伝子、性格を決める遺伝子、いろいろなものが次々発見されています。君という人間はDNAで全て決まっているのでしょうか?努力しても無駄なのでしょうか?この本では、分子遺伝学者である著者が難解な専門用語を使わず、これらの疑問に答えてくれます。未来における架空の二人の女性の全く異なる運命をSF調に描くことから始まり、私たちの遺伝子と運命の関係を科学的に解き明かしてくれる異色の読み物です。
北大ではどこにある?
人のゲノムの全配列が決まりました。クローン人間を作ることも技術的には可能です。病気になりやすさを決める遺伝子、性格を決める遺伝子、いろいろなものが次々発見されています。君という人間はDNAで全て決まっているのでしょうか?努力しても無駄なのでしょうか?この本では、分子遺伝学者である著者が難解な専門用語を使わず、これらの疑問に答えてくれます。未来における架空の二人の女性の全く異なる運命をSF調に描くことから始まり、私たちの遺伝子と運命の関係を科学的に解き明かしてくれる異色の読み物です。
目次
1.夢と悪夢
2.なぜヒトはみな違って... [続きを読む] -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
世界を知るには自分を知ろう――日本の文化のDNAを知る最良の書
二重言語国家・日本 / 石川九楊著. - 日本放送出版協会, 1999.5
 北大ではどこにある?
著者は書道家として知られる一方、文字を通じ、われわれの日本文化(漢字・かな文化)について、中国文明(漢字文明圏)、ヨーロッパ文明(アルファベット文字文明圏)など世界全体の文明構造の中から解き明かす著作と論考を数多く発表しており、本書はその代表作。われわれが何気なく使っている漢字、かな、そして明治以降のアルファベットを通して、われわれの歴史、文化、ものの考え方の特徴が、それこそ目からウロコが落ちるように見えてくる。のみならず、現在の米中、日中関係すらも透けて見えてくるのは著者の思索の深さゆえか。同著者の『
北大ではどこにある?
著者は書道家として知られる一方、文字を通じ、われわれの日本文化(漢字・かな文化)について、中国文明(漢字文明圏)、ヨーロッパ文明(アルファベット文字文明圏)など世界全体の文明構造の中から解き明かす著作と論考を数多く発表しており、本書はその代表作。われわれが何気なく使っている漢字、かな、そして明治以降のアルファベットを通して、われわれの歴史、文化、ものの考え方の特徴が、それこそ目からウロコが落ちるように見えてくる。のみならず、現在の米中、日中関係すらも透けて見えてくるのは著者の思索の深さゆえか。同著者の『 -
推薦者 : 山本 興太朗 (理学研究科)
Biology of plants / Peter H. Raven, Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn. - W. H. Freeman and Company : Worth Publishers, c1999
 北大ではどこにある?
この本は植物科学全般を扱った教科書で、分子レベルの植物の機能の話から生態学、分類学まで扱われている。そういう総合的な教科書としては今のところ世界で最良のものであろう。残念なことに英語で書かれているのでこれを通読するわけにはいかないが、この本の優れた点はカラーの図と写真が豊富にあることなので、それを眺めるだけで十分利用価値がある。
北大ではどこにある?
この本は植物科学全般を扱った教科書で、分子レベルの植物の機能の話から生態学、分類学まで扱われている。そういう総合的な教科書としては今のところ世界で最良のものであろう。残念なことに英語で書かれているのでこれを通読するわけにはいかないが、この本の優れた点はカラーの図と写真が豊富にあることなので、それを眺めるだけで十分利用価値がある。
植物科学の個別の分野の教科書は図書館にも多数あるが、みんな白黒の図版しかない。そういう教科書を読んだ後でこの本を開き、該当個所の写真だけ見るという使い方も非常に有効だろう。植物の形を白黒で見るか... [続きを読む]登録日 : 2005-08-02
-
推薦者 : 山下 正兼 (理学研究科)
生殖細胞 : 形態から分子へ / 岡田益吉, 長濱嘉孝編著. - 共立出版, 1996.4
 北大ではどこにある?
我々ヒトも含め、多くの多細胞生物の一生は卵と精子が合体(受精)することから始まる。卵や精子は生殖細胞と呼ばれる。生物を形づくる多くの細胞(体細胞)が、個体そのものを維持するために働くのに対し、生殖細胞は生 命を次世代に受け渡すために働く。卵や精子は高度に特殊化(分化)した細胞だが、ある意味では未分化なままで止まっている(あらゆる種類の細胞になりうる能力を持つ )細胞でもある。
北大ではどこにある?
我々ヒトも含め、多くの多細胞生物の一生は卵と精子が合体(受精)することから始まる。卵や精子は生殖細胞と呼ばれる。生物を形づくる多くの細胞(体細胞)が、個体そのものを維持するために働くのに対し、生殖細胞は生 命を次世代に受け渡すために働く。卵や精子は高度に特殊化(分化)した細胞だが、ある意味では未分化なままで止まっている(あらゆる種類の細胞になりうる能力を持つ )細胞でもある。
このように、生殖細胞は「分化した未分化細胞」という一見矛盾する性質をもつ不思議な存在であるが、このおかげで生物は限られた個 体の寿命を越え、種を存続さ... [続きを読む]登録日 : 2005-08-02
-
推薦者 : 宮浦 憲夫 (工学研究科)
CMをにぎわしたヒット商品 : その化学的カラクリと開発の舞台裏 : 企業で開発研究をめざす人たちへ / 『化学』編集部編集. - 化学同人, 1997.6
 北大ではどこにある?
CMヒット商品を生み出した舞台裏とその化学的からくりを解説している。日頃何気なく手にしている商品の開発物語を通して化学のおもしろさが実感でき、また企業における研究がどのようなものであるかが手に取るように解る。
北大ではどこにある?
CMヒット商品を生み出した舞台裏とその化学的からくりを解説している。日頃何気なく手にしている商品の開発物語を通して化学のおもしろさが実感でき、また企業における研究がどのようなものであるかが手に取るように解る。登録日 : 2005-08-02
-
推薦者 : 吉野 悦雄 (経済学研究科)
楢山節考 / 深沢七郎著. - 新潮社, 1987.11
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
登録日 : 2005-08-02
-
推薦者 : 樽本 英樹 (文学研究科)
国際社会学 : 国家を超える現象をどうとらえるか / 梶田孝道編. - 名古屋大学出版会, 1996.4
 北大ではどこにある?
国民国家システムというグローバルな構造が変動し、様々な側面から「国際化」が生じている。それに伴い、「社会」を社会現象の分析 枠組とすることに疑問符がつけられるようになった。ではどのような問題にどのようなアプローチを行えばよいのか。
北大ではどこにある?
国民国家システムというグローバルな構造が変動し、様々な側面から「国際化」が生じている。それに伴い、「社会」を社会現象の分析 枠組とすることに疑問符がつけられるようになった。ではどのような問題にどのようなアプローチを行えばよいのか。
この疑問に「国際社会学」という立場で答えようとしているのが本書である。トランスナショナルな主体、グローバライゼイション、エスニシティ、ナショナリズム、人の国際移動等のテーマを掲げながら、「国際社会学」という新たな分野を開拓しようとしている意欲作である。登録日 : 2005-08-02
-
推薦者 : 吉野 悦雄 (経済学研究科)
草の花 / 福永武彦著. - 新潮社, 1967
 北大ではどこにある?
「福永武彦全集第2巻」(北大所蔵2)および新潮文庫(北大所蔵1)および「昭和文学全集第23巻」(北大所蔵3)に収録されています。
北大ではどこにある?
「福永武彦全集第2巻」(北大所蔵2)および新潮文庫(北大所蔵1)および「昭和文学全集第23巻」(北大所蔵3)に収録されています。
内容については読んでください。中編小説です。
大学1年のときの英語経済書演習の時間に,加藤栄一教授は,授業とは無関係に「雪の中尊寺は良い」とつぶやきました。その年の冬,仙台地方に初雪が降った朝,思い立って汽車に乗りました。観光客のいない境内を散策し,旧国鉄の平泉駅で帰りの汽車を1時間ほど待つことになりました。
駅前に書店兼文房具店兼食堂という店があり,その店の書棚にあった『草の花』という文庫... [続きを読む]登録日 : 2005-08-02
-
推薦者 : 山崎 健一 (地球環境科学研究院)
生物学の教科書の中では、最高の物
細胞の分子生物学 / Bruce Alberts [ほか] 著 ; 中村桂子, 松原謙一監訳. - ニュートンプレス, 2004.12
 北大ではどこにある?
私が今までに出会った生物学の教科書の中では、最高の物である。版を重ねるごとに最新の情報を考慮に入れながら書き換えているだけでなく、生物学における重要な概念を出来るだけ分かりやすく解説しているので、読者を飽きさせない。
北大ではどこにある?
私が今までに出会った生物学の教科書の中では、最高の物である。版を重ねるごとに最新の情報を考慮に入れながら書き換えているだけでなく、生物学における重要な概念を出来るだけ分かりやすく解説しているので、読者を飽きさせない。
1300ページに及ぶ量には圧倒されるが、1ページ目から順に読む必要はない。パラパラページをめくって興味をそそられた図を見て読み始めればよい。
大切なのは自分の興味を引き出すことである。一度読み始めさえすれば、結局全部読みたくなる。本書は英語版が出ているが、大学院生以下の若い学生諸君には薦めません。英語版を読んで書かれてい... [続きを読む]登録日 : 2005-08-02
-
推薦者 : 神保 秀一 (理学研究科)
カオス入門 / 山口昌哉著. - 朝倉書店, 1996.9
 北大ではどこにある?
高校や大学の多くの学生の諸君は数学(数学現象)の世界は,実際に宇宙で起こる自然現象たちに較べて,非常に整備されていて,整然としているという印象をもっているのではないであろうか。
北大ではどこにある?
高校や大学の多くの学生の諸君は数学(数学現象)の世界は,実際に宇宙で起こる自然現象たちに較べて,非常に整備されていて,整然としているという印象をもっているのではないであろうか。
期末試験や大学入試の数学の問題はきちんときれいな正解が用意されていて,いつも何事もちゃんとできているので,このような硬質で 無機質なイメージをもつのだと思う。また,そもそも数学の扱う対象は自然現象とはあまり関係ないとさえ思っている人も多いようです。しかし,実際は,それらはいろいろな局面において密接に関連していて,宇宙の現象が複雑であると同様に数学に... [続きを読む]登録日 : 2005-08-02
-
推薦者 : 宮浦 憲夫 (工学研究科)
ボルハルト・ショアー現代有機化学 / K.P.C. Vollhardt, N.E. Schore [著] ; 大嶌幸一郎 [ほか] 訳. - 化学同人, 2004
 北大ではどこにある?
最新の有機化学の方向性を把握した上で、それに関連する基礎的内容について懇切丁寧に解説されている。重要なポイントを強調しながら議論が展開されており、多色刷りの効果も加わり、有機反応の系統的な理解を助けている。
北大ではどこにある?
最新の有機化学の方向性を把握した上で、それに関連する基礎的内容について懇切丁寧に解説されている。重要なポイントを強調しながら議論が展開されており、多色刷りの効果も加わり、有機反応の系統的な理解を助けている。
(上)有機分子の構造と結合/アルカンの反応/立体異性体/ハロアルカンの反応/アルコ−ルの反応とエ−テルの化学/NMRによる構造決定 /アルケンの反応アルキン/他
(下)環状セクステット電子系の特別な安定性/ベンゼン誘導体への求電子攻撃アルデヒドとケトン/エノ−ルとエノン/カルボン酸誘導 体と質量分析法/炭水物/他の解説
登録日 : 2005-08-02
-
推薦者 : 宮浦 憲夫 (工学研究科)
あなたも狙え!ノーベル賞 : 科学者99人の受賞物語 / 石田寅夫著. - 化学同人, 1995.10
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
登録日 : 2005-08-02
-
推薦者 : 吉野 悦雄 (経済学研究科)
年の残り / 丸谷才一著. - 文芸春秋, 1968
 北大ではどこにある?
内容については読んでください。短編小説です。
北大ではどこにある?
内容については読んでください。短編小説です。
北海道大学でも,学部一貫教育が始まり,授業科目にも新しい試みが導入されました。
そのひとつに論文指導(講義)というものがあります。しかしわたしの学生時代には,そんな親切な授業などはありませんでした。わたしは,この小説を声に出して読み,一部はノートに書き写すようにして正しい日本語を書く練習をしました。
上述の福永武彦氏が美しい日本語についての感性を生来持ち合わせていたのに対して,丸谷才一氏にはそれがなく,努力と訓練と工夫に よって正しい日本語が書けるようになったのではないでしょ... [続きを読む]登録日 : 2005-08-02
-
推薦者 : 山下 正兼 (理学研究科)
発生生物学 : 分子から形態進化まで / スコット F.ギルバート著 ; 塩川光一郎〔ほか〕訳. - トッパン, 1991.1-3
 北大ではどこにある?
近年における生物学の発展はめざましいものがある。急速に発達した分子生物学的手法により、生命現象を分子の相互作用として捉え、その根本原理を物理・化学反応の言葉で明らかにする ことが可能になった。 特に最近は、生物の発生や脳の機能といった複雑な系でも分子レベルの解析が進められており、発生生物学や神経生物学は今、最も脚光を浴びている自然科学分野の一つである。
北大ではどこにある?
近年における生物学の発展はめざましいものがある。急速に発達した分子生物学的手法により、生命現象を分子の相互作用として捉え、その根本原理を物理・化学反応の言葉で明らかにする ことが可能になった。 特に最近は、生物の発生や脳の機能といった複雑な系でも分子レベルの解析が進められており、発生生物学や神経生物学は今、最も脚光を浴びている自然科学分野の一つである。
本書は現代の発生生物学におけるバイブルと呼べるもので、発生生物学を志す学生には必読の書である。また、それ以外の自然科学を志す学生にとっても本書から得るものは多いと思われる。
... [続きを読む]登録日 : 2005-08-02
-
推薦者 : 小泉 格 (総合博物館)
新しい気候の科学 / トマス・レヴェンソン著 ; 原田朗訳. - 晶文社, 1995.8
 北大ではどこにある?
この本は、[Ice Time- Climate, Science, and Life on Earth] Harper & Row 1989 (「氷の時代ー気候、科学そして地球の生命」)の全訳である。
北大ではどこにある?
この本は、[Ice Time- Climate, Science, and Life on Earth] Harper & Row 1989 (「氷の時代ー気候、科学そして地球の生命」)の全訳である。
私たちは,間氷期にあっても高緯度域が氷河に覆われている,氷の時代に生きているのだという環境設定から始って,気候科学とはどんな科学か,私たちの社会とどうかかわっているか,気候科学が担っている使命とはなにかなどについて述べている。
この本では,気候を非常の長い時間スケ−ルでとらえ,それから次第に近くに焦点をあわせ,現在の天気が,地球という星の形成や大昔から続いてきた天候という仕組みの機能(システム)とどのように関連して... [続きを読む]登録日 : 2005-07-29
-
推薦者 : 小泉 格 (総合博物館)
気候変動論 (岩波講座地球惑星科学 ; 11) / 住明正 [ほか]著. - 岩波書店, 1996.9
 北大ではどこにある?
地球の表層環境を形成している「気候システム」は,大気,海洋,雪氷,土壌,植生などの様々なサブシステムから構成される総合的なシステムであるので,気候システムんの変動をよく理解するためには,様々なサブシステム間の相互作用とフィ−ドバックによる気候システム全体の変動を理解することが必要になる。また,気候システムの変動には,様々な時間スケ−ルの現象が含まれており,それらが相互に関連しあっている。
北大ではどこにある?
地球の表層環境を形成している「気候システム」は,大気,海洋,雪氷,土壌,植生などの様々なサブシステムから構成される総合的なシステムであるので,気候システムんの変動をよく理解するためには,様々なサブシステム間の相互作用とフィ−ドバックによる気候システム全体の変動を理解することが必要になる。また,気候システムの変動には,様々な時間スケ−ルの現象が含まれており,それらが相互に関連しあっている。
この本では,気候システムの変動を時間スケ−ルの短い変動から長い変動までエルニ−ニョが,気候システムの変動として最大限度に近 い変動の振幅を... [続きを読む]登録日 : 2005-07-29
-
推薦者 : 小泉 格 (総合博物館)
深海底の科学 : 日本列島を潜ってみれば (NHKブックス;814) / 藤岡換太郎著. - 日本放送出版協会, 1997.11
 北大ではどこにある?
表記の「NHKブックス814」は、一つ一つの話題が要領よくまとめられているので、どこから読んでも良いところが特徴と言える。
北大ではどこにある?
表記の「NHKブックス814」は、一つ一つの話題が要領よくまとめられているので、どこから読んでも良いところが特徴と言える。
骨子となる六章は組み立てが良く考えられていて、
序章 地球の見方−潜水調査船科学への招待
第一章 地球科学の基礎知識−動かざること大地の如し
第二章 深海から見た東日本列島−ふるいプレ−トの沈み込むところ
第三章 深海から見た西日本列島−若いプレ−トが沈み込むところ
第四章 海の後ろに海がある−日本海の背弧海盆に潜る
第五章 日本列島周辺のプレ−トの境界
終章 深海探査に何ができるか−環境・災害・資源
... [続きを読む]登録日 : 2005-07-29
-
推薦者 : 加納 邦光 (メディア・コミュニケーション研究院)
ビスマルク伝 / エーリッヒ・アイク著 ; 救仁郷繁訳. - ぺりかん社, 1993.6-1999.6
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
登録日 : 2005-07-29
-
推薦者 : 神谷 忠孝 (文学研究科)
梅桃が実るとき / 吉行あぐり著. - 文園社, 1985.12
 北大ではどこにある?
平成九年にNHKで放送された連続テレビドラマ「あぐり」は90歳になっても現役の美容師として働く吉行あぐりの本を題材にしています。3人の子供のうち淳之介、理恵は兄妹で芥川賞を受賞し、和子は女優として活躍しています。テレビのブームによってあぐりの夫である吉行エイスケという作家にも光があたりました。
北大ではどこにある?
平成九年にNHKで放送された連続テレビドラマ「あぐり」は90歳になっても現役の美容師として働く吉行あぐりの本を題材にしています。3人の子供のうち淳之介、理恵は兄妹で芥川賞を受賞し、和子は女優として活躍しています。テレビのブームによってあぐりの夫である吉行エイスケという作家にも光があたりました。
昭和15年に34歳で亡くなったエイスケは川端康成、林芙美子、梶井基次郎、牧野信一、伊藤整、坂口安吾、武田麟太郎、辻潤などとともに1920年代に活躍した作家です。
私が昭和52年に「登録日 : 2005-07-29