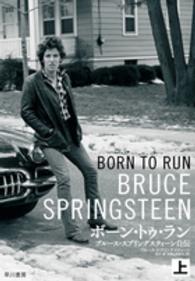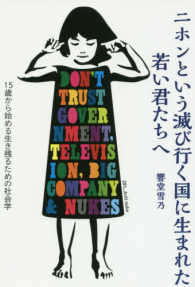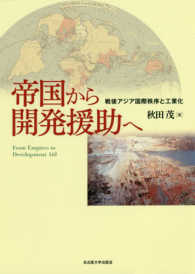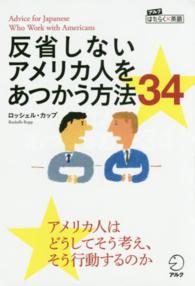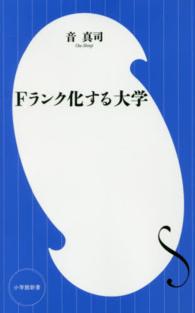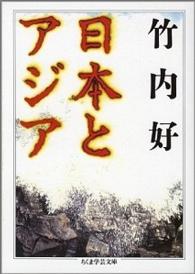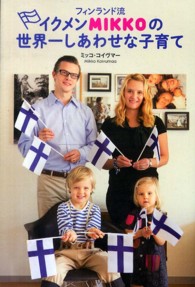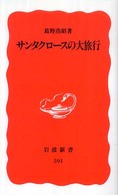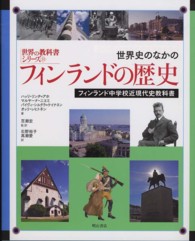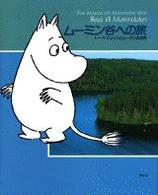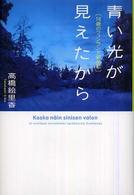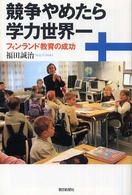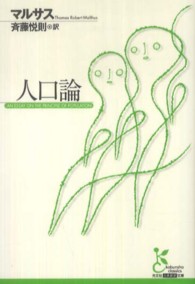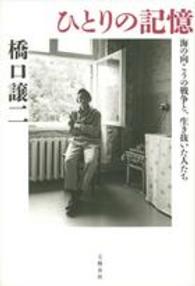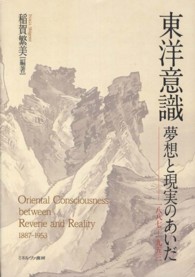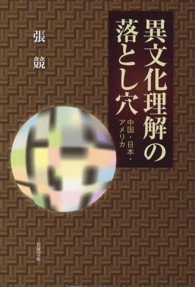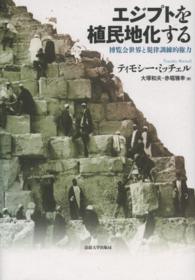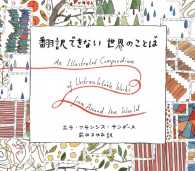-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
アメリカに生まれて生きる、とは
ボーン・トゥ・ラン : ブルース・スプリングスティーン自伝 / ブルース・スプリングスティーン著 ; 鈴木恵, 加賀山卓朗他訳. - 早川書房, 2016
 北大ではどこにある?
“ボス”と呼ばれるアメリカのロックンロール・ミュージシャン、ブルース・スプリングスティーンが7年をかけて執筆した自伝である。この本から彼の音楽に対する姿勢を窺えるのは当然だが、それ以上にアメリカ東海岸の労働者階級の家庭にアイルランド系、イタリア系、オランダ系という様々な血脈を受けて生まれ育ったスプリングスティーンが自分の出自を絶えず意識しながら音楽を作り演奏していく姿は、日本人のかなりの部分=日本(ヤマト)民族という出自を普段意識することのない存在には、強い印象を与えるであろう。彼の音楽が好きな人だけでなく、帰属意識(カタカナ言... [続きを読む]
北大ではどこにある?
“ボス”と呼ばれるアメリカのロックンロール・ミュージシャン、ブルース・スプリングスティーンが7年をかけて執筆した自伝である。この本から彼の音楽に対する姿勢を窺えるのは当然だが、それ以上にアメリカ東海岸の労働者階級の家庭にアイルランド系、イタリア系、オランダ系という様々な血脈を受けて生まれ育ったスプリングスティーンが自分の出自を絶えず意識しながら音楽を作り演奏していく姿は、日本人のかなりの部分=日本(ヤマト)民族という出自を普段意識することのない存在には、強い印象を与えるであろう。彼の音楽が好きな人だけでなく、帰属意識(カタカナ言... [続きを読む] -
推薦者 : 今井 一郎 (水産科学研究院・教員)
ニホンという滅び行く国に生まれた若い君たちへ送る言葉
ニホンという滅び行く国に生まれた若い君たちへ : 15歳から始める生き残るための社会学 / 響堂雪乃著. - 白馬社, 2017
 北大ではどこにある?
かつては「陰謀論」あるいは「都市伝説」と言われて一笑に付される様な一見荒唐無稽とも思える事項が,実は真実の場合がある。アメリカ同時多発テロ事件は,陰謀論の最たるものと言われて来た。しかし,死の床にあった元 CIA 局員、マルコム・ハワード氏は、ビル等の破壊に関する経歴や技術を持っていたことから、ニューヨークの世界貿易センタービルの破壊プロジェクトを CIA の幹部から強要されたとの内容を告白した。この事から,同時多発テロ事件は CIA の実行した,アメリカ政府による自作自演のテロである事がつい先日(2017年7月13日)判明した。この事件はアルカイダによる... [続きを読む]
北大ではどこにある?
かつては「陰謀論」あるいは「都市伝説」と言われて一笑に付される様な一見荒唐無稽とも思える事項が,実は真実の場合がある。アメリカ同時多発テロ事件は,陰謀論の最たるものと言われて来た。しかし,死の床にあった元 CIA 局員、マルコム・ハワード氏は、ビル等の破壊に関する経歴や技術を持っていたことから、ニューヨークの世界貿易センタービルの破壊プロジェクトを CIA の幹部から強要されたとの内容を告白した。この事から,同時多発テロ事件は CIA の実行した,アメリカ政府による自作自演のテロである事がつい先日(2017年7月13日)判明した。この事件はアルカイダによる... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
国際関係を複眼的に解きほぐす
大英帝国の親日派 : なぜ開戦は避けられなかったか / アントニー・ベスト著 ; 武田知己訳. - 中央公論新社, 2015
 北大ではどこにある?
国際関係、分けても戦時期の国際関係を理解することは容易ではない。この本は、日英の政治家(外交官)に対象を絞り、それぞれの言説と行動を分析しつつ第二次大戦期の日英関係を解明しようとするものである。その際、直接の対象である日英関係の背後にあって大きな影響を及ぼしていた日中、英中、英米、英露の国際関係にも目を配り、当時の国際関係が複眼的に理解できるようになっている点が特徴である。国際関係論や政治学のみならず、歴史記述の方法についても学ぶところの多い本である。
北大ではどこにある?
国際関係、分けても戦時期の国際関係を理解することは容易ではない。この本は、日英の政治家(外交官)に対象を絞り、それぞれの言説と行動を分析しつつ第二次大戦期の日英関係を解明しようとするものである。その際、直接の対象である日英関係の背後にあって大きな影響を及ぼしていた日中、英中、英米、英露の国際関係にも目を配り、当時の国際関係が複眼的に理解できるようになっている点が特徴である。国際関係論や政治学のみならず、歴史記述の方法についても学ぶところの多い本である。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
哲学を体現した人の生涯
ウィトゲンシュタイン : 天才哲学者の思い出 / ノーマン・マルコム著 ; 板坂元訳. - 平凡社, 1998
 北大ではどこにある?
20世紀以降の哲学に最も影響力のあった哲学者ウィトゲンシュタインに親しく接した著者が、その人柄、哲学に対する姿勢、同時代人との関わりからゼミナールの雰囲気までを生き生きと描いた人物伝である。ウィトゲンシュタインの哲学に関心がなくても、哲学者という人びとが自分の思索にどのような姿勢で臨んでいるかを知る上で一読の価値がある。
北大ではどこにある?
20世紀以降の哲学に最も影響力のあった哲学者ウィトゲンシュタインに親しく接した著者が、その人柄、哲学に対する姿勢、同時代人との関わりからゼミナールの雰囲気までを生き生きと描いた人物伝である。ウィトゲンシュタインの哲学に関心がなくても、哲学者という人びとが自分の思索にどのような姿勢で臨んでいるかを知る上で一読の価値がある。 -
推薦者 : 前田 亮介 (法学研究科・教員)
政治経済史の画期的業績
帝国から開発援助へ : 戦後アジア国際秩序と工業化 / 秋田茂著. - 名古屋大学出版会, 2017
 北大ではどこにある?
第二次世界大戦後のアジア諸国の経済的台頭を可能にした条件の一端を、コロンボ・プランをはじめとするイギリス主導の戦後国際秩序構想から明らかにしようとした、政治経済史の画期的業績である。著者がイギリス帝国史の第一人者ということもあり、コモンウェルス体制の維持・再編に向けた戦後イギリスの生存戦略が、旧帝国からの旧植民地への所得移転や開発援助を通じて、アジア諸国の脱植民地化と(多くが開発独裁的な形態での)国家形成を後押ししていくなかば逆説的な力学が、英米のみならずインドの文書館史料も利用して興味深く分析されている。帝国秩序における戦前... [続きを読む]
北大ではどこにある?
第二次世界大戦後のアジア諸国の経済的台頭を可能にした条件の一端を、コロンボ・プランをはじめとするイギリス主導の戦後国際秩序構想から明らかにしようとした、政治経済史の画期的業績である。著者がイギリス帝国史の第一人者ということもあり、コモンウェルス体制の維持・再編に向けた戦後イギリスの生存戦略が、旧帝国からの旧植民地への所得移転や開発援助を通じて、アジア諸国の脱植民地化と(多くが開発独裁的な形態での)国家形成を後押ししていくなかば逆説的な力学が、英米のみならずインドの文書館史料も利用して興味深く分析されている。帝国秩序における戦前... [続きを読む]登録日 : 2017-08-07
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
君は世界をまたにかけるビジネスパースンになれるか?
反省しないアメリカ人をあつかう方法34 / ロッシェル・カップ著. - アルク, 2015
 北大ではどこにある?
北大生の中には将来外資系企業、あるいは海外で働くことを希望している人もいるだろう。また、国内の職場でも上司や同僚や部下が外国人という環境は最早珍しくない。この本は、「反省しないアメリカ人を~」と書いてあるとおり、アメリカ人の、主に従業員に対してどう接し、どのように良好なビジネス上の関係を構築するかについてアドバイスを述べたものであるが、アメリカ人に限らず異なる文化的背景の人間―日本人でもその範疇に入ってくる可能性は大いにある―と仕事をする上でヒントになるものと思う。比較文化研究や異文化間コミュニケーションに関心のある人には、色... [続きを読む]
北大ではどこにある?
北大生の中には将来外資系企業、あるいは海外で働くことを希望している人もいるだろう。また、国内の職場でも上司や同僚や部下が外国人という環境は最早珍しくない。この本は、「反省しないアメリカ人を~」と書いてあるとおり、アメリカ人の、主に従業員に対してどう接し、どのように良好なビジネス上の関係を構築するかについてアドバイスを述べたものであるが、アメリカ人に限らず異なる文化的背景の人間―日本人でもその範疇に入ってくる可能性は大いにある―と仕事をする上でヒントになるものと思う。比較文化研究や異文化間コミュニケーションに関心のある人には、色... [続きを読む]登録日 : 2017-08-07
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
やっぱり大学の未来は心配だ。
Fランク化する大学 / 音真司著. - 小学館, 2016
 北大ではどこにある?
この本を「本は脳を育てる」に推薦することに対して旧帝国大学である“天下の北海道大学”の真面目な先生や優秀な学生から異論や批判が巻き起こるかもしれない。筆者自身も、この本に書いてあることは100%そのままであるとは思いたくないし、著者がやや大げさに書いている=「話を盛っている」面もあるかもしれないと思っている。しかし、他大学につとめる友人知人の現場の声を聞くと、ここに書いてあることを頭ごなしに否定することもできないと思う。そして、筆者自身が何より恐れるのは、―ここまでひどくないとしても―これらに近似する状況がここ数年の間に静かに北海道... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本を「本は脳を育てる」に推薦することに対して旧帝国大学である“天下の北海道大学”の真面目な先生や優秀な学生から異論や批判が巻き起こるかもしれない。筆者自身も、この本に書いてあることは100%そのままであるとは思いたくないし、著者がやや大げさに書いている=「話を盛っている」面もあるかもしれないと思っている。しかし、他大学につとめる友人知人の現場の声を聞くと、ここに書いてあることを頭ごなしに否定することもできないと思う。そして、筆者自身が何より恐れるのは、―ここまでひどくないとしても―これらに近似する状況がここ数年の間に静かに北海道... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「知の巨人」たちはいかに思索したか
柳田国男と梅棹忠夫 : 自前の学問を求めて / 伊藤幹治著. - 岩波書店, 2011
 北大ではどこにある?
先に竹内好の『日本とアジア』をこの「本は脳を育てる」に推薦したが、その中で竹内好がしばしば言及している一人が梅棹忠夫である。日本の知識人―という言い方を梅棹は嫌うだろうが―のアジア理解、文明観を問題にする上で避けて通れないと竹内は感じ取ったのだろう。その梅棹の知的営為を、先行する柳田国男のそれと対比的に考察し、そこに共通するものと相違するものを読み解こうとしたのが本書である。一つの学問を作り上げることの奥深さを知ることのできる好著として推薦したい。
北大ではどこにある?
先に竹内好の『日本とアジア』をこの「本は脳を育てる」に推薦したが、その中で竹内好がしばしば言及している一人が梅棹忠夫である。日本の知識人―という言い方を梅棹は嫌うだろうが―のアジア理解、文明観を問題にする上で避けて通れないと竹内は感じ取ったのだろう。その梅棹の知的営為を、先行する柳田国男のそれと対比的に考察し、そこに共通するものと相違するものを読み解こうとしたのが本書である。一つの学問を作り上げることの奥深さを知ることのできる好著として推薦したい。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
モンゴルの魅力に近づくために
草原の革命家たち : モンゴル独立への道 / 田中克彦著. - 中央公論社, 1990
 北大ではどこにある?
この「本は脳を育てる」の過去の推薦文に何回か書いたことであるが、僕は1990年代にエジプトに赴任していた。だが、最初に赴任先候補地としてあげられたのは、実はモンゴルであった。それがどこかでどうにかこうにかなってエジプトに落ち着いた(?)のであるが、今でも時々、あのときモンゴルに行っていたらどうなっていただろうかと思うことがある。今は、モンゴルと言えば相撲の世界が思い浮かぶだろうが、多くの日本人の間でこの国の歴史と現在の姿は意外に知られていないと言ってよいだろう。この本は、モンゴルが中国、ソヴィエトという巨大な国に挟まれて―しかもここ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この「本は脳を育てる」の過去の推薦文に何回か書いたことであるが、僕は1990年代にエジプトに赴任していた。だが、最初に赴任先候補地としてあげられたのは、実はモンゴルであった。それがどこかでどうにかこうにかなってエジプトに落ち着いた(?)のであるが、今でも時々、あのときモンゴルに行っていたらどうなっていただろうかと思うことがある。今は、モンゴルと言えば相撲の世界が思い浮かぶだろうが、多くの日本人の間でこの国の歴史と現在の姿は意外に知られていないと言ってよいだろう。この本は、モンゴルが中国、ソヴィエトという巨大な国に挟まれて―しかもここ... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
日本人はアジアとどう向き合ってきたか
日本とアジア / 竹内好著. - 筑摩書房, 1993
 北大ではどこにある?
これは、竹内好という稀代の中国文学者の手になるすぐれた日本、及びアジア研究の書である。初版が刊行されてから50年以上が経過しているが、そこに示される分析(あるいは同時代思想批判の)の観点には今なお学ぶものが多くある。中国、アジアだけでなく、というよりむしろ欧米社会・文化に関心を持つ人にこそ読んでほしいと思う。特に「二つのアジア史観」、「方法としてのアジア」は人文社会科学を勉強する上で貴重な示唆を含んでいる。
北大ではどこにある?
これは、竹内好という稀代の中国文学者の手になるすぐれた日本、及びアジア研究の書である。初版が刊行されてから50年以上が経過しているが、そこに示される分析(あるいは同時代思想批判の)の観点には今なお学ぶものが多くある。中国、アジアだけでなく、というよりむしろ欧米社会・文化に関心を持つ人にこそ読んでほしいと思う。特に「二つのアジア史観」、「方法としてのアジア」は人文社会科学を勉強する上で貴重な示唆を含んでいる。 -
推薦者 : 橋本 努 (経済学院・教員)
「幸福とは何か」「善く生きるとはどういうことか」を問う新しい教養の書
The Routledge handbook of philosophy of well-being / Fletcher, Guy. - Routledge, 2015
 北大ではどこにある?
この数年間で、「幸福」や「ウェルビイング」に関する研究が、社会科学の諸分野を巻き込みつつ大きく発展している。さまざまな国際指標が提案され、膨大な社会調査研究が蓄積されてきた。実証的な成果を受けて、哲学や社会理論においても新たな発展がみられる。本書はこのテーマに関する最新の社会諸科学の研究成果を展望するハンドブックであり、と同時に、「幸福とは何か」「善く生きるとはどういうことか」を問う新しい教養の書といえる。こうした書物を契機に、若い世代から新たな研究が生まれることを願っている。
北大ではどこにある?
この数年間で、「幸福」や「ウェルビイング」に関する研究が、社会科学の諸分野を巻き込みつつ大きく発展している。さまざまな国際指標が提案され、膨大な社会調査研究が蓄積されてきた。実証的な成果を受けて、哲学や社会理論においても新たな発展がみられる。本書はこのテーマに関する最新の社会諸科学の研究成果を展望するハンドブックであり、と同時に、「幸福とは何か」「善く生きるとはどういうことか」を問う新しい教養の書といえる。こうした書物を契機に、若い世代から新たな研究が生まれることを願っている。
登録日 : 2017-08-04
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
それでも君はボランティアをするか?!
ボランティアという病 / 丸山千夏著. - 宝島社, 2016
 北大ではどこにある?
ボランティアはいいことだと思っている人、実際にやってみたことはないが関わってみたいという潜在的な魅力を感じている人は少なくないと思われる。しかし、ボランティアが全て手放しで賞賛されるべきものかというとそうでもない。この本は、「ヤバい」ボランティア、あるいはボランティアの「ヤバさ」についていろいろと教えてくれる。内容には賛否両論あるだろうが、「善意」が無条件にもてはやされることに疑問を感じるなら、折角のボランティア参加が心ならずも不本意な結果に終わらないよう一度目を通しておいてもいいと思う。
北大ではどこにある?
ボランティアはいいことだと思っている人、実際にやってみたことはないが関わってみたいという潜在的な魅力を感じている人は少なくないと思われる。しかし、ボランティアが全て手放しで賞賛されるべきものかというとそうでもない。この本は、「ヤバい」ボランティア、あるいはボランティアの「ヤバさ」についていろいろと教えてくれる。内容には賛否両論あるだろうが、「善意」が無条件にもてはやされることに疑問を感じるなら、折角のボランティア参加が心ならずも不本意な結果に終わらないよう一度目を通しておいてもいいと思う。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
韓国は「異星」である、か?
韓国、愛と思想の旅 / 小倉紀藏. - 大修館書店, 2004
 北大ではどこにある?
仕事柄韓国人留学生とのつきあいが少なからずあるが、いつも彼ら彼女らとの独特の距離の置き方にはかなりデリケートに神経を使う。こういうことを“国際交流”の入り口で仕事をしている人間が書くと問題だと感じる人もいるだろうが、むしろそうした仕事をしているからこそ適度な距離感が必要であるとも言える。この小倉氏の本は、韓国滞在・渡航経験の中でその距離を縮めようとしてついに叶わなかった(もしくは彼なりのやり方でその距離を消滅させていった)異文化間コンフリクトの記録である。韓国に対する読者のスタンスの取り方に応じてそれなりに“ツッコミどころ”も... [続きを読む]
北大ではどこにある?
仕事柄韓国人留学生とのつきあいが少なからずあるが、いつも彼ら彼女らとの独特の距離の置き方にはかなりデリケートに神経を使う。こういうことを“国際交流”の入り口で仕事をしている人間が書くと問題だと感じる人もいるだろうが、むしろそうした仕事をしているからこそ適度な距離感が必要であるとも言える。この小倉氏の本は、韓国滞在・渡航経験の中でその距離を縮めようとしてついに叶わなかった(もしくは彼なりのやり方でその距離を消滅させていった)異文化間コンフリクトの記録である。韓国に対する読者のスタンスの取り方に応じてそれなりに“ツッコミどころ”も... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
その日本語にはわけがある!
揺れ動くニホン語 : 問題なことばの生態 / 田中章夫. - 東京堂書店, 2007
 北大ではどこにある?
「日本語の乱れ」ということが時々メディアを賑わせる。しかし、これは言ってみればジャーナリズムや素朴な庶民感覚レベルの言い方で、その背後には(どこかに)“正しい(あるいは美しい)”日本語のあるべき用い方がある(はずだ)という一種の思い込みが隠れている。言語研究の観点から言えばこれが「乱れ」ではなく「変化」や「揺れ」であることは専門家の間では周知のことである。この本は、多様な現れ方をする日本語の表現を歴史的・計量的に分析し、実は「乱れ」と見えたものもそれなりの背景や理由があることを分かりやすく説明している。言語現象に対する切り口も... [続きを読む]
北大ではどこにある?
「日本語の乱れ」ということが時々メディアを賑わせる。しかし、これは言ってみればジャーナリズムや素朴な庶民感覚レベルの言い方で、その背後には(どこかに)“正しい(あるいは美しい)”日本語のあるべき用い方がある(はずだ)という一種の思い込みが隠れている。言語研究の観点から言えばこれが「乱れ」ではなく「変化」や「揺れ」であることは専門家の間では周知のことである。この本は、多様な現れ方をする日本語の表現を歴史的・計量的に分析し、実は「乱れ」と見えたものもそれなりの背景や理由があることを分かりやすく説明している。言語現象に対する切り口も... [続きを読む] -
推薦者 : 水本 秀明 (外国語教育センター・非常勤講師)
手軽にフィンランドの育児、生活習慣、etc.を知ることができます
フィンランド流イクメンMIKKOの世界一しあわせな子育て / ミッコ・コイヴマー. - かまくら春秋社, 2013
 北大ではどこにある?
現在お母さんと赤ちゃんの相談所「ネウヴォラ」のシステムがフィンランドから日本に紹介され、大きな反響を呼んでいます。肩書は大使館の報道・文化参事官だけれどもごく普通のフィンランド人の父親から見た理想の子育ての姿からはたくさん得るものがあります。
北大ではどこにある?
現在お母さんと赤ちゃんの相談所「ネウヴォラ」のシステムがフィンランドから日本に紹介され、大きな反響を呼んでいます。肩書は大使館の報道・文化参事官だけれどもごく普通のフィンランド人の父親から見た理想の子育ての姿からはたくさん得るものがあります。 -
推薦者 : 水本 秀明 (外国語教育センター・非常勤講師)
ムーミン以外にもトーベ・ヤンソンの著作は多数あり
島暮らしの記録 / トーベ・ヤンソン文 ; トゥーリッキ・ピエティラ画 ; 冨原眞弓訳. - 筑摩書房, 1999
 北大ではどこにある?
ムーミンシリーズばかりが取り上げられることの多いトーベ・ヤンソンですが、優れた短編小説や随筆もたくさん執筆しており、多くが和訳されています。ムーミンの世界がどのように生まれたか、この本の中にヒントがあるかもしれません。
北大ではどこにある?
ムーミンシリーズばかりが取り上げられることの多いトーベ・ヤンソンですが、優れた短編小説や随筆もたくさん執筆しており、多くが和訳されています。ムーミンの世界がどのように生まれたか、この本の中にヒントがあるかもしれません。 -
推薦者 : 水本 秀明 (外国語教育センター・その他)
日本初の本格的な日本語・フィンランド語辞典
日本語・フィンランド語辞典 = Japani-Suomi sanakirja / 日本フィンランド協会編. - 日本フィンランド協会, 2017
 北大ではどこにある?
企画から約20年、何度か頓挫しかけた日本語・フィンランド語辞典が日本フィンランド語協会の手でやっと2017年2月完成しました。フィン日、フィン英辞典はこれまでそれなりのものが手に入りましたが、日フィン辞典としては日本初の本格的なものです。学習用にぜひ利用してください。2017年6月には電子版もリリース予定です。
北大ではどこにある?
企画から約20年、何度か頓挫しかけた日本語・フィンランド語辞典が日本フィンランド語協会の手でやっと2017年2月完成しました。フィン日、フィン英辞典はこれまでそれなりのものが手に入りましたが、日フィン辞典としては日本初の本格的なものです。学習用にぜひ利用してください。2017年6月には電子版もリリース予定です。 -
推薦者 : 水本 秀明 (外国語教育センター・非常勤講師)
サンタクロースについてどれだけあなたは知っていますか?
サンタクロースの大旅行 / 葛野浩昭著. - 岩波書店, 1998
 北大ではどこにある?
サンタクロースはフィンランド語でjoulupukki、すなわち「クリスマス(joulu)」+「山羊(pukki)」。いったい「山羊」は何を表しているのでしょう?この本を読むと、とんがり帽子に赤い衣装で煙突からプレゼント配達に来る、といったサンタクロースの一般的なイメージが大きく覆されるはずです。好著!
北大ではどこにある?
サンタクロースはフィンランド語でjoulupukki、すなわち「クリスマス(joulu)」+「山羊(pukki)」。いったい「山羊」は何を表しているのでしょう?この本を読むと、とんがり帽子に赤い衣装で煙突からプレゼント配達に来る、といったサンタクロースの一般的なイメージが大きく覆されるはずです。好著! -
推薦者 : 水本 秀明 (外国語教育センター・非常勤講師)
ムーミン物語の作者トーベ・ヤンソンの実像が見られる
Haru, The Island of the Solitary : ハル、孤独の島 (DVD) / . - Victor Entertainment, 2014
 北大ではどこにある?
ムーミン物語で知られるトーベ・ヤンソンとはどのような人だったのでしょう。トーベが50歳の頃から77歳まで毎年のように夏を過ごしたフィンランドの小島「グルーブ・ハル」での生活の様子が、彼女自身およびパートナーのトゥーリッキ・ピエティラが8mmカメラで撮影した映像をもとに編集されています。DVDに付属の解説ノートも大変よくできています。
北大ではどこにある?
ムーミン物語で知られるトーベ・ヤンソンとはどのような人だったのでしょう。トーベが50歳の頃から77歳まで毎年のように夏を過ごしたフィンランドの小島「グルーブ・ハル」での生活の様子が、彼女自身およびパートナーのトゥーリッキ・ピエティラが8mmカメラで撮影した映像をもとに編集されています。DVDに付属の解説ノートも大変よくできています。
-
推薦者 : 田畑 伸一郎 (スラブ・ユーラシア研究センター・教員)
フィンランドの中学における歴史教科書
世界史のなかのフィンランドの歴史 : フィンランド中学校近現代史教科書 / ハッリ・リンタ=アホ [ほか] 著 ; 石野裕子, 高瀬愛訳. - 明石書店, 2011
 北大ではどこにある?
フィンランドの中学で使われている歴史教科書を翻訳したものです。フィンランドの歴史が平易に書かれています。フィンランドの歴史がよく分かるだけでなく,どのように歴史が教えられているのかについてもよく分かります。
北大ではどこにある?
フィンランドの中学で使われている歴史教科書を翻訳したものです。フィンランドの歴史が平易に書かれています。フィンランドの歴史がよく分かるだけでなく,どのように歴史が教えられているのかについてもよく分かります。 -
推薦者 : 池田 文人 (高等教育推進機構・教員)
ムーミンワールドへようこそ!
ムーミン谷への旅 : トーベ・ヤンソンとムーミンの世界 / . - 講談社, 1994
 北大ではどこにある?
世界中で愛されるムーミン物語が生まれたフィンランドの魅力とともに、ムーミン物語の奥の深さも感じることができます。フィンランドの美しい景色の写真とムーミン物語の挿絵から、ムーミンたちの住む世界の風景を見て、音を聞き、空気を感じることができます。
北大ではどこにある?
世界中で愛されるムーミン物語が生まれたフィンランドの魅力とともに、ムーミン物語の奥の深さも感じることができます。フィンランドの美しい景色の写真とムーミン物語の挿絵から、ムーミンたちの住む世界の風景を見て、音を聞き、空気を感じることができます。 -
推薦者 : 池田 文人 (高等教育推進機構・教員)
感動します!
青い光が見えたから : 16歳のフィンランド留学記 / 高橋絵里香著. - 講談社, 2007
 北大ではどこにある?
北海道で育った著者が、中学校でいじめに会い、絶望の中で見た青い光・フィンランド。苦労してフィンランドの高校に入学し、フィンランド語に苦戦しながらも、高校を卒業し、大学へ進学します。日本とは違い、個性と自主性を尊重するフィンランドの人々に囲まれ、自分らしさを取り戻していきます。自分に素直になれる素晴らしさにきっと感動するでしょう。
北大ではどこにある?
北海道で育った著者が、中学校でいじめに会い、絶望の中で見た青い光・フィンランド。苦労してフィンランドの高校に入学し、フィンランド語に苦戦しながらも、高校を卒業し、大学へ進学します。日本とは違い、個性と自主性を尊重するフィンランドの人々に囲まれ、自分らしさを取り戻していきます。自分に素直になれる素晴らしさにきっと感動するでしょう。 -
推薦者 : 田畑 伸一郎 (スラブ・ユーラシア研究センター・教員)
フィンランドの歴史を深く理解するための好著
「大フィンランド」思想の誕生と変遷 : 叙事詩カレワラと知識人 / 石野裕子著. - 岩波書店, 2012
 北大ではどこにある?
フィンランドの文化を知るうえで重要な叙事詩カレワラが同国の歴史において,あるいは同国が独立を遂げていくなかでどんな役割を果たしのかがよく分かります。フィンランドの歴史について思想面を含めて深く学びたい人にとって必読書です。
北大ではどこにある?
フィンランドの文化を知るうえで重要な叙事詩カレワラが同国の歴史において,あるいは同国が独立を遂げていくなかでどんな役割を果たしのかがよく分かります。フィンランドの歴史について思想面を含めて深く学びたい人にとって必読書です。 -
推薦者 : 池田 文人 (高等教育推進機構・教員)
学力世界一の秘密
競争やめたら学力世界一 : フィンランド教育の成功 / 福田誠治. - 朝日新聞社, 2006
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
真実の発見に生涯をかけた医師のドラマ
手洗いの疫学とゼンメルワイスの闘い / 玉城英彦. - 人間と歴史社, 2017
 北大ではどこにある?
今年2月のある日、この本の著者である玉城英彦先生(現名誉教授)が僕の研究室に突然いらして、「中村先生、最近元気ないみたいだけどこの本を読めば元気になるよ」と仰言ってサイン入りの本をくださった。その頃そんなに元気がなさそうだったのか、自分では分からないのだけれども成績提出などのドタバタで疲れていたことは確かだ。折角頂いたご本なのだが、その後もあれこれと忙しく、5月になってからようやく読むことができた。そして、確かに少し元気になれたので、こうして推薦することにした次第である。
北大ではどこにある?
今年2月のある日、この本の著者である玉城英彦先生(現名誉教授)が僕の研究室に突然いらして、「中村先生、最近元気ないみたいだけどこの本を読めば元気になるよ」と仰言ってサイン入りの本をくださった。その頃そんなに元気がなさそうだったのか、自分では分からないのだけれども成績提出などのドタバタで疲れていたことは確かだ。折角頂いたご本なのだが、その後もあれこれと忙しく、5月になってからようやく読むことができた。そして、確かに少し元気になれたので、こうして推薦することにした次第である。
ゼンメルワイスと産褥熱の研究については、僕も中学生時代に読... [続きを読む] -
推薦者 : 小泉 均 (工学研究院・教員)
英語に関する素朴な疑問について、英語の歴史に基づき答える本
はじめての英語史 : 英語の「なぜ?」に答える / 堀田隆一. - 研究社, 2016
 北大ではどこにある?
英語に関する素朴な疑問について、英語の歴史に基づき答えている本である。なぜ母音で始まる単語の前の不定冠詞はanで子音で始まる単語の前はaなのか?(通常の英文法の解説とは逆で、oneの弱形のanがはじめにあり、子音で始まる単語では、子音が連続するためnが脱落した)、数詞oneに対して、なぜ1番目はfirstなのか?なぜ日本語では姓+名の順なのに、英語では名+姓の順なのかなど興味深い話題が多い。このような事を知らなくても、英語の習得には支障はないのかもしれない。しかし、そうなる理由がわかっている方が記憶に残るし、英語に対する興味が増す。英語の修得に、必ず... [続きを読む]
北大ではどこにある?
英語に関する素朴な疑問について、英語の歴史に基づき答えている本である。なぜ母音で始まる単語の前の不定冠詞はanで子音で始まる単語の前はaなのか?(通常の英文法の解説とは逆で、oneの弱形のanがはじめにあり、子音で始まる単語では、子音が連続するためnが脱落した)、数詞oneに対して、なぜ1番目はfirstなのか?なぜ日本語では姓+名の順なのに、英語では名+姓の順なのかなど興味深い話題が多い。このような事を知らなくても、英語の習得には支障はないのかもしれない。しかし、そうなる理由がわかっている方が記憶に残るし、英語に対する興味が増す。英語の修得に、必ず... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
言語をめぐる思惟を広く捉えるために
ドイツ言語哲学の諸相 / 麻生建. - 東京大学出版会, 1989
 北大ではどこにある?
以前奨めてくれる人があって、飯田隆『言語哲学大全Ⅰ~Ⅳ』(勁草書房)を読んでみたことがある。確かに現代の言語哲学、あるいは分析哲学をフレーゲからデヴィッドソンまで熱く語っている良書ではあるのだが、これをもって「大全」ということには大きな不満を覚える。その点は飯田氏も分かっているようで、第Ⅰ巻の冒頭で「『大全』というのは、さすがに私にしても調子に乗り過ぎという感がしないでもない」と書いている。この本を「大全」と言ってほしくないのは、対象がフレーゲとヴィトゲン... [続きを読む]
北大ではどこにある?
以前奨めてくれる人があって、飯田隆『言語哲学大全Ⅰ~Ⅳ』(勁草書房)を読んでみたことがある。確かに現代の言語哲学、あるいは分析哲学をフレーゲからデヴィッドソンまで熱く語っている良書ではあるのだが、これをもって「大全」ということには大きな不満を覚える。その点は飯田氏も分かっているようで、第Ⅰ巻の冒頭で「『大全』というのは、さすがに私にしても調子に乗り過ぎという感がしないでもない」と書いている。この本を「大全」と言ってほしくないのは、対象がフレーゲとヴィトゲン... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「日本語を教える」現場の熱気を伝える
世界の日本語教室から-日本を伝える30ヵ国の日本語教師レポート- / 国際交流基金. - アルク, 2009
 北大ではどこにある?
ここ何年か国際教育研究センターで(旧留学生センター時代から)全学教育科目に「外国人に日本語を教える」という「総合科目」を提供している。受講動機は様々であろうが日本語教育に関心を持ってくれる学生が一定数いるようで関係者としては有り難く思っている。この本は、そんな、日本語教育に関心を持っている学生がちょっとだけその―特に海外の―現場を覗いてみたいと思った時に気軽に読めるものとして紹介しておきたい。内容は、外務省の外郭団体である国際交流基金が世界各国に派遣した日本語教育専門家の手になる現地レポートである。日本語教育の現場の雰囲気を少しで... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ここ何年か国際教育研究センターで(旧留学生センター時代から)全学教育科目に「外国人に日本語を教える」という「総合科目」を提供している。受講動機は様々であろうが日本語教育に関心を持ってくれる学生が一定数いるようで関係者としては有り難く思っている。この本は、そんな、日本語教育に関心を持っている学生がちょっとだけその―特に海外の―現場を覗いてみたいと思った時に気軽に読めるものとして紹介しておきたい。内容は、外務省の外郭団体である国際交流基金が世界各国に派遣した日本語教育専門家の手になる現地レポートである。日本語教育の現場の雰囲気を少しで... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
イスラム教を「信じる」とはどのようなことか
日本の中でイスラム教を信じる / 佐藤兼永. - 文藝春秋社, 2015
 北大ではどこにある?
日本社会の中ではイスラム教信者、中でも特に日本人の信者というのは姿が見えにくい存在である。この本は、日本社会の中でイスラム教信仰に生きる人びとの姿を描いたルポルタージュであり、イスラム世界というものが西アジア・中東・アフリカという遠いところにある(だけな)のではなく、我々のすぐそばにもあるものだということに気づかせてくれる。現在、多少緩和されたとはいえ、まだイスラム教に対する様々な偏見が社会の中に存在することは否定できない。著者の佐藤氏は、その偏見を我々も持つことを認めた上でそれを肯定的なものへと転換する契機を示してくれている... [続きを読む]
北大ではどこにある?
日本社会の中ではイスラム教信者、中でも特に日本人の信者というのは姿が見えにくい存在である。この本は、日本社会の中でイスラム教信仰に生きる人びとの姿を描いたルポルタージュであり、イスラム世界というものが西アジア・中東・アフリカという遠いところにある(だけな)のではなく、我々のすぐそばにもあるものだということに気づかせてくれる。現在、多少緩和されたとはいえ、まだイスラム教に対する様々な偏見が社会の中に存在することは否定できない。著者の佐藤氏は、その偏見を我々も持つことを認めた上でそれを肯定的なものへと転換する契機を示してくれている... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
現代に活きる「古典」
人口論 / マルサス. - 光文社, 2011
 北大ではどこにある?
この『人口論』は、食糧供給と人口増加の関係を軸に貧困や失業や労働移動などの社会問題にどのように対応するべきかを考察した古典である。18世紀のイングランドが叙述の背景となっているが、マルサスが述べる考察は現代のアクチュアルな問題に通じるものであることを納得できるであろう。古典が現代に活きることを示すものとして薦めたい。
北大ではどこにある?
この『人口論』は、食糧供給と人口増加の関係を軸に貧困や失業や労働移動などの社会問題にどのように対応するべきかを考察した古典である。18世紀のイングランドが叙述の背景となっているが、マルサスが述べる考察は現代のアクチュアルな問題に通じるものであることを納得できるであろう。古典が現代に活きることを示すものとして薦めたい。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「ボランティア」のあり方を見つめ直すために
「ボランティア」の誕生と終焉 : 「贈与のパラドックス」の知識社会学 / 仁平典宏. - 名古屋大学出版会, 2011
 北大ではどこにある?
学生時代に7年ほどあるボランティア活動に携わっていたことがあるのだが、最初に活動に参加しようとした時、親に言われたのは「自分の頭のハエも追えない奴が偉そうに人助けなんかやるな!」という暴言(!)であった。今考えてもあんまりな言い方だと思うが、そうした意識は程度の差こそあれ日本の社会にある時期流通していたボランティア理解ではなかったかとも思う。この本の帯には「『善意』と『冷笑』の狭間で」と書かれているのだが、このことばはボランティアというものに対して注がれる、あるいは浴びせられる視線の複雑さを見事に言い当てている。そうした複雑さを... [続きを読む]
北大ではどこにある?
学生時代に7年ほどあるボランティア活動に携わっていたことがあるのだが、最初に活動に参加しようとした時、親に言われたのは「自分の頭のハエも追えない奴が偉そうに人助けなんかやるな!」という暴言(!)であった。今考えてもあんまりな言い方だと思うが、そうした意識は程度の差こそあれ日本の社会にある時期流通していたボランティア理解ではなかったかとも思う。この本の帯には「『善意』と『冷笑』の狭間で」と書かれているのだが、このことばはボランティアというものに対して注がれる、あるいは浴びせられる視線の複雑さを見事に言い当てている。そうした複雑さを... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
ネット空間で被害者にも加害者にもならないようにするために。
ネット炎上の研究 : 誰があおり、どう対処するのか / 田中辰雄, 山口真一著. - 勁草書房, 2016
 北大ではどこにある?
この本は、インターネット上で発生するいわゆる「炎上」という現象を分析し、その実態と歴史(!)と対応策を分かりやすく述べている。特に最後の「付録 炎上リテラシー教育のひな型」では、高校生を対象として想定し、「炎上」の仕組みとそれに巻き込まれそうになったらどうするべきかを丁寧に説いてくれている。インターネットがこれだけ広範囲に利用されるようになった社会で安全に生活し、かつ自分が加害者にならないためにも読んでおくべき1冊である。
北大ではどこにある?
この本は、インターネット上で発生するいわゆる「炎上」という現象を分析し、その実態と歴史(!)と対応策を分かりやすく述べている。特に最後の「付録 炎上リテラシー教育のひな型」では、高校生を対象として想定し、「炎上」の仕組みとそれに巻き込まれそうになったらどうするべきかを丁寧に説いてくれている。インターネットがこれだけ広範囲に利用されるようになった社会で安全に生活し、かつ自分が加害者にならないためにも読んでおくべき1冊である。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「戦争」を陳腐なことばで語らないために
ひとりの記憶 : 海の向こうの戦争と、生き抜いた人たち / 橋口譲二. - 文藝春秋, 2016
 北大ではどこにある?
この本は、太平洋戦争前後に植民地を含む海外に渡り、様々な事情でその地に残り、あるいは再渡航してそこで生き抜くことを選んだ人々からの聞き取りの記録である。現代に於ける戦争に対する反対・批判・抑止のことばの一つとして「戦争は人間の運命を狂わせる」といったものがある。それを否定するつもりはないし、そうした事例もあることを認めはするが、この本を読んだあとでここに描かれている人々の人生が戦争によって“狂った(あるいは狂わされた)”と―「戦争を知らない子供たち」である我々が―いうことには大きな躊躇いを覚えてしまう。その背後にあったはずのお... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、太平洋戦争前後に植民地を含む海外に渡り、様々な事情でその地に残り、あるいは再渡航してそこで生き抜くことを選んだ人々からの聞き取りの記録である。現代に於ける戦争に対する反対・批判・抑止のことばの一つとして「戦争は人間の運命を狂わせる」といったものがある。それを否定するつもりはないし、そうした事例もあることを認めはするが、この本を読んだあとでここに描かれている人々の人生が戦争によって“狂った(あるいは狂わされた)”と―「戦争を知らない子供たち」である我々が―いうことには大きな躊躇いを覚えてしまう。その背後にあったはずのお... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「東洋」と「西洋」とは何か、あらためて考える。
東洋意識 : 夢想と現実のあいだ1887-1953 / 稲賀繁美編著. - ミネルヴァ書房, 2012
 北大ではどこにある?
学問―特に人文科学―の世界に於ける「東洋-西洋」という枠組み或いは二分法は、実は相当にうさんくさい。そのうさんくささを“学問的に”剔抉したのは言うまでもなくエドワード・サイードの『オリエンタリズム』だったが、そのとらえ方自体が西洋的な学問世界の中で一定の権威になってしまうという戯画的な状況が生まれ、相変わらず「東洋-西洋」という枠組みをめぐる思索は混迷している。今回推薦する本は、編著者の稲賀氏自身が書いているように「『東洋』と呼ばれる―あるいは時代遅れとな... [続きを読む]
北大ではどこにある?
学問―特に人文科学―の世界に於ける「東洋-西洋」という枠組み或いは二分法は、実は相当にうさんくさい。そのうさんくささを“学問的に”剔抉したのは言うまでもなくエドワード・サイードの『オリエンタリズム』だったが、そのとらえ方自体が西洋的な学問世界の中で一定の権威になってしまうという戯画的な状況が生まれ、相変わらず「東洋-西洋」という枠組みをめぐる思索は混迷している。今回推薦する本は、編著者の稲賀氏自身が書いているように「『東洋』と呼ばれる―あるいは時代遅れとな... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
異文化理解はぼちぼちこのあたりから…。
異文化理解の落とし穴 : 中国・日本・アメリカ / 張競. - 岩波書店, 2011
 北大ではどこにある?
この本は、上海出身中国人で日本に留学し学位を得て日本で教職に就きアメリカで研究生活も送った著者の異文化体験の記録である。読後感としては標題にあるような「異文化理解」というレベルに達しているとは思えないし、ましてやその「落とし穴」を明解にしているとも言い切れない。むしろ表層的な体験と感想が連ねられているというのが率直なところである。しかし、それは裏を返せば、「異文化理解」ということに到達するには誰もがこの段階をくぐらなければならないということを示す一つの基準点になり得ている、ということであり、また、日本に限らず「文化」というもの... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、上海出身中国人で日本に留学し学位を得て日本で教職に就きアメリカで研究生活も送った著者の異文化体験の記録である。読後感としては標題にあるような「異文化理解」というレベルに達しているとは思えないし、ましてやその「落とし穴」を明解にしているとも言い切れない。むしろ表層的な体験と感想が連ねられているというのが率直なところである。しかし、それは裏を返せば、「異文化理解」ということに到達するには誰もがこの段階をくぐらなければならないということを示す一つの基準点になり得ている、ということであり、また、日本に限らず「文化」というもの... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
世界はどうしてこうなっているのか。
エジプトを植民地化する : 博覧会世界と規律訓練的権力 / ティモシー・ミッチェル著 ; 大塚和夫, 赤堀雅幸訳. - 法政大学出版局, 2014
 北大ではどこにある?
一見この本とは関係なさそうな話から推薦文を書く。みなさんは、観光旅行に行くとはどのようなことだと思っているだろうか。理由はいろいろあるにせよ、大きな共通点は世界遺産に代表されるような歴史的建造物や名所旧跡を辿ることが目的である、ということだろう。しかし、である。その時、観光旅行する我々は、実は名所旧跡を”見に”行っているのではなく、ガイドブックなどに一定の秩序で並べられた空間の”確認”をしに行っているに過ぎないのである。なぜそう言えるのか、の答えを与えてくれるのが、この本の副題になっている「博覧会世界」である。
北大ではどこにある?
一見この本とは関係なさそうな話から推薦文を書く。みなさんは、観光旅行に行くとはどのようなことだと思っているだろうか。理由はいろいろあるにせよ、大きな共通点は世界遺産に代表されるような歴史的建造物や名所旧跡を辿ることが目的である、ということだろう。しかし、である。その時、観光旅行する我々は、実は名所旧跡を”見に”行っているのではなく、ガイドブックなどに一定の秩序で並べられた空間の”確認”をしに行っているに過ぎないのである。なぜそう言えるのか、の答えを与えてくれるのが、この本の副題になっている「博覧会世界」である。
この本は、表題か... [続きを読む] -
推薦者 : 松田 康子 (教育学研究院・教員)
すべての学び手に
ケアの本質 : 生きることの意味 / ミルトン・メイヤロフ著 ; 田村真, 向野宣之訳. - ゆみる出版, 1987
 北大ではどこにある?
本書は、MILTON MAYEROFF著 On Caringの訳書です。対人援助職にとどまらず、すべてのケアの担い手にとって、ケアの営みにおいて常に立ち戻るべき本質が示されており、哲学書にしてはやさしい言葉で綴られている書物です。日本語も英語も一見すると、平易な言葉が並んでいるのですが、何度でも噛み締め味わうことができる論考です。高等教育機関において、「すべての学び手に」としてオススメしたい点は、メイヤロフが、ケアの対象を人のみならず、芸術、概念、理念というものにまで広げて考えているところです。メイヤロフは、ケアリングとは、ケアの受け手が他の誰かをケアできるよ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
本書は、MILTON MAYEROFF著 On Caringの訳書です。対人援助職にとどまらず、すべてのケアの担い手にとって、ケアの営みにおいて常に立ち戻るべき本質が示されており、哲学書にしてはやさしい言葉で綴られている書物です。日本語も英語も一見すると、平易な言葉が並んでいるのですが、何度でも噛み締め味わうことができる論考です。高等教育機関において、「すべての学び手に」としてオススメしたい点は、メイヤロフが、ケアの対象を人のみならず、芸術、概念、理念というものにまで広げて考えているところです。メイヤロフは、ケアリングとは、ケアの受け手が他の誰かをケアできるよ... [続きを読む] -
推薦者 : 武村 理雪 (国際連携機構・その他)
自身の問いを見つめなおす機会に
途上国の人々との話し方 : 国際協力メタファシリテーションの手法 / 和田信明, 中田豊一. - みずのわ出版, 2010
 北大ではどこにある?
途上国支援に限らず、様々な職業で活かすことのできる知識と技術を学べる書籍です。
北大ではどこにある?
途上国支援に限らず、様々な職業で活かすことのできる知識と技術を学べる書籍です。
実は私も本学の教員に薦められて読み始めました。自らの無知とコミュニケーション技術のなさを痛感させられた刺激的な書籍です。
責任と配慮をもって問いを発し、その問いをきっかけに希望が開かれるよう、この書籍を片手に精進していきたいと思わされました。
ある程度の業務経験があると、内容理解が進み易いだろうと推測します。一方で、今は十分に理解できない部分があったとしても、最後まで読んでみることで学生は将来の糧を得られるのではないかと思います。 -
推薦者 : 小俣 友輝 (URAステーション・その他)
言葉の違い、考え方の違いは面白い!
翻訳できない世界のことば / エラ・フランシス・サンダース著イラスト ; 前田まゆみ訳. - 創元社, 2016
 北大ではどこにある?
生まれたところ、住んでいるところが違えば、人の気持ちやことばも違ってくるようです。
北大ではどこにある?
生まれたところ、住んでいるところが違えば、人の気持ちやことばも違ってくるようです。
様々な国で使われていることばが表すものは、外国人である自分の想像を超えているにも関わらず、なるほどと思えるものでした。
新しいものの見方・考え方に触れられるのと同時に、ことばを使う世界の人々とのつながりをも感じるのでした。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
おじさんも、若い人も語学を楽しむために
おじさん、語学する / 塩田勉. - 集英社, 2001
 北大ではどこにある?
あるきっかけからフランス語を勉強することになったおじさんの奮闘記、という形をとって語学を身につけるための秘訣と、それだけでなく異文化との関わり方を気づかせてくれるユニークな本。語学大好きな人にも語学嫌いな人にもお薦めしたい。
北大ではどこにある?
あるきっかけからフランス語を勉強することになったおじさんの奮闘記、という形をとって語学を身につけるための秘訣と、それだけでなく異文化との関わり方を気づかせてくれるユニークな本。語学大好きな人にも語学嫌いな人にもお薦めしたい。
ただ、悲しいかな外国語の先生は日本語はお得意ではないようで、この中にも日本語の間違いが一箇所ある。探してみてほしい。