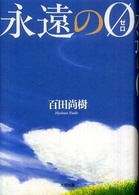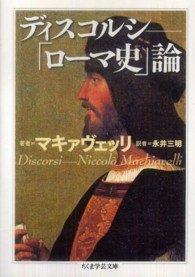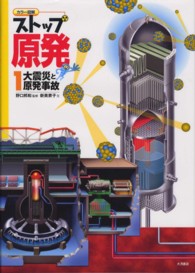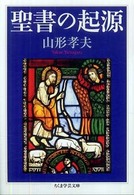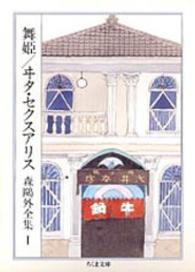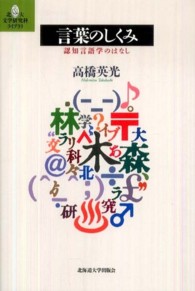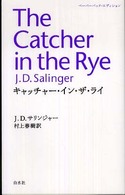-
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
learn how to make the world a better place
The Unfair Trade: How Our Broken Global Financial System Destroys the Middle Class / Michael Casey. - Crown Business, 2012
 北大ではどこにある?
If you enjoy 池上彰's easy to understand explanations of finance, economics, and politics, and if you seek a career on the global stage, then read this book. At the very least you will learn how to form a convincing argument. On average, you will learn that nation states ought to realize global growth can help their domestic economies -- that a smaller piece of a bigger pie might be bigger than a bigger piece of a smaller pie. And if you and I are fortunate, then you will create knowledge and acquire influence that will make the world a better place. This book gives us ideas on how to make that happen. Be maximally ambitious. Or, as Buzz Lightyear might say, To infinity and beyond!
北大ではどこにある?
If you enjoy 池上彰's easy to understand explanations of finance, economics, and politics, and if you seek a career on the global stage, then read this book. At the very least you will learn how to form a convincing argument. On average, you will learn that nation states ought to realize global growth can help their domestic economies -- that a smaller piece of a bigger pie might be bigger than a bigger piece of a smaller pie. And if you and I are fortunate, then you will create knowledge and acquire influence that will make the world a better place. This book gives us ideas on how to make that happen. Be maximally ambitious. Or, as Buzz Lightyear might say, To infinity and beyond! -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
Succinctly describes a global horror
The Second World War / Antony Beevor. - Little, Brown and Company, 2012
 北大ではどこにある?
Japan war memory is dying (at least the people with hands-on experience with warfare are), and nothing is taught (shameful that Japan cannot confront itself, compared to Germany for instance). This book should shed some light on what happened during those painful years. The book is long but so was the war. Considering the deadliness of it all, the book treats everything swiftly.
北大ではどこにある?
Japan war memory is dying (at least the people with hands-on experience with warfare are), and nothing is taught (shameful that Japan cannot confront itself, compared to Germany for instance). This book should shed some light on what happened during those painful years. The book is long but so was the war. Considering the deadliness of it all, the book treats everything swiftly. -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
a montage of a fighter pilot who wanted to live
永遠の0 (ゼロ) / 百田尚樹. - 太田出版, 2006
 北大ではどこにある?
I teach 99 percent of Hokudai's entire freshman class. 99 percent of all undergraduates have taken a course that I teach. They may not remember me, nor do I remember all of them, but as a whole generation, I do have a clear impression of who my students are. One characteristic is that our students rarely if ever exert themselves to the fullest. What they believe is an honest effort is, sadly, barely a start compared to people who lived during and after the war. This book is about a fictitious navy aviator (they weren't called pilots back then) who, after a one-week marriage, determines not to get killed so he can return home, see his wife, and meet his baby girl. The individuals are imaginary but the stories are not. Most Hokudai students will shed a tear reading this story. Whiners shoul... [続きを読む]
北大ではどこにある?
I teach 99 percent of Hokudai's entire freshman class. 99 percent of all undergraduates have taken a course that I teach. They may not remember me, nor do I remember all of them, but as a whole generation, I do have a clear impression of who my students are. One characteristic is that our students rarely if ever exert themselves to the fullest. What they believe is an honest effort is, sadly, barely a start compared to people who lived during and after the war. This book is about a fictitious navy aviator (they weren't called pilots back then) who, after a one-week marriage, determines not to get killed so he can return home, see his wife, and meet his baby girl. The individuals are imaginary but the stories are not. Most Hokudai students will shed a tear reading this story. Whiners shoul... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
理想郷とは?
失われた地平線 / ジェイムズ・ヒルトン. - 新潮社, 1959
 北大ではどこにある?
ジェイムズ・ヒルトンといえば『チップス先生、さようなら』で広く知られているけれども、この『失われた地平線』は、彼のもう一つの代表作とも言える、不思議な雰囲気をたたえたユートピア小説である。第一次大戦後の動揺するインドからヒマラヤを舞台に、英米人の主人公たちが思いがけない事件に巻きこまれて一種の理想郷的世界に紛れ込んでいく。特に、この小説の後半をしめるラマ教寺院の院長とイギリス人外交官の対話、そこから急転する脱出劇は読むものを引きつけて放さない面白さがある。(この小説に出てくる「シャングリラ」ということばは後に“理想郷”を示す代... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ジェイムズ・ヒルトンといえば『チップス先生、さようなら』で広く知られているけれども、この『失われた地平線』は、彼のもう一つの代表作とも言える、不思議な雰囲気をたたえたユートピア小説である。第一次大戦後の動揺するインドからヒマラヤを舞台に、英米人の主人公たちが思いがけない事件に巻きこまれて一種の理想郷的世界に紛れ込んでいく。特に、この小説の後半をしめるラマ教寺院の院長とイギリス人外交官の対話、そこから急転する脱出劇は読むものを引きつけて放さない面白さがある。(この小説に出てくる「シャングリラ」ということばは後に“理想郷”を示す代... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
もう一つの「ローマ人の物語」
ディスコルシ-「ローマ史」論- / マキアヴェッリ. - 筑摩書房, 2011
 北大ではどこにある?
「ローマ人の物語」といえば塩野七生さんの著作があまりにも有名であるが、この『ディスコルシ』はマキアヴェッリによるもう一つのローマ史である。マキアヴェッリは、この本を書く時に間違いなく彼が生きていた時代のイタリアの運命を考えながら-その姿勢は『君主論』にもつながる-筆を走らせていた。歴史から何事かを学ぶ、ということがどのようなものか、この本から浮かび上がってくるだろう。
北大ではどこにある?
「ローマ人の物語」といえば塩野七生さんの著作があまりにも有名であるが、この『ディスコルシ』はマキアヴェッリによるもう一つのローマ史である。マキアヴェッリは、この本を書く時に間違いなく彼が生きていた時代のイタリアの運命を考えながら-その姿勢は『君主論』にもつながる-筆を走らせていた。歴史から何事かを学ぶ、ということがどのようなものか、この本から浮かび上がってくるだろう。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
本は脳を鍛える!
クアトロ・ラガッツィ-天正少年使節と世界帝国- / 若桑みどり. - 集英社, 2003
 北大ではどこにある?
天正少年使節と言えば、高校の日本史や世界史で習った記憶があるだろう。これは、博覧強記の著者が、西欧の図書館や文書館に収蔵されている第一次史料を丹念に読み解いて、天正少年使節をとりまく権力者たちとキリスト教信者たち、そしてキリスト教会内の様々な駆け引きを世界史の大きな変動の中に於いて捉えようとした大著である。
北大ではどこにある?
天正少年使節と言えば、高校の日本史や世界史で習った記憶があるだろう。これは、博覧強記の著者が、西欧の図書館や文書館に収蔵されている第一次史料を丹念に読み解いて、天正少年使節をとりまく権力者たちとキリスト教信者たち、そしてキリスト教会内の様々な駆け引きを世界史の大きな変動の中に於いて捉えようとした大著である。
ただ、表題に惹かれて読んでみたものの羊頭狗肉の感は否めない。550ページにのぼるこの本を230ページくらいまで読まないとそもそも天正少年使節が出てこないし、彼らのヨーロッパでの体験もむしろ彼ら少年使節よりはキリスト教会と教皇庁、そし... [続きを読む]登録日 : 2012-05-01
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
誤解の連続は新たな思想を生むか
仏教、本当の教え-インド、中国、日本の理解と誤解- / 植木雅俊. - 中央公論新社, 2011
 北大ではどこにある?
大学で哲学を学んでいた時、先輩から「結局ドイツ観念論哲学というのは、フィヒテとシェリングとヘーゲルがカントをどのように“誤読”したかの歴史だ」と言われて、へえぇ、そんなもんなの、と思ったことがある。この本は、帯に書かれた「壮大な伝言ゲームの果てに。」という一句に惹かれて買ってしまったのだが、読んでみると結構面白かった。その面白さというのは、-著者には申し訳ないけれど-謂わば底意地の悪い面白さで、これまでの翻訳者(=謂わばその学問の世界ではお偉いさん)や、さらには道元や親鸞などの宗祖までもがどのように仏典を誤読してきたかが、宗教... [続きを読む]
北大ではどこにある?
大学で哲学を学んでいた時、先輩から「結局ドイツ観念論哲学というのは、フィヒテとシェリングとヘーゲルがカントをどのように“誤読”したかの歴史だ」と言われて、へえぇ、そんなもんなの、と思ったことがある。この本は、帯に書かれた「壮大な伝言ゲームの果てに。」という一句に惹かれて買ってしまったのだが、読んでみると結構面白かった。その面白さというのは、-著者には申し訳ないけれど-謂わば底意地の悪い面白さで、これまでの翻訳者(=謂わばその学問の世界ではお偉いさん)や、さらには道元や親鸞などの宗祖までもがどのように仏典を誤読してきたかが、宗教... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
breathtaking photography and commentary
Shaped by War / Don McCullin. - Jonathan Cape, 2010
 北大ではどこにある?
Many photography books are mostly photos. This book contains textual commentary that guides the reader through the graphic narrative, and provides valuable insight into what transpired in the mind of the photographer. Don McCullin is a renowned war photojournalist. His Nikon F camera being hit by a bullet is a well-known story. I saw the actual camera at an exhibit in London.
北大ではどこにある?
Many photography books are mostly photos. This book contains textual commentary that guides the reader through the graphic narrative, and provides valuable insight into what transpired in the mind of the photographer. Don McCullin is a renowned war photojournalist. His Nikon F camera being hit by a bullet is a well-known story. I saw the actual camera at an exhibit in London. -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
risk life for adventures
The Heart of the Great Alone: Scott, Shackleton, and Antarctic Photography / David Hempleman-Adams. - The Royal Collection, 2011
 北大ではどこにある?
Risking your life for adventure and exploration are not as fashionable these days as it was in the 19th century. Consider, for example, the death of Noguchi Hideyo to yellow fever. Or the death of Robert Falcon Scott and his team in their race to the South Pole. The photographs in this book are rare records of what mankind has done, and perhaps ought to continue to do, in the search of science, curiosity, and glory.
北大ではどこにある?
Risking your life for adventure and exploration are not as fashionable these days as it was in the 19th century. Consider, for example, the death of Noguchi Hideyo to yellow fever. Or the death of Robert Falcon Scott and his team in their race to the South Pole. The photographs in this book are rare records of what mankind has done, and perhaps ought to continue to do, in the search of science, curiosity, and glory. -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
evolution of portrait photography
Queen Elizabeth II: Portraits by Cecil Beaton / Susanna Brown. - V & A Publishing, 2011
 北大ではどこにある?
See how portrait photography has evolved over the years through the graphic representation of the longest reigning monarch in Britain. Posture, lighting, background, and composition have changed considerably. Another aspect of interest is the transformation of facial expressions. Queen Elizabeth II has had 11 prime ministers so far starting with Winston Churchill when she was 25. The maturing and aging of a experienced monarch makes a fascinating pictorial record.
北大ではどこにある?
See how portrait photography has evolved over the years through the graphic representation of the longest reigning monarch in Britain. Posture, lighting, background, and composition have changed considerably. Another aspect of interest is the transformation of facial expressions. Queen Elizabeth II has had 11 prime ministers so far starting with Winston Churchill when she was 25. The maturing and aging of a experienced monarch makes a fascinating pictorial record. -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
think hard, act decisively
カラー図解 ストップ原発〈1〉大震災と原発事故 (全4巻) / 新美景子. - 大月書店, 2011
 北大ではどこにある?
Japan lacks investigative journalism. Scientific journalism is almost as scarce. Read this series of 4 illustrated books for children. Familiarize yourself with the theory, history, objectives, advantages, and costs of nuclear energy. You may wonder why you knew so little before picking up these books.
北大ではどこにある?
Japan lacks investigative journalism. Scientific journalism is almost as scarce. Read this series of 4 illustrated books for children. Familiarize yourself with the theory, history, objectives, advantages, and costs of nuclear energy. You may wonder why you knew so little before picking up these books.
I vehemently oppose nuclear power plants. You may agree or disagree with me. Either way, you owe it to yourself and the world to learn all about the issue, particularly the aspects that the government and industry strive to hide. -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
日本社会の病い
まやかしの安全の国 / 田辺文也. - 角川SSC新書137, 2011
 北大ではどこにある?
去る3月11日の地震・津波による福島第一原発の事故は様々な疑問を投げかけます。事故の発生という事実に直面してからでは遅いといわれそうですが、原子力に携わる人々や事故に対処する政府関係者や事故の直接の当事者などの個人的資質にも疑念を呈したくなりますし、それを許容する社会の制度にも不信を抱かざるをえません。この本はそういう疑問に答えてくれそうですし、考えるきっかけを与えてくれそうです。以下、著者のあとがきより引用します。
北大ではどこにある?
去る3月11日の地震・津波による福島第一原発の事故は様々な疑問を投げかけます。事故の発生という事実に直面してからでは遅いといわれそうですが、原子力に携わる人々や事故に対処する政府関係者や事故の直接の当事者などの個人的資質にも疑念を呈したくなりますし、それを許容する社会の制度にも不信を抱かざるをえません。この本はそういう疑問に答えてくれそうですし、考えるきっかけを与えてくれそうです。以下、著者のあとがきより引用します。
・・・・・原子力のような巨大システムの安全確保に不可欠なのは、設備の運転や保守に携わる人のシステムに対する深い... [続きを読む] -
推薦者 : 小泉 均 (工学研究院)
これだけあるタバコの百害
タバコやめますか人間やめますか / 広島県医師会. - ごま書房, 1992
 北大ではどこにある?
1992年初版の古い本であるが、健康の専門家である医師が、一般向けに、きちんとしたデータに基づき、タバコの有害性、タバコによって引き起こされる疾患、禁煙法について、わかりやすく解説している。この本を読みタバコの有害性を理解し、タバコについて興味を持っている人は、喫煙始めることをやめ、すでに喫煙している人は、喫煙という悪い習慣をやめて、卒業していってほしい。タバコは、百害あって一利無しである。タバコやめますか、人間やめますか?答えは明白である。
北大ではどこにある?
1992年初版の古い本であるが、健康の専門家である医師が、一般向けに、きちんとしたデータに基づき、タバコの有害性、タバコによって引き起こされる疾患、禁煙法について、わかりやすく解説している。この本を読みタバコの有害性を理解し、タバコについて興味を持っている人は、喫煙始めることをやめ、すでに喫煙している人は、喫煙という悪い習慣をやめて、卒業していってほしい。タバコは、百害あって一利無しである。タバコやめますか、人間やめますか?答えは明白である。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
文章を書くことが苦手な人に安心を与えてくれる本
「書くのが苦手」をみきわめる / 渡辺哲司. - 学術出版会, 2010
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
Meticulous study of a piece of historical architecture
フランク・ロイド・ライトの帝国ホテル / 明石 信道、村井 修. - 建築資料研究社, 2004
 北大ではどこにある?
After many years of wishing, some months ago I finally visited the old Imperial Hotel, now relocated to the Meijimura open-air museum in Inuyama, Aichi. I sat in the hotel lobby for 2 hours to soak in the atmosphere.
北大ではどこにある?
After many years of wishing, some months ago I finally visited the old Imperial Hotel, now relocated to the Meijimura open-air museum in Inuyama, Aichi. I sat in the hotel lobby for 2 hours to soak in the atmosphere.
This book explains the history, design, and philosophy of the Imperial Hotel and the architect behind it. I am no fan of Frank Lloyd Wright as a family man (he deserted his first wife because he became infatuated in another woman; shame on him!). Nor am I impressed with how he treated his clients (cost over-runs were commonplace -- one client remarked "We had an unlimited budget, and we exceeded it" -- and many clients were shocked to receive bills for unsolicited "gifts" sent to them by Wright). But his designs have continued to fascinate me.
This book is an in-depth ... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
『聖書』成立のドラマに迫る
聖書の起源 / 山形孝夫. - 筑摩書房, 2010
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「田辺元ルネサンス」のために
田辺元哲学選I~IV(全4冊) / 田辺元. - 岩波書店, 2010
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
惹きこまれ一気に読める素粒子宇宙論入門
宇宙に終わりはあるのか?素粒子が解き明かす宇宙の歴史 / 村山斉. - ナノオプトニクス・エナジー出版局, 2010
 北大ではどこにある?
評者の書架には素粒子論や宇宙論の基本書、入門書が何冊かほこりをかぶっている。本書は稀なことにも「分かる」という感覚を頁毎に持続しながら、惹きこまれて一気に読むことができた入門書です。150頁の小著ということもありましょうが、評者には幸いな出会いをもたらしてくれ、あいまいで雑然としたなまかじりの知識に秩序と生命を与えてくれました。書名副題にあるように、著者は極微の素粒子の世界の解明が130億年の宇宙の構造と歴史の解明の手掛かりであることを明晰かつ簡明にそして説得的に展開しています。物理学のこの領域においては何が問題になっており、... [続きを読む]
北大ではどこにある?
評者の書架には素粒子論や宇宙論の基本書、入門書が何冊かほこりをかぶっている。本書は稀なことにも「分かる」という感覚を頁毎に持続しながら、惹きこまれて一気に読むことができた入門書です。150頁の小著ということもありましょうが、評者には幸いな出会いをもたらしてくれ、あいまいで雑然としたなまかじりの知識に秩序と生命を与えてくれました。書名副題にあるように、著者は極微の素粒子の世界の解明が130億年の宇宙の構造と歴史の解明の手掛かりであることを明晰かつ簡明にそして説得的に展開しています。物理学のこの領域においては何が問題になっており、... [続きを読む] -
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
哲学の始原がよくわかる
Definition in Greek Philosophy / ed.David Charles. - Oxford University Press, 2010
 北大ではどこにある?
本書により哲学の揺籃であるギリシア哲学において、とりわけソクラテスがこだわった事物の同一性とその認識の問題がプラトン、アリストテレスそしてストアにおいてどのように理解され、哲学理論へと展開されていったかをテクストに即して理解することができる。周知のようにソクラテスは会う人ごとに、勇気とは、節制とは正義とはそして幸福とは「何であるか?」を尋ね、共に探求した。当時の人々同様多くの人が持つ哲学の理屈っぽさのイメージはこのソクラテスの問答の持つ吟味、論駁の詳細さそして厳密さに起因しているように思われる。しかし、本書によりこの「何である... [続きを読む]
北大ではどこにある?
本書により哲学の揺籃であるギリシア哲学において、とりわけソクラテスがこだわった事物の同一性とその認識の問題がプラトン、アリストテレスそしてストアにおいてどのように理解され、哲学理論へと展開されていったかをテクストに即して理解することができる。周知のようにソクラテスは会う人ごとに、勇気とは、節制とは正義とはそして幸福とは「何であるか?」を尋ね、共に探求した。当時の人々同様多くの人が持つ哲学の理屈っぽさのイメージはこのソクラテスの問答の持つ吟味、論駁の詳細さそして厳密さに起因しているように思われる。しかし、本書によりこの「何である... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
類まれな人間観察の鋭さ
君主論 / マキアヴェッリ. - 岩波書店, 1959
 北大ではどこにある?
マキアヴェッリあるいは『君主論』というと、後世に染みついた「権謀術数を弄する奴」というイメージが浮かぶが、実際の彼はそういうことを中心的な思想として言いたかったわけではない、というのが今日では一般的な理解となっている。この本は時として“政治思想の古典”などと言われるが、そういう読み方を一旦脇に置いて、彼がこの本の中でどのように人間を描き出しているかを読み取っていくと意外に面白い。それも、表だって書かれている様々の君主ではなく、名前すらも分からないような一般人や兵士たちを、国や君主にとってどのような存在と見ていたかに焦点を当て... [続きを読む]
北大ではどこにある?
マキアヴェッリあるいは『君主論』というと、後世に染みついた「権謀術数を弄する奴」というイメージが浮かぶが、実際の彼はそういうことを中心的な思想として言いたかったわけではない、というのが今日では一般的な理解となっている。この本は時として“政治思想の古典”などと言われるが、そういう読み方を一旦脇に置いて、彼がこの本の中でどのように人間を描き出しているかを読み取っていくと意外に面白い。それも、表だって書かれている様々の君主ではなく、名前すらも分からないような一般人や兵士たちを、国や君主にとってどのような存在と見ていたかに焦点を当て... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「哲学」のススメ
善の研究 / 西田幾多郎. - 岩波書店, 1979
 北大ではどこにある?
『善の研究』については、これまで嫌になるくらい論文や研究書があり、僕もかつてその手のものを書いたことがある。それだけいろいろな読み方・解釈が可能だという点では紛れもなく「古典」であるが、同時に何回読んでもすっきりと分かった感じになれないところもある。そういうところから、「西田哲学を理解するためにも実際に参禅をしなければならない」(久松真一)といった言説が出てくるのだろう。
北大ではどこにある?
『善の研究』については、これまで嫌になるくらい論文や研究書があり、僕もかつてその手のものを書いたことがある。それだけいろいろな読み方・解釈が可能だという点では紛れもなく「古典」であるが、同時に何回読んでもすっきりと分かった感じになれないところもある。そういうところから、「西田哲学を理解するためにも実際に参禅をしなければならない」(久松真一)といった言説が出てくるのだろう。
『善の研究』は、すぐ分かるようでありながら実は分かりにくいし、まさにその「分かる=理解」という営みそのものを問題にしているところがあるので、どこまで行って... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
高校で読まされてウンザリした人に敢えて今勧める
舞姫 / 森鴎外. - 筑摩書房, 1995
 北大ではどこにある?
今回、この「本は脳を育てる」に推薦された本を全部見てみた。(僕は別として)北大の優秀な先生方が思い入れ充分に推薦しておられるのだからそれなりに読む価値があるのだとは思うけれども、なぜか古典と言われる作品が洋の東西を問わず少ない。僕も書いたことがあるから他人のことをあげつらってはいけないのだが、何となく新刊書の紹介のようになっている観がある。古典は高校までの間に読んでいるはずだから、今更勧める必要もないという考え方もあるかもしれないが、古典が古典と言われるほどまで時代を超えて生き続けるのは、人間の成長とともに様々な新しい読み方を... [続きを読む]
北大ではどこにある?
今回、この「本は脳を育てる」に推薦された本を全部見てみた。(僕は別として)北大の優秀な先生方が思い入れ充分に推薦しておられるのだからそれなりに読む価値があるのだとは思うけれども、なぜか古典と言われる作品が洋の東西を問わず少ない。僕も書いたことがあるから他人のことをあげつらってはいけないのだが、何となく新刊書の紹介のようになっている観がある。古典は高校までの間に読んでいるはずだから、今更勧める必要もないという考え方もあるかもしれないが、古典が古典と言われるほどまで時代を超えて生き続けるのは、人間の成長とともに様々な新しい読み方を... [続きを読む] -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
少年一人大地を行く
たった独りの引き揚げ隊 / 石村博子. - 角川書店, 2009
 北大ではどこにある?
第2次大戦が終わった翌年、満州に残った民間の日本人はやっと引き揚げることになった。日本人とロシア人の混血の少年(日本国籍)は一人で日本に渡ろうとする。ところが彼はロシア人だと大人の引揚者に荷物を奪われ、引揚げ列車から叩き出され、置き去りにされる。まだ10歳の少年は荷物もなくただ一人満州の荒野を縦断して1000キロ彼方の集合地へと歩き始める。ナイフ1本で彼は2カ月の旅を生き抜く。彼は母方のコサックの血を引いており、生き抜く意志を捨てない。彼は後に格闘技サンボのチャンピオンになり、世界に有名なサンボマスターとなる。この勇者の物語の裏に、他の民... [続きを読む]
北大ではどこにある?
第2次大戦が終わった翌年、満州に残った民間の日本人はやっと引き揚げることになった。日本人とロシア人の混血の少年(日本国籍)は一人で日本に渡ろうとする。ところが彼はロシア人だと大人の引揚者に荷物を奪われ、引揚げ列車から叩き出され、置き去りにされる。まだ10歳の少年は荷物もなくただ一人満州の荒野を縦断して1000キロ彼方の集合地へと歩き始める。ナイフ1本で彼は2カ月の旅を生き抜く。彼は母方のコサックの血を引いており、生き抜く意志を捨てない。彼は後に格闘技サンボのチャンピオンになり、世界に有名なサンボマスターとなる。この勇者の物語の裏に、他の民... [続きを読む] -
推薦者 : 佐藤 淳二 (文学研究科)
21世紀の人間は、ポスト・マラルメ主義者とならねばならない!
詩・イジチュール / マラルメ. - 筑摩書房, 2010
 北大ではどこにある?
ポスト・マラルメ主義とは何か? それは「従って」を切断する戦いの行動原則であり、革命理論である。しかし、その理論はまだその全容を現してはいない。若い世代がそれを実現していくことを期待されているのだ。
北大ではどこにある?
ポスト・マラルメ主義とは何か? それは「従って」を切断する戦いの行動原則であり、革命理論である。しかし、その理論はまだその全容を現してはいない。若い世代がそれを実現していくことを期待されているのだ。
その来るべき理論は、原因理由を表す接続詞で繋がる連鎖を革命的に断ち切り、世界を原因結果の連鎖、必然性の連関から解放する文化的政治的運動原理とならねばならない。それがポスト・マラルメ主義の根幹でなくてはならない!
「従って」は、われわれのあらゆる認識、文化、ひいては科学を形成する根幹の装置であるが、ここに爆薬を仕掛けた危険きわまりない... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
映像芸術の極致!
オルフェ(DVD,VHS) / ジャン・コクトー. - アイ・ヴィー・シー,
 北大ではどこにある?
フランスが生んだ万能の芸術家-その活動は詩、小説、音楽、絵画、舞台演出、映画に及ぶ拡がりを持つ-ジャン・コクトーの、まさに幻想・幻視芸術の粋を極めた作品である。この映画を高校生の時に初めてテレビで見たのだけれども、見終わって恥ずかしげもなく「ジャン・コクトーは天才だ!」と叫んでしまったことを覚えている。その後何回もこの映画を見てきたが、見るたびに上の感想は間違いなかったと感じている。
北大ではどこにある?
フランスが生んだ万能の芸術家-その活動は詩、小説、音楽、絵画、舞台演出、映画に及ぶ拡がりを持つ-ジャン・コクトーの、まさに幻想・幻視芸術の粋を極めた作品である。この映画を高校生の時に初めてテレビで見たのだけれども、見終わって恥ずかしげもなく「ジャン・コクトーは天才だ!」と叫んでしまったことを覚えている。その後何回もこの映画を見てきたが、見るたびに上の感想は間違いなかったと感じている。
物語は、ギリシャ神話のオルフェウスとエウリュディケーの悲劇を下敷きにしているが、コクトーの奔放不羈な想像力によって、生と死、詩人(芸術家)の運命、... [続きを読む] -
推薦者 : 高橋 英光 (文学研究科)
北大の全学教育から誕生した言語学の本
言葉のしくみー認知言語学のはなしー / 高橋英光. - 北海道大学出版会, 2010
 北大ではどこにある?
なぜ言葉は自分の思いをそのまま伝えてくれないのか、なぜ母語の学習はふつう成功するのに外国語の学習は失敗するのか、交通標識などの記号と言語の共通点は何か相違点は何か、日本語は特殊な言葉か否か、日本語のようなS0V言語と英語のようなSVO言語はどちらが多いのか、ヒトはなぜメタファーが好きなのか、「明日は忙しくて、ごめんなさい」はなぜ断りになるのか、そもそもなぜどの言語にも語彙と文法があるのか、などの疑問をもったことはないだろうか。
北大ではどこにある?
なぜ言葉は自分の思いをそのまま伝えてくれないのか、なぜ母語の学習はふつう成功するのに外国語の学習は失敗するのか、交通標識などの記号と言語の共通点は何か相違点は何か、日本語は特殊な言葉か否か、日本語のようなS0V言語と英語のようなSVO言語はどちらが多いのか、ヒトはなぜメタファーが好きなのか、「明日は忙しくて、ごめんなさい」はなぜ断りになるのか、そもそもなぜどの言語にも語彙と文法があるのか、などの疑問をもったことはないだろうか。
本書は、これらの疑問に触れながら言葉のしくみを丁寧に噛み砕いて説明する。豊富なエピソードとイラストを用い... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
一つの国を知るということ
オーストラリアの言語教育政策 / 青木麻衣子. - 東信堂, 2008
 北大ではどこにある?
オーストラリアという国は、私が小学生の頃(!)は「白豪主義」というキーワードとともに社会科で教えられていた。しかし、その後この国は「白豪主義」から「多文化主義」へと大きな方針転換を遂げることになる。本書は、オーストラリアの言語教育政策に焦点を絞って、上記の方針転換過程でそこに浮かび上がる「国家統合」と「多文化主義」の緊張関係を明らかにした労作である。しかし、ただ言語教育政策の検討だけでなく、(比較)教育研究や地域研究、マイノリティ研究に関してもこの本が提供してくれる知見は多い。広い意味での社会科学研究とは何かを、そしてまた、その方法... [続きを読む]
北大ではどこにある?
オーストラリアという国は、私が小学生の頃(!)は「白豪主義」というキーワードとともに社会科で教えられていた。しかし、その後この国は「白豪主義」から「多文化主義」へと大きな方針転換を遂げることになる。本書は、オーストラリアの言語教育政策に焦点を絞って、上記の方針転換過程でそこに浮かび上がる「国家統合」と「多文化主義」の緊張関係を明らかにした労作である。しかし、ただ言語教育政策の検討だけでなく、(比較)教育研究や地域研究、マイノリティ研究に関してもこの本が提供してくれる知見は多い。広い意味での社会科学研究とは何かを、そしてまた、その方法... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「倫理」は可能か?
支配と服従の倫理学 / 羽入辰郎. - ミネルヴァ書房, 2009
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
老いと社会のつながりを考える
暴走老人! / 藤原智美. - 文藝春秋, 2007
 北大ではどこにある?
最近、老人(高齢者)の犯罪がメディアで報道されることが多くなったように思う。老人が犯罪をするからメディアがニュースネタとして飛びつくのか、本当に老人の犯罪が増えているのかは慎重に考える必要があるだろう。しかし、少なくともこれまでの社会の(あるいはメディアの)あり方として、若者の犯罪や不作法には寛容ではなかった一方で老人の犯罪や不作法(特に後者)が大目に見られてきた面はある。このページを読んでいる人の中にも、町中での老人の振る舞いに「年寄りだから何でも許されるってわけじゃねーよ!」と思ったことがある人がそこそこいるに違いない(実は、... [続きを読む]
北大ではどこにある?
最近、老人(高齢者)の犯罪がメディアで報道されることが多くなったように思う。老人が犯罪をするからメディアがニュースネタとして飛びつくのか、本当に老人の犯罪が増えているのかは慎重に考える必要があるだろう。しかし、少なくともこれまでの社会の(あるいはメディアの)あり方として、若者の犯罪や不作法には寛容ではなかった一方で老人の犯罪や不作法(特に後者)が大目に見られてきた面はある。このページを読んでいる人の中にも、町中での老人の振る舞いに「年寄りだから何でも許されるってわけじゃねーよ!」と思ったことがある人がそこそこいるに違いない(実は、... [続きを読む] -
推薦者 : 佐藤 淳二 (文学研究科)
モーツァルトを思考しよう!
モーツァルト22 DVDボックス / . - ドイツグラモフォン,
 北大ではどこにある?
モーツアルトは、「感覚」で聴ける代表的な「天才音楽家」として受け取られてきたし、現に、「心で感じればいいんです、モーツァルトの音楽は!」というたぐいの、愚かな言葉たちによって、モーツァルトの思考は踏みにじられ続けている。植物さえもモーツァルトを流していれば生育がいいように、われわれの「脳」モーツァルトによって育つという虫のいい話が、まことしやかに流通している。
北大ではどこにある?
モーツアルトは、「感覚」で聴ける代表的な「天才音楽家」として受け取られてきたし、現に、「心で感じればいいんです、モーツァルトの音楽は!」というたぐいの、愚かな言葉たちによって、モーツァルトの思考は踏みにじられ続けている。植物さえもモーツァルトを流していれば生育がいいように、われわれの「脳」モーツァルトによって育つという虫のいい話が、まことしやかに流通している。
そうではない! モーツァルトの残したオペラを見るならば、そこに疑いもなく、鋭利な人間観察と皮肉な知性、そして何よりも深い無意識的とも言える世界への探求が、見ようと思う者... [続きを読む] -
推薦者 : 清水 誠 (文学研究科)
比較言語学の最前線
East and West. Papers in Indo-European Studies / Kazuhiko Yoshida, Brent Vine (eds.). - Ute Hempen, 2009
 北大ではどこにある?
インドからヨーロッパ全域までに広がり、世界中に伝播した印欧語は、私たちが学んでいる英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、スペイン語などをすべて含んだ世界最大の大言語群です。歴史的系統関係を同一にする印欧諸語は、古くからの豊富な文献を備え、グリム兄弟たちが活躍した19世紀にその礎が築かれました。これをもって、言語学が初めて独立した学問分野として誕生したのです。この本はその研究の最前線を日本のすぐれた研究者たちが主導しつつ、世界のトップレベルの研究者たちと共同研究した成果が再録されています。編者の吉田和彦先生は京都大学言語学科教授で、... [続きを読む]
北大ではどこにある?
インドからヨーロッパ全域までに広がり、世界中に伝播した印欧語は、私たちが学んでいる英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、スペイン語などをすべて含んだ世界最大の大言語群です。歴史的系統関係を同一にする印欧諸語は、古くからの豊富な文献を備え、グリム兄弟たちが活躍した19世紀にその礎が築かれました。これをもって、言語学が初めて独立した学問分野として誕生したのです。この本はその研究の最前線を日本のすぐれた研究者たちが主導しつつ、世界のトップレベルの研究者たちと共同研究した成果が再録されています。編者の吉田和彦先生は京都大学言語学科教授で、... [続きを読む] -
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
学際的研究の模範
光と視覚の科学―神話・哲学・芸術と現代科学の融合― / アーサー・ザイエンス. - 白掦社, 1997
 北大ではどこにある?
本書は物理学者であるザイエンスによる、一切のものの基礎にある光についての哲学、宗教、芸術など人間の知力と想像力を駆使して解明にせまる、通史としての学際的研究の著しい成功例である。光の解明に取り組む物理学者、哲学者、数学者たちの知的営為が彼らの人間性を知らせる興味深いエピソードとともに、わかりやすく解説されている。「あらゆる物理系の振る舞いの背後、あらゆる物理法則の背後に何があるのか」という問いが本書を読むことにより道理あるものとして受け止められるのは、事物の一切に浸透する光という形而上学的な対象の故にであろう。アインシュタイン... [続きを読む]
北大ではどこにある?
本書は物理学者であるザイエンスによる、一切のものの基礎にある光についての哲学、宗教、芸術など人間の知力と想像力を駆使して解明にせまる、通史としての学際的研究の著しい成功例である。光の解明に取り組む物理学者、哲学者、数学者たちの知的営為が彼らの人間性を知らせる興味深いエピソードとともに、わかりやすく解説されている。「あらゆる物理系の振る舞いの背後、あらゆる物理法則の背後に何があるのか」という問いが本書を読むことにより道理あるものとして受け止められるのは、事物の一切に浸透する光という形而上学的な対象の故にであろう。アインシュタイン... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「大学」の行く末を考えたい人に
学問の下流化 / 竹内洋. - 中央公論新社, 2008
 北大ではどこにある?
竹内洋の著書を既に何冊か読んでいる人が、その社会学的分析によって表題の「学問の下流化」という現象を理論的に解明し、その処方箋を論じたものであると期待して読むとやや肩すかしを喰います。これは別段否定的に評価しようというわけではなく、書評や短い評論の集成という書き方のスタイルに起因するもので、内容は広い意味での学問論や大学論を幅広く取り上げ、そのある種の病理的状況を竹内氏独特の切り口と語り口で捌いていくものになっています。「学問の下流化」そのものが全体的な主題とは言い難い面があるので、読み方によっては不満が残る面もあるかもしれませ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
竹内洋の著書を既に何冊か読んでいる人が、その社会学的分析によって表題の「学問の下流化」という現象を理論的に解明し、その処方箋を論じたものであると期待して読むとやや肩すかしを喰います。これは別段否定的に評価しようというわけではなく、書評や短い評論の集成という書き方のスタイルに起因するもので、内容は広い意味での学問論や大学論を幅広く取り上げ、そのある種の病理的状況を竹内氏独特の切り口と語り口で捌いていくものになっています。「学問の下流化」そのものが全体的な主題とは言い難い面があるので、読み方によっては不満が残る面もあるかもしれませ... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
芸術は人生を救済するか
虚空遍歴 / 山本周五郎. - 新潮社, 1966
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
read, weep, and live
二式大艇空戦記 -- 海軍801空搭乗員の死闘 / 長峯 五郎. - 光人社, 2006
 北大ではどこにある?
I picked up this book because I am a floatplane pilot (a floatplane is a plane that takes off and lands on water).
北大ではどこにある?
I picked up this book because I am a floatplane pilot (a floatplane is a plane that takes off and lands on water).
The wife of my good friend (also a floatplane pilot) was named Emily.
Emily is the code name given by the Allies to the Imperial Japanese Navy Type 2 Flying Boat.
Although readers of this book would be helped with a bit of aviation knowledge (the book does not explain how airplanes fly, nor how the Type 2 Flying Boat was built and flown), readers will not miss the anguish and dedication Goro Nagamine endured before, during, and after his kamikaze tokko attack.
No, he was not unafraid. No, he did not volunteer. No, he was not killed in action.
He was young, energetic, and full of life. Just like you.
Read an honest story of a young man, 21 years old on 15 August 1945... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「自分」の深奥をのぞく
砂漠の修道院 / 山形孝夫. - 平凡社, 1998
 北大ではどこにある?
ややもすれば抹香臭い表題ですが、エジプトの砂漠の修道院に引きつけられてきた人々の心の遍歴と葛藤、そのような心性を生み出すエジプトの社会と歴史が生き生きと描かれている、読み応えのある本です。特に修道士一人一人の聞き取り調査に基づくストーリーは、普段うかがい知ることが難しい「修道院」の生活と、そこに何かを求める魂のありようをキリスト教という枠組みを超えて明らかにしてくれます。キリスト者であってもなくてもここに描かれた修道士の誰かに、読者が共感できる人物を見つけることができると思います。「世間」と「自分」との葛藤をどう受け止めるかと... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ややもすれば抹香臭い表題ですが、エジプトの砂漠の修道院に引きつけられてきた人々の心の遍歴と葛藤、そのような心性を生み出すエジプトの社会と歴史が生き生きと描かれている、読み応えのある本です。特に修道士一人一人の聞き取り調査に基づくストーリーは、普段うかがい知ることが難しい「修道院」の生活と、そこに何かを求める魂のありようをキリスト教という枠組みを超えて明らかにしてくれます。キリスト者であってもなくてもここに描かれた修道士の誰かに、読者が共感できる人物を見つけることができると思います。「世間」と「自分」との葛藤をどう受け止めるかと... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
「大志」をこえるもの
キャッチャー・イン・ザ・ライ / J.D.サリンジャー著(村上春樹訳). - 白水社, 2006
 北大ではどこにある?
自分に対して誠実であろうとすればするほど社会の規範に従うことを潔しとしない、ということはよくあることです。ひとは年を重ねるにつれ、誠実さと従順さの間に折り合いをつけ、その折り合いをつけたことにも鈍感になってゆきます。これはまだ学校という擬似社会にもまれ始めたばかりの高校生のそういう事態に直面し挫折をくりかえすはなし。(挫折とは社会が強いるもののようです。)
北大ではどこにある?
自分に対して誠実であろうとすればするほど社会の規範に従うことを潔しとしない、ということはよくあることです。ひとは年を重ねるにつれ、誠実さと従順さの間に折り合いをつけ、その折り合いをつけたことにも鈍感になってゆきます。これはまだ学校という擬似社会にもまれ始めたばかりの高校生のそういう事態に直面し挫折をくりかえすはなし。(挫折とは社会が強いるもののようです。)
この16歳の少年は、ライ麦畑で「キャッチャー」になりたい、と言います。本文を読まないとその意味するところは明らかでありませんが、すでに大人びた体格の自分が弱い子を危険からまもる... [続きを読む] -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
映像文化論関係
ドキュメンタリーは嘘をつく / 森達也著. - 草思社, 2005.3
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
Detecting, correcting, and preventing academic dishonesty
Crisis on campus : confronting academic misconduct / Wilfried Decoo with a contribution by Jozef Colpaert. - MIT Press, 2002
 北大ではどこにある?
Unlike some schools, Hokudai does not ask its constituents to
北大ではどこにある?
Unlike some schools, Hokudai does not ask its constituents to
explicitly declare academic integrity.
Instead, the code of ethics is implicit.
The lack of declaration or affirmation is not by itself detrimental (although a formal ceremony or signing of a statement might add weight to the commitment).
The danger lies in two aspects.
(a) Risk of unfairness. Unspecified rules are difficult to apply consistently.
(b) Risk of reluctant compliance. Researchers who do not understand why such rules exist are less likely to abide by the spirit of the rules. Scientists who do not embrace high standards may view them as a bureaucratic hinderance, or worse, connive methods to
circumvent them.
This book explains several methods for sustaining academic integrity.
The authors were di... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
数学と人間と
The Mathematician's Brain / David Ruelle. - Princeton University Press, 2007
 北大ではどこにある?
数学という学問では論理的に正しい事柄、論理的に検証可能な事柄だけをもとめます。その論理にだけ注目すると数学はきわめて退屈な学問、形式的な学問といえそうです。(論理計算が正当化どうかを調べるには、記号の羅列が文法規則に従っているかどうかを見るだけでよくその意味を問う必要がないので、計算機にでもやらせることができるからです。)それでもギリシャ人はその前提となっていた自明の理を疑わず数学を真理の学問と神聖視しましたが、無限を取り扱う必要にかられた現代の数学者はそれほど幸せとはいえません。ほとんどの数学者のよりどころとしている自明の理... [続きを読む]
北大ではどこにある?
数学という学問では論理的に正しい事柄、論理的に検証可能な事柄だけをもとめます。その論理にだけ注目すると数学はきわめて退屈な学問、形式的な学問といえそうです。(論理計算が正当化どうかを調べるには、記号の羅列が文法規則に従っているかどうかを見るだけでよくその意味を問う必要がないので、計算機にでもやらせることができるからです。)それでもギリシャ人はその前提となっていた自明の理を疑わず数学を真理の学問と神聖視しましたが、無限を取り扱う必要にかられた現代の数学者はそれほど幸せとはいえません。ほとんどの数学者のよりどころとしている自明の理... [続きを読む]