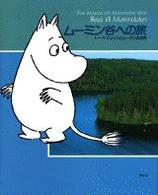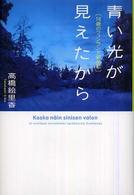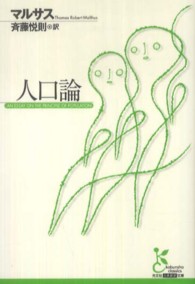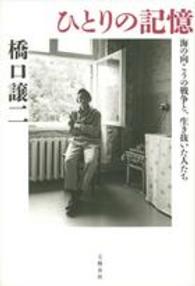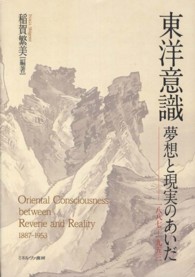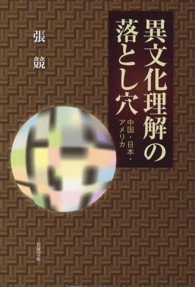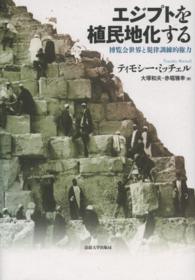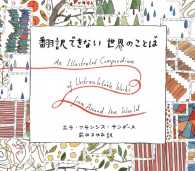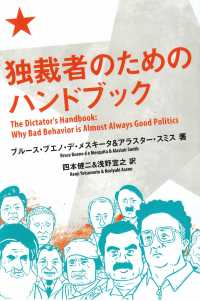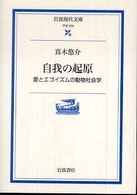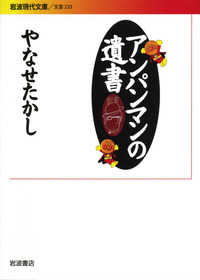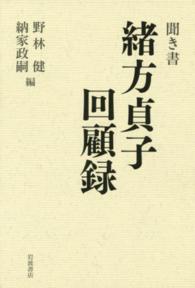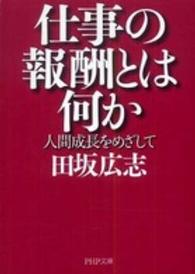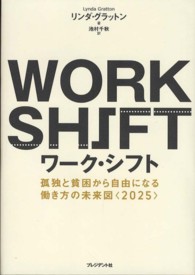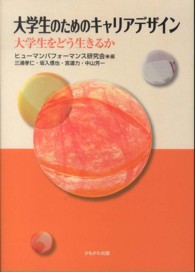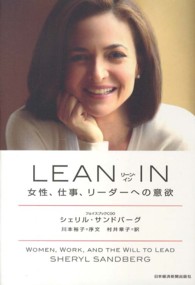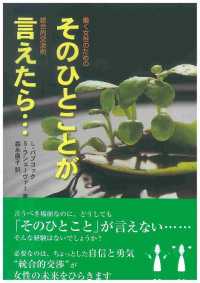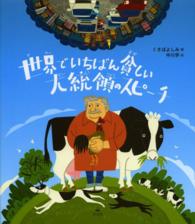-
推薦者 : 池田 文人 (高等教育推進機構・教員)
ムーミンワールドへようこそ!
ムーミン谷への旅 : トーベ・ヤンソンとムーミンの世界 / . - 講談社, 1994
 北大ではどこにある?
世界中で愛されるムーミン物語が生まれたフィンランドの魅力とともに、ムーミン物語の奥の深さも感じることができます。フィンランドの美しい景色の写真とムーミン物語の挿絵から、ムーミンたちの住む世界の風景を見て、音を聞き、空気を感じることができます。
北大ではどこにある?
世界中で愛されるムーミン物語が生まれたフィンランドの魅力とともに、ムーミン物語の奥の深さも感じることができます。フィンランドの美しい景色の写真とムーミン物語の挿絵から、ムーミンたちの住む世界の風景を見て、音を聞き、空気を感じることができます。 -
推薦者 : 田畑 伸一郎 (スラブ・ユーラシア研究センター・教員)
フィンランドの歴史を深く理解するための好著
「大フィンランド」思想の誕生と変遷 : 叙事詩カレワラと知識人 / 石野裕子著. - 岩波書店, 2012
 北大ではどこにある?
フィンランドの文化を知るうえで重要な叙事詩カレワラが同国の歴史において,あるいは同国が独立を遂げていくなかでどんな役割を果たしのかがよく分かります。フィンランドの歴史について思想面を含めて深く学びたい人にとって必読書です。
北大ではどこにある?
フィンランドの文化を知るうえで重要な叙事詩カレワラが同国の歴史において,あるいは同国が独立を遂げていくなかでどんな役割を果たしのかがよく分かります。フィンランドの歴史について思想面を含めて深く学びたい人にとって必読書です。 -
推薦者 : 池田 文人 (高等教育推進機構・教員)
感動します!
青い光が見えたから : 16歳のフィンランド留学記 / 高橋絵里香著. - 講談社, 2007
 北大ではどこにある?
北海道で育った著者が、中学校でいじめに会い、絶望の中で見た青い光・フィンランド。苦労してフィンランドの高校に入学し、フィンランド語に苦戦しながらも、高校を卒業し、大学へ進学します。日本とは違い、個性と自主性を尊重するフィンランドの人々に囲まれ、自分らしさを取り戻していきます。自分に素直になれる素晴らしさにきっと感動するでしょう。
北大ではどこにある?
北海道で育った著者が、中学校でいじめに会い、絶望の中で見た青い光・フィンランド。苦労してフィンランドの高校に入学し、フィンランド語に苦戦しながらも、高校を卒業し、大学へ進学します。日本とは違い、個性と自主性を尊重するフィンランドの人々に囲まれ、自分らしさを取り戻していきます。自分に素直になれる素晴らしさにきっと感動するでしょう。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
真実の発見に生涯をかけた医師のドラマ
手洗いの疫学とゼンメルワイスの闘い / 玉城英彦. - 人間と歴史社, 2017
 北大ではどこにある?
今年2月のある日、この本の著者である玉城英彦先生(現名誉教授)が僕の研究室に突然いらして、「中村先生、最近元気ないみたいだけどこの本を読めば元気になるよ」と仰言ってサイン入りの本をくださった。その頃そんなに元気がなさそうだったのか、自分では分からないのだけれども成績提出などのドタバタで疲れていたことは確かだ。折角頂いたご本なのだが、その後もあれこれと忙しく、5月になってからようやく読むことができた。そして、確かに少し元気になれたので、こうして推薦することにした次第である。
北大ではどこにある?
今年2月のある日、この本の著者である玉城英彦先生(現名誉教授)が僕の研究室に突然いらして、「中村先生、最近元気ないみたいだけどこの本を読めば元気になるよ」と仰言ってサイン入りの本をくださった。その頃そんなに元気がなさそうだったのか、自分では分からないのだけれども成績提出などのドタバタで疲れていたことは確かだ。折角頂いたご本なのだが、その後もあれこれと忙しく、5月になってからようやく読むことができた。そして、確かに少し元気になれたので、こうして推薦することにした次第である。
ゼンメルワイスと産褥熱の研究については、僕も中学生時代に読... [続きを読む] -
推薦者 : 小泉 均 (工学研究院・教員)
英語に関する素朴な疑問について、英語の歴史に基づき答える本
はじめての英語史 : 英語の「なぜ?」に答える / 堀田隆一. - 研究社, 2016
 北大ではどこにある?
英語に関する素朴な疑問について、英語の歴史に基づき答えている本である。なぜ母音で始まる単語の前の不定冠詞はanで子音で始まる単語の前はaなのか?(通常の英文法の解説とは逆で、oneの弱形のanがはじめにあり、子音で始まる単語では、子音が連続するためnが脱落した)、数詞oneに対して、なぜ1番目はfirstなのか?なぜ日本語では姓+名の順なのに、英語では名+姓の順なのかなど興味深い話題が多い。このような事を知らなくても、英語の習得には支障はないのかもしれない。しかし、そうなる理由がわかっている方が記憶に残るし、英語に対する興味が増す。英語の修得に、必ず... [続きを読む]
北大ではどこにある?
英語に関する素朴な疑問について、英語の歴史に基づき答えている本である。なぜ母音で始まる単語の前の不定冠詞はanで子音で始まる単語の前はaなのか?(通常の英文法の解説とは逆で、oneの弱形のanがはじめにあり、子音で始まる単語では、子音が連続するためnが脱落した)、数詞oneに対して、なぜ1番目はfirstなのか?なぜ日本語では姓+名の順なのに、英語では名+姓の順なのかなど興味深い話題が多い。このような事を知らなくても、英語の習得には支障はないのかもしれない。しかし、そうなる理由がわかっている方が記憶に残るし、英語に対する興味が増す。英語の修得に、必ず... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
言語をめぐる思惟を広く捉えるために
ドイツ言語哲学の諸相 / 麻生建. - 東京大学出版会, 1989
 北大ではどこにある?
以前奨めてくれる人があって、飯田隆『言語哲学大全Ⅰ~Ⅳ』(勁草書房)を読んでみたことがある。確かに現代の言語哲学、あるいは分析哲学をフレーゲからデヴィッドソンまで熱く語っている良書ではあるのだが、これをもって「大全」ということには大きな不満を覚える。その点は飯田氏も分かっているようで、第Ⅰ巻の冒頭で「『大全』というのは、さすがに私にしても調子に乗り過ぎという感がしないでもない」と書いている。この本を「大全」と言ってほしくないのは、対象がフレーゲとヴィトゲン... [続きを読む]
北大ではどこにある?
以前奨めてくれる人があって、飯田隆『言語哲学大全Ⅰ~Ⅳ』(勁草書房)を読んでみたことがある。確かに現代の言語哲学、あるいは分析哲学をフレーゲからデヴィッドソンまで熱く語っている良書ではあるのだが、これをもって「大全」ということには大きな不満を覚える。その点は飯田氏も分かっているようで、第Ⅰ巻の冒頭で「『大全』というのは、さすがに私にしても調子に乗り過ぎという感がしないでもない」と書いている。この本を「大全」と言ってほしくないのは、対象がフレーゲとヴィトゲン... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「日本語を教える」現場の熱気を伝える
世界の日本語教室から-日本を伝える30ヵ国の日本語教師レポート- / 国際交流基金. - アルク, 2009
 北大ではどこにある?
ここ何年か国際教育研究センターで(旧留学生センター時代から)全学教育科目に「外国人に日本語を教える」という「総合科目」を提供している。受講動機は様々であろうが日本語教育に関心を持ってくれる学生が一定数いるようで関係者としては有り難く思っている。この本は、そんな、日本語教育に関心を持っている学生がちょっとだけその―特に海外の―現場を覗いてみたいと思った時に気軽に読めるものとして紹介しておきたい。内容は、外務省の外郭団体である国際交流基金が世界各国に派遣した日本語教育専門家の手になる現地レポートである。日本語教育の現場の雰囲気を少しで... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ここ何年か国際教育研究センターで(旧留学生センター時代から)全学教育科目に「外国人に日本語を教える」という「総合科目」を提供している。受講動機は様々であろうが日本語教育に関心を持ってくれる学生が一定数いるようで関係者としては有り難く思っている。この本は、そんな、日本語教育に関心を持っている学生がちょっとだけその―特に海外の―現場を覗いてみたいと思った時に気軽に読めるものとして紹介しておきたい。内容は、外務省の外郭団体である国際交流基金が世界各国に派遣した日本語教育専門家の手になる現地レポートである。日本語教育の現場の雰囲気を少しで... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
イスラム教を「信じる」とはどのようなことか
日本の中でイスラム教を信じる / 佐藤兼永. - 文藝春秋社, 2015
 北大ではどこにある?
日本社会の中ではイスラム教信者、中でも特に日本人の信者というのは姿が見えにくい存在である。この本は、日本社会の中でイスラム教信仰に生きる人びとの姿を描いたルポルタージュであり、イスラム世界というものが西アジア・中東・アフリカという遠いところにある(だけな)のではなく、我々のすぐそばにもあるものだということに気づかせてくれる。現在、多少緩和されたとはいえ、まだイスラム教に対する様々な偏見が社会の中に存在することは否定できない。著者の佐藤氏は、その偏見を我々も持つことを認めた上でそれを肯定的なものへと転換する契機を示してくれている... [続きを読む]
北大ではどこにある?
日本社会の中ではイスラム教信者、中でも特に日本人の信者というのは姿が見えにくい存在である。この本は、日本社会の中でイスラム教信仰に生きる人びとの姿を描いたルポルタージュであり、イスラム世界というものが西アジア・中東・アフリカという遠いところにある(だけな)のではなく、我々のすぐそばにもあるものだということに気づかせてくれる。現在、多少緩和されたとはいえ、まだイスラム教に対する様々な偏見が社会の中に存在することは否定できない。著者の佐藤氏は、その偏見を我々も持つことを認めた上でそれを肯定的なものへと転換する契機を示してくれている... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
現代に活きる「古典」
人口論 / マルサス. - 光文社, 2011
 北大ではどこにある?
この『人口論』は、食糧供給と人口増加の関係を軸に貧困や失業や労働移動などの社会問題にどのように対応するべきかを考察した古典である。18世紀のイングランドが叙述の背景となっているが、マルサスが述べる考察は現代のアクチュアルな問題に通じるものであることを納得できるであろう。古典が現代に活きることを示すものとして薦めたい。
北大ではどこにある?
この『人口論』は、食糧供給と人口増加の関係を軸に貧困や失業や労働移動などの社会問題にどのように対応するべきかを考察した古典である。18世紀のイングランドが叙述の背景となっているが、マルサスが述べる考察は現代のアクチュアルな問題に通じるものであることを納得できるであろう。古典が現代に活きることを示すものとして薦めたい。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「ボランティア」のあり方を見つめ直すために
「ボランティア」の誕生と終焉 : 「贈与のパラドックス」の知識社会学 / 仁平典宏. - 名古屋大学出版会, 2011
 北大ではどこにある?
学生時代に7年ほどあるボランティア活動に携わっていたことがあるのだが、最初に活動に参加しようとした時、親に言われたのは「自分の頭のハエも追えない奴が偉そうに人助けなんかやるな!」という暴言(!)であった。今考えてもあんまりな言い方だと思うが、そうした意識は程度の差こそあれ日本の社会にある時期流通していたボランティア理解ではなかったかとも思う。この本の帯には「『善意』と『冷笑』の狭間で」と書かれているのだが、このことばはボランティアというものに対して注がれる、あるいは浴びせられる視線の複雑さを見事に言い当てている。そうした複雑さを... [続きを読む]
北大ではどこにある?
学生時代に7年ほどあるボランティア活動に携わっていたことがあるのだが、最初に活動に参加しようとした時、親に言われたのは「自分の頭のハエも追えない奴が偉そうに人助けなんかやるな!」という暴言(!)であった。今考えてもあんまりな言い方だと思うが、そうした意識は程度の差こそあれ日本の社会にある時期流通していたボランティア理解ではなかったかとも思う。この本の帯には「『善意』と『冷笑』の狭間で」と書かれているのだが、このことばはボランティアというものに対して注がれる、あるいは浴びせられる視線の複雑さを見事に言い当てている。そうした複雑さを... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
ネット空間で被害者にも加害者にもならないようにするために。
ネット炎上の研究 : 誰があおり、どう対処するのか / 田中辰雄, 山口真一著. - 勁草書房, 2016
 北大ではどこにある?
この本は、インターネット上で発生するいわゆる「炎上」という現象を分析し、その実態と歴史(!)と対応策を分かりやすく述べている。特に最後の「付録 炎上リテラシー教育のひな型」では、高校生を対象として想定し、「炎上」の仕組みとそれに巻き込まれそうになったらどうするべきかを丁寧に説いてくれている。インターネットがこれだけ広範囲に利用されるようになった社会で安全に生活し、かつ自分が加害者にならないためにも読んでおくべき1冊である。
北大ではどこにある?
この本は、インターネット上で発生するいわゆる「炎上」という現象を分析し、その実態と歴史(!)と対応策を分かりやすく述べている。特に最後の「付録 炎上リテラシー教育のひな型」では、高校生を対象として想定し、「炎上」の仕組みとそれに巻き込まれそうになったらどうするべきかを丁寧に説いてくれている。インターネットがこれだけ広範囲に利用されるようになった社会で安全に生活し、かつ自分が加害者にならないためにも読んでおくべき1冊である。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「戦争」を陳腐なことばで語らないために
ひとりの記憶 : 海の向こうの戦争と、生き抜いた人たち / 橋口譲二. - 文藝春秋, 2016
 北大ではどこにある?
この本は、太平洋戦争前後に植民地を含む海外に渡り、様々な事情でその地に残り、あるいは再渡航してそこで生き抜くことを選んだ人々からの聞き取りの記録である。現代に於ける戦争に対する反対・批判・抑止のことばの一つとして「戦争は人間の運命を狂わせる」といったものがある。それを否定するつもりはないし、そうした事例もあることを認めはするが、この本を読んだあとでここに描かれている人々の人生が戦争によって“狂った(あるいは狂わされた)”と―「戦争を知らない子供たち」である我々が―いうことには大きな躊躇いを覚えてしまう。その背後にあったはずのお... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、太平洋戦争前後に植民地を含む海外に渡り、様々な事情でその地に残り、あるいは再渡航してそこで生き抜くことを選んだ人々からの聞き取りの記録である。現代に於ける戦争に対する反対・批判・抑止のことばの一つとして「戦争は人間の運命を狂わせる」といったものがある。それを否定するつもりはないし、そうした事例もあることを認めはするが、この本を読んだあとでここに描かれている人々の人生が戦争によって“狂った(あるいは狂わされた)”と―「戦争を知らない子供たち」である我々が―いうことには大きな躊躇いを覚えてしまう。その背後にあったはずのお... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「東洋」と「西洋」とは何か、あらためて考える。
東洋意識 : 夢想と現実のあいだ1887-1953 / 稲賀繁美編著. - ミネルヴァ書房, 2012
 北大ではどこにある?
学問―特に人文科学―の世界に於ける「東洋-西洋」という枠組み或いは二分法は、実は相当にうさんくさい。そのうさんくささを“学問的に”剔抉したのは言うまでもなくエドワード・サイードの『オリエンタリズム』だったが、そのとらえ方自体が西洋的な学問世界の中で一定の権威になってしまうという戯画的な状況が生まれ、相変わらず「東洋-西洋」という枠組みをめぐる思索は混迷している。今回推薦する本は、編著者の稲賀氏自身が書いているように「『東洋』と呼ばれる―あるいは時代遅れとな... [続きを読む]
北大ではどこにある?
学問―特に人文科学―の世界に於ける「東洋-西洋」という枠組み或いは二分法は、実は相当にうさんくさい。そのうさんくささを“学問的に”剔抉したのは言うまでもなくエドワード・サイードの『オリエンタリズム』だったが、そのとらえ方自体が西洋的な学問世界の中で一定の権威になってしまうという戯画的な状況が生まれ、相変わらず「東洋-西洋」という枠組みをめぐる思索は混迷している。今回推薦する本は、編著者の稲賀氏自身が書いているように「『東洋』と呼ばれる―あるいは時代遅れとな... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
異文化理解はぼちぼちこのあたりから…。
異文化理解の落とし穴 : 中国・日本・アメリカ / 張競. - 岩波書店, 2011
 北大ではどこにある?
この本は、上海出身中国人で日本に留学し学位を得て日本で教職に就きアメリカで研究生活も送った著者の異文化体験の記録である。読後感としては標題にあるような「異文化理解」というレベルに達しているとは思えないし、ましてやその「落とし穴」を明解にしているとも言い切れない。むしろ表層的な体験と感想が連ねられているというのが率直なところである。しかし、それは裏を返せば、「異文化理解」ということに到達するには誰もがこの段階をくぐらなければならないということを示す一つの基準点になり得ている、ということであり、また、日本に限らず「文化」というもの... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、上海出身中国人で日本に留学し学位を得て日本で教職に就きアメリカで研究生活も送った著者の異文化体験の記録である。読後感としては標題にあるような「異文化理解」というレベルに達しているとは思えないし、ましてやその「落とし穴」を明解にしているとも言い切れない。むしろ表層的な体験と感想が連ねられているというのが率直なところである。しかし、それは裏を返せば、「異文化理解」ということに到達するには誰もがこの段階をくぐらなければならないということを示す一つの基準点になり得ている、ということであり、また、日本に限らず「文化」というもの... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
世界はどうしてこうなっているのか。
エジプトを植民地化する : 博覧会世界と規律訓練的権力 / ティモシー・ミッチェル著 ; 大塚和夫, 赤堀雅幸訳. - 法政大学出版局, 2014
 北大ではどこにある?
一見この本とは関係なさそうな話から推薦文を書く。みなさんは、観光旅行に行くとはどのようなことだと思っているだろうか。理由はいろいろあるにせよ、大きな共通点は世界遺産に代表されるような歴史的建造物や名所旧跡を辿ることが目的である、ということだろう。しかし、である。その時、観光旅行する我々は、実は名所旧跡を”見に”行っているのではなく、ガイドブックなどに一定の秩序で並べられた空間の”確認”をしに行っているに過ぎないのである。なぜそう言えるのか、の答えを与えてくれるのが、この本の副題になっている「博覧会世界」である。
北大ではどこにある?
一見この本とは関係なさそうな話から推薦文を書く。みなさんは、観光旅行に行くとはどのようなことだと思っているだろうか。理由はいろいろあるにせよ、大きな共通点は世界遺産に代表されるような歴史的建造物や名所旧跡を辿ることが目的である、ということだろう。しかし、である。その時、観光旅行する我々は、実は名所旧跡を”見に”行っているのではなく、ガイドブックなどに一定の秩序で並べられた空間の”確認”をしに行っているに過ぎないのである。なぜそう言えるのか、の答えを与えてくれるのが、この本の副題になっている「博覧会世界」である。
この本は、表題か... [続きを読む] -
推薦者 : 松田 康子 (教育学研究院・教員)
すべての学び手に
ケアの本質 : 生きることの意味 / ミルトン・メイヤロフ著 ; 田村真, 向野宣之訳. - ゆみる出版, 1987
 北大ではどこにある?
本書は、MILTON MAYEROFF著 On Caringの訳書です。対人援助職にとどまらず、すべてのケアの担い手にとって、ケアの営みにおいて常に立ち戻るべき本質が示されており、哲学書にしてはやさしい言葉で綴られている書物です。日本語も英語も一見すると、平易な言葉が並んでいるのですが、何度でも噛み締め味わうことができる論考です。高等教育機関において、「すべての学び手に」としてオススメしたい点は、メイヤロフが、ケアの対象を人のみならず、芸術、概念、理念というものにまで広げて考えているところです。メイヤロフは、ケアリングとは、ケアの受け手が他の誰かをケアできるよ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
本書は、MILTON MAYEROFF著 On Caringの訳書です。対人援助職にとどまらず、すべてのケアの担い手にとって、ケアの営みにおいて常に立ち戻るべき本質が示されており、哲学書にしてはやさしい言葉で綴られている書物です。日本語も英語も一見すると、平易な言葉が並んでいるのですが、何度でも噛み締め味わうことができる論考です。高等教育機関において、「すべての学び手に」としてオススメしたい点は、メイヤロフが、ケアの対象を人のみならず、芸術、概念、理念というものにまで広げて考えているところです。メイヤロフは、ケアリングとは、ケアの受け手が他の誰かをケアできるよ... [続きを読む] -
推薦者 : 武村 理雪 (国際連携機構・その他)
自身の問いを見つめなおす機会に
途上国の人々との話し方 : 国際協力メタファシリテーションの手法 / 和田信明, 中田豊一. - みずのわ出版, 2010
 北大ではどこにある?
途上国支援に限らず、様々な職業で活かすことのできる知識と技術を学べる書籍です。
北大ではどこにある?
途上国支援に限らず、様々な職業で活かすことのできる知識と技術を学べる書籍です。
実は私も本学の教員に薦められて読み始めました。自らの無知とコミュニケーション技術のなさを痛感させられた刺激的な書籍です。
責任と配慮をもって問いを発し、その問いをきっかけに希望が開かれるよう、この書籍を片手に精進していきたいと思わされました。
ある程度の業務経験があると、内容理解が進み易いだろうと推測します。一方で、今は十分に理解できない部分があったとしても、最後まで読んでみることで学生は将来の糧を得られるのではないかと思います。 -
推薦者 : 小俣 友輝 (URAステーション・その他)
言葉の違い、考え方の違いは面白い!
翻訳できない世界のことば / エラ・フランシス・サンダース著イラスト ; 前田まゆみ訳. - 創元社, 2016
 北大ではどこにある?
生まれたところ、住んでいるところが違えば、人の気持ちやことばも違ってくるようです。
北大ではどこにある?
生まれたところ、住んでいるところが違えば、人の気持ちやことばも違ってくるようです。
様々な国で使われていることばが表すものは、外国人である自分の想像を超えているにも関わらず、なるほどと思えるものでした。
新しいものの見方・考え方に触れられるのと同時に、ことばを使う世界の人々とのつながりをも感じるのでした。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
おじさんも、若い人も語学を楽しむために
おじさん、語学する / 塩田勉. - 集英社, 2001
 北大ではどこにある?
あるきっかけからフランス語を勉強することになったおじさんの奮闘記、という形をとって語学を身につけるための秘訣と、それだけでなく異文化との関わり方を気づかせてくれるユニークな本。語学大好きな人にも語学嫌いな人にもお薦めしたい。
北大ではどこにある?
あるきっかけからフランス語を勉強することになったおじさんの奮闘記、という形をとって語学を身につけるための秘訣と、それだけでなく異文化との関わり方を気づかせてくれるユニークな本。語学大好きな人にも語学嫌いな人にもお薦めしたい。
ただ、悲しいかな外国語の先生は日本語はお得意ではないようで、この中にも日本語の間違いが一箇所ある。探してみてほしい。 -
推薦者 : 野中 雄司 (附属図書館・職員)
これから「どう生きるか」を改めて考えたいときに
君たちはどう生きるか / 吉野源三郎. - 岩波書店, 1982
 北大ではどこにある?
この本は、軍国主義が勢力を強めつつあった昭和十二年に山本有三が少年少女向けに偏狭な国枠主義を越えた自由で豊かな文化のあることを伝えようとして編纂した『日本少国民文庫』シリーズ中の「倫理」を扱ったものです。私はこの少年少女向けの本を25歳を過ぎてから読みましたが、恥ずかしながら「勉強する意味」などハッとさせられる部分が多くあり感銘を受けました。読了後少し恥ずかしく思いつつ解説を読んでいると、なんとかの丸山眞男も大卒後東大法学部の助手になり研究者になった後に読み「私の魂をゆるがした」と記されており、驚いたのと同時にほっとしたことを覚... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、軍国主義が勢力を強めつつあった昭和十二年に山本有三が少年少女向けに偏狭な国枠主義を越えた自由で豊かな文化のあることを伝えようとして編纂した『日本少国民文庫』シリーズ中の「倫理」を扱ったものです。私はこの少年少女向けの本を25歳を過ぎてから読みましたが、恥ずかしながら「勉強する意味」などハッとさせられる部分が多くあり感銘を受けました。読了後少し恥ずかしく思いつつ解説を読んでいると、なんとかの丸山眞男も大卒後東大法学部の助手になり研究者になった後に読み「私の魂をゆるがした」と記されており、驚いたのと同時にほっとしたことを覚... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
やっぱり東京大学は凄い…。
アクティブラーニングのデザイン : 東京大学の新しい教養教育 / 永田敬, 林一雅編. - 東京大学出版会, 2016
 北大ではどこにある?
平成24年8月24日付中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~」に於いて、今後の中等教育・大学教育に積極的にアクティブ・ラーニング型授業を導入するべきであることが打ち出された。この本は、東京大学教養学部で実践されたアクティブラーニングの理念と方略を報告したものである。読者としては、これからアクティブラーニングに取り組もうとする大学教員を想定しているものであるが、学生が読んでも21世紀に求められる能力をどの... [続きを読む]
北大ではどこにある?
平成24年8月24日付中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~」に於いて、今後の中等教育・大学教育に積極的にアクティブ・ラーニング型授業を導入するべきであることが打ち出された。この本は、東京大学教養学部で実践されたアクティブラーニングの理念と方略を報告したものである。読者としては、これからアクティブラーニングに取り組もうとする大学教員を想定しているものであるが、学生が読んでも21世紀に求められる能力をどの... [続きを読む] -
推薦者 : 小浜 祥子 (公共政策学連携研究部・法学研究科・教員)
政治学の最先端理論を分かりやすく
独裁者のためのハンドブック / ブルース・ブエノ・デ・メスキータ, アラスター・スミス著 ; 四本健二, 浅野宜之訳. - 亜紀書房, 2013
 北大ではどこにある?
なぜ国民を弾圧し飢えさせる独裁者がこれほど長く権力の座に居続けるのか?なぜ往々にして、資源の豊かな国ほど国民が貧しいのか?対外援助は本当に人々を救うのか?なぜ民主主義国家はこれほど戦争に強いのか?
北大ではどこにある?
なぜ国民を弾圧し飢えさせる独裁者がこれほど長く権力の座に居続けるのか?なぜ往々にして、資源の豊かな国ほど国民が貧しいのか?対外援助は本当に人々を救うのか?なぜ民主主義国家はこれほど戦争に強いのか?
本書では、第一線で活躍する政治学者二人がこれらの謎を解き明かす。彼らがこの本を書いた理由は「問題に取り組む方法を学生に教えること、問題解決のための訓練をきちんとほどこしてから彼らを世の中に出すこと…自分が事態を良くしているのか、それとも悪くしているのかもわからず、ただものごとを掻き乱すだけの人間を、世界に送り出したくない」からだという... [続きを読む] -
推薦者 : 武藤 俊雄 (公共政策大学院・教員)
文系・理系区分なんてぶっ飛ばせ!
自我の起原 : 愛とエゴイズムの動物社会学 / 真木悠介. - 岩波書店, 2008
 北大ではどこにある?
日々更新されてゆく自然科学は、私たちに新しい生命や、人間の理解を提示してくれる。そうしたサイエンスとしての生命と人間の理解を、人文・社会科学の知見と自在に往復しながら、深く問いかけてくる名著である。学問領域の枠にとらわれない、生き生きとした精神の持ち主に読んで欲しい。
北大ではどこにある?
日々更新されてゆく自然科学は、私たちに新しい生命や、人間の理解を提示してくれる。そうしたサイエンスとしての生命と人間の理解を、人文・社会科学の知見と自在に往復しながら、深く問いかけてくる名著である。学問領域の枠にとらわれない、生き生きとした精神の持ち主に読んで欲しい。 -
推薦者 : 武藤 俊雄 (公共政策大学院・教員)
「市町村」はどう作られたか?
町村合併から生まれた日本近代 : 明治の経験 / 松沢裕作. - 講談社, 2013
 北大ではどこにある?
現在の市町村という、基本的な行政区分がどのような歴史的経緯で形成されてきたのかを、明治期の変革を中心に描いている本である。わが国の社会構成の基本単位が形成される過程には、近代へと向かう人々のダイナミックな動きが見て取れる。私たちが目にする社会の基本構造を支えている「基盤」のようなものの存在を知ることは、少子高齢化・人口減少という大きな変動期を迎える今、ここから先を見通す知的な武器になるだろう。
北大ではどこにある?
現在の市町村という、基本的な行政区分がどのような歴史的経緯で形成されてきたのかを、明治期の変革を中心に描いている本である。わが国の社会構成の基本単位が形成される過程には、近代へと向かう人々のダイナミックな動きが見て取れる。私たちが目にする社会の基本構造を支えている「基盤」のようなものの存在を知ることは、少子高齢化・人口減少という大きな変動期を迎える今、ここから先を見通す知的な武器になるだろう。 -
推薦者 : 小浜 祥子 (公共政策学連携研究部・法学研究科・教員)
突如として権力者が消えた世界、そこで何が起こるか
別荘 : Casa de campo / ホセ・ドノソ著 ; 寺尾隆吉訳. - 現代企画室, 2014
 北大ではどこにある?
権力と自由こそ、政治学におけるメインテーマである。チリの作家ホセ・ドノソの傑作『別荘』では、ある小国で栄華を誇るベントゥーラ家の大人たちがピクニックに出かけ、33人の子どもたちだけが別荘に残される。突如として権力者が消えてしまった世界で、何が起こるのか。本作は1973年にチリで起こったアウグスト・ピノチェト将軍によるクーデターに着想を得て執筆されたものと言われている。ぜひ自分を取り巻く権力と自由に思いを馳せながら、このドラマチックな小説を楽しんでほしい。チリや中南米の政治史を学べばよりいっそう味わい深いに違いない。
北大ではどこにある?
権力と自由こそ、政治学におけるメインテーマである。チリの作家ホセ・ドノソの傑作『別荘』では、ある小国で栄華を誇るベントゥーラ家の大人たちがピクニックに出かけ、33人の子どもたちだけが別荘に残される。突如として権力者が消えてしまった世界で、何が起こるのか。本作は1973年にチリで起こったアウグスト・ピノチェト将軍によるクーデターに着想を得て執筆されたものと言われている。ぜひ自分を取り巻く権力と自由に思いを馳せながら、このドラマチックな小説を楽しんでほしい。チリや中南米の政治史を学べばよりいっそう味わい深いに違いない。 -
推薦者 : 宮本 淳 (高等教育推進機構・教員)
「少年よ、迷い悩め」
アンパンマンの遺書 / やなせたかし. - 岩波書店, 2013
 北大ではどこにある?
この本のタイトルにちょっとドキッとした人もいるかもしれません。「遺書」とありますし、この本の著者で、アンパンマンの作者であるやなせたかしさんは、2013年10月13日に94歳で永眠されています。でも、タイトルを見て是非読んでみたいと思った人もいませんか?小さいころ大好きだったアンパンマンの遺書?!何が書かれているのだろう...ちなみに絵本ではありません。推薦する私がこの本を読んだ理由は2つです。ひとつは、私の実家が高知県にあること。高知県はやなせさんの出身地です。私は高知で暮らしたことがありませんが、両親がリタイヤ後に自分たちのふるさとである... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本のタイトルにちょっとドキッとした人もいるかもしれません。「遺書」とありますし、この本の著者で、アンパンマンの作者であるやなせたかしさんは、2013年10月13日に94歳で永眠されています。でも、タイトルを見て是非読んでみたいと思った人もいませんか?小さいころ大好きだったアンパンマンの遺書?!何が書かれているのだろう...ちなみに絵本ではありません。推薦する私がこの本を読んだ理由は2つです。ひとつは、私の実家が高知県にあること。高知県はやなせさんの出身地です。私は高知で暮らしたことがありませんが、両親がリタイヤ後に自分たちのふるさとである... [続きを読む] -
推薦者 : 増田 哲子 (メディア・コミュニケーション研究院・教員)
選択をする「自分」について知ること
おとなの進路教室。 / 山田ズーニー. - 河出書房新社, 2007
 北大ではどこにある?
著者の山田ズーニーさんは、企業や大学でコミュニケーションや文章表現についての研修・教育を行っている方です。著者自身、30代後半に教育系の大手出版社を辞め、独立という大きな選択をしました。
北大ではどこにある?
著者の山田ズーニーさんは、企業や大学でコミュニケーションや文章表現についての研修・教育を行っている方です。著者自身、30代後半に教育系の大手出版社を辞め、独立という大きな選択をしました。
大学進学、就職、転職といったさまざまな進路選択において、選ぶ基準となる自分自身の気持ちをどのように掘り下げ、どのように表現するのか?本書は、こうした問いについて、著者自身の経験や著者が出会ったさまざまな人たちのケースから考えさせてくれます。
人生のなかで、進路選択は1回きりではありません。高校進学、大学進学、就職の後も、まだまだ選択の機... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (外国語教育センター・教員)
大名の生活を英語で説明しよう
The life and culture of samurai lords : masterworks from the Tokugawa Art Museum / The Tokugawa Art Museum. - 徳川美術館, 2016
 北大ではどこにある?
諸君、和服が着られるかな?女の子なら振袖を着た経験があるだろうか?男の子なら羽織・袴。しかし所有していない人も多いのでは?まさか着方を知らない?日本の民俗衣裳だぞ。しかも意外と安いのもある。
北大ではどこにある?
諸君、和服が着られるかな?女の子なら振袖を着た経験があるだろうか?男の子なら羽織・袴。しかし所有していない人も多いのでは?まさか着方を知らない?日本の民俗衣裳だぞ。しかも意外と安いのもある。
さてさて。日本の文化を英語で説明できれば、日本の文化を知っているといえるだろうし、日本の文化を知ってもらう力を有しているともいえるだろう。
本書は、御三家大名のひとつ尾張名古屋の徳川藩ゆかりの徳川美術館が著した、大名生活の英語による説明だ。日本を知り、日本を知ってもらう力を身につけよう。 -
推薦者 : 髙橋 彩 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
仕事・生き方を模索するあなたに
聞き書緒方貞子回顧録 / 緒方貞子 [述] ; 野林健, 納家政嗣編. - 岩波書店, 2015
 北大ではどこにある?
本書をあえてキャリア支援の書として紹介したい。
北大ではどこにある?
本書をあえてキャリア支援の書として紹介したい。
国連難民高等弁務官として様々な難局に立ち向かった緒方貞子氏には数々の賞賛があろう。また、本書は国際政治学、外交史、国際関係論など、いくつかの分野で貴重な資料ともなろう。
しかし、ここでは緒方氏の人生が一人の人間と歩みとして描かれていることに注目したい。
心あるその人が、仕事の各局面で、何を考え、どのような意思を持って、どう行動したのか。分野や進路を問わず、今後、社会の未来とどう向き合っていくのかを、読者自身が問われているようだ。 -
推薦者 : 小林 和也 (高等教育推進機構オープンエデュケーションセンター・職員)
生き方について考えることをやめて何らかの実験を生きるには
千のプラトー : 資本主義と分裂症 / ジル・ドゥルーズ, フェリックス・ガタリ [著] ; 宇野邦一 [ほか] 訳. - 河出書房新社, 1994
 北大ではどこにある?
生き方がわからないなんて不思議なお話だ。だって君は現に生きているのに? それでも問うてみたくなるのはなぜだろう。生きているのは苦しいし、悩みは耐えない。だからなぜこんなに苦労してまで生き続けなければならないの? どう生きればいい?と問いたくなるものだ。
北大ではどこにある?
生き方がわからないなんて不思議なお話だ。だって君は現に生きているのに? それでも問うてみたくなるのはなぜだろう。生きているのは苦しいし、悩みは耐えない。だからなぜこんなに苦労してまで生き続けなければならないの? どう生きればいい?と問いたくなるものだ。
こういう時はたいてい「生き方」なんていう言葉遣いが分析・分節されてつくしていないからだ。こういう乱暴な言葉遣いには気をつけたほうがいい。「生き方」が違うから分かり合えません。じゃあどうやって人とやっていくのさ?
言葉を分析するには、どうしたらいいだろう。こう考えることはで... [続きを読む] -
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
関西弁のゾウの神様に教わる人生で大事なこと
夢をかなえるゾウ / 水野敬也. - 飛鳥新社, 2011
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 加藤 真樹 (大学力強化推進本部 / 理学研究院・職員)
生物学をベースにしたムツゴロウさんのSF小説
海からきたチフス / 畑正憲. - 角川書店, 1973
 北大ではどこにある?
動物王国のムツゴロウさんこと畑正憲氏が初めて書いたSF小説。離島で起きた無細胞生物「ヌル」による不思議な事件の謎に生物好きの家族が挑むサイエンスフィクションです。ムツゴロウさん自身、東京大学で生理学を学んでいたこともあり、細胞生物学の知見をちりばめた謎解きは今読んでみても面白いです。
北大ではどこにある?
動物王国のムツゴロウさんこと畑正憲氏が初めて書いたSF小説。離島で起きた無細胞生物「ヌル」による不思議な事件の謎に生物好きの家族が挑むサイエンスフィクションです。ムツゴロウさん自身、東京大学で生理学を学んでいたこともあり、細胞生物学の知見をちりばめた謎解きは今読んでみても面白いです。 -
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
仕事の報酬は”収入・能力・仕事・成長”
仕事の報酬とは何か : 人間成長をめざして / 田坂広志. - PHP研究所, 2008
 北大ではどこにある?
「働かない人生なんてあり得ない?!」
北大ではどこにある?
「働かない人生なんてあり得ない?!」
「何のために働くのか?」という問いに、シンプルかつ本質的に答えています。
「仕事には、目に見える報酬と目に見えない報酬がある」仕事の報酬とは「収入・能力・仕事・成長」~気になった方は是非、読んでみてください。
仕事とはそもそも何なのか自分なりに答えを見つけたい方、将来仕事と子育て(家庭)の両立で悩むかも、、、と漠然と思っている方、おススメです。
働いて何年たって読み返しても、自分がその仕事をする目的やモチベーションを再確認することができる良本です。
-
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
2025年、働き方はどうなっているか?
ワーク・シフト : 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図「2025」 = Work shift / リンダ・グラットン著 ; 池村千秋訳. - プレジデント社, 2012
 北大ではどこにある?
”2025年”に、今大学生の皆さんは、ちょうど30歳前後です。あなたはその時、どのような働き方をしていますか?
北大ではどこにある?
”2025年”に、今大学生の皆さんは、ちょうど30歳前後です。あなたはその時、どのような働き方をしていますか?
自分の親世代の常識から、働き方の常識が大きく変わってきています。大きく3つのシフトが予測されています。「食えるだけの仕事」から意味を感じる仕事へ。忙しいだけの仕事から価値ある経験としての仕事へ。勝つための仕事からともに生きるための仕事へ。
現在40代の私の世代でも、既にその変化は広がっています。
自然に見聞きする情報だけで将来を考えてはもったいない。未来への理解を深め、幸せに生きるための働き方に興味がある方はぜひ、読ん... [続きを読む] -
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
将来のキャリアと”今”をつなげよう
大学生のためのキャリアデザイン : 大学生をどう生きるか / ヒューマンパフォーマンス研究会編 ; 三浦孝仁 [ほか執筆]. - かもがわ出版, 2013
 北大ではどこにある?
学生向けに書かれた「キャリア」本が各種ある中で、キャリア開発の考え方と学びつつ「学生時代の今をどう過ごすか?」についての指南を与えてくれる本です。
北大ではどこにある?
学生向けに書かれた「キャリア」本が各種ある中で、キャリア開発の考え方と学びつつ「学生時代の今をどう過ごすか?」についての指南を与えてくれる本です。
大学生の時期は、自分を理解し、自己管理能力を身につける大変良い時期です。やみくもに努力するよりも、キャリア開発の知識を持ったうえでの努力の方が、より成長につながると思います。
-
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
フィールドワークと出産・育児の両立ノウハウ
女も男もフィールドへ / 椎野若菜, 的場澄人編. - 古今書院, 2016
 北大ではどこにある?
野生動物の研究、地球や環境科学の研究、言語学の研究、文化人類学の研究まで、調査対象を求めて世界各地に出かけるフィールドワークはたくさんあります。フィールドワークとと出産・育児って両立できるの?どうやって?という疑問に、様々な分野のフィールドワーカーが実例で答えてくれています。研究者の仕事に興味がある方、女性に不利(?)と思われがちな分野での仕事に興味がある方、ヒントがたくさん詰まっていますよ。
北大ではどこにある?
野生動物の研究、地球や環境科学の研究、言語学の研究、文化人類学の研究まで、調査対象を求めて世界各地に出かけるフィールドワークはたくさんあります。フィールドワークとと出産・育児って両立できるの?どうやって?という疑問に、様々な分野のフィールドワーカーが実例で答えてくれています。研究者の仕事に興味がある方、女性に不利(?)と思われがちな分野での仕事に興味がある方、ヒントがたくさん詰まっていますよ。 -
推薦者 : 小林 和也 (高等教育推進機構オープンエデュケーションセンター・職員)
ゾーンへの招待
ストーカー / アルカジイ・ストルガツキー,ボリス・ストルガツキー著 ; 深見弾訳. - 早川書房, 1983
 北大ではどこにある?
アンドレイ・タルコフスキー監督による映画のほうが有名かもしれないが、この原作もまた偉大な文学作品だ。
北大ではどこにある?
アンドレイ・タルコフスキー監督による映画のほうが有名かもしれないが、この原作もまた偉大な文学作品だ。
本作は通常SFとされる。しかしそれだけではない。戦争や核汚染後の世界のメタファーとも言える突如現れた謎の危険地帯「ゾーン」。ストーカーはそこに侵入して、異星人が残したとされる異物を採取する。ストーカーとは何者であるのか? この問いに対する答えを、主人公レドリックの述懐に読み取ることができなければ、それはこの本との出会い損ね、悲しい接触と言わざるをえない。 -
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
社会は理不尽だ、、、それでも一歩踏み出そう!
Lean in (リーン・イン) : 女性、仕事、リーダーへの意欲 / シェリル・サンドバーグ著 ; 村井章子訳. - 日本経済新聞出版社, 2013
 北大ではどこにある?
ある社会的に成功した女性の個人の経験をもとにしていますが、その時に感じた「壁」について、様々な統計と理論から多面的に考察しています。社会には女性にとって理不尽なことがまだまだたくさんあります。何故、理不尽を感じるのか?その仕組みについても解説されています。ひとつひとつの理不尽に対して「それは不公正である」ことを社会に伝える努力と、理不尽な現実を前提として自分がどう考え行動していくか、個人の戦略としての努力のどちらも必要ですが、それらをバランス考えていくことが大事だ、ということが分かる内容です。
北大ではどこにある?
ある社会的に成功した女性の個人の経験をもとにしていますが、その時に感じた「壁」について、様々な統計と理論から多面的に考察しています。社会には女性にとって理不尽なことがまだまだたくさんあります。何故、理不尽を感じるのか?その仕組みについても解説されています。ひとつひとつの理不尽に対して「それは不公正である」ことを社会に伝える努力と、理不尽な現実を前提として自分がどう考え行動していくか、個人の戦略としての努力のどちらも必要ですが、それらをバランス考えていくことが大事だ、ということが分かる内容です。 -
推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)
女性を”交渉が苦手”にさせているメカニズムとは?
そのひとことが言えたら… : 働く女性のための統合的交渉術 / L.バブコック, S.ラシェーヴァー著 ; 森永康子訳. - 北大路書房, 2005
 北大ではどこにある?
女子学生の皆さんに質問です。
北大ではどこにある?
女子学生の皆さんに質問です。
「自分のほしいものを欲しいと言えますか?」
「自分にふさわしい評価を求めていますか?」?”
「パートナー(彼氏)に、フェアじゃないと思いつつ、何となく料理や家事を提供する側になっていませんか?」
それは「女性は自分の気持ちを抑えるように周囲から期待され、気づかないうちにその期待に沿うように行動してしまっている」場合があるからです。その仕組みを理解してはじめて「どうすればよいか?」「どのように言えば良いか?」How toが役に立ちます。
男子3人を育てている親として、女子も男子も「幸せなパートナーシップ」を築き... [続きを読む] -
推薦者 : 池見 真由 (経済学研究科・教員)
今日の経済と社会と自分を見つめ直す
世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ / [ムヒカ述] ; くさばよしみ編 ; 中川学絵. - 汐文社, 2014
 北大ではどこにある?
「経済」とは元々、お金を儲けることや利潤を増やすことではなく、経世済民、つまり世の中をうまく経(おさ)めて民を救済する・幸せにすることが本来の意味だったと思います。
北大ではどこにある?
「経済」とは元々、お金を儲けることや利潤を増やすことではなく、経世済民、つまり世の中をうまく経(おさ)めて民を救済する・幸せにすることが本来の意味だったと思います。
あなたは、ホセ・ムヒカ氏の立ち振る舞いや言葉に感銘し、彼の考え方を理解し、共感できる人であるでしょうか?
そしてあなたは、現在の世界経済や国際社会のあり方に興味関心を向け、「こんなんじゃだめだ」と、自分のことのように危機感を感じられる人であるでしょうか?
もしそうであれば、あなたは私にとって見ず知らずの他人ですが、それでも、自分のことのようにとても嬉しいです。
こんな... [続きを読む]