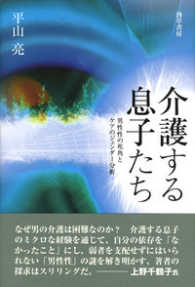推薦者: 中村 重穂
所属: 国際連携機構国際教育研究センター
身分: 教員
研究分野: 日本語教育史、意味論
不愉快な、しかし有益な本
タイトル(書名):
介護する息子たち : 男性性の死角とケアのジェンダー分析
著者:
平山亮
出版者:
勁草書房
出版年:
2017
ISBN:
4326654058
北大所蔵:
推薦コメント
これを書いている僕は3月31日付けで北海道大学を退職する。理由は介護離職、つまりこの本の標題にもなっている「介護する息子」になるわけだ。この本は、そのような「介護する息子」になる前に参考とするべき点を調べようと思って読んだのだが、内容は全く違っていて、所謂ジェンダー社会学の立場から「介護する息子」たちが一見親の介護で苦労しているように見えながら、その背後には女性(配偶者や姉妹)からの支援や女性に対する差別やジェンダー的不均衡があるという可視性の低い問題点をこれでもかとばかりに暴き出す研究書だった。
考えてみれば著者の平山氏は上野千鶴子の門下と書いてあるから、男性優位社会の批判と女性差別を告発・批判する論調になっていて何ら不思議はないと読んでから気がついた。
この本が“学術的に”解明していることはおそらくその通りだろうと思う。しかし、これから職を辞して「介護する息子」になろうとする僕にとっては、実際の介護の場面に直結して役に立つことは少なく、著者の平山氏の“私は女性の味方です”的な意識が見え隠れして些か不快だった。以前、「本は脳を育てる」に推薦した『砂漠の修道院』(平凡社)の中で著者の山形孝夫先生が「悲しみの分析によって悲しみが癒やされることがない」と書いていらしたように、これから介護の現場に直面する人間にとっては想定される介護の苦労を何ら軽減してくれるものではなかったが、―繰り返すけれども―ジェンダー社会学の研究書としては、表から見えにくい息子介護の現場での男女間の不均衡とその原因を緻密に解明している点で学ぶところの多い本であり、そのような問題に関心を持つ学生には一読を薦めたい。
但し、現在介護に関わっている人やこれから介護に関わることになる人にとっては東田勉『親の介護をする前に読む本』(講談社現代新書)の方が遙かに具体的に役に立つ本であることを付言しておく。
考えてみれば著者の平山氏は上野千鶴子の門下と書いてあるから、男性優位社会の批判と女性差別を告発・批判する論調になっていて何ら不思議はないと読んでから気がついた。
この本が“学術的に”解明していることはおそらくその通りだろうと思う。しかし、これから職を辞して「介護する息子」になろうとする僕にとっては、実際の介護の場面に直結して役に立つことは少なく、著者の平山氏の“私は女性の味方です”的な意識が見え隠れして些か不快だった。以前、「本は脳を育てる」に推薦した『砂漠の修道院』(平凡社)の中で著者の山形孝夫先生が「悲しみの分析によって悲しみが癒やされることがない」と書いていらしたように、これから介護の現場に直面する人間にとっては想定される介護の苦労を何ら軽減してくれるものではなかったが、―繰り返すけれども―ジェンダー社会学の研究書としては、表から見えにくい息子介護の現場での男女間の不均衡とその原因を緻密に解明している点で学ぶところの多い本であり、そのような問題に関心を持つ学生には一読を薦めたい。
但し、現在介護に関わっている人やこれから介護に関わることになる人にとっては東田勉『親の介護をする前に読む本』(講談社現代新書)の方が遙かに具体的に役に立つ本であることを付言しておく。
※推薦者のプロフィールは当時のものです。