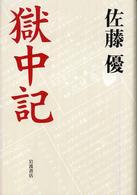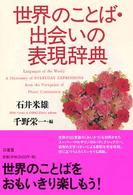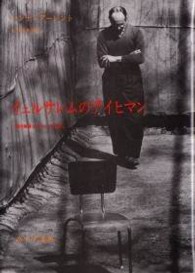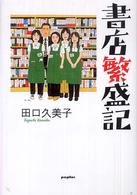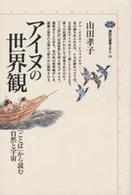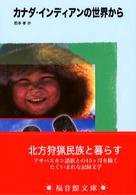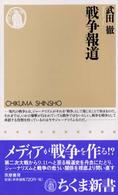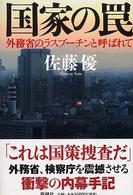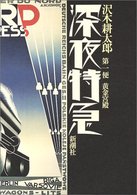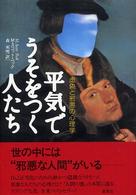-
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
人文学はどのようなひとを育てるか
哲学修業時代 / H.G.ガーダマー (中村志朗訳). - 未来社 , 1982
 北大ではどこにある?
本書は哲学、そして広くは文学、神学などを含む人文学一般への、生き生きした人物評伝を媒介にしたものとしては、最良の入門書であろう。1900年ドイツ生まれという著者が生きたその時代が人類史においても特筆すべき時代であったことからくる興味深さもさることながら、本書は人文学を学んだひとはどのようなひととなり、そしてどのように人々と交わるかを、さらに人間を愛情をもってどれほど豊かなものとして、また正確さにおいて説得的なものとして描きうるかをいかんなく伝えている。それにしても彼の交流のなんと豊かなことか、P.ナトルプ、E.フッサール、N.ハルトマン、R.... [続きを読む]
北大ではどこにある?
本書は哲学、そして広くは文学、神学などを含む人文学一般への、生き生きした人物評伝を媒介にしたものとしては、最良の入門書であろう。1900年ドイツ生まれという著者が生きたその時代が人類史においても特筆すべき時代であったことからくる興味深さもさることながら、本書は人文学を学んだひとはどのようなひととなり、そしてどのように人々と交わるかを、さらに人間を愛情をもってどれほど豊かなものとして、また正確さにおいて説得的なものとして描きうるかをいかんなく伝えている。それにしても彼の交流のなんと豊かなことか、P.ナトルプ、E.フッサール、N.ハルトマン、R.... [続きを読む] -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
「考える」という営みへの最良の入門書
哲学、脳を揺さぶる / 河本英夫. - 日経BP, 2007
 北大ではどこにある?
分類すれば哲学という分野に入るのだろうが、思考のエクササイズはもとより、芸術あり、科学あり、身体論あり、イメージ論あり、認知論あり、といった具合に間口はひろく、総合的であり、そして(多少は苦労もしながら)ひとたび読み終わってみれば、脳は活性化し、何やらいっぱしの知的ナヴィゲーションをしてきた充実感が得られること間違いなし。著者は、「考える」という人間の不思議なイトナミに深く広く分け入らんとする先端的な探求者のひとり。大学生たる者、たまにはこうした本を読みこなさなくちゃ。
北大ではどこにある?
分類すれば哲学という分野に入るのだろうが、思考のエクササイズはもとより、芸術あり、科学あり、身体論あり、イメージ論あり、認知論あり、といった具合に間口はひろく、総合的であり、そして(多少は苦労もしながら)ひとたび読み終わってみれば、脳は活性化し、何やらいっぱしの知的ナヴィゲーションをしてきた充実感が得られること間違いなし。著者は、「考える」という人間の不思議なイトナミに深く広く分け入らんとする先端的な探求者のひとり。大学生たる者、たまにはこうした本を読みこなさなくちゃ。 -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
人は弱いものらしい
The Lucifer Effect -- Understanding How Good People Turn Evil / Philip Zimbardo. - Random House, 2007
 北大ではどこにある?
最近の日本政府は先の大戦で我国の犯した残虐行為を軽視する傾向にあるようです。先ごろも、「従軍慰安婦の募集は軍部の強制によるのではない」という発言をしたひとが、米国で物議をかもすと、わざわざ向こうの大統領の前で釈明し「その謝罪を受け入れる」というお墨付きをもらうという訳のわからないことがありました。
北大ではどこにある?
最近の日本政府は先の大戦で我国の犯した残虐行為を軽視する傾向にあるようです。先ごろも、「従軍慰安婦の募集は軍部の強制によるのではない」という発言をしたひとが、米国で物議をかもすと、わざわざ向こうの大統領の前で釈明し「その謝罪を受け入れる」というお墨付きをもらうという訳のわからないことがありました。
正直なところこの問題は当時の日本の犯した犯罪行為としては軽微な方だったのではないかと思われます。それよりも、たとえば強制労働のほうが問題です。これは規模も大きく死亡率も(他国の同様の場合と比べ)かなり高かったようです。さらに、これが... [続きを読む] -
推薦者 : 清水 誠 (文学研究科)
未知の言語の全体像が手に取るようにわかる
「言葉のしくみ」シリーズ / . - 白水社, 2005-
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 吉野 悦雄 (経済学研究科)
正しい日本語を書くために
日本語文法セルフ・マスターシリーズ / 寺村秀夫企画・編集 全7巻 / 野田尚史 ほか. - くろしお出版, 1986
 北大ではどこにある?
問 次の(1)〜(4)のうち日本語として誤っているものを選びない(複数回答可)。
北大ではどこにある?
問 次の(1)〜(4)のうち日本語として誤っているものを選びない(複数回答可)。
(1)今日の夜は図書館は何時まで開いていますか。
(2)今日の夜は図書館が何時まで開いていますか。
(3)象の鼻は長い。
(4)象は鼻が長い。
この解(正解はこの文章の最後にあります)を間違えた方,少し考えこんだ方には次の全7巻の本,特に第1巻をお薦めします。出版者などは上記のとおりです。
第1巻 はとが / 野田尚史著
第2巻 する・した・している / 砂川有里子... [続きを読む] -
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
心理学と人類学のコラボレーション
集団生活の論理と実践―互恵性を巡る心理学と人類学的検討 / 煎本孝、高橋伸幸、山岸俊男(編著). - 北海道大学出版会, 2007年
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 須田 勝彦 (教育学部)
論理学とは何か
論理学―思考の法則と科学の方法 / 鰺坂 真他. - 世界思想社, 1987年
 北大ではどこにある?
論理学は,アリストテレスの時代から現代まで,変容を遂げながら進化を続けてきている。「論理的思考とは何か」を考えるためにはやはり論理学についての認識が必要だろう。この書は,哲学における論理と,数学の一領域となった記号論理学との,ほどよい橋渡しとなってくれるだろう。
北大ではどこにある?
論理学は,アリストテレスの時代から現代まで,変容を遂げながら進化を続けてきている。「論理的思考とは何か」を考えるためにはやはり論理学についての認識が必要だろう。この書は,哲学における論理と,数学の一領域となった記号論理学との,ほどよい橋渡しとなってくれるだろう。 -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
どこでも勉強はできる
獄中記 / 佐藤優. - 岩波書店, 2006
 北大ではどこにある?
著者が512日間東京拘置所に勾留された日々の記録。鈴木宗男氏と共に逮捕、起訴され、公判に臨んだ著者は、拘置所の中で何をしていたのか。公判について弁護士と手紙のやりとりはあたりまえだが、興味深いのは、大量の本を読み、ノートに思索を記録し、ラテン語やドイツ語を勉強する姿である。神学の研究者でもある著者の旺盛な勉学欲には驚かされる。国策捜査の標的になり、自由を奪われても、勉強を続ける姿に若い人は何かを感じてほしい。
北大ではどこにある?
著者が512日間東京拘置所に勾留された日々の記録。鈴木宗男氏と共に逮捕、起訴され、公判に臨んだ著者は、拘置所の中で何をしていたのか。公判について弁護士と手紙のやりとりはあたりまえだが、興味深いのは、大量の本を読み、ノートに思索を記録し、ラテン語やドイツ語を勉強する姿である。神学の研究者でもある著者の旺盛な勉学欲には驚かされる。国策捜査の標的になり、自由を奪われても、勉強を続ける姿に若い人は何かを感じてほしい。 -
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
鋭くバランスのよい人間洞察
アリストテレス『ニコマコス倫理学』 / アリストテレス (訳者朴一功). - 京都大学出版会 西洋古典叢書, 2002
 北大ではどこにある?
本書はその後のヨーロッパのひとびとの精神形成のうえで『聖書』とならんで大きな影響を与えた名著です。本書においては、幸福や徳そして抑制のなさなど人間の魂の諸様態が分析されますが、ここには個人的には誰をも拘束しないが、普遍的には万人を拘束するそのようなロゴスの普遍的な力があります。鋭い魂の動きの観察と同時に人間であること全体の広い視野のなかで、魂の分析が問いの美しさと鋭さのなかで遂行され、問いから答え、答えから問いの連鎖において思考が着実に前進し、人間本性の解明が力強くしかも繊細になされています。人類が持ちえた最良の頭脳がどれほど... [続きを読む]
北大ではどこにある?
本書はその後のヨーロッパのひとびとの精神形成のうえで『聖書』とならんで大きな影響を与えた名著です。本書においては、幸福や徳そして抑制のなさなど人間の魂の諸様態が分析されますが、ここには個人的には誰をも拘束しないが、普遍的には万人を拘束するそのようなロゴスの普遍的な力があります。鋭い魂の動きの観察と同時に人間であること全体の広い視野のなかで、魂の分析が問いの美しさと鋭さのなかで遂行され、問いから答え、答えから問いの連鎖において思考が着実に前進し、人間本性の解明が力強くしかも繊細になされています。人類が持ちえた最良の頭脳がどれほど... [続きを読む] -
推薦者 : 清水 誠 (文学研究科)
世界のことばの多様性に目を向けよう
世界のことば・出会いの表現辞典 / 石井米雄・千野栄一(編). - 三省堂, 2004
 北大ではどこにある?
同じ人間に生まれて、外国語ほど不思議なものはありません。大学生になったことを実感するのは、多くの場合、英語以外の外国語を学ぶという、時には苦しい体験を通じてではないでしょうか。現在、世界で起こっているさまざまの問題も、ことばを通じてとらえ直すとき、別の角度から問題の本質が見えてくることがあります。世界の言語は本当に多様であって、異質な歴史的文化的背景の一端を垣間見るとき、だれでも大きな驚きを覚えることでしょう。
北大ではどこにある?
同じ人間に生まれて、外国語ほど不思議なものはありません。大学生になったことを実感するのは、多くの場合、英語以外の外国語を学ぶという、時には苦しい体験を通じてではないでしょうか。現在、世界で起こっているさまざまの問題も、ことばを通じてとらえ直すとき、別の角度から問題の本質が見えてくることがあります。世界の言語は本当に多様であって、異質な歴史的文化的背景の一端を垣間見るとき、だれでも大きな驚きを覚えることでしょう。
ことばそのものは、すべての話者にとって本質的に固有で、しかも平等なものであるはずです。わたしたち日本人には、日本... [続きを読む] -
推薦者 : 鍋島 孝子 (メディア・コミュニケーション研究院)
自分も虐殺に荷担してしまうかもしれない
イェルサレムのアイヒマン 悪の陳腐さについての報告 / ハンナ・アーレント. - みすず書房, 1969年
 北大ではどこにある?
アドルフ・オットー・アイヒマンはナチス・ドイツの元親衛隊中佐。強制収容所にユダヤ人を組織的、且つ大量に送り込みました。戦後、逃亡の末、捕らえられ、イスラエルで人道に反する罪に問われて裁判を受けました。
北大ではどこにある?
アドルフ・オットー・アイヒマンはナチス・ドイツの元親衛隊中佐。強制収容所にユダヤ人を組織的、且つ大量に送り込みました。戦後、逃亡の末、捕らえられ、イスラエルで人道に反する罪に問われて裁判を受けました。
著者ハンナ・アーレントはユダヤ系の思想家。アイヒマンの裁判を通じて、平凡な人が国家の命令に従い、いかに蛮行に至ったかを論じています。読者は個人のモラルとは、組織とは、国家の統制とは何かと考えさせられるでしょう。
皆さんは将来、御自分が所属する社会に押しつぶされそうになったとき、どうしますか。良心から反対できますか。それとも流... [続きを読む] -
推薦者 : 須田 勝彦 (教育学部)
知とは何か,という対話
形而上学(上) / アリストテレス[著] ,出隆訳. - 岩波文庫, 2006年
 北大ではどこにある?
BC.340年ころ,ギリシアで書かれたこの本が今も読まれている。哲学者でもなく,古典語を読めるわけでもない私は,当然日本語訳しか読めないが,この書がとても好きになった。今の私たちとまったく違った思惟様式において書かれたこの書が,それにもかかわらず,多くの対話が可能であることに驚かされる。
北大ではどこにある?
BC.340年ころ,ギリシアで書かれたこの本が今も読まれている。哲学者でもなく,古典語を読めるわけでもない私は,当然日本語訳しか読めないが,この書がとても好きになった。今の私たちとまったく違った思惟様式において書かれたこの書が,それにもかかわらず,多くの対話が可能であることに驚かされる。 -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
いつの時代も青春は
青が散る (宮本輝全集 第3巻) / 宮本輝. - 新潮社, 1992
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
本屋は好きですか
書店繁盛記 / 田口久美子. - ポプラ社, 2006
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
アイヌの世界観を知ろう
アイヌの世界観 : 「ことば」から読む自然と宇宙 / 山田孝子. - 講談社, 1994.8
 北大ではどこにある?
クマ・オオカミ・シマフクロウ・・・・・。魚の満ちあふれる川、シカが群れつどう山。大自然をアイヌはカムイ(神)としてとらえる。彼らの信仰はいかにして形成されたのか?「ことば」が「生活世界」を切り取るプロセス。秘密はそこにある。北の民の世界観がいま、認識人類学の立場から鮮やかに解明される。
北大ではどこにある?
クマ・オオカミ・シマフクロウ・・・・・。魚の満ちあふれる川、シカが群れつどう山。大自然をアイヌはカムイ(神)としてとらえる。彼らの信仰はいかにして形成されたのか?「ことば」が「生活世界」を切り取るプロセス。秘密はそこにある。北の民の世界観がいま、認識人類学の立場から鮮やかに解明される。
本書の内容
・プロローグ
・アイヌの宇宙観
・霊魂とカムイ
・アイヌの植物命名法
・動物の分類と動物観
・諸民族との比較
・世界観の探求−認識人類学的アプローチ -
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
変容著しい東北アジアの文化と言語の現在を読み解く!
東北アジア諸民族の文化動態 / 煎本孝編著. - 北海道大学図書刊行会, 2002.2
 北大ではどこにある?
日本、ロシア、中国、モンゴルを含む東北アジアには、広大で多様な環境が展開している。それは、民族学(文化人類学)的には北アジア、中央アジア、東アジアを含む地域である。生態的にも、地理的にもけっして閉鎖的な地域ではないこの多様な環境に生活する人々は、さまざまな文化と言語とをもっている。本書では東北アジアの文化と言語の動態を多角的に比較検討し、東北アジアの現在について考察する。
北大ではどこにある?
日本、ロシア、中国、モンゴルを含む東北アジアには、広大で多様な環境が展開している。それは、民族学(文化人類学)的には北アジア、中央アジア、東アジアを含む地域である。生態的にも、地理的にもけっして閉鎖的な地域ではないこの多様な環境に生活する人々は、さまざまな文化と言語とをもっている。本書では東北アジアの文化と言語の動態を多角的に比較検討し、東北アジアの現在について考察する。 -
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
自然とは?文化とは?人類学とは?
文化の自然誌 / 煎本孝. - 東京大学出版会, 1996.6
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
空想すくすく、ノンフィクション文庫版
カナダ・インディアンの世界から / 煎本孝. - 福音館書店, 2002.11
 北大ではどこにある?
トナカイを求めて、凍てつく雪原を来る日も来る日も犬橇を走らせるカナダ・インディアンの男たち。「トナカイは人が飢えている時、その肉を与えに自分からやってくるものだ」と彼らは言う。本書は、その魂に、“自然”の力を宿し、季節と共にその内なる力を育みつつ生きてゆく人びとの、たぐいまれなる記録である。丹念な取材に裏付けされた事実に基づく自然誌、成熟した読者にも読み応えのある作品。
北大ではどこにある?
トナカイを求めて、凍てつく雪原を来る日も来る日も犬橇を走らせるカナダ・インディアンの男たち。「トナカイは人が飢えている時、その肉を与えに自分からやってくるものだ」と彼らは言う。本書は、その魂に、“自然”の力を宿し、季節と共にその内なる力を育みつつ生きてゆく人びとの、たぐいまれなる記録である。丹念な取材に裏付けされた事実に基づく自然誌、成熟した読者にも読み応えのある作品。 -
推薦者 : 陳 省仁 (教育学研究科)
翻訳哲学書は何故読みにくいか
輸入学問の功罪 : この翻訳わかりますか? / 鈴木直. - 筑摩書房, 2007.1
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
宗教と科学
The God Delusion / Richard Dawkins. - Bantam Press, 2006
 北大ではどこにある?
ドーキンス氏はこの書において、神が存在しないことがその存在することよりも圧倒的に確からしいことを、進化論的観点から示します。(ただし、ここでいう神とは、万物を創造し人間に賞罰を与える超自然的存在のことで、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の神が想定されています。)しかし、有史以来、人類は宗教とともに歩んできたようです。宗教を信奉するひとが無宗教のひととの相克に勝ち抜き、自然淘汰の試練を潜り抜けてきたからには、少なくとも宗教に存在価値があるからではないかという疑問が起こります。著者は、それが危険に満ちた環境での人類の生存に適した心... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ドーキンス氏はこの書において、神が存在しないことがその存在することよりも圧倒的に確からしいことを、進化論的観点から示します。(ただし、ここでいう神とは、万物を創造し人間に賞罰を与える超自然的存在のことで、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の神が想定されています。)しかし、有史以来、人類は宗教とともに歩んできたようです。宗教を信奉するひとが無宗教のひととの相克に勝ち抜き、自然淘汰の試練を潜り抜けてきたからには、少なくとも宗教に存在価値があるからではないかという疑問が起こります。著者は、それが危険に満ちた環境での人類の生存に適した心... [続きを読む] -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
メディアとは 2
戦争報道 / 武田徹. - ちくま新書, 2003
 北大ではどこにある?
ジャーナリズムは戦争の悲惨さを伝える一方、9.11以後のアメリカのように戦争を煽る愛国報道になる。第二次世界大戦からアフガン戦争まで戦争と報道の問題を論じる。そして戦時においては中立の報道どころか広告(プロパガンダ)に加担する姿を示す。これで基礎知識を得てから、他の戦争とメディア論に進むと良いと思う。
北大ではどこにある?
ジャーナリズムは戦争の悲惨さを伝える一方、9.11以後のアメリカのように戦争を煽る愛国報道になる。第二次世界大戦からアフガン戦争まで戦争と報道の問題を論じる。そして戦時においては中立の報道どころか広告(プロパガンダ)に加担する姿を示す。これで基礎知識を得てから、他の戦争とメディア論に進むと良いと思う。 -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
メディアとは 1
国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて / 佐藤優. - 新潮社, 2005
 北大ではどこにある?
あなたは鈴木宗男議員を知っているだろうか。マスメディアでは汚い政治家の代表とされ、北方領土関係などで癒着を指弾され、疑惑の総合商社と言われ、逮捕・起訴された政治家である。彼と共に歩み、外務省を毒したとされた外交官が著者である。彼も逮捕・起訴された。私たちはそのようなイメージを自明のものと受け取ってきた。しかし彼らの言い分をちゃんと聞いたことがあったろうか。この本を読むと政治の裏の複雑さと権力抗争のすざまじさを知ることができる。国益を巡る立場の違いを知ると、一面的に著者を弾劾することはためらわれる。鈴木議員に関しても同じである... [続きを読む]
北大ではどこにある?
あなたは鈴木宗男議員を知っているだろうか。マスメディアでは汚い政治家の代表とされ、北方領土関係などで癒着を指弾され、疑惑の総合商社と言われ、逮捕・起訴された政治家である。彼と共に歩み、外務省を毒したとされた外交官が著者である。彼も逮捕・起訴された。私たちはそのようなイメージを自明のものと受け取ってきた。しかし彼らの言い分をちゃんと聞いたことがあったろうか。この本を読むと政治の裏の複雑さと権力抗争のすざまじさを知ることができる。国益を巡る立場の違いを知ると、一面的に著者を弾劾することはためらわれる。鈴木議員に関しても同じである... [続きを読む] -
推薦者 : 高井 哲彦 (経済学研究科)
世界を目指すグローバルな若者のバイブル
深夜特急 / 沢木耕太郎. - 新潮社, 1986-1992
 北大ではどこにある?
著者はある日突然、乗り合いバスによる貧乏旅行を思いつく。香港・マカオ、マレー半島・シンガポール、インド・ネパール、そしてシルクロードを経て、トルコ・ギリシャ・地中海、最後に南ヨーロッパ・ロンドン。その旅程は著者自身の成長過程でもあり、とくに異文化と出会う前半部は新鮮だ。
北大ではどこにある?
著者はある日突然、乗り合いバスによる貧乏旅行を思いつく。香港・マカオ、マレー半島・シンガポール、インド・ネパール、そしてシルクロードを経て、トルコ・ギリシャ・地中海、最後に南ヨーロッパ・ロンドン。その旅程は著者自身の成長過程でもあり、とくに異文化と出会う前半部は新鮮だ。
21歳のぼくがはじめてインドを訪れたのも、突然だった。ロンドン滞在から帰国する際に思い立って、インド経由に変更したのだった。ヴァラナシ=コルコタ間の夜行2等席では、トイレに往復する人が肩の上を踏んで歩くほど鮨詰めの満員立席で、ショックの余り言葉が話せなくなった。ラン... [続きを読む] -
推薦者 : 池田 清治 (法学研究科)
原始キリスト教の多様性を探る
禁じられた福音書 : ナグ・ハマディ文書の解明 / エレーヌ・ペイゲルス(松田和也訳). - 青土社, 2005.3
 北大ではどこにある?
昨今『捏造された聖書』(柏書房、2006年)など)、西洋思想の源流を辿りたい方には是非とも一読を薦めたい。
北大ではどこにある?
昨今『捏造された聖書』(柏書房、2006年)など)、西洋思想の源流を辿りたい方には是非とも一読を薦めたい。 -
推薦者 : 花井 一典 (文学研究科)
待望の名著復刊
ラテン広文典 / 泉井 久之助. - 白水社, 2005
 北大ではどこにある?
ラテン語入門書は数多いが、これはウェルギリウスの叙事詩『アエネイス』の翻訳や、言語学者フンボルトの紹介、研究で知られる一代の碩学がものしただけあって単なる語学書ではない。どの行間にも自ずと滲む底知れぬ無言の学識、悠揚迫らざるおおどかな叙述、それはひとつの作品の風格を備えており、読者は触角さえ伸ばせばどこからでも言語の深みにはまるようにできている。本書味読の後では人はラテン語の(否、総じて外国語の)修得を「ただの語学」呼ばわりすることを恥じるであろう。
北大ではどこにある?
ラテン語入門書は数多いが、これはウェルギリウスの叙事詩『アエネイス』の翻訳や、言語学者フンボルトの紹介、研究で知られる一代の碩学がものしただけあって単なる語学書ではない。どの行間にも自ずと滲む底知れぬ無言の学識、悠揚迫らざるおおどかな叙述、それはひとつの作品の風格を備えており、読者は触角さえ伸ばせばどこからでも言語の深みにはまるようにできている。本書味読の後では人はラテン語の(否、総じて外国語の)修得を「ただの語学」呼ばわりすることを恥じるであろう。 -
推薦者 : 内田 努 (工学研究科)
「西堀流」創造的生き方のお話です。
[新版]石橋を叩けば渡れない。 / 西堀栄三郎. - 生産性出版, 1999
 北大ではどこにある?
第1次南極越冬隊長、東芝では真空管の研究者、ヒマラヤ登山隊長、など様々な経歴を持つ著者が、その生き方のヒントをいっぱい紹介している本です。
北大ではどこにある?
第1次南極越冬隊長、東芝では真空管の研究者、ヒマラヤ登山隊長、など様々な経歴を持つ著者が、その生き方のヒントをいっぱい紹介している本です。
「人間というものは経験を積むために生まれてきた」
「欠点は個性であり、変えるのではなく生かすものである」
「創意工夫する能力こそは、神が人間に与えた特権」
など、随所に腑に落ちる言葉が出てきます。
また特に理系の人には、「科学」と「技術」の違いについて考えてみていただければと思います。
そして科学者として、あるいは技術者としてどんな風に生きていったら良いか、考えてみてください。
登録日 : 2006-06-08
-
推薦者 : 眞崎 睦子 (メディア・コミュニケーション研究院)
北海道、はじめて?
北海道わくわく地図えほん / 堀川 真. - 北海道新聞社, 2006
 北大ではどこにある?
地元の小さな川の名前は全部知っているのに、
北大ではどこにある?
地元の小さな川の名前は全部知っているのに、
都道府県パズル得意だったのに、
あこがれの北大に来てみたら、
北海道物産展に来ていた美味しいもの以外、
北海道のこと何にも知らないっ!
あの家の横のカニみたいなものは何?(灯油タンクでした、念のため)
「投げといて」って言われても、何をどこにっ?
…と2年前の私のようにあせっている新入生はいませんか?
こんな読書もたまにはいいと思います。
これから暮らす北海道のこと、
豊かな自然から、まちの暮らし、方言まで、わくわくしながら学べます。
登録日 : 2006-04-18
-
推薦者 : 吉野 悦雄 (経済学研究科)
論理を体験する
論理トレーニング101題 / 野矢茂樹著. - 産業図書, 2001.5
 北大ではどこにある?
この本は脳を鍛えるのにふさわしい本です。決してパズル問題集ではありません。どの問題にも,集合と補集合という初歩的な概念からはじまって,ド・モルガンの法則など高度な記号論理学の論理が埋め込まれています。公務員試験や法科大学院をめざす4年生には定番の参考書となっています。しかしその内容は平易で,高校生にも理解できます。文系学部のみなさんにとっても無理なく読み進めることのできる本です。附属図書館の本館と北分館の開架図書におさめられていますが,人気のある本なので,ご自分で購入してもよいでしょう。
北大ではどこにある?
この本は脳を鍛えるのにふさわしい本です。決してパズル問題集ではありません。どの問題にも,集合と補集合という初歩的な概念からはじまって,ド・モルガンの法則など高度な記号論理学の論理が埋め込まれています。公務員試験や法科大学院をめざす4年生には定番の参考書となっています。しかしその内容は平易で,高校生にも理解できます。文系学部のみなさんにとっても無理なく読み進めることのできる本です。附属図書館の本館と北分館の開架図書におさめられていますが,人気のある本なので,ご自分で購入してもよいでしょう。 -
推薦者 : 羽部 朝男 (理学研究科)
デカルトはおもしろい
哲学原理 / デカルト著 ; 桂寿一訳. - 岩波書店, 1964.4
 北大ではどこにある?
デカルトは高校時代に哲学者として勉強したことがあると思う。哲学は難しいというイメージがある。まして、物理の先生が,哲学の本を薦めるのはなぜかといぶかしく思うかもしれない。デカルトは、座標を思いついた人で物理学と関係が深い。物理学ではxyz座標をデカルト座標と呼び座標が無くては,物理学の発展は無かったと言ってもいいだろう。この本を読んでみると、デカルトの合理的なものの考え方が当時の限られた自然科学の知識を使って、よく説明されており、わかりやすくとても面白い。ぜひ、読んでほしい。
北大ではどこにある?
デカルトは高校時代に哲学者として勉強したことがあると思う。哲学は難しいというイメージがある。まして、物理の先生が,哲学の本を薦めるのはなぜかといぶかしく思うかもしれない。デカルトは、座標を思いついた人で物理学と関係が深い。物理学ではxyz座標をデカルト座標と呼び座標が無くては,物理学の発展は無かったと言ってもいいだろう。この本を読んでみると、デカルトの合理的なものの考え方が当時の限られた自然科学の知識を使って、よく説明されており、わかりやすくとても面白い。ぜひ、読んでほしい。 -
推薦者 : 下澤 楯夫 (電子科学研究所)
邪悪と勇気
平気でうそをつく人たち : 虚偽と邪悪の心理学 / M・スコット・ペック著 ; 森英明訳. - 草思社, 1996.12
 北大ではどこにある?
人間は一人では生きられず、言葉と行動を通して多くの他個体と相互作用し、社会構造をつくり出し、その中で生きる生物である。その中では、弱い人間を助ける作用も重要な性質(心)として保存される。しかし、作り出された社会構造や機能にただ乗りして生きる邪悪な個体も必ず現れる。
北大ではどこにある?
人間は一人では生きられず、言葉と行動を通して多くの他個体と相互作用し、社会構造をつくり出し、その中で生きる生物である。その中では、弱い人間を助ける作用も重要な性質(心)として保存される。しかし、作り出された社会構造や機能にただ乗りして生きる邪悪な個体も必ず現れる。
邪悪なずるい個体は、弱いフリをし、弱者を助ける傾向を持った善良な個体を、虚偽と邪悪で満ちた心の闇に引きずり込む。このような「平気で嘘をつくひと」に出会ったとき、「神の慈悲」にすがるだけではなく、自らの力で虚偽と邪悪を切り捨てる勇気だけが自分を救う。
-
推薦者 : 蔵田 伸雄 (文学研究科)
哲学とはどういうことか
ゴルギアス / プラトン著 ; 加来彰俊訳. - 岩波書店, 1967.6
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 園田 勝英 (言語文化部)
最良の英単語参考書
英語語義イメージ辞典 / 政村秀實著 ; Paulus Pimomo英文校閲. - 大修館書店, 2002.5
 北大ではどこにある?
『永久記憶の英単語』、『ネイティブスピーカーの単語力』、『語源とイラストで一気に覚える英単語』、などなど。あの手この手の書名とともに売り出される英単語の参考書の数は、おそらく明治以来数百冊になるであろう。このように数ある英単語参考書の中で私が現在もっとも良いと思っているのがこの本である。約3,000の見出し語について、発音記号、定訳、原義... [続きを読む]
北大ではどこにある?
『永久記憶の英単語』、『ネイティブスピーカーの単語力』、『語源とイラストで一気に覚える英単語』、などなど。あの手この手の書名とともに売り出される英単語の参考書の数は、おそらく明治以来数百冊になるであろう。このように数ある英単語参考書の中で私が現在もっとも良いと思っているのがこの本である。約3,000の見出し語について、発音記号、定訳、原義... [続きを読む] -
推薦者 : 佐伯 宏樹 (水産科学院・水産科学研究院)
科学を志す人にとって座右の一冊!
理科系の作文技術 / 木下是雄著. - 中央公論社, 1981.9
 北大ではどこにある?
「私の文章のどこがいけないのかわからない?」
北大ではどこにある?
「私の文章のどこがいけないのかわからない?」
「考察がなっていないって指摘されたけど,いったいどこが悪いのだろう?」
レポートを返却されてこんな悩みを持った人に一読をお薦めします!
***********
皆さんはこれから,さまざまな実験・実習を体験し,続いて卒業研究,さらには大学院での本格的な研究活動を経て社会に巣立つことになります。この過程で学ぶべきレベルは,日を追うごとに高くなりますが,一方で,学部,修士課程,博士課程のいずれの場合にも実験結果を文章で表現するという作業が求められ続けます。
***********
科学の分野で「ものを書く」ということは... [続きを読む] -
推薦者 : 花井 一典 (文学研究科)
自分の中の魔物を見つめて!
仏教vs.倫理 / 末木文美士著. - 筑摩書房, 2006.2
 北大ではどこにある?
思想研究の課題は過去の思想の解説にあるわけではない。キレイゴトの倫理道徳の手に負えない何かをいつも抱えているのが人間であって、実はそうした人間の中の魔物を冷静に見定めるところに研究の最終目的があると言ってよいくらいである。著者は専門の仏教思想を交えながらも、現代の闇をどこまでも追究しており、裃を脱いだその語り口は魔の世界を体験した者だけがもつ不思議な明るさが漂っている。情けない、ダメな自分に滅入っていてはいけない。自分のそうした部分を見つめることで人は本当に成長するのだから。
北大ではどこにある?
思想研究の課題は過去の思想の解説にあるわけではない。キレイゴトの倫理道徳の手に負えない何かをいつも抱えているのが人間であって、実はそうした人間の中の魔物を冷静に見定めるところに研究の最終目的があると言ってよいくらいである。著者は専門の仏教思想を交えながらも、現代の闇をどこまでも追究しており、裃を脱いだその語り口は魔の世界を体験した者だけがもつ不思議な明るさが漂っている。情けない、ダメな自分に滅入っていてはいけない。自分のそうした部分を見つめることで人は本当に成長するのだから。 -
推薦者 : 稗貫 俊文 (法学研究科)
高校生向きだって侮れないぞ!
アメリカ式勉強法 / ロン・フライ著 ; 金利光訳. - 東京図書, 1996.11
 北大ではどこにある?
アメリカの高校生向きに書かれた本の翻訳です。アメリカ式とは日本の本屋さんが勝手につけたタイトルです。しかし、さすが、あの勤勉家のB・フランクリンを生んだ国の本だなーという印象をもちます(暇があれば「論文作法 : 調査・研究・執筆の技術と手順』という本のことです。(北分館2007/03/07)
北大ではどこにある?
アメリカの高校生向きに書かれた本の翻訳です。アメリカ式とは日本の本屋さんが勝手につけたタイトルです。しかし、さすが、あの勤勉家のB・フランクリンを生んだ国の本だなーという印象をもちます(暇があれば「論文作法 : 調査・研究・執筆の技術と手順』という本のことです。(北分館2007/03/07) -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
Plan your research career now
The craft of research / Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams. - University of Chicago Press, 2003
 北大ではどこにある?
Those of you considering research as a profession should read this
北大ではどこにある?
Those of you considering research as a profession should read this
book for two reasons: it demonstrates the steps of academic research
(many books do this), and it prepares you mentally for research (this
is the best book I've ever seen on this issue).
I define research as the systematic pursuit of curiosity. Research is
fundamentally no different from other kinds of work. A business
person employs the same energy and creativity as any scientist. We
both focus on our customers (we call them our audience in academia).
We both prepare ourselves to succeed. Preparation involves skills and
attitude.
This is a book I wish I had read, or better, had a mentor explain to
me when I was in high school. I embarked on my research career late
in life. Don't repeat m... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
Historical linguistics at its best
The American heritage dictionary of Indo-European roots / revised and edited by Calvert Watkins. - Houghton Mifflin, 2000
 北大ではどこにある?
Archaeology tells us where ancient people lived, what food they ate, what tools they used. But it doesn't tell us much about their religion, family structure, or knowledge of the world. Language tells
北大ではどこにある?
Archaeology tells us where ancient people lived, what food they ate, what tools they used. But it doesn't tell us much about their religion, family structure, or knowledge of the world. Language tells
us more than material artifacts.
Watkin's book is mostly a dictionary. Read the introduction (not the dictionary) to learn how people 8,000 years ago viewed the world. The Indo-European family of languages includes English, Dutch, Danish, French, German, Latin, Greek and Sanskrit. Their ancestors spoke a common language. By reconstructing a common ancestral language, we learn more than the remaining historical record.
From words common in all existing languages, we know the proto-Indo-Europeans (as they are called) formed a patriarchal society, kept livestock, drank honey, celebrate... [続きを読む] -
推薦者 : 佐藤 淳二 (文学研究科)
21世紀はドゥルーズの時代だ そしてもはや我々は21世紀に生きている
差異と反復 / ジル・ドゥルーズ〔著〕 ; 財津理訳. - 河出書房新社, 1992.11
 北大ではどこにある?
この時代を生きるのに欠かせない地図が何枚かある。
北大ではどこにある?
この時代を生きるのに欠かせない地図が何枚かある。
たとえばデリダの『エクリチュールと差異』やドゥルーズの『差異と反復』はそのような地図であり、またドゥルーズとガタリが組んだ『カフカ』『アンチ・オイディプス』『 -
推薦者 : 𢎭(弓巾/ゆはず) 和順 (文学研究科)
儒教の本質を考える上での好著
儒教とは何か / 加地伸行著. - 中央公論社, 1990.10
 北大ではどこにある?
中国・朝鮮半島・日本を含む東アジアの思想文化を考究するとき、回避することのできないテーマのひとつとして、孔子の思想、すなわち儒教が挙げられる。本書は、儒教の成立・展開、さらにはその日本への影響などを詳述することを通して、従来、倫理道徳と見なされてきた儒教について、その本質は死と密接に結びついた宗教であると主張する。その当否はともかく、儒教とは何か、また宗教とは何かを考える上で、刺戟的な一冊であることに間違いはない。
北大ではどこにある?
中国・朝鮮半島・日本を含む東アジアの思想文化を考究するとき、回避することのできないテーマのひとつとして、孔子の思想、すなわち儒教が挙げられる。本書は、儒教の成立・展開、さらにはその日本への影響などを詳述することを通して、従来、倫理道徳と見なされてきた儒教について、その本質は死と密接に結びついた宗教であると主張する。その当否はともかく、儒教とは何か、また宗教とは何かを考える上で、刺戟的な一冊であることに間違いはない。 -
推薦者 : 栗原 秀幸 (水産科学院・水産科学研究院)
理科系というよりは大人の作文技術?!
理科系の作文技術 / 木下是雄著. - 中央公論社, 1981.9
 北大ではどこにある?
これまで皆さんは「作文」や「読書感想文」などの文章を書いてきました。しかし,このような文章を書く機会はこれから激減します。大学に入り,やがて社会に出る皆さんにとって,これから書く文章の多くは,「書いている自分と読む他人が,まったく同じ内容を頭に描くことができる文章」です。理系の実験レポート,文系のレポート,学位をとるための論文,社会に出たら出張や業務の報告書等々です。
北大ではどこにある?
これまで皆さんは「作文」や「読書感想文」などの文章を書いてきました。しかし,このような文章を書く機会はこれから激減します。大学に入り,やがて社会に出る皆さんにとって,これから書く文章の多くは,「書いている自分と読む他人が,まったく同じ内容を頭に描くことができる文章」です。理系の実験レポート,文系のレポート,学位をとるための論文,社会に出たら出張や業務の報告書等々です。
皆さんの多くはこのような文章を書くトレーニングをすることなく,大学まで進んだはずです(私もそうでした)。この本を読むと,どんな文章を書くと他人に「ひとつの意味... [続きを読む]