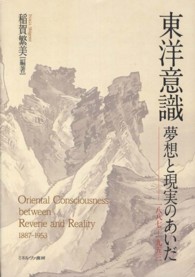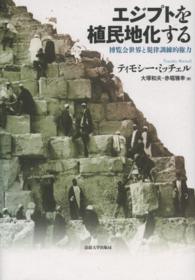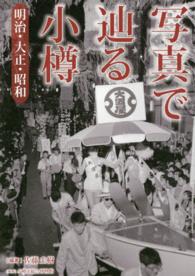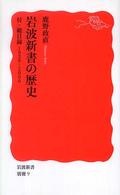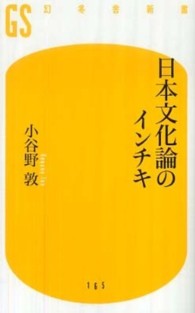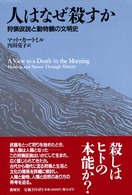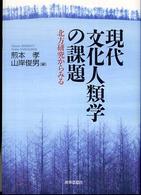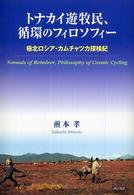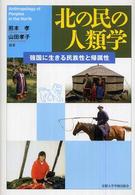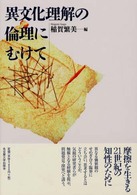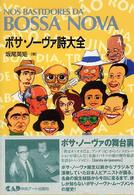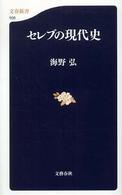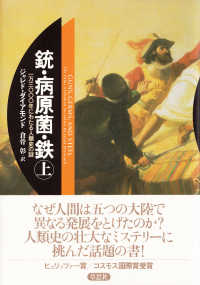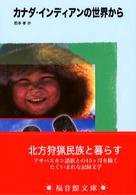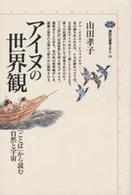-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「ボランティア」のあり方を見つめ直すために
「ボランティア」の誕生と終焉 : 「贈与のパラドックス」の知識社会学 / 仁平典宏. - 名古屋大学出版会, 2011
 北大ではどこにある?
学生時代に7年ほどあるボランティア活動に携わっていたことがあるのだが、最初に活動に参加しようとした時、親に言われたのは「自分の頭のハエも追えない奴が偉そうに人助けなんかやるな!」という暴言(!)であった。今考えてもあんまりな言い方だと思うが、そうした意識は程度の差こそあれ日本の社会にある時期流通していたボランティア理解ではなかったかとも思う。この本の帯には「『善意』と『冷笑』の狭間で」と書かれているのだが、このことばはボランティアというものに対して注がれる、あるいは浴びせられる視線の複雑さを見事に言い当てている。そうした複雑さを... [続きを読む]
北大ではどこにある?
学生時代に7年ほどあるボランティア活動に携わっていたことがあるのだが、最初に活動に参加しようとした時、親に言われたのは「自分の頭のハエも追えない奴が偉そうに人助けなんかやるな!」という暴言(!)であった。今考えてもあんまりな言い方だと思うが、そうした意識は程度の差こそあれ日本の社会にある時期流通していたボランティア理解ではなかったかとも思う。この本の帯には「『善意』と『冷笑』の狭間で」と書かれているのだが、このことばはボランティアというものに対して注がれる、あるいは浴びせられる視線の複雑さを見事に言い当てている。そうした複雑さを... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
「東洋」と「西洋」とは何か、あらためて考える。
東洋意識 : 夢想と現実のあいだ1887-1953 / 稲賀繁美編著. - ミネルヴァ書房, 2012
 北大ではどこにある?
学問―特に人文科学―の世界に於ける「東洋-西洋」という枠組み或いは二分法は、実は相当にうさんくさい。そのうさんくささを“学問的に”剔抉したのは言うまでもなくエドワード・サイードの『オリエンタリズム』だったが、そのとらえ方自体が西洋的な学問世界の中で一定の権威になってしまうという戯画的な状況が生まれ、相変わらず「東洋-西洋」という枠組みをめぐる思索は混迷している。今回推薦する本は、編著者の稲賀氏自身が書いているように「『東洋』と呼ばれる―あるいは時代遅れとな... [続きを読む]
北大ではどこにある?
学問―特に人文科学―の世界に於ける「東洋-西洋」という枠組み或いは二分法は、実は相当にうさんくさい。そのうさんくささを“学問的に”剔抉したのは言うまでもなくエドワード・サイードの『オリエンタリズム』だったが、そのとらえ方自体が西洋的な学問世界の中で一定の権威になってしまうという戯画的な状況が生まれ、相変わらず「東洋-西洋」という枠組みをめぐる思索は混迷している。今回推薦する本は、編著者の稲賀氏自身が書いているように「『東洋』と呼ばれる―あるいは時代遅れとな... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
世界はどうしてこうなっているのか。
エジプトを植民地化する : 博覧会世界と規律訓練的権力 / ティモシー・ミッチェル著 ; 大塚和夫, 赤堀雅幸訳. - 法政大学出版局, 2014
 北大ではどこにある?
一見この本とは関係なさそうな話から推薦文を書く。みなさんは、観光旅行に行くとはどのようなことだと思っているだろうか。理由はいろいろあるにせよ、大きな共通点は世界遺産に代表されるような歴史的建造物や名所旧跡を辿ることが目的である、ということだろう。しかし、である。その時、観光旅行する我々は、実は名所旧跡を”見に”行っているのではなく、ガイドブックなどに一定の秩序で並べられた空間の”確認”をしに行っているに過ぎないのである。なぜそう言えるのか、の答えを与えてくれるのが、この本の副題になっている「博覧会世界」である。
北大ではどこにある?
一見この本とは関係なさそうな話から推薦文を書く。みなさんは、観光旅行に行くとはどのようなことだと思っているだろうか。理由はいろいろあるにせよ、大きな共通点は世界遺産に代表されるような歴史的建造物や名所旧跡を辿ることが目的である、ということだろう。しかし、である。その時、観光旅行する我々は、実は名所旧跡を”見に”行っているのではなく、ガイドブックなどに一定の秩序で並べられた空間の”確認”をしに行っているに過ぎないのである。なぜそう言えるのか、の答えを与えてくれるのが、この本の副題になっている「博覧会世界」である。
この本は、表題か... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
温故知新
写真で辿る小樽 明治・大正・昭和 / 佐藤 圭樹. - 北海道新聞社, 2014
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
昭和をまだノスタルジーにするな!
昭和時代年表 増補版 / 中村政則. - 岩波書店, 1986
 北大ではどこにある?
ここ何年かの間に、メディアで「昭和の○○」といったことばを少なからず読んだり聞いたりすることがある。女優の黒木華さんは「昭和顔」と言われているそうだ。昭和32年(=考えてみればちょうど昭和の半分の年)生まれで、経済の高度成長とともに成長し、1988年のバブル最盛期に就職した僕から見ると、「『昭和』をそんなに簡単にノスタルジーにするな!」という怒りにも似た気持ちを禁じ得ない。それは、僕個人にとって昭和がリアルタイムであると言うだけのことではなく、昭和時代に現れ、あるいは作られた様々な問題・課題から我々が未だに解き放たれているとは言えない... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ここ何年かの間に、メディアで「昭和の○○」といったことばを少なからず読んだり聞いたりすることがある。女優の黒木華さんは「昭和顔」と言われているそうだ。昭和32年(=考えてみればちょうど昭和の半分の年)生まれで、経済の高度成長とともに成長し、1988年のバブル最盛期に就職した僕から見ると、「『昭和』をそんなに簡単にノスタルジーにするな!」という怒りにも似た気持ちを禁じ得ない。それは、僕個人にとって昭和がリアルタイムであると言うだけのことではなく、昭和時代に現れ、あるいは作られた様々な問題・課題から我々が未だに解き放たれているとは言えない... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
岩波新書は不滅です!
岩波新書の歴史 : 付・総目録1938-2006 / 鹿野政直. - 岩波書店, 2006
 北大ではどこにある?
前にこの「本は脳を育てる」に岩波新書(青版)の鈴木八司『ナイルに沈む歴史』を推薦した際に、「最近(特に今世紀になってから)、岩波新書(新赤版)がつまらなくなってきた。」と書いたが、そうはいってもやはり岩波新書は「腐っても鯛」-という書き方は失礼かもしれないけれども-である。「岩波文化人」という、一種の鼻持ちならないエリートを作り出したという問題点はあるが、間違いなく日本近代、あるいは昭和以降の「教養」の担い手として大きな存在感を発揮したことは否定しようがない。この鹿野氏の著作は、岩波新書がどのような価値観を時代に対する「教養」... [続きを読む]
北大ではどこにある?
前にこの「本は脳を育てる」に岩波新書(青版)の鈴木八司『ナイルに沈む歴史』を推薦した際に、「最近(特に今世紀になってから)、岩波新書(新赤版)がつまらなくなってきた。」と書いたが、そうはいってもやはり岩波新書は「腐っても鯛」-という書き方は失礼かもしれないけれども-である。「岩波文化人」という、一種の鼻持ちならないエリートを作り出したという問題点はあるが、間違いなく日本近代、あるいは昭和以降の「教養」の担い手として大きな存在感を発揮したことは否定しようがない。この鹿野氏の著作は、岩波新書がどのような価値観を時代に対する「教養」... [続きを読む] -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
「日本人論」の系譜と「日本人論ブーム」の社会的背景を探る!
「日本人論」再考 / 船曳建夫. - 日本放送出版協会, 2003
 北大ではどこにある?
近代以降の日本では数々の「日本人論」が刊行されてきた。『武士道』『菊と刀』『「甘え」の構造』『ジャパンアズナンバーワン』が代表的ですが、近年の藤原雅彦『国家の品格』なども「日本人論」といえましょう。
北大ではどこにある?
近代以降の日本では数々の「日本人論」が刊行されてきた。『武士道』『菊と刀』『「甘え」の構造』『ジャパンアズナンバーワン』が代表的ですが、近年の藤原雅彦『国家の品格』なども「日本人論」といえましょう。
ではなぜ「日本人論」が生産され、広く人口に膾炙したのか?
ブームの背景にある日本社会の「不安」、アイデンティティの「揺らぎ」といった社会的・心理的背景を本書は探ります。また本書は「日本人的なるもの」をいわゆる「サムライ」「武士道」などに限定せず、戦時中の「国民」さらには、今日でも日常的に使われる「人間」「職人」といった概念に見られる... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
家族が「家族」として語られるとき
戦略としての家族-近代日本の国民国家形成と女性- / 牟田和恵. - 新曜社, 1996
 北大ではどこにある?
多くの人にとっては家族というのは気がついたら存在している(という意味で)自然な環境である。この本は、その自然なはずの家族が近代日本のジャーナリズムの中でどのように論じられ、どのようにその論じ方が転換し、どのように教育の中に取り込まれてきたかを考察し、近代日本人の意識の中に「家族」として根付く過程を明らかにしている。今日の夫婦別姓や、性別役割分担の問題、あるいは家族の「絆」ということを考えたい、あるいは、そうしたことに興味がある学生にお薦めしたい本である。
北大ではどこにある?
多くの人にとっては家族というのは気がついたら存在している(という意味で)自然な環境である。この本は、その自然なはずの家族が近代日本のジャーナリズムの中でどのように論じられ、どのようにその論じ方が転換し、どのように教育の中に取り込まれてきたかを考察し、近代日本人の意識の中に「家族」として根付く過程を明らかにしている。今日の夫婦別姓や、性別役割分担の問題、あるいは家族の「絆」ということを考えたい、あるいは、そうしたことに興味がある学生にお薦めしたい本である。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
日本と日本人を見る目の背後にあるもの
日本人論・日本論の系譜 / 石澤靖治. - 丸善, 1997
 北大ではどこにある?
この本は、ルース・ベネディクトの『菊と刀』以後の代表的な日本人論・日本論を取り上げてそれらを関連づけて論じることを通して日本と日本人に対する内外の見方がどのように関連し合ってどう変化してきたかのわかりやすい見取り図を描き出すものである。
北大ではどこにある?
この本は、ルース・ベネディクトの『菊と刀』以後の代表的な日本人論・日本論を取り上げてそれらを関連づけて論じることを通して日本と日本人に対する内外の見方がどのように関連し合ってどう変化してきたかのわかりやすい見取り図を描き出すものである。
この本の眼目は、所謂広義の「日本(文化)論」と言われるものを「日本論」と「日本人論」に分けてそれぞれが登場してくる歴史的・政治的文脈を明らかにしている点である。これを読むと、結局のところ、“代表的な”(と言われている)「日本人論」や「日本論」は、実は-カレル・ヴァン・ウォルフレンを除くと-基本的にア... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
日本文化に絡まる「思いこみ」を引き剥がす
希望の倫理学-日本文化と暴力をめぐって- / 持田季未子. - 平凡社, 1998
 北大ではどこにある?
「日本文化」は、実は様々な「思いこみ」や、近代に於ける「意味づけ」に絡め取られている。俗耳に入ってくるものの一つとして例えば「日本人は古来から自然を愛する」が挙げられよう。この本は、中世謡曲から始まって近代の帝国主義的イデオロギーまでを分析し、「日本文化」に絡みついている思いこみ、俗説、恣意的な意味付与を引き剥がそうとする試みである。その中から見えてくる「日本文化(と言われるもの)」の根底にはどうしようもない暴力的、閉塞的な性格が顕れてくる。それは単なる“ステレオタイプ”などと言ってすませられるレベルではない、重い倫理的課題を我々... [続きを読む]
北大ではどこにある?
「日本文化」は、実は様々な「思いこみ」や、近代に於ける「意味づけ」に絡め取られている。俗耳に入ってくるものの一つとして例えば「日本人は古来から自然を愛する」が挙げられよう。この本は、中世謡曲から始まって近代の帝国主義的イデオロギーまでを分析し、「日本文化」に絡みついている思いこみ、俗説、恣意的な意味付与を引き剥がそうとする試みである。その中から見えてくる「日本文化(と言われるもの)」の根底にはどうしようもない暴力的、閉塞的な性格が顕れてくる。それは単なる“ステレオタイプ”などと言ってすませられるレベルではない、重い倫理的課題を我々... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
インチキを見抜く考え方を学ぶ
日本文化論のインチキ / 小谷野敦. - 幻冬舎, 2010
 北大ではどこにある?
日本文化論というグループに括られる書物はものすごく(と言っていいほど)多くのものが出版されていて、他方、それらに対する批判の書も少なからず出されている。大学で日本文化を専門として学び研究する人間にとってそうした批判に目を通しておくのは当然だが、小谷野氏は、「日本文化論批判は行われているものの、批判のほうはいっこうに広まらないのである」と嘆いており、それがこの本を書いた動機の一部となっている。
北大ではどこにある?
日本文化論というグループに括られる書物はものすごく(と言っていいほど)多くのものが出版されていて、他方、それらに対する批判の書も少なからず出されている。大学で日本文化を専門として学び研究する人間にとってそうした批判に目を通しておくのは当然だが、小谷野氏は、「日本文化論批判は行われているものの、批判のほうはいっこうに広まらないのである」と嘆いており、それがこの本を書いた動機の一部となっている。
内容は、土居健郎『「甘え」の構造』やベネディクト『菊と刀』以来の日本文化論をめぐる研究状況に対するやや毒舌めいた批判であるが、新書版という-... [続きを読む] -
推薦者 : 川村 周三 (農学研究科)
なぜ日本人はモチを食べるのか?
照葉樹林文化とは何か 東アジアの森が生み出した文明 / 佐々木高明. - 中公新書, 2007
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
《2008年ノーベル文学賞受賞!!》芸術、文学、ヨーロッパ思想を学ぶ者にとって必読の書
悪魔祓い / J.M.G.ル・クレジオ〔著〕 ; 高山鉄男訳. - 新潮社, 1975
 北大ではどこにある?
ル・クレジオは現代のフランスの作家。1960年代に前衛的作家として華々しくフランスの文壇にデビューしたあと、現代の西洋文明に飽き足らず、パナマでアメリカ先住民とともに長らく暮らし、スペインに征服される前のメキシコの文明に深く分け入って、芸術とは何か、文学とは何か、文明とは何かを、人類的なトータルな視野から探り続けてきた。本書は、パナマ先住民との生活を通して、彼らの芸術観、生命観、宇宙観をヨーロッパとの比較のもとで描き出したもの。ル・クレジオは、よくあるように、アメリカ先住民の文明を、西洋文明にまだ犯されていない無垢なるものとして語... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ル・クレジオは現代のフランスの作家。1960年代に前衛的作家として華々しくフランスの文壇にデビューしたあと、現代の西洋文明に飽き足らず、パナマでアメリカ先住民とともに長らく暮らし、スペインに征服される前のメキシコの文明に深く分け入って、芸術とは何か、文学とは何か、文明とは何かを、人類的なトータルな視野から探り続けてきた。本書は、パナマ先住民との生活を通して、彼らの芸術観、生命観、宇宙観をヨーロッパとの比較のもとで描き出したもの。ル・クレジオは、よくあるように、アメリカ先住民の文明を、西洋文明にまだ犯されていない無垢なるものとして語... [続きを読む] -
推薦者 : 小川 泰寛 (メディア・コミュニケーション研究院)
狩りの観点からなされた西欧文明批判の書
人はなぜ殺すか : 狩猟仮説と動物観の文明史 / マット・カートミル著 ; 内田亮子訳. - 新曜社, 1995
 北大ではどこにある?
狩りの観点からなされた西欧文明批判の書。
北大ではどこにある?
狩りの観点からなされた西欧文明批判の書。
西欧文明において、動物は征服されるべき自然の一環とみなされた。受難は必至だった。これが著者の論点。創見ではないにもせよ、独自の説得力がある。というのも、本書では犠牲になる動物に目線が置かれているからである。
本書で展開されているのはしかし、本質的には人間論である。端的に言えば、人はなぜ何の罪もない動物を慰みに狩るのか。邦題に謳われているように、そもそも「人はなぜ殺すか」。この重い問いが終始省察されている。
生物人類学と解剖学が著者の専門。ただ、本書には西洋古典学、神学、精神分析学... [続きを読む] -
推薦者 : 岡田 敦美 (メディア・コミュニケーション研究院)
遠い世界の「他者」へ、思いをはせる
先住民ミヘの静かな変容―メキシコで考える / 黒田悦子. - 朝日選書, 1996
 北大ではどこにある?
ラテンアメリカの民族誌として定評ある一冊で、メキシコ南部オアハカ州での参与観察に基づいた著者の研究は、現地メキシコでも出版されているほどです。だまされたと思って、読んでみてください。
北大ではどこにある?
ラテンアメリカの民族誌として定評ある一冊で、メキシコ南部オアハカ州での参与観察に基づいた著者の研究は、現地メキシコでも出版されているほどです。だまされたと思って、読んでみてください。
1970年代にミヘの村に住んで、調査を済ませてから10年以上経った1990年代に、ミヘの村を再訪するところからこの本は始まります。出稼ぎや、都市への移住をはじめとする村の外部との行き来を通して、大きな変貌を遂げたミヘの人々を、「心の触れ合える人たち」として身近にとらえる、著者、すなわちフィールドワーカーの目を通して、私たちは遠いメキシコの先住民の人々の世界... [続きを読む] -
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
地域研究から人間性の探究へ。
現代文化人類学の課題―北方研究からみる― / 煎本孝、山岸俊男(編著). - 世界思想社, 2007
 北大ではどこにある?
地球規模で進行する急激な変動の時代、北方文化を語ることは、単なる地域研究の枠を超えて、人類学が抱えている普遍的課題に立ち向かうことである。「人間とは何か」というテーマのもと、現代の文化人類学が直面する喫緊の問題を鋭くえぐり出す。
北大ではどこにある?
地球規模で進行する急激な変動の時代、北方文化を語ることは、単なる地域研究の枠を超えて、人類学が抱えている普遍的課題に立ち向かうことである。「人間とは何か」というテーマのもと、現代の文化人類学が直面する喫緊の問題を鋭くえぐり出す。
詰論的展開 第1章 北方研究の展開/第2章 心の文化・生態学的基盤
狂Φ罎亮匆馘役割 第3章 研究論理と先住民族アイヌの人権/第4章 北海道大学におけるアイヌ・北方文化研究とアイヌ新法の制定
恵狼經超問題と開発 第5章 人類の生態と地球環境問題―ポスト社会主義下におけるクジラの利用と保護/第6章 北方... [続きを読む] -
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
たんけん、ワクワク。
トナカイ遊牧民、循環のフィロソフィー ―極北ロシア・カムチャツカ探検記― / 煎本 孝. - 明石書店, 2007
 北大ではどこにある?
期待と、同時に少しのあきらめに似た沈痛な気持ちの中、新潟空港を飛び立った一人の人類学徒の物語。
北大ではどこにある?
期待と、同時に少しのあきらめに似た沈痛な気持ちの中、新潟空港を飛び立った一人の人類学徒の物語。
「それはすばらしい時代でした。たくさんの人々がおり、また、その中のある者たちはシャマンでもありました。子供たちは枝を折り取り、それでトナカイを作り、互いに『トナカイ遊びをしよう』と言い合いながら遊んでいました…」と彼らが語るトナカイ遊牧の起源。
神々に捧げるトナカイの供犠、幻覚キノコの夢の中で訪れる死者の世界、ペレストロイカ以後の急激に変化するロシアで民族と国家とが対峙し、新しい文化が創造される最前線、そして、宇宙における生と死の永... [続きを読む] -
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
北方周極地域に生きる
北の民の人類学―強国に生きる民族性と帰属性― / 煎本孝 山田孝子(編著). - 京都大学学術出版会, 2007年
 北大ではどこにある?
ロシア、アメリカ、中国などの強国において、さまざまに揺れ動く社会状況の中で生きる北方周極地域の少数民族。圧倒的な力をもつ多数派集団と共生する彼らのエスニシティ(民族性)とアイデンティティ(帰属性)の動態を、人類学的視点から描き出す。
北大ではどこにある?
ロシア、アメリカ、中国などの強国において、さまざまに揺れ動く社会状況の中で生きる北方周極地域の少数民族。圧倒的な力をもつ多数派集団と共生する彼らのエスニシティ(民族性)とアイデンティティ(帰属性)の動態を、人類学的視点から描き出す。
序章:北の民の民族性と帰属性、第吃堯Фβ犬悗瞭察‖茖云魯▲ぅ綿顕修砲ける死の儀礼の復興をめぐる葛藤と帰属性/第2章カナダ・イヌイットの文化的アイデンティティとエスニック・アイデンティティ、第局堯А崋然」のシンボル化 第3章自然との共生/第4章「我々はカリブーの民である」/第5章アイデンティティ構築におけ... [続きを読む] -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
グローバル時代を真摯に生きるための知の指南書
異文化理解の倫理にむけて / 稲賀繁美(編). - 名古屋大学出版会, 2000
 北大ではどこにある?
異文化理解論については凡百の書が出ているが、この本はその中で出色ものである。特筆すべきは、大学での教科書としてつくられていながら、多くの類書とは全く違って、文化接触の生の現場を通して、思考する営みへと読者を導いてゆく内容構成がなされていることである。それは巻頭に掲げられている以下の「本書のねらい」が雄弁に語っている。
北大ではどこにある?
異文化理解論については凡百の書が出ているが、この本はその中で出色ものである。特筆すべきは、大学での教科書としてつくられていながら、多くの類書とは全く違って、文化接触の生の現場を通して、思考する営みへと読者を導いてゆく内容構成がなされていることである。それは巻頭に掲げられている以下の「本書のねらい」が雄弁に語っている。
1.異文化衝突の現場を提示する
2.文化間の価値観の相克、葛藤を浮き彫りにする
3.現場を知る専門家ならではの、読者へのメッセージ
4.概論提示ではなく、読者を理論構築へと誘う
5.読者による探求の道しるべを
こ... [続きを読む] -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
南米文化を知ろう
ボサ・ノーヴァ詩大全 / 坂尾英矩. - 中央アート出版, 2006
 北大ではどこにある?
音楽が好きな人、特にポップスが好きな人はボサノバ(旧来表記)を知っているだろう。「イパネマの娘」や「おいしい水」ぐらいは。しかしボサノバだけでなくフォークローレやその他の音楽もある。アルゼンチンタンゴもある。中南米は音楽の宝庫だ。また格闘技の好きな人はブラジルのカポエラやブラジリアン柔術も知っているはずだ。しかしカポエラが手を鎖で縛られた奴隷の護身術から発生したことは知っているだろうか(だから足技です)。文化を学ぶとはこういうことなのです。ジェローム・レ・バンナはフランス読みするとジェローム・ル・バネールです。これは日本にお... [続きを読む]
北大ではどこにある?
音楽が好きな人、特にポップスが好きな人はボサノバ(旧来表記)を知っているだろう。「イパネマの娘」や「おいしい水」ぐらいは。しかしボサノバだけでなくフォークローレやその他の音楽もある。アルゼンチンタンゴもある。中南米は音楽の宝庫だ。また格闘技の好きな人はブラジルのカポエラやブラジリアン柔術も知っているはずだ。しかしカポエラが手を鎖で縛られた奴隷の護身術から発生したことは知っているだろうか(だから足技です)。文化を学ぶとはこういうことなのです。ジェローム・レ・バンナはフランス読みするとジェローム・ル・バネールです。これは日本にお... [続きを読む] -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
人気の秘密
セレブの現代史 / 海野弘. - 文春新書,
 北大ではどこにある?
どうして有名人は影響力があるのか。教養の感じられない政治家がもてはやされるのか、この疑問の一つの答である。不倫のプリンセス、ワンフレーズの権力者、XX姉妹(XXには適当な文字を、解答複数)、なぜ彼らに人気があるのか。しかし少し怖い状況である。明日の世界はどうなる?
北大ではどこにある?
どうして有名人は影響力があるのか。教養の感じられない政治家がもてはやされるのか、この疑問の一つの答である。不倫のプリンセス、ワンフレーズの権力者、XX姉妹(XXには適当な文字を、解答複数)、なぜ彼らに人気があるのか。しかし少し怖い状況である。明日の世界はどうなる? -
推薦者 : 上田宏 (北方生物圏フィールド科学センター)
教科書が完成しました
フィールド科学への招待 / 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター. - 三共出版, 2006年
 北大ではどこにある?
全学教育「フィールド科学への招待」の教科書が出版されました。北海道大学の教育理念である“実学の重視”を実践している、北方生物圏フィールド科学センターの教員自らがフィールドで行なってきた研究成果を肉付けして教科書にしました。今、地球ではー人間が直面している課題ー、私たちはどのように対応するかーフィールド科学の実践例ー、人間活動の負荷を軽減するーフィールド科学の応用ー、フィールド科学の力など、新しい学問であるフィールド科学について学べます。
北大ではどこにある?
全学教育「フィールド科学への招待」の教科書が出版されました。北海道大学の教育理念である“実学の重視”を実践している、北方生物圏フィールド科学センターの教員自らがフィールドで行なってきた研究成果を肉付けして教科書にしました。今、地球ではー人間が直面している課題ー、私たちはどのように対応するかーフィールド科学の実践例ー、人間活動の負荷を軽減するーフィールド科学の応用ー、フィールド科学の力など、新しい学問であるフィールド科学について学べます。 -
推薦者 : 眞崎 睦子 (メディア・コミュニケーション研究院)
「このおれがアイヌだよ」
知里真志保の生涯―アイヌ学復権の闘い / 藤本英夫. - 草風館, 1994
 北大ではどこにある?
「知里君、北海道ならアイヌを見たかい」
北大ではどこにある?
「知里君、北海道ならアイヌを見たかい」
「アイヌが見たかったら、このおれがアイヌだよ」
……この「知里君」が辿った道(寄り道を含めて)
どうぞ読んでみてください。
「北海道に来たんだからこんな本でも読んでみよう」と
思った私の心に、もっとも怒りを感じるのは
誰でもない、この「知里君」なのだと思い知らされた一冊。 -
推薦者 : 下澤 楯夫 (電子科学研究所)
なぜ侵略されなければならないのか?
銃・病原菌・鉄 : 一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 / ジャレド・ダイアモンド著 ; 倉骨彰訳. - 草思社, 2000.10
 北大ではどこにある?
なぜ東南アジアは侵略されねばならないのか?なぜヨーロッパ人がアフリカや南北アメリカを侵略し、その逆は起こらなかったのか?文明の衝突というのなら、逆が起こっても良いではないか?
北大ではどこにある?
なぜ東南アジアは侵略されねばならないのか?なぜヨーロッパ人がアフリカや南北アメリカを侵略し、その逆は起こらなかったのか?文明の衝突というのなら、逆が起こっても良いではないか?
鳥類生態学の調査途上で出会った素朴な疑問に対する答えも、極めて単純なことだった。優越人種などいない。どの民族も、同じ能力を発揮できる。違いは単に「何処に住んでいたか」だけだったのだ。地球上の異なる大陸に住んでいた人種が出会ったとき、どちらが優位かは既に決まっていた。
-
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
コメディへの理解の方へ
ちはやふる奥の細道 / 小林信彦著. - 新潮社, 1988.11
 北大ではどこにある?
異文化理解を風刺した偽書(外人が書いた松尾芭蕉の伝記の訳書という体裁)。注にまでギャグがある。ドリフターズ以後しか知らない世代にとっては喜劇やミステリー、映画などについての小林信彦の本は格好の入門書である。映画や喜劇についてはその歴史も知らなければ論じることはできない。基礎知識を得るのに必読の著作家である。
北大ではどこにある?
異文化理解を風刺した偽書(外人が書いた松尾芭蕉の伝記の訳書という体裁)。注にまでギャグがある。ドリフターズ以後しか知らない世代にとっては喜劇やミステリー、映画などについての小林信彦の本は格好の入門書である。映画や喜劇についてはその歴史も知らなければ論じることはできない。基礎知識を得るのに必読の著作家である。 -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
国際地域文化論関係
クレオール主義 : the heterology of culture / 今福龍太著. - 青土社, 2001.9
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
表象文化論関係
東大オタク学講座 / 岡田斗司夫著. - 講談社, 1997.9
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 野坂 政司 (情報基盤センター)
ことばの地盤を掘り返してみよう
声の文化と文字の文化 / W.J.オング [著] ; 桜井直文, 林正寛, 糟谷啓介訳. - 藤原書店, 1991.10
 北大ではどこにある?
無文字社会の文化がどのように成立し、どのように伝承されていたかということは、想像も難しいし、考える糸口がどこにあるかも見つけにくい問題でしょう。
北大ではどこにある?
無文字社会の文化がどのように成立し、どのように伝承されていたかということは、想像も難しいし、考える糸口がどこにあるかも見つけにくい問題でしょう。
文字を手にした人間が、その後さらに多彩な表現メディアを獲得しつつ今日の情報文化社会を生活環境とするに至る過程で、声の文化がどのように生き延びてきたか、あるいは生きる環境を制限されてきたかという問題性は簡単には扱いきれない大きな問題です。
本を読んで考える、考えたことを書く、という文字という形を持ったことばに直面する作業は、大学において基本的かつ日常的な行動ですが、電子的メディア環... [続きを読む] -
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
空想すくすく、ノンフィクション文庫版
カナダ・インディアンの世界から / 煎本孝作. - 福音館書店, 2002.11
 北大ではどこにある?
トナカイを求めて、凍てつく雪原を来る日も来る日も犬橇を走らせるカナダ・インディアンの男たち。「トナカイは人が飢えている時、その肉を与えに自分からやってくるものだ」と彼らは言う。本書は、その魂に、“自然”の力を宿し、季節と共にその内なる力を育みつつ生きてゆく人びとの、たぐいまれなる記録である。丹念な取材に裏付けされた事実に基づく自然誌、成熟した読者にも読み応えのある作品。
北大ではどこにある?
トナカイを求めて、凍てつく雪原を来る日も来る日も犬橇を走らせるカナダ・インディアンの男たち。「トナカイは人が飢えている時、その肉を与えに自分からやってくるものだ」と彼らは言う。本書は、その魂に、“自然”の力を宿し、季節と共にその内なる力を育みつつ生きてゆく人びとの、たぐいまれなる記録である。丹念な取材に裏付けされた事実に基づく自然誌、成熟した読者にも読み応えのある作品。 -
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
アイヌの世界観を知ろう
アイヌの世界観 : 「ことば」から読む自然と宇宙 / 山田孝子著. - 講談社, 1994.8
 北大ではどこにある?
クマ・オオカミ・シマフクロウ・・・・・。魚の満ちあふれる川、シカが群れつどう山。大自然をアイヌはカムイ(神)としてとらえる。彼らの信仰はいかにして形成されたのか?「ことば」が「生活世界」を切り取るプロセス。秘密はそこにある。北の民の世界観がいま、認識人類学の立場から鮮やかに解明される。本書の内容・プロローグ、・アイヌの宇宙観、・霊魂とカムイ、・アイヌの植物命名法、・動物の分類と動物観、・諸民族との比較、・世界観の探求−認識人類学的アプローチ
北大ではどこにある?
クマ・オオカミ・シマフクロウ・・・・・。魚の満ちあふれる川、シカが群れつどう山。大自然をアイヌはカムイ(神)としてとらえる。彼らの信仰はいかにして形成されたのか?「ことば」が「生活世界」を切り取るプロセス。秘密はそこにある。北の民の世界観がいま、認識人類学の立場から鮮やかに解明される。本書の内容・プロローグ、・アイヌの宇宙観、・霊魂とカムイ、・アイヌの植物命名法、・動物の分類と動物観、・諸民族との比較、・世界観の探求−認識人類学的アプローチ -
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
自然とは?文化とは?人類学とは?
文化の自然誌 / 煎本孝著. - 東京大学出版会, 1996.6
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
変容著しい東北アジアの文化と言語の現在を読み解く!
東北アジア諸民族の文化動態 / 煎本孝編著. - 北海道大学図書刊行会, 2002.2
 北大ではどこにある?
日本、ロシア、中国、モンゴルを含む東北アジアには、広大で多様な環境が展開している。それは、民族学(文化人類学)的には北アジア、中央アジア、東アジアを含む地域である。生態的にも、地理的にもけっして閉鎖的な地域ではないこの多様な環境に生活する人々は、さまざまな文化と言語とをもっている。本書では東北アジアの文化と言語の動態を多角的に比較検討し、東北アジアの現在について考察する。
北大ではどこにある?
日本、ロシア、中国、モンゴルを含む東北アジアには、広大で多様な環境が展開している。それは、民族学(文化人類学)的には北アジア、中央アジア、東アジアを含む地域である。生態的にも、地理的にもけっして閉鎖的な地域ではないこの多様な環境に生活する人々は、さまざまな文化と言語とをもっている。本書では東北アジアの文化と言語の動態を多角的に比較検討し、東北アジアの現在について考察する。 -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
So this is how knowledge is put together
Guns, germs, and steel : the fates of human societies / Jared Diamond. - W.W. Norton, 2003
 北大ではどこにある?
Jared Diamond's Pulitzer-winning book of how geography affects
北大ではどこにある?
Jared Diamond's Pulitzer-winning book of how geography affects
civilizations is one example of how bits and pieces of scientific
fact are put together to form a testable hypothesis. While some may
disagree with Diamond's conclusions, it is difficult to disagree with
his logic.
Scientists (whom I define as any person practicing the scientific
method) base their argument on observable facts and procedures
suitable for interpreting those facts. As a scientist, I constantly
search for generalizable, universal rules or tendencies that predict
outcomes of yet-to-be-observed phenomena.
In his quest for rules that govern the rise and propagation of
civilizations, Diamond shows us how broad tendencies are extracted
from seemingly unrelated facts. Read his book to... [続きを読む] -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
世界を知るには自分を知ろう――日本の文化のDNAを知る最良の書
二重言語国家・日本 / 石川九楊著. - 日本放送出版協会, 1999.5
 北大ではどこにある?
著者は書道家として知られる一方、文字を通じ、われわれの日本文化(漢字・かな文化)について、中国文明(漢字文明圏)、ヨーロッパ文明(アルファベット文字文明圏)など世界全体の文明構造の中から解き明かす著作と論考を数多く発表しており、本書はその代表作。われわれが何気なく使っている漢字、かな、そして明治以降のアルファベットを通して、われわれの歴史、文化、ものの考え方の特徴が、それこそ目からウロコが落ちるように見えてくる。のみならず、現在の米中、日中関係すらも透けて見えてくるのは著者の思索の深さゆえか。同著者の『
北大ではどこにある?
著者は書道家として知られる一方、文字を通じ、われわれの日本文化(漢字・かな文化)について、中国文明(漢字文明圏)、ヨーロッパ文明(アルファベット文字文明圏)など世界全体の文明構造の中から解き明かす著作と論考を数多く発表しており、本書はその代表作。われわれが何気なく使っている漢字、かな、そして明治以降のアルファベットを通して、われわれの歴史、文化、ものの考え方の特徴が、それこそ目からウロコが落ちるように見えてくる。のみならず、現在の米中、日中関係すらも透けて見えてくるのは著者の思索の深さゆえか。同著者の『