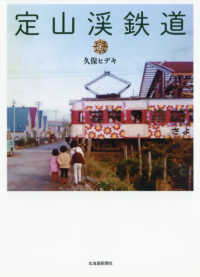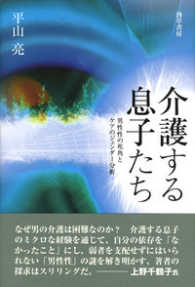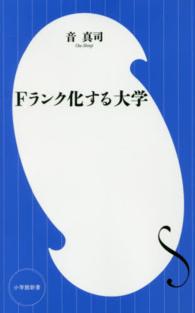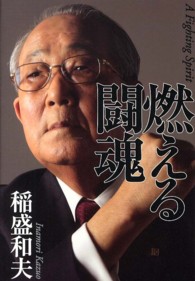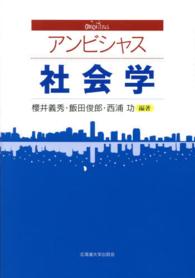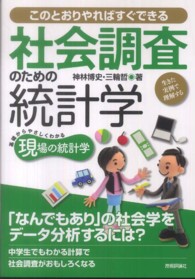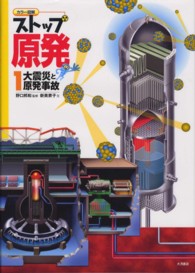-
推薦者 : 河合 剛 (外国語教育センター・教員)
国策教育の破綻
検証 迷走する英語入試――スピーキング導入と民間委託 / 南風原 朝和. - 岩波書店, 2018
 北大ではどこにある?
本書は大学入試における英語科目について述べているけれども、論理はさまざまな選考に適用できるので、諸君が将来人選するときに参考になろう。
北大ではどこにある?
本書は大学入試における英語科目について述べているけれども、論理はさまざまな選考に適用できるので、諸君が将来人選するときに参考になろう。
英語を読む・書く・聞く・話す能力(4技能)を高校で教えさせるため、大学入試に出題せよと文部科学省が命じた。試験の問題を作ったり、試験を実施したりするのは試験をなりわいとするプロにまかせろとの命令である。
試験とは能力を測る道具。どのような能力を身につけるのが望ましいのだろうか。
使える・通じる能力を求めるならば(自動車の運転免許のように)能力の閾値を上回れば合格(もしかすると全員入学... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (外国語教育センター・教員)
福島事故の隠蔽も似ている
Midnight in Chernobyl: The Untold Story of the World's Greatest Nuclear Disaster / Adam Higginbotham. - Simon & Schuster, 2019
 北大ではどこにある?
旧ソ連の秘密主義・隠蔽体質・国民軽視は為政者の権力維持・自己防衛が動機だったと考えられる。わが国の福島原発事故後の報道沈黙と東京電力経営者の責任回避も類似した動機に基づくかもしれない。西側職は、なまじ自由主義を標榜するあまり、マスコミや財界の中理性・信憑性が高いと誤解されやすい。
北大ではどこにある?
旧ソ連の秘密主義・隠蔽体質・国民軽視は為政者の権力維持・自己防衛が動機だったと考えられる。わが国の福島原発事故後の報道沈黙と東京電力経営者の責任回避も類似した動機に基づくかもしれない。西側職は、なまじ自由主義を標榜するあまり、マスコミや財界の中理性・信憑性が高いと誤解されやすい。
本書はチェルノブイリ原発事故の背景と経緯を記している。読者諸賢におかれては、事故の過程を技術と政策の両面から知り、わが国で起きた複数の原発事故をどのように報道すべきかを判断していただきたい。
書評が下記に。
https://www.nytimes.com/2019/02/06/books/review-midn... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (外国語教育センター・教員)
札幌の変貌を学び、未来を知る
定山渓鉄道 / 久保ヒデキ. - 北海道新聞社, 2018
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
不愉快な、しかし有益な本
介護する息子たち : 男性性の死角とケアのジェンダー分析 / 平山亮. - 勁草書房, 2017
 北大ではどこにある?
これを書いている僕は3月31日付けで北海道大学を退職する。理由は介護離職、つまりこの本の標題にもなっている「介護する息子」になるわけだ。この本は、そのような「介護する息子」になる前に参考とするべき点を調べようと思って読んだのだが、内容は全く違っていて、所謂ジェンダー社会学の立場から「介護する息子」たちが一見親の介護で苦労しているように見えながら、その背後には女性(配偶者や姉妹)からの支援や女性に対する差別やジェンダー的不均衡があるという可視性の低い問題点をこれでもかとばかりに暴き出す研究書だった。
北大ではどこにある?
これを書いている僕は3月31日付けで北海道大学を退職する。理由は介護離職、つまりこの本の標題にもなっている「介護する息子」になるわけだ。この本は、そのような「介護する息子」になる前に参考とするべき点を調べようと思って読んだのだが、内容は全く違っていて、所謂ジェンダー社会学の立場から「介護する息子」たちが一見親の介護で苦労しているように見えながら、その背後には女性(配偶者や姉妹)からの支援や女性に対する差別やジェンダー的不均衡があるという可視性の低い問題点をこれでもかとばかりに暴き出す研究書だった。
考えてみれば著者の平山氏は... [続きを読む] -
推薦者 : 小泉 均 (工学研究院・教員)
錆(さび、腐食)と取り組むさまざまな人々の仕事と人間像を描いた本
錆と人間 : ビール缶から戦艦まで / ジョナサン・ウォルドマン著 ; 三木直子訳. - 築地書館, 2016
 北大ではどこにある?
錆(さび、腐食)と取り組むさまざまな人々の仕事と人間像を描いた本である。錆と人間の歴史から、自由の女神の腐食と補修、ステンレス鋼の発明、缶の腐食と環境ホルモン、錆を撮り続ける写真家、アメリカ国防総省の防食担当者、防食技術者という職業について、石油パイプラインと錆探知ロボットなど、さまざまな事について取り上げている。錆という点で共通しているだけで、全体として一貫したテーマがあるようには見えない。書き方も各章でバラバラである。しかし、錆というものが、どのような科学や工学、社会、政治、人間とかかわっているか概観でき、非常におもしろく... [続きを読む]
北大ではどこにある?
錆(さび、腐食)と取り組むさまざまな人々の仕事と人間像を描いた本である。錆と人間の歴史から、自由の女神の腐食と補修、ステンレス鋼の発明、缶の腐食と環境ホルモン、錆を撮り続ける写真家、アメリカ国防総省の防食担当者、防食技術者という職業について、石油パイプラインと錆探知ロボットなど、さまざまな事について取り上げている。錆という点で共通しているだけで、全体として一貫したテーマがあるようには見えない。書き方も各章でバラバラである。しかし、錆というものが、どのような科学や工学、社会、政治、人間とかかわっているか概観でき、非常におもしろく... [続きを読む]登録日 : 2017-10-19
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
やっぱり大学の未来は心配だ。
Fランク化する大学 / 音真司著. - 小学館, 2016
 北大ではどこにある?
この本を「本は脳を育てる」に推薦することに対して旧帝国大学である“天下の北海道大学”の真面目な先生や優秀な学生から異論や批判が巻き起こるかもしれない。筆者自身も、この本に書いてあることは100%そのままであるとは思いたくないし、著者がやや大げさに書いている=「話を盛っている」面もあるかもしれないと思っている。しかし、他大学につとめる友人知人の現場の声を聞くと、ここに書いてあることを頭ごなしに否定することもできないと思う。そして、筆者自身が何より恐れるのは、―ここまでひどくないとしても―これらに近似する状況がここ数年の間に静かに北海道... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本を「本は脳を育てる」に推薦することに対して旧帝国大学である“天下の北海道大学”の真面目な先生や優秀な学生から異論や批判が巻き起こるかもしれない。筆者自身も、この本に書いてあることは100%そのままであるとは思いたくないし、著者がやや大げさに書いている=「話を盛っている」面もあるかもしれないと思っている。しかし、他大学につとめる友人知人の現場の声を聞くと、ここに書いてあることを頭ごなしに否定することもできないと思う。そして、筆者自身が何より恐れるのは、―ここまでひどくないとしても―これらに近似する状況がここ数年の間に静かに北海道... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
ネット空間で被害者にも加害者にもならないようにするために。
ネット炎上の研究 : 誰があおり、どう対処するのか / 田中辰雄, 山口真一著. - 勁草書房, 2016
 北大ではどこにある?
この本は、インターネット上で発生するいわゆる「炎上」という現象を分析し、その実態と歴史(!)と対応策を分かりやすく述べている。特に最後の「付録 炎上リテラシー教育のひな型」では、高校生を対象として想定し、「炎上」の仕組みとそれに巻き込まれそうになったらどうするべきかを丁寧に説いてくれている。インターネットがこれだけ広範囲に利用されるようになった社会で安全に生活し、かつ自分が加害者にならないためにも読んでおくべき1冊である。
北大ではどこにある?
この本は、インターネット上で発生するいわゆる「炎上」という現象を分析し、その実態と歴史(!)と対応策を分かりやすく述べている。特に最後の「付録 炎上リテラシー教育のひな型」では、高校生を対象として想定し、「炎上」の仕組みとそれに巻き込まれそうになったらどうするべきかを丁寧に説いてくれている。インターネットがこれだけ広範囲に利用されるようになった社会で安全に生活し、かつ自分が加害者にならないためにも読んでおくべき1冊である。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「研究」ということの神髄に触れる
師範学校制度史研究-15年戦争下の教師教育- / 逸見勝亮. - 北海道大学図書刊行会, 1991
 北大ではどこにある?
この本は、僕の専門分野と関わりがあるので読んだものだが、推薦文としては「良書だから読むべし!」としか言いようがない。実は,僕はこの著者である逸見先生(元教育学部長・現名誉教授)の“ファン”なのである。まだ逸見先生がご在職中にこの本を読んで疑問に思った点があったので、直接教えを請う機会をいただいたのだが、逸見先生のご教示、お人柄、生き方に痺れて、ファンになり今に至っている。その意味ではここに推薦するのが遅すぎたくらいだ。こういう推薦の仕方にきっと先生には眉をひそめられるかもしれないが、そこはお許しいただいて、多くの学生に読んでも... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、僕の専門分野と関わりがあるので読んだものだが、推薦文としては「良書だから読むべし!」としか言いようがない。実は,僕はこの著者である逸見先生(元教育学部長・現名誉教授)の“ファン”なのである。まだ逸見先生がご在職中にこの本を読んで疑問に思った点があったので、直接教えを請う機会をいただいたのだが、逸見先生のご教示、お人柄、生き方に痺れて、ファンになり今に至っている。その意味ではここに推薦するのが遅すぎたくらいだ。こういう推薦の仕方にきっと先生には眉をひそめられるかもしれないが、そこはお許しいただいて、多くの学生に読んでも... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
信仰をめぐる様々な問題を考えさせる本
黒い海の記憶-いま、死者の語りを聞くこと- / 山形孝夫. - 岩波書店, 2013
 北大ではどこにある?
山形孝夫氏の本をすでに「本は脳を育てる」に2冊推薦したが、この『黒い海の記憶』は東日本大震災による犠牲者の鎮魂を軸として、山形氏自身の留学体験や信仰に触れながら宗教或いは信仰が持つ功罪両面に鋭い考察を加えたものである。盛り込まれた話題が豊富であり、読者はそれぞれの関心に応じて思考を触発されると思う。僕は、若き日の山形氏が留学先で出会った黒人キリスト教会をめぐる体験談と白人によるキリスト教のあり方の考察、そして、死者の祟りの封じ込めのための宗教へと変質した仏教に対する批判に考えさせられるものがあった。
北大ではどこにある?
山形孝夫氏の本をすでに「本は脳を育てる」に2冊推薦したが、この『黒い海の記憶』は東日本大震災による犠牲者の鎮魂を軸として、山形氏自身の留学体験や信仰に触れながら宗教或いは信仰が持つ功罪両面に鋭い考察を加えたものである。盛り込まれた話題が豊富であり、読者はそれぞれの関心に応じて思考を触発されると思う。僕は、若き日の山形氏が留学先で出会った黒人キリスト教会をめぐる体験談と白人によるキリスト教のあり方の考察、そして、死者の祟りの封じ込めのための宗教へと変質した仏教に対する批判に考えさせられるものがあった。
ただ、残念なのは、これほどの... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
とりあえず元気になりたい人に。
燃える闘魂 / 稲盛和夫. - 毎日新聞社, 2013
 北大ではどこにある?
正直に言えばこの本を「本は脳を育てる」に推薦するのは躊躇いがあった。こう書いている今も、図書館のA係長の困り切った表情が目に浮かんでくるようだ。それはそれで分かる。所謂典型的な日本の経営者のビジネス精神論だからだ。ビジネスは研究の対象になるが、精神論(或いは根性論)は研究の対象にはなり得ない。それでもなぜ推薦したかというと、最近の僕の周りの人間は教員も事務職員も学生も元気がない人たちが多いからだ。そういうときには”空元気”でいいから、とにかくテンションが上がる本を読みたい。そういうわけでここに推薦してしまった。
北大ではどこにある?
正直に言えばこの本を「本は脳を育てる」に推薦するのは躊躇いがあった。こう書いている今も、図書館のA係長の困り切った表情が目に浮かんでくるようだ。それはそれで分かる。所謂典型的な日本の経営者のビジネス精神論だからだ。ビジネスは研究の対象になるが、精神論(或いは根性論)は研究の対象にはなり得ない。それでもなぜ推薦したかというと、最近の僕の周りの人間は教員も事務職員も学生も元気がない人たちが多いからだ。そういうときには”空元気”でいいから、とにかくテンションが上がる本を読みたい。そういうわけでここに推薦してしまった。
ちなみに僕も... [続きを読む] -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
社会科学方法論の名著
創造の方法学 / 高根正昭. - 筑摩書房, 1979
 北大ではどこにある?
入門~。社会科学の方法論についてわかりやすく解説した名著です。
北大ではどこにある?
入門~。社会科学の方法論についてわかりやすく解説した名著です。
理論とは何か、概念とは何か、モデルとは何か、理論をどのようにして具体的なデータで検証するのか、条件を統制するとはどういうことなのか、といったことが著者のアメリカでの研究生活の話を交えながら丁寧に説明されています。特に実験との対比させながら社会調査における分析のロジックを説明しているのがわかりやすいと思います。社会科学専攻の人に限らず多くの人々に是非一度手に取ってもらいたい一冊です。 -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
社会調査法の充実したテキスト
入門・社会調査法─2ステップで基礎から学ぶ(第2版) / 轟亮, 杉野勇編. - 法律文化社, 2013
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
報道記事の読み方、分析手順、科学的分析のロジック
データはウソをつく─科学的な社会調査の技法 / 谷岡一郎. - 筑摩書房, 2007
 北大ではどこにある?
特に社会調査に基づいた報道記事を読む際のコツについて多くのページが割かれています。実際のデータ分析の段取りや科学的分析のロジックについても初学者向けにわかりやすく述べられています。社会調査に関心をもった場合は、まず本書を手に取ってみることをお勧めします。
北大ではどこにある?
特に社会調査に基づいた報道記事を読む際のコツについて多くのページが割かれています。実際のデータ分析の段取りや科学的分析のロジックについても初学者向けにわかりやすく述べられています。社会調査に関心をもった場合は、まず本書を手に取ってみることをお勧めします。 -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
入門から上級まで幅広く使える社会学の教科書
アンビシャス社会学 / 櫻井義秀, 飯田俊郎, 西浦功編著. - 北海道大学出版会, 2014
 北大ではどこにある?
北海道大学文学研究科社会システム科学講座の関係者を中心に作成した社会学テキスト。現代日本における様々な社会的トピックについて、具体的な事例を提示しつつその分野での基本概念・用語などをしっかり身に付けられる構成になっています。
北大ではどこにある?
北海道大学文学研究科社会システム科学講座の関係者を中心に作成した社会学テキスト。現代日本における様々な社会的トピックについて、具体的な事例を提示しつつその分野での基本概念・用語などをしっかり身に付けられる構成になっています。
会学の入門書としてはもちろんのこと、各種試験対策(公務員、社会福祉士、大学院入試など)にも対応できるように作っています。 -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
社会調査のための、極めてわかりやすい統計の入門書
このとおりやればすぐできる社会調査のための統計学-生きた実例で理解する- / 神林博史, 三輪哲. - 技術評論社, 2011
 北大ではどこにある?
よく使われる社会調査の統計解析の初歩が解説されています。記述統計を中心にクロス集計や統計的検定、疑似相関と因果関係などについてわかりやすく書かれています。表や図の作り方など非常にわかりやすく、また途中ではさまれる会話がより一層わかりやすさを引き立てています。統計アレルギーの人、統計学の授業で挫折してしまった人は一度手に取ってみると良いでしょう。
北大ではどこにある?
よく使われる社会調査の統計解析の初歩が解説されています。記述統計を中心にクロス集計や統計的検定、疑似相関と因果関係などについてわかりやすく書かれています。表や図の作り方など非常にわかりやすく、また途中ではさまれる会話がより一層わかりやすさを引き立てています。統計アレルギーの人、統計学の授業で挫折してしまった人は一度手に取ってみると良いでしょう。 -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
質的社会調査のハンドブック
よくわかる質的社会調査─技法編 / 谷富夫, 芦田徹郎編著. - ミネルヴァ書房, 2009
 北大ではどこにある?
社会調査の中の質的調査について、様々な技法が紹介されています。インタビュー、フィールドワーク、グランデッド・セオリー・アプローチ、ライフヒストリー法、ワークショップ、アクションリサーチ、内容分析などが扱われています。各調査の理論的背景や心構えよりも、むしろ具体的なやり方を詳しく説明しています。どうやってアポをとるのか、どうやってインタビューデータを整理するのか、どうやってワークショップを開くのかなど具体的な話が豊富ですので、手元に置いておくと便利な一冊です。
北大ではどこにある?
社会調査の中の質的調査について、様々な技法が紹介されています。インタビュー、フィールドワーク、グランデッド・セオリー・アプローチ、ライフヒストリー法、ワークショップ、アクションリサーチ、内容分析などが扱われています。各調査の理論的背景や心構えよりも、むしろ具体的なやり方を詳しく説明しています。どうやってアポをとるのか、どうやってインタビューデータを整理するのか、どうやってワークショップを開くのかなど具体的な話が豊富ですので、手元に置いておくと便利な一冊です。
なお姉妹編として「プロセス編」もありますので合わせて読むと質的社会調査... [続きを読む] -
推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)
ひとりで学ぶ計量分析
データアーカイブSRDQで学ぶ社会調査の計量分析 / 川端亮編著. - ミネルヴァ書房, 2010
 北大ではどこにある?
大阪大学のSRDQシステムを用いて計量分析を学ぶためのテキストです。
北大ではどこにある?
大阪大学のSRDQシステムを用いて計量分析を学ぶためのテキストです。
本書の最大の特徴は、SRDQに寄託された本物の社会調査データの分析を行えることです。
テキストの各章ではその分析方法を用いた論文が提示されています。まずこの論文を読み、次にテキストを見ながらSRDQ(ネット環境があればどこでも使用可能)を使ってその論文の分析を再現していきます。最後に章末の練習問題を解くことでより分析のコツがのみこめるようになります。
実際の論文を読みその分析を追体験しながら分析を身に着けていくという実践的スタイルが本書の目玉と言えるでしょう。分析方法はクロス... [続きを読む] -
推薦者 : 岸 玲子 (環境健康科学研究教育センター)
広範囲な予防医学や公衆衛生学の諸領域をわかりやすく理念に基づいて記述
NEW予防医学・公衆衛生学(改訂第3版) / 岸玲子 [ほか] 編. - 南江堂, 2012
 北大ではどこにある?
予防医学・公衆衛生学の目的や理念がわかりやすい学習書です。
北大ではどこにある?
予防医学・公衆衛生学の目的や理念がわかりやすい学習書です。
人々の健康と疾病予防の重要性を歴史や社会との関係で学ぶことができます。
50人を超える専門家がそれぞれの章を書いており学問的にも高いレベルです。 -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
think hard, act decisively
カラー図解 ストップ原発〈1〉大震災と原発事故 (全4巻) / 新美景子. - 大月書店, 2011
 北大ではどこにある?
Japan lacks investigative journalism. Scientific journalism is almost as scarce. Read this series of 4 illustrated books for children. Familiarize yourself with the theory, history, objectives, advantages, and costs of nuclear energy. You may wonder why you knew so little before picking up these books.
北大ではどこにある?
Japan lacks investigative journalism. Scientific journalism is almost as scarce. Read this series of 4 illustrated books for children. Familiarize yourself with the theory, history, objectives, advantages, and costs of nuclear energy. You may wonder why you knew so little before picking up these books.
I vehemently oppose nuclear power plants. You may agree or disagree with me. Either way, you owe it to yourself and the world to learn all about the issue, particularly the aspects that the government and industry strive to hide. -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
日本社会の病い
まやかしの安全の国 / 田辺文也. - 角川SSC新書137, 2011
 北大ではどこにある?
去る3月11日の地震・津波による福島第一原発の事故は様々な疑問を投げかけます。事故の発生という事実に直面してからでは遅いといわれそうですが、原子力に携わる人々や事故に対処する政府関係者や事故の直接の当事者などの個人的資質にも疑念を呈したくなりますし、それを許容する社会の制度にも不信を抱かざるをえません。この本はそういう疑問に答えてくれそうですし、考えるきっかけを与えてくれそうです。以下、著者のあとがきより引用します。
北大ではどこにある?
去る3月11日の地震・津波による福島第一原発の事故は様々な疑問を投げかけます。事故の発生という事実に直面してからでは遅いといわれそうですが、原子力に携わる人々や事故に対処する政府関係者や事故の直接の当事者などの個人的資質にも疑念を呈したくなりますし、それを許容する社会の制度にも不信を抱かざるをえません。この本はそういう疑問に答えてくれそうですし、考えるきっかけを与えてくれそうです。以下、著者のあとがきより引用します。
・・・・・原子力のような巨大システムの安全確保に不可欠なのは、設備の運転や保守に携わる人のシステムに対する深い... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
老いと社会のつながりを考える
暴走老人! / 藤原智美. - 文藝春秋, 2007
 北大ではどこにある?
最近、老人(高齢者)の犯罪がメディアで報道されることが多くなったように思う。老人が犯罪をするからメディアがニュースネタとして飛びつくのか、本当に老人の犯罪が増えているのかは慎重に考える必要があるだろう。しかし、少なくともこれまでの社会の(あるいはメディアの)あり方として、若者の犯罪や不作法には寛容ではなかった一方で老人の犯罪や不作法(特に後者)が大目に見られてきた面はある。このページを読んでいる人の中にも、町中での老人の振る舞いに「年寄りだから何でも許されるってわけじゃねーよ!」と思ったことがある人がそこそこいるに違いない(実は、... [続きを読む]
北大ではどこにある?
最近、老人(高齢者)の犯罪がメディアで報道されることが多くなったように思う。老人が犯罪をするからメディアがニュースネタとして飛びつくのか、本当に老人の犯罪が増えているのかは慎重に考える必要があるだろう。しかし、少なくともこれまでの社会の(あるいはメディアの)あり方として、若者の犯罪や不作法には寛容ではなかった一方で老人の犯罪や不作法(特に後者)が大目に見られてきた面はある。このページを読んでいる人の中にも、町中での老人の振る舞いに「年寄りだから何でも許されるってわけじゃねーよ!」と思ったことがある人がそこそこいるに違いない(実は、... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
Detecting, correcting, and preventing academic dishonesty
Crisis on campus : confronting academic misconduct / Wilfried Decoo with a contribution by Jozef Colpaert. - MIT Press, 2002
 北大ではどこにある?
Unlike some schools, Hokudai does not ask its constituents to
北大ではどこにある?
Unlike some schools, Hokudai does not ask its constituents to
explicitly declare academic integrity.
Instead, the code of ethics is implicit.
The lack of declaration or affirmation is not by itself detrimental (although a formal ceremony or signing of a statement might add weight to the commitment).
The danger lies in two aspects.
(a) Risk of unfairness. Unspecified rules are difficult to apply consistently.
(b) Risk of reluctant compliance. Researchers who do not understand why such rules exist are less likely to abide by the spirit of the rules. Scientists who do not embrace high standards may view them as a bureaucratic hinderance, or worse, connive methods to
circumvent them.
This book explains several methods for sustaining academic integrity.
The authors were di... [続きを読む] -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
教育学部以外の学生諸君もぜひ
子どもが見ている背中 : 良心と抵抗の教育 / 野田正彰. - 岩波書店, 2006
 北大ではどこにある?
北大医学部出身の精神医学者が、教育、特に国旗・国歌の強制から教育基本法の改定にいたる動きを論じた本。広島県の二人の校長が自殺に追い込まれ、それを利用して国旗国歌法が制定されたこと(自殺は一方的に反対した教師たちのせいではない事実)、教育現場への締め付けを告発している。この問題に関する著者の主張に賛成、反対は別にして、いろいろな事実や背景を知った上で自分の意見を決めねば、指導者の言うことやメディアの論調に流されてしまう。それは広告と同じで、イメージ戦略にのってしまうことである。同じ問題を扱った旧著
北大ではどこにある?
北大医学部出身の精神医学者が、教育、特に国旗・国歌の強制から教育基本法の改定にいたる動きを論じた本。広島県の二人の校長が自殺に追い込まれ、それを利用して国旗国歌法が制定されたこと(自殺は一方的に反対した教師たちのせいではない事実)、教育現場への締め付けを告発している。この問題に関する著者の主張に賛成、反対は別にして、いろいろな事実や背景を知った上で自分の意見を決めねば、指導者の言うことやメディアの論調に流されてしまう。それは広告と同じで、イメージ戦略にのってしまうことである。同じ問題を扱った旧著 -
推薦者 : 蔵田 伸雄 (文学研究科)
この社会の中で対話を実現していくために
「対話」のない社会 : 思いやりと優しさが圧殺するもの / 中島義道著. - PHP研究所, 1997.11
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 高井 潔司 (メディア・コミュニケーション研究院)
情報化社会を読み解く書
世論 / W.リップマン著 ; 掛川トミ子訳. - 岩波書店, 1987.7
 北大ではどこにある?
情報伝達手段の急速な発展で、私たちはいやおうなく情報に取り囲まれ、ともすれば、実生活よりも情報との関わりの中で、生きていることに気づく。そして、一歩引き下がって考えてみると、情報化社会によってどれほど悲劇も生じているかが見えてくる。
北大ではどこにある?
情報伝達手段の急速な発展で、私たちはいやおうなく情報に取り囲まれ、ともすれば、実生活よりも情報との関わりの中で、生きていることに気づく。そして、一歩引き下がって考えてみると、情報化社会によってどれほど悲劇も生じているかが見えてくる。
情報化社会を生き抜いていくには、そもそも情報とはどのようにして作られるのか、どのような性質を持っているのか、マスメディアが伝える情報とどう向き合うべきなのか。インターネットは本当にマスメディアよりも信頼できるメディアなのかーーなどの問題をきちんと考えていく必要があるだろう。
こうした問題を考え... [続きを読む] -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
表象文化論関係
初潮という切札 : 「少女」批評・序説 / 横川寿美子著. - JICC出版局, 1991.3
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 陳 省仁 (教育学研究科)
世界を知る視点
Letters to Lily : on how the world works / Alan Macfarlane. - Profile Books, 2005
 北大ではどこにある?
インド生まれの英国ケンブリッジ大学の人類学・歴史学者による好著。
北大ではどこにある?
インド生まれの英国ケンブリッジ大学の人類学・歴史学者による好著。
現在7歳の孫娘が17歳になる時に読むための20通の手紙という形で、
現代人が生きていくための重要な問題を幅広い視点から考察する。
文章は読みやすく、流麗な英語である。
著者のウェブページもとっても興味深い勉強になる内容が一杯詰まっている。
http://www.alanmacfarlane.com/
HPの左下「Letters to Lily」のアイコンをクリックすれば、
本書の最初の3通を著者の肉声で聞くことができる。 -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
国際地域文化論関係
戦争の世紀を超えて : その場所で語られるべき戦争の記憶がある / 森達也, 姜尚中著. - 講談社, 2004.11
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?