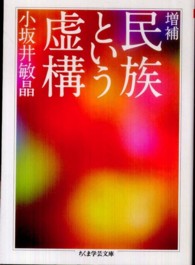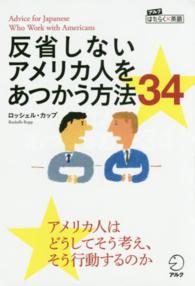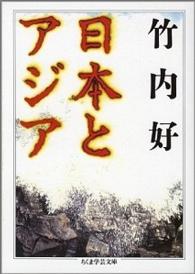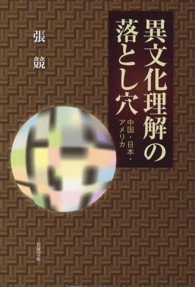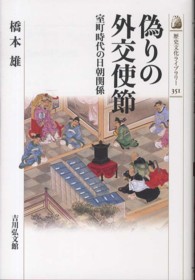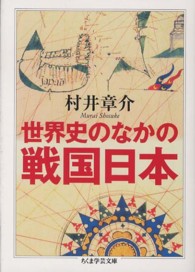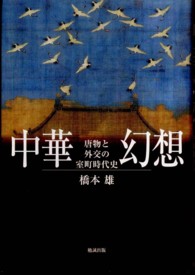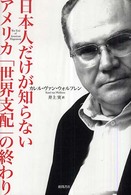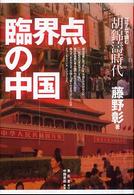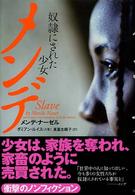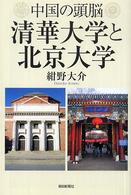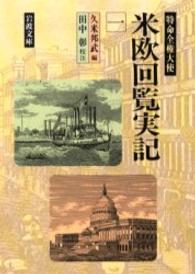-
推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科(日本史学講座)・教員)
常識を突き崩してみよう。
民族という虚構 / 小坂井敏晶著. - 筑摩書房, 2011
 北大ではどこにある?
本書は、強いていえば、著者小坂井氏の〈本籍〉からして、社会心理学の成果と言えるでしょうか。しかしながら本書は、グローバル時代に生きる者すべてが参照すべき卓見に満ちあふれています。隣人・隣国とのより良い関係のために書かれた書として、歴史学にとっても重要な一書と考えます。
北大ではどこにある?
本書は、強いていえば、著者小坂井氏の〈本籍〉からして、社会心理学の成果と言えるでしょうか。しかしながら本書は、グローバル時代に生きる者すべてが参照すべき卓見に満ちあふれています。隣人・隣国とのより良い関係のために書かれた書として、歴史学にとっても重要な一書と考えます。
本書の「あとがき」によると、「生物学・社会学・政治哲学など広い領域に触れ、学際的試論の性格を持つ」、真に学際的な成果です。また、「民族同一性の脱構築を試み、近代的合理主義を批判する」ことを目指したものだともいいます。そのいずれにおいても成功を収めた快著だと私は考え... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
君は世界をまたにかけるビジネスパースンになれるか?
反省しないアメリカ人をあつかう方法34 / ロッシェル・カップ著. - アルク, 2015
 北大ではどこにある?
北大生の中には将来外資系企業、あるいは海外で働くことを希望している人もいるだろう。また、国内の職場でも上司や同僚や部下が外国人という環境は最早珍しくない。この本は、「反省しないアメリカ人を~」と書いてあるとおり、アメリカ人の、主に従業員に対してどう接し、どのように良好なビジネス上の関係を構築するかについてアドバイスを述べたものであるが、アメリカ人に限らず異なる文化的背景の人間―日本人でもその範疇に入ってくる可能性は大いにある―と仕事をする上でヒントになるものと思う。比較文化研究や異文化間コミュニケーションに関心のある人には、色... [続きを読む]
北大ではどこにある?
北大生の中には将来外資系企業、あるいは海外で働くことを希望している人もいるだろう。また、国内の職場でも上司や同僚や部下が外国人という環境は最早珍しくない。この本は、「反省しないアメリカ人を~」と書いてあるとおり、アメリカ人の、主に従業員に対してどう接し、どのように良好なビジネス上の関係を構築するかについてアドバイスを述べたものであるが、アメリカ人に限らず異なる文化的背景の人間―日本人でもその範疇に入ってくる可能性は大いにある―と仕事をする上でヒントになるものと思う。比較文化研究や異文化間コミュニケーションに関心のある人には、色... [続きを読む]登録日 : 2017-08-07
-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
日本人はアジアとどう向き合ってきたか
日本とアジア / 竹内好著. - 筑摩書房, 1993
 北大ではどこにある?
これは、竹内好という稀代の中国文学者の手になるすぐれた日本、及びアジア研究の書である。初版が刊行されてから50年以上が経過しているが、そこに示される分析(あるいは同時代思想批判の)の観点には今なお学ぶものが多くある。中国、アジアだけでなく、というよりむしろ欧米社会・文化に関心を持つ人にこそ読んでほしいと思う。特に「二つのアジア史観」、「方法としてのアジア」は人文社会科学を勉強する上で貴重な示唆を含んでいる。
北大ではどこにある?
これは、竹内好という稀代の中国文学者の手になるすぐれた日本、及びアジア研究の書である。初版が刊行されてから50年以上が経過しているが、そこに示される分析(あるいは同時代思想批判の)の観点には今なお学ぶものが多くある。中国、アジアだけでなく、というよりむしろ欧米社会・文化に関心を持つ人にこそ読んでほしいと思う。特に「二つのアジア史観」、「方法としてのアジア」は人文社会科学を勉強する上で貴重な示唆を含んでいる。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
モンゴルの魅力に近づくために
草原の革命家たち : モンゴル独立への道 / 田中克彦著. - 中央公論社, 1990
 北大ではどこにある?
この「本は脳を育てる」の過去の推薦文に何回か書いたことであるが、僕は1990年代にエジプトに赴任していた。だが、最初に赴任先候補地としてあげられたのは、実はモンゴルであった。それがどこかでどうにかこうにかなってエジプトに落ち着いた(?)のであるが、今でも時々、あのときモンゴルに行っていたらどうなっていただろうかと思うことがある。今は、モンゴルと言えば相撲の世界が思い浮かぶだろうが、多くの日本人の間でこの国の歴史と現在の姿は意外に知られていないと言ってよいだろう。この本は、モンゴルが中国、ソヴィエトという巨大な国に挟まれて―しかもここ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この「本は脳を育てる」の過去の推薦文に何回か書いたことであるが、僕は1990年代にエジプトに赴任していた。だが、最初に赴任先候補地としてあげられたのは、実はモンゴルであった。それがどこかでどうにかこうにかなってエジプトに落ち着いた(?)のであるが、今でも時々、あのときモンゴルに行っていたらどうなっていただろうかと思うことがある。今は、モンゴルと言えば相撲の世界が思い浮かぶだろうが、多くの日本人の間でこの国の歴史と現在の姿は意外に知られていないと言ってよいだろう。この本は、モンゴルが中国、ソヴィエトという巨大な国に挟まれて―しかもここ... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
韓国は「異星」である、か?
韓国、愛と思想の旅 / 小倉紀藏. - 大修館書店, 2004
 北大ではどこにある?
仕事柄韓国人留学生とのつきあいが少なからずあるが、いつも彼ら彼女らとの独特の距離の置き方にはかなりデリケートに神経を使う。こういうことを“国際交流”の入り口で仕事をしている人間が書くと問題だと感じる人もいるだろうが、むしろそうした仕事をしているからこそ適度な距離感が必要であるとも言える。この小倉氏の本は、韓国滞在・渡航経験の中でその距離を縮めようとしてついに叶わなかった(もしくは彼なりのやり方でその距離を消滅させていった)異文化間コンフリクトの記録である。韓国に対する読者のスタンスの取り方に応じてそれなりに“ツッコミどころ”も... [続きを読む]
北大ではどこにある?
仕事柄韓国人留学生とのつきあいが少なからずあるが、いつも彼ら彼女らとの独特の距離の置き方にはかなりデリケートに神経を使う。こういうことを“国際交流”の入り口で仕事をしている人間が書くと問題だと感じる人もいるだろうが、むしろそうした仕事をしているからこそ適度な距離感が必要であるとも言える。この小倉氏の本は、韓国滞在・渡航経験の中でその距離を縮めようとしてついに叶わなかった(もしくは彼なりのやり方でその距離を消滅させていった)異文化間コンフリクトの記録である。韓国に対する読者のスタンスの取り方に応じてそれなりに“ツッコミどころ”も... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
異文化理解はぼちぼちこのあたりから…。
異文化理解の落とし穴 : 中国・日本・アメリカ / 張競. - 岩波書店, 2011
 北大ではどこにある?
この本は、上海出身中国人で日本に留学し学位を得て日本で教職に就きアメリカで研究生活も送った著者の異文化体験の記録である。読後感としては標題にあるような「異文化理解」というレベルに達しているとは思えないし、ましてやその「落とし穴」を明解にしているとも言い切れない。むしろ表層的な体験と感想が連ねられているというのが率直なところである。しかし、それは裏を返せば、「異文化理解」ということに到達するには誰もがこの段階をくぐらなければならないということを示す一つの基準点になり得ている、ということであり、また、日本に限らず「文化」というもの... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、上海出身中国人で日本に留学し学位を得て日本で教職に就きアメリカで研究生活も送った著者の異文化体験の記録である。読後感としては標題にあるような「異文化理解」というレベルに達しているとは思えないし、ましてやその「落とし穴」を明解にしているとも言い切れない。むしろ表層的な体験と感想が連ねられているというのが率直なところである。しかし、それは裏を返せば、「異文化理解」ということに到達するには誰もがこの段階をくぐらなければならないということを示す一つの基準点になり得ている、ということであり、また、日本に限らず「文化」というもの... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
日本語教育と国語教育をめぐる日中の結びつきを知る
現代中国の日本語教育史-大学専攻教育と教科書をめぐって- / 田中祐輔. - 国書刊行会, 2015
 北大ではどこにある?
僕が30年以上前、初めて日本語教育に関わったときに学校から与えられた教科書は東京外国語大学附属日本語学校編『日本語Ⅱ』だった。内容を一目見て驚いたのは、僕自身が小学校の国語教科書で勉強した文章が幾つか教材として課を為していることだった。当時、日本語教育についての知識も技術もろくになかった僕でも「日本人小学生向けの教科書と外国人留学生向けの教科書が同じでいいものか」と疑問に思ったのを覚えている。しかし、実態としては、日本の国語科教科書の文章は、様々な形で外国人向け日本語教科書に取り入れられていたのである。そして、それは日本国内で出版... [続きを読む]
北大ではどこにある?
僕が30年以上前、初めて日本語教育に関わったときに学校から与えられた教科書は東京外国語大学附属日本語学校編『日本語Ⅱ』だった。内容を一目見て驚いたのは、僕自身が小学校の国語教科書で勉強した文章が幾つか教材として課を為していることだった。当時、日本語教育についての知識も技術もろくになかった僕でも「日本人小学生向けの教科書と外国人留学生向けの教科書が同じでいいものか」と疑問に思ったのを覚えている。しかし、実態としては、日本の国語科教科書の文章は、様々な形で外国人向け日本語教科書に取り入れられていたのである。そして、それは日本国内で出版... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
文学という営みを通してみた日本人像とは
近代日本人の発想の諸形式 / 伊藤整. - 1981, 岩波書店
 北大ではどこにある?
標題となっている論文で、著者は、日本人の手によって行われた文学(創作と作品)を「逃避型と破滅型」、「上昇型と下降型」等いくつかの切り口から鋭く考察し、日本に於いてその文学的な風土がどのように形成されたかという問題に取り組んでいる。その過程で一つの鍵となるのは、創作の専門性とそれを体現する”文士”という存在である。そうした観点から見たとき、多くの人が常識的に(?)受け止めている「文豪」漱石と鴎外への批判は苛烈を極める。
北大ではどこにある?
標題となっている論文で、著者は、日本人の手によって行われた文学(創作と作品)を「逃避型と破滅型」、「上昇型と下降型」等いくつかの切り口から鋭く考察し、日本に於いてその文学的な風土がどのように形成されたかという問題に取り組んでいる。その過程で一つの鍵となるのは、創作の専門性とそれを体現する”文士”という存在である。そうした観点から見たとき、多くの人が常識的に(?)受け止めている「文豪」漱石と鴎外への批判は苛烈を極める。
20世紀末から日本哲学(史)の研究が徐々に隆盛の兆しを見せてきたが、哲学研究者とは別の(「異質」と言っても良い... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
何もそこまで言わなくても…
日本の大学に入ると、なぜ人生を間違うのか / 吉田良治. - PHP研究所, 2015
 北大ではどこにある?
日本の大学で教職に就いている人間から見ると神経を逆なでされるような表題であるが、それなりの面白さと説得力はある本である。著者は、アメリカの大学の「ライフスキル・プログラム」に足場を置いて、国際通用性に乏しいに日本の大学教育を容赦なく批判していく。この著者の議論は、見方によってはアメリカの大学に留学してアメリカかぶれになった人間の一面的な判断ということもできるが、とりあえず日本の大学教育が抱える問題を概観するには便利な書物であるのは間違いない。あとは読んだ人がそれなりにどう考え、実行するかである。
北大ではどこにある?
日本の大学で教職に就いている人間から見ると神経を逆なでされるような表題であるが、それなりの面白さと説得力はある本である。著者は、アメリカの大学の「ライフスキル・プログラム」に足場を置いて、国際通用性に乏しいに日本の大学教育を容赦なく批判していく。この著者の議論は、見方によってはアメリカの大学に留学してアメリカかぶれになった人間の一面的な判断ということもできるが、とりあえず日本の大学教育が抱える問題を概観するには便利な書物であるのは間違いない。あとは読んだ人がそれなりにどう考え、実行するかである。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
異文化は実は…
異文化はおもしろい / 選書メチエ編集部. - 講談社, 2001
 北大ではどこにある?
この本は21人の著者たちによるエッセイの集成である。
北大ではどこにある?
この本は21人の著者たちによるエッセイの集成である。
『異文化はおもしろい』という表題通り、はじめのうちは確かに「おもしろい」のだが、徐々に「そうなのだろうか?」と考えさせる内容になっていき、最後の「V 異文化が照らす自文化」になると実は異文化と関わるということはそれほどおもしろいばかりでもなくむしろややこしいものであるのだということを痛感させられる。しかし、この本に書いてあることぐらいの基礎的な見識を持たないと異文化と関わっていく(はやりことばで言えば「グローバルに活躍する」)ことなどできないのではないかと考える。この本を足がかり... [続きを読む] -
推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)
偽装・捏造・うそ・いつわりの歴史はすぐそこに
偽りの外交使節――室町時代の日朝関係(歴史文化ライブラリー) / 橋本雄. - 吉川弘文館, 2012
 北大ではどこにある?
世の中、詐欺や捏造が至るところで見られます。ところが、一部の心ない日本の人種主義者によって、それは大半が外国人のしわざだ、などという意見がネット上のあちこちに見られます。本当にそうでしょうか? そうした「悪さ」は今でも昔でも、日本人だろうと無かろうと、あちこちでなされてきたことです。
北大ではどこにある?
世の中、詐欺や捏造が至るところで見られます。ところが、一部の心ない日本の人種主義者によって、それは大半が外国人のしわざだ、などという意見がネット上のあちこちに見られます。本当にそうでしょうか? そうした「悪さ」は今でも昔でも、日本人だろうと無かろうと、あちこちでなされてきたことです。
本書では、対馬や博多あたりの人間が「偽使(偽造/偽装された使節)」を頻繁に渡し、朝鮮王朝に無心を繰り返していたことを、その状況や理由、背景等の諸問題に分け入りながら解明しています。通信機器手段のない前近代の外交がどんなものだったのか、皆さん、想像が... [続きを読む] -
推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)
中世前期の日本対外関係史を俯瞰
中世日本の内と外(増補版) / 村井章介. - 筑摩書房, 2013
 北大ではどこにある?
大学初年次向けの授業をそのまま採録。基本的な論点を押さえつつ、平安期から南北朝期頃までの様子がよく分かるように仕立てられています。すなわち、「自尊と憧憬」「人の境、国の境」「鎌倉幕府と武人政権――日本と高麗」といった視角から中世日本の国家像・対外観に肉薄し、「アジアの元寇」「中世の倭人たち」などを論ずることで、国家のもつ虚妄性を見事にあぶりだしてみせた名著です。
北大ではどこにある?
大学初年次向けの授業をそのまま採録。基本的な論点を押さえつつ、平安期から南北朝期頃までの様子がよく分かるように仕立てられています。すなわち、「自尊と憧憬」「人の境、国の境」「鎌倉幕府と武人政権――日本と高麗」といった視角から中世日本の国家像・対外観に肉薄し、「アジアの元寇」「中世の倭人たち」などを論ずることで、国家のもつ虚妄性を見事にあぶりだしてみせた名著です。 -
推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)
中世後期の日本対外関係史を俯瞰
世界史のなかの戦国日本 / 村井章介. - 筑摩書房, 2012
 北大ではどこにある?
中世後期(近世初頭までを含む)の対外関係史の要点を押さえた名著です。ヨーロッパ勢力(「近代世界システム」)の東漸により世界史の舞台に本格的に躍り出た中世日本社会を、南北の境界領域(蝦夷地・琉球王国)も含めて広やかに照射する目配りの広さ! 世界史と日本史とをつなぐことが喫緊の課題である現在、まず参照されるべき書物でしょう。なお、文庫版解説は推薦子が書かせていただいています。
北大ではどこにある?
中世後期(近世初頭までを含む)の対外関係史の要点を押さえた名著です。ヨーロッパ勢力(「近代世界システム」)の東漸により世界史の舞台に本格的に躍り出た中世日本社会を、南北の境界領域(蝦夷地・琉球王国)も含めて広やかに照射する目配りの広さ! 世界史と日本史とをつなぐことが喫緊の課題である現在、まず参照されるべき書物でしょう。なお、文庫版解説は推薦子が書かせていただいています。
※図書館注:ちくま新書『海から見た戦国日本 : 列島史から世界史へ』(1997年刊)の改題増補版です。 -
推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)
室町時代史と対外関係史とを接合する
中華幻想――唐物と外交の室町時代史 / 橋本雄. - 勉誠出版, 2011
 北大ではどこにある?
1990年代以降、日本中世史のなかで急速に研究が進んでいる分野に、室町時代史と対外関係史とがあります。ところが2000年代まで、それらはほとんど没交渉のまま存在してきたと言ってもいいでしょう。しかしながら、それぞれの分野が孤立したままの状態では、いずれ学問全体のバランスを失いかねません。何より、隣の果実と掛け合わせることでさらに豊かな成果を得られます。そこで、唐物(舶来品)文化や外交儀礼などの諸側面を通じて両者の接続を図ったのが本書です。扱う史資料は問題の性質上、文献(文字資料)だけとは限りません。絵画、書跡、染織、五山文学……。どんな「... [続きを読む]
北大ではどこにある?
1990年代以降、日本中世史のなかで急速に研究が進んでいる分野に、室町時代史と対外関係史とがあります。ところが2000年代まで、それらはほとんど没交渉のまま存在してきたと言ってもいいでしょう。しかしながら、それぞれの分野が孤立したままの状態では、いずれ学問全体のバランスを失いかねません。何より、隣の果実と掛け合わせることでさらに豊かな成果を得られます。そこで、唐物(舶来品)文化や外交儀礼などの諸側面を通じて両者の接続を図ったのが本書です。扱う史資料は問題の性質上、文献(文字資料)だけとは限りません。絵画、書跡、染織、五山文学……。どんな「... [続きを読む] -
推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)
室町幕府の対中国外交史を4本立てのドラマで!
”日本国王”と勘合貿易(NHKさかのぼり日本史・外交篇7・室町) / 橋本雄. - NHK出版, 2013
 北大ではどこにある?
歴史をさかのぼって考える(倒叙法)という、2012年11月放映のEテレ(NHK教育)歴史番組を書籍化したものです。「義政、勘合貿易の再開(1451年)」>「義満、明使との接見(1402年)」>「懐良親王への明使の捕縛(1372年)」>「天龍寺船の派遣決定(1341年)」という4本柱を立てました。自説のみならず、最新の諸研究を参考にしながら、室町期日明関係史の刷新を図っています。勘合ってどんなかたちのものだったのか? なぜ足利将軍家は中華皇帝に「朝貢」したのか? 義満ら足利将軍は心から中国に臣従したのか?――などなど、さまざまな謎解きも楽しんでもらえるはずです。
北大ではどこにある?
歴史をさかのぼって考える(倒叙法)という、2012年11月放映のEテレ(NHK教育)歴史番組を書籍化したものです。「義政、勘合貿易の再開(1451年)」>「義満、明使との接見(1402年)」>「懐良親王への明使の捕縛(1372年)」>「天龍寺船の派遣決定(1341年)」という4本柱を立てました。自説のみならず、最新の諸研究を参考にしながら、室町期日明関係史の刷新を図っています。勘合ってどんなかたちのものだったのか? なぜ足利将軍家は中華皇帝に「朝貢」したのか? 義満ら足利将軍は心から中国に臣従したのか?――などなど、さまざまな謎解きも楽しんでもらえるはずです。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
東ユーラシア世界に目を開く
「シベリアに独立を!」-諸民族の祖国(パトリ)をとりもどす- / 田中 克彦. - 岩波書店, 2013
 北大ではどこにある?
推薦者の義父は戦後シベリアで抑留生活を送った。そのことについて推薦者には何も語らずに亡くなったが、そこでの苦労は並大抵のことばで語れるものではなかったようである。シベリア、と聞けば推薦者も含めてかなりの日本人は戦後のシベリア抑留のことを、あるいはまた天然ガスパイプラインを、さらには水野晴郎の映画『シベリア超特急』を思い浮かべるかと思うが、この本で描かれるのは、そうしたイメージとは異なる自然豊かなシベリアで独立運動を戦い抜いたポターニンという人物の生涯である。そのまわりには、ドストエフスキーやバクーニンをはじめ、アイヌ語研究で有... [続きを読む]
北大ではどこにある?
推薦者の義父は戦後シベリアで抑留生活を送った。そのことについて推薦者には何も語らずに亡くなったが、そこでの苦労は並大抵のことばで語れるものではなかったようである。シベリア、と聞けば推薦者も含めてかなりの日本人は戦後のシベリア抑留のことを、あるいはまた天然ガスパイプラインを、さらには水野晴郎の映画『シベリア超特急』を思い浮かべるかと思うが、この本で描かれるのは、そうしたイメージとは異なる自然豊かなシベリアで独立運動を戦い抜いたポターニンという人物の生涯である。そのまわりには、ドストエフスキーやバクーニンをはじめ、アイヌ語研究で有... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
アメリカの覇権と現状
日本人だけが知らないアメリカ「世界支配」の終わり / カレル・ヴァン・ウォルフレン. - 徳間書店, 2007
 北大ではどこにある?
見事な風景に接して、それを描こうとしても、きっとどこかで見た絵画のものまねになるように、この世界の現実を突きつけられても、それよりひとつの物語を紡ごうとすれば、きっとどこかで刷り込まれた解釈の焼き直しになるようです。著者によると(あるいは常識というべきでしょうか)、この世界の解釈は長いあいだアメリカより発信されてきました。たとえば、自由信仰にもとづく経済が世界に繁栄と安定をもたらすという託宣です。しかし(日本を除く)世界の国々はこの米国主導の解釈に対して疑念を抱き始めたようです。(例えば、昔からアメリカの支配下にあった中南米の国々... [続きを読む]
北大ではどこにある?
見事な風景に接して、それを描こうとしても、きっとどこかで見た絵画のものまねになるように、この世界の現実を突きつけられても、それよりひとつの物語を紡ごうとすれば、きっとどこかで刷り込まれた解釈の焼き直しになるようです。著者によると(あるいは常識というべきでしょうか)、この世界の解釈は長いあいだアメリカより発信されてきました。たとえば、自由信仰にもとづく経済が世界に繁栄と安定をもたらすという託宣です。しかし(日本を除く)世界の国々はこの米国主導の解釈に対して疑念を抱き始めたようです。(例えば、昔からアメリカの支配下にあった中南米の国々... [続きを読む] -
推薦者 : 高井 潔司 (メディア・コミュニケーション研究院)
研究や他者を批判することの厳しさを知る
激辛書評で知る中国の政治・経済の虚実 / 矢吹晋. - 日経BP社, 2007
 北大ではどこにある?
本書は、中国関係図書に対する書評を通して、中国の政治・経済の実相を知るスタイルを取っている。台頭する中国をめぐってはさまざまな著作が出版されているが、ベストセラーとなっている本の中にも、偏見や憎しみに基づいて編集され、事実からかけ離れたものがある。著者は、生半可な書評ではなく、該博な知識と厳密な調査に基づいて、ベストセラーになった中国関係図書を解剖し、辛らつな批判を行っている。中国を理解するだけでなく、研究の厳しさ、他者を批判することの厳しさを教えてくれる。
北大ではどこにある?
本書は、中国関係図書に対する書評を通して、中国の政治・経済の実相を知るスタイルを取っている。台頭する中国をめぐってはさまざまな著作が出版されているが、ベストセラーとなっている本の中にも、偏見や憎しみに基づいて編集され、事実からかけ離れたものがある。著者は、生半可な書評ではなく、該博な知識と厳密な調査に基づいて、ベストセラーになった中国関係図書を解剖し、辛らつな批判を行っている。中国を理解するだけでなく、研究の厳しさ、他者を批判することの厳しさを教えてくれる。 -
推薦者 : 高井 潔司 (メディア・コミュニケーション研究院)
全うな現代中国論
臨界点の中国 / 藤野 彰. - 中国書店, 2007年
 北大ではどこにある?
巷にあふれている現代中国論、現実の中国から出発せず、中国脅威論や崩壊論、あるいはそれらとは対極の中国待望論がほとんどである。著者は、10年を超える中国特派員の経験と知識を活用し、中国全土を歩き回り、様々なレベルの中国人の声を集め、それを基礎に穏当な中国論を展開してている。地に足の着いた中国論である。好きであれ、嫌いであれ、日本の将来にとって、対中関係のあり方はますます重要になっている。そのためには、まず中国の実像をしっかり抑えておく必要がある。本書は極めて有用な視点と知識を提供してくれよう。
北大ではどこにある?
巷にあふれている現代中国論、現実の中国から出発せず、中国脅威論や崩壊論、あるいはそれらとは対極の中国待望論がほとんどである。著者は、10年を超える中国特派員の経験と知識を活用し、中国全土を歩き回り、様々なレベルの中国人の声を集め、それを基礎に穏当な中国論を展開してている。地に足の着いた中国論である。好きであれ、嫌いであれ、日本の将来にとって、対中関係のあり方はますます重要になっている。そのためには、まず中国の実像をしっかり抑えておく必要がある。本書は極めて有用な視点と知識を提供してくれよう。 -
推薦者 : 岡田 敦美 (メディア・コミュニケーション研究院)
グローバリゼーション研究の一人者による入門書
グローバリゼーションとは何か―液状化する世界を読み解く / 伊豫谷登士翁. - 平凡社新書, 2002
 北大ではどこにある?
「グローバリゼーション」というとき、それは「国際化」とどう違うのか、そしてグローバリゼーション研究が、いかなる問題意識に立脚して、どのような現象を分析対象としてきたのかを知るうえで、最良の一冊です。
北大ではどこにある?
「グローバリゼーション」というとき、それは「国際化」とどう違うのか、そしてグローバリゼーション研究が、いかなる問題意識に立脚して、どのような現象を分析対象としてきたのかを知るうえで、最良の一冊です。
キーワードは、たとえば国民国家の相対化、世界秩序、南北問題、多国籍企業、メディア、移民、労働市場・・・。アクチュアルな現象に関心がある人、開発援助に関心がある人は、是非読んでみましょう。
第一章:グローバリゼーションの課題は何か、 第二章:時代としてのグローバリゼーション、 第三章:グローバリゼーションをマッピングする、 第四章... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
人類の岐路
覇権か、生存か : アメリカの世界戦略と人類の未来 / ノーム・チョムスキー. - 集英社, 2004
 北大ではどこにある?
北朝鮮の核実験に触発されて、与党の有力者から、わが国も核を保有するべきだ、というような議論が出ました。政府の見解は、非核三原則を貫く、しかし言論は自由なので、将来のことをあれこれ思い巡らすなかに「核武装」という選択肢も残しておく、ということであったようです。ここで肝心なことからわざと目を背けていることに気づきます。この問題のまえに、当然、アメリカの覇権にどう対処するべきか、という議論を済ませておかなければならないからです。(実際に核武装すれば、イスラエルという例外がありますが、アメリカの逆鱗に触れることは確実です。)
北大ではどこにある?
北朝鮮の核実験に触発されて、与党の有力者から、わが国も核を保有するべきだ、というような議論が出ました。政府の見解は、非核三原則を貫く、しかし言論は自由なので、将来のことをあれこれ思い巡らすなかに「核武装」という選択肢も残しておく、ということであったようです。ここで肝心なことからわざと目を背けていることに気づきます。この問題のまえに、当然、アメリカの覇権にどう対処するべきか、という議論を済ませておかなければならないからです。(実際に核武装すれば、イスラエルという例外がありますが、アメリカの逆鱗に触れることは確実です。)
チョム... [続きを読む] -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
知らないことはいくらでもある
メンデ奴隷にされた少女 / メンデ・ナゼール. - ソニーマガジンズ, 2004
 北大ではどこにある?
今の世界にも奴隷は存在する。しかも政府の黙認において。スーダンで家族から拉致された子供たちは売られている。その地域はまさに伝説のマサイ族の地域だ。私たちは何事も知ったつもりになってはいけない。短いワンフレーズのコメントに棹差せば流される。
北大ではどこにある?
今の世界にも奴隷は存在する。しかも政府の黙認において。スーダンで家族から拉致された子供たちは売られている。その地域はまさに伝説のマサイ族の地域だ。私たちは何事も知ったつもりになってはいけない。短いワンフレーズのコメントに棹差せば流される。 -
推薦者 : 寺田 龍男 (メディア・コミュニケーション研究院)
中国の超一流大学を紹介してくれる本
中国の頭脳・精華大学と北京大学 / 紺野大介. - 朝日新聞社, 2006年
 北大ではどこにある?
この本を読むと、今でははやらなくなった「エリート」という言葉を思い出します。中国の若い秀才たちの学習ぶりはすさまじく、学部生段階でアメリカの大学から「ウチに(留学に)きてほしい」と声がかかるとも。日本の学生たちはこの点でまるで眼中にないとの指摘は正直耳が痛い。「だから北大生もがんばれ」というまえに、自分の研究・教育レベルをどうしたら上げられるかと考えてしまった。
北大ではどこにある?
この本を読むと、今でははやらなくなった「エリート」という言葉を思い出します。中国の若い秀才たちの学習ぶりはすさまじく、学部生段階でアメリカの大学から「ウチに(留学に)きてほしい」と声がかかるとも。日本の学生たちはこの点でまるで眼中にないとの指摘は正直耳が痛い。「だから北大生もがんばれ」というまえに、自分の研究・教育レベルをどうしたら上げられるかと考えてしまった。
ただし、この本に書かれているのは巨大な中国社会の一面に過ぎません。中国の大学(すべて国立、約1000校)にも(著者によると)「ピンからキリ」まであり、中には大学とは呼べ... [続きを読む] -
推薦者 : 下澤 楯夫 (電子科学研究所)
特命全権大使米欧回覧実記 / 久米邦武編著 ; 水澤周訳注. - 岩波書店, 1997.9
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 樽本 英樹 (文学研究科)
国際社会学 : 国家を超える現象をどうとらえるか / 梶田孝道編. - 名古屋大学出版会, 1996.4
 北大ではどこにある?
国民国家システムというグローバルな構造が変動し、様々な側面から「国際化」が生じている。それに伴い、「社会」を社会現象の分析 枠組とすることに疑問符がつけられるようになった。ではどのような問題にどのようなアプローチを行えばよいのか。
北大ではどこにある?
国民国家システムというグローバルな構造が変動し、様々な側面から「国際化」が生じている。それに伴い、「社会」を社会現象の分析 枠組とすることに疑問符がつけられるようになった。ではどのような問題にどのようなアプローチを行えばよいのか。
この疑問に「国際社会学」という立場で答えようとしているのが本書である。トランスナショナルな主体、グローバライゼイション、エスニシティ、ナショナリズム、人の国際移動等のテーマを掲げながら、「国際社会学」という新たな分野を開拓しようとしている意欲作である。登録日 : 2005-08-02