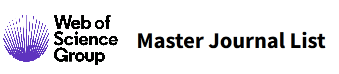注意が必要な「怪しいジャーナル」
注意が必要な「怪しいジャーナル」
近年オープンアクセス化への取組みが進められていくなかで、著者が投稿料を支払うことで読者が無料で論文を読むことができるオープンアクセス誌(OA誌)が増えています。それに伴い、この投稿料による収益を狙った悪質な「predatory journal」の増加が問題となっています。また、既存のジャーナルの名を騙った”偽”のジャーナルサイトの存在にも注意が必要です。
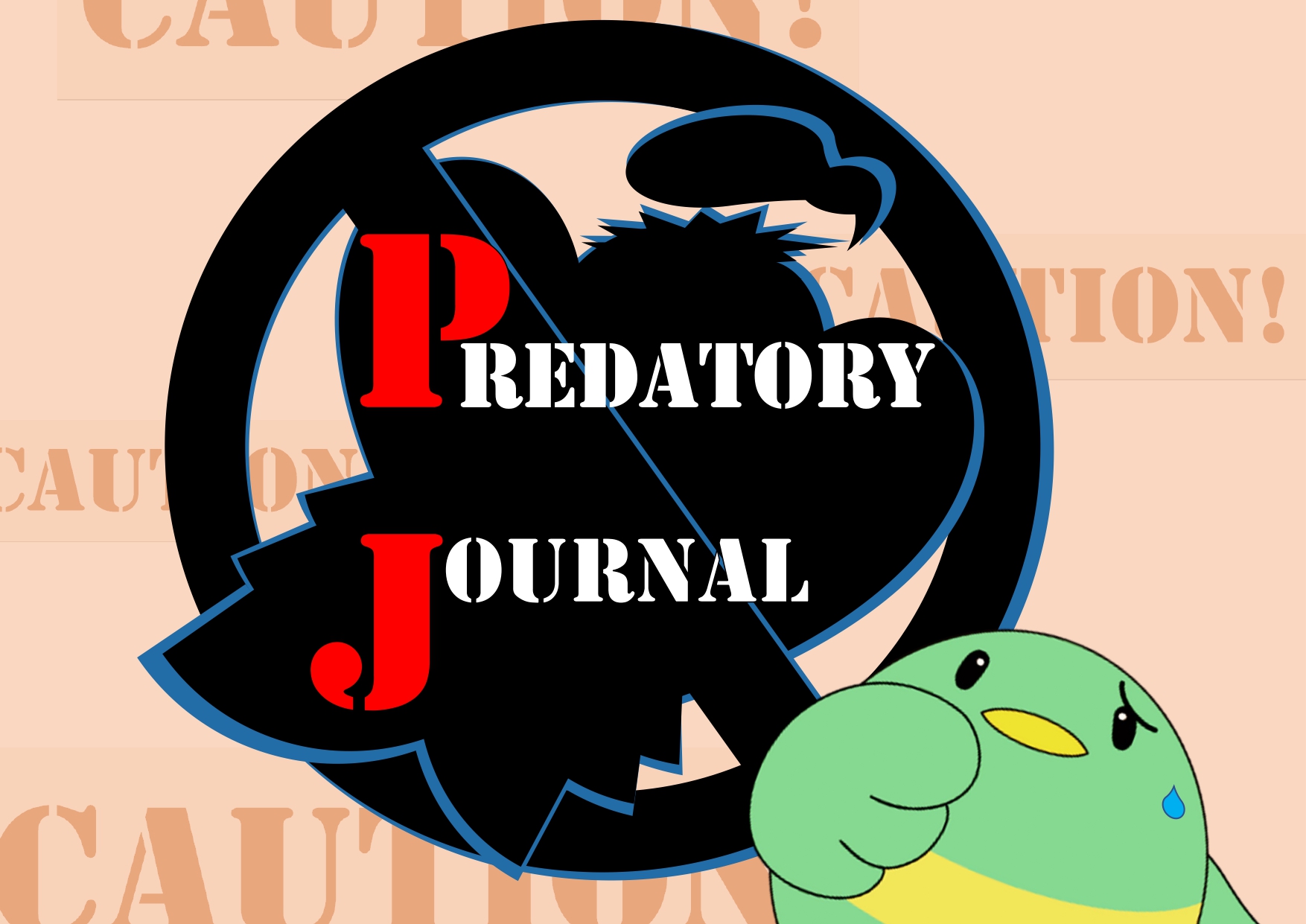
predatory journalとは?
オープンアクセスのビジネスモデルを悪用し、著者が支払う論文投稿料(APC=Article Processing Charge)の詐取を狙った悪質な学術誌です。
日本語では「粗悪学術誌」「ハゲタカジャーナル」「捕食ジャーナル」などと訳されます。
言葉として有名になったのはpredatory journal ( 「ハゲタカジャーナル」 )ですが、ジャーナルの他にpredatory conferenceなどもあります。
predatory journalの問題点としては、以下があります。
- 適切な査読が行われないため、投稿された論文の質が保証されていない。
- 健全なOA誌を装い※、研究者を騙して論文を投稿させて、論文投稿料を詐取する。
※例:「著名な研究者を無断で編集委員として記載する」「インパクトファクターに類似した評価指標を使用する」「有名な学術誌と酷似したロゴや名称を使用する」
predatory journalを発行する出版社の目的は金銭ですが、研究者や社会が受ける被害は金銭に留まりません。
そのため、研究者が論文を投稿する際は、投稿先の見極めが大切なのはもちろんのこと、論文を引用・参照するなど利用する場合にも注意が必要です。
研究者や社会が受ける被害とは?
- predatory journalに論文が掲載されていることで、著者や著者の所属研究機関の評価・信頼が損なわれる。
- 不当に高額な料金請求など投稿料に関わるトラブルが発生する。
- 投稿後predatory journalであると気づいても、論文の撤回が認められず、他の雑誌へ投稿し直すことができなくなる。
- 論文への安定したアクセスが保証されておらず、突然閲覧できなくなる可能性がある。
- 質の保証されていない論文が出回るようになるため、査読論文や学術誌全体の信頼に悪影響を及ぼす。
- 質の保証されていない論文が参照されることにより、社会に影響が及ぶ可能性がある。
- 会費徴収が目的のpredatory conferenceへの参加を勧誘されることがある。
被害を防ぐには?
観点そのものをチェックする
完全な予防策はありません。
現在はチェックポイントやデータベース等のチェックリストが存在しますが、その結果のみを信じ込むことにはリスクがあります。predatory journalは創廃刊のスピードが速く手口が多様であるため、チェックポイントやチェックリストの更新が追い付かなかったり、審査をすり抜けてしまうことがあります。学術誌の評価が後で変わることもあります。また、実際にはpredatoryと即断できる学術誌ばかりではありません。チェックポイントやチェックリストのみを用いることで、predatoryではない学術誌をpredatory journalと断定してしまう恐れもあります。
以下で紹介しているチェックポイントやチェックリストは、「学術誌のどのような特徴がpredatoryであるか/適正であるか」の観点を示すものとして用いることができます。現時点では、predatoryと判定する観点そのものをチェックし、自身の判断にいかすことが最善の予防策とも云えます。周囲の研究者との情報共有も有効と考えられます。
ひょっとすると predatory journalかもしれない・・・投稿する前の注意ポイント
- Think Check Submit (日本語版はこちら)
学術出版に関わる著名な組織が連携して運営する、信頼できる学術誌への投稿を支援するキャンペーン。リストにしたがって投稿先の雑誌の信頼性をチェックすることができる。

チェック項目例
・投稿料など料金に関わる情報が明示されていない
・連絡方法がない、フリーメールを使用している
・査読から出版までの期間が早すぎる
・取り扱う対象分野が広すぎる
・編集や査読に関する情報が曖昧である
・雑誌の名称や他の情報が別の雑誌と酷似している
・編集者や雑誌が各種データベース(下記参照)などで確認できない
- 井出和希, 中山健夫「その学術誌、大丈夫?」
学術誌に関する「大丈夫?」の注意ポイントがスペクトラム状の表になっています。
投稿予定の雑誌が信頼性の高いデータベースに収録されているか
- DOAJ(Directory of Open Access Journals)
- Web of Science:Master Journal List
オープンアクセス学術誌要覧。OA誌の検索が無料でできるデータベースで、21,000誌以上(2025.2.13時点)のジャーナルが収録されている。採録には厳しい審査基準が設けられている。

投稿予定の雑誌の出版社が以下の団体に登録されているか
- COPE(Committee on Publication Ethics)
- OASPA(Open Access Scholarly Publisher's Association)
出版規範委員会 ⇒メンバー検索ページ

オープンアクセス学術出版社協会 ⇒会員リストページ

”偽”の学術誌サイト

実在する学術誌の名を騙った”偽”の学術誌サイトが確認されています。これらのサイトは、既存の学術誌や大学紀要の名称、ISSNを詐称してその学術誌に成りすまし、論文を投稿させ、その掲載料をだまし取ることを目論んでいます。論文を投稿する際は、正規の学術誌サイトであるか、充分にお気をつけください。
- 札幌医科大学附属総合情報センター:「【注意喚起】札幌医学雑誌を名乗る偽サイトについて」
- 京都大学図書館機構:「【図書館機構】偽ジャーナルにご注意ください」
- 鳥取大学附属図書館:「Yonago Acta Medicaを騙る偽のWebサイトについて」
- 獨協医学会:「〔注意喚起〕Dokkyo Journal of Medical Sciencesを騙る偽Webサイトについて」
札幌医科大学『札幌医学雑誌(The Sapporo Medical Journal)』を詐称したWebサイトについての注意喚起です。(※英語版)
京都大学生存圏研究所『Sustainable Humanosphere』を詐称したWebサイトについての注意喚起です。
鳥取大学『Yonago Acta Medica』を詐称したWebサイトについての注意喚起です。
獨協医学会『Dokkyo Journal of Medical Sciences』を詐称したWebサイトについての注意喚起です。
参考情報
北海道大学、北海道大学附属図書館が公開しているpredatory journalに関連した資料
その他参考情報
- 「<翻訳>粗悪な学術誌・学術集会を拡げないために」
- 「Beall's List of Potential Predatory Journals and Publishers」(ビールのリスト*を匿名の有志が復活させたもの。)
- 「Withdrawal of accepted manuscript from predatory journal」(投稿してしまった場合の対応事例)
世界の研究コミュニティによって組織された InterAcademyPartnership(IAP)によるレポートの翻訳記事です。IAPでは学術誌や学術集会に関する略奪的行為をスペクトラム(グラデーション)で定義しており、predatoryであるかわからないものの判断にも有効と考えられます。
* ビールのリスト(Beall's List)
アメリカ・コロラド大学の大学図書館司書 Jeffrey Beall が作成した、predatory journalの疑いがある学術誌及びその出版社をまとめたリスト。同氏のリストは2017年に閉鎖。
COPEフォーラムに寄せられた事例。Predatory Journalに受理されてしまった論文を取り下げるためにはどうすればよいかという相談への回答が紹介されています。
参考:また、この事例を日本語に訳した記事もあります。
⇒「Predator―Predatory Publishingの1例―」(出典:『日本消化器外科学会雑誌』50(11).2017. p.937-940)
【お問い合わせ先】学術情報部学術情報支援課(jsa [at] lib.hokudai.ac.jp)