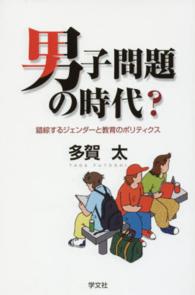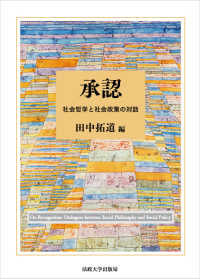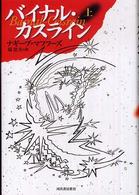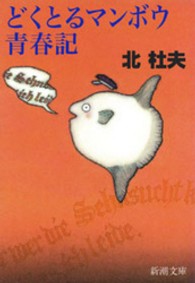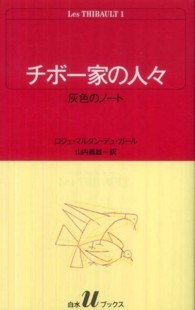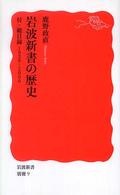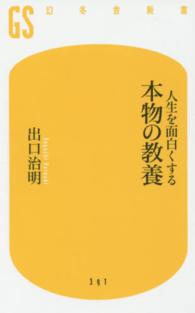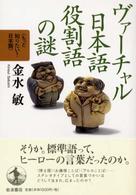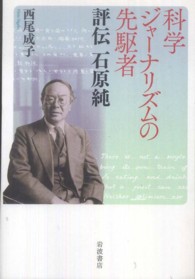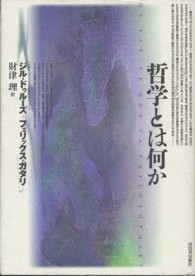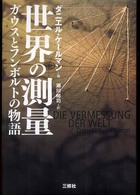-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「男対女」の構図をいかに乗り越えるか
男子問題の時代?-錯綜するジェンダーと教育のポリティクス- / 多賀太. - 学文社, 2016
 北大ではどこにある?
ジェンダー、あるいは男女平等/差別の問題が語られるときにほぼお決まりになっているパターンとして「男は支配する側、女は支配される側」あるいは「男は加害者、女は被害者」という言説がある。日本の社会のかなりの部分でそれは当てはまるのかもしれないが、僕はこの見方には強烈な反発を持っている。それは、“日本語教師”という「女性8割、男性2割」の業界で働いてきた経験から、女性が多数者側になれば「女性は加害者、男性は被害者」という事態も容易に出現することを知っているからである。そのような意味で日本のジェンダー研究はまだ色々なことを考え直さなければ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ジェンダー、あるいは男女平等/差別の問題が語られるときにほぼお決まりになっているパターンとして「男は支配する側、女は支配される側」あるいは「男は加害者、女は被害者」という言説がある。日本の社会のかなりの部分でそれは当てはまるのかもしれないが、僕はこの見方には強烈な反発を持っている。それは、“日本語教師”という「女性8割、男性2割」の業界で働いてきた経験から、女性が多数者側になれば「女性は加害者、男性は被害者」という事態も容易に出現することを知っているからである。そのような意味で日本のジェンダー研究はまだ色々なことを考え直さなければ... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
新たな歴史哲学を考える原点として
歴史における言葉と論理-歴史哲学基礎論- / 神川正彦. - 勁草書房, 1970-1971
 北大ではどこにある?
この本については、少し過激な(?)推薦文を書きたい。
北大ではどこにある?
この本については、少し過激な(?)推薦文を書きたい。
先日、某大学(敢えて名は秘す)の日本現代(1950年代以降)哲学の授業のシラバスを見ていたら、そこで取り上げてられているのが大森莊藏、廣松渉、坂部恵であった。しかしこれでは、結局戦前は「京都学派」で、それが戦後になったら“東大”に変わっただけじゃないか、という印象を拭えない。日本の哲学というのは京大と東大の“官学アカデミズム”の中で選手交代をやっていただけだとしたらあまりにも悲しい。ここに推薦する神川正彦は、今はもう哲学専攻の学生でも名前を知らない人が多いかもしれないが、上記... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「承認」を切り口にして社会を考える
承認-社会哲学と社会政策の対話- / 田中拓道. - 法政大学出版局, 2016
 北大ではどこにある?
「承認」というと堅苦しい響きがあるが、要するに「認めてくれ!」ということである。ではなぜある人びとやある問題が社会の中で認められていないのか、どのようにすればその問題にアプローチできるのか、といったことに気鋭の研究者たちが正面から取り組んだ労作である。その際の基本的視角となっているのは現代ドイツの哲学者アクセル・ホネットの“承認の哲学”と、それに関するナンシー・フレイザーとの論争である。決して易しくはないが、ここからさらに各自の関心に応じて(芋づる式に!)読書の範囲を広げ問題を整理することができるだろう。よく言われる「哲学が何... [続きを読む]
北大ではどこにある?
「承認」というと堅苦しい響きがあるが、要するに「認めてくれ!」ということである。ではなぜある人びとやある問題が社会の中で認められていないのか、どのようにすればその問題にアプローチできるのか、といったことに気鋭の研究者たちが正面から取り組んだ労作である。その際の基本的視角となっているのは現代ドイツの哲学者アクセル・ホネットの“承認の哲学”と、それに関するナンシー・フレイザーとの論争である。決して易しくはないが、ここからさらに各自の関心に応じて(芋づる式に!)読書の範囲を広げ問題を整理することができるだろう。よく言われる「哲学が何... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
古典と現代をつなぐ読み方を知る
社会契約論-ホッブズ、ヒューム、ルソー、ロールズ- / 重田園江. - 筑摩書房, 2013
 北大ではどこにある?
高校の世界史や政治経済の授業で「社会契約論」という考え方を知ったときに感じたのは、ルソーにせよロックにせよなぜあの時代の西ヨーロッパの思想家がそういうことをわざわざ考えなければならなかったのか、という強烈な違和感だった。「社会」というものをみんなで作ろう(?)といった感じで最初に約束事をするという発想自体について行けなかったのである。実は今でもその違和感は抜けきらず、“起源”ということをやたらに理屈を付けて解き明かしたがる(そのくせ割合に最後は「神」が出現して一切が片付く)西欧の思想にとことん付き合いきれない思いがある。
北大ではどこにある?
高校の世界史や政治経済の授業で「社会契約論」という考え方を知ったときに感じたのは、ルソーにせよロックにせよなぜあの時代の西ヨーロッパの思想家がそういうことをわざわざ考えなければならなかったのか、という強烈な違和感だった。「社会」というものをみんなで作ろう(?)といった感じで最初に約束事をするという発想自体について行けなかったのである。実は今でもその違和感は抜けきらず、“起源”ということをやたらに理屈を付けて解き明かしたがる(そのくせ割合に最後は「神」が出現して一切が片付く)西欧の思想にとことん付き合いきれない思いがある。
この本... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
さらに一段上の文章表現力のために
論理が伝わる世界標準の「書く技術」-「パラグラフ・ライティング」入門- / 倉島保美. - 講談社, 2012
 北大ではどこにある?
ここに何度か書いたことだが数年前から「一般教育演習(フレッシュマンセミナー)」で文章表現が苦手な学生のための日本語文章表現法の授業を展開してきた。ただ、色々と訳あってこの授業は今年度で終わりにすることにした。そこで、これに替わるものとして、また、“苦手”のレベルを脱した学生がさらに上のレベルの文章表現力を身につけてもらう上で参考にすることができるようにこの本を推薦しておく。この本は、それ自体が主題としている「パラグラフ・ライティング」によって書かれているので、技法と実例を同時に身につけることができる点で優れている。あとは練習あるの... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ここに何度か書いたことだが数年前から「一般教育演習(フレッシュマンセミナー)」で文章表現が苦手な学生のための日本語文章表現法の授業を展開してきた。ただ、色々と訳あってこの授業は今年度で終わりにすることにした。そこで、これに替わるものとして、また、“苦手”のレベルを脱した学生がさらに上のレベルの文章表現力を身につけてもらう上で参考にすることができるようにこの本を推薦しておく。この本は、それ自体が主題としている「パラグラフ・ライティング」によって書かれているので、技法と実例を同時に身につけることができる点で優れている。あとは練習あるの... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
歴史学者とはどのような人々か
昭和史学史ノート-歴史学の発想- / 斉藤孝. - 小学館, 1984
 北大ではどこにある?
歴史学者が歴史研究を行ったり歴史書を書いたりするときには当然その歴史観が反映される。史学史とはそうした歴史観や歴史記述の態度・意識の歴史である。この本では、具体的な個々の(主に昭和戦前・戦中期の)歴史学者を取り上げて通観することによって昭和の歴史研究がどのようなものであったかを示そうとするものである。歴史に興味のある学生、歴史学者の仕事を覗いてみたい学生、昭和時代を何らかの学問の研究対象としたい学生にお勧めする。
北大ではどこにある?
歴史学者が歴史研究を行ったり歴史書を書いたりするときには当然その歴史観が反映される。史学史とはそうした歴史観や歴史記述の態度・意識の歴史である。この本では、具体的な個々の(主に昭和戦前・戦中期の)歴史学者を取り上げて通観することによって昭和の歴史研究がどのようなものであったかを示そうとするものである。歴史に興味のある学生、歴史学者の仕事を覗いてみたい学生、昭和時代を何らかの学問の研究対象としたい学生にお勧めする。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
戦後日本の思想の絡まりを解きほぐす
現代日本思想論-歴史意識とイデオロギー- / 安丸良夫. - 岩波書店, 2004
 北大ではどこにある?
この本は、戦後日本の社会科学(主として政治学と歴史学)の中で誰がどのような議論を展開しそれが誰に受け継がれ誰に批判されその中からどのような議論が新たに形成されてきたかを論じる第一部と、戦後の主に海外の歴史学研究方法論、丸山眞男の思想史研究、そして著者自身の現代社会状況分析からなる第二部とに分かれている。読者の関心に応じて興味を引かれる部分は異なると思うが、特に第一部は戦後の社会科学研究の“思想地図”といった内容になっており、広く日本の戦後政治や思想を学ぶ上での基本的な知識を提供してくれている。これらの方面に関心のある学生に一読... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、戦後日本の社会科学(主として政治学と歴史学)の中で誰がどのような議論を展開しそれが誰に受け継がれ誰に批判されその中からどのような議論が新たに形成されてきたかを論じる第一部と、戦後の主に海外の歴史学研究方法論、丸山眞男の思想史研究、そして著者自身の現代社会状況分析からなる第二部とに分かれている。読者の関心に応じて興味を引かれる部分は異なると思うが、特に第一部は戦後の社会科学研究の“思想地図”といった内容になっており、広く日本の戦後政治や思想を学ぶ上での基本的な知識を提供してくれている。これらの方面に関心のある学生に一読... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
数学界に革命をもたらした「不完全性定理」とは何か
ゲーデルは何を証明したか-数学から超数学へ- / E.ナーゲル&J.R.ニューマン. - 白揚社, 1999
 北大ではどこにある?
この本は、1968年に『数学から超数学へ : ゲーデルの証明』というタイトルで出された本の新装版である(原著は1958年!)。「ゲーデルの不完全性定理」というのを聞いたことがある人は、理数系でなければ必ずしも多くはないかもしれないが、「アインシュタインの相対性理論」や「ハイゼンベルクの不確定性原理」にも比するべき、数学に大転換を迫った原理である。この本は、その決して易しくはない「不完全性定理」をできる限りわかりやすく解きほぐして説明しようとするものであり、理数系の学生のみ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、1968年に『数学から超数学へ : ゲーデルの証明』というタイトルで出された本の新装版である(原著は1958年!)。「ゲーデルの不完全性定理」というのを聞いたことがある人は、理数系でなければ必ずしも多くはないかもしれないが、「アインシュタインの相対性理論」や「ハイゼンベルクの不確定性原理」にも比するべき、数学に大転換を迫った原理である。この本は、その決して易しくはない「不完全性定理」をできる限りわかりやすく解きほぐして説明しようとするものであり、理数系の学生のみ... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「辞書にはドラマがある」
<辞書屋>列伝-言葉に憑かれた人びと- / 田澤耕. - 中央公論新社, 2014
 北大ではどこにある?
以前の推薦文に、最近岩波新書(新赤版)がつまらなくなってきた、と書いたが、最近の新書(岩波に限らない)ときたら、もう池上彰、佐藤優、島田裕巳、内田樹ばかり目立つ(少し前ならこれに香山リカも入っていた)。商業的に売れる本を書きたいというのは出版社の本音だろうし、若者の読書離れなどということも言われる中で出版社の新書編集部も大変だろうなぁとは思うが、こうも顔ぶれが変わらないと彼らの熱烈なファンでない限り購買意欲が逆にそがれてしまう。それにしても、この四人はよくも新書の大量執筆ができるもので、その点はうらやましい限りである。
北大ではどこにある?
以前の推薦文に、最近岩波新書(新赤版)がつまらなくなってきた、と書いたが、最近の新書(岩波に限らない)ときたら、もう池上彰、佐藤優、島田裕巳、内田樹ばかり目立つ(少し前ならこれに香山リカも入っていた)。商業的に売れる本を書きたいというのは出版社の本音だろうし、若者の読書離れなどということも言われる中で出版社の新書編集部も大変だろうなぁとは思うが、こうも顔ぶれが変わらないと彼らの熱烈なファンでない限り購買意欲が逆にそがれてしまう。それにしても、この四人はよくも新書の大量執筆ができるもので、その点はうらやましい限りである。
閑話... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
私もプロレスの味方です。
新日本プロレス12人の怪人 / 門馬忠雄. - 文藝春秋社, 2012
 北大ではどこにある?
この推薦図書の表題を見て目をむいたそこのあなた、附属図書館の蔵書検索欄に「プロレス」と入力してみるとよい。北大附属図書館には、プロレス関連図書が結構色々あるのだ。つい先日出たばかりの三田佐代子『プロレスという生き方』(中公新書ラクレ)も図書館は入れてくれた。ずっとお堅い本ばかり推薦してきていい加減疲れたというのもあるのだが、プロレスというのは最高のエンターテインメント(の一つ)であって、それについて知ることは自分の世界を広げることになると思い推薦することにした... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この推薦図書の表題を見て目をむいたそこのあなた、附属図書館の蔵書検索欄に「プロレス」と入力してみるとよい。北大附属図書館には、プロレス関連図書が結構色々あるのだ。つい先日出たばかりの三田佐代子『プロレスという生き方』(中公新書ラクレ)も図書館は入れてくれた。ずっとお堅い本ばかり推薦してきていい加減疲れたというのもあるのだが、プロレスというのは最高のエンターテインメント(の一つ)であって、それについて知ることは自分の世界を広げることになると思い推薦することにした... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
あなたの知らないディープな大学図書館
変わりゆく大学図書館 / 逸村裕・竹内比呂也. - 勁草書房, 2005
 北大ではどこにある?
北大図書館を頻繁に利用する人や図書館ウェブサイトをよく見る人の中でどのくらいの人が図書館トップページの一番右にある「附属図書館について」を見ているだろうか。図書館ホームページの中で蔵書検索やお知らせと同じくらい閲覧されていいページはこの「附属図書館について」の中にある様々な情報だと思う。それほど更新頻度が高いわけではないが、図書館がどのように北大の研究・教育活動に貢献しているか、そのために職員の方々がどのような仕事をしていらっしゃるかがよく分かる。時間があるときには是非見てほしい。それと関連して... [続きを読む]
北大ではどこにある?
北大図書館を頻繁に利用する人や図書館ウェブサイトをよく見る人の中でどのくらいの人が図書館トップページの一番右にある「附属図書館について」を見ているだろうか。図書館ホームページの中で蔵書検索やお知らせと同じくらい閲覧されていいページはこの「附属図書館について」の中にある様々な情報だと思う。それほど更新頻度が高いわけではないが、図書館がどのように北大の研究・教育活動に貢献しているか、そのために職員の方々がどのような仕事をしていらっしゃるかがよく分かる。時間があるときには是非見てほしい。それと関連して... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
現代アラブ文学への扉
バイナル・カスライン / ナギーブ・マフフーズ. - 河出書房新社, 1988
 北大ではどこにある?
『千夜一夜物語』以外でアラブ文学を読んだという人は、おそらくごく少数だろう。現代アラブ文学と聞いてもおそらく作家名もイメージも思い浮かばないと思う。かく述べる僕自身も、自分がエジプトに赴任するまでそれらについては全く知らなかった。ここに挙げる『バイナル・カスライン』とその著者ナギーブ・マフフーズについてもエジプトに行ってから周囲の同僚や学生たちに教えられて知ったのだが、その当時既にこの本を含む「現代アラブ小説全集」は刊行されていた。マフフーズは、アラブ世界初のノーベル文学賞受賞者(1988年)であり、僕がカイロにいたときにはまだ存命し... [続きを読む]
北大ではどこにある?
『千夜一夜物語』以外でアラブ文学を読んだという人は、おそらくごく少数だろう。現代アラブ文学と聞いてもおそらく作家名もイメージも思い浮かばないと思う。かく述べる僕自身も、自分がエジプトに赴任するまでそれらについては全く知らなかった。ここに挙げる『バイナル・カスライン』とその著者ナギーブ・マフフーズについてもエジプトに行ってから周囲の同僚や学生たちに教えられて知ったのだが、その当時既にこの本を含む「現代アラブ小説全集」は刊行されていた。マフフーズは、アラブ世界初のノーベル文学賞受賞者(1988年)であり、僕がカイロにいたときにはまだ存命し... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
現代哲学の源流をたどる
人間知性の探究・情念論 / デイヴィッド・ヒューム. - 晢書房, 1990
 北大ではどこにある?
現代哲学、あるいは哲学史に於ける「現代」というのがなに/いつを指すのかは色々議論があるであろうけれども、(ニーチェを別にすれば)20世紀以降の西洋哲学のかなりの部分が目指そうとしたことは、ヒュームの哲学を練り直し、彼が問題としてことを問い直して現代に甦らせようとすることだったと言って良い。(例えば、ジョン・デューイはそのことをはっきりと述べている。) ヒュームは、哲学史の教科書的に言えば、懐疑論者でありイギリス経験論の完成者であるなどと言われるが、-そう見ることも可能であるとしても-彼が目指したのは日常的な経験をいかに概念化して人間の... [続きを読む]
北大ではどこにある?
現代哲学、あるいは哲学史に於ける「現代」というのがなに/いつを指すのかは色々議論があるであろうけれども、(ニーチェを別にすれば)20世紀以降の西洋哲学のかなりの部分が目指そうとしたことは、ヒュームの哲学を練り直し、彼が問題としてことを問い直して現代に甦らせようとすることだったと言って良い。(例えば、ジョン・デューイはそのことをはっきりと述べている。) ヒュームは、哲学史の教科書的に言えば、懐疑論者でありイギリス経験論の完成者であるなどと言われるが、-そう見ることも可能であるとしても-彼が目指したのは日常的な経験をいかに概念化して人間の... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「馬鹿ばかしさのまっただ中で犬死しないための方法」とは何か?
赤頭巾ちゃん気をつけて / 庄司薫. - 新潮社, 2012
 北大ではどこにある?
この小説は、一時期多くの読者の心を捉え、近年また出版社を替えて文庫化されるほどに読み継がれてきた名作である。大学紛争(と言ってももう知識としてしか知らない学生ばかりだろうが)で1969年度の東大入試が中止になるという時代背景の中、東京都立日比谷高校3年生の「庄司薫」君の饒舌的で独白的な文体を軸に綴られたこの作品を高校時代に最初に読んだとき、僕は作者が本当に日比谷高校3年生ではないかと思ったほどである。著者の庄司氏と僕はちょうど20歳の年齢差があるが、僕自身―全盛期末期か凋落期かの違いはあれど―都立高校に在籍し卒業した者として主人公の「薫」君... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この小説は、一時期多くの読者の心を捉え、近年また出版社を替えて文庫化されるほどに読み継がれてきた名作である。大学紛争(と言ってももう知識としてしか知らない学生ばかりだろうが)で1969年度の東大入試が中止になるという時代背景の中、東京都立日比谷高校3年生の「庄司薫」君の饒舌的で独白的な文体を軸に綴られたこの作品を高校時代に最初に読んだとき、僕は作者が本当に日比谷高校3年生ではないかと思ったほどである。著者の庄司氏と僕はちょうど20歳の年齢差があるが、僕自身―全盛期末期か凋落期かの違いはあれど―都立高校に在籍し卒業した者として主人公の「薫」君... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
大学の「勉強」は大変なのである!
「知」の方法論-論文トレーニング- / 岩崎美紀子. - 岩波書店, 2008
 北大ではどこにある?
この本を推薦するに当たっては苦い思い出から始めたい。高校時代の「倫理・社会」の授業で、「大学に行く目的は何か?」というテーマでグループ・ディスカッションをしたことがあった。僕のグループ5人の中で、「大学へは勉強しに行く」という意見を出したのは僕だけで、他の同級生は全員「大学へは遊びに行く」と答えたのである。グループ代表として結論を報告した同級生の、僕を小馬鹿にしたような目つきはいまだに目に浮かぶ。そんな高校だったから、卒業時、男子生徒20名中現役で大学に進学したのは2名だけだった(僕も浪人組)。
北大ではどこにある?
この本を推薦するに当たっては苦い思い出から始めたい。高校時代の「倫理・社会」の授業で、「大学に行く目的は何か?」というテーマでグループ・ディスカッションをしたことがあった。僕のグループ5人の中で、「大学へは勉強しに行く」という意見を出したのは僕だけで、他の同級生は全員「大学へは遊びに行く」と答えたのである。グループ代表として結論を報告した同級生の、僕を小馬鹿にしたような目つきはいまだに目に浮かぶ。そんな高校だったから、卒業時、男子生徒20名中現役で大学に進学したのは2名だけだった(僕も浪人組)。
北大に進学してきた学生諸君の高校... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
もう今はない旧制高校の青春とは
どくとるマンボウ青春記 / 北杜夫. - 新潮社, 2000
 北大ではどこにある?
僕が大学時代に教えを受けた先生方の半数以上は、旧制高等学校の卒業生だった。旧制高校は、戦後は新制大学(の一部)になり、僕ら新制高校卒業世代は知識としてそういうものがあったという形でしか認識していないのだが、実際に旧制高校生活を送った先生方にはその後の人生のスタイル(というと安っぽく聞こえてしまうが)を決定するような大きな影響力のある教育機関だったらしい。最早体験的に知ることのできない、そうした旧制高校の魅力とそこで学生生活を送った著者自身の内面的な成長過程、そして、思わず笑いを誘う、あるいは人生の意味を真剣に考えさせるエピソードの数... [続きを読む]
北大ではどこにある?
僕が大学時代に教えを受けた先生方の半数以上は、旧制高等学校の卒業生だった。旧制高校は、戦後は新制大学(の一部)になり、僕ら新制高校卒業世代は知識としてそういうものがあったという形でしか認識していないのだが、実際に旧制高校生活を送った先生方にはその後の人生のスタイル(というと安っぽく聞こえてしまうが)を決定するような大きな影響力のある教育機関だったらしい。最早体験的に知ることのできない、そうした旧制高校の魅力とそこで学生生活を送った著者自身の内面的な成長過程、そして、思わず笑いを誘う、あるいは人生の意味を真剣に考えさせるエピソードの数... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「研究」ということの神髄に触れる
師範学校制度史研究-15年戦争下の教師教育- / 逸見勝亮. - 北海道大学図書刊行会, 1991
 北大ではどこにある?
この本は、僕の専門分野と関わりがあるので読んだものだが、推薦文としては「良書だから読むべし!」としか言いようがない。実は,僕はこの著者である逸見先生(元教育学部長・現名誉教授)の“ファン”なのである。まだ逸見先生がご在職中にこの本を読んで疑問に思った点があったので、直接教えを請う機会をいただいたのだが、逸見先生のご教示、お人柄、生き方に痺れて、ファンになり今に至っている。その意味ではここに推薦するのが遅すぎたくらいだ。こういう推薦の仕方にきっと先生には眉をひそめられるかもしれないが、そこはお許しいただいて、多くの学生に読んでも... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、僕の専門分野と関わりがあるので読んだものだが、推薦文としては「良書だから読むべし!」としか言いようがない。実は,僕はこの著者である逸見先生(元教育学部長・現名誉教授)の“ファン”なのである。まだ逸見先生がご在職中にこの本を読んで疑問に思った点があったので、直接教えを請う機会をいただいたのだが、逸見先生のご教示、お人柄、生き方に痺れて、ファンになり今に至っている。その意味ではここに推薦するのが遅すぎたくらいだ。こういう推薦の仕方にきっと先生には眉をひそめられるかもしれないが、そこはお許しいただいて、多くの学生に読んでも... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
長編の魅力ここにあり
チボー家の人々 / ロジェ・マルタン・デュ・ガール. - 白水社,
 北大ではどこにある?
実は僕は長編小説(特に日本の)を読むのは苦手である。登場人物が多くなるので関係を覚えきれない、というより覚えるのが面倒くさいという怠惰な精神のせいなのだが、その結果として山岡荘八『徳川家康』、中里介山『大菩薩峠』、塩野七生『ローマ人の物語』、埴谷雄高『死霊』と、挫折した作品は死屍累々である。その割に西洋文学の長編はなぜか日本文学ほど抵抗なくダンテ『神曲』、デュマ『モンテ・クリスト伯』、そしてこの『チボー家の人々』は結構夢中になって読めた。特に『チボー家の人々』は第一次大戦期のフランスという一種重苦しい時代を描きつつも主人公とな... [続きを読む]
北大ではどこにある?
実は僕は長編小説(特に日本の)を読むのは苦手である。登場人物が多くなるので関係を覚えきれない、というより覚えるのが面倒くさいという怠惰な精神のせいなのだが、その結果として山岡荘八『徳川家康』、中里介山『大菩薩峠』、塩野七生『ローマ人の物語』、埴谷雄高『死霊』と、挫折した作品は死屍累々である。その割に西洋文学の長編はなぜか日本文学ほど抵抗なくダンテ『神曲』、デュマ『モンテ・クリスト伯』、そしてこの『チボー家の人々』は結構夢中になって読めた。特に『チボー家の人々』は第一次大戦期のフランスという一種重苦しい時代を描きつつも主人公とな... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
経済学とは結局何なのか、を考える。
戦時下の経済学者 / 牧野邦昭. - 中央公論新社, 2010
 北大ではどこにある?
この本の表題は『戦時下の経済学者』であり、事実経済学者(の学説)に多くのページを割いている。しかし、この本の主眼とするところは人物伝ではなく、著者自身が「あとがき」で書いているように「経済学はなぜこうなっているのか」という問題意識である。僕なりの読み方で言えば戦時下の総力戦体制の中で個々の経済学者の学説が社会の要請と切り結びながらどうしてその学説のような形を取ることを求められたか、を考えようとするものだと言えるだろう。僕はこの本をノートを取りながら割合丹念に読んだのだが、僕自身の関心はむしろ個々の経済学者あるいは研究機関の時代... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本の表題は『戦時下の経済学者』であり、事実経済学者(の学説)に多くのページを割いている。しかし、この本の主眼とするところは人物伝ではなく、著者自身が「あとがき」で書いているように「経済学はなぜこうなっているのか」という問題意識である。僕なりの読み方で言えば戦時下の総力戦体制の中で個々の経済学者の学説が社会の要請と切り結びながらどうしてその学説のような形を取ることを求められたか、を考えようとするものだと言えるだろう。僕はこの本をノートを取りながら割合丹念に読んだのだが、僕自身の関心はむしろ個々の経済学者あるいは研究機関の時代... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
昭和をまだノスタルジーにするな!
昭和時代年表 増補版 / 中村政則. - 岩波書店, 1986
 北大ではどこにある?
ここ何年かの間に、メディアで「昭和の○○」といったことばを少なからず読んだり聞いたりすることがある。女優の黒木華さんは「昭和顔」と言われているそうだ。昭和32年(=考えてみればちょうど昭和の半分の年)生まれで、経済の高度成長とともに成長し、1988年のバブル最盛期に就職した僕から見ると、「『昭和』をそんなに簡単にノスタルジーにするな!」という怒りにも似た気持ちを禁じ得ない。それは、僕個人にとって昭和がリアルタイムであると言うだけのことではなく、昭和時代に現れ、あるいは作られた様々な問題・課題から我々が未だに解き放たれているとは言えない... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ここ何年かの間に、メディアで「昭和の○○」といったことばを少なからず読んだり聞いたりすることがある。女優の黒木華さんは「昭和顔」と言われているそうだ。昭和32年(=考えてみればちょうど昭和の半分の年)生まれで、経済の高度成長とともに成長し、1988年のバブル最盛期に就職した僕から見ると、「『昭和』をそんなに簡単にノスタルジーにするな!」という怒りにも似た気持ちを禁じ得ない。それは、僕個人にとって昭和がリアルタイムであると言うだけのことではなく、昭和時代に現れ、あるいは作られた様々な問題・課題から我々が未だに解き放たれているとは言えない... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
岩波新書は不滅です!
岩波新書の歴史 : 付・総目録1938-2006 / 鹿野政直. - 岩波書店, 2006
 北大ではどこにある?
前にこの「本は脳を育てる」に岩波新書(青版)の鈴木八司『ナイルに沈む歴史』を推薦した際に、「最近(特に今世紀になってから)、岩波新書(新赤版)がつまらなくなってきた。」と書いたが、そうはいってもやはり岩波新書は「腐っても鯛」-という書き方は失礼かもしれないけれども-である。「岩波文化人」という、一種の鼻持ちならないエリートを作り出したという問題点はあるが、間違いなく日本近代、あるいは昭和以降の「教養」の担い手として大きな存在感を発揮したことは否定しようがない。この鹿野氏の著作は、岩波新書がどのような価値観を時代に対する「教養」... [続きを読む]
北大ではどこにある?
前にこの「本は脳を育てる」に岩波新書(青版)の鈴木八司『ナイルに沈む歴史』を推薦した際に、「最近(特に今世紀になってから)、岩波新書(新赤版)がつまらなくなってきた。」と書いたが、そうはいってもやはり岩波新書は「腐っても鯛」-という書き方は失礼かもしれないけれども-である。「岩波文化人」という、一種の鼻持ちならないエリートを作り出したという問題点はあるが、間違いなく日本近代、あるいは昭和以降の「教養」の担い手として大きな存在感を発揮したことは否定しようがない。この鹿野氏の著作は、岩波新書がどのような価値観を時代に対する「教養」... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「教養」は実践するものである。
人生を面白くする本物の教養 / 出口治明. - 幻冬舎, 2015
 北大ではどこにある?
この本の推薦文は、僕の体験したエピソードの紹介を以てこれに替えたいと思う。
北大ではどこにある?
この本の推薦文は、僕の体験したエピソードの紹介を以てこれに替えたいと思う。
大学時代に読んだ本の中に、イギリス人は初対面の相手にまず政治の話題を振って、相手がその話題についてこられなかったら「こいつは付き合う価値のない奴だ」と見切りをつける、という趣旨のことが書いてあった。いくら何でもそれは決めつけすぎだろうと思ったものの、そのことを忘れて十年ほどが経過し、機会を得てエジプトに赴任することになった。そして、彼の地でイギリス人のカップルと知り合い、ある日彼らの家に夕食に招待された。席についてまずワインで乾杯となったのだが、一口... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
日本語研究の面白さに触れる
ヴァーチャル日本語役割語の謎 / 金水敏. - 岩波書店, 2003
 北大ではどこにある?
最近は学問研究、あるいは学術研究の対象化のペースが極度に速くなっていて、ついこの間「オネエ言葉」という表現が使われ出したと思ったらもうオネエ言葉の研究書が出ている、といった具合である。この本は、様々な職業・性別・時代等々に応じて現れる固有の(と見える)表現を「役割語」という概念によって分析することで見えてくる日本語の姿を明らかにしたものであるが、古今東西の文学作品からマンガ、はては『スター・ウォーズ』から『ハリー・ポッター』まで題材にしてまさに縦横無尽に切りまくる、読み応えのある一冊となっている。日本語に興味はあるが難しそうで... [続きを読む]
北大ではどこにある?
最近は学問研究、あるいは学術研究の対象化のペースが極度に速くなっていて、ついこの間「オネエ言葉」という表現が使われ出したと思ったらもうオネエ言葉の研究書が出ている、といった具合である。この本は、様々な職業・性別・時代等々に応じて現れる固有の(と見える)表現を「役割語」という概念によって分析することで見えてくる日本語の姿を明らかにしたものであるが、古今東西の文学作品からマンガ、はては『スター・ウォーズ』から『ハリー・ポッター』まで題材にしてまさに縦横無尽に切りまくる、読み応えのある一冊となっている。日本語に興味はあるが難しそうで... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
巧妙化・複雑化する戦争ビジネスを知る
民営化される戦争-21世紀の民族紛争と企業- / 本山美彦. - ナカニシヤ出版, 2004
 北大ではどこにある?
戦争に関わる企業と聞くと、兵器・武器の製造売買を行う-古いことばで言えば-「死の商人」が思い浮かぶ。それはそれとして現在もあることに変わりはないが、この本を読むと、思いがけないところで思いがけない企業が、国家(この本で主題的に取り上げられるのはアメリカだが)の中枢部と結託して戦争の後方支援活動などに食い込み利益を上げていることが分かる。さらには、こうした企業が、アフリカなどの資源を保有する後進国で資源ビジネスに目を付けてに内戦=民族対立や紛争を煽っている構図までもが明らかにされる。民族紛争の解決と貧困の撲滅は間違いなく21世紀の世... [続きを読む]
北大ではどこにある?
戦争に関わる企業と聞くと、兵器・武器の製造売買を行う-古いことばで言えば-「死の商人」が思い浮かぶ。それはそれとして現在もあることに変わりはないが、この本を読むと、思いがけないところで思いがけない企業が、国家(この本で主題的に取り上げられるのはアメリカだが)の中枢部と結託して戦争の後方支援活動などに食い込み利益を上げていることが分かる。さらには、こうした企業が、アフリカなどの資源を保有する後進国で資源ビジネスに目を付けてに内戦=民族対立や紛争を煽っている構図までもが明らかにされる。民族紛争の解決と貧困の撲滅は間違いなく21世紀の世... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
日本語教育と国語教育をめぐる日中の結びつきを知る
現代中国の日本語教育史-大学専攻教育と教科書をめぐって- / 田中祐輔. - 国書刊行会, 2015
 北大ではどこにある?
僕が30年以上前、初めて日本語教育に関わったときに学校から与えられた教科書は東京外国語大学附属日本語学校編『日本語Ⅱ』だった。内容を一目見て驚いたのは、僕自身が小学校の国語教科書で勉強した文章が幾つか教材として課を為していることだった。当時、日本語教育についての知識も技術もろくになかった僕でも「日本人小学生向けの教科書と外国人留学生向けの教科書が同じでいいものか」と疑問に思ったのを覚えている。しかし、実態としては、日本の国語科教科書の文章は、様々な形で外国人向け日本語教科書に取り入れられていたのである。そして、それは日本国内で出版... [続きを読む]
北大ではどこにある?
僕が30年以上前、初めて日本語教育に関わったときに学校から与えられた教科書は東京外国語大学附属日本語学校編『日本語Ⅱ』だった。内容を一目見て驚いたのは、僕自身が小学校の国語教科書で勉強した文章が幾つか教材として課を為していることだった。当時、日本語教育についての知識も技術もろくになかった僕でも「日本人小学生向けの教科書と外国人留学生向けの教科書が同じでいいものか」と疑問に思ったのを覚えている。しかし、実態としては、日本の国語科教科書の文章は、様々な形で外国人向け日本語教科書に取り入れられていたのである。そして、それは日本国内で出版... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
よりよい働き方をどう実現するか
個人を幸福にしない日本の組織 / 太田肇. - 新潮社, 2016
 北大ではどこにある?
この本は、標題だけを見るとかつてのカレル・ヴァン・ウォルフレンの『人間を幸福にしない日本というシステム』の二番煎じのように見えてしまうが、内容は組織論あるいは経営制度論の観点から見た日本人の働き方/働かせ方の批判的考察である。これを読むと、企業も学校も芸能界も自治体も町内会も、およそ人が集まって作られる目的集団がいかに機能不全を起こしやすいかがよく分かる。筆者はその点について、かなり大胆な処方箋を提示してくれているが、欲を言えばもう少し突っ込んで対策を書いてくれるとより面白くなったと思う。自分の将来の仕事のあり方として会社勤め... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この本は、標題だけを見るとかつてのカレル・ヴァン・ウォルフレンの『人間を幸福にしない日本というシステム』の二番煎じのように見えてしまうが、内容は組織論あるいは経営制度論の観点から見た日本人の働き方/働かせ方の批判的考察である。これを読むと、企業も学校も芸能界も自治体も町内会も、およそ人が集まって作られる目的集団がいかに機能不全を起こしやすいかがよく分かる。筆者はその点について、かなり大胆な処方箋を提示してくれているが、欲を言えばもう少し突っ込んで対策を書いてくれるとより面白くなったと思う。自分の将来の仕事のあり方として会社勤め... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
西洋哲学の基本の「き」
方法序説 / ルネ・デカルト. - 岩波書店, 1997
 北大ではどこにある?
「われ考える、ゆえにわれあり」や「明晰判明」、あるいは”方法的懐疑”といったことばであまりにも有名な、西洋(近世)哲学の始まりを飾る書である。哲学書というと初めから難しいものと考えて敬遠してしまう向きもあるかもしれない-そのような書物があることを否定はしない-が、この本は、きちんと読んでいけばそれなりに分かるように書かれているものである、同時にまた、西洋近世~近現代の哲学が多くの考えるべき課題をそこからくみ取っていった、西洋の知の基本をなす書物でもある。そのようなものを読んでおくことは、洋の東西を問わず学問を研究しようとするも... [続きを読む]
北大ではどこにある?
「われ考える、ゆえにわれあり」や「明晰判明」、あるいは”方法的懐疑”といったことばであまりにも有名な、西洋(近世)哲学の始まりを飾る書である。哲学書というと初めから難しいものと考えて敬遠してしまう向きもあるかもしれない-そのような書物があることを否定はしない-が、この本は、きちんと読んでいけばそれなりに分かるように書かれているものである、同時にまた、西洋近世~近現代の哲学が多くの考えるべき課題をそこからくみ取っていった、西洋の知の基本をなす書物でもある。そのようなものを読んでおくことは、洋の東西を問わず学問を研究しようとするも... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
ことばはどのように情報を伝えるのか?
文法と談話の接点-日本語の談話における主題展開機能の研究- / 砂川有里子. - くろしお出版, 2005
 北大ではどこにある?
この本は、本格的な専門書であるが、丹念に読んでいけばきちんと分かるように書かれた本であり、日本語の働き方について新しい知見を与えてくれるものである。専門的に言えば、談話文法を機能言語学的に考察したものであるが、その内容を噛み砕いて言うならば、日本語の中でどのように情報が情報として現れそれが伝えられていくか、そのメカニズムを明らかにしたものである。将来日本語について研究してみたいと考えている人や、既に談話文法に関心のある人に広く一読を勧めたい。
北大ではどこにある?
この本は、本格的な専門書であるが、丹念に読んでいけばきちんと分かるように書かれた本であり、日本語の働き方について新しい知見を与えてくれるものである。専門的に言えば、談話文法を機能言語学的に考察したものであるが、その内容を噛み砕いて言うならば、日本語の中でどのように情報が情報として現れそれが伝えられていくか、そのメカニズムを明らかにしたものである。将来日本語について研究してみたいと考えている人や、既に談話文法に関心のある人に広く一読を勧めたい。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
もう一つの日本の理論物理学形成史
科学ジャーナリズムの先駆者 評伝 石原純 / 西尾成子. - 岩波書店, 2011
 北大ではどこにある?
石原純という名前を初めて見たのは、大学時代に西田幾多郎の哲学を勉強していたときであった。西田の弟子であった下村寅太郎の文章中に、日本に於ける相対性理論の紹介者といった形で名前が出ていたのを覚えている。この本では、物理学者、相対性理論の研究者・紹介者という面だけでなく、科学ジャーナリストとしての石原に光を当てて多くのページを割いている。昨今、自然科学研究の世界では研究の確実性やその情報の透明性を揺るがすような事案がいくつか起こった。(勿論、人文社会科学でも同様のことはあったし、今後もあり得る。) このような時代に、科学研究の内実... [続きを読む]
北大ではどこにある?
石原純という名前を初めて見たのは、大学時代に西田幾多郎の哲学を勉強していたときであった。西田の弟子であった下村寅太郎の文章中に、日本に於ける相対性理論の紹介者といった形で名前が出ていたのを覚えている。この本では、物理学者、相対性理論の研究者・紹介者という面だけでなく、科学ジャーナリストとしての石原に光を当てて多くのページを割いている。昨今、自然科学研究の世界では研究の確実性やその情報の透明性を揺るがすような事案がいくつか起こった。(勿論、人文社会科学でも同様のことはあったし、今後もあり得る。) このような時代に、科学研究の内実... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
多文化社会とは?
多文化教育の研究ーひと、ことば、つながりー / 朝倉征夫. - 学文社, 2003
 北大ではどこにある?
「多文化社会」や「異文化(間)コミュニケーション」というのは今や大学教育に於ける”流行語”と言ってもいいと思うのだが、他でもないこの北大で「多文化交流科目」を担当していると、学生の殆どが(場合によっては教員も)「多文化」あるいは「異文化」ということを”外国人(非日本人)との交流”だと思い込んでいる実情が見られ、そのたびになんとかしなければ、と思ってしまう。
北大ではどこにある?
「多文化社会」や「異文化(間)コミュニケーション」というのは今や大学教育に於ける”流行語”と言ってもいいと思うのだが、他でもないこの北大で「多文化交流科目」を担当していると、学生の殆どが(場合によっては教員も)「多文化」あるいは「異文化」ということを”外国人(非日本人)との交流”だと思い込んでいる実情が見られ、そのたびになんとかしなければ、と思ってしまう。
この本は三部から成るが、第一部の総論を除くと、半分を占める第二部は外国(人)に関する「多文化」状況ではなく、この日本国内に於いて文化的背景を異にする人々に関する考察である... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
わくわくするナイル源流への旅の記録
ナイルに沈む歴史-ヌビア人と古代遺跡- / 鈴木八司. - 岩波書店, 1970
 北大ではどこにある?
最近(特に今世紀になってから)、岩波新書(新赤版)がつまらなくなってきた。社会の流れが速くなるのに歩調を合わせすぎているのか、時事的なものが多くなり-それはそれで必要だと思うが-長く手元に置いて何度も繰り返して読みたくなるような内容のものが減っている気がする。ここに推薦する青版の『ナイルに沈む歴史』は、僕が中学生の時にでた本であるが、アスワン・ハイダムの建設によるアブ・シンベル神殿の水没を回避するための国際プロジェクトの一環として著者の鈴木氏が行ったエジプト・ナイル川上流地域の踏破記録である。それまでもハワード・カーターによる... [続きを読む]
北大ではどこにある?
最近(特に今世紀になってから)、岩波新書(新赤版)がつまらなくなってきた。社会の流れが速くなるのに歩調を合わせすぎているのか、時事的なものが多くなり-それはそれで必要だと思うが-長く手元に置いて何度も繰り返して読みたくなるような内容のものが減っている気がする。ここに推薦する青版の『ナイルに沈む歴史』は、僕が中学生の時にでた本であるが、アスワン・ハイダムの建設によるアブ・シンベル神殿の水没を回避するための国際プロジェクトの一環として著者の鈴木氏が行ったエジプト・ナイル川上流地域の踏破記録である。それまでもハワード・カーターによる... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「分からなさ」を味わい、楽しむ
哲学とは何か / ジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリ. - 河出書房新社, 1997
 北大ではどこにある?
この推薦文は、「本は脳を育てる」の趣旨には反するが、たまにはこういった推薦もあっていいのではないかと思い、ここに挙げることにした。
北大ではどこにある?
この推薦文は、「本は脳を育てる」の趣旨には反するが、たまにはこういった推薦もあっていいのではないかと思い、ここに挙げることにした。
哲学の本を数多く読んできたが、これほど分からない本を読んだことはない。普通は分からなければなんとか分かろうと努力し、それなりに考えながら読むものであるが、この本は読んでも読んでも分からず、そのうちにその「分からなさ」が心地よく思えてきさえする。読んでいる自分が「分からなさ」という感覚に身をゆだね、それを楽しむ境地(?)に至った気分になってくるのである。それは著者両名の巧妙な仕掛けにあり、著者たちはお... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
文学という営みを通してみた日本人像とは
近代日本人の発想の諸形式 / 伊藤整. - 1981, 岩波書店
 北大ではどこにある?
標題となっている論文で、著者は、日本人の手によって行われた文学(創作と作品)を「逃避型と破滅型」、「上昇型と下降型」等いくつかの切り口から鋭く考察し、日本に於いてその文学的な風土がどのように形成されたかという問題に取り組んでいる。その過程で一つの鍵となるのは、創作の専門性とそれを体現する”文士”という存在である。そうした観点から見たとき、多くの人が常識的に(?)受け止めている「文豪」漱石と鴎外への批判は苛烈を極める。
北大ではどこにある?
標題となっている論文で、著者は、日本人の手によって行われた文学(創作と作品)を「逃避型と破滅型」、「上昇型と下降型」等いくつかの切り口から鋭く考察し、日本に於いてその文学的な風土がどのように形成されたかという問題に取り組んでいる。その過程で一つの鍵となるのは、創作の専門性とそれを体現する”文士”という存在である。そうした観点から見たとき、多くの人が常識的に(?)受け止めている「文豪」漱石と鴎外への批判は苛烈を極める。
20世紀末から日本哲学(史)の研究が徐々に隆盛の兆しを見せてきたが、哲学研究者とは別の(「異質」と言っても良い... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
留学したい人は必読!
バイカルチャルになれる人・なれない人-アメリカで変わる日本人- / 本田正文. - 丸善, 1999
 北大ではどこにある?
この本は、大きく分けると著者である本田氏がアメリカ留学の中で体験した異文化適応の過程の紹介と、専門とする第二言語習得理論(から見たバイリンガリズム)の概説をバイカルチャルという観点で融合させていこうとしたものである。こう書くとなにやら難しそうな本のようであるが、そのようなことはない。むしろ、本田氏が実際にアメリカで何に苦労しそこからどのような「智慧」を見いだして異文化での生活を成り立たせていったかが、時にユーモアを交えながら成長段階を追って書かれている。
北大ではどこにある?
この本は、大きく分けると著者である本田氏がアメリカ留学の中で体験した異文化適応の過程の紹介と、専門とする第二言語習得理論(から見たバイリンガリズム)の概説をバイカルチャルという観点で融合させていこうとしたものである。こう書くとなにやら難しそうな本のようであるが、そのようなことはない。むしろ、本田氏が実際にアメリカで何に苦労しそこからどのような「智慧」を見いだして異文化での生活を成り立たせていったかが、時にユーモアを交えながら成長段階を追って書かれている。
これから海外留学を目指す人には色々な希望と不安があると思うが、留学生活... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
科学という営みを伝えることの大切さを知る
ロウソクの科学 / マイケル・ファラデー. - 岩波書店, 2010
 北大ではどこにある?
この本は、まさに「古典」という名にふさわしい有名な本だから既に読んでいる人が多いかと思うが、今の学生は(ああ、これもまた「古典」的な説教口調だ!)「古典」をあまり読まないらしいので推薦する意味はそれなりにあるだろうと思う。
北大ではどこにある?
この本は、まさに「古典」という名にふさわしい有名な本だから既に読んでいる人が多いかと思うが、今の学生は(ああ、これもまた「古典」的な説教口調だ!)「古典」をあまり読まないらしいので推薦する意味はそれなりにあるだろうと思う。
僕が小学生の頃は、雑誌『子供の科学』が毎月発刊されるのが待ち遠しく、またあかね書房から『少年少女最新科学全集』が刊行され、所謂”科学読み物”が一つの隆盛を迎えていた時代であった。その時期にこの『ロウソクの科学』と初めて接したのであるが、小学生が読むには少し手強かった。僕は、日下実男訳の旺文社文庫版(今は廃... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
世界に働く根本的な力を考える
歴史の終わり(上・下) / フランシス・フクヤマ. - 三笠書房, 1992
 北大ではどこにある?
個人的に2015年はあまり面白い本にめぐり逢わなかった1年だった。その中では比較的面白かったのがこの本である。1992年に刊行されたこの本を20年以上経って読んでみると、著者が重視するリベラルな民主主義が現在の世界で置かれているアクチュアルな立場をよく見通すことができる。20年以上前に書かれた本ではあるが、そこに含まれる観点は20年そこそこの時間の経過の中では古びてしまうということはなく、今なお国際政治・国際関係を考える上で必要な知見を提供してくれると思う。
北大ではどこにある?
個人的に2015年はあまり面白い本にめぐり逢わなかった1年だった。その中では比較的面白かったのがこの本である。1992年に刊行されたこの本を20年以上経って読んでみると、著者が重視するリベラルな民主主義が現在の世界で置かれているアクチュアルな立場をよく見通すことができる。20年以上前に書かれた本ではあるが、そこに含まれる観点は20年そこそこの時間の経過の中では古びてしまうということはなく、今なお国際政治・国際関係を考える上で必要な知見を提供してくれると思う。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
留学する前に読んでおこう!
魯迅の日本 漱石のイギリスー「留学の世紀」を生きた人びとー / 柴崎信三. - 日本経済新聞社, 1999
 北大ではどこにある?
国を挙げての「留学」ばやりである。文部科学省もAKB48まで動員して「トビタテ!留学JAPAN」なるキャンペーンまでやっている。北大から海外協定大学に留学する学生も増えているようで結構なことである。(「留学」したことがない僕はちょっと僻んでこの推薦文を書いているのだが)かつては「留学」というのは決定的にエリートへの道筋であった。筆者はその時代に「留学」し(て苦労し)た代表者としての魯迅と漱石を軸にして、「留学」ということが日中それぞれの社会と個人にどのような意味を持ったかを浮かび上がらせようとしている。今と昔で意味合いは違うものの「留学」と... [続きを読む]
北大ではどこにある?
国を挙げての「留学」ばやりである。文部科学省もAKB48まで動員して「トビタテ!留学JAPAN」なるキャンペーンまでやっている。北大から海外協定大学に留学する学生も増えているようで結構なことである。(「留学」したことがない僕はちょっと僻んでこの推薦文を書いているのだが)かつては「留学」というのは決定的にエリートへの道筋であった。筆者はその時代に「留学」し(て苦労し)た代表者としての魯迅と漱石を軸にして、「留学」ということが日中それぞれの社会と個人にどのような意味を持ったかを浮かび上がらせようとしている。今と昔で意味合いは違うものの「留学」と... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
理論と実例の両面から分かる異文化間コミュニケーション
異文化コミュニケーション : 新・国際人への条件[改訂版] / 古田暁. - 有斐閣, 1996
 北大ではどこにある?
異文化間コミュニケーションについての解説書・研究書は山ほどあるが、内容がまとまっていてしかも頭に入りやすい本はそう多くはない。この本は、異文化間コミュニケーションの理論的側面に重点を置きながらも様々な実例を組み込んでわかりやすい叙述を心がけている。一章の分量もそれほど多くないので、一日に読む分量を決めてノートを取りながら読めば内容を押さえていくことができるだろう。異文化間コミュニケーションの好適な入門書として薦めたい。
北大ではどこにある?
異文化間コミュニケーションについての解説書・研究書は山ほどあるが、内容がまとまっていてしかも頭に入りやすい本はそう多くはない。この本は、異文化間コミュニケーションの理論的側面に重点を置きながらも様々な実例を組み込んでわかりやすい叙述を心がけている。一章の分量もそれほど多くないので、一日に読む分量を決めてノートを取りながら読めば内容を押さえていくことができるだろう。異文化間コミュニケーションの好適な入門書として薦めたい。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
世界の見方を深めるために
現象学という思考-<自明なもの>の知へ- / 田口茂. - 筑摩書房, 2014
 北大ではどこにある?
一昨年度から「多文化交流科目」という授業を始め、一貫して異文化理解、あるいは異文化交流の問題を扱ってきた。難しいのは、異文化理解に関わる理論と異文化交流の実践を教室の内外でどうつなぐかということであり、このことにずっと悩んできた。今年になってからふと「現象学」の考え方からこの問題にアプローチしてはどうだろうかと思ってこの本を読んでみたら、まさに第四章・第五章を中心として示唆に富む記述が満ちていてありがたい思いがした。こうしたアプローチは、僕の曖昧な記憶では確かクラウス・ヘルトが手をつけ、日本では小川侃先生(元京都大学)が触れて... [続きを読む]
北大ではどこにある?
一昨年度から「多文化交流科目」という授業を始め、一貫して異文化理解、あるいは異文化交流の問題を扱ってきた。難しいのは、異文化理解に関わる理論と異文化交流の実践を教室の内外でどうつなぐかということであり、このことにずっと悩んできた。今年になってからふと「現象学」の考え方からこの問題にアプローチしてはどうだろうかと思ってこの本を読んでみたら、まさに第四章・第五章を中心として示唆に富む記述が満ちていてありがたい思いがした。こうしたアプローチは、僕の曖昧な記憶では確かクラウス・ヘルトが手をつけ、日本では小川侃先生(元京都大学)が触れて... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
冒険記は面白い!
世界の測量-ガウスとフンボルトの物語- / ダニエル・ケールマン. - 三修社, 2008
 北大ではどこにある?
この本は、近代ドイツの学術史に屹立する偉人、数学者のガウスと博物学者のフンボルトの知的探求の冒険を描いた作品である。第一章と第十四章でガウスとフンボルトは邂逅するが、それ以外の章は一章ごとにそれぞれの探求の人生が描かれる。異世界に新しい知識と発見を求めて踏み込んでいくことが(単純に)偉業だと考えられていた時代を現代の視点から振り返るどのように表せるか、ということが興味深く読み取れるだろう。
北大ではどこにある?
この本は、近代ドイツの学術史に屹立する偉人、数学者のガウスと博物学者のフンボルトの知的探求の冒険を描いた作品である。第一章と第十四章でガウスとフンボルトは邂逅するが、それ以外の章は一章ごとにそれぞれの探求の人生が描かれる。異世界に新しい知識と発見を求めて踏み込んでいくことが(単純に)偉業だと考えられていた時代を現代の視点から振り返るどのように表せるか、ということが興味深く読み取れるだろう。
勿論、小説なので虚実取り混ぜられており、ガウスが哲学者カントのところに非ユークリッド幾何学の発見を告げに行く部分などは完全なフィクション... [続きを読む]