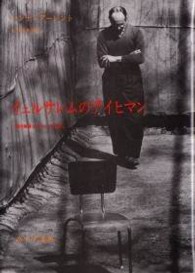-
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「哲学」のススメ
善の研究 / 西田幾多郎. - 岩波書店, 1979
 北大ではどこにある?
『善の研究』については、これまで嫌になるくらい論文や研究書があり、僕もかつてその手のものを書いたことがある。それだけいろいろな読み方・解釈が可能だという点では紛れもなく「古典」であるが、同時に何回読んでもすっきりと分かった感じになれないところもある。そういうところから、「西田哲学を理解するためにも実際に参禅をしなければならない」(久松真一)といった言説が出てくるのだろう。
北大ではどこにある?
『善の研究』については、これまで嫌になるくらい論文や研究書があり、僕もかつてその手のものを書いたことがある。それだけいろいろな読み方・解釈が可能だという点では紛れもなく「古典」であるが、同時に何回読んでもすっきりと分かった感じになれないところもある。そういうところから、「西田哲学を理解するためにも実際に参禅をしなければならない」(久松真一)といった言説が出てくるのだろう。
『善の研究』は、すぐ分かるようでありながら実は分かりにくいし、まさにその「分かる=理解」という営みそのものを問題にしているところがあるので、どこまで行って... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
「倫理」は可能か?
支配と服従の倫理学 / 羽入辰郎. - ミネルヴァ書房, 2009
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
学際的研究の模範
光と視覚の科学―神話・哲学・芸術と現代科学の融合― / アーサー・ザイエンス. - 白掦社, 1997
 北大ではどこにある?
本書は物理学者であるザイエンスによる、一切のものの基礎にある光についての哲学、宗教、芸術など人間の知力と想像力を駆使して解明にせまる、通史としての学際的研究の著しい成功例である。光の解明に取り組む物理学者、哲学者、数学者たちの知的営為が彼らの人間性を知らせる興味深いエピソードとともに、わかりやすく解説されている。「あらゆる物理系の振る舞いの背後、あらゆる物理法則の背後に何があるのか」という問いが本書を読むことにより道理あるものとして受け止められるのは、事物の一切に浸透する光という形而上学的な対象の故にであろう。アインシュタイン... [続きを読む]
北大ではどこにある?
本書は物理学者であるザイエンスによる、一切のものの基礎にある光についての哲学、宗教、芸術など人間の知力と想像力を駆使して解明にせまる、通史としての学際的研究の著しい成功例である。光の解明に取り組む物理学者、哲学者、数学者たちの知的営為が彼らの人間性を知らせる興味深いエピソードとともに、わかりやすく解説されている。「あらゆる物理系の振る舞いの背後、あらゆる物理法則の背後に何があるのか」という問いが本書を読むことにより道理あるものとして受け止められるのは、事物の一切に浸透する光という形而上学的な対象の故にであろう。アインシュタイン... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
西洋文明と哲学
反哲学入門 / 木田元. - 新潮社, 2007
 北大ではどこにある?
アメリカでは最近哲学専攻の学生が増えていると云います(ニューヨークタイムズ2008年4月6日の記事)。ただし、歴史上の哲学者のあれこれに興味があるのではなく、将来の見通しが立たない現代社会にあっては、思索で頭脳を鍛え論争の術を身につける必要があるという認識にたってのようです。哲学がそういう処世術にも通ずる生きた学問だと意識されていることに驚きました。
北大ではどこにある?
アメリカでは最近哲学専攻の学生が増えていると云います(ニューヨークタイムズ2008年4月6日の記事)。ただし、歴史上の哲学者のあれこれに興味があるのではなく、将来の見通しが立たない現代社会にあっては、思索で頭脳を鍛え論争の術を身につける必要があるという認識にたってのようです。哲学がそういう処世術にも通ずる生きた学問だと意識されていることに驚きました。
同時にアメリカ大統領予備選挙の記事を追っていると、度を越したような泥試合のなかにも、時として当事者に正気がもどり、その晴れ間をぬって歴史を貫いてきたギリシャ以来の精神が現前すると思われ... [続きを読む] -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
現代中国を代表する哲学者による回想録
馮友蘭自伝 : 中国現代哲学者の回想 1・2 (東洋文庫 ; 767-768) / 馮友蘭著 ; 吾妻重二訳 . - 平凡社, 2007
 北大ではどこにある?
現代中国を代表する哲学者による回想録。19世紀末から1980年代に至る、変貌の時代を生きた著者が同時代史を記し、自己の経験をまとめた書で、激動の中国近現代史を理解するうえで必読書といってもよい名著の翻訳である。なかでも中華人民共和国成立後の部分は、知識人の内面史として他書に類例をみぬ価値を持つ。翻訳も平明で読みやすい。
北大ではどこにある?
現代中国を代表する哲学者による回想録。19世紀末から1980年代に至る、変貌の時代を生きた著者が同時代史を記し、自己の経験をまとめた書で、激動の中国近現代史を理解するうえで必読書といってもよい名著の翻訳である。なかでも中華人民共和国成立後の部分は、知識人の内面史として他書に類例をみぬ価値を持つ。翻訳も平明で読みやすい。 -
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
人文学はどのようなひとを育てるか
哲学修業時代 / H.G.ガーダマー (中村志朗訳). - 未来社 , 1982
 北大ではどこにある?
本書は哲学、そして広くは文学、神学などを含む人文学一般への、生き生きした人物評伝を媒介にしたものとしては、最良の入門書であろう。1900年ドイツ生まれという著者が生きたその時代が人類史においても特筆すべき時代であったことからくる興味深さもさることながら、本書は人文学を学んだひとはどのようなひととなり、そしてどのように人々と交わるかを、さらに人間を愛情をもってどれほど豊かなものとして、また正確さにおいて説得的なものとして描きうるかをいかんなく伝えている。それにしても彼の交流のなんと豊かなことか、P.ナトルプ、E.フッサール、N.ハルトマン、R.... [続きを読む]
北大ではどこにある?
本書は哲学、そして広くは文学、神学などを含む人文学一般への、生き生きした人物評伝を媒介にしたものとしては、最良の入門書であろう。1900年ドイツ生まれという著者が生きたその時代が人類史においても特筆すべき時代であったことからくる興味深さもさることながら、本書は人文学を学んだひとはどのようなひととなり、そしてどのように人々と交わるかを、さらに人間を愛情をもってどれほど豊かなものとして、また正確さにおいて説得的なものとして描きうるかをいかんなく伝えている。それにしても彼の交流のなんと豊かなことか、P.ナトルプ、E.フッサール、N.ハルトマン、R.... [続きを読む] -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
「考える」という営みへの最良の入門書
哲学、脳を揺さぶる / 河本英夫. - 日経BP, 2007
 北大ではどこにある?
分類すれば哲学という分野に入るのだろうが、思考のエクササイズはもとより、芸術あり、科学あり、身体論あり、イメージ論あり、認知論あり、といった具合に間口はひろく、総合的であり、そして(多少は苦労もしながら)ひとたび読み終わってみれば、脳は活性化し、何やらいっぱしの知的ナヴィゲーションをしてきた充実感が得られること間違いなし。著者は、「考える」という人間の不思議なイトナミに深く広く分け入らんとする先端的な探求者のひとり。大学生たる者、たまにはこうした本を読みこなさなくちゃ。
北大ではどこにある?
分類すれば哲学という分野に入るのだろうが、思考のエクササイズはもとより、芸術あり、科学あり、身体論あり、イメージ論あり、認知論あり、といった具合に間口はひろく、総合的であり、そして(多少は苦労もしながら)ひとたび読み終わってみれば、脳は活性化し、何やらいっぱしの知的ナヴィゲーションをしてきた充実感が得られること間違いなし。著者は、「考える」という人間の不思議なイトナミに深く広く分け入らんとする先端的な探求者のひとり。大学生たる者、たまにはこうした本を読みこなさなくちゃ。 -
推薦者 : 須田 勝彦 (教育学部)
論理学とは何か
論理学―思考の法則と科学の方法 / 鰺坂 真他. - 世界思想社, 1987年
 北大ではどこにある?
論理学は,アリストテレスの時代から現代まで,変容を遂げながら進化を続けてきている。「論理的思考とは何か」を考えるためにはやはり論理学についての認識が必要だろう。この書は,哲学における論理と,数学の一領域となった記号論理学との,ほどよい橋渡しとなってくれるだろう。
北大ではどこにある?
論理学は,アリストテレスの時代から現代まで,変容を遂げながら進化を続けてきている。「論理的思考とは何か」を考えるためにはやはり論理学についての認識が必要だろう。この書は,哲学における論理と,数学の一領域となった記号論理学との,ほどよい橋渡しとなってくれるだろう。 -
推薦者 : 千葉 惠 (文学研究科)
鋭くバランスのよい人間洞察
アリストテレス『ニコマコス倫理学』 / アリストテレス (訳者朴一功). - 京都大学出版会 西洋古典叢書, 2002
 北大ではどこにある?
本書はその後のヨーロッパのひとびとの精神形成のうえで『聖書』とならんで大きな影響を与えた名著です。本書においては、幸福や徳そして抑制のなさなど人間の魂の諸様態が分析されますが、ここには個人的には誰をも拘束しないが、普遍的には万人を拘束するそのようなロゴスの普遍的な力があります。鋭い魂の動きの観察と同時に人間であること全体の広い視野のなかで、魂の分析が問いの美しさと鋭さのなかで遂行され、問いから答え、答えから問いの連鎖において思考が着実に前進し、人間本性の解明が力強くしかも繊細になされています。人類が持ちえた最良の頭脳がどれほど... [続きを読む]
北大ではどこにある?
本書はその後のヨーロッパのひとびとの精神形成のうえで『聖書』とならんで大きな影響を与えた名著です。本書においては、幸福や徳そして抑制のなさなど人間の魂の諸様態が分析されますが、ここには個人的には誰をも拘束しないが、普遍的には万人を拘束するそのようなロゴスの普遍的な力があります。鋭い魂の動きの観察と同時に人間であること全体の広い視野のなかで、魂の分析が問いの美しさと鋭さのなかで遂行され、問いから答え、答えから問いの連鎖において思考が着実に前進し、人間本性の解明が力強くしかも繊細になされています。人類が持ちえた最良の頭脳がどれほど... [続きを読む] -
推薦者 : 鍋島 孝子 (メディア・コミュニケーション研究院)
自分も虐殺に荷担してしまうかもしれない
イェルサレムのアイヒマン 悪の陳腐さについての報告 / ハンナ・アーレント. - みすず書房, 1969年
 北大ではどこにある?
アドルフ・オットー・アイヒマンはナチス・ドイツの元親衛隊中佐。強制収容所にユダヤ人を組織的、且つ大量に送り込みました。戦後、逃亡の末、捕らえられ、イスラエルで人道に反する罪に問われて裁判を受けました。
北大ではどこにある?
アドルフ・オットー・アイヒマンはナチス・ドイツの元親衛隊中佐。強制収容所にユダヤ人を組織的、且つ大量に送り込みました。戦後、逃亡の末、捕らえられ、イスラエルで人道に反する罪に問われて裁判を受けました。
著者ハンナ・アーレントはユダヤ系の思想家。アイヒマンの裁判を通じて、平凡な人が国家の命令に従い、いかに蛮行に至ったかを論じています。読者は個人のモラルとは、組織とは、国家の統制とは何かと考えさせられるでしょう。
皆さんは将来、御自分が所属する社会に押しつぶされそうになったとき、どうしますか。良心から反対できますか。それとも流... [続きを読む] -
推薦者 : 須田 勝彦 (教育学部)
知とは何か,という対話
形而上学(上) / アリストテレス[著] ,出隆訳. - 岩波文庫, 2006年
 北大ではどこにある?
BC.340年ころ,ギリシアで書かれたこの本が今も読まれている。哲学者でもなく,古典語を読めるわけでもない私は,当然日本語訳しか読めないが,この書がとても好きになった。今の私たちとまったく違った思惟様式において書かれたこの書が,それにもかかわらず,多くの対話が可能であることに驚かされる。
北大ではどこにある?
BC.340年ころ,ギリシアで書かれたこの本が今も読まれている。哲学者でもなく,古典語を読めるわけでもない私は,当然日本語訳しか読めないが,この書がとても好きになった。今の私たちとまったく違った思惟様式において書かれたこの書が,それにもかかわらず,多くの対話が可能であることに驚かされる。 -
推薦者 : 陳 省仁 (教育学研究科)
翻訳哲学書は何故読みにくいか
輸入学問の功罪 : この翻訳わかりますか? / 鈴木直. - 筑摩書房, 2007.1
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 羽部 朝男 (理学研究科)
デカルトはおもしろい
哲学原理 / デカルト著 ; 桂寿一訳. - 岩波書店, 1964.4
 北大ではどこにある?
デカルトは高校時代に哲学者として勉強したことがあると思う。哲学は難しいというイメージがある。まして、物理の先生が,哲学の本を薦めるのはなぜかといぶかしく思うかもしれない。デカルトは、座標を思いついた人で物理学と関係が深い。物理学ではxyz座標をデカルト座標と呼び座標が無くては,物理学の発展は無かったと言ってもいいだろう。この本を読んでみると、デカルトの合理的なものの考え方が当時の限られた自然科学の知識を使って、よく説明されており、わかりやすくとても面白い。ぜひ、読んでほしい。
北大ではどこにある?
デカルトは高校時代に哲学者として勉強したことがあると思う。哲学は難しいというイメージがある。まして、物理の先生が,哲学の本を薦めるのはなぜかといぶかしく思うかもしれない。デカルトは、座標を思いついた人で物理学と関係が深い。物理学ではxyz座標をデカルト座標と呼び座標が無くては,物理学の発展は無かったと言ってもいいだろう。この本を読んでみると、デカルトの合理的なものの考え方が当時の限られた自然科学の知識を使って、よく説明されており、わかりやすくとても面白い。ぜひ、読んでほしい。 -
推薦者 : 蔵田 伸雄 (文学研究科)
哲学とはどういうことか
ゴルギアス / プラトン著 ; 加来彰俊訳. - 岩波書店, 1967.6
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 佐藤 淳二 (文学研究科)
21世紀はドゥルーズの時代だ そしてもはや我々は21世紀に生きている
差異と反復 / ジル・ドゥルーズ〔著〕 ; 財津理訳. - 河出書房新社, 1992.11
 北大ではどこにある?
この時代を生きるのに欠かせない地図が何枚かある。
北大ではどこにある?
この時代を生きるのに欠かせない地図が何枚かある。
たとえばデリダの『エクリチュールと差異』やドゥルーズの『差異と反復』はそのような地図であり、またドゥルーズとガタリが組んだ『カフカ』『アンチ・オイディプス』『 -
推薦者 : 𢎭(弓巾/ゆはず) 和順 (文学研究科)
儒教の本質を考える上での好著
儒教とは何か / 加地伸行著. - 中央公論社, 1990.10
 北大ではどこにある?
中国・朝鮮半島・日本を含む東アジアの思想文化を考究するとき、回避することのできないテーマのひとつとして、孔子の思想、すなわち儒教が挙げられる。本書は、儒教の成立・展開、さらにはその日本への影響などを詳述することを通して、従来、倫理道徳と見なされてきた儒教について、その本質は死と密接に結びついた宗教であると主張する。その当否はともかく、儒教とは何か、また宗教とは何かを考える上で、刺戟的な一冊であることに間違いはない。
北大ではどこにある?
中国・朝鮮半島・日本を含む東アジアの思想文化を考究するとき、回避することのできないテーマのひとつとして、孔子の思想、すなわち儒教が挙げられる。本書は、儒教の成立・展開、さらにはその日本への影響などを詳述することを通して、従来、倫理道徳と見なされてきた儒教について、その本質は死と密接に結びついた宗教であると主張する。その当否はともかく、儒教とは何か、また宗教とは何かを考える上で、刺戟的な一冊であることに間違いはない。