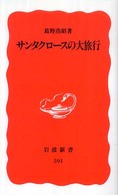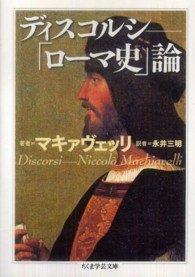-
推薦者 : 山口 良文 (低温科学研究所・教員)
今の時代にこそあらためて
夜と霧 / ヴィクトール・E・フランクル. - みすず書房, 2002
 北大ではどこにある?
ナチス・ドイツによる強制収容所生活を生き延びた精神科医フランクルによる、その体験と分析記録。ここで改めて紹介するまでもなく色々なところで紹介されている名著ですが、まだこちらのリストにはないようだったので挙げておきます。
北大ではどこにある?
ナチス・ドイツによる強制収容所生活を生き延びた精神科医フランクルによる、その体験と分析記録。ここで改めて紹介するまでもなく色々なところで紹介されている名著ですが、まだこちらのリストにはないようだったので挙げておきます。
生命の危機どころか生きる意欲をも見失うような極限状態に置かれたとき、人はどのように振る舞うのか。そして、そこをどう乗り越えるのか。この究極的な問に対する箴言の数々がのっています。
”「生きていることにもうなんにも期待がもてない」こんな言葉にたいして、いったいどう応えたらいいのだろう。
ここで必要なのは、生きる... [続きを読む] -
推薦者 : 朝倉 清高 (触媒科学研究所・教員)
理系も文系もとにかく一読する。
Homo Deus : A Brief History of Tomorrow / Yuval Noah Harari. - Vintage, 2017
 北大ではどこにある?
今、AI、深層学習といったことが話題になっている。それを単に便利な道具と考えているかもしれません。しかし、本書は農業革命、産業革命に匹敵する情報革命という社会の大革命としてとらえ、“人類”の置かれた立場を考えさせる本です。
北大ではどこにある?
今、AI、深層学習といったことが話題になっている。それを単に便利な道具と考えているかもしれません。しかし、本書は農業革命、産業革命に匹敵する情報革命という社会の大革命としてとらえ、“人類”の置かれた立場を考えさせる本です。
“Homo Sapiens will vanish”(p443) ということも言っています。皆さんが自分の未来を思い描くときに参考になると思います。
邦文もありますので、そちらで読まれるとよいかもしれません。
ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンスの未来 / ユヴァル・ノア・ハラリ著 ; 柴... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)
国際関係を複眼的に解きほぐす
大英帝国の親日派 : なぜ開戦は避けられなかったか / アントニー・ベスト著 ; 武田知己訳. - 中央公論新社, 2015
 北大ではどこにある?
国際関係、分けても戦時期の国際関係を理解することは容易ではない。この本は、日英の政治家(外交官)に対象を絞り、それぞれの言説と行動を分析しつつ第二次大戦期の日英関係を解明しようとするものである。その際、直接の対象である日英関係の背後にあって大きな影響を及ぼしていた日中、英中、英米、英露の国際関係にも目を配り、当時の国際関係が複眼的に理解できるようになっている点が特徴である。国際関係論や政治学のみならず、歴史記述の方法についても学ぶところの多い本である。
北大ではどこにある?
国際関係、分けても戦時期の国際関係を理解することは容易ではない。この本は、日英の政治家(外交官)に対象を絞り、それぞれの言説と行動を分析しつつ第二次大戦期の日英関係を解明しようとするものである。その際、直接の対象である日英関係の背後にあって大きな影響を及ぼしていた日中、英中、英米、英露の国際関係にも目を配り、当時の国際関係が複眼的に理解できるようになっている点が特徴である。国際関係論や政治学のみならず、歴史記述の方法についても学ぶところの多い本である。 -
推薦者 : 水本 秀明 (外国語教育センター・非常勤講師)
サンタクロースについてどれだけあなたは知っていますか?
サンタクロースの大旅行 / 葛野浩昭著. - 岩波書店, 1998
 北大ではどこにある?
サンタクロースはフィンランド語でjoulupukki、すなわち「クリスマス(joulu)」+「山羊(pukki)」。いったい「山羊」は何を表しているのでしょう?この本を読むと、とんがり帽子に赤い衣装で煙突からプレゼント配達に来る、といったサンタクロースの一般的なイメージが大きく覆されるはずです。好著!
北大ではどこにある?
サンタクロースはフィンランド語でjoulupukki、すなわち「クリスマス(joulu)」+「山羊(pukki)」。いったい「山羊」は何を表しているのでしょう?この本を読むと、とんがり帽子に赤い衣装で煙突からプレゼント配達に来る、といったサンタクロースの一般的なイメージが大きく覆されるはずです。好著! -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
わくわくするナイル源流への旅の記録
ナイルに沈む歴史-ヌビア人と古代遺跡- / 鈴木八司. - 岩波書店, 1970
 北大ではどこにある?
最近(特に今世紀になってから)、岩波新書(新赤版)がつまらなくなってきた。社会の流れが速くなるのに歩調を合わせすぎているのか、時事的なものが多くなり-それはそれで必要だと思うが-長く手元に置いて何度も繰り返して読みたくなるような内容のものが減っている気がする。ここに推薦する青版の『ナイルに沈む歴史』は、僕が中学生の時にでた本であるが、アスワン・ハイダムの建設によるアブ・シンベル神殿の水没を回避するための国際プロジェクトの一環として著者の鈴木氏が行ったエジプト・ナイル川上流地域の踏破記録である。それまでもハワード・カーターによる... [続きを読む]
北大ではどこにある?
最近(特に今世紀になってから)、岩波新書(新赤版)がつまらなくなってきた。社会の流れが速くなるのに歩調を合わせすぎているのか、時事的なものが多くなり-それはそれで必要だと思うが-長く手元に置いて何度も繰り返して読みたくなるような内容のものが減っている気がする。ここに推薦する青版の『ナイルに沈む歴史』は、僕が中学生の時にでた本であるが、アスワン・ハイダムの建設によるアブ・シンベル神殿の水没を回避するための国際プロジェクトの一環として著者の鈴木氏が行ったエジプト・ナイル川上流地域の踏破記録である。それまでもハワード・カーターによる... [続きを読む] -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
世界に働く根本的な力を考える
歴史の終わり(上・下) / フランシス・フクヤマ. - 三笠書房, 1992
 北大ではどこにある?
個人的に2015年はあまり面白い本にめぐり逢わなかった1年だった。その中では比較的面白かったのがこの本である。1992年に刊行されたこの本を20年以上経って読んでみると、著者が重視するリベラルな民主主義が現在の世界で置かれているアクチュアルな立場をよく見通すことができる。20年以上前に書かれた本ではあるが、そこに含まれる観点は20年そこそこの時間の経過の中では古びてしまうということはなく、今なお国際政治・国際関係を考える上で必要な知見を提供してくれると思う。
北大ではどこにある?
個人的に2015年はあまり面白い本にめぐり逢わなかった1年だった。その中では比較的面白かったのがこの本である。1992年に刊行されたこの本を20年以上経って読んでみると、著者が重視するリベラルな民主主義が現在の世界で置かれているアクチュアルな立場をよく見通すことができる。20年以上前に書かれた本ではあるが、そこに含まれる観点は20年そこそこの時間の経過の中では古びてしまうということはなく、今なお国際政治・国際関係を考える上で必要な知見を提供してくれると思う。 -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
留学する前に読んでおこう!
魯迅の日本 漱石のイギリスー「留学の世紀」を生きた人びとー / 柴崎信三. - 日本経済新聞社, 1999
 北大ではどこにある?
国を挙げての「留学」ばやりである。文部科学省もAKB48まで動員して「トビタテ!留学JAPAN」なるキャンペーンまでやっている。北大から海外協定大学に留学する学生も増えているようで結構なことである。(「留学」したことがない僕はちょっと僻んでこの推薦文を書いているのだが)かつては「留学」というのは決定的にエリートへの道筋であった。筆者はその時代に「留学」し(て苦労し)た代表者としての魯迅と漱石を軸にして、「留学」ということが日中それぞれの社会と個人にどのような意味を持ったかを浮かび上がらせようとしている。今と昔で意味合いは違うものの「留学」と... [続きを読む]
北大ではどこにある?
国を挙げての「留学」ばやりである。文部科学省もAKB48まで動員して「トビタテ!留学JAPAN」なるキャンペーンまでやっている。北大から海外協定大学に留学する学生も増えているようで結構なことである。(「留学」したことがない僕はちょっと僻んでこの推薦文を書いているのだが)かつては「留学」というのは決定的にエリートへの道筋であった。筆者はその時代に「留学」し(て苦労し)た代表者としての魯迅と漱石を軸にして、「留学」ということが日中それぞれの社会と個人にどのような意味を持ったかを浮かび上がらせようとしている。今と昔で意味合いは違うものの「留学」と... [続きを読む] -
推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)
Succinctly describes a global horror
The Second World War / Antony Beevor. - Little, Brown and Company, 2012
 北大ではどこにある?
Japan war memory is dying (at least the people with hands-on experience with warfare are), and nothing is taught (shameful that Japan cannot confront itself, compared to Germany for instance). This book should shed some light on what happened during those painful years. The book is long but so was the war. Considering the deadliness of it all, the book treats everything swiftly.
北大ではどこにある?
Japan war memory is dying (at least the people with hands-on experience with warfare are), and nothing is taught (shameful that Japan cannot confront itself, compared to Germany for instance). This book should shed some light on what happened during those painful years. The book is long but so was the war. Considering the deadliness of it all, the book treats everything swiftly. -
推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)
もう一つの「ローマ人の物語」
ディスコルシ-「ローマ史」論- / マキアヴェッリ. - 筑摩書房, 2011
 北大ではどこにある?
「ローマ人の物語」といえば塩野七生さんの著作があまりにも有名であるが、この『ディスコルシ』はマキアヴェッリによるもう一つのローマ史である。マキアヴェッリは、この本を書く時に間違いなく彼が生きていた時代のイタリアの運命を考えながら-その姿勢は『君主論』にもつながる-筆を走らせていた。歴史から何事かを学ぶ、ということがどのようなものか、この本から浮かび上がってくるだろう。
北大ではどこにある?
「ローマ人の物語」といえば塩野七生さんの著作があまりにも有名であるが、この『ディスコルシ』はマキアヴェッリによるもう一つのローマ史である。マキアヴェッリは、この本を書く時に間違いなく彼が生きていた時代のイタリアの運命を考えながら-その姿勢は『君主論』にもつながる-筆を走らせていた。歴史から何事かを学ぶ、ということがどのようなものか、この本から浮かび上がってくるだろう。 -
推薦者 : 筑和 正格 (メディア・コミュニケーション研究院)
歴史の決定的転換点を追体験する!
世界に衝撃を与えた日 全30巻 (DVD) / BBC Active. - キュービカル・エンタテインメント (発売), 2006
 北大ではどこにある?
貴重な映像資料が閲覧できるようになった。
北大ではどこにある?
貴重な映像資料が閲覧できるようになった。
イギリスBBC作成の30巻に及ぶドキュメンタリー映像は、私たちに歴史の決定的転換点を追体験させてくれる。
「世界に衝撃を与える事件」は、歴史が、また時代・社会が内包する矛盾が、何らかの形で顕在化したものだと捉えることができる。
したがって、私たちは、映像がもつ迫力をまず受け止めながら、その矛盾と矛盾を通じて伝えられる時代像・社会像について考えるという喜びを経験できるのである。
学生諸君には、是非一度閲覧していただきたいものである。 -
推薦者 : 鍋島 孝子 (メディア・コミュニケーション研究院)
人種差別の狂気と現実
ビーコウ、アパルトヘイトとの限りなき戦い / ドナルド・ウッズ. - 岩波書店, 1990年
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 高井 哲彦 (経済学研究科)
国境・領域を超越するユニークな世界交易史
ナマコの眼 / 鶴見良行著. - 筑摩書房, 1990
 北大ではどこにある?
表題だけを見て、近頃流行の食べ物や生き物に関するエッセイだと勘違いすると、良い意味で大きく裏切られるはずだ。この本は、ちっぽけな食材(ナマコ)を切り口にしながら実は、アジア太平洋に生きる人間と交易の世界史を論じる、本格派の社会科学書だからだ。
北大ではどこにある?
表題だけを見て、近頃流行の食べ物や生き物に関するエッセイだと勘違いすると、良い意味で大きく裏切られるはずだ。この本は、ちっぽけな食材(ナマコ)を切り口にしながら実は、アジア太平洋に生きる人間と交易の世界史を論じる、本格派の社会科学書だからだ。
国境・領域を越えて縦横無尽に駆け巡る構成の壮大さと、モノを軸に万物を網羅しようと試みる実証の緻密さは圧巻だ。この手法は、鶴見良行『カツオとかつお節の同時代史』(コモンズ)にも共通する。
しかも鶴見は、「歩きながら考える」現場主... [続きを読む]登録日 : 2006-04-20
-
推薦者 : 池田 清治 (法学研究科)
西欧文明の源流をたどる
十二世紀ルネサンス : 西欧世界へのアラビア文明の影響 / 伊東俊太郎著. - 岩波書店, 1993.1
 北大ではどこにある?
西欧文明が事実上グローバル・スタンダードとして作用しつつある今日において、その相対化を図る意味からも、西欧文明の由来を探る作業は重要である。それはギリシャ文明に直線的にさかのぼるとイメージされがちだが、実際にはギリシャ文明はまずアラビア世界に伝えられ、そこからヨーロッパ世界にもたらされたものであること、そのため、西欧社会が実際にはアラビア文明に多くを負っていることを本書は教えてくれる。ここから導かれうる示唆は決して一様ではない。しかし、西欧文明に単純に反発するわけでもなく、洗脳されるわけでもないという透徹した態度が可能となろ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
西欧文明が事実上グローバル・スタンダードとして作用しつつある今日において、その相対化を図る意味からも、西欧文明の由来を探る作業は重要である。それはギリシャ文明に直線的にさかのぼるとイメージされがちだが、実際にはギリシャ文明はまずアラビア世界に伝えられ、そこからヨーロッパ世界にもたらされたものであること、そのため、西欧社会が実際にはアラビア文明に多くを負っていることを本書は教えてくれる。ここから導かれうる示唆は決して一様ではない。しかし、西欧文明に単純に反発するわけでもなく、洗脳されるわけでもないという透徹した態度が可能となろ... [続きを読む]