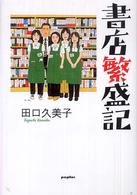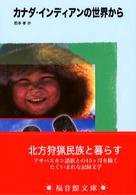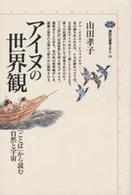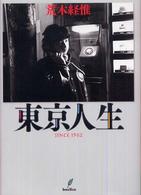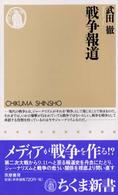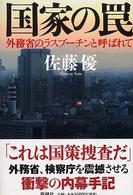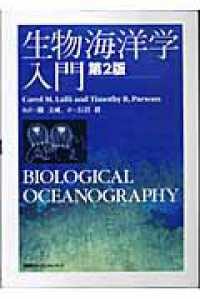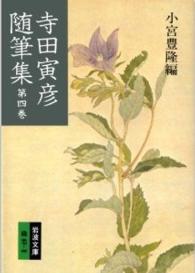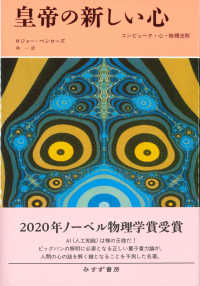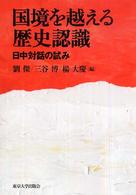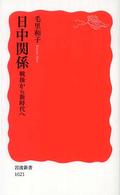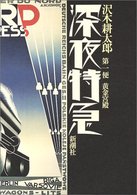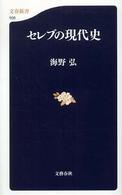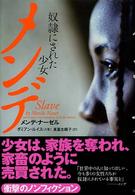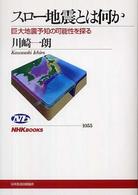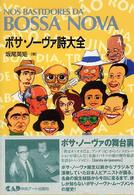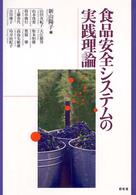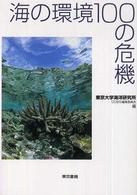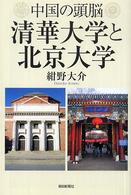-
推薦者 : 羽部 朝男 (理学研究科)
宇宙について知ろう
宇宙 起源をめぐる140億年の旅 / ニール・ドグラース・タイソン, ドナルド・ゴールドスミス著 ; 水谷淳訳. - 早川書房, 2005
 北大ではどこにある?
最近,宇宙についての理解が大いに進んだ。にもかかわらず、高校で宇宙のことを勉強する機会がほとんどないのが現状だろう。NHKで時々取り上げられるが,系統的な解説を行なうには番組の時間が短すぎるため、尻切れとんぼの感が否めない。この本は、最近の宇宙の研究がどこまで進んでいるのかを分かりやすく書いてある。しかも,著者は宇宙の観測による一流の研究者であるので、観測事実に即しながら話しを展開してるので分かりやすい。宇宙の科学に興味ある方はぜひ読んでほしい。
北大ではどこにある?
最近,宇宙についての理解が大いに進んだ。にもかかわらず、高校で宇宙のことを勉強する機会がほとんどないのが現状だろう。NHKで時々取り上げられるが,系統的な解説を行なうには番組の時間が短すぎるため、尻切れとんぼの感が否めない。この本は、最近の宇宙の研究がどこまで進んでいるのかを分かりやすく書いてある。しかも,著者は宇宙の観測による一流の研究者であるので、観測事実に即しながら話しを展開してるので分かりやすい。宇宙の科学に興味ある方はぜひ読んでほしい。 -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
本屋は好きですか
書店繁盛記 / 田口久美子. - ポプラ社, 2006
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
知らない歴史もある
ひめゆり忠臣蔵 増補新版 / 吉田司. - 太田出版, 2000
 北大ではどこにある?
沖縄の「ひめゆり部隊」は知られている。しかし沖縄戦は沖縄の悲劇であり、沖縄の人々は軍国主義日本の被害者とだけ言って良いのだろうか。戦後占領し統治したアメリカに対して、復帰運動の中心になった教職員組合は戦前戦中はなにをしたのか(戦後アメリカの援助でアメリカ留学した人もいる)。そしてひめゆりはただ犠牲になった無辜の乙女たちだったのか。著者は人が隠し見たくないこと、忘れてしまいたいことを暴き出す。その主張に賛成できなくとも、歴史は一方からだけでなく、複眼で見なければならないことを痛感させられる。広島、長崎の原爆もなぜそこが選ばれたの... [続きを読む]
北大ではどこにある?
沖縄の「ひめゆり部隊」は知られている。しかし沖縄戦は沖縄の悲劇であり、沖縄の人々は軍国主義日本の被害者とだけ言って良いのだろうか。戦後占領し統治したアメリカに対して、復帰運動の中心になった教職員組合は戦前戦中はなにをしたのか(戦後アメリカの援助でアメリカ留学した人もいる)。そしてひめゆりはただ犠牲になった無辜の乙女たちだったのか。著者は人が隠し見たくないこと、忘れてしまいたいことを暴き出す。その主張に賛成できなくとも、歴史は一方からだけでなく、複眼で見なければならないことを痛感させられる。広島、長崎の原爆もなぜそこが選ばれたの... [続きを読む] -
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
変容著しい東北アジアの文化と言語の現在を読み解く!
東北アジア諸民族の文化動態 / 煎本孝編著. - 北海道大学図書刊行会, 2002.2
 北大ではどこにある?
日本、ロシア、中国、モンゴルを含む東北アジアには、広大で多様な環境が展開している。それは、民族学(文化人類学)的には北アジア、中央アジア、東アジアを含む地域である。生態的にも、地理的にもけっして閉鎖的な地域ではないこの多様な環境に生活する人々は、さまざまな文化と言語とをもっている。本書では東北アジアの文化と言語の動態を多角的に比較検討し、東北アジアの現在について考察する。
北大ではどこにある?
日本、ロシア、中国、モンゴルを含む東北アジアには、広大で多様な環境が展開している。それは、民族学(文化人類学)的には北アジア、中央アジア、東アジアを含む地域である。生態的にも、地理的にもけっして閉鎖的な地域ではないこの多様な環境に生活する人々は、さまざまな文化と言語とをもっている。本書では東北アジアの文化と言語の動態を多角的に比較検討し、東北アジアの現在について考察する。 -
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
空想すくすく、ノンフィクション文庫版
カナダ・インディアンの世界から / 煎本孝. - 福音館書店, 2002.11
 北大ではどこにある?
トナカイを求めて、凍てつく雪原を来る日も来る日も犬橇を走らせるカナダ・インディアンの男たち。「トナカイは人が飢えている時、その肉を与えに自分からやってくるものだ」と彼らは言う。本書は、その魂に、“自然”の力を宿し、季節と共にその内なる力を育みつつ生きてゆく人びとの、たぐいまれなる記録である。丹念な取材に裏付けされた事実に基づく自然誌、成熟した読者にも読み応えのある作品。
北大ではどこにある?
トナカイを求めて、凍てつく雪原を来る日も来る日も犬橇を走らせるカナダ・インディアンの男たち。「トナカイは人が飢えている時、その肉を与えに自分からやってくるものだ」と彼らは言う。本書は、その魂に、“自然”の力を宿し、季節と共にその内なる力を育みつつ生きてゆく人びとの、たぐいまれなる記録である。丹念な取材に裏付けされた事実に基づく自然誌、成熟した読者にも読み応えのある作品。 -
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
アイヌの世界観を知ろう
アイヌの世界観 : 「ことば」から読む自然と宇宙 / 山田孝子. - 講談社, 1994.8
 北大ではどこにある?
クマ・オオカミ・シマフクロウ・・・・・。魚の満ちあふれる川、シカが群れつどう山。大自然をアイヌはカムイ(神)としてとらえる。彼らの信仰はいかにして形成されたのか?「ことば」が「生活世界」を切り取るプロセス。秘密はそこにある。北の民の世界観がいま、認識人類学の立場から鮮やかに解明される。
北大ではどこにある?
クマ・オオカミ・シマフクロウ・・・・・。魚の満ちあふれる川、シカが群れつどう山。大自然をアイヌはカムイ(神)としてとらえる。彼らの信仰はいかにして形成されたのか?「ことば」が「生活世界」を切り取るプロセス。秘密はそこにある。北の民の世界観がいま、認識人類学の立場から鮮やかに解明される。
本書の内容
・プロローグ
・アイヌの宇宙観
・霊魂とカムイ
・アイヌの植物命名法
・動物の分類と動物観
・諸民族との比較
・世界観の探求−認識人類学的アプローチ -
推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)
自然とは?文化とは?人類学とは?
文化の自然誌 / 煎本孝. - 東京大学出版会, 1996.6
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 陳 省仁 (教育学研究科)
翻訳哲学書は何故読みにくいか
輸入学問の功罪 : この翻訳わかりますか? / 鈴木直. - 筑摩書房, 2007.1
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
教育学部以外の学生諸君もぜひ
子どもが見ている背中 : 良心と抵抗の教育 / 野田正彰. - 岩波書店, 2006
 北大ではどこにある?
北大医学部出身の精神医学者が、教育、特に国旗・国歌の強制から教育基本法の改定にいたる動きを論じた本。広島県の二人の校長が自殺に追い込まれ、それを利用して国旗国歌法が制定されたこと(自殺は一方的に反対した教師たちのせいではない事実)、教育現場への締め付けを告発している。この問題に関する著者の主張に賛成、反対は別にして、いろいろな事実や背景を知った上で自分の意見を決めねば、指導者の言うことやメディアの論調に流されてしまう。それは広告と同じで、イメージ戦略にのってしまうことである。同じ問題を扱った旧著
北大ではどこにある?
北大医学部出身の精神医学者が、教育、特に国旗・国歌の強制から教育基本法の改定にいたる動きを論じた本。広島県の二人の校長が自殺に追い込まれ、それを利用して国旗国歌法が制定されたこと(自殺は一方的に反対した教師たちのせいではない事実)、教育現場への締め付けを告発している。この問題に関する著者の主張に賛成、反対は別にして、いろいろな事実や背景を知った上で自分の意見を決めねば、指導者の言うことやメディアの論調に流されてしまう。それは広告と同じで、イメージ戦略にのってしまうことである。同じ問題を扱った旧著 -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
アラーキーを理解する
東京人生 since 1962 / 荒木経惟. - バジリコ株式会社, 2006
 北大ではどこにある?
写真家荒木経惟が彼の大量の著作と作品から自ら選んだ写真を集め、自らコメントをつけた本。写真集を一冊見ても写真家は分らない。有名な彼のヌード写真も作品の一部(大きなテーマだが)にすぎない。荒木の写真の恰好の入門書。
北大ではどこにある?
写真家荒木経惟が彼の大量の著作と作品から自ら選んだ写真を集め、自らコメントをつけた本。写真集を一冊見ても写真家は分らない。有名な彼のヌード写真も作品の一部(大きなテーマだが)にすぎない。荒木の写真の恰好の入門書。 -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
憲法は、政府に対する命令である。
憲法は、政府に対する命令である。 / ダグラス・ラミス. - 平凡社, 2006
 北大ではどこにある?
キャンベラにマグナカルタプレイスという小さな緑地があります。碑文によるとオーストラリア建国(1901年)はこのマグナカルタ(1225年)を礎としているということだったと思います。もっともあとで調べてみるとその国の憲法にはそんな一文はなく、建国の手続きばかりのようでした(総督の給与をいくらにするとか)。英国から移民したひとたちにとってマグナカルタの占める位置は当然のことだったのでしょうか。
北大ではどこにある?
キャンベラにマグナカルタプレイスという小さな緑地があります。碑文によるとオーストラリア建国(1901年)はこのマグナカルタ(1225年)を礎としているということだったと思います。もっともあとで調べてみるとその国の憲法にはそんな一文はなく、建国の手続きばかりのようでした(総督の給与をいくらにするとか)。英国から移民したひとたちにとってマグナカルタの占める位置は当然のことだったのでしょうか。
残念ながらこの国は法というほどのものを生み出しませんでした。有史以来(?)天皇家がこの国を統治しているということに非常な価値を見出している人... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
宗教と科学
The God Delusion / Richard Dawkins. - Bantam Press, 2006
 北大ではどこにある?
ドーキンス氏はこの書において、神が存在しないことがその存在することよりも圧倒的に確からしいことを、進化論的観点から示します。(ただし、ここでいう神とは、万物を創造し人間に賞罰を与える超自然的存在のことで、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の神が想定されています。)しかし、有史以来、人類は宗教とともに歩んできたようです。宗教を信奉するひとが無宗教のひととの相克に勝ち抜き、自然淘汰の試練を潜り抜けてきたからには、少なくとも宗教に存在価値があるからではないかという疑問が起こります。著者は、それが危険に満ちた環境での人類の生存に適した心... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ドーキンス氏はこの書において、神が存在しないことがその存在することよりも圧倒的に確からしいことを、進化論的観点から示します。(ただし、ここでいう神とは、万物を創造し人間に賞罰を与える超自然的存在のことで、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の神が想定されています。)しかし、有史以来、人類は宗教とともに歩んできたようです。宗教を信奉するひとが無宗教のひととの相克に勝ち抜き、自然淘汰の試練を潜り抜けてきたからには、少なくとも宗教に存在価値があるからではないかという疑問が起こります。著者は、それが危険に満ちた環境での人類の生存に適した心... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
占領下日本と憲法
敗北を抱きしめて(上下) / ジョン・ダワー. - 岩波書店, 2001,2004
 北大ではどこにある?
この国の憲法を「押し付けられたものだから」(を理由のひとつとして)改正しようとする動きがあります。近隣諸国との諍いをも厭わず戦死者の霊を慰めることに熱心な人たちですから、敗戦後の生活の塗炭の苦しみに加えて意に染まぬ憲法を押し付けられるという精神的苦痛を味わった当時の庶民への同情に突き動かされて発議したのかと思っていましたら、そうでもなさそうです。いかに歴史を学ばないひとでも、当時の人々のほとんどが解放感に包まれてこれを歓迎したことは知っているでしょう。それとも、その始祖たる時の首相吉田茂が天皇裕仁のまえで「臣茂」と名乗ること... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この国の憲法を「押し付けられたものだから」(を理由のひとつとして)改正しようとする動きがあります。近隣諸国との諍いをも厭わず戦死者の霊を慰めることに熱心な人たちですから、敗戦後の生活の塗炭の苦しみに加えて意に染まぬ憲法を押し付けられるという精神的苦痛を味わった当時の庶民への同情に突き動かされて発議したのかと思っていましたら、そうでもなさそうです。いかに歴史を学ばないひとでも、当時の人々のほとんどが解放感に包まれてこれを歓迎したことは知っているでしょう。それとも、その始祖たる時の首相吉田茂が天皇裕仁のまえで「臣茂」と名乗ること... [続きを読む] -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
メディアとは 2
戦争報道 / 武田徹. - ちくま新書, 2003
 北大ではどこにある?
ジャーナリズムは戦争の悲惨さを伝える一方、9.11以後のアメリカのように戦争を煽る愛国報道になる。第二次世界大戦からアフガン戦争まで戦争と報道の問題を論じる。そして戦時においては中立の報道どころか広告(プロパガンダ)に加担する姿を示す。これで基礎知識を得てから、他の戦争とメディア論に進むと良いと思う。
北大ではどこにある?
ジャーナリズムは戦争の悲惨さを伝える一方、9.11以後のアメリカのように戦争を煽る愛国報道になる。第二次世界大戦からアフガン戦争まで戦争と報道の問題を論じる。そして戦時においては中立の報道どころか広告(プロパガンダ)に加担する姿を示す。これで基礎知識を得てから、他の戦争とメディア論に進むと良いと思う。 -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
メディアとは 1
国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて / 佐藤優. - 新潮社, 2005
 北大ではどこにある?
あなたは鈴木宗男議員を知っているだろうか。マスメディアでは汚い政治家の代表とされ、北方領土関係などで癒着を指弾され、疑惑の総合商社と言われ、逮捕・起訴された政治家である。彼と共に歩み、外務省を毒したとされた外交官が著者である。彼も逮捕・起訴された。私たちはそのようなイメージを自明のものと受け取ってきた。しかし彼らの言い分をちゃんと聞いたことがあったろうか。この本を読むと政治の裏の複雑さと権力抗争のすざまじさを知ることができる。国益を巡る立場の違いを知ると、一面的に著者を弾劾することはためらわれる。鈴木議員に関しても同じである... [続きを読む]
北大ではどこにある?
あなたは鈴木宗男議員を知っているだろうか。マスメディアでは汚い政治家の代表とされ、北方領土関係などで癒着を指弾され、疑惑の総合商社と言われ、逮捕・起訴された政治家である。彼と共に歩み、外務省を毒したとされた外交官が著者である。彼も逮捕・起訴された。私たちはそのようなイメージを自明のものと受け取ってきた。しかし彼らの言い分をちゃんと聞いたことがあったろうか。この本を読むと政治の裏の複雑さと権力抗争のすざまじさを知ることができる。国益を巡る立場の違いを知ると、一面的に著者を弾劾することはためらわれる。鈴木議員に関しても同じである... [続きを読む] -
推薦者 : 蓬田 清 (理学研究科)
プレートテクトニクスの基礎
続 プレートテクトニクスの基礎 / 瀬野 徹三. - 朝倉書店 , 2001
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 岸 道郎 (水産学研究科)
海洋生物学の座右の名著
生物海洋学入門 第2版 / Carol M. Lalli and Timothy R. Parsons. - 講談社, 2005
 北大ではどこにある?
海洋生物の研究をしている人なら誰でも持っている名著である。海洋物理学的な背景から始まって、バクテリアから魚類までのピラミッド構造を非常にていねいに記述している。大学1年生から院生まで、広く読まれている本である。著者のLalliさんとParsonsさん夫妻はカナダの偉大な海洋学者である。親日家としても知られている。特にParsonsさんは日本人の弟子も多く、日本の海洋生物学の発展に果たした役割も大きい。「2001年日本国際賞」の受賞者でもある。
北大ではどこにある?
海洋生物の研究をしている人なら誰でも持っている名著である。海洋物理学的な背景から始まって、バクテリアから魚類までのピラミッド構造を非常にていねいに記述している。大学1年生から院生まで、広く読まれている本である。著者のLalliさんとParsonsさん夫妻はカナダの偉大な海洋学者である。親日家としても知られている。特にParsonsさんは日本人の弟子も多く、日本の海洋生物学の発展に果たした役割も大きい。「2001年日本国際賞」の受賞者でもある。 -
推薦者 : 奥 聡 (メディア・コミュニケーション研究院)
いつ読み返しても新鮮
寺田寅彦随筆集第4巻 / 寺田寅彦. - 岩波文庫,
 北大ではどこにある?
60年も前に書かれた寅彦のエッセイ集だが、内容は少しも古くない。科学と文学・芸術を縦横に行き来した自由な心を覗いてみて欲しい。「専門バカ」や効率主義一辺倒の今の大学や社会へのアンチテーゼも読み取れる。特に、研究者を目指したいが自分の能力に不安を感じている人は「科学者とあたま」がお勧め。
北大ではどこにある?
60年も前に書かれた寅彦のエッセイ集だが、内容は少しも古くない。科学と文学・芸術を縦横に行き来した自由な心を覗いてみて欲しい。「専門バカ」や効率主義一辺倒の今の大学や社会へのアンチテーゼも読み取れる。特に、研究者を目指したいが自分の能力に不安を感じている人は「科学者とあたま」がお勧め。 -
推薦者 : 行木 孝夫 (理学研究科)
微積分学の基本図書
解析概論 / 高木貞治. - 岩波書店, 1983
 北大ではどこにある?
近年は教育におけるわかりやすさを優先する傾向が強く、歴史的な教科書はその存在も知られないことが多くなっているように思われます。本書は自然科学の基礎を成す微積分学を記述した随一の書です。導入部では数学の学習における心構えを説き、実数の定義をはじめとする微積分学を網羅します。読みきることができなくても十分に数学の基礎を感じとれるでしょう。
北大ではどこにある?
近年は教育におけるわかりやすさを優先する傾向が強く、歴史的な教科書はその存在も知られないことが多くなっているように思われます。本書は自然科学の基礎を成す微積分学を記述した随一の書です。導入部では数学の学習における心構えを説き、実数の定義をはじめとする微積分学を網羅します。読みきることができなくても十分に数学の基礎を感じとれるでしょう。 -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
科学を志すとは
皇帝の新しい心 : コンピュータ・心・物理法則 / ロジャー・ペンローズ. - みすず書房, 1994
 北大ではどこにある?
科学を探究するとはこういうことかと思わせる書物です。つまり、科学の本来目的とするところは、人間とその周りに広がる世界に対する理解を深めることであるはずです。著者はきっと若いときからその科学の目的を見据えて学者としての道を歩んで来たのでしょう。なぜなら、自分の足跡をまとめるだけで、科学の発展とそれに伴う哲学上の変遷を読者に提示することができて、多分現代におけるもっとも困難な問題、心の問題に取り組めるというのですから。(具体的には、論理学、計算理論、量子論、宇宙論などを扱ったうえで、脳と意識を論じています。)
北大ではどこにある?
科学を探究するとはこういうことかと思わせる書物です。つまり、科学の本来目的とするところは、人間とその周りに広がる世界に対する理解を深めることであるはずです。著者はきっと若いときからその科学の目的を見据えて学者としての道を歩んで来たのでしょう。なぜなら、自分の足跡をまとめるだけで、科学の発展とそれに伴う哲学上の変遷を読者に提示することができて、多分現代におけるもっとも困難な問題、心の問題に取り組めるというのですから。(具体的には、論理学、計算理論、量子論、宇宙論などを扱ったうえで、脳と意識を論じています。)
ペンローズ氏は高名な... [続きを読む] -
推薦者 : 川島 真 (公共政策大学院)
東アジアの歴史認識問題と対処案を知る一書
国境を越える歴史認識 / 三谷博・劉傑・楊大慶編著. - 東京大学出版会, 2006年
 北大ではどこにある?
東アジアの歴史認識問題が大きな課題となっていますが、情緒的に結論を出すのではなく、なぜこれほどまでに歴史認識が異なるのか、そして具体的にどのように異なるのか、さらにではどうしていくべきなのか、ということについて記された一書。
北大ではどこにある?
東アジアの歴史認識問題が大きな課題となっていますが、情緒的に結論を出すのではなく、なぜこれほどまでに歴史認識が異なるのか、そして具体的にどのように異なるのか、さらにではどうしていくべきなのか、ということについて記された一書。 -
推薦者 : 川島 真 (公共政策大学院)
戦後の日中関係を知る基本書
日中関係 : 戦後から新時代へ / 毛里和子. - 岩波書店(岩波新書), 2006
 北大ではどこにある?
日中関係は、ますます難しい段階に入ってきました。しかし一方で、経済文化交流はきわめて盛んになり、学生諸君が将来にわたって中国と無関係でいるということは、ほとんどなくなってきています。日本と中国のかかわりの経緯と現状、そして将来についてコンパクトに知ることができる一書です。
北大ではどこにある?
日中関係は、ますます難しい段階に入ってきました。しかし一方で、経済文化交流はきわめて盛んになり、学生諸君が将来にわたって中国と無関係でいるということは、ほとんどなくなってきています。日本と中国のかかわりの経緯と現状、そして将来についてコンパクトに知ることができる一書です。 -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
歴史を通じて現在をみる
憲法で読むアメリカ史(上下) / 阿川尚之. - PHP研究所, 2004
 北大ではどこにある?
アメリカは歴史の浅い国というひとがいますが、それは果たして真実でしょうか。アメリカは13の州が連合して1776年に独立し、今に有効な憲法を1788年に制定しました。(世界で現に通用している憲法のなかで最古だそうです。)日本でいえば江戸時代半ばに制定された法律が本質的な変更なく今も、民主主義とその制度を宣言する文書として機能し模範とされていることを想像してみてください。江戸幕府はせいぜい幾つかの「諸法度」のもとで成立していたのです。もちろん、この憲法にも「瑕瑾」がありました。奴隷制度を容認しているととれる条項があることです(しか... [続きを読む]
北大ではどこにある?
アメリカは歴史の浅い国というひとがいますが、それは果たして真実でしょうか。アメリカは13の州が連合して1776年に独立し、今に有効な憲法を1788年に制定しました。(世界で現に通用している憲法のなかで最古だそうです。)日本でいえば江戸時代半ばに制定された法律が本質的な変更なく今も、民主主義とその制度を宣言する文書として機能し模範とされていることを想像してみてください。江戸幕府はせいぜい幾つかの「諸法度」のもとで成立していたのです。もちろん、この憲法にも「瑕瑾」がありました。奴隷制度を容認しているととれる条項があることです(しか... [続きを読む] -
推薦者 : 高井 哲彦 (経済学研究科)
世界を目指すグローバルな若者のバイブル
深夜特急 / 沢木耕太郎. - 新潮社, 1986-1992
 北大ではどこにある?
著者はある日突然、乗り合いバスによる貧乏旅行を思いつく。香港・マカオ、マレー半島・シンガポール、インド・ネパール、そしてシルクロードを経て、トルコ・ギリシャ・地中海、最後に南ヨーロッパ・ロンドン。その旅程は著者自身の成長過程でもあり、とくに異文化と出会う前半部は新鮮だ。
北大ではどこにある?
著者はある日突然、乗り合いバスによる貧乏旅行を思いつく。香港・マカオ、マレー半島・シンガポール、インド・ネパール、そしてシルクロードを経て、トルコ・ギリシャ・地中海、最後に南ヨーロッパ・ロンドン。その旅程は著者自身の成長過程でもあり、とくに異文化と出会う前半部は新鮮だ。
21歳のぼくがはじめてインドを訪れたのも、突然だった。ロンドン滞在から帰国する際に思い立って、インド経由に変更したのだった。ヴァラナシ=コルコタ間の夜行2等席では、トイレに往復する人が肩の上を踏んで歩くほど鮨詰めの満員立席で、ショックの余り言葉が話せなくなった。ラン... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
文明の将来を考える書
American Theocracy / Kevin Phillips. - Viking, 2006
 北大ではどこにある?
Theocracyは神権政治と訳します。これは、アメリカがむかし神権政治の国であったというのでもなく、将来そうなるという警世の書でもなく、現に(ブッシュ政権が)神権政治に陥ったことに対する慷慨の書なのです。
北大ではどこにある?
Theocracyは神権政治と訳します。これは、アメリカがむかし神権政治の国であったというのでもなく、将来そうなるという警世の書でもなく、現に(ブッシュ政権が)神権政治に陥ったことに対する慷慨の書なのです。
キリスト教国では「神のお恵みを」とか、イスラム教国では「アッラーの神に」とかを、政治家も民衆に使っているようです(もっとも実際にはわたしは聞いたことがないのですが)。わたしはこれを言葉の綾と思って注意を払ってきませんでした。これは「心の問題」であって、人それぞれに解釈すればいいことでしょう。このことが心の問題として済ませられなくなるの... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
歴史を通じて世界経済を考える書
超帝国主義アメリカの内幕 / マイケル・ハドソン. - 徳間書店, 2002
 北大ではどこにある?
もし書店の棚にこういう題名の本を見かけたとしても、今、どれほどの人が手にとって見る気を起こすものなのか、想像がつきかねます。しかし、私の若いころは(1960年代)、若者がよく「アメリカ帝国主義反対」などと金切り声をあげていました。その当時とそれより暫くのあいだは、私のような政治的に鈍感なひとにとっても、世界というものを理解するうえで、これが喉につかえた小骨のようなものであったかもしれません。少なくとも、亜米利加追従我国安泰と割り切れるひとはほとんどいなかったのではないか、と思います。
北大ではどこにある?
もし書店の棚にこういう題名の本を見かけたとしても、今、どれほどの人が手にとって見る気を起こすものなのか、想像がつきかねます。しかし、私の若いころは(1960年代)、若者がよく「アメリカ帝国主義反対」などと金切り声をあげていました。その当時とそれより暫くのあいだは、私のような政治的に鈍感なひとにとっても、世界というものを理解するうえで、これが喉につかえた小骨のようなものであったかもしれません。少なくとも、亜米利加追従我国安泰と割り切れるひとはほとんどいなかったのではないか、と思います。
日本語の題名には辟易するひともあろうかと思い... [続きを読む] -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
人気の秘密
セレブの現代史 / 海野弘. - 文春新書,
 北大ではどこにある?
どうして有名人は影響力があるのか。教養の感じられない政治家がもてはやされるのか、この疑問の一つの答である。不倫のプリンセス、ワンフレーズの権力者、XX姉妹(XXには適当な文字を、解答複数)、なぜ彼らに人気があるのか。しかし少し怖い状況である。明日の世界はどうなる?
北大ではどこにある?
どうして有名人は影響力があるのか。教養の感じられない政治家がもてはやされるのか、この疑問の一つの答である。不倫のプリンセス、ワンフレーズの権力者、XX姉妹(XXには適当な文字を、解答複数)、なぜ彼らに人気があるのか。しかし少し怖い状況である。明日の世界はどうなる? -
推薦者 : 池田 清治 (法学研究科)
原始キリスト教の多様性を探る
禁じられた福音書 : ナグ・ハマディ文書の解明 / エレーヌ・ペイゲルス(松田和也訳). - 青土社, 2005.3
 北大ではどこにある?
昨今『捏造された聖書』(柏書房、2006年)など)、西洋思想の源流を辿りたい方には是非とも一読を薦めたい。
北大ではどこにある?
昨今『捏造された聖書』(柏書房、2006年)など)、西洋思想の源流を辿りたい方には是非とも一読を薦めたい。 -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
知らないことはいくらでもある
メンデ奴隷にされた少女 / メンデ・ナゼール. - ソニーマガジンズ, 2004
 北大ではどこにある?
今の世界にも奴隷は存在する。しかも政府の黙認において。スーダンで家族から拉致された子供たちは売られている。その地域はまさに伝説のマサイ族の地域だ。私たちは何事も知ったつもりになってはいけない。短いワンフレーズのコメントに棹差せば流される。
北大ではどこにある?
今の世界にも奴隷は存在する。しかも政府の黙認において。スーダンで家族から拉致された子供たちは売られている。その地域はまさに伝説のマサイ族の地域だ。私たちは何事も知ったつもりになってはいけない。短いワンフレーズのコメントに棹差せば流される。 -
推薦者 : 日置 幸介 (理学研究科)
地震が足りない?消えたエネルギーはどこへ行ってしまうのか‥
スロー地震とは何か: 巨大地震予知の可能性を探る / 川崎一朗. - 日本放送出版協会, 2006年
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
南米文化を知ろう
ボサ・ノーヴァ詩大全 / 坂尾英矩. - 中央アート出版, 2006
 北大ではどこにある?
音楽が好きな人、特にポップスが好きな人はボサノバ(旧来表記)を知っているだろう。「イパネマの娘」や「おいしい水」ぐらいは。しかしボサノバだけでなくフォークローレやその他の音楽もある。アルゼンチンタンゴもある。中南米は音楽の宝庫だ。また格闘技の好きな人はブラジルのカポエラやブラジリアン柔術も知っているはずだ。しかしカポエラが手を鎖で縛られた奴隷の護身術から発生したことは知っているだろうか(だから足技です)。文化を学ぶとはこういうことなのです。ジェローム・レ・バンナはフランス読みするとジェローム・ル・バネールです。これは日本にお... [続きを読む]
北大ではどこにある?
音楽が好きな人、特にポップスが好きな人はボサノバ(旧来表記)を知っているだろう。「イパネマの娘」や「おいしい水」ぐらいは。しかしボサノバだけでなくフォークローレやその他の音楽もある。アルゼンチンタンゴもある。中南米は音楽の宝庫だ。また格闘技の好きな人はブラジルのカポエラやブラジリアン柔術も知っているはずだ。しかしカポエラが手を鎖で縛られた奴隷の護身術から発生したことは知っているだろうか(だから足技です)。文化を学ぶとはこういうことなのです。ジェローム・レ・バンナはフランス読みするとジェローム・ル・バネールです。これは日本にお... [続きを読む] -
推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)
基本的知識の必要
パリの女は産んでいる / 中島さおり. - ポプラ社, 2005
 北大ではどこにある?
ある元首相が結婚しない、子供を産まない女性に年金を与えるのはとんでもないという暴言を公言した。それに比べてフランスでは出産率は維持されている。それは政策として女性をサポートする体制があるという事実を紹介する書物。外国崇拝ではなく、わが国の社会保障と福祉の欺瞞(介護保険の改正などや自己責任、個人情報保護を口実にする隠蔽化)を考える資料になる。
北大ではどこにある?
ある元首相が結婚しない、子供を産まない女性に年金を与えるのはとんでもないという暴言を公言した。それに比べてフランスでは出産率は維持されている。それは政策として女性をサポートする体制があるという事実を紹介する書物。外国崇拝ではなく、わが国の社会保障と福祉の欺瞞(介護保険の改正などや自己責任、個人情報保護を口実にする隠蔽化)を考える資料になる。 -
推薦者 : 川村 周三 (農学研究科)
食品の安全をどのように確保するか
食品安全システムの実践理論 / 新山陽子 編. - 昭和堂, 2004
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 川村 周三 (農学研究科)
日本文化の源流を探る
雲南の照葉樹のもとで / 佐々木高明 編著. - 日本放送出版協会, 1984
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 川村 周三 (農学研究科)
稲作の起源はどこか?
中国古代遺跡が語る稲作の起源 / 岡彦一 編訳. - 八坂書房, 1997
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 花井 一典 (文学研究科)
待望の名著復刊
ラテン広文典 / 泉井 久之助. - 白水社, 2005
 北大ではどこにある?
ラテン語入門書は数多いが、これはウェルギリウスの叙事詩『アエネイス』の翻訳や、言語学者フンボルトの紹介、研究で知られる一代の碩学がものしただけあって単なる語学書ではない。どの行間にも自ずと滲む底知れぬ無言の学識、悠揚迫らざるおおどかな叙述、それはひとつの作品の風格を備えており、読者は触角さえ伸ばせばどこからでも言語の深みにはまるようにできている。本書味読の後では人はラテン語の(否、総じて外国語の)修得を「ただの語学」呼ばわりすることを恥じるであろう。
北大ではどこにある?
ラテン語入門書は数多いが、これはウェルギリウスの叙事詩『アエネイス』の翻訳や、言語学者フンボルトの紹介、研究で知られる一代の碩学がものしただけあって単なる語学書ではない。どの行間にも自ずと滲む底知れぬ無言の学識、悠揚迫らざるおおどかな叙述、それはひとつの作品の風格を備えており、読者は触角さえ伸ばせばどこからでも言語の深みにはまるようにできている。本書味読の後では人はラテン語の(否、総じて外国語の)修得を「ただの語学」呼ばわりすることを恥じるであろう。 -
推薦者 : 上田 宏 (北方生物圏フィールド科学センター)
海が教えてくれること、私たちができること
海の環境100の危機 / 東京大学海洋研究所DOBIS編集委員会編. - 東京書籍, 2006年
 北大ではどこにある?
地球温暖化、環境汚染、ゴミ問題、そして崩壊する生態系。海を守るために、自然と共生するためには、私たちは何ができるのかに関して、第1章「海の生態系の危機」、第2章「海の環境の危機」、第3章「環境保護・人間と社会の取り組み」に分けて、100の事例をわかりやすく解説したおすすめの一冊です。
北大ではどこにある?
地球温暖化、環境汚染、ゴミ問題、そして崩壊する生態系。海を守るために、自然と共生するためには、私たちは何ができるのかに関して、第1章「海の生態系の危機」、第2章「海の環境の危機」、第3章「環境保護・人間と社会の取り組み」に分けて、100の事例をわかりやすく解説したおすすめの一冊です。 -
推薦者 : 寺田 龍男 (メディア・コミュニケーション研究院)
中国の超一流大学を紹介してくれる本
中国の頭脳・精華大学と北京大学 / 紺野大介. - 朝日新聞社, 2006年
 北大ではどこにある?
この本を読むと、今でははやらなくなった「エリート」という言葉を思い出します。中国の若い秀才たちの学習ぶりはすさまじく、学部生段階でアメリカの大学から「ウチに(留学に)きてほしい」と声がかかるとも。日本の学生たちはこの点でまるで眼中にないとの指摘は正直耳が痛い。「だから北大生もがんばれ」というまえに、自分の研究・教育レベルをどうしたら上げられるかと考えてしまった。
北大ではどこにある?
この本を読むと、今でははやらなくなった「エリート」という言葉を思い出します。中国の若い秀才たちの学習ぶりはすさまじく、学部生段階でアメリカの大学から「ウチに(留学に)きてほしい」と声がかかるとも。日本の学生たちはこの点でまるで眼中にないとの指摘は正直耳が痛い。「だから北大生もがんばれ」というまえに、自分の研究・教育レベルをどうしたら上げられるかと考えてしまった。
ただし、この本に書かれているのは巨大な中国社会の一面に過ぎません。中国の大学(すべて国立、約1000校)にも(著者によると)「ピンからキリ」まであり、中には大学とは呼べ... [続きを読む] -
推薦者 : 上田宏 (北方生物圏フィールド科学センター)
教科書が完成しました
フィールド科学への招待 / 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター. - 三共出版, 2006年
 北大ではどこにある?
全学教育「フィールド科学への招待」の教科書が出版されました。北海道大学の教育理念である“実学の重視”を実践している、北方生物圏フィールド科学センターの教員自らがフィールドで行なってきた研究成果を肉付けして教科書にしました。今、地球ではー人間が直面している課題ー、私たちはどのように対応するかーフィールド科学の実践例ー、人間活動の負荷を軽減するーフィールド科学の応用ー、フィールド科学の力など、新しい学問であるフィールド科学について学べます。
北大ではどこにある?
全学教育「フィールド科学への招待」の教科書が出版されました。北海道大学の教育理念である“実学の重視”を実践している、北方生物圏フィールド科学センターの教員自らがフィールドで行なってきた研究成果を肉付けして教科書にしました。今、地球ではー人間が直面している課題ー、私たちはどのように対応するかーフィールド科学の実践例ー、人間活動の負荷を軽減するーフィールド科学の応用ー、フィールド科学の力など、新しい学問であるフィールド科学について学べます。 -
推薦者 : 内田 努 (工学研究科)
「西堀流」創造的生き方のお話です。
[新版]石橋を叩けば渡れない。 / 西堀栄三郎. - 生産性出版, 1999
 北大ではどこにある?
第1次南極越冬隊長、東芝では真空管の研究者、ヒマラヤ登山隊長、など様々な経歴を持つ著者が、その生き方のヒントをいっぱい紹介している本です。
北大ではどこにある?
第1次南極越冬隊長、東芝では真空管の研究者、ヒマラヤ登山隊長、など様々な経歴を持つ著者が、その生き方のヒントをいっぱい紹介している本です。
「人間というものは経験を積むために生まれてきた」
「欠点は個性であり、変えるのではなく生かすものである」
「創意工夫する能力こそは、神が人間に与えた特権」
など、随所に腑に落ちる言葉が出てきます。
また特に理系の人には、「科学」と「技術」の違いについて考えてみていただければと思います。
そして科学者として、あるいは技術者としてどんな風に生きていったら良いか、考えてみてください。
登録日 : 2006-06-08