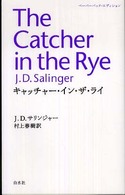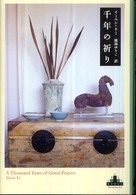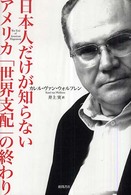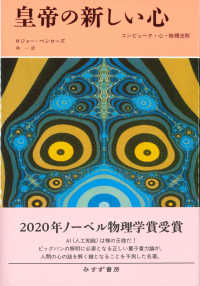-
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
日本社会の病い
まやかしの安全の国 / 田辺文也. - 角川SSC新書137, 2011
 北大ではどこにある?
去る3月11日の地震・津波による福島第一原発の事故は様々な疑問を投げかけます。事故の発生という事実に直面してからでは遅いといわれそうですが、原子力に携わる人々や事故に対処する政府関係者や事故の直接の当事者などの個人的資質にも疑念を呈したくなりますし、それを許容する社会の制度にも不信を抱かざるをえません。この本はそういう疑問に答えてくれそうですし、考えるきっかけを与えてくれそうです。以下、著者のあとがきより引用します。
北大ではどこにある?
去る3月11日の地震・津波による福島第一原発の事故は様々な疑問を投げかけます。事故の発生という事実に直面してからでは遅いといわれそうですが、原子力に携わる人々や事故に対処する政府関係者や事故の直接の当事者などの個人的資質にも疑念を呈したくなりますし、それを許容する社会の制度にも不信を抱かざるをえません。この本はそういう疑問に答えてくれそうですし、考えるきっかけを与えてくれそうです。以下、著者のあとがきより引用します。
・・・・・原子力のような巨大システムの安全確保に不可欠なのは、設備の運転や保守に携わる人のシステムに対する深い... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
「大志」をこえるもの
キャッチャー・イン・ザ・ライ / J.D.サリンジャー著(村上春樹訳). - 白水社, 2006
 北大ではどこにある?
自分に対して誠実であろうとすればするほど社会の規範に従うことを潔しとしない、ということはよくあることです。ひとは年を重ねるにつれ、誠実さと従順さの間に折り合いをつけ、その折り合いをつけたことにも鈍感になってゆきます。これはまだ学校という擬似社会にもまれ始めたばかりの高校生のそういう事態に直面し挫折をくりかえすはなし。(挫折とは社会が強いるもののようです。)
北大ではどこにある?
自分に対して誠実であろうとすればするほど社会の規範に従うことを潔しとしない、ということはよくあることです。ひとは年を重ねるにつれ、誠実さと従順さの間に折り合いをつけ、その折り合いをつけたことにも鈍感になってゆきます。これはまだ学校という擬似社会にもまれ始めたばかりの高校生のそういう事態に直面し挫折をくりかえすはなし。(挫折とは社会が強いるもののようです。)
この16歳の少年は、ライ麦畑で「キャッチャー」になりたい、と言います。本文を読まないとその意味するところは明らかでありませんが、すでに大人びた体格の自分が弱い子を危険からまもる... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
数学と人間と
The Mathematician's Brain / David Ruelle. - Princeton University Press, 2007
 北大ではどこにある?
数学という学問では論理的に正しい事柄、論理的に検証可能な事柄だけをもとめます。その論理にだけ注目すると数学はきわめて退屈な学問、形式的な学問といえそうです。(論理計算が正当化どうかを調べるには、記号の羅列が文法規則に従っているかどうかを見るだけでよくその意味を問う必要がないので、計算機にでもやらせることができるからです。)それでもギリシャ人はその前提となっていた自明の理を疑わず数学を真理の学問と神聖視しましたが、無限を取り扱う必要にかられた現代の数学者はそれほど幸せとはいえません。ほとんどの数学者のよりどころとしている自明の理... [続きを読む]
北大ではどこにある?
数学という学問では論理的に正しい事柄、論理的に検証可能な事柄だけをもとめます。その論理にだけ注目すると数学はきわめて退屈な学問、形式的な学問といえそうです。(論理計算が正当化どうかを調べるには、記号の羅列が文法規則に従っているかどうかを見るだけでよくその意味を問う必要がないので、計算機にでもやらせることができるからです。)それでもギリシャ人はその前提となっていた自明の理を疑わず数学を真理の学問と神聖視しましたが、無限を取り扱う必要にかられた現代の数学者はそれほど幸せとはいえません。ほとんどの数学者のよりどころとしている自明の理... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
西洋文明と哲学
反哲学入門 / 木田元. - 新潮社, 2007
 北大ではどこにある?
アメリカでは最近哲学専攻の学生が増えていると云います(ニューヨークタイムズ2008年4月6日の記事)。ただし、歴史上の哲学者のあれこれに興味があるのではなく、将来の見通しが立たない現代社会にあっては、思索で頭脳を鍛え論争の術を身につける必要があるという認識にたってのようです。哲学がそういう処世術にも通ずる生きた学問だと意識されていることに驚きました。
北大ではどこにある?
アメリカでは最近哲学専攻の学生が増えていると云います(ニューヨークタイムズ2008年4月6日の記事)。ただし、歴史上の哲学者のあれこれに興味があるのではなく、将来の見通しが立たない現代社会にあっては、思索で頭脳を鍛え論争の術を身につける必要があるという認識にたってのようです。哲学がそういう処世術にも通ずる生きた学問だと意識されていることに驚きました。
同時にアメリカ大統領予備選挙の記事を追っていると、度を越したような泥試合のなかにも、時として当事者に正気がもどり、その晴れ間をぬって歴史を貫いてきたギリシャ以来の精神が現前すると思われ... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
小説のなかの中国・米国
千年の祈り / イーユン・リー (篠崎ゆりこ訳). - 新潮社, 2007
 北大ではどこにある?
アメリカンドリームという言葉があります。こういう言葉が長いあいだ一国において命脈を保ってきたというのは、島国にすむものとしては不思議な気がしますが、思うに、常に受け入れてきた移民という新陳代謝が大いに関与しているのかもしれません。その希望の国が(ローマが共和制の衣を脱ぎ帝政の鎧をまとうことになる歴史の転換点にも似て)希望を捨て不安の投網のなかに市民を絡めとりつつあるという悲観的な見方もあるのですが(Naomi Wolf: The end of America, 2007)、なかなかどうして、こういう本に接す... [続きを読む]
北大ではどこにある?
アメリカンドリームという言葉があります。こういう言葉が長いあいだ一国において命脈を保ってきたというのは、島国にすむものとしては不思議な気がしますが、思うに、常に受け入れてきた移民という新陳代謝が大いに関与しているのかもしれません。その希望の国が(ローマが共和制の衣を脱ぎ帝政の鎧をまとうことになる歴史の転換点にも似て)希望を捨て不安の投網のなかに市民を絡めとりつつあるという悲観的な見方もあるのですが(Naomi Wolf: The end of America, 2007)、なかなかどうして、こういう本に接す... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
天才数学者列伝
God created the integers / Stephen Hawking. - Running Press, 2007
 北大ではどこにある?
ピタゴラスは、エーゲ海に浮かぶサモス島で、宇宙は全き数(自然数)によって表される、と考えたそうです。そののちルート2が全き数の割合で表されない(有理数でない)ことを発見したとき、自らの宇宙観への危機をひそかに感じ、その秘匿を弟子たちに命じました。漏洩者には死がまっていました。
北大ではどこにある?
ピタゴラスは、エーゲ海に浮かぶサモス島で、宇宙は全き数(自然数)によって表される、と考えたそうです。そののちルート2が全き数の割合で表されない(有理数でない)ことを発見したとき、自らの宇宙観への危機をひそかに感じ、その秘匿を弟子たちに命じました。漏洩者には死がまっていました。
ギリシャの人々の数学にかけた情熱は、広大無辺の宇宙に肉薄しようという真理にかけた宗教的情熱と一体不可分のようです。後のキリスト教の席巻はこの情熱を本物の宗教的情熱で窒息させてしまい、ギリシャ数学への新風はデカルト(1596−1650)までお預けになりま... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
アメリカの覇権と現状
日本人だけが知らないアメリカ「世界支配」の終わり / カレル・ヴァン・ウォルフレン. - 徳間書店, 2007
 北大ではどこにある?
見事な風景に接して、それを描こうとしても、きっとどこかで見た絵画のものまねになるように、この世界の現実を突きつけられても、それよりひとつの物語を紡ごうとすれば、きっとどこかで刷り込まれた解釈の焼き直しになるようです。著者によると(あるいは常識というべきでしょうか)、この世界の解釈は長いあいだアメリカより発信されてきました。たとえば、自由信仰にもとづく経済が世界に繁栄と安定をもたらすという託宣です。しかし(日本を除く)世界の国々はこの米国主導の解釈に対して疑念を抱き始めたようです。(例えば、昔からアメリカの支配下にあった中南米の国々... [続きを読む]
北大ではどこにある?
見事な風景に接して、それを描こうとしても、きっとどこかで見た絵画のものまねになるように、この世界の現実を突きつけられても、それよりひとつの物語を紡ごうとすれば、きっとどこかで刷り込まれた解釈の焼き直しになるようです。著者によると(あるいは常識というべきでしょうか)、この世界の解釈は長いあいだアメリカより発信されてきました。たとえば、自由信仰にもとづく経済が世界に繁栄と安定をもたらすという託宣です。しかし(日本を除く)世界の国々はこの米国主導の解釈に対して疑念を抱き始めたようです。(例えば、昔からアメリカの支配下にあった中南米の国々... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
人は弱いものらしい
The Lucifer Effect -- Understanding How Good People Turn Evil / Philip Zimbardo. - Random House, 2007
 北大ではどこにある?
最近の日本政府は先の大戦で我国の犯した残虐行為を軽視する傾向にあるようです。先ごろも、「従軍慰安婦の募集は軍部の強制によるのではない」という発言をしたひとが、米国で物議をかもすと、わざわざ向こうの大統領の前で釈明し「その謝罪を受け入れる」というお墨付きをもらうという訳のわからないことがありました。
北大ではどこにある?
最近の日本政府は先の大戦で我国の犯した残虐行為を軽視する傾向にあるようです。先ごろも、「従軍慰安婦の募集は軍部の強制によるのではない」という発言をしたひとが、米国で物議をかもすと、わざわざ向こうの大統領の前で釈明し「その謝罪を受け入れる」というお墨付きをもらうという訳のわからないことがありました。
正直なところこの問題は当時の日本の犯した犯罪行為としては軽微な方だったのではないかと思われます。それよりも、たとえば強制労働のほうが問題です。これは規模も大きく死亡率も(他国の同様の場合と比べ)かなり高かったようです。さらに、これが... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
人類の岐路
覇権か、生存か : アメリカの世界戦略と人類の未来 / ノーム・チョムスキー. - 集英社, 2004
 北大ではどこにある?
北朝鮮の核実験に触発されて、与党の有力者から、わが国も核を保有するべきだ、というような議論が出ました。政府の見解は、非核三原則を貫く、しかし言論は自由なので、将来のことをあれこれ思い巡らすなかに「核武装」という選択肢も残しておく、ということであったようです。ここで肝心なことからわざと目を背けていることに気づきます。この問題のまえに、当然、アメリカの覇権にどう対処するべきか、という議論を済ませておかなければならないからです。(実際に核武装すれば、イスラエルという例外がありますが、アメリカの逆鱗に触れることは確実です。)
北大ではどこにある?
北朝鮮の核実験に触発されて、与党の有力者から、わが国も核を保有するべきだ、というような議論が出ました。政府の見解は、非核三原則を貫く、しかし言論は自由なので、将来のことをあれこれ思い巡らすなかに「核武装」という選択肢も残しておく、ということであったようです。ここで肝心なことからわざと目を背けていることに気づきます。この問題のまえに、当然、アメリカの覇権にどう対処するべきか、という議論を済ませておかなければならないからです。(実際に核武装すれば、イスラエルという例外がありますが、アメリカの逆鱗に触れることは確実です。)
チョム... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
宗教と科学
The God Delusion / Richard Dawkins. - Bantam Press, 2006
 北大ではどこにある?
ドーキンス氏はこの書において、神が存在しないことがその存在することよりも圧倒的に確からしいことを、進化論的観点から示します。(ただし、ここでいう神とは、万物を創造し人間に賞罰を与える超自然的存在のことで、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の神が想定されています。)しかし、有史以来、人類は宗教とともに歩んできたようです。宗教を信奉するひとが無宗教のひととの相克に勝ち抜き、自然淘汰の試練を潜り抜けてきたからには、少なくとも宗教に存在価値があるからではないかという疑問が起こります。著者は、それが危険に満ちた環境での人類の生存に適した心... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ドーキンス氏はこの書において、神が存在しないことがその存在することよりも圧倒的に確からしいことを、進化論的観点から示します。(ただし、ここでいう神とは、万物を創造し人間に賞罰を与える超自然的存在のことで、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の神が想定されています。)しかし、有史以来、人類は宗教とともに歩んできたようです。宗教を信奉するひとが無宗教のひととの相克に勝ち抜き、自然淘汰の試練を潜り抜けてきたからには、少なくとも宗教に存在価値があるからではないかという疑問が起こります。著者は、それが危険に満ちた環境での人類の生存に適した心... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
憲法は、政府に対する命令である。
憲法は、政府に対する命令である。 / ダグラス・ラミス. - 平凡社, 2006
 北大ではどこにある?
キャンベラにマグナカルタプレイスという小さな緑地があります。碑文によるとオーストラリア建国(1901年)はこのマグナカルタ(1225年)を礎としているということだったと思います。もっともあとで調べてみるとその国の憲法にはそんな一文はなく、建国の手続きばかりのようでした(総督の給与をいくらにするとか)。英国から移民したひとたちにとってマグナカルタの占める位置は当然のことだったのでしょうか。
北大ではどこにある?
キャンベラにマグナカルタプレイスという小さな緑地があります。碑文によるとオーストラリア建国(1901年)はこのマグナカルタ(1225年)を礎としているということだったと思います。もっともあとで調べてみるとその国の憲法にはそんな一文はなく、建国の手続きばかりのようでした(総督の給与をいくらにするとか)。英国から移民したひとたちにとってマグナカルタの占める位置は当然のことだったのでしょうか。
残念ながらこの国は法というほどのものを生み出しませんでした。有史以来(?)天皇家がこの国を統治しているということに非常な価値を見出している人... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
占領下日本と憲法
敗北を抱きしめて(上下) / ジョン・ダワー. - 岩波書店, 2001,2004
 北大ではどこにある?
この国の憲法を「押し付けられたものだから」(を理由のひとつとして)改正しようとする動きがあります。近隣諸国との諍いをも厭わず戦死者の霊を慰めることに熱心な人たちですから、敗戦後の生活の塗炭の苦しみに加えて意に染まぬ憲法を押し付けられるという精神的苦痛を味わった当時の庶民への同情に突き動かされて発議したのかと思っていましたら、そうでもなさそうです。いかに歴史を学ばないひとでも、当時の人々のほとんどが解放感に包まれてこれを歓迎したことは知っているでしょう。それとも、その始祖たる時の首相吉田茂が天皇裕仁のまえで「臣茂」と名乗ること... [続きを読む]
北大ではどこにある?
この国の憲法を「押し付けられたものだから」(を理由のひとつとして)改正しようとする動きがあります。近隣諸国との諍いをも厭わず戦死者の霊を慰めることに熱心な人たちですから、敗戦後の生活の塗炭の苦しみに加えて意に染まぬ憲法を押し付けられるという精神的苦痛を味わった当時の庶民への同情に突き動かされて発議したのかと思っていましたら、そうでもなさそうです。いかに歴史を学ばないひとでも、当時の人々のほとんどが解放感に包まれてこれを歓迎したことは知っているでしょう。それとも、その始祖たる時の首相吉田茂が天皇裕仁のまえで「臣茂」と名乗ること... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
科学を志すとは
皇帝の新しい心 : コンピュータ・心・物理法則 / ロジャー・ペンローズ. - みすず書房, 1994
 北大ではどこにある?
科学を探究するとはこういうことかと思わせる書物です。つまり、科学の本来目的とするところは、人間とその周りに広がる世界に対する理解を深めることであるはずです。著者はきっと若いときからその科学の目的を見据えて学者としての道を歩んで来たのでしょう。なぜなら、自分の足跡をまとめるだけで、科学の発展とそれに伴う哲学上の変遷を読者に提示することができて、多分現代におけるもっとも困難な問題、心の問題に取り組めるというのですから。(具体的には、論理学、計算理論、量子論、宇宙論などを扱ったうえで、脳と意識を論じています。)
北大ではどこにある?
科学を探究するとはこういうことかと思わせる書物です。つまり、科学の本来目的とするところは、人間とその周りに広がる世界に対する理解を深めることであるはずです。著者はきっと若いときからその科学の目的を見据えて学者としての道を歩んで来たのでしょう。なぜなら、自分の足跡をまとめるだけで、科学の発展とそれに伴う哲学上の変遷を読者に提示することができて、多分現代におけるもっとも困難な問題、心の問題に取り組めるというのですから。(具体的には、論理学、計算理論、量子論、宇宙論などを扱ったうえで、脳と意識を論じています。)
ペンローズ氏は高名な... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
歴史を通じて現在をみる
憲法で読むアメリカ史(上下) / 阿川尚之. - PHP研究所, 2004
 北大ではどこにある?
アメリカは歴史の浅い国というひとがいますが、それは果たして真実でしょうか。アメリカは13の州が連合して1776年に独立し、今に有効な憲法を1788年に制定しました。(世界で現に通用している憲法のなかで最古だそうです。)日本でいえば江戸時代半ばに制定された法律が本質的な変更なく今も、民主主義とその制度を宣言する文書として機能し模範とされていることを想像してみてください。江戸幕府はせいぜい幾つかの「諸法度」のもとで成立していたのです。もちろん、この憲法にも「瑕瑾」がありました。奴隷制度を容認しているととれる条項があることです(しか... [続きを読む]
北大ではどこにある?
アメリカは歴史の浅い国というひとがいますが、それは果たして真実でしょうか。アメリカは13の州が連合して1776年に独立し、今に有効な憲法を1788年に制定しました。(世界で現に通用している憲法のなかで最古だそうです。)日本でいえば江戸時代半ばに制定された法律が本質的な変更なく今も、民主主義とその制度を宣言する文書として機能し模範とされていることを想像してみてください。江戸幕府はせいぜい幾つかの「諸法度」のもとで成立していたのです。もちろん、この憲法にも「瑕瑾」がありました。奴隷制度を容認しているととれる条項があることです(しか... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
文明の将来を考える書
American Theocracy / Kevin Phillips. - Viking, 2006
 北大ではどこにある?
Theocracyは神権政治と訳します。これは、アメリカがむかし神権政治の国であったというのでもなく、将来そうなるという警世の書でもなく、現に(ブッシュ政権が)神権政治に陥ったことに対する慷慨の書なのです。
北大ではどこにある?
Theocracyは神権政治と訳します。これは、アメリカがむかし神権政治の国であったというのでもなく、将来そうなるという警世の書でもなく、現に(ブッシュ政権が)神権政治に陥ったことに対する慷慨の書なのです。
キリスト教国では「神のお恵みを」とか、イスラム教国では「アッラーの神に」とかを、政治家も民衆に使っているようです(もっとも実際にはわたしは聞いたことがないのですが)。わたしはこれを言葉の綾と思って注意を払ってきませんでした。これは「心の問題」であって、人それぞれに解釈すればいいことでしょう。このことが心の問題として済ませられなくなるの... [続きを読む] -
推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)
歴史を通じて世界経済を考える書
超帝国主義アメリカの内幕 / マイケル・ハドソン. - 徳間書店, 2002
 北大ではどこにある?
もし書店の棚にこういう題名の本を見かけたとしても、今、どれほどの人が手にとって見る気を起こすものなのか、想像がつきかねます。しかし、私の若いころは(1960年代)、若者がよく「アメリカ帝国主義反対」などと金切り声をあげていました。その当時とそれより暫くのあいだは、私のような政治的に鈍感なひとにとっても、世界というものを理解するうえで、これが喉につかえた小骨のようなものであったかもしれません。少なくとも、亜米利加追従我国安泰と割り切れるひとはほとんどいなかったのではないか、と思います。
北大ではどこにある?
もし書店の棚にこういう題名の本を見かけたとしても、今、どれほどの人が手にとって見る気を起こすものなのか、想像がつきかねます。しかし、私の若いころは(1960年代)、若者がよく「アメリカ帝国主義反対」などと金切り声をあげていました。その当時とそれより暫くのあいだは、私のような政治的に鈍感なひとにとっても、世界というものを理解するうえで、これが喉につかえた小骨のようなものであったかもしれません。少なくとも、亜米利加追従我国安泰と割り切れるひとはほとんどいなかったのではないか、と思います。
日本語の題名には辟易するひともあろうかと思い... [続きを読む]