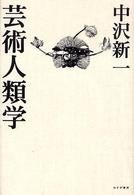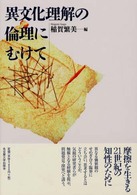-
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
フランス人画家が描く日本古代神話の色彩曼陀羅の世界
日本神話 / マークエステル. - Xiang-Hap社(香港), 2006
 北大ではどこにある?
このずっしりと重い大判の画集を開いてゆくと、驚きを禁じえない。日本の原点とされてきた『古事記』の世界が、われわれが何となく思い描いていたものとはまるで違う壮大な色彩宇宙として展開してゆくのだ。古事記の物語世界に肉迫してゆくそのイメージ力の雄渾さ。創世神話を彩って華麗に舞い上がるその色彩のド迫力。これまで誰がこのような途轍もないスペクトルでわれわれの神話世界を表現してきただろうか。
北大ではどこにある?
このずっしりと重い大判の画集を開いてゆくと、驚きを禁じえない。日本の原点とされてきた『古事記』の世界が、われわれが何となく思い描いていたものとはまるで違う壮大な色彩宇宙として展開してゆくのだ。古事記の物語世界に肉迫してゆくそのイメージ力の雄渾さ。創世神話を彩って華麗に舞い上がるその色彩のド迫力。これまで誰がこのような途轍もないスペクトルでわれわれの神話世界を表現してきただろうか。
描いているのは、大の親日家であり――首相経験者から著名歌手にまで及ぶその交友の広さは驚くばかりである――、日本文化に非常に造詣の深い現代フランス人... [続きを読む] -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
《2008年ノーベル文学賞受賞!!》芸術、文学、ヨーロッパ思想を学ぶ者にとって必読の書
悪魔祓い / J.M.G.ル・クレジオ〔著〕 ; 高山鉄男訳. - 新潮社, 1975
 北大ではどこにある?
ル・クレジオは現代のフランスの作家。1960年代に前衛的作家として華々しくフランスの文壇にデビューしたあと、現代の西洋文明に飽き足らず、パナマでアメリカ先住民とともに長らく暮らし、スペインに征服される前のメキシコの文明に深く分け入って、芸術とは何か、文学とは何か、文明とは何かを、人類的なトータルな視野から探り続けてきた。本書は、パナマ先住民との生活を通して、彼らの芸術観、生命観、宇宙観をヨーロッパとの比較のもとで描き出したもの。ル・クレジオは、よくあるように、アメリカ先住民の文明を、西洋文明にまだ犯されていない無垢なるものとして語... [続きを読む]
北大ではどこにある?
ル・クレジオは現代のフランスの作家。1960年代に前衛的作家として華々しくフランスの文壇にデビューしたあと、現代の西洋文明に飽き足らず、パナマでアメリカ先住民とともに長らく暮らし、スペインに征服される前のメキシコの文明に深く分け入って、芸術とは何か、文学とは何か、文明とは何かを、人類的なトータルな視野から探り続けてきた。本書は、パナマ先住民との生活を通して、彼らの芸術観、生命観、宇宙観をヨーロッパとの比較のもとで描き出したもの。ル・クレジオは、よくあるように、アメリカ先住民の文明を、西洋文明にまだ犯されていない無垢なるものとして語... [続きを読む] -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
「考える」という営みへの最良の入門書
哲学、脳を揺さぶる / 河本英夫. - 日経BP, 2007
 北大ではどこにある?
分類すれば哲学という分野に入るのだろうが、思考のエクササイズはもとより、芸術あり、科学あり、身体論あり、イメージ論あり、認知論あり、といった具合に間口はひろく、総合的であり、そして(多少は苦労もしながら)ひとたび読み終わってみれば、脳は活性化し、何やらいっぱしの知的ナヴィゲーションをしてきた充実感が得られること間違いなし。著者は、「考える」という人間の不思議なイトナミに深く広く分け入らんとする先端的な探求者のひとり。大学生たる者、たまにはこうした本を読みこなさなくちゃ。
北大ではどこにある?
分類すれば哲学という分野に入るのだろうが、思考のエクササイズはもとより、芸術あり、科学あり、身体論あり、イメージ論あり、認知論あり、といった具合に間口はひろく、総合的であり、そして(多少は苦労もしながら)ひとたび読み終わってみれば、脳は活性化し、何やらいっぱしの知的ナヴィゲーションをしてきた充実感が得られること間違いなし。著者は、「考える」という人間の不思議なイトナミに深く広く分け入らんとする先端的な探求者のひとり。大学生たる者、たまにはこうした本を読みこなさなくちゃ。 -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
私という存在を操縦している生命なるものの仕組みを知ろう
生物と無生物のあいだ / 福岡伸一. - 講談社(講談社現代新書), 2007
 北大ではどこにある?
目下(2007年8月時点)大評判の書である。生命というとすぐ自然科学と思うなかれ、科学についてのみならず、人間について、世界について関心がある者すべてにこの書は開かれている。生命の謎を解明してゆく分子生物学の最先端の探究を語りながら、いつの間にかこの本は、現代における科学のあり方や人間の生き方までをも、著者独特の広角レンズでみごとに浮かび上がらせてくれる。著者の語り口は一級のストーリー・テラーのように冴え渡っていて、読む者は、まるで冒険小説を読むように、生命の演ずる壮大なドラマにぐいぐいと引き込まれてゆく。知的興奮をたっぷりと与えられ... [続きを読む]
北大ではどこにある?
目下(2007年8月時点)大評判の書である。生命というとすぐ自然科学と思うなかれ、科学についてのみならず、人間について、世界について関心がある者すべてにこの書は開かれている。生命の謎を解明してゆく分子生物学の最先端の探究を語りながら、いつの間にかこの本は、現代における科学のあり方や人間の生き方までをも、著者独特の広角レンズでみごとに浮かび上がらせてくれる。著者の語り口は一級のストーリー・テラーのように冴え渡っていて、読む者は、まるで冒険小説を読むように、生命の演ずる壮大なドラマにぐいぐいと引き込まれてゆく。知的興奮をたっぷりと与えられ... [続きを読む] -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
個の表現ではなく、知的未来のための芸術に向けて
芸術人類学 / 中沢新一. - みすず書房, 2006
 北大ではどこにある?
「芸術」という考え方が、「科学」という考え方と同様に、そしてまた「資本主義」や「民主主義」と同じように、ここ二、三百年における「Made in Europe」の産物であることをご存知だろうか。つまりそれらは現在においていかにもユニヴァーサルな価値として流布しているが、実はこうした事象そのものが、ヨーロッパの価値尺度のグローバル化の結果にほかならないのだ。人類学者、宗教学者として著名であり、現在多摩美術大学の芸術人類学研究所の所長を務める著者は、ヨーロッパにおいては「芸術」と呼ばれている思考が、いわゆる「未開社会」などの非ヨーロッパ文化圏においては... [続きを読む]
北大ではどこにある?
「芸術」という考え方が、「科学」という考え方と同様に、そしてまた「資本主義」や「民主主義」と同じように、ここ二、三百年における「Made in Europe」の産物であることをご存知だろうか。つまりそれらは現在においていかにもユニヴァーサルな価値として流布しているが、実はこうした事象そのものが、ヨーロッパの価値尺度のグローバル化の結果にほかならないのだ。人類学者、宗教学者として著名であり、現在多摩美術大学の芸術人類学研究所の所長を務める著者は、ヨーロッパにおいては「芸術」と呼ばれている思考が、いわゆる「未開社会」などの非ヨーロッパ文化圏においては... [続きを読む] -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
グローバル時代を真摯に生きるための知の指南書
異文化理解の倫理にむけて / 稲賀繁美(編). - 名古屋大学出版会, 2000
 北大ではどこにある?
異文化理解論については凡百の書が出ているが、この本はその中で出色ものである。特筆すべきは、大学での教科書としてつくられていながら、多くの類書とは全く違って、文化接触の生の現場を通して、思考する営みへと読者を導いてゆく内容構成がなされていることである。それは巻頭に掲げられている以下の「本書のねらい」が雄弁に語っている。
北大ではどこにある?
異文化理解論については凡百の書が出ているが、この本はその中で出色ものである。特筆すべきは、大学での教科書としてつくられていながら、多くの類書とは全く違って、文化接触の生の現場を通して、思考する営みへと読者を導いてゆく内容構成がなされていることである。それは巻頭に掲げられている以下の「本書のねらい」が雄弁に語っている。
1.異文化衝突の現場を提示する
2.文化間の価値観の相克、葛藤を浮き彫りにする
3.現場を知る専門家ならではの、読者へのメッセージ
4.概論提示ではなく、読者を理論構築へと誘う
5.読者による探求の道しるべを
こ... [続きを読む] -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
コンピュータ、コロンブス、ユダヤ思想、そして今のアメリカ――、一見まるで無関係なこれらをつなぐ隠れた文明の糸。この糸を通して、コンピュータが生まれた知的背景、そして今の国際世界が見えてくる。
1492年のマリア / 西垣通著. - 講談社, 2002.7
 北大ではどこにある?
著者は著名な情報学者(東大教授)。
北大ではどこにある?
著者は著名な情報学者(東大教授)。
氏は、コンピュータを単なる技術の機械にとどめず、それを壮大な文明の歴史
の中に読み込んで、この見事な歴史サスペンス小説を書き上げた。 1492年のコ
ロンブスの出航の陰で進行するユダヤ人追放令と、そのドラマを壮絶に生きる主
人公のアロンソ(コロンブスの航海に参加)と愛人マリア。波乱万丈のストー
リー展開の中で、13世紀思想家ルルスの「大いなる普遍の術」(アルス・マグ
ナ)、コロンブスの航海、そして500年後にアメリカで花開く思考機械コンピュー
タを結ぶ「暗号の糸」が浮かび上がる。
コンピュータ学、情報学... [続きを読む] -
推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)
世界を知るには自分を知ろう――日本の文化のDNAを知る最良の書
二重言語国家・日本 / 石川九楊著. - 日本放送出版協会, 1999.5
 北大ではどこにある?
著者は書道家として知られる一方、文字を通じ、われわれの日本文化(漢字・かな文化)について、中国文明(漢字文明圏)、ヨーロッパ文明(アルファベット文字文明圏)など世界全体の文明構造の中から解き明かす著作と論考を数多く発表しており、本書はその代表作。われわれが何気なく使っている漢字、かな、そして明治以降のアルファベットを通して、われわれの歴史、文化、ものの考え方の特徴が、それこそ目からウロコが落ちるように見えてくる。のみならず、現在の米中、日中関係すらも透けて見えてくるのは著者の思索の深さゆえか。同著者の『
北大ではどこにある?
著者は書道家として知られる一方、文字を通じ、われわれの日本文化(漢字・かな文化)について、中国文明(漢字文明圏)、ヨーロッパ文明(アルファベット文字文明圏)など世界全体の文明構造の中から解き明かす著作と論考を数多く発表しており、本書はその代表作。われわれが何気なく使っている漢字、かな、そして明治以降のアルファベットを通して、われわれの歴史、文化、ものの考え方の特徴が、それこそ目からウロコが落ちるように見えてくる。のみならず、現在の米中、日中関係すらも透けて見えてくるのは著者の思索の深さゆえか。同著者の『