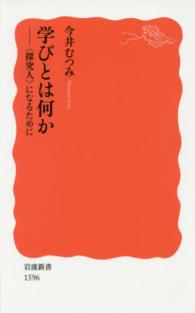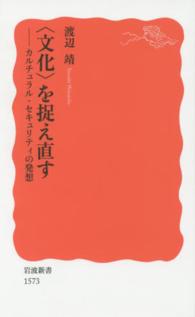-
推薦者 : 敷田 麻実 (高等教育推進機構・教員)
学ぶことを学べる本
学びとは何か : 「探究人」になるために / 今井むつみ. - 岩波書店, 2016
 北大ではどこにある?
大学を出たときが学びのピークで、それ以降は知識レベルが下がっていくだけという批判には三分の理を認めるが、それは学習や学びをなめてかかっている。本当は社会に出てからが学びの本番であり、答えのない問題を解くチャンスに日々恵まれる。学校を出たときが学力のピークだという考えは、教室でインプットした知識だけで社会が理解できるという誤解に基づいている。学びは重要である。大学では、膨大な資料を読み、それを知ったうえでの研究を求められる。そのため、知識を得ること、レクチャーされることが大学生活の中心となりがちである。しかし、本書を読めば、知る... [続きを読む]
北大ではどこにある?
大学を出たときが学びのピークで、それ以降は知識レベルが下がっていくだけという批判には三分の理を認めるが、それは学習や学びをなめてかかっている。本当は社会に出てからが学びの本番であり、答えのない問題を解くチャンスに日々恵まれる。学校を出たときが学力のピークだという考えは、教室でインプットした知識だけで社会が理解できるという誤解に基づいている。学びは重要である。大学では、膨大な資料を読み、それを知ったうえでの研究を求められる。そのため、知識を得ること、レクチャーされることが大学生活の中心となりがちである。しかし、本書を読めば、知る... [続きを読む] -
推薦者 : 敷田 麻実 (高等教育推進機構・教員)
この難しい時代のグローバル化政策を学ぶ
「文化」を捉え直す : カルチュラル・セキュリティの発想 / 渡辺靖. - 岩波書店, 2015
 北大ではどこにある?
グローバリゼーションは、国際社会とは関係がない私たちの日常にも影響する。こちらの都合や好き嫌いにかかわらず、勝手に影響してくるのがグローバル化であって、自治体が意図して進めていく国際化とは大きな差がある。大学の近くの保育園には、異なる国々の子供たちが通う保育園をよく見かけるが、地域が好んでインターナショナルスクールを誘致したのではない。立地する大学の教職員、留学生の影響で結果的にそうなったのだ。
北大ではどこにある?
グローバリゼーションは、国際社会とは関係がない私たちの日常にも影響する。こちらの都合や好き嫌いにかかわらず、勝手に影響してくるのがグローバル化であって、自治体が意図して進めていく国際化とは大きな差がある。大学の近くの保育園には、異なる国々の子供たちが通う保育園をよく見かけるが、地域が好んでインターナショナルスクールを誘致したのではない。立地する大学の教職員、留学生の影響で結果的にそうなったのだ。
このようにグローバル化の中では、新しい文化が遠慮なく地域に入ってくる。しかしその一方で、固有の伝統文化の維持は難しくなってきてい... [続きを読む] -
推薦者 : 敷田 麻実 (高等教育推進機構・教員)
調査で「なぜ」と聞いてはいけない
途上国の人々との話し方 : 国際協力メタファシリテーションの手法 / 和田信明, 中田豊一著. - みずのわ出版, 2010
 北大ではどこにある?
本書の筆者である和田と中田は国際協力のベテランであり、アジアなどの途上国の現場で学んだこと、特に、相手の状態を理解する調査について、ていねいに解説している。相手を知ることの第一は観察であるが、その次は質問を介したコミュニケーションである。それは地域調査でのやり取りでも同じである。
北大ではどこにある?
本書の筆者である和田と中田は国際協力のベテランであり、アジアなどの途上国の現場で学んだこと、特に、相手の状態を理解する調査について、ていねいに解説している。相手を知ることの第一は観察であるが、その次は質問を介したコミュニケーションである。それは地域調査でのやり取りでも同じである。
彼らは「問題は何か」や「原因は何か」と相手に聞いてはいけないと述べる。例示された、医者は患者を前に「なんで熱があるのか?」と聞くのではなく、医者が聞くべきは「いつから熱が出たのか」という事実であるというアドバイスは、まったく当を得ている。考えを聞... [続きを読む] -
推薦者 : 敷田 麻実 (高等教育推進機構・教員)
君は、「面白い研究」をつまらなくプレゼンできないはずだ
勝率2割の仕事論 : ヒットは「臆病」から生まれる / 岡康道. - 光文社, 2016
 北大ではどこにある?
岡はクリエイティブディレクターであり、またコマーシャルを作成するプランナーの肩書きを持つ。大手の広告代理店に勤めた後、仲間と独立し「TUGBOAT(タグボート)」(広告代理店)の代表を努めている。その岡が本書で強調するのは、「仕事の勝率は2割でよい」ということではない。岡が、クライアントの要求を超えて、彼らが気づいていない隠れた意図を提案したり、メッセージ性の強い仕事をしていると、結果的に勝率は2割になってしまうということだ。
北大ではどこにある?
岡はクリエイティブディレクターであり、またコマーシャルを作成するプランナーの肩書きを持つ。大手の広告代理店に勤めた後、仲間と独立し「TUGBOAT(タグボート)」(広告代理店)の代表を努めている。その岡が本書で強調するのは、「仕事の勝率は2割でよい」ということではない。岡が、クライアントの要求を超えて、彼らが気づいていない隠れた意図を提案したり、メッセージ性の強い仕事をしていると、結果的に勝率は2割になってしまうということだ。
彼の仕事と研究者の仕事の共通点は、「人の金」を使って仕事をしていることである。彼らはクライアントの資金を使い... [続きを読む]