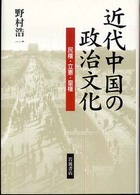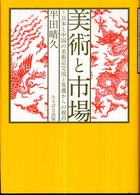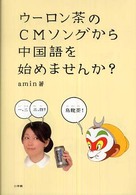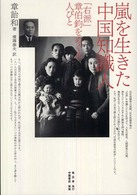-
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
日中関係の近代美術における交流
中国の近代美術と日本:20世紀日中関係の一断面 / 陸偉榮著. - 大学教育出版, 2007
 北大ではどこにある?
北大ではどこにある?
-
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
現代中国を代表する哲学者による回想録
馮友蘭自伝 : 中国現代哲学者の回想 1・2 (東洋文庫 ; 767-768) / 馮友蘭著 ; 吾妻重二訳 . - 平凡社, 2007
 北大ではどこにある?
現代中国を代表する哲学者による回想録。19世紀末から1980年代に至る、変貌の時代を生きた著者が同時代史を記し、自己の経験をまとめた書で、激動の中国近現代史を理解するうえで必読書といってもよい名著の翻訳である。なかでも中華人民共和国成立後の部分は、知識人の内面史として他書に類例をみぬ価値を持つ。翻訳も平明で読みやすい。
北大ではどこにある?
現代中国を代表する哲学者による回想録。19世紀末から1980年代に至る、変貌の時代を生きた著者が同時代史を記し、自己の経験をまとめた書で、激動の中国近現代史を理解するうえで必読書といってもよい名著の翻訳である。なかでも中華人民共和国成立後の部分は、知識人の内面史として他書に類例をみぬ価値を持つ。翻訳も平明で読みやすい。 -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
現代中国理解のために
近代中国の政治文化 : 民権・立憲・皇権 / 野村浩一. - 岩波書店, 2007
 北大ではどこにある?
改革開放の進む中国では近年、魯迅と同時代に活躍した現代中国を代表する知識人・胡適の研究がますます盛んになっているが、日本では残念ながらあまり注目されていない。その胡適を中心に近代中国における「自由主義」の位置づけを試みた第三章は本書の圧巻で、現代中国理解のためにも一読に値する。
北大ではどこにある?
改革開放の進む中国では近年、魯迅と同時代に活躍した現代中国を代表する知識人・胡適の研究がますます盛んになっているが、日本では残念ながらあまり注目されていない。その胡適を中心に近代中国における「自由主義」の位置づけを試みた第三章は本書の圧巻で、現代中国理解のためにも一読に値する。 -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
日中関係について美術品の交流とそのマーケットという視点から迫ろうというユニークな書
美術と市場 : 日本と中国の美術品交流と変遷からの視点 / 半田晴久著. - たちばな出版, 2007
 北大ではどこにある?
日中関係について美術品の交流とそのマーケットという視点から迫ろうというユニークな書。美術はもちろん芸術品であるが、それと同時に、価格がつき、売買される、れっきとした〈商品〉としての一面も無視することはできない。アートを通じた国際交流が今後ますます盛んになっていくであろう現在、考え、行動するためのヒントが見つかるかもしれない。
北大ではどこにある?
日中関係について美術品の交流とそのマーケットという視点から迫ろうというユニークな書。美術はもちろん芸術品であるが、それと同時に、価格がつき、売買される、れっきとした〈商品〉としての一面も無視することはできない。アートを通じた国際交流が今後ますます盛んになっていくであろう現在、考え、行動するためのヒントが見つかるかもしれない。 -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
現代中国社会の悲哀を、リアルに、多少の皮肉も交じえ、温かい目で描く物語
飛べない龍 / 蘇童著 ; 村上満里子訳. - 文芸社, 2007
 北大ではどこにある?
著者は現代中国文壇を代表する作家の一人。経済成長著しい中国社会の底辺で、もがきながら生きる男と女。目まぐるしい変化と発展の中で、取り残されたままの人々の姿、そして現代中国社会の悲哀を、リアルに、多少の皮肉も交じえ、温かい目で描く物語。
北大ではどこにある?
著者は現代中国文壇を代表する作家の一人。経済成長著しい中国社会の底辺で、もがきながら生きる男と女。目まぐるしい変化と発展の中で、取り残されたままの人々の姿、そして現代中国社会の悲哀を、リアルに、多少の皮肉も交じえ、温かい目で描く物語。 -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
楽しみながら中国語を学ぶ入門書
ウーロン茶のCMソングから中国語を始めませんか? / amin著. - 小学館,
 北大ではどこにある?
おなじみの烏龍茶CMソングの歌詞から、楽しみながら中国語を学ぶ入門書。中国人歌手として史上初のNHK紅白歌合戦出場を果たしたamin(阿明)自らが吹きこんだ解説CD付き。中国人の前で歌がうたえれば絶対ウケるし、なにより楽しい。楽しいがいちばん!
北大ではどこにある?
おなじみの烏龍茶CMソングの歌詞から、楽しみながら中国語を学ぶ入門書。中国人歌手として史上初のNHK紅白歌合戦出場を果たしたamin(阿明)自らが吹きこんだ解説CD付き。中国人の前で歌がうたえれば絶対ウケるし、なにより楽しい。楽しいがいちばん! -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
現代中国への認識を深めるのに一読の価値あり
嵐を生きた中国知識人 : 「右派」章伯鈞をめぐる人びと / 章詒和著 ; 横澤泰夫訳. - 集広舎, 2007
 北大ではどこにある?
現代中国への認識を深めるのに一読の価値あり。50年前に開始された「反右派闘争」の中で「最大の右派」とされた父・章伯鈞をめぐる人びとを活写することにより、「中国共産党の政治」のあり方を世に問うた問題作。流麗な文章と深い人間理解、歴史への洞察によって中国内外で高い評価を受けたものの、発売後2ヶ月で再版不許可・発禁処分となった『往事並不如煙』を香港で改題・出版した完全版『最後的貴族』(香港・牛津大学出版社2004年)の日本語版。
北大ではどこにある?
現代中国への認識を深めるのに一読の価値あり。50年前に開始された「反右派闘争」の中で「最大の右派」とされた父・章伯鈞をめぐる人びとを活写することにより、「中国共産党の政治」のあり方を世に問うた問題作。流麗な文章と深い人間理解、歴史への洞察によって中国内外で高い評価を受けたものの、発売後2ヶ月で再版不許可・発禁処分となった『往事並不如煙』を香港で改題・出版した完全版『最後的貴族』(香港・牛津大学出版社2004年)の日本語版。 -
推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)
「外地」研究の新しい研究動向
大日本帝国のクレオール : 植民地期台湾の日本語文学 / フェイ・阮・クリーマン著 ; 林ゆう子訳 . - 慶應義塾大学出版会, 2007
 北大ではどこにある?
台湾の日本植民地時代に創作された日本語文学(植民地下での公用語・日本語によって書かれた文学)を〈クレオール=文化的混淆〉という視点から読み解き、米国・台湾等で高い評価を得た研究論文の日本語版。「外地」研究は本学の「伝統的」学問の一つの柱をなす部分であり、本学図書館は戦前の台湾関係文献資料を豊富に所蔵することで、その分野ではつとに有名であるが、こうした新しい研究動向もしっかりフォローしていきたいものである。
北大ではどこにある?
台湾の日本植民地時代に創作された日本語文学(植民地下での公用語・日本語によって書かれた文学)を〈クレオール=文化的混淆〉という視点から読み解き、米国・台湾等で高い評価を得た研究論文の日本語版。「外地」研究は本学の「伝統的」学問の一つの柱をなす部分であり、本学図書館は戦前の台湾関係文献資料を豊富に所蔵することで、その分野ではつとに有名であるが、こうした新しい研究動向もしっかりフォローしていきたいものである。