|
北 海 道 地 図 の 変 遷
−江戸初期から明治初年まで− 高木 崇世芝 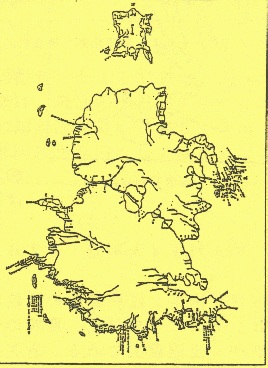 江戸時代初期から明治初年までの約280年間に作製された北方地図(ここでは、蝦夷地本島、カラフト島、千島列島の島々、および黒龍江からオホーツク沿岸、さらにカムチャツカ半島にいたるまでの各図)は膨大な数にのぼるであろう。江戸時代、江戸や上方に住む人々は遠い津軽の北端からさらに海を隔てた異域の「蝦夷地」に対して、どのような地理的認識をもっていたのであろうか。また、広大な原始林に覆われたこの地の地図は、どのような変遷を経て正確さを増していったのか。北方図の作製上で大きな節目となる時期を考慮して、ここでは三期に分けて、それぞれの時期の概略を記してみたいと思う。 元禄国絵図「松前島絵図」 初 期(正保期:1644〜天明期:1788) 約140年間
慶長4年(1599)、初代松前藩主・慶広が、大坂城において徳川家康に謁見し、松前系譜と蝦夷島之図をご覧に入れる、と史書に見えるのが、蝦夷地図の記録に現れる最初である。以後、松前藩が蝦夷地全島の調査、地図作製、里程測量、さらにカラフト島の調 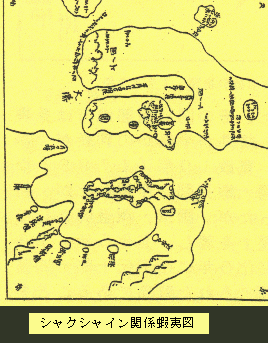 査など、たびたび実施した記録はあるが、いずれも現存しない。江戸幕府は、慶長9年(1604:第1回)、正保元年(1644:第2回)、元禄10年(1697:第3回)の3度にわたって全国の大名に国絵図の作製提出を命じた。松前藩は正保、元禄の2度、北方図を作製 して提出している。これが、現存最古の実地調査に基づく北方図である。松前藩提出の北方図(国絵図)は以後、転写され今に残っている写図が多い。寛文9年(1669)6月、東蝦夷地にシャクシャインの戦いが開始された。この戦いは3年余り続くことになるが、この時、津軽藩や南部藩によって作製または写されたと思われる地図があるがいずれも半島状の特異な地形をもつ蝦夷図である。これ以降、上方や江戸にも蝦夷地の様子が徐々に広まったようで木版の日本地図の中に初めて蝦夷地の南端部分が描写された。また、井原西鶴の『一目玉鉾』では、絵図と文章で蝦夷地を紹介している。さらに『和漢三才図会』という現在の百科事典にあたる書物が発行され、蝦夷地図が掲載されるまでになった。 査など、たびたび実施した記録はあるが、いずれも現存しない。江戸幕府は、慶長9年(1604:第1回)、正保元年(1644:第2回)、元禄10年(1697:第3回)の3度にわたって全国の大名に国絵図の作製提出を命じた。松前藩は正保、元禄の2度、北方図を作製 して提出している。これが、現存最古の実地調査に基づく北方図である。松前藩提出の北方図(国絵図)は以後、転写され今に残っている写図が多い。寛文9年(1669)6月、東蝦夷地にシャクシャインの戦いが開始された。この戦いは3年余り続くことになるが、この時、津軽藩や南部藩によって作製または写されたと思われる地図があるがいずれも半島状の特異な地形をもつ蝦夷図である。これ以降、上方や江戸にも蝦夷地の様子が徐々に広まったようで木版の日本地図の中に初めて蝦夷地の南端部分が描写された。また、井原西鶴の『一目玉鉾』では、絵図と文章で蝦夷地を紹介している。さらに『和漢三才図会』という現在の百科事典にあたる書物が発行され、蝦夷地図が掲載されるまでになった。この後、天明期に至るほぼ100年間に作られた北方図は、「初期蝦夷図」と総称されるが、その大きな特徴は、蝦夷地の図形にある。すなわち、今日我々の認識する北海道の輪郭とは似ても似つかぬ輪郭をもつ図がいのである。その一例をあげて見ると、南北に細長い島状の図、曲がりくねった半島や岬をもつ図、多くの島々を寄せ集めた図、石狩低地から二分される図、など実に夷地の周辺に想像上の島、すなわち現在か 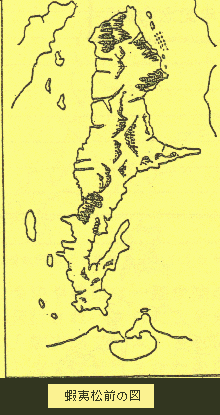 ら見ると架空の島々がいくつも描写されていることである。それらの島々には「小人島・大黒島・はだか島・女島」などと記されて、当時 ら見ると架空の島々がいくつも描写されていることである。それらの島々には「小人島・大黒島・はだか島・女島」などと記されて、当時の一般の人々の地理的認識の一端を窺うことができるかも知れない。天明期に入って著名な人物の蝦夷図が出現する。一人は、仙台の海防学者・林子平であり、いま一人は備中の地理学者・古川古松軒である。林子平は長崎に遊学し、ヨーロッパの知識をも学んで有名な『三国通覧図説』を発行した。 この書物の付図の1枚が「蝦夷図全図」であり、最初の木版蝦夷図であった。この図は、蝦夷地が南北に細長く、カラフト島は半島状、そして別に「サガリイン」という島も描写した。古川古松軒は幕府の東北・蝦夷地の巡見使一行に加わって松前に渡った。そして松前藩所蔵の蝦夷図を拝借して自ら蝦夷図を作製した。しかし、子平と古松軒の作製した蝦夷図はもはや最新の図とはいいがたいものであった。 中 期(天明期:1781〜天保期:1844) 約60年間 18世紀後半、江戸幕府の財政はひっ迫状態にあった。そのような 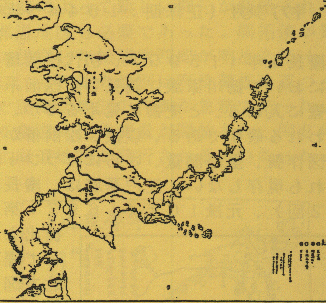 時期、幕府の中枢に登場したのが老中・田沼意次 である。意次の重要政策は積極的な財政の建て直しであったがその一つとして計画されたのが、蝦夷地開発である。調査は意次の失脚によりわずか2年余りで中止となったが、この時作製された蝦夷図は従来の北方図を一新する見事な図である。それは、蝦夷地全体の輪郭が、初めて実形に近づき、千島列島も初めて一直線に並んだのである。以後、幕府は幕末に至るまで、幾度となく蝦夷地を中心に周辺の島々にも幕吏を派遣して探検、調査を実施することになった。享和元年(1801)、中村小市郎と高橋次太夫はカラフト島の探検を命じられ、東西に分かれて南部海岸を実地調査しその成果によってカラフト島図を作製した。その図は南部地方は見事なものであったが、北部は先住民の見聞のみに基づいたため、離島か半島かの判断 がつかず、結局、両説を取り入れた図に仕上げて いる。近藤重蔵は、寛政10年(1798)以来、エト ロフ島の開発や蝦夷地の内陸部を調査し、千島列 島図・蝦夷図を作製したが、特に蝦夷図の地形は 蝦夷地墨引絵図 1786年 見事なものである。秦檍丸は幕府の雇いであったが、画家・ 測量師として技量を存分に発揮して、有名なアイヌ風俗画 帳『蝦夷島奇観』を著し、文化5年(1808)には実測に基づ く蝦夷図を作製している。 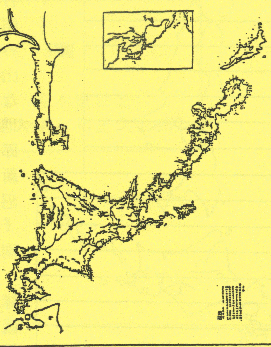 また、同じ文化5年に松田伝十郎と間宮林蔵はカラフト島北部の探検に向かい、同島が海峡によって隔てられた離島であることを確認した。翌6年、林蔵は単身で対岸の黒龍江沿岸に渡って満州仮府のあるデレンに到着し、ここでの交易の様子を詳細に調査して報告した。この探検結果によって作製されたカラフト島図は見事なものであり、海峡発見は広く欧州にまで知られることとなったのである。伊能忠敬の測量は、寛政12年(1800)の奥州街道と東蝦夷地の実測が最初であり、前後17年間におよぶ、全国の沿岸測量によって『大日本沿海興地全図』が完成したのは、文政4年(1821)であった。なお、忠敬の未測量だった西蝦夷地の測量は間宮林蔵によって行われ、この両名の実測によって、蝦夷地全体の輪郭が初めて科学的で正確なものとなった。天保年間に入ると、北方図作製の上で大きな出来事があった。そのひとつは、松前藩士で測量師であった今井八九郎が蝦夷地の全沿岸を実地測量して、その実測地図を作製したことである。八九郎は間宮林蔵から測量術を学んだといわれ、現存の地図はいずれも科学的で詳細なものである。 もう一つは、 幕府が4度目の国絵図を全国の大名に命じて作製したこと 近藤重蔵 「蝦夷地図」 1802年 である。天保6年(1835)に命令を出し、同9年に完成した 天保国絵図は、最後の国絵図であったがその全国の原本全てが現存している。松前藩が作製したこの国絵図を見ると縦6.7m、横5.5mの大きな彩色図で、地名も詳細であるが、輪郭は何故か当時としては歪んだ図形である。 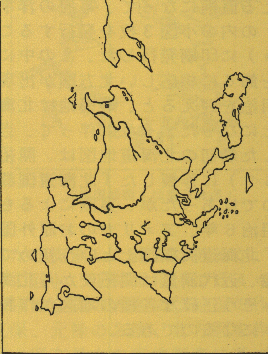 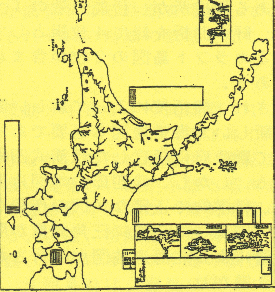 泰 檍丸 「蝦夷島地図」 1808年 天保国絵図 「松前島図」 1838年 後 期(弘化期:1844〜明治10年頃:1877)約30年間
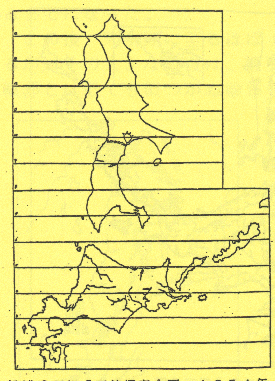 幕末になって北方図は大きな転換期を迎えた。それは幕末最大の北方探検家・松浦武四郎の蝦夷地探検が開始されたからである。伊勢国(現三重県)出身の武四郎は、若い時から諸国を遊歴し、長崎・平戸に滞在中に遠い蝦夷地の情勢を知るところとなり、一転して蝦夷地調査を志し、弘化2年(1845)、ついに蝦夷地に渡海し東蝦夷地を探検した。以後、前後6回にわたって、カラフト島やクナシリ・エトロフ島までもその足跡を残し多くの報告書、書籍、地図などを著作した。武四郎が作製したり発行した北方図は8種におよび、そのうち大図は3種類ある。その一つは嘉永7年(1854)に作製した『三航蝦夷全図』14枚組である。各種の地図や文献を参考にして仕上げられたが、蝦夷地は南北に扁平となり、カラフト島の北部は想像の域を出なかった。それから5年後の安政6年に発行された『東西蝦夷山川地理取調図』28枚組は前図を一新する見事なものとなった。まず蝦夷地の輪郭は、伊能忠敬の『大日本沿海興地全図』の中の蝦夷地部分の輪郭を借用し、内陸部は武四郎自身の調査によるデーターを駆使し、山地の表現には最新のケバ法を用いる。記された地名(山名・川名・湖沼名なども含む)も膨大な数であるさらに、翌7年には『北蝦夷山川地理取調図』19枚も作成したが、これは印刷されることなく終わった。 松浦武四郎 「三航蝦夷全図」 1854年 嘉永6年(1853)突如、ペリーの率いるアメリカ艦隊が浦賀 に来航し、幕府に開国を要求した。翌年、日米和親条約が結ばれ、箱館の開港が決定した。ペリー自身の箱館来航、箱館奉行所の再設置、幕吏の蝦夷地・カラフト島の視察、ロシアとの国境交渉など北辺の動向が慌ただしく蝦夷地や箱館は一躍世間の注目を浴びることとなった。江戸では、続々と北方図・箱館図が発行され、さらに、それまで無かった蝦夷地を掲載する日本図も次々と発行され、まさに「蝦夷図ブーム」ともいうべき現象 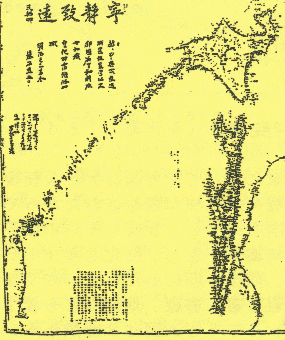 が起きたのである。嘉永6年から安政2年(1855)までに発行されたのは、北方図11点、箱館図1点、蝦夷地を掲載する日本図6点で僅か3年間に、なんと18点の北方関係図が発行されたのである。そして、幕府の終焉を迎える直前になって、幕府の洋学研究所である開成所が、伊能忠敬の『大日本沿海興地全図』の内の小図3枚を発行することになり、紆余曲折を経て4枚組として慶応元年(1865)に印刷発行した。この中に蝦夷地図とカラフト島図の2枚が含まれ、江戸時代の最後を飾るに相応しい北方図が出現したのである。 が起きたのである。嘉永6年から安政2年(1855)までに発行されたのは、北方図11点、箱館図1点、蝦夷地を掲載する日本図6点で僅か3年間に、なんと18点の北方関係図が発行されたのである。そして、幕府の終焉を迎える直前になって、幕府の洋学研究所である開成所が、伊能忠敬の『大日本沿海興地全図』の内の小図3枚を発行することになり、紆余曲折を経て4枚組として慶応元年(1865)に印刷発行した。この中に蝦夷地図とカラフト島図の2枚が含まれ、江戸時代の最後を飾るに相応しい北方図が出現したのである。明治を迎えると、蝦夷地は北海道と改称され、開拓使によって新しい開拓が開始されることになった。それに伴って、当然ながら新しい北海道地図も必要であった。開拓使が発行した最初の北海道地図は、開拓判官として新政府に任官した松浦武四郎が明治2年(1869)に作製した『北海道国郡図』である。しかし、武四郎の地図は実地調査に基づくものではあったが、実測によるものでなく、科学的で正確な地図の作製が急務であった 。 明治6年、アメリカのお雇外国人・ディーによって全道 に三角測量が開始され、同8年に『北海道実測図』と いう初めての近代測量による北海道地図が発行されるにいたった。以後、近代測量は開拓使から北海道庁に引き継がれ、いっそう正確な各種の地図が作製・発行されてい 松浦武四郎 「北海道国郡図」 1869年 くようになるのである。 (北海道大学創基125周年記念事業の一つとして、平成13年9月25日、百年記念会館において開催 された講演会の際、出席者に配布された資料を、講師の許可を得てここに採録させていただいた。) ◆前の記事へ戻る ◆目次へ戻る  ホームページへ戻る ホームページへ戻る |