|
「北海道帝國大學平面圖」ほか
工学研究科助手 池上 重康
今年2001年が北海道大学創基125周年にあたるというのは、皆さん周知のことと思う。 北大の古くからの建築図面や施設配置図などを、数年前より事務局に足しげく通い、漁ってきたこともあり、昨年、125 年史編集室員の任を受け、主に「写真集」の編集にたずさわることになった。25年前に発行された『写真集北大百年 1876-1976』とは雰囲気の違ったものにしようと、1章を「札幌キャンパスの125年」、2章ではそれ以外の附属施設など を扱い、3章を「トピックで綴る北大の125年」として構成することに、おおよそ意見がまとまっている。 当初は最近25年間の写真を集めながら、先の写真集で用いなかった旧知の写真や図面などで再構成する程度のものを 考えていたが、125年も歴史があると所蔵史料の懐も深く、意外にも未知の史料に少なからず遭遇することになった。 今回紹介する3枚の配置図は、この史料発掘の作業の中で発見されたもので、本学の歴史を語るにおいて重要 な史料といえる。概要は以下の通りである。
昨年春に附属図書館北方資料室で見つけた時は、しばらく放置されたことを物語るかの如く破れが目立ち、さらに は長年にわたり吸ってきた埃で彩色もはっきりせぬほど黒ずんだ状況であった。幸い総長裁量経費の研究助成を受け、 その一部でこれら配置図の洗浄および額装をすることができた。80余年の時を越え、総合大学に昇格した時の感 動と意気込みが、鮮やかな色彩で私たちの眼前に蘇ったのである。 ①の図面は北1条キャンパス(現在時計台のあるあたり)の様子を示しており、廣井勇が1880年4月に描いた”Forth Annual Report of the Sapporo Agricultural College, Japan for 1879-1880” 巻頭に掲載されている”Plan of the Sapporo Agricultural College Garden & Arboretum” の原図を模写したものと推察される。北3条西1丁目のブロックが苗圃およ び植物園であった状況を知ることのできる貴重な史料である。シンメトリカルな幾何学的配置構成や1876(明治9)年に L. ベーマー設計により建築された温室(1886年10月に現附属植物園内に移築)の位置がわかる。いつ模写されたか は不明だが、おそらく後述する2枚と同じ時期に旧キャンパスを偲ぶ意味も込めて描かれたのであろう。 ②の図面は附属植物園のもので、図面名称の「北海道帝国大学農科大学」という記述から1918(大正7)年度内に描か れたことがわかる(北海道帝国大学農科大学という組織は1918年4月1日設置、翌1919年3月31日廃止)。現在と比較し ても、管理棟の有無や温室の規模の違い程度で、遊歩道や幽庭湖など、ほとんど変化がないといえる。 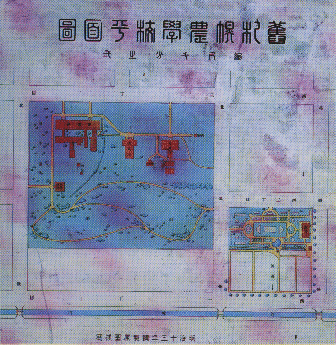 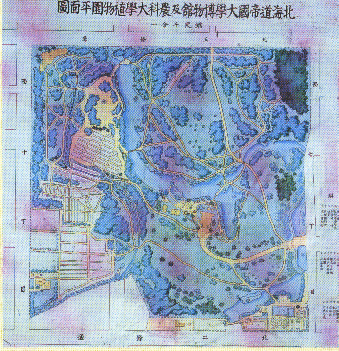 ①舊札幌農學校平面圖 ②北海道帝國大學博物館及 農科大學植物園平面圖 ③は帝国大学昇格を機に作成されたと考えられるものである。現在のメインストリートに相当する道路が形成されてい るが、工学部(いわゆる白亜館)は未だ姿を見せず、「医科大学」と書かれた医学部の施設群は建設予定、さらには北13 条通りの途中にロータリーを設けている。現在のキャンパスの骨格が見え始めているとはいえ、1970年以前の木造校舎 がふんだんにあった時代のキャンパスをご記憶の方々は、何となく雰囲気が違うと思われるに違いない。その理由は、北 13条通り北側一帯の附属病院(正確には当時は附属医院)が、その後まったく異なった姿で建築されたことにある。で は、この配置図は何を描いたものなのか。 ここに描かれる医学部の配置は、文部省が東京帝大医学部に準じて設計したものである。実は、これまで大正7年4月 1日「北海タイムス」掲載の不鮮明な図でしか、この文部省案の様子を知ることができなかった。設計変更の紆余曲折を ここで簡単に紹介したい。 基礎科(北13条通り南側)の諸施設がおおよそ姿を現わしたころ、後に初代病院長となる有馬英二がこの設計案に「 昔私らが勤務していた、明治41年頃の東大病室と同型のもの」と難色を示し、更に「初めて之を見た時の私の驚きはど んなでしたらう。…之は全然設計変更をして最新式の大病室を建て今後数十年吾が北海の天地が大いに開け人口が数 百万増加するとも障碍のないような永久的のものを造らなければならぬと決心」し、「鉄筋コンクリート造の3階建の高層 建築を推奨」した。が、予算との折が合わず不採用。それでも当初の意気込み通り「病院の模範を全日本に示してやろ う」と、ドイツの最新式の病院建築に範をとった各科病棟独立の並行配置を提案し、それが当時の営繕課長に受け入れ られた。病棟の設計には各臨床科教授が進んで参画、提案をしたという。 また、医学部を2つに分ける北13条通りは、当時の病理学教授今裕(後の第4代総長)が提案したものという。今が「 ダブルアレ」と表現する歩車分離の道路は当時の北海道では珍しく、今は「何しろ唯の10年前まで道幅は馬鹿に広いが 人道車道の区別もなく道は一本に限るものと思ひこんでいる札幌人士の眼からは気狂ひの沙汰だと思はれたのも無理 はない」と懐述する。秋には色彩のトレモロで人々を魅了するイチョウ並木は、当初は桜や紅葉が植えられていた。秋だ けでなく春にも人の目を楽しませてくれた道路だった。北13条通りの歩車分離道路は、植栽は変わったものの現在でも そのままの形式で残っている。 文部省案には茫漠たるロータリーが見えるだけである。 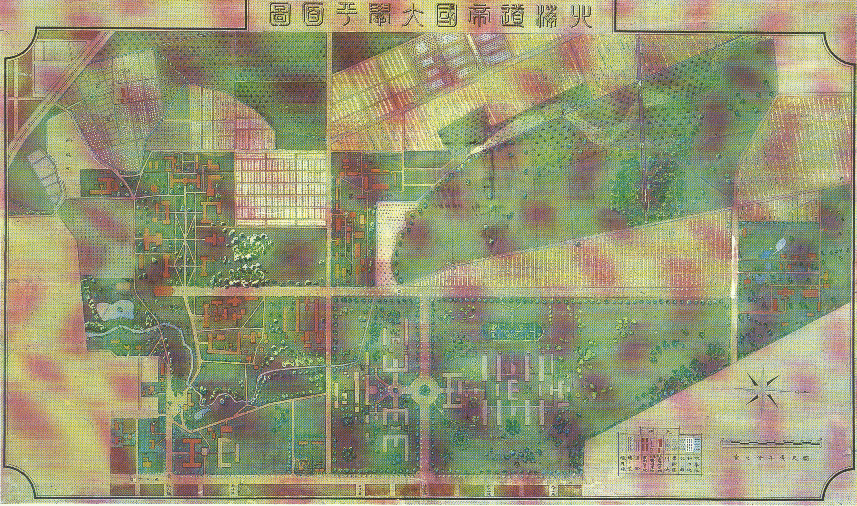 ③北海道帝國大學平面圖 1枚の古図から、忘れられつつある大学の歴史の一ページが繙かれる。先人たちの努力と情熱は、現代の私たちの心 に熱い何かを語りかけてくれる。 果たして21世紀の北海道大学、未来を見据えた高邁なる野心と理想をもって、どのような形の全国に範たるキャンパ ス計画を提示するであろ。 ◆目次へ戻る  ホームページへ戻る ホームページへ戻る |