学術振興会の招きで埼玉大学に滞在中のビクトル・ハルラーモフ氏をお招きして、『革命前ロシアにおける書、検閲、読書』と題する研究会をおこなったのは、1996月24日のことでした。
今にして思えば、通訳をはさんで1時間半という予定時間は、ハルラーモフさんにあまりにも短すぎました。(佐々木照央氏が通訳をしてくださいました)。ノビコフとエカチェリナ2世に始まって、アレクサンドル1世の検閲改革、ルミャンツェフ伯の歴史編纂事業から、結局ソビエト時代にまで話は及びました。尽きるところを知らない、熱気を帯びた話ぶりでした。
ハルラーモフ氏は、モスクワのロシア国立図書館にお勤めであり、若くして図書史部長、副館長といった要職にあった方です。しかし、その雰囲気は飾りのなく人なつこい純真な学者そのものでした。研究会がはねたあとのお酒の席で、乾杯の音頭を取るのに、「ロシア国立図書館の未来のために」と言ったところ、顔を
曇らせていらしたのを、今も覚えています。
ところが、昨年の暮れになって、氏が交通事故により急逝したとの連絡が入りました。
1948年11月生まれの氏は48才の誕生日を迎えたばかりでした。
年が明けて、新聞記事をチェックしていると、かつて彼の同僚だったロシア書籍史学の長老ネミロフスキーによる追悼文が目に入りました(『図書評論』紙1997.
1. 21付)。
それによると、レーニン図書館のネミロフスキー稀本部長は、稀本部図書史課が課題としていた革命後のソビエト図書史編集のために、歴史家が必要と考えていました。そこで、ボリス・イテンベルク(ソ連邦科学アカデミー歴史研究所)とミハイル・セドーフ(モスクワ大教授)から、ハルラーモフ氏を推薦されたということです。イテンベルクとセドーフはともにナロードニキの研究者であるが、その一方でイテンベルクは、『19世紀ロシア非合法・発禁印刷物総合目録』(1971年刊)の編集を指導し、セドーフもその仕事の助言者として重要だったとのことです。2人とも、図書館の事業に深い関心と理解を持って関わっていたわけです。
彼らの推薦状を携えて、ハルラーモフ氏はネミロフスキーと出会いました。1980年5月のことです。そして以後、ハルラーモフ氏は『ソ連図書史』シリーズの編集・執筆者としてネミロフスキーともに働き、82年にネミロフスキーの退いた後も事業の継続に力を注いだのでした。
既にニュース67号(Oct.
1996)でお知らせしたように、センターではイテンベルク氏の蔵書の一部を購入しています。
われわれのところでの研究会の後、ハルラーモフ氏は数日札幌に滞在し、センターと北大附属図書館を利用していかれました。帰国後、これらの印象について、イテンベルク氏に語ることがあったのかどうかはわかりません。しかし、これらの資料を見ていると、イテンベルクとレーニン図書館との関わり、ハルラーモフ氏との交わりが想起され、そしてセンターにイテンベルクの蔵書があるということで、センターがこれらの世界とつながっていることが感じられるのです。[兎内]▲ top
前号でもお知らせしましたように、1996年度は、前年度に引き続き、TsKhSD(同時代文書保存センター)のフォンド6(統制委員会)の部分を購入してきましたが、このフォンドについて既作成分の収集を完了しました。さらに同じ文書館のフォンド89(裁判にかけられた共産党)についても、目録および文書本体の購入を終えました。
現在、RTsKhIDNI(ロシア現代史文書保存・研究センター)のフォンド17(党中央委員会)の文書の購入を始めたところです。
いずれも、購入後1, 2ヶ月で利用可能になっております。[兎内]▲ top
第1期分を購入したことについては、ニュースNo.
64(Jan.1996)で既にお伝えしましたが、1996年度は第2期、1997年度は第3期分を購入しました。これによって、第1回(1919)−第7回(1935)大会の資料が収集されました。全て利用可能です。[兎内]▲ top
この資料は、UCLAの所蔵するユーゴスラビアの主に歴史と文化に関する2,075点のパンフレットとモノグラフを109リールのマイクロフィルムに収めたもので、言語はセルボ・クロアチア語が多く、時代的には中世から1960年代までをカバーします。
付録のガイドブックによると、このコレクションは1961-62年にかけてUCLAが、ユーゴスラビア資料を将来充実させていく基礎にするため、現地で収集したもので、保存のためにマイクロフィルム化することとなったとのことです。
東欧諸国、特にバルカン地域の資料が手薄なセンターにとっては、非常に有用なものと考え、96年度の学内緊急経費で要求したところ、関係者の理解を得て購入することができましたのでお知らせします。
付録のガイドブックにはタイトル、著者、件名の索引があり、アプローチが容易になっています。
現在、利用可能です。[兎内]▲ top
1995年に、伊藤清久氏のご遺族から寄せて頂いた蔵書の内、選択をおこない、584冊を受け入れました。ほとんどがロシア語の資料です。
内容的には、歴史、文学から、経済、石油に関する技術的なものまで含まれていましたが、特に際だったのは第2次大戦関係の資料が豊富なことで、ソ連の軍人によるメモワールや、戦争にまつわる文学作品を多く補充することができました。1997年夏に整理が完了し、利用可能です。▲ top
ロシア・東欧関係の資料に関する話題を扱う私的な情報交換の場として、メイリング・リストを開設しましたので、お知らせします。
関心のある方は、次のアドレスまでご一報下さい。 usagi@slav.hokudai.ac.jp 兎内宛て [兎内] ▲
top
昨年暮、緊急経費により、ハンガリーの歴史雑誌Szazadokの第1巻(1867)から第100巻(1966)までを購入しました。
この他、次の新聞のマイクロフィルムを受け入れました。
Sovetskaia
Sibir’ 1919-1994.
Sankt-Peterburgskie vedomosti 1762-1782.
Sotsialistik
Qazaqstan 1944-1986.
Sovet Turkmenistany 1943, 1945-1947, 1951-1980.
Sovet
Uzbekistoni 1965-1986.
Sovettik Kyrgyzstan 1956-1980.
Tochikistoni
soveti 1955-1980.
Pravda
Vostoka 1930-1954.
正教新報 1880-1912.
正教時報 1912-1939.
(欠号部分もありますので詳細はお問い合わせください)
また、Akty,
sobrannye Kavkazskoiu arkheograficheskoiu kommissieiu. t. 1-12, 1866-1904.
のマイクロフィッシュ、および、Comintern archiveのうち第7回大会(1934-35)を扱う3rd
Installmentまでを購入しました。[兎内] ▲ top
センターはニューヨーク在住のスラブ言語学・文献学者ジョージ
・Y・シェヴェロフ博士の旧蔵書を購入することとなり、その第1陣として図書832冊、雑誌806冊がこの2月末に到着しました。 シェヴェロフ博士は、1908年にポーランドのウォムジャに生まれ、コロンビア大学教授として長く活躍されました。博士の仕事の領域は,ウクライナ語を中心としながら、スラブ諸語を広くカバーするものであり、その蔵書はセンターの言語学関係資料の核となることが期待されます。
なお、博士の蔵書は、協定により、個人コレクションとして将来的にも他の資料とは区別して管理されることとなっています。[兎内]
▲ top
図書室では、現在、ロシア東欧地域の新聞を約100紙購読しています。特に、1990年に全国共同利用施設となって以後、大幅なタイトル増をしたわけですが、一方で、資料の収蔵スペースには限界があり、購読紙を製本して保存することは困難になりつつあります。
そこで、本年度より、1997年受入れの新聞で、マイクロフィルムでバックナンバーが得られる分については、マイクロフィルムを別個に購入して保存することとしました。
読みやすい、ページをめくりやすいなど、原紙の長所も承知はしておりますが、以後、順次切り替わりますので、ご了承願います。[兎内]
▲ top
上記のセットは、以前ニュースNo. 67(1996. 10)でご紹介した北大附属図書館で購入した資料で、内容的にはPolnoe
sobranie zakonov Rossiiskoi
Imperiiなど、18世紀にとどまらない、ロシア史研究の基本資料を多く含んでいます。 残念ながら、しばらく未整理状態で、利用に不便がありましたが、附属図書館のご努力で、昨年度、全点整理されましたのでお知らせします。 北大図書館のデータベースで検索できるほか、附属図書館とセンター図書室には冊子の目録も備えました。[兎内]
▲ top
この春より、センターCOE非常勤研究員諸氏の協力を得て、センターの収集したマイクロ資料の書誌データの学術情報センター総合目録システへの入力を始めました。
現在、ここ2〜3年の間に収集した、元が図書や逐次刊行物である資料を対象に、入力作業を進めております。当然のことながら入力データは北大の図書館システムにもロードされ、北大附属図書館のオンライン目録でも提供されます。従来も、特に新聞雑誌については重点的に入力してきましたが、これによって遠隔地からでもより網羅的に検索ができるようになります。
なお、現在センター内にあるマイクロ資料の仮カード目録の編成も継続し、並行して提供します。[兎内]
▲ top
スラブ研では、平成6年度に、旧ソ連のほぼ全体をカバーする1:200,000地図4500枚余りを購入しましたが、今年度の緊急経費の申請が認められたことにより、この地図に接続する、旧ソ連作成の中国東北部および内蒙古地域および南北朝鮮の1:200,000地図が購入の運びとなりました。
東北アジア地域を、国境を越えた視点で研究するためのツールとして、さまざまな分野での活用が期待されます。[兎内]▲ top
これまでこの紙面でご紹介してきましたのは、高額のセットものなどが中心でしたが、今回は、それに比べて小物かも知れないが気になる資料をいくつか紹介してみます。
・Slovansky sjezd v Praze roku 1848.: sbirka dokumentu. Edited by Vaclav Zacek
and Zdenek Tobolka. Praha: Nakl. Ceskoslovenske akademie ved, 1958. 614 p.
パラツキーの主導で1848年にプラハで開かれたスラブ人会議に関する史料集。会議の開催に至るまでの動き、諸民族の会議に対する態度、会議の進行にかかわる書簡、議事録などが集められている。
・Sabrana dela Vuka Karadzica. Knj. 1-13, 15-21, 36 (1965-1988)
セルビアの民俗学者、言語学者の著作集。全巻揃っていませんが未完結と思われる。
各巻の内容は、次の通り。
- Mala prostonarodnja slaveno-serbska pjesnarica (1814). 1965.
- Srpski rjecnik (1818) 1966.
- Narodne srpske pripovijetke (1821); Srpske narodne pripovijetke (1853).
1988.
- Srpske narodne pjesme. Knj. 1-4. 1975-1988.
- Danica 1826, 1827, 1828, 1829, 1834. 1969.
- Srpske narodne poslovice. 1965.
- Novi zavjet Gospoda nasega Isusa Hrista. 1974.
- Srpski rjecnik (1852). In 2 vols. 1986-1987.
- O jeziku i knjizevnosti. 1968-1986.
- Istorijski spisi. 1969.
- Etnografski spisi. 1972.
- O Crnoj gori; Razni spisi. 1972.
- Deutsch-serbisches Worterbuch. 1971.
- Prepiska. 1. 1811-1821.1988.
- Prepiska. 2. 1822-1825. 1988.
- Bibliografija spisa Vuka Karadzica. 1974.
・Etnohrafichnyi visnyk. Kn.1-7. Kyiv: Ukrains’ka akademiia nauk. 1925-1928.
V.
Kubijovic編のEncyclopedia of Ukraine. Vol. 1.(Toronto: University of Toronto
Press,
1984)の記述によれば、1932年までに全部で10冊出たとのことであるから、センターの蔵書は最後の3冊を欠いていることになる。2冊に合冊製本されており、随所に“Slawischen
Seminar der Deutschen Karls=Universitat in Prag”の丸印が見られる。[兎内]▲
top
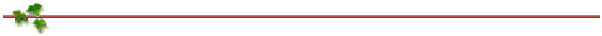
内容は、次の通り
- Zhernakov, V.N. Nikolai Apollonovich Baikov : (biographical outline and
bibliography). 1968.19 p.
- Zhernakov, V.N. Vladimir Vasil'evich Ponosov : (biographical outline and
bibliography). 1972. 16
- Aleksei Pavlovich Khionin : (biographical outline and bibliography). 1973.
5 p.
- Halafoff, I. Irina Vladimirovna Halafoff : an autobiographical sketch.
1988. 55 p.
- 11. Korenev, O.S. Russkoe Blagotvoritel'noe Obshchestvo v Sidnee. 1988. 24
p.
- Shnittser-Smolianinov, I.M. Mikhail Nikolaevich Volin. 1989. 0 p.
- Cowall, L. Zinaida Georgievna (Sika) Kerry. [ca. 1990.] 8 p.
- Potter, Michelle. Kira Bousloff : founder of the West Ausralian ballet.
1991. 30 p.
- Koreneva-Kulinich, O.S. Russian women in Australia. Pt. 1. 1992. 44 p.
- Kamensky, Yu.A. History of the St John of Kronstadt Russian Welfare
Society in Victoria. 1993. 43 p.
- Frolova, M.D. Russians in Australia. 1996. 215 p.
- Vinocuroff, V., Kamensky, Yu. Russian engineers in Australia. 1996. 107
- Kanevskaya, G.I. Russian migrant community in Australia, 1923-1947. 1998.
83
学情センターの総合目録データベースでは、いずれも書誌はありません。 [兎内]▲ top
図書室ではこれまでもシベリア出版物の入手に力を入れてきましたが、ロシアの書籍流通の現状から、その充実は困難でした。そもそも現地でも、シベリアの別の町の出版物が入手困難であるばかりか、何が出ているのかさえもわからないことが多い様子なのです。
当室では、ハバロフスクの国立極東科学図書館との国際交換をおこなっていますが、当室の重複資料リストを先方に送ったところ、返ってきたリクエストの多くは、リストに申し訳程度に載ったロシア領極東の出版物だったことがあります。
最近、図書室では、1998年度に外国人研究員としてセンターに滞在した、ロシア科学アカデミーシベリア支部のシシキン教授の協力を得て、シベリア出版物の充実を図ることができました。例えば、次のような、戦後に出版された、シベリアとその周辺のいくつかの州の文書館ガイドブックです。
Флеров,
ВС (ред.)Государственный архив Томской области: путеводитель. Томск. 1960. 256
с.
Государственный архив Омской области и его филиал в г.Таре:
путеводитель. ч. 1. Омск. 1984. 170 с.
Государственный архив Омской
области и его филиал в г.Таре: путеводитель. ч. 2. Изд. 2-е, перер. идоп. Омск,
1987. 291 с.(ч. 1)
Государственный архив Иркутской области:
путеводитель: дополнение к изданию. 1975 г. Иркутск. 1987. 251
с.
Государственный архив Семипалатинской области : путеводитель.
Алма-Ата. 1988. 214 с.
図書室ではこの他にも、各種史料集、事典類、統計、その他研究書、論文集などを揃え、広く要望に応えられるように資料を整備していきたいと考えています。[兎内]
▲ top
スラブ研究センターでは、アムステルダムの国際社会史研究所が所蔵するロシア社会革命党文書のマイクロフィルムの購入費を、大学本部に緊急経費として要求していましたが、このほど認められ、年度内に調達することとなりました。
頒布元のIDC社のホームページ(http://www.idc.nl)によりますと、社会革命党の創立時に、P.
Lavrovの蔵書が党の図書館とされたが、このLavrov
fondをもとに、後年別のメンバーの資料が加わったものとのこと。所在は、第一次大戦前はパリ、20年代はプラハにあり、1934年にベオグラードに移転の後、社会史研究所の働きかけで1938年にオランダに移され、大戦中は英国に疎開していてたとのことです。現在は、社会史研究所の所蔵です。
全145リール。目録は、次の資料として刊行されています。
Hermien
van Veen. Inventory of the archives of the
Partija
Socialistov-Revoljucionerov (PSR), (1834-)1870-1934.
Amsterdam:
Stichting beheer IISG,1994. XIV, 96 pp.
(IISG Working Papers no. 26, ISSN
0921-4585; 26).
[兎内 1999年12月 センター Mailing List より] ▲
top
スラブ研究センターでは、今年度の附属図書館の大型コレクション収集候補として、カナダのロシア歴史地理学の専門家であるJames R.
Gibsonヨーク大学名誉教授の蔵書の購入を推薦していたが、このほど文部省から経費が認められ、年度内に購入の運びとなった。
ロシア、シベリア、アラスカの歴史と地理に関する重要な研究と資料を長年にわたって広い視野から収集したGibson教授の蔵書は,全2,000点以上に及び、ロシア、シベリア、その他の北方地域に関する、北大附属図書館、特にその北方資料室とスラブ研究センターの蔵書を強化する上で大きく貢献するであろう。
なお、Gibson教授は、1981-1982年に、外国人研究員としてセンターに滞在されたことがある。主な著書としては、
Feeding
the Russian Fur Trade : Provisionment of the Okhotsk Seaboard and the Kamchatka
Peninsula, 1639-1856 (Madison, 1969);
Imperial Russia in Frontier America
: The Changing Geography of Supply of Russian America, 1784-1867 (New York,
1976);
Otter Skins, Boston Ships and China Goods : The Maritime Fur Trade
of the Northwest Coast, 1785-1841 (Seattle, 1992) がある。[兎内] ▲
top
コミンテルン文書については、今年度は、第8回執行委員会総会(1927年)および第9回執行委員会総会(1928年)の資料を収めるInstallment
7を購入した。ソヴェト共産党および国家文書については、ロシア現代史文書保存・研究センター(RTsKhIDNI)の既製作分は、延々と果てしもなく続く1920年代の党員調査ドキュメントを除いて一応の収集が終わったので、ロシア連邦国家文書館(GARF)に手をつけることとした。
現在、フォンドr-393[内務人民委員部]の文書本体を収集中である。[兎内] ▲ top
最初に報告させていただきたいのは、キエフ神学大学紀要(Труды
Киевской духовной академии)т. 1-58. 1860-1917年. [マイクロフィッシュ版]. IDC社.
の購入である。
革命前のロシアには、キエフ、モスクワ、ペテルブルク、カザンの4つの神学大学があったが、キエフ神学大学はその中でも、1615年設立のキエフ兄弟団学校(のちのキエフ・モヒラ・アカデミー)に遡る、最も長い伝統を誇っていた。1860年に創刊されたその紀要は、主として西方教父の著作の翻訳およびキリスト教研究のオリジナルな成果を収める。1860-1904年および1905-1914年をカバーする記事索引が付録する。なお、この購入には1999年度特別設備費の一部を使用した。
また、センター図書室は、この関連資料として、キエフ神学校評議会議事録(Протоколы
заседаний Совета Киевской духовной академии)
1875-1895年分のマイクロフィッシュを所蔵する。これは、UMI社から提供されるRussian History and
CultureシリーズにRH20680として含まれる。
この他、昨年度は、帝国科学アカデミーの出版物であったХристианский Восток.
т.1-6. 1912-1920.、北京駐在ロシア宣教団のТруды членов Российской духовной миссии в Пекине.
т. 1-4.
1852-1866.も購入した。後者は、中国の歴史、習俗、宗教事情、産業などを扱い、ロシアによる戦略的中国地域研究の様相を示す。
次に紹介しておきたいのは、ロシア帝国正教関係政令・指令集Полное
собрание постано-влений и распоряжений по ведомству православного исповедания
Российской Империи.
である。これは宗務院の発足した1721年以後について、主に宗務院の文書館に残されていた文書から編年的に編集したもので、1869年から1915年にわたって分冊刊行された。途中エリザベータ・ペトローヴナ(在位1741-1762年)以降の分は皇帝の治世毎に編集されたが、これは完成を早めるためであろう。しかし、残念ながら刊行できたのはパーヴェル1世の治世(1796-1801年)以前の分と、1825-1835年をカバーするニコライ1世の治世の最初の巻までであった。センター図書室は、Norman
Ross社が製作したこのマイクロフィッシュ版を購入した。
なおこの資料は、П.А. Зайончковскийの編集したСправочники по
истории дореволю-ционной России. Изд. 2-е. М. 1978.
では1250-1254番にあたる。
最後に触れておきたいのは、これと同じくNorman Ross社から購入した、文部省政令集Сборник
постановлений по Министерству народного просвещения.т. 1-17.
である。これは文部省の創立以来の文部関係法令を、1864年から1904年にかけて刊行したもので、1802年から1900年までをカバーする。なお、このマイクロフィッシュ版は、改訂第2版があるときは、それを使用しているようである。1802-1881年および1881-1900年をカバーする索引を付す。Зайончковскийの編集した上掲書では、1339番にあたる。
なお、以上の資料の収集には、原暉之教授を代表者として1999年度に開始された科研費プロジェクト「近現代ロシアにおける国家・教会・社会
: ロシア正教会と宣教団」に依るところが大きいことを付言する。▲ top
センター図書室は、前号でお知らせしたキエフ神学大学紀要に続き、カザン神学大学の紀要であった『正教の対話者 Православный
собесщдник』 1855-1917.
のマイクロフィッシュ版を購入することとなった。さきごろ現品が到着し、現在受入手続き中なので、近日中に利用いただけるようになるであろう。
カザン神学大学の創立は1842年とされる。他の3つの神学大学に比べて遅れた出発であるが、その前身である主教区初等学校Архиерейская
элементальная
школаが設立されたのは1723年にさかのぼる。この学校はキエフ神学校を範として1732年に神学校に改組され、1797年にはペテルブルク神学校とともに神学大学に改組されたのだが、資金難などから1818年に閉鎖され、この年にようやく再興されたのだった。
カザン神学大学は、研究レベルの高さと、イスラム教徒その他の異教徒への布教活動への関与によって特徴づけられる。その雑誌は、主にボルガ流域やシベリアでの正教会と異教徒との関係、異民族や分離派のあり方を知るための手がかりとして、活用が期待されよう。
なお、今回のセットには、付録として刊行された『異民族評論『Инородческое
обозренике』.т 1-2
(1912-1917)があわせて収録されている。
また、この資料は一橋大学附属図書館にも収蔵されており、センターはおそらく国内2番目の所蔵館である。
[兎内] ▲ top
Norman
Ross社は、革命前ロシアの県報知(губернские
ведомости)のマイクロフィルム版を製作するプロジェクトを、ペテルブルクのロシア国立図書館(Российская национальная
библиотека)の協力を得て進めており、現在、7県について入手可能となっている。
センター図書室では、このうち、アクモリンスク州(1871-1919年)および沿アムール総督府(1894-1917年)の分を1998年に購入しているが、今回、さらにキエフ県(1838-1917年)およびカザン県(1838-1917年)についても購入することとなった。現在、すでにフィルムは到着しており、受入手続き中である。県報知は、当該地方に伝達される中央政府および地方機関からの法令・布告等を収める公式部分と、それ以外の地域関連情報を報ずる非公式部分から成り、革命前のロシア地方社会の動きを追う上での基本資料として、今後の活用が期待される。[兎内]
▲ top
今年度から3ヶ年年計画で、上記資料を収集することになったので、お知らせしたい。
野々村一雄教授は、1913年愛知県に生まれ、大阪商科大学を卒業後、満鉄調査部等を経て、戦後は一橋大学経済研究所教授、千葉商科大学教授を務められた、戦後の代表的なソヴィエト経済専門家の一人と言えよう。1998年没。
センターでは、氏の旧蔵書のうち、学内で重複のない露文、欧文、和文図書、約1,400点の収集を予定し、現在、受入作業が進行中である。蔵書の中心は、1950年代から70年代にかけて出版されたソ連経済に関する専門書であるが、調査してみたところ、この部分に関してセンターの蔵書は必ずしも充実していなかったことがわかった。旧蔵書の受入は、この欠を埋める点で大いに貢献してくれそうである。また、受入が決まった資料について、作業の傍ら国立情報学研究所の総合目録をチェックすると、2-3館しか所蔵のない資料が多いのは意外であった。当時の大学図書館のロシア語図書収集量は、この程度のものだったのであろうか、それとも、遡及入力がなかなか進行していないためであろうか。[兎内]
▲ top
昨年夏のことであるが、1995年度より継続受入中のSoviet Communist Party and Soviet
Stateシリーズの、最初に納品された部分が、一部、茶色に変色した筋が出ていることが判明した。この筋の部分は、フィルム上にきちんと定着しておらず、リーダーを使用して読影中に、フィルムが通った部分に滓を残すこともあった。
代理店にクレームし、調査を要望したところ、半年近くのやり取りの結果、現像プロセスにおいて、水洗いが不十分だったためであり、該当フィルムを新しく製造したものと交換することになった。当方で調査の結果、問題の生じたフィルムは全部で115リールあったが、去る9月に新しい製品が到着して、交換をおこなったところである。
マイクロ資料は、使用した材料と保存環境が適切であれば、長期保存に耐えるものと考えられているが、ときにこのような問題が生じることがあり、放ったままにしておかないのがよさそうである。[兎内]
▲ top
ロシア国家歴史文書館の所蔵するロシア各県の県知事が皇帝あてに提出した年次報告書は、19世紀ロシアの諸地域の状況を知るための基本資料といわれている。センター図書室は、Norman
Ross社がその一部について製作したマイクロフィッシュをこのほど購入することができた。
収録範囲は、次の12県の、それぞれ1855-1864年の分である。アルハンゲリスク県、エカテリノスラフ県、カザン県、サラトフ県、トボリスク県、ニジェゴロト県、ノヴゴロト県、ペテルブルク県、ペルミ県、ボロネシ県、モスクワ県、ヤロスラヴリ県。いくつかの報告書をリーダーにかけてみたところでは、報告書は書記官が手書きで作成したものと見られる。大きな字で丁寧に書かれているが、タイプ打ちの文書と違って多少の慣れが必要であろう。
なお、最近、この資料について書かれた次の論文を目にしたことを付記する。▲ top
スラブ研究センター図書室では、上記のマイクロフィルムセット、全86リールを購入した。
これは、1990年代はじめまでユーゴスラヴィアを構成していた地域の主要なものについて、大戦前にそれぞれの地域において作成された統計類のコレクションである。セルビア・クロアチア語もしくはドイツ語のものが多い。当時の事情の反映であろうが、地域や分野に精粗が見られるのは致し方あるまい。またオスマン・トルコの治下に作成されたものは含まれていない。しかし、セルビア王国統計年鑑(1893-1910年分)、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ統計年鑑(1906-1916年分)の他、人口、農業、家畜、教育、鉄道、貿易、犯罪などの統計を含み、基本資料としての活用が期待される。収録資料の点数を地域毎に示すと、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ:76点、クロアチア・スラボニア:79点、セルビア:166点、モンテネグロ:1点、である。
この資料の購入にあたっては,科学研究費補助金「東欧・中央ユーラシアにおける“近代”と“ネイション”」(基盤研究A,
研究代表 林忠行)が活用された。なお、このセットは、一橋大学経済研究所も所蔵している。[兎内] ▲ top
1995年度に収集を開始した、オランダIDC社の製作する上記セットの収集を、ほぼ5年がかりでようやく完結させることができた。
これは、ロシア国家社会政治史文書館(Российский
государственный архив социально-политической истории,
略称РГАСПИ、1999年までの旧称РЦХИДНИ)が収蔵するコミンテルン文書の、マイクロフィッシュによる複製である。文書の検索には、資料中に含まれるописиによる他、IDCが製作したCD-ROMが使用できる。
なお、この資料は、早稲田大学中央図書館においても収集済とのことである。[兎内]
▲ top
雑誌
『Странник 巡礼者』は、1860年から1916年まで、ペテルブルクで刊行された月刊誌である。1860年前後は、アレクサンドル2世治下の自由な雰囲気において、ジャーナリズムが発展し、さまざまな雑誌が登場し言論がたたかわされた時代であるが、ロシア正教会においても、いくつもの雑誌が創刊された。Странникは、そうした雑誌の一つだが、Igor
Smolitschにおいては、60年代においては、教会史的に価値の高い記事を多く掲載したが、その後より大衆的な方向に転換し、読者の幅を広げたと評されている。(История русской
церкви, 1700-1917. ч.2. М. 1997. с.55)。正教会と公衆との接点にあった雑誌として、今後の活用が期待される。[兎内] ▲ top
スラブ研究センター図書室では、上記のマイクロフィルムセット、全513リールの収集に着手し、その一部を購入した。
これは、19世紀後半から第一次世界大戦にかけての時代に、ハプスブルク帝国治下にあったウクライナ西部で刊行された新聞・雑誌類を主としており、199タイトルを収録する。
ウクライナ語出版物が中心であるが、ハンガリー語、ドイツ語、ロシア語による出版物も含むこの資料は、東ガリツィアを中心に、ブコビナ、ザカルパチエなど、ウクライナ西部地域の当時の言論を分析する上での基本資料として役立つものと考えられる。ウクライナ・ナショナリズムの源流を探り、多民族社会としてのウクライナの実相を考える上で、興味深い材料を提供してくれることであろう。
今回購入した分は、このセットの冒頭からアルファベット順に、AからKarpatskii
kraiまでの220リールであるが、今後2-3年のうちに全体を揃えたいと考えている。[兎内] ▲ top
スラブ研究センター図書室では、COE特別推進研究経費によって、1995年度より上記のマイクロフィルムセットを継続的に購入してきた。その量は、2000年度末現在で4,120リールに達したが、まだ多くの未収集部分を残している。しかし、今年度に入ってから、特別推進研究経費の交付が留保され、収集を進めることが難しい状況になった。
この資料は、目録部分や共産党裁判関係ファイルなど、部分的には、東京大学社会科学研究所をはじめとするいくつかの機関で利用できるが、全体的に収集しようとしているのは当センターなどごく一部に限られると思われ、今後、何らかの形で収集が継続できるよう、努力していきたい。[兎内]
▲ top
北海道大学附属図書館では、近年、資料収蔵能力が限界に近づいていましたが、取り敢えず2001年度において、西書庫2階部分を電動集密化することとなりました。この工事により、センターから管理換した資料は、西書庫2階より、東書庫1階の集密書架に移転することとなりましたので、北大附属図書館に来館された際にはご注意願います。[兎内]
▲ top
センターでは、1981年度以来、特別設備費の交付を受けて、四次にわたる基本図書整備計画を推進し、図書館資料の充実に努力してきました。最初の頃と比べると、その金額は大きく削減され、現在では年間700万円程度となっているのですが、校費に次ぐ重要な財源として、最近では特に中央アジアやウクライナ、シベリア、極東などの地域の資料整備促進に充てられてきました。しかし、特別設備費の交付は2001年度で打切られ、以後、そのような費目自体がなくなるとのことで、1998年度から2002年度までということで進行中であった第四次基本図書整備計画は、残念ながら1年早く完了することとなりました。なお、今年度は、最終年度分の前倒しとして、700万円の追加配当を受け、これによって昨年度に収集を開始したRare
Ukrainian Serial Publications
の残り部分を全て収集することができました。
今後の資料整備を進めていくためには、新しい制度下での工夫が必定であります。[兎内] ▲ top
スラブ研究センター図書室では、米国 Norman
Ross 社の製作する革命前ロシアの県報知 Губернские ведомости 一部を、1997 年度および 2000
年度に続いて購入することができた。今回新たに収蔵されたのは、ミンスク県 (1838-1917 年、122 リール) およびワルシャワ県 (1867-1915
年、38 リール) である。
センター図書室の所蔵する革命前ロシアの県報知は、これ以外は次の 4 県である。
アクモリンスク州
(1871-1919 年、42 リール)、カザン県 (1838-1917 年、71 リール)、キエフ県 (1838-1917 年、136
リール)、およびプリアムーリエ (1894-1917 年、48 リール)。 [兎内] ▲ top
上記と同じく、米国 Norman
Ross
社の製作するこのマイクロフィルムのセットは、中央アジアを中心に、沿ボルガ地方やカフカースなどで発行された新聞を集めている。この中には、一部ロシア語のものもあるが、大多数はトルコ系の言語をアラビア文字によって表記したものであり、帝政ロシア末期からソビエト政権初期における、とりわけ非ロシア人地域の事情や知識人のありかたを読み取る上での基本史料と言えるだろう。
センター図書室では、このうち、既収分などを除いた
410 リールを昨年度末に購入した。なお、このための支払い総額は、361 万円余であり、1 リールあたり 9,000
円以下にとどまった。これは、まとまった分量を購入するためディスカウントを得られたことによる他、直接輸入することにより代理店手数料が不要であったこと、最近の円安傾向にかかわらず、財務省の定める支出官事務規程により、この
3 月までの校費の外国送金においては、米ドルの換算率が 1 USD = ¥107
と設定されていたこと、商品としてでなく学術研究資料として輸入するため、日本側と積み出し側の両方において消費税を免除されること
(通常は日本の通関時に消費税を徴収される) が寄与している。
聞くところでは、このセットは既に国内の 2,3
の図書館においても収蔵され、デジタル化を実施したところもあるようである (例えば小松久男 「イスラーム地域研究の試み: アラビア文字資料のデジタル画像化」
(http://www.l.u-tokyo.ac.jp/IAS/Japanese/library/online%20library/komatsu03.html#komatsu3top)
を参照)。しかし、ロシア、旧ソ連の地方出版物の充実に力を入れているセンターとしては、この資料の整備は必至のことであったと考えている。 [兎内] ▲ top
センター図書室の収集した資料は、参考図書、マイクロ資料等を除いて、附属図書館に管理換えされ、利用者に提供されている。そうした管理換え済み資料は、大部分が附属図書館の西書庫
2 階にまとまって配置されてきた。しかし、附属図書館において 2001
年度にこの場所に電動集密書架が設置されることになり、センターから管理換えされた資料は、2002 年 1 月をもって東書庫 1
階の集密書架に移動したことをお知らせしたい。
なお、新規の電動書架設置工事は、すでに完了しているが、センターから管理換えされた資料は、当分新しい所在にとどまることとなりそうである。[兎内]
▲ top
スラブ言語学・文献学、とりわけウクライナ語学に重要な足跡を残した言語学者、ジョージ Y. シェヴェロフ氏は、2002 年4 月 12
日、ニューヨーク市内の病院にて逝去されました。 93 歳でした。
氏は、学界のみならず、在米亡命ウクライナ人社会にあっても、非常に大きな存在であったと察せられ、心からお悔やみを申し上げたいと思います。
既に本誌の誌上にてお知らせしてきましたように
(73 号 [1998 年春] 等を参照)、センターは氏との協定により 1997
年度から蔵書の購入を開始し、現在、その途上にあります。
伝えられるところでは、氏は、重病の中、残った蔵書のことをたいへん気にされていたとのことですが、ラトガース大学のミロスラヴァ・ズナエンコ教授と、相続人セオドア・コスチューク氏の迅速な手配によって、その後まもなく蔵書は日本に向けて発送され、6
月には東京に到着しました。
たいへん有り難いことであります。
今回の到着分によって、センターのシェヴェロフ・コレクションは近く完結を迎えることになるでしょう。[兎内] ▲ top
センター図書室は、最近、駐露公使としてペテルブルクに在勤していた花房義質(1842-1917)の日記を購入しましたのでご報告します。花房義質は、岡山藩士花房端連の長男として岡山に生まれました。緒方洪庵の塾に学び、1867年には長崎から洋行の旅に出て、欧州、米国を経て翌年帰国。1870年から外国官御用掛として出仕。1872年、ペルー国船マリア・ルース号に乗船の清国苦力の虐待問題につき、仲介裁判のための代理公使としてペテルブルクに派遣され、訴訟の後は、日露国境画定交渉のため派遣された榎本武揚全権公使を補佐しました。その後、朝鮮に駐在し、壬午事変(1882年)においては、包囲された公使館を脱出して帰国、済物浦条約により、事変による損害の補償とともに、京城への駐兵などを認めさせました。
翌1883年より1886年までの3年間にわたり、駐露公使としてペテルブルクに滞在しました。
その後は農商務省次官、帝室会計審査局長、宮内次官、枢密顧問官、日本赤十字社社長などを歴任しました。
今回購入した日記は、官用常用日記簿3冊から成ります。すなわち、ペテルブルクに到着した1883年5月に始まり、1885年末に終わっています。主にペン書きですが、一部、鉛筆書きで、その日の出来事が簡潔に、時折出費額を伴って記されています。自署などは見られませんが、駿河台大学の広瀬順皓氏に見ていただいたところでは、日記に描かれる交際ぶりは公使にふさわしいとのことであります。
花房義質関係文書としては、これまで東京都立大学付属図書館および外務省外交史料館所蔵のもの、および宮内庁書陵部所蔵のものが知られています。
駐露公使時代の花房の活動は、その伝記『子爵花房義質君事略』(黒瀬義門編,
1913年刊)によれば、皇帝の即位式に出席し、条約改正問題に関与したという程度で、あとは淡々としたものだったようです。むしろ、当時の外交官の日常を窺うための材料ということになるのかも知れません。[兎内]
▲ top
スラブ研究センター図書室は、上記のマイクロフィルムセットを購入することとなり、現在、大学本部において購入手続き中であることをお知らせしたい。
このフィルムは、А.С. Зернова の編集した総合目録 Книги кирилловской печати, изданные в Москве в
XVI - XVII веках: сводный каталог (Москва, 1958) に基づいて、レーニン図書館 (現ロシア国立図書館)
等の蔵書を撮影して製作されたものである。 従って、ヴィリニュスやリヴォフ、オストロークなどでの出版物は含まれない。
付録してきたリストを見た限りでは、書誌に掲載された資料 500 点余の資料のうち、10 点余りの例外を除いて、ほとんどの資料を収録していて、リール数は 320
を超える。 これは、もともとは、General Microfilm Publications 社によって製作・販売されたが、現在は Norman Ross
社が販売しているものである。 国内で、このマイクロフィルムのセットを所蔵するのは、おそらくこれが最初であろう。
これとは別に、スラブ研究センターは、18 世紀ロシア出版物集成を収集中であり、今回の購入によって、モスクワで出版が開始されてから、18
世紀に至るまでのロシアの出版物ののかなりの部分をセンターにいながら利用できるようになった。 [兎内] ▲ top
ロシア在外歴史文書館 Русский заграничный исторический архив в Праге は、1923
年にプラハに設立された、ロシア人亡命者に関する資料センターである。 文書館には、文書部 отдел документов と並んで刊本部 отдел
печатных изданий および新聞部 газетный отдел
が設けられ、ロシア革命前および革命後の両方について、在外ロシア人に関する資料の最も包括的なコレクションがここに形成された。
1945 年 5
月にヨーロッパにおける第二次世界大戦が終結してまもなく、ソビエト連邦とチェコ政府との交渉によりロシア在外歴史文書館は解体され、収蔵資料の多くは、ソ連邦科学アカデミーに寄贈するという名のもと、ソビエト側に引き渡されることとなり、文書資料の多くは十月革命中央国家文書館
ЦГАОР (現在のロシア連邦国家文書館 ГАРФ)
に搬入された。しかし、刊本部および新聞部の収蔵資料はその対象外とされ、大部分がプラハのスラヴ図書館に保管された。
ただし、その存在は公表されないままにおかれ、公開には 1991 年を待たなくてはならなかった。
今回図書室が購入したのは、プラハのチェコ国立図書館の一部であるスラヴ図書館に現存する、ロシア在外歴史文書館刊本部および新聞部のカード目録を撮影して製作したマイクロフィッシュである。
図書の部 82 枚、雑誌の部 22 枚から成り、各フィッシュは、縦 18 コマ、横 28 コマづつ目録カードを収録する。 新聞の部は、163
枚から成り、各フィッシュの収録コマ数は、縦 13、横 16 である。
図書の部は、革命前から戦間期にかけてロシア・ソ連邦内外で出版された約 4 万タイトルの資料を目録している。 タイプ打ちの部分もあるが、手書きの方が多い。
新聞の部は、ほとんど手書きであり、ところどころ判読困難な部分があるものの、各号の受入記録が付いた完全なものであり、それ自体亡命ロシア人研究の基本資料として意義深い。
[兎内]
▲ top
スラブ研究センター図書室は、このほど、次の3点の資料のマイクロフィッシュ版を購入したので、ご報告したい。
①Ежегодник Министерства иностранных дел. год 1 (1861) -53 (1916)。ただし год 7-8
(1867-1868) および год 47 (1910) を欠く。 ザイオンチコフスキーの Справочиник по истории
дореволюционной России. Изд. 2-е(М.,1978) によれば、 後者は大臣の命令により破棄され出版されなかったという。
このタイトルが付くようになったのは途中からであり、 当初は仏語で、 Annuaire diplomatique de l'Empire de Russie
.と題された。 Год39(1902) までは仏文、以後は露文。 内容は、皇族リスト、政府首脳部人名表、外務省中央および在外公館に勤務する幹部職員表、
在露外国公館リスト、勅令等の関係主要法令、予算、省内規定、対外条約・協定等の資料から成る。帝政ロシアの外交関係に関する基本史料として役立つものであろう。
②Известия Министерства иностранных дел. [г.1] кн. 1. (1912) - г. 6. кн. 1/2.
(1917).隔月刊の本誌は、ロシアの締結した条約類、対外関係に関係するロシアの法令類、
その他の資料(外務大臣の国会演説など)、領事報告、および関係論文を収録する非公式部分から成る。
わずか5年余りしか刊行されなかったのが残念だが、①と並ぶ当時のロシア外交に関する基本史料として
位置づけられよう。ただし、前述のザイオンチコフスキーの本には載っていないようである。
③Сборник Московского главного архива Министерства иностранных дел. Вып. 1
(1880)- 7 (1900)_外務省文書館に保管される文書を多数紹介する。また Вып.1の最初の部分には、文書館の所蔵する
文書の概要を述べたフランス語の論文がおかれている。なお、この文書館の所蔵史料は、 ロシア革命後の転変を経て、現在はロシア帝国外交文書館Архив внешней
политики Российской Империи, 略称 АВПРИ に収蔵されている。
[兎内] ▲ top
日露戦争時には、日本国内各地に捕虜としたロシア軍将兵の収容所が順次設置され、戦争末期には7万人を超える収容者があった。スラブ研究センター図書室は、最近、このうち姫路および福知山に設置された収容所に関する若干の資料を購入することができたので、ご報告したい。
姫路俘虜収容所は、松山および丸亀に続く3番目の収容所として1904年8月1日に開設され翌1905年12月28日に閉鎖された。福知山俘虜収容所は4番目の収容所として1904年9月9日に開設され、1906年1月6日に閉鎖された。いずれも下士卒のみを収容し、姫路収容所は陸軍1760名、海軍424名の計2184名を収容する、どちらかといえば大規模の、福知山収容所は陸軍390名、海軍1名の計391名を収容する小規模の収容所であった。
今回入手した資料は、それぞれ別個の古書店を経た2つの部分から成る。すなわちその第1部分は、写真帖2冊、絵葉書帖1冊、および収容所日誌6冊、「俘虜ニ関スル取調書」、「福知山収容所職員名簿」等18点の文書、書簡30通より成る。
追って別ルートより入手した第2の部分は、写真帖3冊、厚紙の台紙に貼った写真11枚、および書簡21通より成る。
いずれの部分についても、書簡の受取人はそのほとんどが田中昌太郎後備役陸軍中尉であり、その他の文書類、写真帖に関しても、全てが田中中尉の管理下にあった品と推定している。
本年1月29日より2月1日までセンターにおいて開催された国際シンポジウム『20世紀初頭のロシア・東アジア・日本:
日露戦争の再検討』に際して、写真展『捕虜となったロシア軍将兵:日露戦争の一断面』を1月28日〜31日の間開催したが、第1部分の資料をこれに展示することができた。
日露戦争時のロシア軍捕虜収容所に関しては、当時の陸軍省の手になる『明治三十七八年戦役俘虜取扱顛末』(有斐閣書房、1907年)があり、また才神時雄『松山捕虜収容所』(中央公論社、1969年)などもあるが、個別の収容所に関する記録、文書、研究は決して多くなく、100年の歳月を経た現在、不明の部分が大きい。
今回入手した資料の所持者であった田中昌太郎は、福知山収容所の開設と同時にそこに着任し、翌1905年6月には姫路収容所に異動したが、この間一貫して収容所運営上キーパーソンの位置にあったと考えられる。
姫路および福知山収容所に関しては、これまで桧山真一氏による仕事「福知山俘虜収容所のロシア人下士官の手記」(『共同研究日本とロシア』(早稲田大学安井亮平研究室、1987年)所収)および「俘虜と製革:姫路のポーランド人ミハウ・ムラフスキ」(同第3集、一橋大学中村喜和研究室、1992年所収)があるが、今回入手した資料が今後の研究の発展に資するよう、逐次、解題・翻刻等を進める予定である。
[兎内]
▲ top
1993年から94年度にかけてスラブ研究センターは、ロシア革命・社会主義運動に関する重要史料である米国スタンフォードのフーヴァー研究所文書館が所蔵するボリス・ニコラエフスキー・コレクションのマイクロフィルムのUnit
1から11までを購入している(センターニュースno. 58(1994.7)を参照)。
しかし、その後、Unit
12以下が製作されたとの情報に接していたが、残念ながら長いこと追加補充ができずにいた。2003年度において、センターの21世紀COEプロジェクトが採択されたことから、このほどUnit
12-14を補充することができたので、お知らせしたい。Unit 12は41リール、Unit 13は35リール、Unit
14は41リールの計117リールから成る。まだ残りのUnitがあるが、遠からず完結させることができるものと期待している。
[兎内] ▲ top
図書室と附属図書館との業務統合
スラブ研究センター図書室は、ここ数年、資料収蔵スペースのやりくりに苦慮してきました。センターがこれまでに収集した資料は今や16万点を超え、年々6,000から10,000点が新規に加わってきました。この全体をセンター内で管理することは単に物理的な意味でも到底不可能であり、図書や製本雑誌の大部分を附属図書館に管理換した上で、他の資料とは別置して利用者の便宜を図るというのが従来の方式でした。しかし、1990年代後半から附属図書館書庫の狭隘化が深刻化したこと、および、これを契機として附属図書館側より、書庫スペースの占有根拠について強い疑問が提示され、書庫にセンターの収集した資料を排架する前提として、業務統合の実施をわれわれに迫ってきたのは2001年秋のことでした。
これを受けて翌2002年度に、附属図書館副館長を委員長とする「スラブ研究センター図書業務統合計画委員会」が発足し、どのような方法で統合をおこなうか検討が開始され、約2年を経た2004年3月25日の第4回委員会において、図書業務統合の大要が「申し合わせ」および「実施要領」の形にまとめられ、了承されるに至りました。その後、この案件は4月13日のセンター協議員会において承認され、近日開催が予定されている附属図書館の図書館委員会で承認されれば、いよいよ正式実施に向けて準備が整うこととなります。
今回の統合案の要点は、次のようにまとめられるでしょう。
スラブ研究センター図書室業務のうち、資料の発注、受入、目録等の業務は附属図書館に移管される。それによって、統合以後にセンターが収集した資料は、はじめから附属図書館の資料となる。資料費は、センターから附属図書館への流用によってまかなわれる。(これまでに附属図書館と図書業務を統合した他部局と同じ)
センターに配置されている図書系事務職員は、附属図書館に配置換される。(センターの当該職員は1名しかいないので、センターには図書系職員がいなくなる)移管業務の遂行のために必要な人員の不足分については、資料費に基づく計算式により算出し、非常勤職員の人件費という形でセンターが負担する。
スラブ研究センター図書室は、スラブ研究資料室と改称し、従来通りサービスポイントとして維持される。
センターの収集した資料のうち欧文図書、露文図書および学位論文は、スラブ・コレクションとして、他と混排しない。
附属図書館書庫の狭隘状態により、当面、本来附属図書館へ配置すべき資料であっても、センター内に暫定排架できる。
9年前の赴任以来、附属図書館との関係には、心理的になかなか微妙なものがあることを感じてきたのですが、今回の業務統合はそれを正常化し、将来的に双方が普通に付き合っていくためのステップとして必要なものと感じています。
早ければ6月にも予想される統合の実施に向けて、以上の統合の枠組みを前提とした業務の再編成を進めているところです。
[兎内] ▲ top
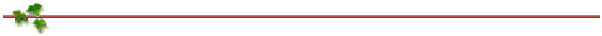
ロシア国家軍事史文書館所蔵日露戦争関係史料その他
スラブ研究センターはこのほど、2003年度に開始された21世紀COEプロジェクトの経費により、Primary Source
Media 社の販売する The Russo-Japanese War, 1904-1905 from the Military Science Archive
を購入しました。これは、ロシア国家軍事文書館( Российский государственный
военно-исторический архив, 略称 РГВИА)の所蔵する日露戦争関係ファイル(
Фонд 846. опись 16.
)の文書を選択の上、マイクロフィルム全170巻に収めたものです。
日露戦争の終結後、ロシア軍事省はワシーリー・グルコ少将(1864-1937)を長とするチームを編成し公式戦史の編纂を命じた。こうして生まれたのが、1910年に9巻16分冊で刊行された
Русско-японская война 1904-1905 гг. Работа Военно-исторической
коммиссии по описанию Русско-японской войны, СПб.: А.Ф. Маркс, 1910.
ですが、今回購入したセットは、上記戦史の編纂のためにロシア帝国軍の戦史部が収集した史料約11,000点がもとになっており、ちょうど100年前に戦われたこの戦争に関するロシア側の原史料集成として重要性は大きいと言えます。
ついでながら、センターではこの他、同じロシア国家軍事史文書館の所蔵する内戦関係文書についても購入しました。赤軍関係文書
The papers of the Red Army, 1918-1923 が全76リール、白軍関係文書 The papers of the White
Army, 1918-1921 が全71リールで、発売元は同じく Primary Source Media 社です。[兎内] ▲
top
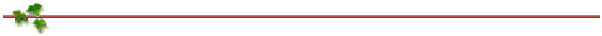
«Туркестанские
ведомости»(『トルキスタン報知』)の購入
このたびスラブ研究センター図書室は帝政ロシアの新聞 «Туркестанские
ведомости»(以下『トルキスタン報知』と表記)のマイクロフィルム版を購入した。『トルキスタン報知』は1870年4月28日の第1号にはじまり、1917年12月27日までタシケントで刊行されたトルキスタン総督府の官報である。刊行頻度は1870年から1903年までは日曜と木曜の週2回、1904年には日曜、水曜、金曜の週3回、1905年から1907年にかけては日曜、火曜、水曜、金曜の週4回、1908年以降は祝日の翌日を除く毎日刊行された。1917年の二月革命による帝政崩壊を契機に、同年3月19日号より同新聞の発行主体は臨時政府トルキスタン執行委員会に移された。今回収集されたマイクロフィルム収録範囲は、1894年2月6日号(通巻第1247号)から1911年12月31日号(通巻第4173号)までである。なお、1915年1月1日号(通巻5026号)から1917年12月27日号までについては、2002年に収集された「19世紀末–20世紀初頭の中央アジア新聞集成」に収録され、同じくマイクロフィルムで読むことができる(本誌89号(2002.5)参照)。
センター図書室は、トルキスタン総督府に隣接するステップ総督府が発行した『ステップ地方新聞』(«Dala walayatïnïng gazetí».1888–1902.
Омск)のマイクロフィルムを併せて所蔵している。『ステップ地方新聞』が同一紙面上にアラビア文字カザフ語版とロシア語版とを併記するに対し、『トルキスタン報知』の紙面は全てロシア語であり、同官報はもっぱら総督府管内のロシア人を主な購読層として想定していたと判断できる。しかしこれと並行するかたちで発行された
『トルキスタン地方新聞』(«Turkistan wilayatning gazeti».1870–1917.
Tashkent)はアラビア文字ウズベク語(初期はカザフ語でも書かれた)を使用しており、同じくセンター図書室で閲覧可能(マイクロフィルム)である。これら各紙のより詳細な比較検討は今後の課題と考える。
『トルキスタン報知』の紙面は大きく「公式欄
официальный отдел」と「非公式欄 неофициальный
отдел」に分かれる。公式欄は総督府内部における命令や通達、役職人事、中央官庁の命令などを記載する。非公式欄ではその当時総督府内で持ち上がっていた政治、社会に関する様々な議論が紹介され、同時代のトルキスタン総督府官界の様相を垣間見ることができる。それは例えば鉄道の敷設、綿花産業、現地民の教育問題、植民問題など多岐にわたるものである。また植民地現地民の慣習や習俗などの民族誌、自然環境などが紹介される。タシケントを中心とする定住民地域に関するものが多いが、天山山脈をはじめとする山間部の遊牧民地域についても少なからぬ情報を提供してくれる。我々はまさにロシア人が征服地域に関して様々な情報を収集し、支配地域として構築していこうとする過程に立ち会うのである。トピックは総督府管内にばかり限定されるものではない。非公式欄では、続けてロシア帝国内の各種情報が報告され、さらに「外国情報」として世界各地の情報が外国の新聞を抜粋する形で紹介されている。特に英露間のグレート・ゲームを反映してかイラン、アフガニスタン、インド、中国の情勢はその中でも大きな比重を占める。まさに「帝国の時代」のなかのトルキスタンが読者の前に姿を現すにちがいない。
[スラブ社会文化論専修博士後期課程1年 秋山徹]
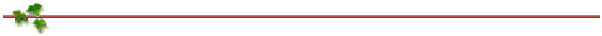
ハプスブルク帝国統計年鑑の購入
スラブ研究センター図書室では、資料の収集の中心はロシアにありつつも、それと同時に少なからぬ注意を東ヨーロッパに払ってきたことをその蔵書構成は教えてくれる。特に統計年鑑や官報、辞典、参考図書などには高い順位が与えられ、優先的に収集されてきたわけである。ところが、ハプスブルク帝国については、統計年鑑も議会議事録も所蔵しない。これは、ハプスブルク帝国が、その解体以前は欧州の大国であったため、センターあるいは北大では所蔵せずとも、国内的には東大や一橋大などいくつかの図書館がすでに所蔵するということによると思われる。センターが乏しい懐から多額の購入費をそうしたものに振り向けるよりは、センターとして別に収集すべきものがある、という考え方である。
しかし国内にあるとは言っても、札幌の住人にとってはそう手軽に利用できるものではなく、東欧を専門に勉強しようという大学院生たちがぼちぼち札幌に集まりつつあるこのごろ、時機を見て収集しておくことが適当と考えてきた。
今回入手したものの範囲は、Tafeln
zur Statistik der Österreichischen Monarchie.(1842年版–1855/56/57年版)、Statistische
Jahrbuch der Österreichisch–Ungarischen Monarchie. (1863年版–1881年版)、および
Österreichisches statistisches Handbuch. (Jahrg.
1–43,1882年版–1916/1917年版)である。
なお、この資料の購入に際しては、科学研究費補助金「東欧・中央ユーラシアの近代とネイション」(研究代表:林忠行)が使用された。 [兎内] ▲ top
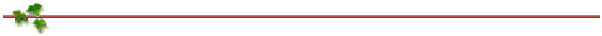
附属図書館との統合実施
センターニュース97号(2004.5)でお知らせした附属図書館との統合は、2004年7月1日より実施されました。[兎内]
▲ top
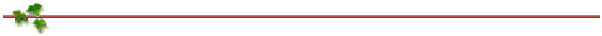
最近の購入資料より
昨年から本年にかけてスラブ研究センター図書室が購入したマイクロ資料より、数点を紹介いたします。
ひとつめは、"дело"(事業)という、ペテルブルクで1866年から1888年にかけて刊行された月刊誌です。この雑誌は、ドミートリー・ピーサレフ(1840-1868)、セルゲイ・ステプニャーク=クラフチンスキー(1851-1895)、ワシーリー・ベルヴィ=フレロフスキー(1829-
1918)、ピョートル・ラヴロフ(1823-1900)など多くのナロードニキ系の論者が寄稿する、影響力のある雑誌でした。なお、この資料は、東京外国語大学附属図書館が1988年度大型コレクションとして収集した「ロシアナロードニキ研究史料集成」にも含まれていて、同館でも利用することが出来るものです。
2番目に挙げるのは"Сын
отечества"(祖国の子)と題する、1812年からペテルブルクで刊行された雑誌です。ニコライ・グレチ(1787-1867)を編集者として出発したこの雑誌は、内外の政治情勢をはじめとして、歴史・地理に関する論文も多く掲載され、さらにはロシア語による文学・評論の発表の場としても重要なものでした。今回は、その創刊から1837年までの分についてマイクロフィッシュ版を購入しました。
3番目に挙げるのは、同じくペテルブルク出版されたウクライナ知識人の雑誌"Основа"(基礎)です。ワシル・ビロゼルスキー(1825-1899)を編集者とし1861年に創刊された本誌は、わずか2年足らずで廃刊に追い込まれましたが、パンテレイモン・クリシ(1819-1897)、ミコラ・コストマーロフ(1817-1885)などが参画し、文学、言語、教育、歴史を論じて、ウクライナ民族運動の画期となったものです。
最後に紹介するのは、1848年のドイツ三月革命期に開催されたフランクフルト国民議会の議事録Stenografische Bericht über die
Verhandlungen der deutschen Constituirenden National-versammlung zu Frankfurt am
Main.です。全部で78シートに収められたこの史料は、民族運動の揺籃期にあった中欧における政治運動の基本的な記録と言えましょう。 [兎内] ▲ top
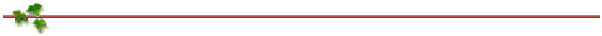
東京外語大のロシア語遡及入力事業進む
NIIの総合目録上でのロシア語資料の登録状況を見ていますと、最近、東京外国語大学附属図書館が入力したレコードが頻繁に目に付くようになりました。ここ数年、総合目録主要参加館のロシア語資料登録状況を観察し続けてきましたところ、東京外国語大学附属図書館の所蔵レコードが付けられたロシア語図書書誌レコード数は、2001年5月には2,622でしたのが、2005年2月には21,577と、8倍以上に増加しました。これは、NII登録に登録されたロシア語書誌レコード163,615件の13.2%にあたり、大学別では、北海道大の76,421、
東京大の43,776、神戸大の28,212に次いで4位ということになります。
同館では、総合目録への接続が国立大学の中では比較的遅く、遡及入力が進んでいないことから、2004年度にロシア語資料の遡及入力経費をNIIに申請し、認められたと担当者から伺っておりますので、その成果の現われということになりましょう。八杉文庫、吉原文庫、菊地文庫等の個人文庫の整理も、この機会に進んだ様子が見えます。ただし、戦前以来の資料を含んだ「旧分類」資料の遡及入力は、これからの課題とのことです。
[兎内]
▲ top
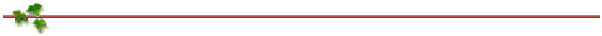
反ソヴィエト系新聞コレクション
スラブ研究センター図書室では、オランダIDC社の製作した反ソヴィエト系新聞Anti-Soviet
Newspapers(全91リール)の購入を開始しました。これは、サンクト・ペテルブルクにあるロシア国民図書館Российская национальная
библиотекаの非公開特別保管庫спецхранに保管されてきた、主としてロシア内線期にボリシェヴィキ権力支配地域外で刊行されていた新聞、
500紙余りを収録するもので、その目録は、同館より、Несоветские газеты 1918-1922 :каталог собрания
Российской национальной библиотеки. (Санкт-Петербург,
2003)として出版されています。
目録の序文によると、1990年に当時のレーニン図書館(現ロシア国立図書館 Российская
государственная библиотека)、サルティコフ・シチェドリン公共図書館(現ロシア国民図書館)および全連邦書籍院Всесоюзная
книжная палатаが新聞総合目録Газеты первых лет советской власти1917-1922.(全4巻,
北大未所蔵)を共同出版しましたが、公開フォンド分だけを扱っていて、ここに収録された新聞は、その範囲外をカバーするとのことです。という訳で、ここに収録される新聞の傾向は全てが必ずしも反ソヴィエト系ということではなく、むしろソ連時代の情報統制を反映したものと理解すべきでしょう。たとえば、チタで発行された極東共和国政府の機関紙
Дальне-Восточная Республика
の1920年5月から1921年7月分はここに収録されており、さらに上記総合目録への参照がなされています。これは、ソ連時代において同紙は1921年7月以降の分が公開フォンドにあったことを示唆するものと思われます。
目録の巻末には、出版地索引および人名索引が付せられています。出版地索引を見ると、シベリア,
極東の諸都市ではトボリスク(12紙)、トムスク(15紙)、バルナウル(14紙)、クラスノヤルスク(12紙)、ヤクーツク(6紙)、イルクーツク(16紙)、チタ(20紙)、ウラジオストク(22紙)が目に付きます。中東鉄道の拠点ハルビンは7紙、尼港事件で知られるニコラエフスク・ナ・アムーレは5紙を収録します。ボルガ・ウラル地域では、カザン(5紙)、オレンブルク(11紙)、サマラ(15紙)、ウファ(12紙)、チェリャビンスク(9
紙)、ペルミ(7紙)。ステップ総督府所在地のオムスクは41紙を収録し、セミパラチンスクは10紙あります。カフカス地域では、チフリス(4紙)、バクー(5紙)、ピャチゴルスク(12紙)、ウクライナでは、キエフ(12紙)、ハリコフ(24紙)、オデッサ(15紙)など、北ロシアでは、アルハンゲリスクの10紙が目に付きます。
個々の新聞の収録状況については、断片的なものが多く含まれるのは、発行当時の混乱した政治・社会情勢により致し方ありません。しかし、かなりの程度揃っているものも含まれており、内戦期の諸地域/諸勢力の動向や社会情勢を知る上で、重要な情報源となることと思われます。
[兎内] ▲ top
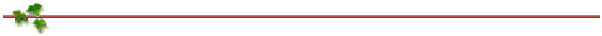
中村泰三氏所蔵資料の受贈について
中村泰三氏は、1933年生まれ。ロシア・東欧の地理学を専門とされ、大阪市立大学において長く活躍されてきました、わが国におけるこの分野の数少ない専門家のひとりです。本センターにおいても、1992-1993年度に客員教授を務められました。現職は、京都女子大学教授です。
昨年、センターの原暉之教授を通じて、所蔵資料の寄贈についてのご相談をいただきました。リストをいただいて調べましたところ、全部で2,300点を超える資料の大部分はロシア語資料ですが、一部、ポーランド語、ブルガリア語など東欧諸国語のものも含まれること、分野的には、大きく分けて、経済学関係のものと地理関係のものがあり、そのうち、前者は半分以上北大既存の資料と重複するものの、後者については重複しない資料が相当あることが判りました。ロシア・東欧の地理関係のコレクションは、全国的に見ても、九州大学の三上文庫、北大附属図書館のギブソン文庫等がありますが、まだまだ手薄な領域のため、北大に収蔵することは意義が大きいということで、附属図書館に相談申し上げましたところ、重複部分を除いた上で、個人文庫として扱うことができるということで理解をいただくことができました。本年7月に資料を受贈し、現在、附属図書館において登録および目録の作業が進行中です。最終的な受入数量は確定していませんが、1,600点程度と見込まれます。
本資料は、2005年度末前後には整理が完了し、附属図書館本館書庫西4階に排架されて利用可能となる見込みです。
[兎内] ▲ top
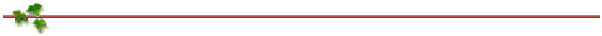
『軍事論集Военный
сборник』(1858-1917)について
『軍事論集Военный
сборник』は、1858年に創刊されたロシア陸軍省の月刊雑誌です。その発刊に際しては、当時カフカス軍参謀長で、その後1861年から1881年まで陸軍大臣を務めたドミトリー・ミリューチン(1816-1912)のイニシャチブがありました。帝政ロシア政府機関の定期刊行物によくあるように、当初、内容は公式部
официальная часть と非公式部 неофициальная
частьに分れ、公式部には、軍政、軍令関係の布告類を掲載し、非公式部には、軍事関係の論文や回想などの記事を収めていました。その後、1869年になって『ロシアの傷病兵』紙を同じ編集部で編集することとなり、公式部は『ロシアの傷病兵
Русский
инвалид』に引き継がれました。
同誌の編集に長く携わったФ.А.Макшеевは、19世紀初以来のロシアの軍事関係雑誌および同誌の成り立ちと発展を回顧する文章をその1908年
4、5、6、11月号および1916年6月号以降に連載しましたが、残念ながら、1871年までの分で中絶しています。
スラブ研究センター図書室は、同誌の創刊より1917年1月号までを収めた、オランダIDC社の製作したマイクロフィッシュ4201枚を購入しました。センター図書室は、同誌に先立つ1848年に創刊されたロシア海軍の雑誌『海事論集
Морской сборник』について、マイクロフィッシュをすでに所蔵しますが、『軍事論集Военный
сборник』が加わったことで、帝政ロシア軍事史を辿る雑誌の両輪を得たと言えるでしょう。 [兎内] ▲
top
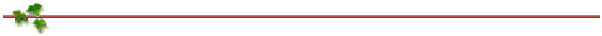
ハプスブルク帝国期オーストリア議会議事録(1861-1918)
ハプスブルク帝国の帝国議会Reichsratは、ハプスブルク家諸領邦の身分制議会にその起源を持つとされる。1848年のオーストリア三月革命に際して召集された憲法制定帝国議会Reichstagは7月に開会したが、10月にウィーンがヴィンデシュグレーツ将軍の手に落ちると、モラヴィアのクレムジルに移り、憲法草案の審議を続けた。しかし、政府は翌1849年3月にこれを武力によって解散し、欽定憲法を公布した。さらに、この憲法も発効することなく、1851年末のシルヴェスター勅令によって廃止された。
1859年のイタリア戦争での敗北後、1860年に出された十月勅令は、領邦議会の代表からなる帝国議会Reichsratを設置し、これに限定的な立法権を付与したが、翌1861年の二月勅令はこれを修正し、皇帝の任命する議員から成る貴族院Herrenhausと領邦議会の代表から成る衆議院
Abgeordnetenhausの二院から構成される、より広範な立法権を持つ議会として、これを規定し直した。この帝国議会は同年5月に開会されたが、ハンガリー、クロアチア、トランシルバニアなどはこれに反対して代表を送らず、また、開会後に、チェコ人、ポーランド人がここから退場するなど、議会運営は軌道に乗らなかった。
普墺戦争(1866年)の敗戦の翌1867年、帝国はハンガリー王国との和協(アウスグライヒ)によって、オーストリア=ハンガリー二重君主国として再編成された。帝国の西半分のオーストリア側と、東半分を占めるハンガリー王国は、共通の君主を戴きながら、別個の政府と議会を組織し、共通事項である外交・軍事・財政以外はそれぞれが別個におこなうこととなった。オーストリア帝国議会は、1867年これを認め、同年末に発布された十二月憲法とよばれる新憲法の下で再出発した。
新帝国議会においては、皇帝の任命する議員から成る貴族院Herrenhausと領邦議会の代表者から成る衆議院Abgeordnetenhausの二院の権能は対等とされ、皇帝には依然として議会の解散をはじめとする多くの大権が留保されるなど、絶対主義的な性格が濃厚な体制がとられたが、このオーストリアで実質的にはじめての立憲君主制は、第一次世界大戦末までのほぼ半世紀にわたって維持された。ただしこの間、衆議院選挙制度は、1873年に領邦議会議員の互選から直接選挙制に移行し(ただし4つのクーリエから成る制限選挙)、1896年には、これに普通選挙により選出する72議席が追加され、
1907年にはクーリエ制が廃されて選挙制が男子普通選挙に統一されるなどの改正を経たが、ナショナリズムの勃興期における多民族国家を背景にした議会運営には困難が多く、法案も予算も審議できない機能不全の状態に陥ることも稀ではなかった。
本センター図書室は、ハプスブルク帝国史研究上の基本史料として、Olmus社の製作した上記オーストリア帝国議会議事録(Stenographische
Protokolle über die Sitzungen des Herrenhauses des Österreichischen
ReichsratesおよびStenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der
Abgeordneten des Österreichischen
Reichsrates)のマイクロフィッシュ版(それぞれ698枚と5229枚)の購入を2004年から進めていたが、昨年秋に完結させることができた。これが、東欧史研究に関する北大のポテンシャル向上に資することを期待したい。
なお、本資料は、国内では他に早稲田大学図書館、および慶応大学三田メディアセンターでも所蔵する他、九州大学には原版のかなりの部分が揃っているとの情報がある。
[兎内] ▲ top
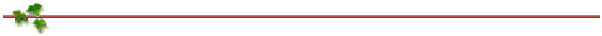
ソ連共産党・国家文書の補充
1995年度以来、スラブ研究センターでは、Hoover
InstitutionとРосархивの共同事業として製作されChadwick-Healey社から販売される
«Archives of the Soviet Communist Party and Soviet
State»について、当時のCOEプロジェクト経費などを使用して逐次購入をしてきましたが、COEプロジェクトが廃止された後は、なかなかこれに手が回らない状況が続いていました(センターニュース87号,
2001年10月を参照)。しかし、昨年度の終わり近くになって、若干の補充を果たすことができましたので、お知らせします。
昨年度の購入分は、ГАРФの収蔵する文書中、リール番号で3.2723-3.2949の全227リールです。これは、ピローゴフ通りにある旧ЦГАОР СССРに所在するフォンドr-393
内務人民委員部の文書の一部であり、年代的には1923-1925年のものです。なお、このフォンドは、相当膨大なもので、これまで約2600リールを購入してきましたが、なお1000リール以上が残されています。
[兎内] ▲ top
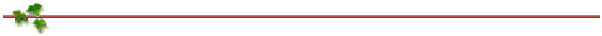
シェヴェロフ・コレクションの整理の進捗
本誌90号(2002年7月)で、シェヴェロフ氏旧蔵書の受入完了が近いことをお知らせしたが、それを並べる場所の確保が困難だったことなどもあり、その後の整理は、必ずしも順調でなかった。本年になって、最近、国立情報学研究所が力を入れるようになった遡及入力支援事業が活用できないかと、附属図書館から申請していただいたところ、これが採択され、5月から整理が急速に進行するようになったので、お知らせしておきたい。
この遡及入力支援事業の対象は、図書として整理できる資料に限定されているため、逐次刊行物類については今後引き続き目録作業の必要があるものの、これによって本年度中に、おそらくはスラヴ言語学・文献学コレクションとしては質・量とも国内最大規模と言えるであろう、本コレクションの大部分について目録が作成済みとなり、オンライン検索可能となる見込みである。
[兎内] ▲ top
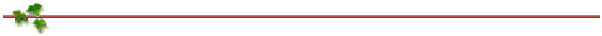
ナウカの破産
7月5日午後、ナウカ(株)札幌営業所の熊坂さんと井上さんが揃ってあいさつに見えて、「当社は、本日、裁判所に破産を申し立てました。明日、決定がくだされることと思います。支援に応えられず、これまでいろいろご迷惑をかけましたが、たいへんお世話になりました。」とのこと。翌日、両人は再度訪問され、「本日、破産が決定しました。明日より、営業所はロックアウトされ、連絡が取れなくなります。」と話されて帰った。
ここ数年、経営が相当苦しくなっていることは承知しているつもりであったが、何とか立ち直れないものかと思っていた。昨年、『窓』が休刊し、最近のカタログが合併号になったのを見て、いよいよ危ういと感じていたが、ついにその日が来てしまったようだ。暗然たる気持ちである。
ロシア語書籍輸入の老舗である同社の札幌営業所は、北大正門すぐそばのビルに居を構え、当センターにとっては、長年にわたって最大の取引先だったと思われる。特に、秋月孝子さんが図書室で腕をふるっていた頃、札幌営業所の担当者だった菅原さんとは大変密に連絡を取っていたとのこと。仕事上の最大のパートナーと言っていいような存在だったと推察される。年間取引量は、軽く1,000万円を越えたことであろう。
1995年にわたしがセンターに赴任した時は、すでに菅原さんは東京に移られたあとだった。
( その後、非常に経営が厳しくなってから社長となられ、昨年亡くなられたが、わたしは亡くなられたことを長く知らなかった。)
ナウカは、依然として大口取引先の一つであったが、次第に取引量は減っていくことになった。ご承知のように、当時、ソ連崩壊後の書籍流通には、大混乱と大転換が生じていた。中央集権的出版と書籍流通の体制が解体され、ナウカを通じて輸出入公団に発注するこれまでの方法では、多数の書籍が、注文しても入荷せず、出版情報も入らなくなった。Новые книги(エヌ・カーと略して呼んだ)
は、まだ出ていたが、それを見て注文しても、入ってくることが少ないことがわかり、使うのをやめた。いつの間にか、エヌ・カーそのものが来なくなった。ナウカのカタログで注文しても、在庫本以外の入荷率は非常に低く、ロシア語書籍は、(株)日ソの見計らい本で入れることが多くなった。しかし、これではいろいろ欠けるものもあるので、それを補うために、二、三の別ルートを併用した。
ナウカとのお付き合いは、主に新聞・雑誌および洋書の方面で続いた。ナウカの洋書目録は、人類学など人文科学系に配慮された編集がされていて、有意義であったが、発注後の入荷の確実性には問題があり、後日クレームすることが少なくなかった。また、前に載せた本を繰り返して載せる傾向があり、過去の発注記録を調べると、注文済みの本であることも少なくなかった。なんとか在庫をさばきたいという切迫した事情があるものと推量されたが、選書の手間を考えると相手にするのは不経済である。また注文しても入荷しないなら、選書・発注業務は無駄となり、かえってコレクションに穴があく。いきおい、ナウカとの取引は減っていくことになった。この他、新聞・雑誌の契約は大幅に他社に移され、数年前からは北大での前金での取引対象外とされた。記録を調べると、センター図書室と2003年度の取引は、逐次刊行物が150万円余り、図書などが500万円弱の、合計650万円余りだったのが、2005年度は、逐次刊行物は160万円弱に対して、図書などが260万円弱、合計で420万弱にとどまる。
ナウカの破産により、ロシア、旧ソ連諸国の書籍輸入を手がける国内の業者は、事実上、日ソだけとなった。現在、大学予算の削減、書物中心の研究方法からの転換等により、洋書輸入業自体が、非常に厳しい経営環境にさらされていると思われる。しかしその一方では、皮肉なことに、こうしていわば脱書物化が進んだせいで、ちょっとした基本的な文献が身近にないことが増え、かえって図書やマイクロなどの資料を組織的に整備することの意義が高まっているようでもある。
今回の破産は不幸なことであったが、センターにとっては、資料の組織的整備を進めていく上での、新たなパートナー模索の始点に立ったとも言える。
[兎内] ▲ top
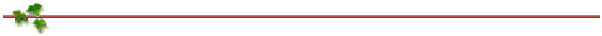
参考図書の遡及入力
ニュース106号(2006.7)
で、シェベロフ・コレクションの目録作成の進捗についてお知らせしました。これは、国立情報学研究所が募集した遡及入力支援事業の一環として、目下進行中ですが、オンライン目録未入力分が多いセンター参考図書室所在資料の遡及入力を、今回の事業の一部として抱き合わせで進めていただくことができましたので、報告します。
これによって、図書室の収集資料のうち、図書については、過去の分も含め、ほぼ全部がオンライン目録で検索できるようになりました。これで、われわれの抱える次なる目録上の宿題の相手は、一部の逐次刊行物類およびマイクロ資料ということになると考えます。
[兎内] ▲ top
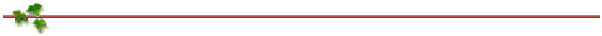
北大図書館の組織変更
北海道大学では、1975年の法学部を皮切りに、主として文科系部局の図書室の附属図書館への業務統合を進めてきましたが、法人化後においては図書業務について全学的な業務統合をおこない、全ての図書系職員を附属図書館の組織に一元化するという方針が打ち出され、この4月より全学的に大幅な組織改変が実施されました。
これによって、これまで個別におこなわれていた各部局図書室の資料の収集、整理業務は、附属図書館に移管されました。また各部局図書室の職員は、身分的には附属図書館の職員ということになります。
センター図書室は、すでに2004年7月より附属図書館と業務統合を実施し、図書系職員のポストを附属図書館に配置換えしており、当面の業務体制においては目だった変動はないものの、全学的な図書館の業務体制が大きく変わったことは、プラス・マイナス含め、今後さまざまな面で図書館の運営に影響することが予想されます。
[兎内] ▲ top
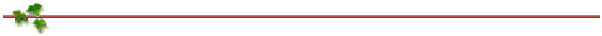
資料紹介:水野操軍医西伯利事変従軍日誌 NEW!
この資料は、センターが2003年に古書店から購入したもので、日誌本体1冊、および附録3冊から成る。水野軍医は、日誌紙面で見るところ、1918年8月に動員され、東京から、朝鮮、満洲を経て、沿アムール州方面で活動した模様で、日誌本体は、動員開始から翌年8月ころまでの、水野が所属した衛生部隊の活動を記している。自筆でなく、ガリ版刷りを綴じたものであり、水野本人も、日誌中に筆者としてでなく登場すること、複数種類の筆跡が見られることから、本人が個人的に作成したものでなく、部隊の活動記録として組織的に作成され、逐次関係者に配布されたものと推察される。日々の部隊の活動を示す日報の他、気象観測記録、部隊配置図、給水装置の図面等の資料が多く綴じ込まれているが、1919年4月以降については、単なる衛生概況旬報の羅列であり、日報は見られなくなる。作成されなくなったのであろうか。
附録は、やはり、資料として部隊に配布されたものと思しき資料類の綴りである。すなわち、本人が作成した衛生旬報(1918年9月〜1920年9月)、「浦汐派遣軍ニ於ケル凍傷ニ就テ」、「寒時衛生上ノ注意書」等の他、「調書ムーヒン」、司令部職員表、地図等が綴られている。この中には、参謀本部による『西伯利出兵史』および『西伯利出兵衛生史』等によってすでに知られている部分も多いが、たとえばムーヒンの尋問調書は、管見の限り、他に掲載されたものはないようであり、シベリア出兵に関する日本側史料として、今後の活用が期待される。
[兎内] ▲ top
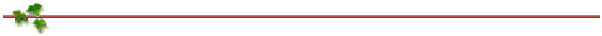
[HOME]
Copyright (C) 2002 Slavic Research Center, Hokkaido
University
![]()